【〇〇性】よく使う言葉(一覧表)
※1:”〇〇性”は、「〇〇の性質・能力」「〇〇の状態・傾向」「〇〇の度合い(=程度)」を表します。
※2:”〇〇性”の意味が複数ある場合は、”「~」など”のように一般的に用いられることが多い意味(「~」)を優先して表記しています。
| 漢字 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| 一過性 | いっかせい | 「病気の症状が、短期間現れてすぐに消える性質」など |
| 陰性 | いんせい | 「特定の病気や病原体が、体内に存在しない状態」 |
| 永続性 | えいぞくせい | 「物事が長続きする性質」 |
| 外向性 | がいこうせい | 「興味や関心が、自分以外の外部の物事に向かう性格特性」 |
| 蓋然性 | がいぜんせい | 「ある物事や事象が起こる確実性の度合い」 |
| 可燃性 | かねんせい | 「火をつけると燃えやすい性質」 |
| 感受性 | かんじゅせい | 「外界から受ける刺激や感情に対して、敏感(びんかん)に反応する性質」 |
| 慣性 | かんせい | 「物体が外部から力を加えられない限り、現在の運動状態を続けるという性質」 |
| 希少性 | きしょうせい | 「特定の物・情報・サービスなどが、人が欲している量(需要)に比べて、存在している量が少ないという状態」 |
| 帰巣性 | きそうせい | 「動物が、自分の巣から遠く離れても、再びそこに戻って来る性質」 |
| 機動性 | きどうせい | 「状況に応じて速やかに対応・行動できる能力」 |
| 機能性 | きのうせい | 「特定の目的や用途に対して、物やシステムなどの機能が適している度合い」 |
| 気密性 | きみつせい | 「気体を通さない性質」 |
| 機密性 | きみつせい | 「特定の情報など、正当な権限を持つ者だけが見たり触れたりできるように保護・管理される性質」 |
| 客観性 | きゃっかんせい | 「誰が見てもそうだと納得できる、そのものの性質」 |
| 吸湿性 | きゅうしつせい | 「空気中の水分(=水蒸気)を吸収する性質」 |
| 吸水性 | きゅうすいせい | 「水(液体)を吸収する性質」 |
| 急性 | きゅうせい | 「症状が急に起こり、症状の進み方が速い病気の性質」 |
| 具体性 | ぐたいせい | 「物事が詳細で明確に示され、曖昧(あいまい)さが排除されてはっきりと知ることができる性質」 |
| 県民性 | けんみんせい | 「日本の各都道府県に所属する人々に共通して見られる性格・習慣・考え方などの傾向」 |
| 抗菌性 | こうきんせい | 「細菌の発育や増殖を抑える性質」 |
| 後天性 | こうてんせい | 「遺伝でなく、生まれてから身についた性質」 |
| 合理性 | ごうりせい | 「無駄がなく、道理(物事の正しい筋道)に適っている物事の性質」 |
| 互換性 | ごかんせい | 「あるものを別のものに置き換えても問題なく機能する性質」 |
| 国民性 | こくみんせい | 「その国の国民に共通して見られる性格・習慣・考え方などの傾向」 |
| 漢字 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| 再現性 | さいげんせい | 「同じ条件・手順の下で、同じ事象が繰り返し発生したり、観察されたりする性質」 |
| 指向性 | しこうせい | 「音波・電波などの強さが、方向によって異なる性質」 |
| 自発性 | じはつせい | 「他から影響・強制されるわけではなく、自分から進んで行動できる性質」 |
| 遮音性 | しゃおんせい | 「音を遮(さえぎ)る性質。外部の音が聞こえないように、また、音が外に漏れないように遮る性質」 |
| 社会性 | しゃかいせい | 「集団を作って生活をするのに必要な性質。また、人間関係を形成し、それを円滑に維持するための社会生活を送る上で必要な能力」 |
| 柔軟性 | じゅうなんせい | 「状況に応じて適切に対応できる性質」など |
| 主観性 | しゅかんせい | 「自分自身の考え・感情・経験を基にした、そのものの性質」 |
| 主体性 | しゅたいせい | 「他から影響されずに、自分の意志・判断で行動できる性質」 |
| 受動性 | じゅどうせい | 「自分の意志からではなく、他からの働きかけによって動かされる性質」 |
| 将来性 | しょうらいせい | 「将来、発展・成功するだろうと見込まれる状態」 |
| 信憑性 | しんぴょうせい | 「証言・噂(うわさ)・口コミなどの情報が、どのくらい信用できるかの度合い」 |
| 親和性 | しんわせい | 「物事を組み合わせたときに相性が良く、結びつきやすい性質」など |
| 水性 | すいせい | 「水に溶けやすい性質。水溶性」など |
| 整合性 | せいごうせい | 「物事や言動に矛盾(むじゅん)がなく、整っている状態」 |
| 生産性 | せいさんせい | 「資源(労働・資本など)から付加価値を生み出す際の効率の度合い」 |
| 脆弱性 | ぜいじゃくせい | 「コンピューターのOSやソフトウェアにおいて、プログラムの不具合や設計上のミスが原因で発生した情報セキュリティ上の欠陥」など |
| 正当性 | せいとうせい | 「正しく道理(物事の正しい筋道)に適っている状態」 |
| 先天性 | せんてんせい | 「生まれつき備わっている性質」 |
| 速乾性 | そっかんせい | 「すぐに乾く性質」 |
| 耐火性 | たいかせい | 「火や高温にさらされても燃えない、または燃えにくい性質」 |
| 耐寒性 | たいかんせい | 「寒さに耐える性質」 |
| 耐震性 | たいしんせい | 「建築物や構造物などが、地震によって壊れにくい性質」 |
| 耐水性 | たいすいせい | 「水を通さず、水によって変質(変形・劣化など)しない性質」 |
| 耐熱性 | たいねつせい | 「高温にさらされても変質(変形・劣化など)しない性質」 |
| 惰性 | だせい | 「今まで続いてきた動作や習慣などをそのまま維持しようとする性質」など |
| 多様性 | たようせい | 「幅広く特徴・特性の異なるものが存在する状態」 |
| 断熱性 | だんねつせい | 「外部から熱が伝わるのを遮る性質」 |
| 通気性 | つうきせい | 「空気を通す性質」 |
| 透明性 | とうめいせい | 「制度の運営や組織の活動状況が、誰にでも理解できるように示されているかの度合い」 |
| 特異性 | とくいせい | 「他のものにはない、そのものにだけ備わっている特別な性質」 |
| 独創性 | どくそうせい | 「他人の真似ではなく、独自の考えで物事をつくり出す性質・能力」 |
| 内向性 | ないこうせい | 「興味や関心が、自分の内部に向かう性格特性」 |
| 人間性 | にんげんせい | 「人間として生まれつき備わっている性質」 |
| 能動性 | のうどうせい | 「自分から他に働きかける性質」 |
| 撥水性 | はっすいせい | 「水をはじく性質」 |
| 必然性 | ひつぜんせい | 「必ずそのような状態になると決まっていて、それ以外の状態になる可能性はないという性質」 |
| 不活性 | ふかっせい | 「化学反応を起こしにくい性質」 |
| 不燃性 | ふねんせい | 「燃えない、あるいは燃えにくい性質」 |
| 普遍性 | ふへんせい | 「全ての物事に当てはまる性質」 |
| 不溶性 | ふようせい | 「液体に溶けない性質」 |
| 保温性 | ほおんせい | 「一定の温かさを保つ性質」 |
| 保水性 | ほすいせい | 「水分(液体)を保つ性質」 |
| 慢性 | まんせい | 「症状の程度はひどいものではないが、完治するのが難しく、その症状が長期にわたって持続する病気の性質」 |
| 油性 | ゆせい | 「油に溶けやすい性質。油溶性」など |
| 陽性 | ようせい | 「特定の病気や病原体が、体内に存在している状態」 |
| 理性 | りせい | 「本能や感情に左右されず、筋道を立てて物事を冷静に考えて判断する能力」 |
| 利便性 | りべんせい | 「便利さの度合い」 |
| 流動性 | りゅうどうせい | 「資産や商品を、損失なく迅速に現金化できる容易さの度合い」など |
【〇〇性】よく使う言葉
※1:”〇〇性”は、「〇〇の性質・能力」「〇〇の状態・傾向」「〇〇の度合い(=程度)」を表します。
※2:”〇〇性”の意味が複数あって、その内の1つの意味だけ特によく用いられる場合は、その意味の横に”⇐一般的によく用いられる”と表記(表記していない場合はどの意味も比較的用いられる)しています。
↓ア行~
【一過性】
読み方:いっかせい
一過性の意味は、
- 病気の症状が、短期間現れてすぐに消える性質
- 現象が、一時的ですぐに消える状態
意味1の例文 「それらの症状は一過性のもので、症状が消えたからといって病気が治ったわけではない」
意味2の例文 「一過性のブームで終わらせないために、定番として長く愛される商品作りを目指している」
【陰性】
読み方:いんせい
陰性の意味は、”特定の病気や病原体が、体内に存在しない状態”。
陰性の対義語は「陽性(ようせい)」で、陰性の英語は「negative(ネガティブ)」になります。
例文1 「彼は薬物検査を受けたが、検査の結果は陰性だった」
例文2 「その病気の初期段階では陰性を示すこともあるので、まだ確実なことは言えない」
【永続性】
読み方:えいぞくせい
永続性の意味は、”物事が長続きする性質”。
例文1 「その事業は国が主体となって運営されていることから、永続性が保証されているようなものだ」
例文2 「価値が高く永続性のあるサービスの実現に向けて努力を重ねてきた」
↓カ行~
【外向性】
読み方:がいこうせい
外向性の意味は、”興味や関心が、自分以外の外部の物事に向かう性格特性”。
外向性は例えば、他人に対して積極的に話しかけたり、他人との交流を好むような性格を指します。
外向性の対義語は、「内向性(ないこうせい)」です。
例文1 「彼は昔から外向性があり、さらに行動力もあるため成功しているのは不思議ではない」
例文2 「外向性が高い人ほど、そのような欲求も強いことが研究結果から見てとれる」
【蓋然性】
読み方:がいぜんせい
蓋然性の意味は、”ある物事や事象が起こる確実性の度合い”。
「蓋然性が高い=それが起こる確率が高い」、「蓋然性が低い=それが起こる確率が低い」ということを指します。
蓋然性の対義語は、「必然性(ひつぜんせい)」です。
例文1 「蓋然性が低くても、成功する可能性がゼロでないなら試す価値はある」
例文2 「その件については蓋然性の問題に過ぎないので、彼を信用しているかどうかは全く関係ない」
【可燃性】
読み方:かねんせい
可燃性の意味は、”火をつけると燃えやすい性質”。
可燃性の対義語は、「不燃性(ふねんせい)」です。
例文1 「その工場では、過去に可燃性ガスを原因とした爆発事故が発生していた」
例文2 「それは可燃性の材料で作られているため、火気には十分注意しなければならない」
【感受性】
読み方:かんじゅせい
感受性の意味は、”外界から受ける刺激や感情に対して、敏感(びんかん)に反応する性質”。
例えば、映画の登場人物に感情移入しやすかったり、些細(ささい)なことで喜んだり悲しんだりする人は「感受性が高い(豊かな)人」だと言えます。
例文1 「彼女は感受性が豊かなので、他の人に比べてストレスがたまりやすいのだろう」
例文2 「彼は幼いころから感受性に欠けていて、喜んだり泣いたりしている姿を一度も見たことがない」
【慣性】
読み方:かんせい
慣性の意味は、”物体が外部から力を加えられない限り、現在の運動状態を続けるという性質”。
身近な慣性の例として、「人の乗っている電車が止まっている状態から走り出す場合」と「電車が走っているときにブレーキをして減速する場合」をそれぞれ見ていきます。
まず「人の乗っている電車が止まっている状態から走り出す場合」は、電車とその中にいる人が止まっている状態から考えていきます。
上図のように電車が動き出すと、電車は進行方向へ力が働くため、電車の床に接している足も同じように進行方向へと動きます。
足以外の部分は慣性によって止まっている状態を維持し続けようとし、足だけが進行方向に進むので、体は後ろ(進行方向と逆側)によろめきます。
次に「電車が走っているときにブレーキをして減速する場合」は、電車とその中にいる人が進行方向に力が働いている状態から考えていきます。
上図のように電車がブレーキで減速すると、電車は進行方向と逆の方向に力が働くため、電車の床に接している足も同じように進行方向と逆の方向へと動きます。
足以外の部分は慣性によって進行方向へと進み続けようとし、足は進行方向と逆の方向に進むので、体は前(進行方向側)によろめきます。
例文1 「人工衛星は地球の周りを慣性飛行しているが、地球に落下することはない」
例文2 「エレベーターが下降するときに慣性によって体が一瞬軽くなったように感じる」
【希少性】
読み方:きしょうせい
希少性の意味は、”特定の物・情報・サービスなどが、人が欲している量(需要)に比べて、存在している量が少ないという状態”。
「希少性が高い=人が欲している量に比べて、存在している量が少ない」、「希少性が低い=人が欲している量に比べて、存在している量が多い」ということを意味しています。
例えば、金はその見た目から様々な装飾品に使われ人気があり、地球上で採掘できる量に限りがあるため希少性が高いです。
仮に金がどこにでも落ちていて誰でも大量に持っていけるようなものなら、今よりも金の希少性はもっと低くなるでしょう。
例文1 「希少性の高さを維持するために、あえて市場への流通量を減らしている」
例文2 「そのカードは世界に3枚しか存在しておらず、1枚数億円で取引されていることからも希少性の高さがうかがえる」
【帰巣性】
読み方:きそうせい
帰巣性の意味は、”動物が、自分の巣から遠く離れても、再びそこに戻って来る性質”。
例文1 「鳩(ハト)は、その帰巣性の高さから通信手段に用いられている」
例文2 「あんなに遠い場所からここまで戻ってくるなんて、動物の帰巣性には驚くばかりだ」
【機動性】
読み方:きどうせい
機動性の意味は、”状況に応じて速やかに対応・行動できる能力”。
機動性の英語は、「mobility(モビリティ)」です。
例文1 「全体的に機体重量を軽量化して、機動性を重視する作りになっている」
例文2 「部隊の人数を増やしすぎると、機動性が失われてしまうのが問題だ」
【機能性】
読み方:きのうせい
機能性の意味は、”特定の目的や用途に対して、物やシステムなどの機能が適している度合い”。
例文1 「機能性を重視しているので、見た目は派手なものでなければ問題ない」
例文2 「いつも彼は機能性よりも好みのデザインかどうかで車を選んでいる」
【気密性】
読み方:きみつせい
気密性の意味は、”気体を通さない性質”。
もっと詳しく言うと、”密閉した空間内に存在する気体が外部にもれない、または減圧した空間内に外部から気体が流入しない性質”です。
「気密性が高い=気体を通しにくい=気体が外部にもれにくく、内部に流入しにくい」、「気密性が低い=気体を通しやすい=気体が外部にもれやすく、内部に流入しやすい」ということを意味します。
気密性の対義語は、「通気性(つうきせい)」です。
例文1 「このマンションは気密性が低く、外気が出入りしやすいため冷暖房が効きにくい」
例文2 「気密性の高い部屋のはずだが、外から甘い香りが漂ってきたのでどこかに隙間がないか点検した」
【機密性】
読み方:きみつせい
機密性の意味は、”特定の情報など、正当な権限を持つ者だけが見たり触れたりできるように保護・管理される性質”。
「機密性が高い=その情報などの重要度が高く、正当な権限を持つ者だけが見たり触れたりできるようにしっかりと保護・管理されている」ということを意味します。
例文1 「その情報は機密性が高く、幹部の中でもごく少数の人しか知らないとされている」
例文2 「この技術により、データ転送時における情報の完全な機密性を保持することができている」
【客観性】
読み方:きゃっかんせい
客観性の意味は、”誰が見てもそうだと納得できる、そのものの性質”。
客観性の対義語は、「主観性(しゅかんせい)」です。
例文1 「その記録は彼のみで行われた実験結果を基にしたもので、客観性はないに等しい」
例文2 「客観性を増すためにも全員の前で実演した方が良いのではないか」
【吸湿性】
読み方:きゅうしつせい
吸湿性の意味は、”空気中の水分(=水蒸気)を吸収する性質”。
空気は、水蒸気(水が蒸発して気体に変化したもの)を含むことができ、”空気中に含まれている水蒸気の割合(%)”を「湿度(しつど)」と言います。
「吸湿性が高い=空気中の水分を吸収しやすい」、「吸湿性が低い=空気中の水分を吸収しにくい」ということを意味しています。
例文1 「生石灰は強い吸湿性を持つため、乾燥剤として使われることも多い」
例文2 「この素材は吸湿性があるため、使わないときは密閉された容器に保管されている」
【吸水性】
読み方:きゅうすいせい
吸水性の意味は、”水(液体)を吸収する性質”。
「吸水性が高い=水(液体)を吸収しやすい」、「吸水性が低い=水(液体)を吸収しにくい」ということを意味しています。
例文1 「この素材には吸水性がないため、タオルなどには向かない」
例文2 「新聞紙は表面にコーティング処理が施されていないので、一般的な他の紙よりも吸水性が高い」
【急性】
読み方:きゅうせい
急性の意味は、”症状が急に起こり、症状の進み方が速い病気の性質”。
急性の対義語は、「慢性(まんせい)」です。
例文1 「彼女は急性心不全によって倒れたが、少しずつ回復してきているそうだ」
例文2 「彼は飲み会でのビールの一気飲みが原因で、急性アルコール消毒に陥り病院に搬送された」
【具体性】
読み方:ぐたいせい
具体性の意味は、”物事が詳細で明確に示され、曖昧(あいまい)さが排除されてはっきりと知ることができる性質”。
具体性の対義語は、「抽象性(ちゅうしょうせい)」です。
例文1 「私が質問すると、彼からは何の解決にもならない具体性のない答えが返ってきた」
例文2 「彼女の話は内容が具体性に欠けていて、いくら説明されてもいまいち全体像が見えてこない」
【県民性】
読み方:けんみんせい
県民性の意味は、”日本の各都道府県に所属する人々に共通して見られる性格・習慣・考え方などの傾向”。
例文1 「彼はその土地に住んでいる人々を取材して、県民性を調べていた」
例文2 「沖縄県民の県民性として、のんびりとしていておおらかな性格のイメージがある」
【抗菌性】
読み方:こうきんせい
抗菌性の意味は、”細菌の発育や増殖を抑える性質”。
抗菌性の英語は、「antibacterial(アンチバクテリアル)」です。
例文1 「接触による感染を防ぐために、持ち手の部分は抗菌性のある素材が使われている」
例文2 「その物質は抗菌性を持っているので、石鹸・洗剤などの成分に含まれることが多い」
【後天性】
読み方:こうてんせい
後天性の意味は、”遺伝でなく、生まれてから身についた性質”。
後天性の対義語は、「先天性(せんてんせい)」です。
例文1 「その病気は後天性のもので、未だに詳しい原因は分かっていない」
例文2 「彼の素晴らしい能力は、今まで彼が努力を積み重ねてきたことで得た後天性のものだ」
【合理性】
読み方:ごうりせい
合理性の意味は、”無駄がなく、道理(物事の正しい筋道)に適っている物事の性質”。
例文1 「経営者が自分の事業の合理性を追求するのは当然のことである」
例文2 「彼は自信満々に説明してくれたが、合理性に欠けているため採用されることはないだろう」
【互換性】
読み方:ごかんせい
互換性の意味は、”あるものを別のものに置き換えても問題なく機能する性質”。
「互換性がある=別のものに置き換えても問題なく機能する」、「互換性がない=別のものに置き換えると機能しなくなる」をいうことを意味します。
例えば「最新製品に使われている部品は、旧製品に使われている部品と互換性がある」のであれば、最新製品の部品が壊れても、互換性のある旧製品の部品を代わりに取りつければ、最新製品は問題なく機能する、という意味です。
例文1 「製品に使われている部品はどれも規格化されているので、互換性は十分に確保されている」
⇒製品の部品は、どれも品質・形状・寸法などが一律に定められた基準で作られていて、交換・修理の際に規格化された部品であれば代わりにすぐに用意して交換することができる
例文2 「無線機は機種やメーカーが違っても互換性はあるので、基本的には交信することができる」
【国民性】
読み方:こくみんせい
国民性の意味は、”その国の国民に共通して見られる性格・習慣・考え方などの傾向”。
国民性の英語は、「national character(ナショナル キャラクター)」です。
例文1 「都市が清潔に保たれているのは国民性によるものだろう」
例文2 「国民性の違いによって苦労することはあるが、否定するのではなくお互いの文化や考え方を尊重するのが大切だ」
↓サ行~
【再現性】
読み方:さいげんせい
再現性の意味は、”同じ条件・手順の下で、同じ事象が繰り返し発生したり、観察されたりする性質”。
「再現性がある=同じ条件・同じ手順の下で実験などを行い、それを何度行っても同じ結果になる」ということを意味します。
また「再現性が高い=同じ条件・手順で行うと、同じ結果が得られやすい」、「再現性が低い=同じ条件・手順で行っても、同じ結果が得られにくい」ということを意味しています。
例文1 「成功者のやり方を真似しても、それが再現性の高いものだとは限らない」
例文2 「そのノウハウに再現性がなかったのではなく、彼が怠けてやるべきことをやっていなかっただけだ」
【指向性】
読み方:しこうせい
指向性の意味は、”音波・電波などの強さが、方向によって異なる性質”。
「指向性が高い(強い)=音波・電波などの放射される角度(範囲)が狭い=目的方向にエネルギーが集中するので放射される音波・電波などが強くなる」、「指向性が低い(弱い)=音波・電波などの放射される角度(範囲)が広い=色々な方向にエネルギーが分散するので放射される音波・電波などが弱くなる」ということを意味します。
例文1 「パラボラアンテナは指向性アンテナなので、信号の送受信を効率よく行うことができる」
例文2 「指向性スピーカーが搭載されているため、特定の場所にいる人だけに音を届けることができる」
【自発性】
読み方:じはつせい
自発性の意味は、”他から影響・強制されるわけではなく、自分から進んで行動できる性質”。
自発性の対義語は、「受動性(じゅどうせい)」です。
例文1 「小さな成功体験を積ませていくことで、仕事における彼の自発性も高まっていくだろう」
例文2 「子どもの自発性を育むことは、自分から友達を誘って繋がりを深めたり、熱中できるものを見つけるためにも重要だ」
【遮音性】
読み方:しゃおんせい
遮音性の意味は、”音を遮(さえぎ)る性質。外部の音が聞こえないように、また、音が外に漏れないように遮る性質”。
「遮音性が高い=外部の音が聞こえにくく、内部の音も外に漏れにくい」、「遮音性が低い=外部の音が聞こえやすく、内部の音も外に漏れやすい」ということを意味しています。
例文1 「ここは遮音性の高い部屋だから、先ほどの大声も外には聞こえていないはずだ」
例文2 「壁や天井には遮音性の高い素材を使っているため、この部屋にはお金もそれなりにかかっている」
【社会性】
読み方:しゃかいせい
社会性の意味は、”集団を作って生活をするのに必要な性質。また、人間関係を形成し、それを円滑に維持するための社会生活を送る上で必要な能力”。
例文1 「人間だけでなく他の動物も社会性が強く、群れを作って行動することが多い」
例文2 「彼に社会性を身につけて欲しいと思う一心で去年から学校に通わせている」
【柔軟性】
読み方:じゅうなんせい
柔軟性の意味は、
- 柔らかく、しなやかな性質
- 状況に応じて適切に対応できる性質
柔軟性の英語は、「flexibility(フレキシビリティ)」です。
意味1の例文 「体の柔軟性を高めることで、運動でのパフォーマンスが上がるだけでなく、ケガもしにくくなる」
意味2の例文 「上司は柔軟性に欠ける指示を出すことが多く、いつも自分で判断して行動している」
【主観性】
読み方:しゅかんせい
主観性の意味は、”自分自身の考え・感情・経験を基にした、そのものの性質”。
主観性の対義語は、「客観性(きゃっかんせい)」です。
例文1 「それは彼の主観性の強い意見であって、チームメンバーの総意ではない」
例文2 「審査員の好みだけで優勝が決まるような採点方法ではなく、主観性を排除した採点方法であるべきだ」
【主体性】
読み方:しゅたいせい
主体性の意味は、”他から影響されずに、自分の意志・判断で行動できる性質”。
主体性の対義語は、「受動性(じゅどうせい)」です。
例文1 「主体性を持って発生した問題を解決する」
例文2 「彼は主体性がないわけではないが、やや自己主張に欠けているのが残念だ」
【受動性】
読み方:じゅどうせい
受動性の意味は、”自分の意志からではなく、他からの働きかけによって動かされる性質”。
受動性の対義語は、「能動性(のうどうせい)」「自発性(じはつせい)」「主体性(しゅたいせい)」です。
例文1 「子どもの頃に受動性を刷り込まれたせいで、大人になってからも自分から行動できずにいる」
例文2 「受動性の強さは、いうなれば自身のなさを表しており、まずは自己肯定感を高めることが必要だ」
【将来性】
読み方:しょうらいせい
将来性の意味は、”将来、発展・成功するだろうと見込まれる状態”。
例文1 「彼は将来性が評価されて国の代表選手に選出された」
例文2 「昔から将来性のない仕事だと言われ続けてきたが、何だかんだで30年もこの仕事を続けている」
【信憑性】
読み方:しんぴょうせい
信憑性の意味は、”証言・噂(うわさ)・口コミなどの情報が、どのくらい信用できるかの度合い”。
「信憑性が高い(信憑性がある)=その情報が信用できる度合いが高い=信用できる」、「信憑性が低い(信憑性がない)=その情報が信用できる度合いが低い=あまり信用できない」ということを意味します。
例文1 「彼の証言は、彼の持ってきた証拠からも分かるように、信憑性が非常に高いとされている」
例文2 「出まかせかと思っていた彼の話も、あながち信憑性がない話というわけでもなさそうだ」
【親和性】
読み方:しんわせい
親和性の意味は、
- ある物質が他の物質と容易に結合する性質
- 物事を組み合わせたときに相性が良く、結びつきやすい性質
「親和性が高い(親和性がある)=相性が良く、結びつきやすい」、「親和性が低い(親和性がない)=相性が悪く、結びつきにくい」ということを意味します。
意味1の例文 「水とエタノールは親和性が高いので混ざりやすいが、水と油は親和性が低いので混ざりにくい」
意味2の例文 「当社のサービスは、御社のサービスとの親和性が非常に高いため、相乗効果が期待できる」
【水性】
読み方:すいせい
水性の意味は、
- 水の性質。水質
- 水に溶けやすい性質。水溶性(すいようせい)(⇐一般的によく用いられる)
水性(意味2)の対義語は、「油性(ゆせい)」です。
意味2の例文1 「水性塗料は、完全に乾燥すれば塗膜が形成されるので、水に濡れても問題はない」
意味2の例文2 「ペンキには水性のものと油性のものが存在するため、用途によって使い分けるのが良い」
【整合性】
読み方:せいごうせい
整合性の意味は、”物事や言動に矛盾(むじゅん)がなく、整っている状態”。
「整合性がある=物事や言動が矛盾していない(整っている状態)」、「整合性がない=物事や言動が矛盾している(整っていない状態)」ということを意味しています。
またよく用いられる表現で「整合性を取る=物事や言動が矛盾しない状態にすること」、「整合性を図る=物事や言動が矛盾しないように試みること」、「整合性を保つ=物事や言動が矛盾しない状態を維持すること」を意味しています。
整合性の英語は、「consistency(コンシステンシー)」です。
例文1 「彼の証言は整合性が取れていて、何も問題はないように感じる」
例文2 「登場人物が増えてくると、その分だけ物語の整合性を保つのが難しくなる」
【生産性】
読み方:せいさんせい
生産性の意味は、”資源(労働・資本など)から付加価値を生み出す際の効率の度合い”。
例えば、1の価値を持つ資源を使って3の価値を持つ商品Aができたら付加価値は「2」で、1の価値を持つ資源を使って10の価値を持つ商品Bができたら付加価値は「9」になります。
この商品Aと商品Bを作る際の生産性を比較するなら、商品Aの場合は「生産性が低い」、商品Bの場合は「生産性が高い」ということを指します。
つまり「生産性が高い=資源から付加価値を生み出す際の効率が良い」、「生産性が低い=資源から付加価値を生み出す際の効率が悪い」ということを意味しています。
生産性の英語は、「productivity(プロダクティビティ)」です。
例文1 「無駄な業務を減らして生産性を向上させたことで売り上げが大幅に伸びた」
例文2 「何でも自分でやろうとするのは生産性を下げるので、誰でもできる作業であれば他の人に任せた方が良い」
【脆弱性】
読み方:ぜいじゃくせい
脆弱性の意味は、
- 脆(もろ)くて弱い性質
- コンピューターのOSやソフトウェアにおいて、プログラムの不具合や設計上のミスが原因で発生した情報セキュリティ上の欠陥
意味1の例文 「今回の件で、一企業に支えられている地域経済の脆弱性を思い知らされた」
意味2の例文 「ソフトウェアにに脆弱性が発見されたため、すぐにセキュリティ更新プログラムが提供された」
【正当性】
読み方:せいとうせい
正当性の意味は、”正しく道理(物事の正しい筋道)に適っている状態”。
例文1 「彼の主張には正当性がなく、最後まで判決は覆らなかった」
例文2 「彼女の行動の正当性は長らく議論されていたが、遂に正当性が認められた」
【先天性】
読み方:せんてんせい
先天性の意味は、”生まれつき備わっている性質”。
先天性の対義語は、「後天性(こうてんせい)」です。
例文1 「それは先天性の障害で、努力でどうにかできるものではない」
例文2 「先天性の病気の場合、完治させることはできなくても症状の悪化を抑えることはできる」
【速乾性】
読み方:そっかんせい
速乾性の意味は、”すぐに乾く性質”。
「速乾性が高い(速乾性に優れる)=すぐに乾きやすい」、「速乾性が低い(速乾性に劣る)=すぐには乾きにくい」ということを意味しています。
例文1 「この素材は吸水性だけでなく速乾性にも優れているので、スポーツウェアとして使うのが良い」
例文2 「速乾性の高いインクなので、書いてからすぐに指で触れても、指にインクがつかない」
↓タ行~
【耐火性】
読み方:たいかせい
耐火性の意味は、”火や高温にさらされても燃えない、または燃えにくい性質”。
「耐火性が高い=火や高温にさらされても燃えない、または燃えにくい」、「耐火性が低い=火や高温にさらされるとすぐに燃えてしまう」ということを意味しています。
例文1 「耐火性については考慮されていないため、火をつけるとすぐに燃えてしまう」
例文2 「これは耐火性に優れている素材なので、耐火シートなどの素材として用いられる」
【耐寒性】
読み方:たいかんせい
耐寒性の意味は、”寒さに耐える性質”。
例えば、生物・植物であれば低い温度でどれだけ耐えて生き延びることができるか、ゴムなどの素材であれば低すぎる温度だと硬化するので、どれだけ硬化せずに耐えられるかを示します。
「耐寒性が高い=低い温度でもよく耐える」、「耐寒性が低い=低い温度には耐えられない」ということを意味しています。
例文1 「その植物は耐寒性のなさから、冬になると枯れてしまう」
例文2 「寒い地方に生息しているのは、耐寒性の高い生物であるのは当然だ」
【耐震性】
読み方:たいしんせい
耐震性の意味は、”建築物や構造物などが、地震によって壊れにくい性質”。
(”建築基準法によって定められた、建築物や構造物が一定の強さの地震に耐えられるようにするための最低限の基準のこと”を「耐震基準」と言います)
「耐震性が高い=建築物や構造物などが、地震によって壊れにくい」、「耐震性が低い=建築物や構造物などが、地震によって壊れやすい」ということを意味しています。
例文1 「耐震性を高めるために、もっと予算を増やす必要がある」
例文2 「建築物の耐震性に問題があることが判明したため、早急に耐震補強等の措置を講じなければならない」
【耐水性】
読み方:たいすいせい
耐水性の意味は、”水を通さず、水によって変質(変形・劣化など)しない性質”。
「耐水性が高い=水を通しにくく、水によって変質しにくい」、「耐水性が低い=水を通しやすく、水によって変質しやすい」ということを意味しています。
例文1 「耐水性に優れているため、水を入れても漏れたりすることはない」
例文2 「このインクは書いた直後は耐水性が低いが、乾燥すると高い耐水性を持つようになる」
【耐熱性】
読み方:たいねつせい
耐熱性の意味は、”高温にさらされても変質(変形・劣化など)しない性質”。
「耐熱性が高い=高温にさらされても変質しにくい」、「耐熱性が低い=高温にさらされると変質しやすい」ということを意味しています。
例文1 「これは耐熱性のガラス容器なので、熱湯を入れても問題はない」
例文2 「その周辺は高温環境となるため、耐熱性の高い素材でできた部品が必要だ」
【惰性】
読み方:だせい
惰性の意味は、
- 今まで続いてきた動作や習慣などをそのまま維持しようとする性質
- 物体が外部から力を加えられない限り、現在の運動状態を続けるという性質。慣性
意味1の例文 「私はただ惰性で仕事をしているだけで、この仕事に働きがいを感じているわけではない」
意味2の例文 「この物体が惰性(=慣性)で進む速度を調べる」
【多様性】
読み方:たようせい
多様性の意味は、”幅広く特徴・特性の異なるものが存在する状態”。
例えば多様性社会というと、「性別、年齢、国籍、文化、価値観、能力など、多様な人々が共存し、それぞれの持っている力を最大限に発揮できる社会」を指します。
多様性の対義語は「画一性(かくいつせい)」で、多様性の英語は「diversity(ダイバーシティ)」です。
例文1 「今まで行われてきた教育の結果として、現在では考え方の多様性が失われてきていると感じる」
例文2 「自分たちの価値観だけが正しいと思うのではなく、時には多様性を認めることも大切だ」
【断熱性】
読み方:だんねつせい
断熱性の意味は、”外部から熱が伝わるのを遮(さえぎ)る性質”。
熱は、温度の高いもの(熱の量が多い)だけでなく、温度の低いもの(熱の量が少ない)でも持っているので、冷たいものの熱を遮る場合も「断熱」という言葉は使われます。
「断熱性が高い=外部からの熱が伝わりにくい」、「断熱性が低い=外部からの熱が伝わりやすい」ということを意味しています。
例えば、断熱性の高い家であれば、外気の影響を受けにくくなるので、室内の温度が一定に保たれやすく(夏は涼しく、冬は暖かく)なります。
例文1 「断熱性が高い断熱材を使っているので、値段もそれなりに高くなる」
例文2 「我が家は断熱性が非常に悪いため、冷暖房をつけてもほとんど効いている感じがしない」
【通気性】
読み方:つうきせい
通気性の意味は、”空気を通す性質”。
「通気性が良い(通気性が高い)=空気を通しやすい」、「通気性が悪い(通気性が低い)=空気を通しにくい」ということを意味しています。
通気性の対義語は、「気密性(きみつせい)」です。
例文1 「蒸れに弱いため、通気性の良い素材で作っている」
例文2 「通気性が悪いと汗が蒸発できないので、夏場は体を冷やすことができず大変だ」
【透明性】
読み方:とうめいせい
透明性の意味は、”制度の運営や組織の活動状況が、誰にでも理解できるように示されているかの度合い”。
「透明性が高い=制度の運営や組織の活動状況が、誰にでも理解できるように示されている」、「透明性が低い=制度の運営や組織の活動状況が、誰にでも理解できるように示されていない」ということを意味しています。
例文1 「企業の透明性を確保するためにも、経営状況は毎年公開している」
例文2 「行政運営は税金で行われているのだから、税金の使い方の透明性が低いなんてことはあってはならない」
【特異性】
読み方:とくいせい
特異性の意味は、”他のものにはない、そのものにだけ備わっている特別な性質”。
特異性の対義語は、「一般性(いっぱんせい)」です。
例文1 「その行動は彼の特異性を示すと同時に、彼がどれだけ危険な存在であるかも示している」
例文2 「いま現在の状況を見るだけでも、この事件の特異性が分かる」
【独創性】
読み方:どくそうせい
独創性の意味は、”他人の真似ではなく、独自の考えで物事をつくり出す性質・能力”。
例文1 「この作品をきっかけに、彼の芸術における独創性が認められるようになった」
例文2 「独創性がないからといって、自分には何も才能がないと諦めるのは早すぎる」
↓ナ行~
【内向性】
読み方:ないこうせい
内向性の意味は、”興味や関心が、自分の内部に向かう性格特性”。
内向性は例えば、他人と積極的にコミュニケーションを取るのが苦手で、一人で過ごす時間を好むような性格を指します。
内向性の対義語は、「外向性(がいこうせい)」です。
例文1 「内向性の人は、コミュニケーションを取るのが苦手な傾向にある」
例文2 「内向性を持っていることは弱みではなく、見方を変えれば外向性にはない強みがあるということだ」
【人間性】
読み方:にんげんせい
人間性の意味は、”人間として生まれつき備わっている性質”。
例えば「他人に対する思いやりの心や気遣いの気持ち、愛情などの内面的な感情のこと」を指し、人間性に外見は含まれません。
例文1 「その一件から、彼の人間性を疑問視する声が上がるようになった」
例文2 「こんなことを長年続けていると、少しずつ人間性が失われていくような感覚がある」
【能動性】
読み方:のうどうせい
能動性の意味は、”自分から他に働きかける性質”。
能動性の対義語は、「受動性(じゅどうせい)」です。
例文1 「能動性を排し受け身に徹することで、周りを先に動き出させるように仕向けた」
例文2 「能動性を持っていないということは、成長する力を持っていないに等しいと言える」
↓ハ行~
【撥水性】
読み方:はっすいせい
撥水性の意味は、”水をはじく性質”。
「撥水性が高い=水をはじきやすい(濡れにくい)」、「撥水性が低い=水をはじきにくい(濡れやすい)」ということを意味しています。
撥水性の対義語は、「親水性(しんすいせい)」です。
例文1 「表面を撥水性の高い物質でコーティングしているので、その部分から濡れることはない」
例文2 「葉の表面には撥水性があるため、水滴ははじかれて水玉となって滑り落ちていく」
【必然性】
読み方:ひつぜんせい
必然性の意味は、”必ずそのような状態になると決まっていて、それ以外の状態になる可能性はないという性質”。
必然性の対義語は、「偶発性(ぐうはつせい)」「蓋然性(がいぜんせい)」です。
例文1 「彼の話には必然性がなく、ただの結果論でしかなかった」
例文2 「何度も彼に裏切られてきたのだから、彼女が彼の行動を疑う必然性を理解することはできる」
【不活性】
読み方:ふかっせい
不活性の意味は、”化学反応を起こしにくい性質”。
不活性化というと、「不活性な状態へと変化させること」を意味しています。
不活性の対義語は、「活性(かっせい)」です。
例文1 「ムカデの毒は熱に弱く、42℃以上で不活性化するので、患部をお湯で5分以上洗い流すのが良い」
⇒ムカデの毒は42℃以上になると毒成分の性質が変化する(体内で化学反応を起こさなくなる)ので、患部をお湯で洗浄することでムカデの毒を無毒化できる
例文2 「袋内に窒素などの不活性ガスを充填することで、材料や製品を劣化させる不要な化学反応を防ぐ役割がある」
⇒窒素などの不活性ガス(化学反応を起こしにくい気体)を袋内に満たすと、袋内に存在する酸素などが激減するため酸化などの材料や製品を劣化させる化学反応を防ぐことができる
【不燃性】
読み方:ふねんせい
不燃性の意味は、”燃えない、あるいは燃えにくい性質”。
不燃性の対義語は、「可燃性(かねんせい)」です。
例文1 「これは壁も天井もすべて不燃性の材料が使われている建築物だ」
例文2 「不燃性ではあるが、ある温度以上まで温度が上がると有毒ガスを発生させてしまう」
【普遍性】
読み方:ふへんせい
普遍性の意味は、”全ての物事に当てはまる性質”。
普遍性の対義語は「希少性(きしょうせい)」、普遍性の英語は「universality(ユニバーサリティ)」です。
例文1 「彼女は歌詞に普遍性を持たせることで、幅広い年代から共感され支持を得ている」
例文2 「物質の物理特性には普遍性があり、エネルギー保存則などの物理法則はどこにいても成立する」
【不溶性】
読み方:ふようせい
不溶性の意味は、”液体に溶けない性質”。
不溶性の対義語は、「可溶性(かようせい)」です。
例文1 「水に対しては不溶性だが、油に対しては可溶性である」
例文2 「資料によるとその物質は、多くの液体への不溶性を示していることが分かる」
【保温性】
読み方:ほおんせい
保温性の意味は、”一定の温かさを保つ性質”。
「保温性が高い=温かさを保ちやすい」、「保温性が低い=温かさを保ちにくい」ということを意味しています。
例文1 「保温性を高めるために、真空構造になっている」
例文2 「ダウンジャケットは繊維の隙間に多くの空気が含まれているので、保温性が高くなっている」
⇒空気は熱を伝えにくい物質で、その空気が多く含まれていることで体温が外へと逃げにくくなる(=保温性が高い)
【保水性】
読み方:ほすいせい
保水性の意味は、”水分(液体)を保つ性質”。
「保水性が高い=水分(液体)を保ちやすい」、「保水性が低い=水分(液体)を保ちにくい」ということを意味しています。
例文1 「植物を育てるには、保水性の高い土壌が理想的だ」
例文2 「これは食品の保水性向上に効果がある製品で、使用者からの評判も良い」
↓マ行~
【慢性】
読み方:まんせい
慢性の意味は、”症状の程度はひどいものではないが、完治するのが難しく、その症状が長期にわたって持続する病気の性質”。
慢性の対義語は、「急性(きゅうせい)」です。
例文1 「鈍い痛みを伴う慢性の腰痛があり、定期的に病院に通っている」
例文2 「慢性のものであれば症状は大したものではないが、完治させるのには長い時間がかかる」
↓ヤ行~
【油性】
読み方:ゆせい
油性の意味は、
- 油の性質
- 油に溶けやすい性質。油溶性(ゆようせい)⇐(一般的によく用いられる)
油性(意味2)の対義語は、「水性(すいせい)」です。
意味2の例文1 「油性ペンで書いたので、水で洗ってもなかなか消えない」
意味2の例文2 「ビニールには撥水性があり、水性ペンでは弾かれるから油性ペンを使うのが良い」
【陽性】
読み方:ようせい
陽性の意味は、”特定の病気や病原体が、体内に存在している状態”。
陽性の対義語は「陰性(いんせい)」で、陽性の英語は「positive(ポジティブ)」になります。
例文1 「検査を受けて陽性だったので、明日の予定はキャンセルした」
例文2 「全ての検査には”偽陽性(ぎようせい)”と呼ばれる、本来は陰性なのに、誤って陽性と判定される場合がある」
↓ラ行~
【理性】
読み方:りせい
理性の意味は、”本能や感情に左右されず、筋道を立てて物事を冷静に考えて判断する能力”。
理性の対義語は、「感性(かんせい)」です。
例文1 「理性を失ってしまったら、見た目は人間でも獣と同じようなものだ」
例文2 「人間の持っている本能から生まれる欲望を、理性だけでコントロールするのはなかなか難しい」
【利便性】
読み方:りべんせい
利便性の意味は、”便利さの度合い”。
「利便性が高い(利便性が良い)=便利である」、「利便性が低い(利便性が悪い)=便利ではない」ということを意味しています。
例文1 「利便性が高いことから、駅の周辺にはデパートや商店街があることが多い」
例文2 「そこの近くには駅もバス停もないので交通の利便性が悪く、基本的には車で行くことしかできない」
【流動性】
読み方:りゅうどうせい
流動性の意味は、
- 液体や気体などのように、一定せず流れ動く性質
- 資産や商品を、損失なく迅速に現金化できる容易さの度合い
「流動性が高い(意味1)=流れるのが速く動きやすい(例:水)」、「流動性が低い(意味1)=流れるのが遅く動きにくい(例:はちみつ)」ということを意味しています。
「流動性が高い(意味2)=取引量が多くて売却しやすいため、現金化しやすい」、「流動性が低い(意味2)=取引量が少なくて売却しにくかったり、売却に手間がかかったりして、現金化しにくい」ということを意味しています。
意味1の例文 「水は流動性の高い物質で、はちみつなどの流動性の低い物質と比べて動きが速い」
意味2の例文 「流動性の高いもので資産形成しているため、手元にある現金が足りなくなっても特に問題はない」
関連ページ
<よく使う言葉>
慣習、準拠、言わずもがな、明文化など
慣習的、致命的、便宜的、作為的など
倦怠感、臨場感、生活感、既視感など
野心、猜疑心、虚栄心、射幸心など
蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など
機動力、語彙力、死力、求心力など
資本主義、社会主義、事勿れ主義、拝金主義など
因果関係、共生関係、相関関係、労使関係など
<読み間違えやすい漢字の一覧>
哀悼、重複、出生、集荷など
依存、過不足、続柄など
<覚えておきたい知識>
鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など
(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど
<難読漢字の一覧>
(写真あり)藜、櫛、羆など
(写真あり)竜髭菜、青梗菜、蕗など
(写真あり)岩魚、栄螺、鱧など
(写真あり)海驢、犀、猫鼬など
(写真あり)花鶏、信天翁、杜鵑など
(写真あり)薊、金木犀、百合など
(写真あり)水黽、蟋蟀、蟷螂など
(写真あり)外郎、皮蛋、雲呑など
(写真あり)行灯、暖簾、轆轤など
秋桜、御手洗、蒲公英、転寝など
愈々、努々、清々しい、瑞々しいなど
誂える、囀る、目眩く、拵えるなど

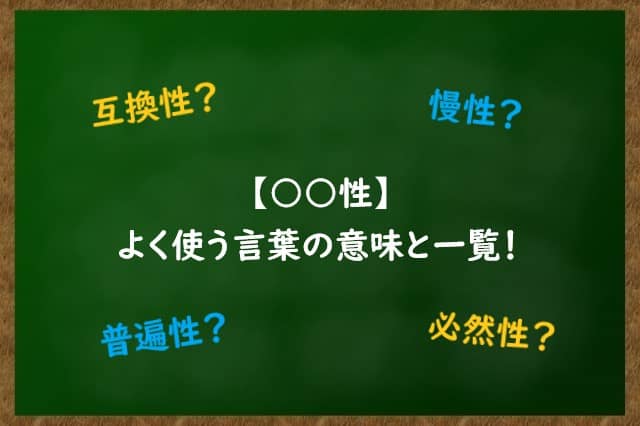
.svg)
.svg)