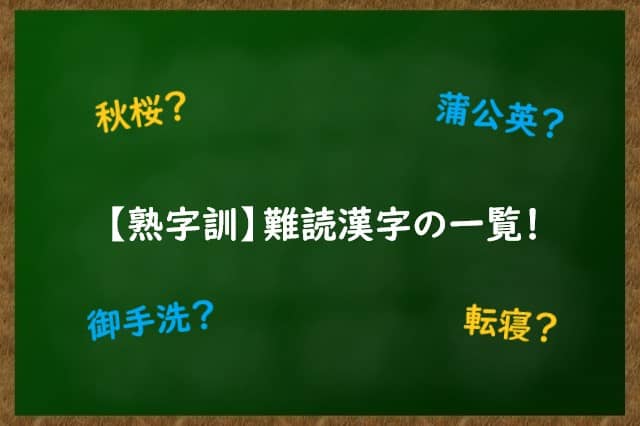熟字訓の難読漢字(一覧)
※1:熟字訓というのは、”熟字(2字以上の漢字の組み合わせ)に対して付けられた訓読みのこと”を意味します。
⇒当て字と熟字訓の違いを分かりやすく解説!(別ページに移動)
※2:漢字表記や漢字の読み方が複数ある場合は、左から順に一般的に用いられることが多く(つまり左側の方がよく使われる)、熟字訓(読み方)には青色マーカーで色をつけています。
漢字表記の例 【鮎魚女、鮎並】 ⇒ 【一般的に使われることが多い漢字表記、比較して一般的に使われることが少ない漢字表記】
漢字の読み方の例 【アーモンド、へんとう】 ⇒ 【一般的に使われることが多い読み方(熟字訓)、比較して一般的に使われることが少ない読み方(熟字訓ではない)】
また、漢字表記に()がついている場合は、()内の漢字表記は熟字訓ではないが、一般的に()内の漢字表記の方がよく使われていることを意味します。
漢字表記の例 【鳳蝶(揚羽蝶)】 ⇒ 【一般的に使われることが少ない熟字訓の漢字表記(比較して一般的に使われることが多い熟字訓ではない漢字表記)】
※3:熟字訓の意味が複数ある場合は、”「~」など”のように一般的に用いられることが多い意味(「~」)を優先して表記しています。
| 漢字 | 読み方 | 意味など |
|---|---|---|
| 扁桃 | アーモンド、へんとう | (アーモンド)「バラ目バラ科サクラ属に分類される落葉高木の一種。また、その仁(種子の中にある食用部分)」、(へんとう)「咽頭(いんとう)にあるリンパ組織」など |
| 彼奴 | あいつ | 「第三者を軽蔑、または親しみの気持ちを込めていう語」 |
| 鮎魚女、鮎並 | アイナメ | 「カサゴ目アイナメ科アイナメ属に分類される海水魚の一種」 |
| 生憎 | あいにく | 「期待や目的に沿わない状況になって残念なさま」 |
| 灰汁 | あく | 「植物に含まれる苦みや渋みのもとになる成分」など |
| 欠伸 | あくび | 「疲労・退屈・眠気などによって、自然に口が大きく開いて行われる呼吸運動」 |
| 胡座、胡坐 | あぐら | 「両足を前で組んで楽な姿勢で座ること」 |
| 鳳蝶(揚羽蝶) | アゲハチョウ | 「鱗翅目(りんしもく)アゲハチョウ科アゲハチョウ属に分類される昆虫の一種」。「アゲハチョウ」は、「並揚羽(ナミアゲハ)」(正式名称)の別名 |
| 木通、通草、山女 | アケビ | 「キンポウゲ目アケビ科アケビ属に分類される落葉低木の一種。また、その果実」 |
| 赤魚鯛 | アコウダイ | 「カサゴ目メバル科メバル属に分類される海水魚の一種」 |
| 牽牛花(朝顔) | アサガオ | 「ナス目ヒルガオ科サツマイモ属に分類される一年草の一種」 |
| 海豹、水豹 | アザラシ | 「食肉目アザラシ科に分類される哺乳類の総称」 |
| 海驢 | アシカ | 「食肉目アシカ科に分類される哺乳類の総称」など |
| 紫陽花 | アジサイ | 「ミズキ目アジサイ科アジサイ属に分類される落葉低木の一種」 |
| 明日 | あした、あす、みょうにち | (あした、みょうにち)「今日の次の日」、(あす)「今日の次の日」など |
| 飛鳥 | あすか | 「旧国名のひとつで、現在の奈良県高市郡明日香村の周辺」 |
| 小豆 | あずき | 「マメ目マメ科ササゲ属に分類される一年草の一種。また、その種子」 |
| 馬酔木 | アセビ | 「ツツジ目ツツジ科アセビ属に分類される常緑低木の一種」 |
| 彼処 | あそこ | 「あの場所。例の場所」など |
| 天晴 | あっぱれ | 「感心するほど見事なさま」など |
| 貴方、貴女、貴男 | あなた | 「立場が同等以下の人を敬っていう語」。相手が女性の場合は”貴女”、男性の場合は”貴男”と区別することもある |
| 家鴨(鶩) | アヒル | 「カモ目カモ科マガモ属に分類される鳥類の一種」 |
| 信天翁 | アホウドリ | 「ミズナギドリ目アホウドリ科キタアホウドリ属に分類される鳥類の一種」など |
| 海女 | あま | 「海に潜って貝・海藻などをとることを職業としている女性」 |
| 天魚(甘子) | アマゴ | 「サケ目サケ科サケ属に分類される淡水魚の一種」 |
| 数多 | あまた | 「数の多いこと。たくさん」 |
| 黄牛 | あめうし | 「透明な黄褐色(黄色みを帯びた茶色)の毛色の牛」 |
| 水黽、水馬 | アメンボ | 「半翅目(はんしもく)アメンボ科に分類される昆虫の一種」など |
| 年魚、香魚(鮎) | アユ | 「キュウリウオ目キュウリウオ科アユ属に分類される淡水魚の一種」 |
| 粗目 | あらめ、ざらめ | (あらめ)「編み目・織り目・木目などが、普通よりも粗いこと」、(ざらめ)「結晶が粗い、ざらざらした砂糖。粗目糖(ざらめとう)の略」 |
| 在処 | ありか | 「物などがある所。また、人などがいる所」 |
| 石決明(鮑) | アワビ | 「ミミガイ科に分類される大型の巻貝の総称」 |
| 許嫁 | いいなずけ | 「幼いときから、双方の親が婚約を結んでおくこと。また、その当人同士のこと」など |
| 硫黄 | いおう | 「非金属元素の1つで、黄色で脆(もろ)い結晶。元素記号は”S”」 |
| 烏賊 | イカ | 「コウイカ目とツツイカ目に分類される軟体動物の総称」 |
| 玉筋魚 | イカナゴ | 「スズキ目イカナゴ科イカナゴ属に分類される海水魚の一種」など |
| 斑鳩 | イカルガ、イカル | 「スズメ目アトリ科イカル属に分類される鳥類の一種」など。「イカルガ」は、「イカル」(正式名称)の別名 |
| 如何 | いかん、いかが | (いかん)「事の次第」など、(いかが)「相手に呼びかけ、勧める語」など |
| 意気地 | いくじ | 「物事をやり抜こうとする気力。また、自分の考えを通そうとする気力」 |
| 幾許、幾何 | いくばく | 「(”幾許か”の形で)わずか。少し」など |
| 鶏魚(伊佐木) | イサキ | 「スズキ目イサキ科イサキ属に分類される海水魚の一種」 |
| 十六夜 | いざよい | 「陰暦(旧暦)における16日の夜のこと。また、陰暦16日の夜に見える月」 |
| 石塊 | いしくれ、いしころ | (いしくれ、いしころ)「小さい石」 |
| 石首魚(石持) | イシモチ | 「スズキ目ニベ科シログチ属に分類される海水魚の一種」。「イシモチ」は、「白口(シログチ)」(正式名称)の別名 |
| 幼気 | いたいけ | 「幼くて(または小さくて)、かわいらしいさま」など |
| 悪戯 | いたずら | 「人が困るような悪さをすること。また、そのさま」など |
| 虎杖 | イタドリ | 「ナデシコ目タデ科ソバカズラ属に分類される多年草の一種」 |
| 無花果、映日果 | イチジク | 「バラ目クワ科イチジク属に分類される落葉低木の一種。また、その果実」 |
| 一寸 | いっすん、ちょっと | (いっすん)「1尺の10分の1の長さ(1寸=約3.03㎝)」、(ちょっと)「数量・程度などがわずかなさま」など |
| 従兄 | いとこ、じゅうけい | (いとこ、じゅうけい)「父または母の兄弟・姉妹の子供で、自分よりも年上の男」 |
| 従兄弟 | いとこ、じゅうけいてい | (いとこ、じゅうけいてい)「父または母の兄弟・姉妹の子供で、自分よりもそれぞれ年上・年下の男」 |
| 従兄妹 | いとこ、じゅうけいまい | (いとこ、じゅうけいまい)「父または母の兄弟・姉妹の子供で、自分よりも年上の男と年下の女」 |
| 従姉 | いとこ、じゅうし | (いとこ、じゅうし)「父または母の兄弟・姉妹の子供で、自分よりも年上の女」 |
| 従姉弟 | いとこ、じゅうしてい | (いとこ、じゅうしてい)「父または母の兄弟・姉妹の子供で、自分よりも年上の女と年下の男」 |
| 従姉妹 | いとこ、じゅうしまい | (いとこ、じゅうしまい)「父または母の兄弟・姉妹の子供で、自分よりもそれぞれ年上・年下の女」 |
| 従弟 | いとこ、じゅうてい | (いとこ、じゅうてい)「父または母の兄弟・姉妹の子供で、自分よりも年下の男」 |
| 従妹 | いとこ、じゅうまい | (いとこ、じゅうまい)「父または母の兄弟・姉妹の子供で、自分よりも年下の女」 |
| 田舎 | いなか | 「都会から離れたところ。地方」など |
| 稲荷 | いなり | 「五穀を司る神である宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)」など |
| 牛膝(猪の子槌) | イノコヅチ | 「ナデシコ目ヒユ科イノコヅチ属に分類される多年草の一種」 |
| 息吹 | いぶき | 「活動の気配。生き生きとした気力」など |
| 今際 | いまわ | 「死ぬ時。最期(さいご)」 |
| 郎女 | いらつめ | 「若い女性を親しんでいう語」 |
| 海豚 | イルカ | 「鯨偶蹄目(くじらぐうていもく)に分類される鯨類のうち、小型の種の総称」 |
| 刺青(入れ墨) | いれずみ | 「皮膚に針や小刀などで傷をつけて墨などを入れ、文字・絵・模様などを描くこと。また、その彫り物。タトゥー」 |
| 岩魚、嘉魚 | イワナ | 「サケ目サケ科イワナ属に分類される淡水魚の一種」 |
| 所謂 | いわゆる | 「世間一般に言われる。俗に言うところの」 |
| 浮子(浮き) | うき | 「水面に浮かせて、水中の網の位置を知らせるために漁網に付ける、中が空洞のガラス球やプラスチック球」など |
| 石斑魚(鯎) | ウグイ | 「コイ目コイ科ウグイ属に分類される淡水魚の一種」 |
| 泡沫 | うたかた | 「水に浮かぶ泡のように、消えやすく儚(はかな)いもののたとえ」など |
| 転寝 | うたたね、ごろね | (うたたね)「寝るつもりもないまま、うとうと眠ること」、(ごろね)「寝る支度もせず、そのまま横になって眠ること」 |
| 団扇 | うちわ | 「あおいで風を起こす道具」 |
| 現身 | うつしみ | 「この世に生きている身。現在の姿の体」 |
| 独活、土当帰 | ウド | 「セリ目ウコギ科タラノキ属に分類される多年草の一種」 |
| 善知鳥 | ウトウ | 「チドリ目ウミスズメ科ウトウ属に分類される鳥類の一種」 |
| 海原 | うなばら | 「広々とした海」など |
| 海胆、海栗、雲丹 | ウニ | (海胆)「殻から取り出した生のウニ」、(海栗)「トゲがついたままの状態のウニ」、(雲丹)「食品用に加熱・加工されたウニ」 |
| 自惚れ | うぬぼれ | 「自分の力を過信し、実際以上に優れていると思うこと」 |
| 乳母 | うば | 「母親に代わって子供に乳を飲ませて育てる女性」 |
| 産土 | うぶすな | 「その人の生まれた土地」など |
| 上手い | うまい | 「技術や手法が優れているさま」 |
| 五月蝿い、五月蠅い | うるさい | 「音や声が大きくて不快なこと」など |
| 狼狽える | うろたえる | 「どうしたらいいか分からず、慌て迷うこと」 |
| 彷徨く | うろつく | 「目的もなくあちこち歩き回ること。その辺りを行ったり来たりすること」 |
| 浮気 | うわき | 「配偶者など特定の異性がありながら、他の異性と情を通じること」など |
| 浮塵子 | ウンカ | 「半翅目ウンカ科とその近縁の科に分類される昆虫の総称」 |
| 運命 | うんめい、さだめ | (うんめい、さだめ)「人の意思ではどうにもならない、幸・不幸の巡り合わせ」 |
| 雲母 | うんも、きらら | (うんも、きらら)「単斜晶系、六角板状の結晶をしているケイ酸塩の鉱物」。「きらら」は、「うんも」(正式名称)の別名 |
| 海鷂魚 | エイ | 「板鰓亜綱(ばんさいあこう)に分類される軟骨魚類のうち、鰓(エラ)が体の下面に開くものの総称」 |
| 永久 | えいきゅう、とわ、とこしえ | (えいきゅう、とわ、とこしえ)「時間的に限りなく続くこと。また、そのさま」 |
| 似非 | えせ | 「似てはいるが本物ではないこと。偽物」 |
| 狗母魚 | エソ | 「ヒメ目エソ科に分類される海水魚の総称」 |
| 猿公 | えてこう | 「猿を擬人化(ぎじんか)した言い方」 |
| 干支 | えと | 「十干(じっかん)と十二支を組み合わせたもの」など |
| 胞衣 | えな | 「胎児(たいじ)を包んでいた膜と胎盤」 |
| 海老 | エビ | 「甲殻類エビ目に分類される長尾類の総称」 |
| 烏帽子 | えぼし | 「昔、成人した男子がつけた被り物のひとつ」 |
| 蝦夷 | えみし、えぞ | (えみし)「”えぞ”(民族)の古称」、(えぞ)「古代、奥羽地方や北海道に住んでいた民族」など |
| 美味しい | おいしい | 「食べ物・飲み物の味が良いこと」など |
| 花魁 | おいらん | 「位の高い女郎・遊女」など |
| 近江 | おうみ | 「旧国名のひとつで、現在の滋賀県にあたる地域」 |
| 嗚咽 | おえつ | 「息を詰まらせるように泣くこと。咽(むせ)び泣くこと」 |
| 大分 | おおいた、だいぶ | (おおいた)「九州地方東部にある県」、(だいぶ)「数量・程度などがかなり大きいさま」 |
| 大凡 | おおよそ | 「大雑把な内容。おおかた」など |
| 大鋸屑 | おがくず | 「鋸(のこぎり)で木材を切るときに出る木屑(きくず)」 |
| 可笑しい | おかしい | 「バカバカしくて笑いたくなるさま」など |
| 御菜 | おかず | 「食事の際の副食物」 |
| 陸稲 | おかぼ | 「畑地(はたち)に栽培する稲」 |
| 女将 | おかみ | 「料理屋・旅館などの女主人」 |
| 雪花菜 | おから、きらず | (おから、きらず)「豆腐を作るときにできる、大豆(だいず)をしぼったカス」。「きらず」は、「おから」(正式名称)の別名 |
| 晩生 | おくて | 「普通より遅く開花・成熟する植物」など |
| 童男 | おぐな | 「男の子。少年」 |
| 烏滸がましい | おこがましい | 「出過ぎていて生意気なこと。身の程知らずなこと」 |
| 伯父 | おじ、はくふ | 「父母の兄。また、父母の姉の夫」 |
| 叔父 | おじ、しゅくふ | 「父母の弟。また、父母の妹の夫」 |
| 含羞草(御辞儀草) | オジギソウ | 「マメ目マメ科オジギソウ属に分類される多年草の一種」 |
| 白粉 | おしろい | 「顔などに塗り、色を白く見せるための化粧品」 |
| 膃肭臍、海狗 | オットセイ | 「食肉目アシカ科のうち、キタオットセイ属とミナミオットセイ属に分類される哺乳類の総称」 |
| 男郎花 | オトコエシ | 「マツムシソウ目オミナエシ科オミナエシ属に分類される多年草の一種」 |
| 一昨日 | おととい、いっさくじつ | (おととい、いっさくじつ)「昨日の前日のこと。2日前」 |
| 一昨年 | おととし、いっさくねん | (おととし、いっさくねん)「去年の前の年のこと。2年前」 |
| 大人 | おとな | 「十分に成長した人」など |
| 大人しい、温和しい | おとなしい | 「(性質・態度などが)落ち着いていて穏やかなさま」など |
| 乙女 | おとめ | 「年の若い女」など |
| 各々(=各各) | おのおの | 「それぞれ。各自」 |
| 伯母 | おば、はくぼ | 「父母の姉。また、父母の兄の妻」 |
| 叔母 | おば、しゅくぼ | 「父母の妹。また、父母の弟の妻」 |
| 十八番 | おはこ、じゅうはちばん | (おはこ、じゅうはちばん)「最も得意とする芸や技」など |
| 女郎花 | オミナエシ | 「マツムシソウ目オミナエシ科オミナエシ属に分類される多年草の一種」 |
| 沢瀉 | オモダカ | 「オモダカ目オモダカ科オモダカ属に分類される多年草の一種」 |
| 玩具 | おもちゃ、がんぐ | (おもちゃ、がんぐ)「子供が持って遊ぶ道具」など |
| 万年青 | オモト | 「キジカクシ目キジカクシ科オモト属に分類される多年草の一種」 |
| 母屋 | おもや | 「物置や離れなどに対して、住居に用いる主な建物」など |
| 女形 | おやま | 「歌舞伎で、女の役をする男の役者」など |
| 漢字 | 読み方 | 意味など |
|---|---|---|
| 外方 | がいほう、そっぽ | (がいほう)「ある範囲の外。外側の方」、(そっぽ)「正面でないよその方。別の方」 |
| 傀儡 | かいらい、くぐつ | (かいらい)「陰にいる人物に思い通りに操られ、利用されている人」など、(くぐつ)「芝居などに用いられる操り人形」 |
| 鶏冠木(楓) | カエデ | 「ムクロジ目ムクロジ科カエデ属に分類される落葉高木の総称」 |
| 案山子、鹿驚 | かかし | 「田畑の作物を荒らす鳥獣を防ぐために立てる人形や似たような仕掛け」など |
| 大蚊 | ガガンボ | 「双翅目(そうしもく)ガガンボ科とその近縁の科に分類される昆虫の総称」 |
| 牡蠣 | カキ | 「ウグイスガイ目イタボガキ科とベッコウガキ科に分類される二枚貝の総称」 |
| 燕子花、杜若 | カキツバタ | 「キジカクシ目アヤメ科アヤメ属に分類される多年草の一種」 |
| 神楽 | かぐら | 「神を祭るために奏(そう)する舞楽」 |
| 欠片 | かけら | 「欠けた一片」など |
| 陽炎 | かげろう | 「春の暖かい日に、地面から空気が炎のように揺らめいて立ち上る現象」 |
| 鍛冶 | かじ | 「鉄などの金属を熱して、それを打ち鍛え、色々な器物を作ること。また、それを仕事とする人」 |
| 河岸 | かし、かがん、かわぎし | (かし)「舟から人や荷物をあげおろしする川の岸辺」など、(かがん、かわぎし)「川の岸辺」 |
| 杜父魚(鰍) | カジカ | 「スズキ目カジカ科カジカ属に分類される淡水魚の一種」など |
| 旗魚(梶木) | カジキ | 「スズキ目マカジキ科とメカジキ科に分類される海水魚の総称」 |
| 風邪 | かぜ | 「寒気・頭痛・鼻水・せき・発熱などの症状を伴う呼吸器系の病気の総称」 |
| 固唾 | かたず | 「緊張して息をこらすときに口の中にたまる唾(つば)」 |
| 蝸牛 | カタツムリ | 「腹足綱(ふくそくこう)柄眼目(へいがんもく)に分類される、陸に生息する巻き貝の総称」 |
| 帷子 | かたびら | 「裏地を付けない衣服」 |
| 堅魚、松魚(鰹) | カツオ | 「スズキ目サバ科カツオ属に分類される海水魚の一種」 |
| 彼方 | かなた | 「遠くの方。向こうの方」 |
| 金糸雀 | カナリア | 「スズメ目アトリ科カナリア属に分類される鳥類の一種」 |
| 南瓜 | カボチャ | 「ウリ科カボチャ属に分類される蔓性(つるせい)の一年草の一種。また、その果実」 |
| 梭魚、梭子魚(魳) | カマス | 「スズキ目カマス科に分類される海水魚の総称」 |
| 蒲魚 | かまとと | 「知っているくせに知らないふりをして、上品ぶったり、純情らしく振る舞ったりするさま。また、そのような人」 |
| 天牛(髪切虫) | カミキリムシ | 「甲虫目カミキリムシ科に分類される昆虫の総称」 |
| 剃刀 | かみそり | 「髪やひげを剃(そ)るのに使う、鋭利な刃物」など |
| 氈鹿、羚羊 | カモシカ | 「鯨偶蹄目ウシ科カモシカ属に分類される哺乳類の一種。日本氈鹿(ニホンカモシカ)のこと」など |
| 蚊帳 | かや | 「麻(あさ)・木綿(もめん)などで網状に作り、蚊を防ぐために吊って寝床を覆うもの」 |
| 揶揄う | からかう | 「相手を困らせたり怒らせたりするような言動をして面白がること」 |
| 硝子 | ガラス | 「石英・石灰石・炭酸ナトリウムなどを高温で溶かし、冷却して作った透明な物質」 |
| 落葉松(唐松) | カラマツ | 「マツ目マツ科カラマツ属に分類される落葉高木の一種」 |
| 骨牌(歌留多) | かるた | 「遊びや博打(ばくち)に使う、絵や文字の書かれた長方形の小さい厚紙の札。また、それを使った遊び」 |
| 乾飯 | かれいい | 「炊いた飯(お米)を干した、携帯用の食料」 |
| 為替 | かわせ | 「離れた場所にいる人との金銭の決済を、現金を送らず手形・小切手などの信用手段で処理する方法」 |
| 翡翠、魚狗 | カワセミ | 「ブッポウソウ目カワセミ科カワセミ属に分類される鳥類の一種」など |
| 甘藷 | かんしょ、サツマイモ | (かんしょ、サツマイモ)「ナス目ヒルガオ科サツマイモ属に分類される蔓性の多年草の一種。また、その塊根」。「かんしょ」は、「サツマイモ」(正式名称)の別名 |
| 上達部 | かんだちめ | 「昔、朝廷に仕えた太政大臣・左右大臣・大中納言・参議および三位(さんみ)以上の高官」 |
| 甘藍 | かんらん、キャベツ | (かんらん、キャベツ)「アブラナ目アブラナ科アブラナ属に分類される多年草の一種」。「かんらん」は、「キャベツ」(正式名称)の別名 |
| 木屑 | きくず、こけら | (きくず)「木材を切ったり削ったりしたときに出る屑(くず)」、(こけら)「木材を切ったり削ったりしたときに出る屑」など |
| 木耳 | キクラゲ | 「キクラゲ目キクラゲ科キクラゲ属に分類されるキノコの一種」 |
| 気障 | きざ | 「服装・言葉遣い・態度などが気取っていて、嫌な感じを持たせること」 |
| 如月 | きさらぎ | 「陰暦(旧暦)における2月」 |
| 羊蹄 | ギシギシ | 「ナデシコ目タデ科スイバ属に分類される多年草の一種」 |
| 気質 | きしつ、かたぎ | (きしつ)「生まれながらの性質」など、(かたぎ)「同じ環境・身分・職業などの人に共通する特有の性格」 |
| 煙管 | きせる | 「刻みタバコを吸うための道具」 |
| 啄木鳥 | キツツキ | 「キツツキ目キツツキ科に分類される鳥類の総称」 |
| 昨日 | きのう、さくじつ | (きのう、さくじつ)「今日より1日前の日」 |
| 黍魚子 | キビナゴ | 「ニシン目キビナゴ科キビナゴ属に分類される海水魚の一種」 |
| 肌理 | きめ | 「皮膚や物の表面に見える筋目や模様」など |
| 胡瓜、黄瓜 | キュウリ | 「ウリ目ウリ科キュウリ属に分類される蔓性の一年草の一種。また、その果実」 |
| 今日 | きょう、こんにち | (きょう)「いま過ごしている日の午前0時から、午後12時まで」、(こんにち)「近頃。この頃」など |
| 銀杏 | ぎんなん、イチョウ | (ぎんなん)「イチョウの種子」など、(イチョウ)「イチョウ目イチョウ科イチョウ属に分類される落葉高木の一種」 |
| 水鶏 | クイナ | 「ツル目クイナ科クイナ属に分類される鳥類の一種」など |
| 苦汁 | くじゅう、にがり | (くじゅう)「苦しみ。苦い経験」など、(にがり)「海水を煮詰めて食塩を取り出した後に残る苦い液体」 |
| 草臥れる | くたびれる | 「くたくたに疲れること」など |
| 果物 | くだもの | 「食用となる果実」 |
| 梔子、山梔子 | クチナシ | 「リンドウ目アカネ科クチナシ属に分類される常緑低木の一種」 |
| 海月、水母 | クラゲ | 「刺胞(しほう)動物のうち、淡水または海水で浮遊して生活する動物の総称」 |
| 胡桃 | クルミ | 「ブナ目クルミ科クルミ属に分類される落葉高木の一種。また、その種子と仁(種子の中にある食用部分)」 |
| 曲輪 | くるわ | 「城・砦(とりで)などの周囲に築いた囲い。また、その囲いの内側の地域」 |
| 経緯 | けいい、いきさつ | (けいい)「物事の細かい事情のこと」、(いきさつ)「物事の細かい事情のこと」など |
| 今朝 | けさ | 「今日の朝」 |
| 景色 | けしき | 「山や川など自然の眺め」 |
| 化粧 | けしょう、けわい | (けしょう、けわい)「白粉(おしろい)などで顔を美しく飾ること」 |
| 現世 | げんせ、うつしよ | (げんせ、うつしよ)「現在の世。この世」 |
| 沙蚕 | ゴカイ | 「サシバゴカイ目ゴカイ科に分類される環形(かんけい)動物の総称」 |
| 此処 | ここ | 「自分のいる所・場面」など |
| 孤児 | こじ、みなしご | (こじ、みなしご)「両親のいない子供」 |
| 豆汁 | ごじる、ご | (ごじる)「水に浸して柔らかくした大豆をすり潰したものを入れた味噌汁(=”ご”を入れた味噌汁)」、(ご)「大豆を水に浸してすり潰した汁」 |
| 秋桜 | コスモス | 「キク目キク科コスモス属に分類される一年草の一種。大春車菊(オオハルシャギク)のこと」など |
| 東風 | こち | 「東の方から吹く風のこと。春風」 |
| 牛尾魚(鯒) | コチ | 「スズキ目コチ科に分類される海水魚の総称」 |
| 此方 | こちら | 「話し手に近い場所・方向を指し示す語」など |
| 今年 | ことし、こんねん | (ことし、こんねん)「現在を含んでいる年。この年」 |
| 二合半、小半 | こなから | 「半分の半分(つまり4分の1)。四半分(しはんぶん)」など |
| 木皮 | こはだ | 「木の皮。樹皮」 |
| 辛夷 | こぶし | 「モクレン目モクレン科モクレン属に分類される落葉高木の一種」 |
| 独楽 | こま | 「木や金属などでできた、厚みのある円形の胴の中心に心棒を通した玩具(おもちゃ)」 |
| 氷下魚、氷魚 | コマイ | 「タラ目タラ科コマイ属に分類される海水魚の一種」 |
| 顳顬、蟀谷 | こめかみ | 「耳の上部と目尻(めじり)との間にある、物を噛むと動く部分」 |
| 破落戸 | ごろつき | 「定職がなく、ゆすりなどの悪事をして暮らす者」 |
| 小童 | こわっぱ | 「子供、年少者を罵(ののし)っていう語」 |
| 混凝土 | コンクリート | 「セメントに砂・砂利などの骨材と水を適当な割合で混ぜ、こねたもの。また、それを固めたもの」 |
| 漢字 | 読み方 | 意味など |
|---|---|---|
| 賽子、骰子 | サイコロ | 「双六(すごろく)・博打(ばくち)などで用いられ、小さい立方体の各面に1から6までの目を記したもの」 |
| 月代 | さかやき | 「男の頭髪を頭の中央にかけて半月形に剃(そ)り落とした、その部分」 |
| 主典 | さかん | 「律令制の四等官(しとうかん)の最下位」 |
| 防人 | さきもり | 「昔に、筑紫(つくし)・壱岐(いき)・対馬(つしま)など北九州の防備に当たった兵士」 |
| 昨夜 | さくや、ゆうべ | (さくや、ゆうべ)「昨日の夜」 |
| 桜桃 | サクランボ、おうとう | (サクランボ、おうとう)「桜の果実の総称。特に、西洋実桜(セイヨウミザクラ)の果実」 |
| 石榴、柘榴 | ザクロ | 「フトモモ目ミソハギ科ザクロ属に分類される落葉高木の一種。また、その果実」 |
| 雑魚 | ざこ | 「大したことのない人」など |
| 小波 | さざなみ | 「小さな波」など |
| 細雪 | ささめゆき | 「細(こま)かに降る雪。まばらに降る雪」 |
| 細石 | さざれいし | 「細かい石。小石」 |
| 流石 | さすが | 「世間の評判通り。予想された通り」など |
| 流離 | さすらい | 「あてもなく彷徨(さまよ)うこと」 |
| 流離う | さすらう | 「あてもなく彷徨(さまよ)い歩くこと。また、目的もなく歩き回ること」 |
| 皐月、五月 | さつき | 「陰暦(旧暦)における5月」 |
| 拶双魚 | サッパ | 「ニシン目ニシン科サッパ属に分類される海水魚の一種」 |
| 仙人掌、覇王樹 | サボテン | 「ナデシコ目サボテン科に分類される植物の総称」 |
| 朱欒 | ザボン | 「ムクロジ目ミカン科ミカン属に分類される常緑高木の一種。また、その果実」 |
| 彷徨う | さまよう | 「あてもなく歩くこと」など |
| 五月雨 | さみだれ | 「旧暦の5月頃に降る長雨。梅雨」など |
| 白湯 | さゆ、パイタン | (さゆ)「何も混ぜていない、水を沸かしただけのお湯。また、それを飲める温度まで冷ましたもの」、(パイタン)「豚骨・鶏ガラなどを煮込んで作る、白く濁ったスープ」 |
| 細魚(鱵) | サヨリ | 「ダツ目サヨリ科サヨリ属に分類される海水魚の一種」など |
| 百日紅 | サルスベリ | 「フトモモ目ミソハギ科サルスベリ属に分類される落葉高木の一種」 |
| 馬鮫魚(鰆) | サワラ | 「サバ目サバ科サワラ属に分類される海水魚の一種」など |
| 秋刀魚 | サンマ | 「ダツ目サンマ科サンマ属に分類される海水魚の一種」 |
| 鬼頭魚(鱪) | シイラ | 「スズキ目シイラ科シイラ属に分類される海水魚の一種」 |
| 時雨 | しぐれ | 「秋の終わりから冬にかけて、一時的に降ったり止んだりする雨」など |
| 時化 | しけ | 「風雨のために海が荒れること。また、海が荒れて魚が獲れないこと」など |
| 柳葉魚 | シシャモ | 「キュウリウオ目キュウリウオ科シシャモ属に分類される海水魚の一種」 |
| 羊歯 | シダ | 「胞子で増え、主に陸上に生えるシダ植物の総称」など |
| 疾風 | しっぷう、はやて | (しっぷう、はやて)「急に吹く速い風」 |
| 尻尾 | しっぽ | 「動物などの尾」など |
| 竹刀 | しない | 「剣道で用いられる、四つ割りの竹を束ね合わせて作った刀」 |
| 老舗 | しにせ、ろうほ | (しにせ、ろうほ)「先祖代々にわたって続いていて、格式や信用のあるお店(会社)」 |
| 東雲 | しののめ | 「明け方。夜明け」など |
| 芝生 | しばふ | 「芝(しば)が一面に生えている所」 |
| 風巻 | しまき | 「風が激しく吹き荒れること。また、その風」 |
| 紙魚、衣魚 | シミ | 「総尾目(そうびもく)に分類される昆虫の総称」 |
| 清水 | しみず | 「地下から湧(わ)き出る澄んだきれいな水」 |
| 注連 | しめ | 「土地の所有や場所の区画を示し、立ち入りを禁じたりするためのしるし」など |
| 石楠花 | シャクナゲ | 「ツツジ目ツツジ科ツツジ属シャクナゲ亜属に分類される常緑低木の総称」 |
| 吃逆 | しゃっくり | 「横隔膜(おうかくまく)の痙攣(けいれん)により、急に空気が吸い込まれ、声門が開いて音を発する現象」 |
| 三味線 | しゃみせん | 「犬や猫の皮を張った胴の部分に棹(さお)を付けて、張っている弦(げん)を撥(ばち)という道具で弾いて演奏する日本の弦楽器」 |
| 軍鶏 | シャモ | 「キジ目キジ科ヤケイ属に分類される鳥類の一種。鶏(ニワトリ)の一品種」 |
| 砂利 | じゃり | 「小石。また、小石に砂の混じったもの」 |
| 洒落 | しゃれ | 「粋(いき)で気の利(き)いていること」など |
| 終夜 | しゅうや、よもすがら | (しゅうや、よもすがら)「夜の間ずっと。日没から夜明けまで」 |
| 数珠 | じゅず | 「仏を拝むときや念仏の回数を数えるときに手にかける、小さな珠(たま)に糸を通して輪にしたもの」 |
| 生姜 | ショウガ | 「ショウガ目ショウガ科ショウガ属に分類される多年草の一種。また、その根茎」 |
| 上手 | じょうず、うわて、かみて | (じょうず)「物事のやり方が巧みで、手際の良いこと」など、(うわて)「他より地位や能力が優れていること」など、(かみて)「位置・方向が上の方」 |
| 菖蒲 | ショウブ、アヤメ | (ショウブ)「ショウブ目ショウブ科ショウブ属に分類される多年草の一種」など、(アヤメ)「キジカクシ目アヤメ科アヤメ属に分類される多年草の一種」など |
| 初心 | しょしん、うぶ | (しょしん)「最初に心に決めたこと。最初の決意」など、(うぶ)「世間慣れしておらず、純情なさま。特に男女の情に通じていないさま」 |
| 白髪 | しらが、はくはつ | (しらが)「白くなった毛髪(一部が白い髪の場合)」、(はくはつ)「白くなった毛髪(ほぼ全部が白い髪の場合)」 |
| 不知火 | しらぬい | 「夜の海上に多くの光が点在して、揺らめいて見える現象」 |
| 素面 | しらふ | 「お酒に酔っていない普段の状態。また、そのときの顔」 |
| 師走 | しわす | 「陰暦(旧暦)における12月」 |
| 心算 | しんさん、つもり | (しんさん)「心の中の計画」、(つもり)「実際はそうではないが、そうなっているような気持ち」など |
| 身体 | しんたい、からだ | (しんたい、からだ)「人や動物の頭・胴・手足などの肉体全部」など |
| 沈丁花 | ジンチョウゲ | 「フトモモ目ジンチョウゲ科ジンチョウゲ属に分類される常緑低木の一種」 |
| 西瓜 | スイカ | 「ウリ目ウリ科スイカ属に分類される蔓性の一年草の一種。また、その果実」 |
| 忍冬(吸い葛) | スイカズラ | 「マツムシソウ目スイカズラ科スイカズラ属に分類される常緑蔓性木本の一種」 |
| 芋茎 | ずいき | 「里芋の葉柄(葉の一部で、葉を茎や枝に繋いでいる細い部分)」 |
| 清々しい(=清清しい) | すがすがしい | 「(物事の様子・態度・性格などが)さっぱりとしていて気持ちが良いこと。爽快(そうかい)なさま」 |
| 双六 | すごろく | 「サイコロを振り、出た目の数で振り出しから駒を進めていき、あがりの早さを競う遊び」 |
| 生絹 | すずし | 「生糸(きいと)で織った絹織物」 |
| 金鐘児(鈴虫) | スズムシ | 「直翅目(ちょくしもく)コオロギ科に分類される昆虫の一種」 |
| 寸々(=寸寸) | ずたずた | 「細かくいくつにも切れているさま」 |
| 清汁 | すまし | 「だし汁に、醤油と塩で味付けをした透明な吸い物」 |
| 住処 | すみか | 「住んでいる場所」 |
| 相撲、角力 | すもう | 「まわしを付けた裸の2人が、土俵内で取り組む競技」など |
| 掏摸 | すり | 「他人が身につけている金品を、その人に気付かれないように盗み取ること。また、そのような人」 |
| 海象 | セイウチ | 「食肉目セイウチ科セイウチ属に分類される哺乳類の一種」 |
| 静寂 | せいじゃく、しじま | (せいじゃく、しじま)「物音ひとつしないで静まりかえっていること」 |
| 生命 | せいめい、いのち | (せいめい、いのち)「生物に内在する、生物が生物として存在できる原動力」など |
| 蒸籠 | せいろ、せいろう | (せいろ、せいろう)「食べ物を蒸すための、底がすのこ状になっている木や竹製の道具」 |
| 女衒 | ぜげん | 「江戸時代に、女を遊女屋に売るのを商売にした者」 |
| 冷笑う | せせらわらう | 「小ばかにして冷ややかに笑うこと。冷笑すること」 |
| 台詞、科白 | せりふ | 「俳優が劇中で話す言葉」など |
| 旋風 | せんぷう、つむじかぜ | (せんぷう)「渦(うず)のように巻いて吹き上がる風」など、(つむじかぜ)「渦のように巻いて吹き上がる風」 |
| 発条 | ぜんまい、ばね | (ぜんまい)「弾性に富む鋼などを薄く細長くして、渦巻状に巻いたもの」、(ばね)「弾性に富む鋼などを薄く細長くして、渦巻状に巻いたもの」など |
| 素麺 | そうめん | 「小麦粉に塩水を加えてこね、線状に細く伸ばして乾燥させた食品」 |
| 草履 | ぞうり | 「鼻緒(はなお)がある底が平たい履物」 |
| 曹達 | ソーダ | 「ソーダ水の略」など |
| 其処 | そこ | 「その場所・その点・その局面・その程度。それほど」など |
| 其方 | そちら、そなた | (そちら)「聞き手の近くにある物を指す語」など、(そなた)「やや丁寧な言い方として、目下の相手を指す語」など |
| 雀斑 | そばかす、じゃくはん | (そばかす、じゃくはん)「顔面にできる茶色の細かい斑点」 |
| 抑々(=抑抑) | そもそも | 「ある事柄の説明を始めるときに用いる語」など |
| 冬青 | ソヨゴ | 「ニシキギ目モチノキ科モチノキ属に分類される常緑低木の一種」 |
| 蚕豆(空豆) | ソラマメ | 「マメ目マメ科ソラマメ属に分類される一年草または二年草の一種。また、その種子」 |
| 算盤 | そろばん | 「枠の中の珠(たま)を上下させて計算する道具」など |
| 漢字 | 読み方 | 意味など |
|---|---|---|
| 大蛇 | だいじゃ、おろち | (だいじゃ、おろち)「大きな蛇(ヘビ)」 |
| 松明 | たいまつ | 「長い棒の先端に、松脂(まつやに)など燃えやすいものを浸した布切れを巻き付けたもの」 |
| 章魚(蛸) | タコ | 「頭足類タコ目に分類される軟体動物の総称」 |
| 出汁 | だし | 「旨味(うまみ)のある汁」など |
| 山車 | だし | 「祭りのときに、飾り物などをして引いたり担いだりする屋台(やたい)」 |
| 黄昏 | たそがれ | 「夕暮れ。夕方の薄暗いとき」 |
| 三和土 | たたき | 「赤土・砂利などに、消石灰と苦汁(にがり)を混ぜて練り、それを塗って叩き固めたもの」 |
| 太刀 | たち | 「日本刀のうち、刃渡りが60cm以上の刀」 |
| 殺陣 | たて、さつじん | (たて、さつじん)「演劇や映画で、切り合いや捕り物などの格闘における型。立ち回り」 |
| 伊達 | だて | 「外見を飾ること。見栄を張ること」など |
| 七夕 | たなばた | 「五節句のひとつで、7月7日に行う織姫(おりひめ)と彦星(ひこぼし)を祭る行事」 |
| 煙草 | たばこ | 「タバコ(植物)の葉を乾かして作った嗜好品(しこうひん)」など |
| 足袋 | たび | 「爪先(つまさき)が2つに分かれた袋状の履物」 |
| 吉丁虫(玉虫) | タマムシ | 「甲虫目タマムシ科ルリタマムシ属に分類される昆虫の一種」など |
| 玉響 | たまゆら | 「少しの間」 |
| 濁声 | だみごえ | 「濁った声」など |
| 容易い | たやすい | 「簡単にできること」など |
| 大口魚(鱈) | タラ | 「タラ目タラ科に分類される海水魚の総称」 |
| 達磨 | だるま | 「達磨(人物)の座禅姿をかたどった置物」など |
| 束子 | たわし | 「器物の汚れをこすって落とす用具」 |
| 楽車 | だんじり | 「主に関西・西日本で、祭礼に引いて歩く屋台」 |
| 蒲公英 | タンポポ | 「キク目キク科タンポポ属に分類される多年草の総称」 |
| 主税 | ちから | 「主税寮(しゅぜいりょう)の略」 |
| 炒飯 | チャーハン | 「炊いた米を肉・卵・野菜などと一緒に炒めて、味付けした料理」 |
| 卓袱台 | ちゃぶだい | 「短い脚の付いた食事用の台」 |
| 手水 | ちょうず | 「参拝する前などに、手や口を水で洗い清めること。また、その水」など |
| 手斧 | ちょうな、ておの | (ちょうな、ておの)「大具道具のひとつで、主に片手で振る小型の斧(おの)」 |
| 草石蚕 | チョロギ | 「シソ目シソ科イヌゴマ属に分類される多年草の一種。また、その塊茎」 |
| 縮緬 | ちりめん | 「表面にしぼと呼ばれるしわのある絹織物の総称」 |
| 一日 | ついたち、いちにち | (ついたち)「月の最初の日」、(いちにち)「午前0時から午後12時までの24時間」など |
| 月次 | つきなみ | 「平凡なこと」など |
| 築山 | つきやま | 「庭園などに、山に見立てて土砂・石などを用いて築いたもの」 |
| 土筆 | ツクシ | 「杉菜(スギナ:トクサ目トクサ科トクサ属に分類される多年草の一種)の胞子茎(ほうしけい)」 |
| 九十九 | つくも | 「九十九髪(つくもがみ)の略」 |
| 黄楊、柘植 | ツゲ | 「ツゲ目ツゲ科ツゲ属に分類される常緑低木の一種」など |
| 美人局 | つつもたせ | 「男女が共謀してその女が別の男を誘惑し、別の男が引っ掛かると、それを言いがかりとしてその男から金銭などをゆすること」 |
| 海石榴、山茶(椿) | ツバキ | 「ツツジ目ツバキ科ツバキ属に分類される常緑高木の一種。藪椿(ヤブツバキ)のこと」 |
| 玄鳥(燕) | ツバメ | 「スズメ目ツバメ科ツバメ属に分類される鳥類の一種」など |
| 飛礫 | つぶて | 「小石を投げること。また、その小石」 |
| 旋毛 | つむじ | 「頭の毛が渦巻(うずまき)のように生えている部分」 |
| 梅雨 | つゆ、ばいう | (つゆ、ばいう)「6月頃に降り続く長雨。また、その雨期」 |
| 氷柱 | つらら、ひょうちゅう | (つらら)「軒(のき)などから滴(したた)る水滴が凍って、棒状に垂れ下がったもの」、(ひょうちゅう)「夏に、冷感を高めるために置く角柱形の氷」など |
| 石蕗 | ツワブキ | 「キク目キク科ツワブキ属に分類される多年草の一種」 |
| 悪阻 | つわり、おそ | (つわり)「妊娠の初期に、吐き気や食欲不振、飲食物に対する嗜好の変化などを起こす症状」、(おそ)「つわりの症状が悪化した状態」 |
| 為体(体たらく) | ていたらく | 「ありさま。様子。状態」 |
| 木偶 | でく | 「役に立たない人」など |
| 天蚕糸 | てぐす | 「山繭(ヤママユ)の幼虫の絹糸腺(けんしせん)から作った白色透明の糸」 |
| 出会す | でくわす | 「偶然に出会うこと。ばったりと会うこと」 |
| 凸凹 | でこぼこ | 「物の表面に高低があり、平らでないこと」など |
| 手伝う | てつだう | 「他人の仕事を助けること。手助けすること」など |
| 黄鼬(貂) | テン | 「食肉目イタチ科テン属に分類される哺乳類の一種」 |
| 投網 | とあみ | 「円錐形の網の上部に手綱(たづな)、下部に重りを付け、船上などから水面に投げ広げ、被せて引き上げる漁法。また、その網」 |
| 満天星 | ドウダンツツジ、ドウダン | (ドウダンツツジ、ドウダン)「ツツジ目ツツジ科ドウダンツツジ属に分類される落葉低木の一種」。「ドウダン」は、「ドウダンツツジ」(正式名称)の略 |
| 同胞 | どうほう、はらから | (どうほう、はらから)「同じ国民・民族」など |
| 玉蜀黍 | トウモロコシ | 「イネ目イネ科トウモロコシ属に分類される一年草の一種」 |
| 蜥蜴、石竜子 | トカゲ | 「有隣目(ゆうりんもく)トカゲ亜目に分類される爬虫類の総称」 |
| 朱鷺、桃花鳥 | トキ | 「ペリカン目トキ科トキ属に分類される鳥類の一種」 |
| 木賊 | トクサ | 「トクサ目トクサ科トクサ属に分類される多年草の一種」 |
| 蜷局 | とぐろ | 「蛇などが、体を渦巻き状に巻くこと。また、その巻いた状態」 |
| 髑髏 | どくろ、しゃれこうべ | (どくろ、しゃれこうべ)「風雨に晒(さら)され、まわりの肉が落ちてしまった頭の骨」 |
| 時計 | とけい | 「時刻を示し、時間を測る器械」 |
| 何処 | どこ、いずこ | (どこ、いずこ)「不明または不特定の場所を示すのに用いる語」 |
| 野老 | トコロ | 「ユリ目ヤマノイモ科ヤマノイモ属に分類される多年草の一種。鬼野老(オニドコロ)のこと」など |
| 心太 | ところてん | 「天草(テングサ)の煮汁を濾(こ)して型に入れ、ゼリー状に固めた食品」など |
| 何方 | どちら、どなた | (どちら)「不明または不特定の方向・場所を指す語」など、(どなた)「”だれ”の敬称」など |
| 馴鹿 | トナカイ | 「鯨偶蹄目シカ科トナカイ属に分類される哺乳類の一種」 |
| 濁酒 | どぶろく、だくしゅ | (どぶろく、だくしゅ)「醪(もろみ)を搾(しぼ)らず、濾していない白く濁った酒」 |
| 薯蕷 | とろろ、しょよ | (とろろ)「とろろ芋(長芋や自然薯をすって作った食べ物)の略」など、(しょよ)「長芋または山の芋(=自然薯)の別名」 |
| 蜻蛉 | トンボ | 「トンボ目に分類される昆虫の総称」 |
| 中生 | なかて | 「農作物などにおいて、早生(わせ)と晩生(おくて)の中間のもの」 |
| 就中 | なかんずく | 「その中でも。とりわけ。特に」 |
| 亡骸 | なきがら | 「死体。遺体」 |
| 薙刀、長刀、眉尖刀 | なぎなた | 「長い柄(え)の先に、幅の広い反(そ)った刃を付けた武器」 |
| 名残 | なごり | 「物事が過ぎ去った後、その気配や影響が残ること」など |
| 茄子 | ナス、なすび | (ナス、なすび)「ナス目ナス科ナス属に分類される一年草の一種。また、その果実」。「なすび」は、「ナス」(正式名称)の別名 |
| 何故 | なぜ、なにゆえ | (なぜ、なにゆえ)「どうして。どういうわけで」 |
| 刀豆(鉈豆) | ナタマメ | 「マメ目マメ科ナタマメ属に分類される蔓性の一年草の一種」 |
| 雪崩 | なだれ | 「傾斜地の積雪が大量に崩れ落ちる現象」 |
| 何某 | なにがし | 「名称・数量がはっきりしないとき、またはわざとぼかして言うときの語」など |
| 何卒 | なにとぞ | 「相手に対して強く願い望む気持ちを表すときに用いる語。どうか」 |
| 海鼠 | ナマコ | 「ナマコ綱に分類される棘皮動物の総称」 |
| 生業 | なりわい | 「生計を立てるための職業のこと。家業」 |
| 何時 | なんじ、なんどき、いつ | (なんじ)「時刻が不明なとき、または特に指定する必要のないときに用いる語」、(なんどき)「はっきりしていない時を表す語」など、(いつ)「はっきりしていない時を表す語」など |
| 仮漆 | ニス | 「ワニス(樹脂を溶かした塗料で、顔料は含まず、光沢のある透明な薄膜を形成するもの)の略」 |
| 若気る | にやける | 「口元が緩(ゆる)んで笑顔になること」 |
| 接骨木 | ニワトコ | 「マツムシソウ目ガマズミ科ニワトコ属に分類される落葉低木の一種」 |
| 大蒜 | ニンニク | 「キジカクシ目ヒガンバナ科ネギ属に分類される多年草の一種。また、その鱗茎(りんけい)」 |
| 泥濘む | ぬかるむ | 「雨や雪解けなどで地面が泥状になること」 |
| 微温い(温い) | ぬるい | 「少し温かい。生温かいこと」など |
| 螺子、捻子、捩子 | ねじ | 「物を締め付けるための螺旋(らせん)状の溝(みぞ)のある用具」など |
| 合歓木 | ネムノキ | 「マメ目マメ科ネムノキ属に分類される落葉高木の一種」 |
| 熨斗 | のし | 「喜び祝う気持ちを表すために、贈答品(ぞうとうひん)に添えるもの」 |
| 海苔 | のり | 「紅藻類・緑藻類・藍藻類の海藻で、食用とするものの総称」など |
| 祝詞 | のりと | 「神に祈る言葉」 |
| 惚気 | のろけ | 「自分の夫・妻・恋人との仲が良いことを嬉しそうに人に話すこと」 |
| 狼煙、烽火 | のろし | 「事を起こすための合図や信号」など |
| 漢字 | 読み方 | 意味など |
|---|---|---|
| 高襟 | ハイカラ | 「西洋風を気取ったり、流行を追ってしゃれたりするさま。また、そのような人」 |
| 鳳梨 | パイナップル | 「イネ目パイナップル科アナナス属に分類される常緑多年草の一種。また、その果実」 |
| 南風 | はえ | 「南の方から吹く風」 |
| 博士 | はかせ、はくし | (はかせ)「ある学問や分野に深く通じていて詳しい人」、(はくし)「大学院での博士課程を修了した者に与えられる最高位の学位。ドクター」 |
| 刷毛 | はけ | 「動物の毛などを束ねて柄(え)を付けたもの」 |
| 方舟 | はこぶね | 「旧約聖書の”ノアの方舟”のこと」など |
| 狭間 | はざま | 「事柄と事柄との間の短い時間」など |
| 麻疹 | はしか、ましん | (はしか、ましん)「発疹性(ほっしんせい)の急性感染症」 |
| 梯子 | はしご | 「高い所へ登るための道具」など |
| 沙魚、蝦虎魚 | ハゼ | 「スズキ目ハゼ亜目に分類される魚類の総称」 |
| 旅籠 | はたご | 「旅籠屋(はたごや:旅人を宿泊させる所。宿屋・旅館)の略」など |
| 二十歳 | はたち、にじ(ゅ)っさい | (はたち、にじ(ゅ)っさい)「20歳」 |
| 燭魚(鰰) | ハタハタ | 「スズキ目ハタハタ科ハタハタ属に分類される海水魚の一種」 |
| 二十日 | はつか、にじゅうにち | (はつか、にじゅうにち)「月の20番目の日」など |
| 飛蝗 | バッタ | 「直翅目バッタ亜目に分類される昆虫の総称」 |
| 服部 | はっとり | 「名字(苗字)のひとつ」 |
| 波止場 | はとば | 「港で、波止(はと:陸から海へ細長く突き出した構造物)を築いた所」 |
| 甘蕉 | バナナ、かんしょう | (バナナ、かんしょう)「ショウガ目バショウ科バショウ属の植物のうち、果実を食用とする品種の総称。また、その果実」。「かんしょう」は、「バナナ」(正式名称)の別名 |
| 含羞む | はにかむ | 「恥ずかしがること。恥ずかしそうな表情をすること」 |
| 埴生 | はにゅう | 「粘土の多い土地」など |
| 羽撃く、羽搏く | はばたく | 「鳥などが翼を広げて上下に強く動かすこと」など |
| 蔓延る | はびこる | 「好ましくないものの勢いが盛んになって広がること」など |
| 聖林 | ハリウッド | 「アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス市北西部の地域」 |
| 熊猫 | パンダ | 「大熊猫(ジャイアントパンダ)と小熊猫(レッサーパンダ)の総称」 |
| 麦酒 | ビール、ばくしゅ | (ビール、ばくしゅ)「麦芽を粉砕して、穀類・水と一緒に加熱して、糖化した汁にホップを加えて苦みや香りをつけ、発酵させたアルコール飲料」 |
| 日雀 | ヒガラ | 「スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属に分類される鳥類の一種」 |
| 抽斗 | ひきだし | 「机や箪笥(たんす)などに物を入れるように取り付けた、抜き差しのできる箱」 |
| 魚籠 | びく | 「獲った魚を入れる籠(かご)」 |
| 鹿尾菜、羊栖菜 | ひじき | 「ヒバマタ目ホンダワラ科ホンダワラ属に分類される褐藻(かっそう)の一種」 |
| 只管 | ひたすら | 「ただそのことだけに心を集中して行うさま」 |
| 吃驚 | びっくり | 「突然のことや意外なことに一瞬驚くこと」 |
| 非道い(酷い) | ひどい | 「残酷であること」など |
| 他人事 | ひとごと | 「自分には関係のないこと。他人に関すること」 |
| 海星 | ヒトデ | 「ヒトデ綱に分類される棘皮動物の総称」 |
| 一人 | ひとり | 「人の数が一つであること。一個の人」など |
| 日向 | ひなた、ひゅうが | (ひなた)「日光の当たっているところ」、(ひゅうが)「旧国名のひとつで、現在の宮崎県あたりの地域」 |
| 雲雀、告天子 | ヒバリ | 「スズメ目ヒバリ科ヒバリ属に分類される鳥類の一種」 |
| 微風 | びふう、そよかぜ | (びふう、そよかぜ)「わずかに吹く風のこと。そよそよと吹く風」 |
| 向日葵 | ヒマワリ | 「キク目キク科ヒマワリ属に分類される一年草の一種」 |
| 風信子 | ヒヤシンス | 「キジカクシ目キジカクシ科ヒヤシンス属に分類される多年草の一種」 |
| 日和 | ひより | 「(”○○日和”の形で)何かをするのにちょうど良い天気」など |
| 比目魚(鮃、平目) | ヒラメ | 「カレイ目ヒラメ科ヒラメ属に分類される海水魚の一種」など |
| 領巾、肩巾 | ひれ | 「昔、貴婦人が正装したときに肩にかけて飾りとした細長く薄い布」 |
| 檜皮 | ひわだ | 「檜(ヒノキ)の樹皮」など |
| 夫婦 | ふうふ、めおと | (ふうふ、めおと)「結婚している1組の男女。夫と妻」 |
| 雲脂 | ふけ | 「頭の皮膚にできる、角質に分泌物が混じって乾いた、うろこ状の白いもの」 |
| 相応しい | ふさわしい | 「釣り合っていること。似合っていること」 |
| 武士 | ぶし、もののふ | (ぶし)「武芸を身に付け、戦陣に立つ人」、(もののふ)「武芸を身に付け、戦陣に立つ人」など |
| 浮腫 | ふしゅ、むくみ | (ふしゅ、むくみ)「皮膚の下などに体液が大量に溜(た)まった状態」 |
| 二人 | ふたり | 「人の数が二つであること。二個の人」 |
| 二日 | ふつか、ににち | (ふつか、ににち)「月の2番目の日」など |
| 山毛欅 | ブナ | 「ブナ目ブナ科ブナ属に分類される落葉高木の一種」 |
| 吹雪 | ふぶき | 「強い風を伴って激しく降る雪」など |
| 下手 | へた、したて、しもて | (へた)「物事のやり方が巧みでないこと。手際が悪いこと。また、そのさまやその人」など、(したて)「相手に対して遜(へりくだ)ること」など、(しもて)「位置・方向が下の方」 |
| 糸瓜 | ヘチマ | 「ウリ目ウリ科ヘチマ属に分類される蔓性の一年草の一種。また、その果実」 |
| 反吐 | へど | 「飲食して胃に入れたものを吐き戻すこと。また、その吐き戻したもの」 |
| 可坊 | べらぼう | 「程度がひどいこと。甚だしいこと」など |
| 竹麦魚 | ホウボウ | 「スズキ目ホウボウ科ホウボウ属に分類される海水魚の一種」など |
| 鬼灯 | ホオズキ | 「ナス目ナス科ホオズキ属に分類される多年草の一種」 |
| 黒子 | ほくろ、くろこ | (ほくろ)「皮膚の表面にある黒色の小さな斑点」、(くろこ)「歌舞伎などにおいて、黒い衣服を着ている舞台上で役者をサポートする人」など |
| 反故、反古 | ほご | 「取り消すこと。破棄すること」など |
| 時鳥、杜鵑、不如帰 | ホトトギス | 「カッコウ目カッコウ科カッコウ属に分類される鳥類の一種」 |
| 海鞘、老海鼠 | ホヤ | 「ホヤ綱に分類される海産動物の総称」 |
| 小火 | ぼや | 「小さな火事」 |
| 微酔 | ほろよい | 「少し酒に酔うこと。また、少し酒に酔った状態」 |
| 雪洞 | ぼんぼり | 「小さな行灯(あんどん:木や竹の枠に紙を貼り、中に油皿を入れて火をともす照明具)」 |
| 真面目 | まじめ | 「本気であるさま。真剣であるさま」など |
| 不味い | まずい | 「食べ物・飲み物の味が悪いこと」など |
| 木天蓼 | マタタビ | 「ツバキ目マタタビ科マタタビ属に分類される落葉低木の一種」 |
| 燐寸 | マッチ | 「軸木(じくぎ)の先に発火剤をつけた、摩擦によって火をつける道具」 |
| 馬刀貝 | マテガイ | 「マルスダレガイ目マテガイ科マテガイ属に分類される二枚貝の一種」など |
| 微睡む | まどろむ | 「うとうとすること。少しの間眠ること」 |
| 真魚 | まな | 「食用の魚」 |
| 真似 | まね | 「形だけ似せること。真似ること。模倣(もほう)」など |
| 金縷梅(満作、万作) | マンサク | 「ユキノシタ目マンサク科マンサク属に分類される落葉小高木の一種」 |
| 翻車魚 | マンボウ | 「フグ目マンボウ科マンボウ属に分類される海水魚の一種」など |
| 木乃伊 | ミイラ | 「人間または動物の死体が永(なが)く原形に近い形をとどめているもの」 |
| 神酒 | みき | 「神に供える酒」 |
| 三行半 | みくだりはん | 「(現在では)夫婦や恋人の関係を断つこと。離縁すること」など |
| 巫女 | みこ | 「神に仕えて神事を行ったり、神意をうかがって神託を告げる女性」 |
| 神輿 | みこし | 「祭礼のときに担ぐ、神霊を安置した輿(こし:屋形の下に担ぐための2本の長い棒を付けた乗り物)」 |
| 身動ぐ | みじろぐ | 「体を少し動かすこと。身動(みうご)きすること」 |
| 鳩尾 | みぞおち | 「胸骨の下方中央にある、くぼんだ骨がない部分」 |
| 晦日、三十日 | みそか | 「月の30番目の日」など |
| 三十路 | みそじ | 「30歳」など |
| 御手洗 | みたらし、みたらい、おてあらい | (みたらし、みたらい)「神社の入り口にあり、参拝者が手や口を洗い清める所」、(おてあらい)「トイレ。便所」など |
| 見惚れる | みとれる | 「我を忘れて見つめること。うっとりと見入ること」 |
| 土産 | みやげ | 「旅先や外出先から持ち帰るその土地の産物」など |
| 海松、水松 | ミル | 「ミル目ミル科ミル属に分類される緑藻の一種」 |
| 零余子 | むかご | 「腋芽(わきめ:葉の付け根にできる芽)が養分を蓄えて球状となったもの」 |
| 百足 | ムカデ | 「唇脚綱(しんきゃくこう)に分類される節足動物のうち、ゲジ類を除いたものの総称」 |
| 息子 | むすこ | 「親からみた、男の子供」 |
| 眼鏡 | めがね、がんきょう | (めがね)「視力の調整や目を保護するための器具」など、(がんきょう)「視力の調整や目を保護するための器具」 |
| 和布蕪 | めかぶ | 「若布(わかめ)の根際の茎の左右についているひだ状の厚い葉」 |
| 目処 | めど | 「ある事柄について立てた見込み」など |
| 目眩、眩暈 | めまい | 「目が眩(くら)むこと。目が回ってくらくらすること」 |
| 莫大小 | めりやす | 「綿糸または毛糸を機械で編んだ、よく伸縮する編み物」 |
| 甜瓜 | メロン、てんか | (メロン、てんか)「ウリ目ウリ科キュウリ属に分類される蔓性の一年草の一種。また、その果実」。「てんか」は、「メロン」(正式名称)の別名 |
| 土竜 | モグラ | 「真無盲腸目モグラ科に分類される哺乳類の総称」 |
| 木蘭(木蓮) | モクレン | 「モクレン目モクレン科モクレン属に分類される落葉低木の一種」 |
| 猛者 | もさ | 「勇猛で力技の優れた人」 |
| 百舌、百舌鳥 | モズ | 「スズメ目モズ科モズ属に分類される鳥類の一種」など |
| 水雲 | モズク | 「シオミドロ目ナガマツモ科モズク属に分類される褐藻の一種」 |
| 紅葉 | もみじ、こうよう | (もみじ)「ムクロジ目ムクロジ科カエデ属に分類される落葉高木の総称。楓(カエデ)のこと」など、(こうよう)「木の葉が黄・赤色に変わること。また、その色づいた木の葉」 |
| 木綿 | もめん | 「ワタ(植物)の種子からとった白くてやわらかい繊維のこと。また、その繊維で作られた糸や織物」 |
| 主水 | もんど | 「主水司(もんどのつかさ)の略」 |
| 翻筋斗 | もんどり | 「空中で体を1回転させること。宙返り」 |
| 漢字 | 読み方 | 意味など |
|---|---|---|
| 八百長 | やおちょう | 「勝負事において、表面上は真剣に争っているように見せて、前もって打ち合わせた通りに勝負をつけること」 |
| 八百屋 | やおや | 「野菜などを売る店。また、売る人」など |
| 八百万 | やおよろず | 「数が非常に多いこと」 |
| 山羊 | ヤギ | 「鯨偶蹄目ウシ科ヤギ属に分類される哺乳類の総称」 |
| 自棄 | やけ | 「物事が思うようにならず、投げやりになって無茶な言動をすること」 |
| 火傷 | やけど、かしょう | (やけど)「高熱によって皮膚が傷つくこと。また、その傷」など、(かしょう)「高熱によって皮膚が傷つくこと。また、その傷」 |
| 玄孫 | やしゃご | 「孫の孫のこと。曽孫(ひまご)の子」 |
| 馬陸 | ヤスデ | 「倍脚綱(ばいきゃくこう)に分類される節足動物の総称」 |
| 寄居虫(宿借) | ヤドカリ | 「十脚目ヤドカリ科・ホンヤドカリ科・オカヤドカリ科などに分類される甲殻類の総称」 |
| 寄生木(宿り木) | ヤドリギ | 「ビャクダン目ビャクダン科ヤドリギ属に分類される常緑低木の一種」 |
| 流鏑馬 | やぶさめ | 「馬を走らせながら鏑矢(かぶらや)で3つの的を射る競技」 |
| 山鼠、冬眠鼠 | ヤマネ | 「齧歯目(げっしもく)ヤマネ科ヤマネ属に分類される哺乳類の一種」 |
| 守宮、家守 | ヤモリ | 「有隣目ヤモリ科ヤモリ属に分類される爬虫類の一種。日本守宮(ニホンヤモリ)のこと」など |
| 弥生 | やよい | 「陰暦(旧暦)における3月」 |
| 夕星 | ゆうずつ | 「夕方、西の空に輝いている金星。宵の明星(よいのみょうじょう)のこと」 |
| 所以 | ゆえん | 「わけ。理由」 |
| 浴衣 | ゆかた、よくい | (ゆかた)「入浴後や夏に着る、木綿で作った単衣(ひとえ)の着物」、(よくい)「入浴の際、または入浴後に着る衣服」 |
| 所縁 | ゆかり | 「何らかの関係や繋がりがあること」 |
| 虎耳草(雪の下) | ユキノシタ | 「ユキノシタ目ユキノシタ科ユキノシタ属に分類される多年草の一種」 |
| 行方 | ゆくえ | 「行った先」など |
| 動揺る(揺さ振る) | ゆさぶる | 「意図的に何かを仕掛けて、相手を動揺させること」など |
| 強請(揺すり) | ゆすり | 「人を脅(おど)して金銭や品物などを無理に出させること。また、そういうことをする人」 |
| 強請る(揺する) | ゆする | 「人を脅して、金品を無理に出させること」 |
| 豆腐皮(湯葉、湯波) | ゆば | 「豆乳を煮立てて、その表面にできた薄い皮をすくいとって作った食品」。京都では「湯葉」、日光では「湯波」と表記される |
| 百合 | ユリ | 「ユリ目ユリ科ユリ属に分類される多年草の総称」 |
| 寄席 | よせ | 「講談・落語・漫才などを興行(こうぎょう)する場所」 |
| 他所 | よそ、たしょ | (よそ)「その人に直接関係のない物事や場所」など、(たしょ)「その場所と違った所。他の所」 |
| 余熱 | よねつ、ほとぼり | (よねつ)「冷めずに残っている熱」、(ほとぼり)「事件などが終わったあとまで残っている世間の関心」など |
| 黄泉 | よみ | 「死後に魂が行くとされる所。死者の国」 |
| 四方 | よも | 「東西南北。前後左右。四方」など |
| 海獺、猟虎 | ラッコ | 「食肉目イタチ科ラッコ属に分類される哺乳類の一種」 |
| 洋灯 | ランプ、ようとう | (ランプ、ようとう)「石油を入れた器に火を点(とも)す芯(しん)をさし、その周りをガラス製の筒(つつ)で覆った照明具」 |
| 栗鼠 | リス | 「齧歯目リス科に分類される哺乳類の総称」 |
| 流行 | りゅうこう、はやり | (りゅうこう、はやり)「ある物事などが、社会に一時的に広く行われること。また、その行われている物事」 |
| 檸檬 | レモン | 「ムクロジ目ミカン科ミカン属に分類される常緑低木。また、その果実」 |
| 公魚 | ワカサギ | 「キュウリウオ目キュウリウオ科ワカサギ属に分類される淡水・汽水魚の一種」 |
| 若布、和布 | わかめ | 「コンブ目チガイソ科ワカメ属に分類される海藻の一種」 |
| 病葉 | わくらば | 「病気や害虫におかされて変色した葉」 |
| 山葵 | ワサビ | 「フウチョウソウ目アブラナ科ワサビ属に分類される多年草。また、その根茎」 |
| 勿忘草 | ワスレナグサ | 「シソ目ムラサキ科ワスレナグサ属に分類される多年草の一種。真勿忘草(シンワスレナグサ)のこと」など |
| 早生 | わせ | 「野菜や果物などで熟すのが早いもの」など |
| 海神 | わたつみ、わだつみ | (わたつみ、わだつみ)「海の神」など |
| 草鞋 | わらじ | 「藁(わら)で編んだ草履(ぞうり)状の履物」 |
| 吾亦紅 | ワレモコウ | 「バラ目バラ科ワレモコウ属に分類される多年草の一種」 |
| 雲呑 | ワンタン | 「中華料理の一種。小麦粉をこねて薄くのばした皮に、豚の挽肉(ひきにく)やネギなどを包んだ料理」 |
関連ページ
<難読漢字の一覧>
(写真あり)藜、櫛、羆など
(写真あり)竜髭菜、青梗菜、蕗など
(写真あり)岩魚、栄螺、鱧など
(写真あり)海驢、犀、猫鼬など
(写真あり)花鶏、信天翁、杜鵑など
(写真あり)薊、金木犀、百合など
(写真あり)水黽、蟋蟀、蟷螂など
(写真あり)外郎、皮蛋、雲呑など
(写真あり)行灯、暖簾、轆轤など
愈々、努々、清々しい、瑞々しいなど
誂える、囀る、目眩く、拵えるなど
<読み間違えやすい漢字の一覧>
哀悼、重複、出生、集荷など
<難読漢字の一覧(偏)>
(写真あり)鯆、鰍、鰉など
(写真あり)蝗、蠍、蝮など
(写真あり)梲、栂、樅など
(写真あり)鎹、鍬、釦など
<覚えておきたい知識>
鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など
(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど
<よく使う言葉>
慣習、準拠、言わずもがな、明文化など
慣習的、致命的、便宜的、作為的など
互換性、慢性、普遍性、必然性など