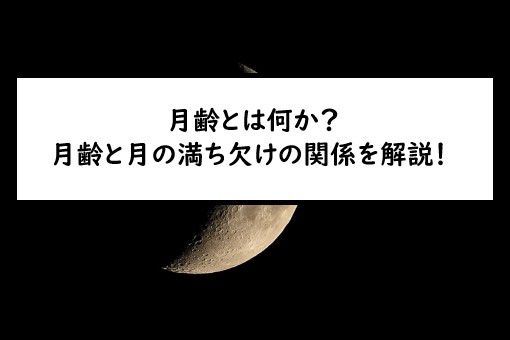1.月齢とは?

結論から言ってしまうと月齢(げつれい)とは、
新月を0として数えたときの日数で、月の満ち欠けの度合いを示したものです。
月齢は新月のときを0として、それから1日経過するごとに数字を1つずつ足していき、
月齢1・月齢2・月齢3....のように数えていきます。
(月齢を用いるときは”月齢1日”のようには言わず、”月齢1”とだけ言います)
ただしこれは1日経過するごとに区切った場合の月齢の数え方で、
区切り方を日ではなく時間などで区切る場合には月齢に小数点が付きます。
(月齢1.3のように小数点が付く場合もある)
ちなみに新月というのは何も見えない状態の月のことを言い、
完全な円で見える状態の満月とは反対の意味としても使われます。
2.月齢と月の満ち欠けの関係をわかりやすく図で解説!
月齢は月の満ち欠けの度合いを表したもので、
月齢29までいくとその次は最初の月齢0(新月)へと戻っていきます。
なぜ月齢0へと戻るのかと言うと、月の満ち欠けが月齢29が終わった時点で1周するからです。
(つまり月の満ち欠けの周期が、1周するのに約29日かかることを意味します)
月の満ち欠けというのは月が地球の周りを移動することにより起こるもので、
その月の満ち欠けが1周するのにかかるのが約29日なので月齢29が最後となります。
この月齢と月の満ち欠けの関係を図で表すと下のようになります。
上図のように月齢が分かれば、月の満ち欠けの度合いも簡単に分かるようになります。
(満月は月齢14~15あたりに見える月で、ここでは月齢14としています)
また月の満ち欠けが1周するのにかかるのは29日(正確には約29.5日)ですが、
実は月が地球の周りを1周するのにかかる時間は約27.3日となっています。
つまり地球が1周するのにかかる時間と、月の満ち欠けが1周するのにかかる時間には、
約2.2日の誤差が生じているということなんですね。
なぜこのような誤差が生じてしまうのか、詳しくは下記をご覧ください。
以上が「月齢とは?月齢と月の満ち欠けの関係をわかりやすく図で解説!」でした。
3.まとめ
これまで説明したことをまとめますと、
- 月齢とは、新月を数字の0として数えたときの日数で、月の満ち欠けの度合いを示したもの。
- 月の満ち欠けは29日で1周するので月齢は”月齢0~月齢29”となる。
関連ページ
⇒月の満ち欠けの仕組みとは?月の満ち欠けの名称を簡単に図で解説!
⇒なぜ三日月は夜に見えないのか?その仕組みを簡単に図で解説!
⇒上弦の月と下弦の月の違いと見分け方とは?どんな形の月をしている?
⇒月はなぜ光るのか?太陽と地球と月の位置関係をわかりやすく図で解説!
⇒月が見える時間帯はなぜ違うのか?月出と月没の時間帯について解説!
<覚えておきたい知識>
鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など
哀悼、重複、出生、集荷など
(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど
(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど
(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など
<豆知識>
(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など
<名前は知っているけどわからないもの>
(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど
(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など
(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど
<よく使う言葉>
慣習、準拠、言わずもがな、明文化など
慣習的、致命的、便宜的、作為的など
互換性、慢性、普遍性、必然性など
蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など