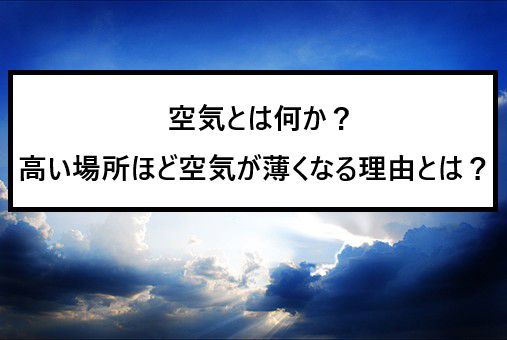1.空気とは何か?
空気(くうき)とは、主に窒素・酸素などの気体によって構成されている混合気体のことです。
空気は、地球の大気圏の下層部分を構成している気体になります。
空気を構成している気体のほとんど(約99%)を占めているのが窒素と酸素で、
他の約1%の中にアルゴンや二酸化炭素など数多くの気体が含まれています。
空気についての詳細な気体構成は下図のようになります。
空気を構成している気体は上図のような構成になりますが、
人間などの生物が生きていくために必要なのは空気中の酸素になります。
酸素は人間などの生物が動くために必要なエネルギーになるので、
十分に酸素を体内に取り入れることができないと酸欠状態になり体の機能が低下します。
このように呼吸することで体内に空気中の酸素を取り入れています。
また呼吸のときに空気中の酸素を取り込み、二酸化炭素を体外へと排出します。
このとき体内に取り入れた酸素がすべて二酸化炭素に変わるのかと言えば、そうではありません。
あくまで呼吸で使われる空気中の酸素はほんの一部で、
体内でエネルギーを生み出す過程で微量の二酸化炭素が発生するだけです。
なので呼吸によっていずれ空気中の酸素がなくなるなんてことはありません。
ちなみに空気というのは無色透明の気体です。
これについては私たちが生活している中ですでに理解していただけていると思います。
そして空気が無色透明な理由は、空気が無色透明な気体だけで構成されているからです。
少しでも色の付いている気体が混ざっていれば無色透明にはなりません。
次の章では高い場所ほど空気が薄くなる理由について説明していきます。
2.高い場所ほど空気が薄くなる理由とは?
結論から言ってしまうと高い場所ほど空気が薄くなる理由は、
地球から離れるほど空気に重力がかかりにくくなるからです。
空気というのは目に見えない無色透明の気体です。
しかし空気が無色透明な気体だからいって、質量がないわけではありません。
すごく軽いですが空気にも質量は存在します。
そして地球上に存在している質量のあるものすべてに、
地球からの重力(中心に引き寄せられる力)が働きます。
なので地球からの重力は無色透明の気体である空気にも働きます。
重力は地球の中心に近づけば近づくほど強く働くので、
地上が最も重力が働く場所ということになります(穴を掘らない限り)。

上図のように高い場所ほど空気が薄くなる(少なくなる)のは、
地上に比べて高い場所のほうが地球の中心から離れてしまうからなんですね。
これにより高い場所に存在する空気に重力がかかりにくくなるので、
高い場所ほど空気が集まらなくなります。
ちなみに同じ地上でも重力の強い場所と弱い場所がある(中心からの距離が異なる)ため、
地上ならすべての場所で等しく重力がかかるわけではないので注意してください。
以上が「空気とは何か?高い場所ほど空気が薄くなる理由とは?」でした。
3.まとめ
これまで説明したことをまとめますと、
- 空気とは、無色透明で主に窒素・酸素などの気体によって構成されている混合気体のこと。
- 高い場所ほど空気が薄くなる理由は、地球から離れるほど空気に重力がかかりにくくなるから。
関連ページ
<覚えておきたい知識>
鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など
哀悼、重複、出生、集荷など
(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど
(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど
(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など
<豆知識>
(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など
<名前は知っているけどわからないもの>
(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど
(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など
(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど
<よく使う言葉>
慣習、準拠、言わずもがな、明文化など
慣習的、致命的、便宜的、作為的など
互換性、慢性、普遍性、必然性など
蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など