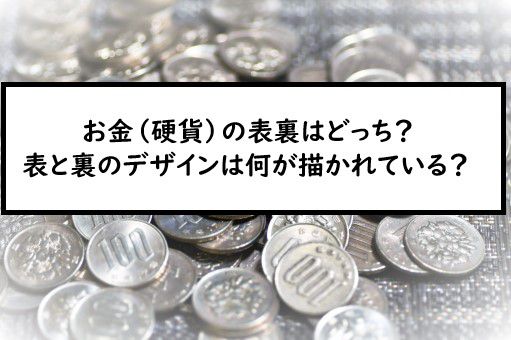
このページではお金(硬貨)の表裏とデザインについて簡単に解説しています。
目次
1.お金(硬貨)の表と裏はどっち?
お金(硬貨)のどっちが表でどっちが裏なのか、下に簡単にまとめてみました。
上のようにお金(硬貨)は”植物や建物などが描かれている面が表”で、
”数字が書かれている面が裏”になります(5円玉のみ例外)。
数字が書かれている面が硬貨の表だと思っていた人も多いですよね。
ただし5円玉だけ他の硬貨と違って裏に数字が書かれていないので注意が必要ですが、
判別するのにより確実なのは何円玉なのかが漢数字で表されているかどうかです。
上のように何円なのかが漢数字(算用数字ではない)で表されていれば、
その面が硬貨の表になりますのでぜひ覚えておいてください。
さて次の章から硬貨の表裏にそれぞれ何が描かれているのかを解説していきますね。
1円玉の表裏とデザイン
では1円玉の表裏とデザインについて見ていきましょう。
1円玉の表には若木、裏には1という数字が描かれています。
また1円玉の素材はアルミニウムでできています。
.jpg)
1円玉の表裏のデザインは一般公募で選出されたものです。
1円玉の表に描かれている若木は特定の植物をデザインしたものではありません。
若木は伸びゆく日本という意味で1円玉に描かれています。
5円玉の表裏とデザイン
では5円玉の表裏とデザインについて見ていきましょう。
5円玉の表には稲穂と水と歯車が、裏には双葉(ふたば)が描かれています。
また5円玉の素材は黄銅でできています。
.jpg)
表のデザインは当時の日本の主な産業を表していて、
稲穂は農業、水が水産業、歯車は工業を表しています。
そして裏面の双葉は、民主主義に向かって伸びていく日本を表しています。
双葉とは植物が芽を出したときに見られる2つの葉のことなので、特定の植物のことではありません。
10円玉の表裏とデザイン
では10円玉の表裏とデザインについて見ていきましょう。
10円玉の表には平等院鳳凰堂と唐草模様が、裏には常盤木(ときわぎ)が描かれています。
また10円玉の素材は青銅でできています。
.jpg)
常盤木というのは特定の植物のことではなく、主に広葉樹からなる森林のことを表しています。
50円玉の表裏とデザイン
では50円玉の表裏とデザインについて見ていきましょう。
50円玉の表には菊が、裏には50という数字が描かれています。
また50円玉の素材は白銅でできています。
.jpg)
50円玉のデザインは1円玉のデザインと同様に、一般公募で選出されたものです。
100円玉の表裏とデザイン
では100円玉の表裏とデザインについて見ていきましょう。
100円玉の表には桜が、裏には100という数字が描かれています。
また100円玉の素材は、50円玉と同じ白銅でできています。
.jpg)
100円玉は最初から桜が描かれていたわけではありません。
最初のデザインは鳳凰、次が稲穂で現在は桜が描かれるようになりました。
500円玉の表裏とデザイン
では500円玉の表裏とデザインについて見ていきましょう。
500円玉の表には桐(きり)が、裏には竹と橘(たちばな)が描かれています。
500円玉の素材はニッケル黄銅でできています。
.jpg)
ちなみに500円玉は硬貨としては価値が高いため、様々な偽造防止の技術が施されています。
以上が「お金(硬貨)の表裏はどっち?表と裏のデザインは何が描かれている?」でした。
2.まとめ
これまで説明したことをまとめますと、
- お金(硬貨)は何円玉なのかが漢数字で書かれている面が表になる。
<日本の硬貨(お金)の表裏とデザイン>
- 1円玉の表には若木、裏には1という数字。
- 5円玉の表には稲穂と水と歯車、裏には双葉。
- 10円玉の表には平等院鳳凰堂と唐草模様、裏には常盤木。
- 50円玉の表には菊、裏には50という数字。
- 100円玉の表には桜、裏には100という数字。
- 500円玉の表には桐、裏には竹と橘。
関連ページ
<覚えておきたい知識>
鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など
哀悼、重複、出生、集荷など
(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど
(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど
(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など
<豆知識>
(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など
<名前は知っているけどわからないもの>
(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど
(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など
(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど
<よく使う言葉>
慣習、準拠、言わずもがな、明文化など
慣習的、致命的、便宜的、作為的など
互換性、慢性、普遍性、必然性など
蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など

の表裏.svg)
の表裏は漢数字.svg)