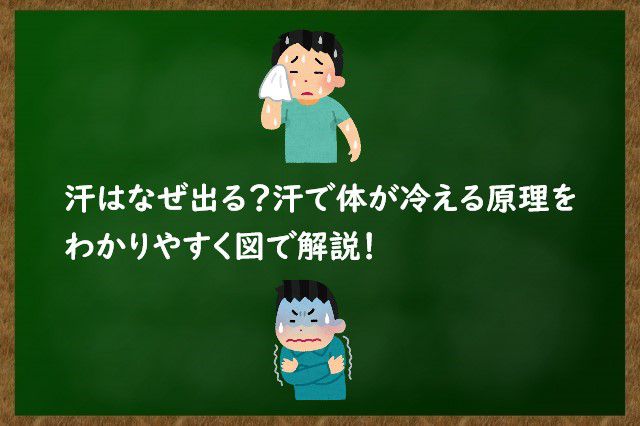
このページでは汗はなぜ出るのか。また、汗で体が冷える原理をわかりやすく図で解説しています。
目次
1.汗はなぜ出るのか?

結論からいってしまうと汗が出る理由は、”体温を下げるため”です。
汗が出るということは、(病気や精神的なものを除いて)体に熱がたまっていて、その熱を体外へ放出する(体温を下げる)ように脳が体に(汗を出すように)指示している、ということです。
体に熱がたまりすぎる(体温が上がりすぎる)と、体を構成しているタンパク質の性質が変化するため、それにより体の機能が正常に働かなくなって生命活動に影響が出てしまうため、汗を出して体温を調節しようとします。
”汗が出ること=体温が下がる”というわけではなく、皮膚表面に汗が出てきて、その汗(水分)が蒸発するときに、蒸発して汗から変化した水蒸気が熱を持ったまま体から離れていく(熱が奪われる)ため体温は下がっていきます。
このように液体(ここでは汗)が蒸発するために必要な熱のことを「気化熱(きかねつ)」といい、”体から気化熱が奪われることで体温が下がる”のように表現されることが多いです。
(次の章でイメージしやすいように汗の気化熱で体が冷える原理を簡単に解説していますが、正確にいうと気化熱は潜熱(せんねつ)の一種です)
2.汗で体が冷える原理について
汗で体が冷えるのは、”汗(水分)が接している皮膚表面から気体に変化するために必要な熱(気化熱)を奪って、気体に変化したときに奪った熱を持ったまま(熱を奪った)皮膚表面から離れていくから”です。
では汗で体が冷える(体温が下がる)原理について、以下の順番で詳しく解説していきます。
- 2.1 汗が出るということは、皮膚表面に水分(液体)が付着しているということ
- 2.2 温度は物質の持っている熱の平均を指し、同じ物質でも10℃や90℃に相当する熱を持つ原子・分子がある
- 2.3 水を構成している水分子の中で、100℃に相当する熱を得た水分子から蒸発していく(汗も同じ)
- 2.4 汗の水分が蒸発すると熱を持ったまま水蒸気が空気中へと出ていき、残った汗の持っている熱は減少する
- 2.5 残った汗は温度が低くなり、温度の高い皮膚表面から熱を奪い(体は冷える)、その熱は汗の蒸発に使われる
2.1 汗が出るということは、皮膚表面に水分(液体)が付着しているということ
汗が出るということは、皮膚表面に水分(液体)が付着しているということです。

汗は約99%が水(液体)からできていて、他にはミネラルなどが含まれています。
2.2 温度は物質の持っている熱の平均を指し、同じ物質でも10℃や90℃に相当する熱を持つ原子・分子がある
温度は物質の持っている熱の平均のことを指し、同じ物質でも10℃や90℃に相当する熱を持っている原子・分子があります。
世の中の物質は原子・分子(小さな粒子)で構成されていて、水の場合だと水分子がたくさん集まることで構成されています。
例えば40℃の水は、全ての水分子が40℃に相当する熱を持っているわけではありません。
上図(数値は適当)のように10℃に相当する熱を持っている水分子もあれば、90℃に相当する熱を持っている水分子も存在し、温度は物質を構成している原子・分子の持っている熱を平均して数値化したものを指しています。
関連:熱と温度の違いとは?
2.3 水を構成している水分子の中で、100℃に相当する熱を得た水分子から蒸発していく(汗も同じ)
水を構成している水分子の中で、100℃に相当する熱を得た水分子から蒸発していきます(汗は約99%が水なので同じ)。
(なので水の温度が高い(水を構成している水分子の持っている熱の平均が高い)ほど、水分子が100℃に相当する熱を獲得しやすいため蒸発しやすくなります)
水を構成している水分子は、水分子同士で常に熱の移動(つまり水分子同士で熱を与えたり奪ったり)を繰り返しています。
この水分子同士の熱の移動により、水を構成している水分子の中で100℃に相当する熱を得た(液体から気体に変化するために必要な熱(気化熱)が集まった)ものは気体に変化して水蒸気となります。
これにより水は100℃(100℃に相当する熱の平均)に達していなくても蒸発(液体の表面から気体に変化)していきます。
(水たまりや食器に付着した水滴が、時間が経つと乾いているのはこのためです)
2.4 汗の水分が蒸発すると熱を持ったまま水蒸気が空気中へと出ていき、残った汗の持っている熱は減少する
汗の水分が蒸発(=汗を構成している水分子が100℃に相当する熱を持っている)すると熱を持ったまま水蒸気が空気中へと出ていき、残った汗の持っている熱は減少します。
例えば汗が全部で20(温度[℃]のことではない)の熱を持っているとして、熱の移動により100℃相当の熱を得た(汗を構成している)水分子は、水蒸気に変化して熱を持ったまま空気中へと出ていきます。
これにより残った汗の持っている熱は全部で16(20-4)になるため、残った汗の持っている熱が少なくなります(=残った汗の温度が下がる)。
つまり蒸発して水蒸気に変化した汗は、残った汗から気化熱(液体から気体に変化するために必要な熱)を奪ったことで蒸発することができたということになります。
2.5 残った汗は温度が低くなり、温度の高い皮膚表面から熱を奪い(体は冷える)、その熱は汗の蒸発に使われる
残った汗の温度が低くなった(持っている熱が少なくなった)ことで、残った汗と接している温度の高い(持っている熱が多い)皮膚表面から(残った汗が)熱を奪っていきます。
皮膚表面から熱を奪うことで汗に熱が与えられるため、再び汗の水分は蒸発しやすく(100℃に相当する熱を持つ水分子が発生しやすく)なります。
これを繰り返していくことで汗がどんどん蒸発していき、皮膚表面からもどんどん熱が奪われていくため体は冷える(体温が下がる)、というわけです。
以上が「汗はなぜ出る?汗で体が冷える原理をわかりやすく図で解説!」でした。
3.まとめ
これまで説明したことをまとめますと、
- 汗が出るのは、”体温を下げるため”。
- ”汗が出る=体温が下がる”ではなく、蒸発して汗から変化した水蒸気が熱を持ったまま体から離れていく(熱が奪われる)ため体温は下がる。
- 汗で体が冷えるのは、”汗(水分)が接している皮膚表面から気体に変化するために必要な熱(気化熱)を奪って、気体に変化したときに奪った熱を持ったまま(熱を奪った)皮膚表面から離れていくから”。
関連ページ
<覚えておきたい知識>
鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など
哀悼、重複、出生、集荷など
(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど
(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど
(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など
<豆知識>
(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など
<名前は知っているけどわからないもの>
(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど
(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など
(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど
<よく使う言葉>
慣習、準拠、言わずもがな、明文化など
慣習的、致命的、便宜的、作為的など
互換性、慢性、普遍性、必然性など
蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など




