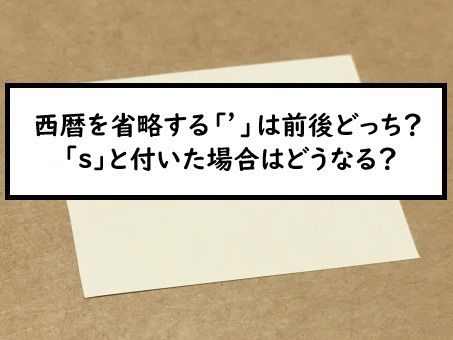
このページでは西暦を省略する「’」は前後どちらに付くのか?。また「s」と付いた場合は何を表しているのかを解説しています。
1.西暦を省略するときの「’」は前後どちらに付くのが正しい?

結論から言ってしまうと、「’」は後ろではなく西暦を表す数字の前に付けます。
「’」の記号の名称は、”アポストロフィー”と言って省略・短縮の意味を持っています。
上のように1999年で言えば、千の位(1)と百の位(9)が省略され、
その省略された部分に「’」が入り、「’99年」と表示されることになります。
なので英語で「I am ⇒ I’m」にするのと考え方は同じです。
また1899年を省略しても「’99」年になってしまうので、
西暦におけるどの年を指しているのかは、前後の文脈から判断するしかないため注意が必要です。
関連:よく使うけどちょっと難しい言葉や表現の一覧!(慣習、準拠、言わずもがな、明文化など)
次の章で西暦の後ろに「s」と付いている場合について解説していきますね。
2.「s」と付いている場合は何を表している?
さっそくですが西暦の後ろに「s」が付いている場合は、その年代のことを表しています。
(1900s ⇒ 1900年代、1930s ⇒ 1930年代)
ここでの「s」というのは英語などでよく用いられている”複数形のs”のことで、
物などが2個以上存在するときにはその単語の後ろに「s」が付きます。
例えば上のように”1900s”であれば1900年代を表しており、
1900年~1999年までの100年間を表していることになります。
他にも”1930s”であれば1930年代のことを表しており、
1930年から1939年までの10年間のことを表していることになります。
このように西暦の後ろに「s」が付いているときはその年代を表し、
「s」とは”複数形のs”のことを表しているというわけです。
ちなみに”1900’s”と表現されている場合も”1900s”と意味は同じで、
どちらかと言えば年代を表すときは、「’」が省略されている方が多いので覚えておきましょう。
以上が「西暦表示を省略する「’」は前後どちらに付く?また「s」と付いた場合はどうなる?」でした。
3.まとめ
これまで説明したことをまとめますと、
- 西暦1999年を省略するときは、「’99年」と数字の前に「’」を表示する。
- 「’」の記号の名称は”アポストロフィー”と言い、省略・短縮などの意味を持つ。
- 西暦の後ろに「s」が付く場合は年代を表し、1900sであれば1900年代のことを表している。
関連ページ
⇒西暦とは何か?西暦はいつから使われた?西暦・和暦・干支の早見表!
⇒紀元前とは?またBCとADの意味や表を分かりやすくまとめました!
⇒2月が28日しかない理由とは?なぜうるう年は2月に調整される?
<覚えておきたい知識>
鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など
哀悼、重複、出生、集荷など
(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど
(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど
(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など
<豆知識>
(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など
<名前は知っているけどわからないもの>
(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど
(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など
(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど
<よく使う言葉>
慣習、準拠、言わずもがな、明文化など
慣習的、致命的、便宜的、作為的など
互換性、慢性、普遍性、必然性など
蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など


