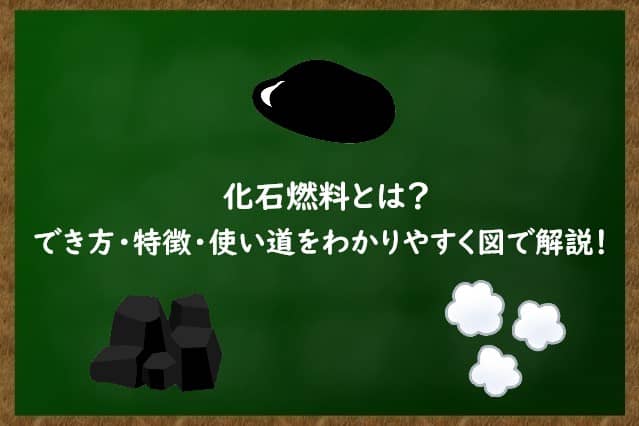
このページでは化石燃料とは何か。化石燃料のでき方・特徴・使い道をわかりやすく図で解説しています。
1.化石燃料とは何か?
結論からいってしまうと化石燃料とは、”古代の生物(主に植物やプランクトン)の死骸が地中に堆積し、長い時間をかけて地圧や地熱などの影響で変化してできた、燃料として用いられるものの総称”です。
(燃料になるまでの過程が、恐竜やアンモナイトなどの化石ができる過程に似ていることから「化石燃料」と呼ばれています)
代表的な化石燃料でいうと「石炭(せきたん)・石油(せきゆ)・天然ガス」の3種類があり、これら以外の化石燃料には「メタンハイドレート(別名:燃える氷)・シェールオイル・シェールガス」が存在します。
化石燃料は、古代の生物の死骸が地中に堆積して変化したものなので、埋蔵量(地中に埋まっている量)には限りがあります。
2020年末時点では「石炭の可採年数=139年」「石油の可採年数=53.5年」「天然ガスの可採年数=48.8年」とされています。
(このように”天然資源において、今後、何年にわたって生産・採掘が可能であるかを示したもの”を「可採年数(かさいねんすう)」と言います)
「可採年数=確認埋蔵量/年間生産量(年間採掘量)」
また化石燃料を燃やすと、「二酸化炭素(CO₂)・二酸化硫黄(SO₂)・窒素酸化物(NOx)」を発生させるため、地球温暖化や酸性雨の原因として知られています。
2.化石燃料のでき方
化石燃料は、”古代の生物(主に植物やプランクトン)の死骸が地中に堆積し、長い時間をかけて地圧や地熱などの影響で変化してできた、燃料として用いられるものの総称”です。
ではどのように化石燃料ができたのかを「石炭のでき方」「石油・天然ガスのでき方」に分けて、もう少し詳しく解説していきます。
石炭のでき方
石炭は、大型のシダ植物が水底に積もり、その上に土や砂が堆積し、長い年月(数千万~数億年)をかけて地圧・地熱によって変化してできたものです。
まず今から数千万年~数億年前に、海や湖の近くに大型のシダ植物が生えていて、そのシダ植物が倒れたり、陸地に倒れたシダ植物がのちに水中に落ちたりして水底に積もっていきます。
(現在と違って古生代ではシダ植物を分解する菌がほとんど存在していないため分解されにくく、さらに酸素の少ない水中ではほとんど分解されずに残る)
そして水底に積もったシダ植物の上から土や砂が堆積し、シダ植物は地圧・地熱によって押し固められて徐々に石炭に変化していき、数千万~数億年かけて石炭になります。
石油・天然ガスのでき方
石油・天然ガスは、主にプランクトンの死骸が水底に積もり、その上に土や砂が堆積し、長い年月(数千万~数億年)をかけて地圧・地熱によって変化してできたものです。
(プランクトンとは、”水中に浮遊し、水流に逆らう遊泳能力を持たないために自由に泳ぐことができない生物の総称”を指します)
まず今から約2億年前に、海中を浮遊していたプランクトンの死骸が水底に沈み、それが積もっていき、長い時間をかけてその上に土や砂が堆積します。
地圧(上に堆積した土や砂による圧力)・地熱の影響によって、積もったプランクトンの死骸などが変化して「ケロジェン」と呼ばれる泥岩(でいがん)を生じます。
そしてケロジェンは地熱の影響でさらに熱分解が進むと、水・原油(精製すると石油になる)・天然ガスに分解される(水⇒原油⇒天然ガスのように重い順に下にたまる)、というわけです。
(泥は地圧で押し固められ頁岩になり、頁岩は気体・液体を通さないため、原油や天然ガスを逃がさない蓋の役割を果たします)
3.化石燃料の特徴と使い道
化石燃料はエネルギー密度が高く、少量で多くのエネルギーを発生させることができるため重宝されています。
(ただ近年ではカーボンニュートラルに向けて、できるだけ化石燃料の使用を減らして自然エネルギーなどで代替する動きになってきています)
では化石燃料の特徴と使い道について以下の順番でそれぞれ解説していきます。
- 石炭の特徴と使い道
- 石油の特徴と使い道
- 天然ガスの特徴と使い道
石炭の特徴と使い道

※上は石炭の写真
石炭の特徴として、他の2つの化石燃料と比べて資源量が豊富で安価に調達できますが、燃やしたときに空気中への二酸化炭素の排出量が多くなってしまうことが挙げられます。
他の2つの化石燃料と比べて石炭は資源量が豊富なため可採年数も長く、安い価格で調達することができます。
また、石炭を燃やしたときの二酸化炭素の発生量を100とすると、石油は80、天然ガスは60の二酸化炭素を発生させます。
石炭の使い道としては、主に「火力発電・セメント製造時などの燃料」「製鉄時の燃料となるコークスの原料」が挙げられます。
日本では電力の約70%を火力発電に頼っており、化石燃料における発電実績として2023年度では「石炭は31.8%」(「天然ガスは35.4%」「石油は1.5%」)となっています。
セメント製造の焼成(原料を高熱で焼いて、性質に変化を生じさせる)工程においても、燃料として主に石炭が使用されています。
また、石炭は製鉄(鉄鉱石から鉄を取り出すこと)時の燃料となるコークスの原料にも使用されています。

※上はコークスの写真
コークスは”石炭を蒸し焼き(乾留)にすることで、石炭から硫黄やアンモニアなどの成分が抜けて、炭素部分だけを残した燃料のこと”で、これにより石炭よりも同じ質量あたりの発熱量が増加(つまり火力が強くなる)します。
そして他にも燃料にコークスを使う理由として、鉄鉱石に含まれる酸素を取り除いて、鉄を取り出すという役割があります。
鉄鉱石の主要成分は酸化鉄(酸素と結びついた鉄)で、簡単に言えば鉄鉱石というのは「錆(さび)の塊」です。
なので鉄鉱石(酸化鉄)から酸素を失わせることができれば、鉄鉱石は鉄になります。
炉内(ろない)でコークス(ほぼ炭素:C)を燃やして熱を発生させ、それに鉄鉱石(酸化鉄:Fe₂O₃)を入れて溶かすことで、鉄鉱石中の酸素(O)をコークスの炭素(C)と反応させて奪う(酸素は、鉄よりも炭素と結びつきやすいため)ことができます。
(正確には他にも石灰石を入れたり細かい手順があったりしますが、ここでは長くなるので省きます)
石油の特徴と使い道
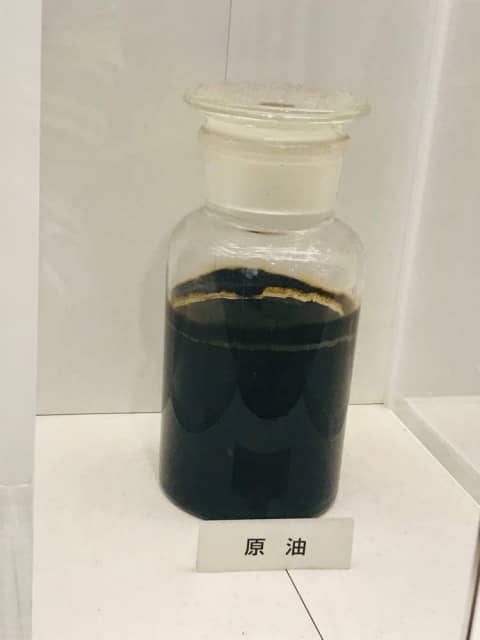
※上は原油(採掘されたままの不純物が多く含まれる石油)の写真
石油の特徴として、他の2つの化石燃料と比べて貯蔵がしやすいですが、原油価格の変動が大きかったり、中東依存度が高くなってしまうことが挙げられます。
(石油というのは、”原油と原油を精製(蒸留)して作られる石油製品(ガソリン・灯油・軽油など)の総称”を指します)
原油価格の変動が大きくなるのには様々な要因がありますが、一例として産油国の連合であるOPEC(オペック:石油輸出国機構)が原油の増産・減産を決め、それにより原油の供給量(売ろうとする量)が需要量(買おうとする量)を上回ると価格は下がり、反対に原油の供給量が需要量を下回ると価格は上がります。
(原油に限らず、基本的に商品の供給量が需要量を上回れば価格は下がり、反対に原油の供給量が需要量を下回ると価格は上がります)
また、他にも中東地域における情勢も原油価格の変動に大きく反映され、例えば中東地域で紛争・戦争が起こることで原油輸送ルートの変更を余儀なくされ、遠回りせざるを得なくなって輸送コストが増えるため、それが原油価格にも反映されて原油価格が上がります。
(中東依存度が高くなってしまうと、上記のようなリスクもある)
石油の使い道としては、主に「火力発電や機械の燃料」「プラスチックなどの原料」が挙げられます。
日本では電力の約70%を火力発電に頼っており、化石燃料における発電実績として2023年度では「石油は1.5%」(「石炭は31.8%」「天然ガスは35.4%」)となっています。
昔は原油(採掘されたままの不純物が多く含まれる石油)をそのまま燃料として使用することもありましたが、現在では原油を精製(分留)してできた石油製品(ガソリン・灯油・軽油など)を使用することがほとんどです。
(「分留(ぶんりゅう)」は、正式には「分別蒸留(ぶんべつじょうりゅう)」と言い、”複数の成分から構成される液体を、各成分の沸点(液体が気体に変化する温度)の違いを利用して分離する技術のこと”を指します)
原油の精製(分留)工程として、原油タンクから加熱炉(かねつろ)に原油が送られて加熱(300℃~350℃)され、その後に加熱された原油は蒸留塔に送られます。
上図のように蒸留塔では分留によって原油が各石油製品に分けられ、それらの石油製品が日常生活において非常に重要な役割を果たしています。
例えば日常生活における石油製品の使い道として、
「LPガス(プロパンガス) ⇒ 主にタクシーの燃料、ガスコンロや給湯器の燃料」
「ガソリン ⇒ 主に自動車の燃料」
「ナフサ ⇒ 主に化学製品(プラスチックなどの合成樹脂・合成ゴム・合成繊維など)の原料」
「灯油 ⇒ 主に暖房器具の燃料」
「ジェット燃料 ⇒ 主に航空機のジェットエンジンの燃料」
「軽油 ⇒ 主にトラック・バスの燃料」
「重油 ⇒ 主に船舶(せんぱく)や火力発電の燃料」
「アスファルト ⇒ 主に道路舗装」
に使用されています。
「LPガス(LPG)」は、「Liquefied Petroleurn Gas(リキファイド ペトロリウム ガス)」の頭文字をとった言葉で、日本語では「液化石油ガス」と言います。
.jpg)
※上はボンベに貯蔵されたLPガス(プロパンガス)の写真
液化石油ガスというのは、”圧力をかけて圧縮することで、常温で容易に液化(気体が液体に変化)できるガス燃料(気体状の燃料)のこと”で、一般的にはプロパンガスがLPガスにあたります。
(LPガスを液化させることで、体積が気体の時の約250分の1に縮小するため、液化させた方がLPガスを効率よく貯蔵・運搬できるようになります)
また、もともとプロパンガスは無色・無臭ですが、ガス漏れを感知できるように付臭され、その臭いはよく”玉ねぎが腐ったような臭い”と表現されます。
天然ガスの特徴と使い道

※上は都市ガス(原料は天然ガス)を貯蔵するガスタンク(正式にはガスホルダー)の写真
天然ガスの特徴として、他の2つの化石燃料と比べて二酸化炭素の排出量が少ないですが、インフラ整備が必要だったり、貯蔵・輸送が難しくなってしまうことが挙げられます。
天然ガスを燃やしたときの二酸化炭素の発生量を60とすると、石油は80、石炭は100の二酸化炭素を発生させます。
また、天然ガスはLPガス(プロパンガス)と違って、(常圧で)-162℃に冷却させないと液化できないため、特殊な設備がなければ貯蔵・輸送が難しくなってしまいます(液化させることで体積が600分の1に縮小する)。
これによりLPガスと同じようにボンベに入れて供給するという方法がコスト面(冷却設備が必要)で現実的ではなく、都市ガス(原料は天然ガス)を使用する場合にはインフラ整備(道路の下のガス管の整備)が必須になってしまいます。
天然ガスの使い道としては、主に「火力発電の燃料」「都市ガスの原料」が挙げられます。
日本では電力の約70%を火力発電に頼っており、化石燃料における発電実績として2023年度では「天然ガスは35.4%」(「石炭は31.8%」「石油は1.5%」)となっています。
天然ガスは、都市ガス(都市部を中心にガス管が整備されている地域で利用できるガス)の原料にも使用されています。
日本では、都市ガスの原料となる天然ガスのほとんどを輸入に頼っており、LNGタンカー(天然ガスを液化させて体積を小さくして大量に輸送するために、特殊な設備の整った大型タンクを搭載した船)を使って海外から運ばれてきます。
(「LNG」は、「Liquefied Natural Gas(リキファイド ナチュラル ガス)」の頭文字をとった言葉で、日本語では「液化天然ガス」と言います)
上図のようにLNGタンカーからLNG貯蔵タンクにLNG(液化天然ガス)が送られ、そこからLNGが気化器に送られて海水で温めることでLNG(液体)から天然ガス(気体)に戻されます。
その後に熱量調整(LPガス(液化石油ガス)などを混ぜて燃やしたときに発生する熱量を調整)をして、付臭装置によって天然ガスに臭いが付けられることで都市ガスが出来上がり、それがガス管を通して各家庭・企業・工場などに供給される、というわけです。
(プロパンガスと同様に、もともと天然ガスも無色・無臭ですが、ガス漏れを感知できるように付臭され、その臭いはよく”玉ねぎが腐ったような臭い”と表現されます)
以上が「化石燃料とは?でき方・特徴・使い道をわかりやすく図で解説!」でした。
4.まとめ
これまで説明したことをまとめますと、
- 化石燃料とは、”古代の生物(主に植物やプランクトン)の死骸が地中に堆積し、長い時間をかけて地圧や地熱などの影響で変化してできた、燃料として用いられるものの総称”。
- 代表的な化石燃料には「石炭(せきたん)・石油(せきゆ)・天然ガス」の3種類が存在する。
- 石炭は、大型のシダ植物が水底に積もり、その上に土や砂が堆積し、長い年月(数千万~数億年)をかけて地圧・地熱によって変化してできたもの。
- 石油・天然ガスは、主にプランクトンの死骸が水底に積もり、その上に土や砂が堆積し、長い年月(数千万~数億年)をかけて地圧・地熱によって変化してできたもの。
- 石炭の使い道は、主に「火力発電・セメント製造時などの燃料」「製鉄時の燃料となるコークスの原料」。
- 石油の使い道は、主に「火力発電や機械の燃料」「化学製品(プラスチックなどの合成樹脂・合成ゴム・合成繊維など)の原料」。
- 天然ガスの使い道は、主に「火力発電の燃料」「都市ガスの原料」。
関連ページ
<覚えておきたい知識>
鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など
哀悼、重複、出生、集荷など
(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど
(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど
(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など
<豆知識>
(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など
<名前は知っているけどわからないもの>
(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど
(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など
(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど
<よく使う言葉>
慣習、準拠、言わずもがな、明文化など
慣習的、致命的、便宜的、作為的など
互換性、慢性、普遍性、必然性など
蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など





.svg)
