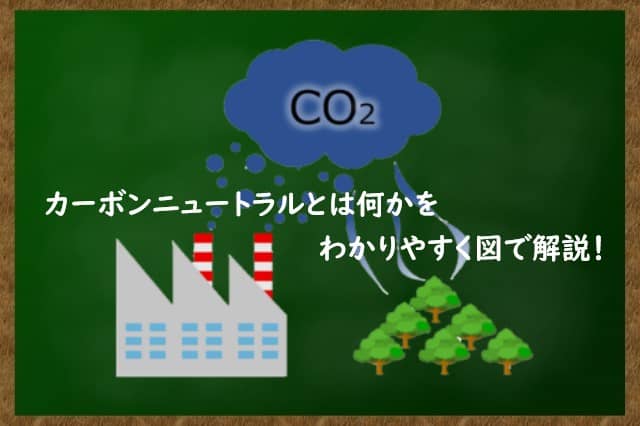
このページではカーボンニュートラルとは何かをわかりやすく図で解説しています。
目次
1.カーボンニュートラルとは何か?
結論からいってしまうとカーボンニュートラルとは、”二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を吸収・除去して(排出量から)差し引くことで、大気中への温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする、という考え方のこと”です。
※出典:環境省:脱炭素ポータル「カーボンニュートラルとは」を元に作成
もっとわかりやすく説明すると、大気中(地球の大気=空気)への温室効果ガスの排出をゼロにすることは非常に難しいため、排出せざるを得なかった分と同じくらいの量の温室効果ガスを吸収・除去することで、大気中への温室効果ガスの排出を実質的にゼロにするというものです。
カーボンニュートラルは、大気中の温室効果ガスの増加が原因で進行している地球温暖化を防止するために生まれた考え方で、直訳すると「カーボン(carbon:炭素)」「ニュートラル(neutral:中立)」となります。
(温室効果ガスには二酸化炭素・水蒸気・メタン・フロンなどがありますが、地球温暖化に最も大きく影響するのが二酸化炭素とされているため、名称にカーボン(炭素)が用いられます)
カーボンニュートラルの取り組みは世界中で行われ、日本では2020年10月に「2050年カーボンニュートラル」(2050年までに大気中への温室効果ガスの排出量から吸収・除去量を差し引いて実質ゼロを目指す)が表明され、国・地方自治体・企業によるカーボンニュートラル実現へ向けた取り組みが行われています。
2.カーボンニュートラル実現のための取り組みの例
ではカーボンニュートラル実現のための取り組みの例について、以下の順番で解説していきます。
- ①化石燃料の代替として再生可能エネルギーを利用し、大気中に発生する二酸化炭素の削減
- ②植林によって、植物の光合成による大気中の二酸化炭素の吸収量の増加
- ③DAC(直接空気回収技術)による大気中の二酸化炭素の除去
①化石燃料の代替として再生可能エネルギーを利用し、大気中に発生する二酸化炭素の削減
化石燃料の代わりに再生可能エネルギーを用いることで、(化石燃料を燃やすことで発生する)大気中への二酸化炭素の排出を減らすことができます。
再生可能エネルギーというのは”自然界に常に存在し、枯渇(こかつ)せずに繰り返し利用できるエネルギーのこと”で、太陽光・風力・水力・地熱などが再生可能エネルギーに該当します。
(化石燃料を燃やすと大気中に二酸化炭素が排出されますが、再生可能エネルギーを利用しても大気中に二酸化炭素は排出されません)
※火力発電、原子力発電は再生可能エネルギーによる発電ではない
例えば一般的には上図のような発電方法がありますが、太陽光発電は”太陽光をエネルギー源として電気エネルギーに変換”し、水力発電は”水が高いところから低いところへと流れるときの水の勢いを利用して電気エネルギーに変換”しています。
(電気自動車(EV)は火力発電で作られた電気を使いますが、燃料に化石燃料を使わないため、ガソリン車よりも発生する二酸化炭素量は少ないです)
火力発電は化石燃料をエネルギー源とし、地中に埋まっている化石燃料は有限なので再生可能エネルギーには含まれず、原子力発電もウランを核分裂させたときの熱をエネルギー源としており、原子力(原子を使ったエネルギー)は自然界に存在するものではないため再生可能エネルギーには含まれません。
(日本では色々な発電方法を組み合わせて電力が確保されていますが、化石燃料を燃やしてエネルギー源とする火力発電によって約7割の電力が作られています)
ただ原子力発電は、大気中に二酸化炭素を排出せずに安定的な電力供給が可能(天候などによって出力が変動しない)な発電方法のため、カーボンニュートラル達成に向けての重要なエネルギー源のひとつとして認識されています。
②植林によって、植物の光合成による大気中の二酸化炭素の吸収量の増加
植林によって木を増やすことで、植物の光合成による大気中の二酸化炭素の吸収量も増加します。
成熟した木よりも、成長期の若い木の方が光合成による大気中の二酸化炭素の吸収量が多く(木に固定される炭素量も多くなる)、二酸化炭素の吸収量と木が呼吸することによる二酸化炭素の排出量の差も大きくなります。
(木は光合成による大気中の二酸化炭素の吸収だけでなく、人間と同じように呼吸をして大気中に二酸化炭素を排出しています)
木は光合成で大気中から二酸化炭素を吸収し、幹(みき)や枝に炭素を蓄えながら成長して酸素を排出するため、炭素の貯蔵庫として機能しています。
なので上図のように成熟した木は(光合成による二酸化炭素の吸収量が減少するため)伐採して資材として利用し、植林して成長期の若い木がどんどん増えていくことで(光合成による二酸化炭素の吸収量が多いため)大気中の二酸化炭素量が減少していきます。
(伐採してその木を燃やすことで大気中に二酸化炭素が排出されますが、伐採しただけでは大気中に二酸化炭素は排出されません)
③DAC(直接空気回収技術)による大気中の二酸化炭素の除去
DAC(Direct Air Capture:直接空気回収技術)によって大気中の二酸化炭素を回収して、それを地中に貯留したり、化学製品や燃料などの資源として有効利用することができます。
(現在、日本ではDACの実用化を目指している段階で、2040年以降の本格普及に向けて研究開発が進められています)
二酸化炭素を回収して貯留する技術をCCS(Carbon dioxide Capture and Storage:二酸化炭素回収・貯留技術)と呼び、現在でもCCSによって工場や発電所から発生する二酸化炭素を大気中に排出される前に回収して地中などに貯留しています。
DACは”大気中に排出された後の低濃度の二酸化炭素を回収する技術(回収した二酸化炭素は資源として利用が可能)”で、CCSは”発電所や工場などの産業施設から大気中に排出される前の高濃度の二酸化炭素を回収して貯留する技術”になります。
(DACとCCSを合わせた”大気中に排出された後の低濃度の二酸化炭素を回収して貯留する技術”をDACCSと呼んでいます)
以上が「カーボンニュートラルとは何かをわかりやすく図で解説!」でした。
3.まとめ
これまで説明したことをまとめますと、
- カーボンニュートラルとは、”二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を吸収・除去して(排出量から)差し引くことで、大気中への温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする、という考え方のこと”。
- カーボンニュートラルは、大気中の温室効果ガスの増加が原因で進行している地球温暖化を防止するために生まれた考え方で、直訳すると「カーボン(carbon:炭素)」「ニュートラル(neutral:中立)」となる。
関連ページ
<覚えておきたい知識>
鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など
哀悼、重複、出生、集荷など
(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど
(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど
(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など
<豆知識>
(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など
<名前は知っているけどわからないもの>
(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど
(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など
(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど
<よく使う言葉>
慣習、準拠、言わずもがな、明文化など
慣習的、致命的、便宜的、作為的など
互換性、慢性、普遍性、必然性など
蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など





