1.分留とは

※上は蒸留装置の写真
結論からいってしまうと分留とは、”3種類以上の物質が混ざった液体から、物質の沸点(液体が気体に変化するときの温度)の違いを利用して、それぞれの物質に分離する方法”です。
分留は略称で、正式名称は「分別蒸留(ぶんべつじょうりゅう)」と言い、分留は”蒸留の一種”になります。
例えば、3種類の物質(物質A:沸点50℃、物質B:沸点100℃、物質C:沸点150℃)が混ざった液体混合物があるとして、それを分留によってそれぞれの物質に分離します。
下図のように液体混合物(物質A+物質B+物質C)を加熱していき、液体混合物の温度が50℃以上になると、まず物質A(沸点50℃)が気体に変化し、液体混合物から分離されて冷やされることで別容器の三角フラスコにたまります。
※上の分留は、単蒸留を繰り返して物質を分離する場合
同じように残った液体混合物(物質B+物質C)を加熱していき、液体混合物の温度が100℃以上になると、次に物質B(沸点100℃)が気体に変化するので分離されて冷やされることで別容器の三角フラスコにたまります。
このような分留によって、3種類の物質が混ざっていた液体混合物は、物質A・物質B・物質Cのそれぞれの物質に分離することができます。
関連:よく使うけどちょっと難しい言葉や表現の一覧!(慣習、準拠、言わずもがな、明文化など)
2.分留の例と原理
では分留の例として、原油(採掘されたままの不純物が多く含まれる石油)を各石油製品(灯油・ガソリン・軽油など)にどのように分留するのかを簡単に解説していきます。
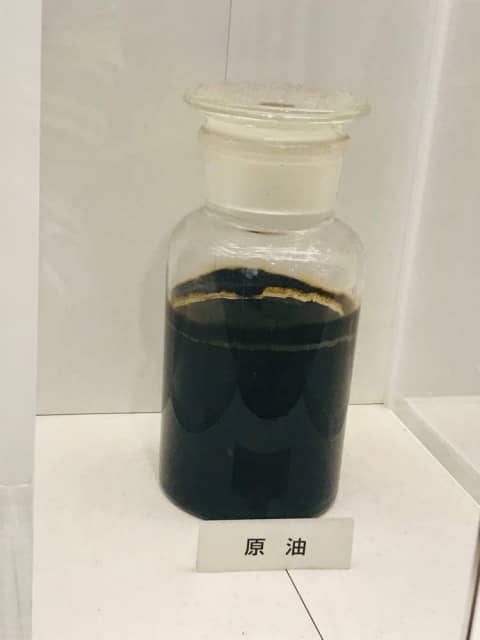
※上は原油(採掘されたままの不純物が多く含まれる石油)の写真
原油の精製(分留)工程として、原油タンクから加熱炉(かねつろ)に原油が送られて加熱(300℃~350℃)され、その後に加熱された原油は蒸留塔に送られます。
そして原油が加熱されて気体に変化した物質は蒸留塔内で上昇していき、気体に変化せずに残った物質は重油・アスファルトに分けられます。
気体に変化して上昇した物質は各層で冷やされていき、沸点の高い物質から順番に気体から液体に戻り、このように分留によって原油は各石油製品へと分けられていきます。
また、原油の他に、空気(気体の混合物)をー190℃に冷却して液体空気(淡青色)にしてから、分留によって窒素・酸素などを得るのにも用いられます。
(大気中の空気を加圧して圧縮(断熱圧縮)させ、その圧縮された空気を冷ました後に、その空気を断熱膨張させるのを繰り返すことで空気の温度を下げていくことができます)
以上が「分留とは?例・原理をわかりやすく図で解説!」でした。
3.まとめ
これまで説明したことをまとめますと、
- 分留とは、”3種類以上の物質が混ざった液体から、物質の沸点(液体が気体に変化するときの温度)の違いを利用して、それぞれの物質に分離する方法”。
- 分留は略称で、正式名称は「分別蒸留」と言い、分留は”蒸留の一種”。
- 分留の例として、原油を各石油製品(灯油・ガソリン・軽油など)に分けたり、液体空気を窒素・酸素などの物質に分けるのに用いられている。
関連ページ
<覚えておきたい知識>
鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など
哀悼、重複、出生、集荷など
(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど
(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど
(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など
<豆知識>
(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など
<名前は知っているけどわからないもの>
(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど
(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など
(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど
<よく使う言葉>
慣習、準拠、言わずもがな、明文化など
慣習的、致命的、便宜的、作為的など
互換性、慢性、普遍性、必然性など
蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など



.svg)