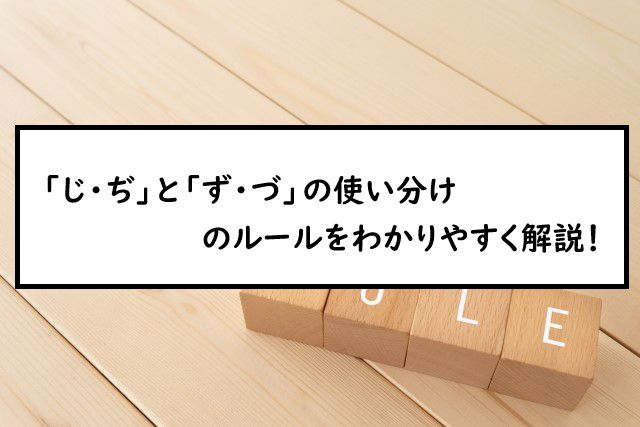
このページでは「じ・ぢ」「ず・づ」の使い分けのルールについてわかりやすく解説しています。
目次
1.「じ・ぢ」「ず・づ」の使い分けのルールについて

まず「じ・ぢ」「ず・づ」の使い分けのルールについて、1986年に内閣告示として出された『現代仮名遣い』という文書を簡単にまとめると、以下の5つになります。
現代仮名遣い(げんだいかなづかい)というのは、”現在、一般的に使われている仮名(平仮名・片仮名)の使い方のこと”です。
① 「ぢ」「づ」は原則として使用しないこと
② 「ちぢむ」「つづく」のように同音が続いた場合に生じるものは、例外とすること
③ 「はなぢ」のように2つの言葉の連合(連濁)によって生じるものは、例外とすること
④ 「せかいじ(ぢ)ゅう」のように、2語に分解すると意味が連想しにくいものは、「じ・ぢ」「ず・づ」のどちらで書いても良い
⑤ 漢字の読み方がもともと濁っているもので、上記「②、③」に当てはまらないものは、そのまま「じ」「ず」を使用すること
ではそれぞれのルールについて詳しく解説していきます。
①「ぢ」「づ」は原則として使用しないこと
原則として「ぢ」「づ」ではなく、「じ」「ず」の方を優先して使用することが定められています。
ただ躓くのように”躓”は本来「つまず(く)」という読み方しかできませんが、
「つまずく」ではなく、「つまづく」についても特に間違いではないとされている例もあります。
これは「つまづく」と間違える人が増えて、それが一般的にも広く定着したために、「つまずく」「つまづく」のどちらも正しいことにしよう!となったものだと考えられます。
この躓くのような例外も存在するため、しっかりと覚えておきましょう。
②同音が続いた場合に生じるものは、例外とすること
”同音が続いた場合に生じるものは、例外とすること”というのは、
①の原則として「ぢ」「づ」を使用しないこと、が当てはまらなくなるということです。
つまり同音が続いた場合に生じるものについては、”そのまま「ぢ」「づ」を使用する”ということです。
例えば、「縮む(ちぢむ)」「続く(つづく)」のように同音が続いている場合には、
①の例外とするため、①に従って「ちじむ」「つずく」とする必要はありません。
なので「縮む(ちじむ)」「続く(つずく)」と書いてしまうと間違いになります。
③2つの言葉の連合(連濁)によって生じるものは、例外とすること
”2つの言葉の連合(連濁)によって生じるものは、例外とすること”というのは、
②と同様に、①の原則として「ぢ」「づ」を使用しないこと、が当てはまらなくなるということです。
ここでの「ぢ」「づ」読みというのは、連濁(れんだく)という現象によって生じるものになります。
連濁というのは、”2つの語が結びついて1つの語になるときに、発音しやすくするために、後ろの語の語頭が清音から濁音に変化する現象のこと”を言います。
鼻血であれば、鼻(はな)+血(ち)なので、血(後ろの語)の語頭である清音の”ち”が濁音の”ぢ”に変化します。
つまり2つの言葉の連合(連濁)によって生じるものについては、”そのまま「ぢ」「づ」を使用する”ということです。
例えば、「鼻血(はなぢ)」「身近(みぢか)」のように2つの言葉の連合(連濁)によって生じるものは、①の例外とするため、①に従って「はなじ」「みじか」とする必要はありません。
なので「鼻血(はなじ)」「身近(みじか)」と書いてしまうと間違いになります。
④2語に分解すると意味が連想しにくいものは、「じ・ぢ」「ず・づ」のどちらでも良い
例えば、世界中は「地球上のあらゆる場所/あらゆる人間社会」の意味があり、
世界 + 中 と2語に分解したときに、その意味が連想しにくいです。
このように2語に分解すると意味が連想しにくいものについては、
それぞれ「じ」「ず」を用いることを本則として、「ぢ・じ」「づ・ず」のどちらで書いても良いとされています。
つまり基本的には「じ」「ず」を使用しますが、「ぢ」「づ」を使用しても間違いではありませんよ、ということです。
なので世界中であれば、基本的には「世界中(せかいじゅう)」と書きますが、
「世界中(せかいぢゅう)」と書いても特に間違いではありません。
他にも稲妻(いなずま)であれば、「空中電気の放電によって生じる電光」の意味があり、稲 + 妻 と2語に分解すると意味を連想しにくいですよね。
ですので稲妻も世界中と同様に、基本的には「いなずま」と書きますが、「いなづま」と書いても特に間違いではありません。
また人妻(ひとづま)であれば「他人の妻」の意味があり、
人 + 妻 と2語に分解しても意味が連想しやすいものなので、そのまま「づ」(「ず」は間違い)のみを用います。
(人妻の「づ」読みは連濁によるもので、人妻を「ひとづま」と読むのは鼻血と同じ③に該当するものです)
この人妻(ひとづま)のように、2語に分解しても意味が連想しやすいものは「じ」「ず」に変化することなく、そのままの読み方が用いられます。
⑤漢字の読み方がもともと濁っているものは、そのまま「じ」「ず」を使用すること
正確には、”漢字の読み方がもともと濁っているもので、「②、③」に当てはまらないものは、そのまま「じ」「ず」を使用すること”です。
②「ちぢむ」「つづく」のように同音が続いた場合に生じるものは、例外とすること
③「はなぢ」のように2つの言葉の連合によって生じるものは、例外とすること
”地”は「じ」、”図”は「ず」のように、これらの漢字はもともと濁った読み方を持っていて、
上記「②、③」に当てはまらないものであれば、そのまま「じ」「ず」を使用するということになります。
例えば、⑤には「地面(じめん)」「布地(ぬのじ)」「略図(りゃくず)」などの言葉が挙げられます。
つまり⑤というのは簡単で、「地(じ)」「図(ず)」のように、もともとその漢字が持っている「じ」「ず」の読み方を使用しましょう、というだけの話です。
なので「地面(ぢめん)」「布地(ぬのぢ)」「略図(りゃくづ)」と書き表すのは間違いになります。
関連:よく使うけどちょっと難しい言葉や表現の一覧!(慣習、準拠、言わずもがな、明文化など)
以上が”「じ・ぢ」と「ず・づ」の使い分けのルールをわかりやすく解説!”でした。
2.まとめ
これまで説明したことをまとめますと、
<「じ・ぢ」「ず・づ」の使い分けのルールについて>
- ① 「ぢ」「づ」は原則として使用しないこと
- ② 「ちぢむ」「つづく」のように同音が続いた場合に生じるものは、例外とすること
- ③ 「はなぢ」のように2つの言葉の連合(連濁)によって生じるものは、例外とすること
- ④ 「せかいじ(ぢ)ゅう」のように、2語に分解すると意味が連想しにくいものは、「じ・ぢ」「ず・づ」のどちらで書いても良い
- ⑤ 漢字の読み方がもともと濁っているもので、上記「②、③」に当てはまらないものは、そのまま「じ」「ず」を使用すること
関連ページ
<覚えておきたい知識>
鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など
哀悼、重複、出生、集荷など
(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど
(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど
(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など
<豆知識>
(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など
<名前は知っているけどわからないもの>
(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど
(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など
(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど
<よく使う言葉>
慣習、準拠、言わずもがな、明文化など
慣習的、致命的、便宜的、作為的など
互換性、慢性、普遍性、必然性など
蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など
