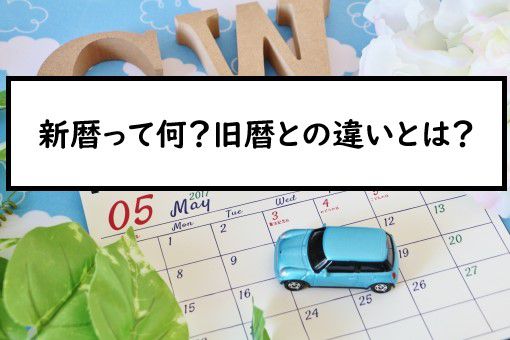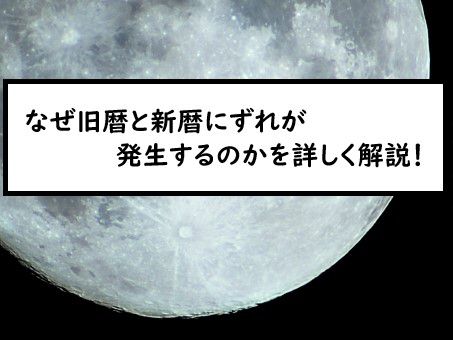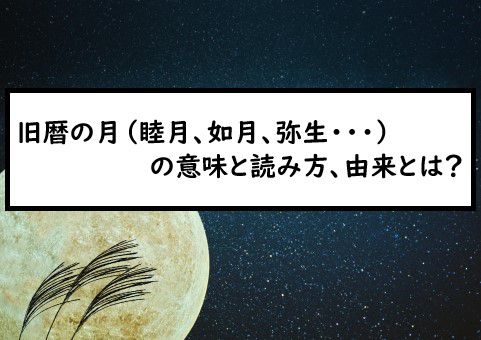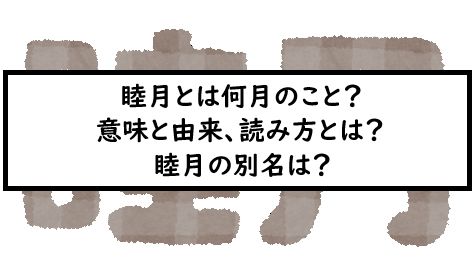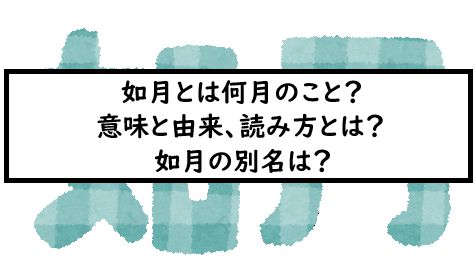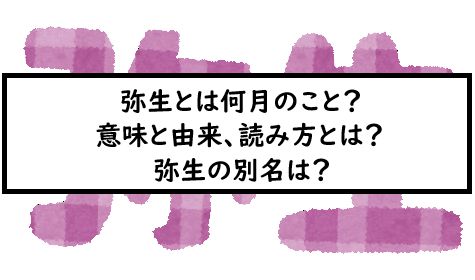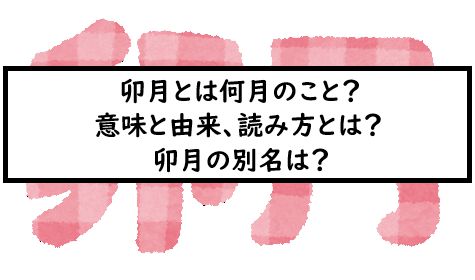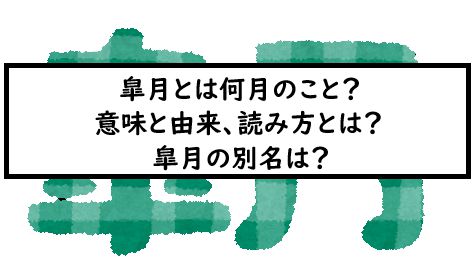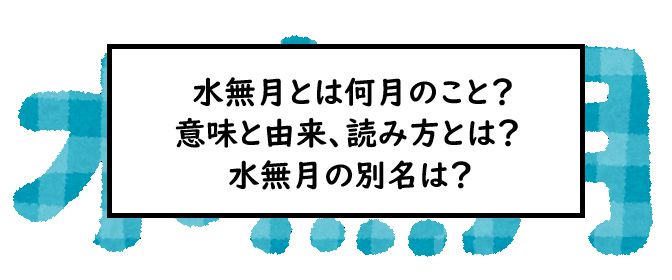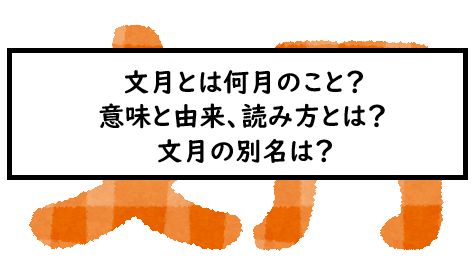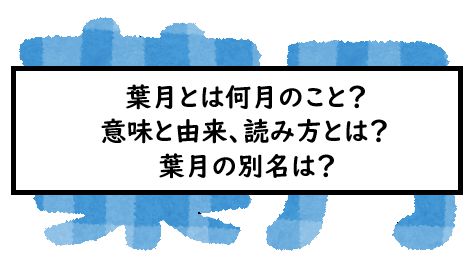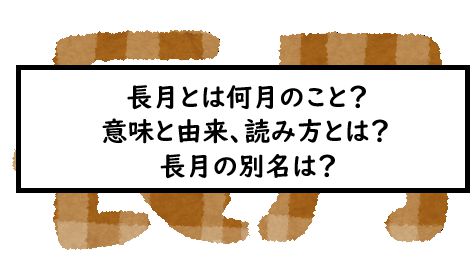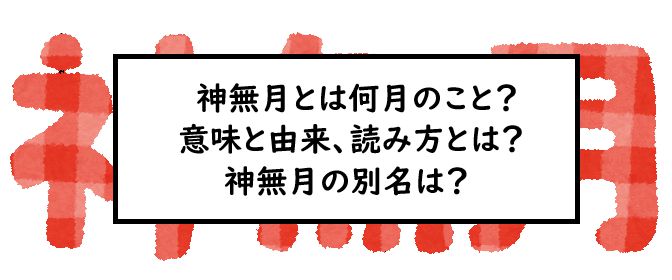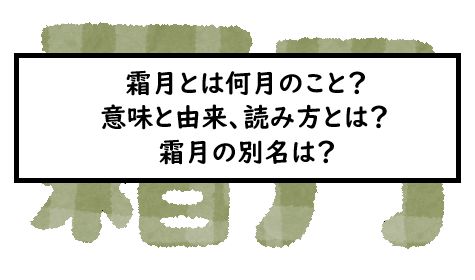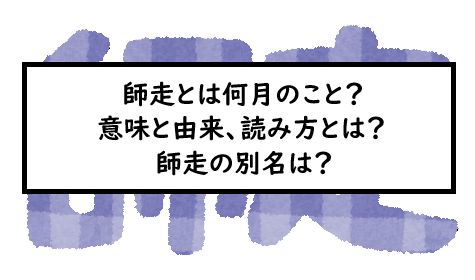さてあなたは新暦と旧暦という言葉についてご存知でしょうか。新暦と旧暦はいま現在私たちがカレンダーなどで使用している暦に、大きく関係しているもので新暦について使用したことがない人はほとんどいないはずです。日常的によく使用される言葉というわけではないですが、ときどき会話の中に出てくることがあるのでぜひ知っておきたい言葉です。そこでこのページでは、新暦と旧暦の違いについて簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次新暦と旧暦の違いについて新暦とは?旧暦とは?まとめ1.新暦と旧暦の違いについてでは新暦と旧暦の違いについて見ていきましょう。結論から言ってしまうと新暦と旧暦の違いは、改暦後の暦のことなのか、改暦前の暦のことなのかです。新暦とは改暦した後の”新しい暦”のことを指していて、旧暦とは改暦する前の”古い暦”のことを指しています。暦(こよみ)というのは、時間の流れを年・月・週・日などの単位で表したものを言います。(私たちが日常的にカレンダーなどで時間を表すために使用しているものが暦です)そして暦は時間の流れを季節に合わせて設けているので、もし使用している暦が季節と大きなずれを生じてしまう場合は改暦する必要性があります。この時間の流れと季節のずれを小さくするために、改暦した後の新しい暦のことを”新暦”と言い、改暦する前の古い暦のことを”旧暦”と言っています。さて新暦と旧暦について詳しく解説していきますね。関連:なぜ旧暦と新暦にずれが発生するのかを詳しく解説!新暦とは?新暦(しんれき)とは、改暦した後の新しい暦のことです。新暦というのは簡単に言えば、”いま現在使用されている暦”のことだと思ってください。(改暦する前に使用されていた暦については旧暦のところで解説します)いま現在私たちが使用している暦(新暦)は”太陽暦”と言われる暦で、地球が太陽の周りを1周する時間を基準にした暦になります。1年間が365日と決まっているのも太陽暦という暦を使用しているからで、地球が太陽を1周する時間が約365日なのでこのように決められています。(正確にはちょうど365日ではありません)そして太陽暦の中にもいくつか種類があって、その太陽暦の中の”グレゴリオ暦”という名称の暦を使用しています。グレゴリオ暦(太陽暦の中のひとつ)は、日本を含めて世界中で使用されている暦になります。ちなみにだいたい4年に1度、1年間が366日になる”うるう年”がありますが、いま現在のカレンダーなどでうるう年が存在するのはグレゴリオ暦という暦法を元に作られているからです。グレゴリオ暦以外の暦法でもうるう年は存在していますが、いま現在のカレンダーなどに反映されているのはグレゴリオ暦を元にしたものです。うるう年が存在するのは地球が太陽を1周する時間が”ちょうど365日ではない”ので、それにより時間の流れと季節に少しずつずれが発生してしまうからです。ここではうるう年の仕組みはあまり解説しませんが、詳しく知りたい人は下記をご覧ください。関連:うるう年(閏年)とは?4年に1度だけ366日になる仕組みを解説!旧暦とは?旧暦(きゅうれき)とは、改暦する前の古い暦のことです。いま現在日本を含めた世界中で使用されている暦は太陽暦のひとつであるグレゴリオ暦ですが、グレゴリオ暦に改暦する前はユリウス暦や天保暦(てんぽうれき)という暦が使用されていました。グレゴリオ暦に改暦する前のローマではユリウス暦(太陽暦の中のひとつ)が使用され、改暦する前の日本では天保暦(太陰太陽暦の中のひとつ)という暦が使用されていました。ですのでローマにおいては新暦がグレゴリオ暦で旧暦がユリウス暦となり、日本においては新暦がグレゴリウス暦で旧暦が天保暦ということになります。いまでは太陽暦であるグレゴリオ暦が世界中で使用されていますが、昔は使用されている暦が違うことも多かったので旧暦はどこも同じではありません。ちなみに何度も言っていますが改暦する理由は、時間の流れと季節のずれを小さくするためです。ローマ教皇によってそのとき使用されていたユリウス暦からグレゴリオ暦に改暦することが命じられ、ローマでは1582年にグレゴリオ暦が正式な暦として使用され始めました。ユリウス暦だと季節と暦に1日分のずれが起こるのが約128年に1回でしたが、改暦後のグレゴリオ暦だと1日分のずれが起こるのが約3323年に1回となりました。(つまり毎年発生する季節と暦のずれがかなり小さくなったということ)また日本にグレゴリオ暦への改暦が行われたのは1873年からで、そのときに日本の暦が天保暦(太陰太陽暦)からグレゴリオ暦(太陽暦)に変更されました。そしてそのままいま現在に至るまで、日本ではグレゴリオ暦が使用されているんですね。関連:ユリウス暦とは?グレゴリオ暦との違いって何?関連:太陽暦とは?太陰暦と太陰太陽暦との違いって何?以上が「新暦って何?旧暦との違いとは?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、新暦とは、改暦した後の”新しい暦”のこと。旧暦とは、改暦する前の”古い暦”のこと。日本における新暦はグレゴリオ暦で、旧暦は天保暦となる(ローマでは旧暦はユリウス暦)。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒西暦とは何か?西暦はいつから使われた?西暦・和暦・干支の早見表!⇒四半世紀の意味とは?また半世紀・三四半世紀が示す期間は?⇒和暦とは?西暦との違いは何か?⇒紀元前とは?またBCとADの意味や表を分かりやすくまとめました!⇒1世紀は何年のこと?21世紀はいつから?22世紀までの早見表あり⇒今年と今年度の違いとは?年度の期間は目的によって異なるって本当?⇒2月が28日しかない理由とは?なぜうるう年は2月に調整される?⇒上旬と下旬と中旬の期間の違いとは?⇒うるう年(閏年)とは?4年に1度だけ366日になる仕組みを解説!⇒睦月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?睦月の別名は?
ギモン雑学
「 旧暦 」の検索結果
-
-
さてあなたは旧暦と新暦において、季節にずれが発生するというのはご存知でしょうか。例えば1月になると新春と言ったりするのも旧暦と新暦の季節のずれによるもので、いまでは1月のことを春だというのはとても考えられないですよね。日本ではこのように旧暦と新暦による季節のずれが影響しているものが多くありますが、なぜ旧暦と新暦に季節のずれが発生するのか理由を知る人は意外と少ないです。そこでこのページでは、なぜ旧暦と新暦にずれが発生するのかを解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次旧暦と新暦にずれが発生する理由とは?旧暦から新暦への改暦の際に日付にずれが生じたからもともと旧暦では1年間で11日分のずれが生じていたからまとめ1.旧暦と新暦にずれが発生する理由とは?では旧暦と新暦にずれが発生する理由とは何かを見ていきましょう。結論から言ってしまうと、旧暦と新暦にずれが発生する理由は以下の2つによるものです。旧暦から新暦への改暦の際に日付にずれが生じたからもともと旧暦では1年間で11日分のずれが生じていたから旧暦と新暦にずれが発生する上記の2つの理由については、もう少しあとで詳しく解説していきます。まず旧暦と新暦(現在の暦のこと)でどのくらいのずれが発生しているのか、下の表で簡単にまとめているのでご覧ください。旧暦の月と現在の月における季節のずれ旧暦の季節旧暦の月現在の月で換算現在の季節現在の月春睦月(むつき)1月下旬~3月上旬冬1月春如月(きさらぎ)2月下旬~4月上旬冬2月春弥生(やよい)3月下旬~5月上旬春3月夏卯月(うづき)4月下旬~6月上旬春4月夏皐月(さつき)5月下旬~7月上旬春5月夏水無月(みなづき)6月下旬~8月上旬夏6月秋文月(ふみづき)7月下旬~9月上旬夏7月秋葉月(はづき)8月下旬~10月上旬夏8月秋長月(ながつき)9月下旬~11月上旬秋9月冬神無月(かんなづき)10月下旬~12月上旬秋10月冬霜月(しもつき)11月下旬~1月上旬秋11月冬師走(しわす)12月下旬~2月上旬冬12月項目1項目2)★ -->※現在の季節に関しては、気象庁によって区分されたものを表に記載しています。上の表を見ても分かるように、旧暦の月と新暦(現在の暦)の月では季節がずれていますよね。この旧暦と新暦の違いによる季節のずれの大きさとしては、”だいたい1ヶ月~2ヶ月ほど”のずれが旧暦と新暦に発生しています。さてなぜ旧暦と新暦にこのような季節のずれが発生するのか、それぞれ詳しく解説していきますね。関連:新暦って何?旧暦との違いとは?旧暦から新暦への改暦の際に日付にずれが生じたからまず旧暦と新暦に大きなずれが生じた理由としては、旧暦から新暦への改暦の際に日付にずれが生じたからです。順を追って解説していきます。旧暦では天保暦(太陰太陽暦のひとつ)が使用されていましたが、旧暦は”明治5年12月2日を最後”にグレゴリオ暦(太陽暦のひとつ)へと改暦することになります。(グレゴリオ暦というのが新暦のことであり、いま現在も私たちが日常的に使用している暦です)旧暦は明治5年12月2日が最後の日なので、新暦の始まりは明治5年12月3日からとされるはずが違う日付に改められました。そして実際に新暦が始まった(改められた)日付というのが、明治6年1月1日からになります。なので本当は新暦は明治5年12月3日から始めなければいけないのに、明治6年1月1日から始めてしまったことで旧暦と新暦でずれが生じたわけなんですね。これによって明治5年12月3日~明治5年12月31日までの日数がなくなり、旧暦と新暦では常に29日分のずれが生じてしまいます。ちなみに旧暦と新暦にずれが生じるのにこのような改暦を行った理由としては、政府が官吏(かんり)へと支払う給料を少なくするためと言われています。(官吏とはいまでいうところの国家公務員のことを指しています)旧暦では3年に1度うるう月が設けられて1年間が13ヶ月になっていましたが、国からすれば新暦に変わることでうるう月を設ける必要がなくなるので、1ヶ月分の給料を抑えることができます。(うるう月については次の章で解説します)さらに日付を昭和6年1月1日に改めたことによって、2日しか働いていない明治5年12月分の給料を支払わないことにしたそうです。働いている側からすればたまったもんではありませんが、それだけ当時の政府の財政状況が危険な状態であったと言えます。(2日分働いているのにその分を支払わないというのは、どうかと思いますが)次の章で旧暦と新暦にずれが生じるもう1つの理由について解説していきますね。関連:太陽暦とは?太陰暦と太陰太陽暦との違いって何?関連:ユリウス暦とは?グレゴリオ暦との違いって何?もともと旧暦では1年間で11日分のずれが生じていたから旧暦と新暦にずれが生じる2つ目の理由としては、もともと旧暦では1年間に11日分のずれが発生していたからです。うるう年というのはこの季節と暦のずれを調整するためにあるのですが、先ほど話の中に出てきた”うるう月”と大きく関係しています。新暦(現在の暦)ではうるう年がだいたい4年に1度ありますが、いまだとうるう年になると1日だけ日数を足して1年間を366日にしますよね。旧暦では普段の1年間の日数が354日といまよりも11日分も少なく、旧暦のうるう年には3年に1度1ヶ月分を足して1年間を13ヶ月としていました。そして”うるう(閏)”というのが普段の年よりも日数や月数が多いことを表していて、”うるう日”だと普段より日数が多く、”うるう月”だと普段より月数が多いことになります。上のように旧暦よりも新暦の方が季節と暦にずれが生じにくいことを意味しています。さて本題に戻りますが、もともと旧暦では1年間に11日分のずれが発生していたので、旧暦から新暦に改暦すると当然のことながら同じようにずれが生じることになります。同じように暦が進んでも新暦ではほとんどずれが発生しないのに対して、旧暦では1年間で11日分のずれが発生するので旧暦と新暦では毎年少しずつずれが生じていきます。旧暦では1年間に11日分ずれて3年間で33日(約1ヶ月)分のずれになりますが、このずれを調整するために3年間に1度うるう月を設けてリセットされます。これにより3年間で最大33日分のずれが生じてしまうわけです。そして前の章で解説していた改暦の際に日付を改めたことによるずれ29日分と、旧暦の1年ごとのずれ(0日~33日分)を合わせると”だいたい1ヶ月~2ヶ月分”になるというわけです。関連:うるう年(閏年)とは?4年に1度だけ366日になる仕組みを解説!以上が「なぜ旧暦と新暦にずれが発生するのかを詳しく解説!」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、旧暦から新暦への改暦の際に日付を改めたことで、29日分のずれが発生する。旧暦における1年間のずれが11日分あり、3年間で最大33日になる(約3年でこのずれはリセットされる)。上記の2つの理由から旧暦と新暦(現在の暦)では、だいたい1ヶ月~2ヶ月ほど季節がずれる。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒旧暦の月(睦月、如月、弥生・・・)の意味と読み方、由来とは?⇒師走とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?師走の別名は?⇒四半世紀の意味とは?また半世紀・三四半世紀が示す期間は?⇒和暦とは?西暦との違いは何か?⇒紀元前とは?またBCとADの意味や表を分かりやすくまとめました!⇒1世紀は何年のこと?21世紀はいつから?22世紀までの早見表あり⇒今年と今年度の違いとは?年度の期間は目的によって異なるって本当?⇒2月が28日しかない理由とは?なぜうるう年は2月に調整される?⇒上旬と下旬と中旬の期間の違いとは?⇒西暦とは何か?西暦はいつから使われた?西暦・和暦・干支の早見表!
-
いま現在の暦では1年間を12ヶ月に分けて、1年間は1月から始まり12月で終わるというのが常識です。ですが以前まで私たちが使用していた暦は旧暦と言われるもので、暦が旧暦のときは1年間の始まりは睦月から始まっていました。いま現在ではこのような月の呼び方をすることはほとんどないですが、旧暦の月名やその由来などを覚えておくとたまに役に立つときがあります。そこでこのページでは、旧暦の月(睦月、如月、弥生・・・)の意味と読み方、由来を簡単に解説しています。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次旧暦の月の意味・読み方・由来について旧暦の月と現在の月では季節にずれがある旧暦における各月の由来について詳しく解説睦月の由来とは?如月の由来とは?弥生の由来とは?卯月の由来とは?皐月の由来とは?水無月の由来とは文月の由来とは?葉月の由来とは?神無月の由来とは?長月の由来とは?霜月の由来とは?師走の由来とは?まとめ1.旧暦の月の意味・読み方・由来についてでは旧暦の月の意味・読み方・由来について見ていきましょう。旧暦の各月における意味・読み方・由来は、簡単にまとめると下の表のようになります。旧暦の各月における季節と意味・読み方・由来のまとめ季節現在の月旧暦の月(読み方)旧暦の月の由来春1月睦月(むつき)親戚や知人が集まって、仲睦(むつ)まじくする月という意味から春2月如月(きさらぎ)寒くなり、衣を更に重ねて着る”衣更着(きさらぎ)”から春3月弥生(やよい)”弥(いよいよ)”草木が”生い”茂るという意味から夏4月卯月(うづき)卯の花(ウツギの花)が咲く月という意味の”卯の花月”から夏5月皐月(さつき)田に早苗(若い稲の苗)を植える月という意味の”早苗月”から夏6月水無月(みなづき)”無”は”の”を意味し、田んぼに再び水を引く月という意味の”水の月”から秋7月文月(ふみづき)七夕のとき短冊に歌や字(文)を書いていたことから秋8月葉月(はづき)葉が落ち始める時期という意味の”葉落ち月”から秋9月長月(ながつき)夜がだんだんと長くなり始める月という意味の”夜長月”から冬10月神無月(かんなづき)全国の神々が出雲大社(島根県)に集まる”神の月”から冬11月霜月(しもつき)霜が降り始める月という意味の”霜降り月”から冬12月師走(しわす)僧(お坊さん)がお経を唱えるため、各地を忙しく走り回ることから項目1項目2)★ -->いま現在の暦(新暦のこと)では1年間は1月から始まり12月で終わりですが、上の表のように旧暦のときは1年間は”睦月”から始まり”師走”で終わっていました。いま現在の暦である新暦に変更になったのは1873年(明治6年)のことなので、その頃から1年間が”睦月~師走”ではなく”1月~12月”という表し方に変わりました。また旧暦における各月の由来について上の表だけでは、いまいち分かりにくいですよね。このページの最後の章で旧暦における各月の由来について詳しく解説していますので、イメージしにくい人はそちらの方をご覧ください。さて次の章で旧暦と現在の暦では季節にずれがあることについて、解説していきます。関連:新暦って何?旧暦との違いとは?関連:太陽暦とは?太陰暦と太陰太陽暦との違いって何?2.旧暦の月と現在の月では季節にずれがあるでは旧暦の月と現在の月では季節は異なるのは本当なのかを見ていきましょう。結論から言ってしまうと旧暦の月といま現在の月では、だいたい1ヶ月から2ヵ月分ぐらいの季節のずれがあります。なぜこんなにも旧暦の月と現在の月でずれが生じてしまうのかというと、それは旧暦から現在の暦(新暦)に切り替えたときの影響によるものが大きいです。旧暦では天保暦(太陰太陽暦のひとつ)が使用されていましたが、明治5年(1872年)12月2日を最後の日としてグレゴリオ暦(太陽暦のひとつ)に切り替えられました。(グレゴリオ暦こそが私たちがいま現在でも使用している暦になります)ですが旧暦から新暦(現在の暦)に切り替えられる際に、本当は明治5年の12月3日からとするところを明治6年の1月1日からと日付を改めました。これによって事実上、明治5年12月3日から先の12月の日数分の期間がなくなり、だいたい1ヶ月ほど旧暦と現在の暦(新暦)にずれが生じることになります。さらにいま現在の暦ではだいたい4年に1度うるう年を設けて1年間に1日だけ足すことで、季節と暦に生じるずれを調整していますが、旧暦では1年間に11日ものずれが発生していました。なので旧暦だと3年間で33日(約1ヶ月)分のずれが生じてしまうため、3年間に1度うるう年を設けて、うるう月という丸1ヶ月分を1年間に足して13ヶ月にしてずれを調整していました。このように旧暦から新暦に切り替わる際に発生した約1ヶ月分のずれと、旧暦における1年間ごとに発生するずれによって、旧暦と新暦では最大でだいたい2ヵ月分のずれが生じてしまうんですね。以上のことを踏まえて、旧暦の月と現在の月の季節のずれを簡単にまとめると下のようになります。旧暦の月と現在の月における季節のずれ旧暦の季節旧暦の月現在の月で換算現在の季節現在の月春睦月(むつき)1月下旬~3月上旬冬1月春如月(きさらぎ)2月下旬~4月上旬冬2月春弥生(やよい)3月下旬~5月上旬春3月夏卯月(うづき)4月下旬~6月上旬春4月夏皐月(さつき)5月下旬~7月上旬春5月夏水無月(みなづき)6月下旬~8月上旬夏6月秋文月(ふみづき)7月下旬~9月上旬夏7月秋葉月(はづき)8月下旬~10月上旬夏8月秋長月(ながつき)9月下旬~11月上旬秋9月冬神無月(かんなづき)10月下旬~12月上旬秋10月冬霜月(しもつき)11月下旬~1月上旬秋11月冬師走(しわす)12月下旬~2月上旬冬12月項目1項目2)★ -->※現在の季節に関しては、気象庁によって区分されたものを表に記載しています。上の表のように旧暦の月と現在の月では、だいたい1ヶ月~2ヶ月分季節がずれています。なので旧暦の月における由来についてはいま現在の月での季節のことではなく、いま現在の季節からだいたい1ヶ月~2ヶ月分ずれているものだと認識してください。さて次の章では旧暦における各月の由来について詳しく解説していきます。関連:うるう年(閏年)とは?4年に1度だけ366日になる仕組みを解説!関連:ユリウス暦とは?グレゴリオ暦との違いって何?3.旧暦における各月の由来について詳しく解説では旧暦における各月の由来について詳しく解説していきますね。はじめの方でも貼っていましたが、再び旧暦の月の由来についてまとめた表を貼っておきます。旧暦の各月における季節と意味・読み方・由来のまとめ季節現在の月旧暦の月(読み方)旧暦の月の由来春1月睦月(むつき)親戚や知人が集まって、仲睦(むつ)まじくする月という意味から春2月如月(きさらぎ)寒くなり、衣を更に重ねて着る”衣更着(きさらぎ)”から春3月弥生(やよい)”弥(いよいよ)”草木が”生い”茂るという意味から夏4月卯月(うづき)卯の花(ウツギの花)が咲く月という意味の”卯の花月”から夏5月皐月(さつき)田に早苗(若い稲の苗)を植える月という意味の”早苗月”から夏6月水無月(みなづき)”無”は”の”を意味し、田んぼに再び水を引く月という意味の”水の月”から秋7月文月(ふみづき)七夕のとき短冊に歌や字(文)を書いていたことから秋8月葉月(はづき)葉が落ち始める時期という意味の”葉落ち月”から秋9月長月(ながつき)夜がだんだんと長くなり始める月という意味の”夜長月”から冬10月神無月(かんなづき)全国の神々が出雲大社(島根県)に集まる”神の月”から冬11月霜月(しもつき)霜が降り始める月という意味の”霜降り月”から冬12月師走(しわす)僧(お坊さん)がお経を唱えるため、各地を忙しく走り回ることから項目1項目2)★ -->旧暦における各月の由来には諸説あって、ここで解説するのはその中でも由来として有力とされている説です。(上の表でまとめられている説のことです)では旧暦における各月の由来について詳しく解説していきます。睦月とは?睦月(むつき)の由来は、親戚や知人が集まって仲睦(むつ)まじくする月という意味からです。睦月とは旧暦における1月のことを指していますが、実際に現在の暦でいうところの1月下旬~3月上旬にあたります。お正月に家族や親せきが集まり、仲睦まじく(仲良く・親密に)過ごすことから”睦び月(むつびつき)”と呼ばれ、その”睦び月”が略されて旧暦における”睦月(むつき)”になったという説が有力です。旧暦でなく新暦のいまでもお正月になると家族や親せきで集まって、美味しいご飯を食べたりして盛り上がりますよね。関連:睦月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?睦月の別名は?如月とは?如月(きさらぎ)の由来は、寒くなり衣を更に重ねて着る”衣更着(きさらぎ)”からです。如月とは旧暦における2月のことを指していますが、実際に現在の暦でいうところの2月下旬~4月上旬にあたります。もともと如月は中国で使用されていた2月の名称のことで、中国では”如月(きさらぎ)”ではなく”如月(にょげつ)”と呼ばれていました。そして”如”という字には”従う”という意味があってこれは、何かが動き出すと他のものも動き出すという意味で使用されています。冬という季節は植物や動物などの動きが活発でない(冬眠する)時期であり、その冬の後の季節である如月はそれらが徐々に動き始める時期でもあります。このような理由から如月という言葉が、旧暦の2月(現在では2月下旬~4月上旬)になっているんですね。如月を”にょげつ”ではなく”きさらぎ”と読むようになったのは、以下の説が有力とされています。新暦(現在の暦)では如月は2月下旬から4月上旬のことになるので、この時期から少しずつ暖かくなり始めますが、そのあと一旦また寒さがぶり返す時期でもあります。このように少しずつ暖かくなる時期ではありますが、再び寒さがぶり返す時期なために、一旦脱いだ衣(服)を更に着るという意味から”衣更着(きさらぎ)”と呼ばれるようになりました。この”衣更着(きさらぎ)”が如月の読み方となり、旧暦における月名の”如月(きさらぎ)”になっています。関連:如月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?如月の別名は?弥生とは?弥生(やよい)の由来は、”弥(いよいよ)”草木が”生い”茂るという意味からです。弥生とは旧暦における3月のことを指していますが、実際に現在の暦でいうところの3月下旬~5月上旬にあたります。如月の頃には草木(植物)はまだ動き始めた段階で活発ではありませんでしたが、弥生になると草木の活動が活発になるので生い茂っていきます。弥生(やよい)はもともと”弥生(いやおい)”が変化したとされるもので、”弥(いや)”は「いよいよ」「ますます」で、”生(おい)”は「生い茂る」の意味となります。このように弥生とは寒い時期(冬)が終わりを迎え、草木が生い茂る時期のことを意味しているんですね。関連:弥生とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?弥生の別名は?卯月とは?※卯の花(ウツギの花)の写真卯月(うづき)の由来は、卯の花(ウツギの花)が咲く月という意味の”卯の花月”からです。卯月とは旧暦における4月のことを指していますが、実際に現在の暦でいうところの4月下旬~6月上旬にあたります。卯の花(ウツギの花)が開花するのは5月中旬~6月頃で、旧暦ではこの卯の花が咲く時期のことを”卯月”と呼んでいたという説が有力です。卯の花はウツギの花とも呼ばれ、卯の花の茎の中が空洞になっていることから、”空木(ウツギ)の花”と呼ばれるようになりました。関連:卯月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?卯月の別名は?皐月とは?※写真中で植えられているのが早苗(若い稲の苗)皐月(さつき)の由来は、田に早苗(若い稲の苗)を植える月という意味の”早苗月”からです。皐月とは旧暦における5月のことを指していますが、実際に現在の暦でいうところの5月下旬~7月上旬にあたります。稲の苗というのは田植えができるようになるまである程度育てる必要があって、田植えを行うことができるまで育った苗のことを”早苗(さなえ)”と言います。そしてこの時期は田んぼに若い稲の苗である早苗を植える月ということから、早苗を植える月なので”早苗月(さなえづき)”となりました。その”早苗月”が略されて旧暦の”皐月(さつき)”になるのですが、もともとさつきの”さ”という字自体に苗植えや耕作の意味があります。さらに皐月の”皐”という漢字があてられているのも、”皐”という字には”神に捧げる稲”という意味があることから皐月となったようです。関連:皐月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?皐月の別名は?水無月とは?水無月(みなづき)の由来は、”無”は”の”を意味し、田んぼに再び水を引く月という意味の”水の月”からです。水無月とは旧暦における6月のことを指していますが、実際に現在の暦でいうところの6月下旬~8月上旬にあたります。水無月には”無”という漢字があるので”水が無い月”と覚えている人も多いのですが、実は水無月の”無”は”ない(存在しない)”ということを表しているのではありません。これは古い日本語の使い方で、”な”は現在の意味における”の”を意味していることから、水無月は”水の月”を意味していることになるんですね。ではなぜ旧暦における6月(現在の6月下旬~8月上旬)が”水の月”になるのかと言うと、それは水が抜かれた田んぼに再び水を引くための作業が行われるからです。※中干し作業後の田んぼの写真旧暦の前の月である皐月には田んぼに早苗を植えていますが、そのあと水無月になると一旦”中干し”と呼ばれる田んぼの水を抜く作業があります。(田んぼの中干しが行われるのは、現在の暦でいうところの7月下旬あたりです)そして中干し作業が終わると再び田んぼに水が引かれるので、旧暦の6月は”水の月”である水無月になったということです。関連:水無月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?水無月の別名は?文月とは?文月(ふみづき)の由来は、七夕のとき短冊に歌や字(文)を書いていたことからです。文月とは旧暦における7月のことを指していますが、実際に現在の暦でいうところの7月下旬~9月上旬にあたります。いまでは七夕になると短冊に願い事を書くというのが一般的ですが、昔は願い事ではなく歌や字(文)を書いて、書道の上達を祈っていたそうです。そのような七夕の風習に因(ちな)んで、旧暦の7月は”文披月(ふみひらきづき)”と呼ばれるようになりました。”披(ひら)くは閉じてあるものを開ける”という意味があることから、”文(ふみ)を広げて晒(さら)す月”という意味で文披月です。その文披月がのちに旧暦の月である”文月(ふみづき)”になったとされています。関連:文月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?文月の別名は?葉月とは?葉月(はづき)の由来は、葉が落ち始める時期という意味の”葉落ち月”からです。葉月とは旧暦における8月のことを指していますが、実際に現在の暦でいうところの8月下旬~10月上旬にあたります。葉月は旧暦では8月ですが、新暦(現在の暦)だと8月下旬~10月上旬と秋のことを指します。そして秋になると青々としていた葉の色が黄色や赤色に変化しはじめ、木から葉が落ちてしまう”落葉(らくよう)”が始まる時期です。このように葉が落ち始める月という意味の”葉落ち月”から由来しており、最終的にはその葉落ち月が略されて”葉月”になったとされています。関連:葉月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?葉月の別名は?長月とは?長月(ながつき)の由来は、夜がだんだんと長くなり始める月という意味の”夜長月”からです。長月とは旧暦における9月のことを指していますが、実際に現在の暦でいうところの9月下旬~11月上旬にあたります。この時期ぐらいになると日が昇っている時間が少しずつ短くなっていき、日が落ちる夜の時間が長くなるため、”夜長月(よながつき)”と呼ばれました。よく聞く言葉に夏至と冬至がありますが、夏至(6月21日前後)は”最も夜が短くなる日”で、冬至(12月21日前後)は”最も夜が長くなる日”だとされています。なので夏至を過ぎて冬至に近づくにつれて少しずつ夜が長くなることを、昔の人もいまと同じように感じていたということです。そしてこの夜長月が略されて、旧暦の月である”長月”となったんですね。関連:長月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?長月の別名は?神無月とは?神無月(かんなづき)の由来は、全国の神々が出雲大社に集まる”神の月”からです。神無月とは旧暦における10月のことを指していますが、実際に現在の暦でいうところの10月下旬~12月上旬にあたります。旧暦の10月になると全国の八百万(やおよろず)の神様たちが、島根県にある出雲大社へと会議のために集まるものだと考えられていました。旧暦の6月である水無月と考え方は同じで”無”は”ない”ではなく”の”を意味するので、神無月に関しても”神のいない月”ではなく”神の月”という意味で捉えます。これにより旧暦の10月は全国から神様が集まる月ということから、”神無月(=神の月)”と呼ばれるようになったんですね。また他にも神無月の”無”をそのまま”ない(=存在しない)”という意味で捉えて、神様がいなくなった地域では旧暦の10月を”神無月(かみなしづき)”と呼んでいたり。反対に全国から神様が集まる地域(出雲)では、”神在月(かみありつき)”と呼ばれていたという説もあります。関連:神無月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?神無月の別名は?霜月とは?※植物に霜(氷の結晶)が付いている写真霜月(しもつき)の由来は、霜が降り始める月という意味の”霜降り月”からです。霜月とは旧暦における11月のことを指していますが、実際に現在の暦でいうところの11月下旬~1月上旬にあたります。段々と寒くなり霜が降り始める月という意味の”霜降り月・霜降月(しもふりつき)”が、旧暦の11月である霜月の由来とされる説で有力とされています。そしてその霜降り月が略されて、旧暦の11月である”霜月”になったんですね。霜は秋の終わりごろから冬にかけて降り始めるものなので、植物などに霜が降り始めたら「そろそろ冬になるんだなあ」と思って良いでしょう。ちなみに現在の日本における初霜(はつしも)は場所によっても時期は異なりますが、北海道では10月中に降り始めて、東京などでは12月下旬頃になることも多いです。このように場所によって霜が降り始める時期というのは大きく異なります。関連:霜月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?霜月の別名は?師走とは?師走(しわす)の由来は、僧(お坊さん)がお経を唱えるため、各地を忙しく走り回ることからです。師走とは旧暦における12月のことを指していますが、実際に現在の暦でいうところの12月下旬~2月上旬にあたります。師走の”師”というのは師匠のことを意味しているのではなく、僧(お坊さん)のことを意味しており、僧などを敬っていう場合の言い方になります。(他にも師は教師のことを表して、学校の先生も忙しく走り回る月という説もあります)昔から年末にはお坊さん(僧)に自分の家まで来てもらい、お経を唱えてもらうというような風習がありました。いまではこのような風習はあまり残っていませんが、それだけ昔は年末になるとお坊さんにとってとても忙しい時期だったのですね。ちなみに”師走(しわす)”という読み方は当て字で、普通に読むと師走をしわすとは読むことはできません。いまでこそ師走と言えばしわすと読むのが常識となっていますが、師走(しわす)については当て字だということを覚えておきましょう。関連:師走とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?師走の別名は?以上が「旧暦の月(睦月、如月、弥生・・・)の意味と読み方、由来とは?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、旧暦と新暦(現在の暦)では、だいたい1ヶ月~2ヵ月の期間ずれている。<旧暦の月の意味・読み方・由来まとめ>睦月(むつき)は旧暦の1月のことで、親戚や知人が集まって仲睦まじくする月が由来。如月(きさらぎ)は旧暦の2月のことで、寒くなり衣を更に重ねて着る”衣更着”から由来。弥生(やよい)は旧暦の3月のことで、”弥(いよいよ)”草木が”生い”茂るから由来。卯月(うづき)は旧暦の4月のことで、卯の花が咲く月という意味の”卯の花月”から由来。皐月(さつき)は旧暦の5月のことで、田に早苗を植える月という”早苗月”から由来。水無月(みなづき)は旧暦の6月のことで、田んぼに再び水を引く月という”水の月”から由来。文月(ふみづき)は旧暦の7月のことで、七夕のとき短冊に歌や字(文)を書いていたことから由来。葉月(はづき)は旧暦の8月のことで、葉が落ち始める月という意味の”葉落ち月”から由来。長月(ながつき)は旧暦の9月のことで、夜が少しずつ長くなり始める月という”夜長月”から由来。神無月(かんなづき)は旧暦の10月のことで、全国の神々が出雲大社に集まる”神の月”から由来。霜月(しもつき)は旧暦の11月のことで、霜が降り始める月という”霜降り月”から由来。師走(しわす)は旧暦の12月のことで、僧(お坊さん)がお経を唱えるため忙しく走り回ることから由来。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒西暦とは何か?西暦はいつから使われた?西暦・和暦・干支の早見表!⇒四半世紀の意味とは?また半世紀・三四半世紀が示す期間は?⇒和暦とは?西暦との違いは何か?⇒紀元前とは?またBCとADの意味や表を分かりやすくまとめました!⇒1世紀は何年のこと?21世紀はいつから?22世紀までの早見表あり⇒今年と今年度の違いとは?年度の期間は目的によって異なるって本当?⇒2月が28日しかない理由とは?なぜうるう年は2月に調整される?⇒上旬と下旬と中旬の期間の違いとは?⇒うるう年(閏年)とは?4年に1度だけ366日になる仕組みを解説!⇒なぜ旧暦と新暦にずれが発生するのかを詳しく解説!
-
さてあなたは睦月とは何かをご存知でしょうか。いま現在では日本での暦は主に新暦が使われていますが、昔は新暦ではなく旧暦が使用されていました。睦月というのは日本での旧暦の時代における月(1月、2月・・・)の名称なのですが、現在ではほとんど使用されることがないので分からない人も多いでしょう。そこでこのページでは睦月とは何月のことを指しているのか?また睦月の意味・由来・読み方・別名について簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次睦月とは何月のことを指しているのか?睦月の意味・由来・読み方について睦月の別名とは何か?初月(しょげつ)初春月(はつはるづき)新春(しんしゅん)他の睦月の別名(箇条書き)まとめ1.睦月とは何月のことを指しているのか?では睦月とは何月のことを指しているのか見ていきましょう。睦月とは旧暦における月(1月、2月、3月・・・)の名称のことで、新暦(いま現在の暦)でいうところの”1月”のことを指しています。いまだと1年間が365日(うるう年だと366日)というのは一般的ですが、それはいま現在使用されているのが新暦だからです。(いま現在使用されている暦は、太陽暦のひとつであるグレゴリオ暦です)日本における旧暦では天保暦(太陰太陽暦のひとつ)が使用されていましたが、旧暦(天保暦)に従った場合は1年間が354日ということになります。そしてこの旧暦が使用されていたときの月の名称が”睦月”であり、暦が新暦に改暦された現在では睦月という名称から”1月”に変更されました。ですが睦月(旧暦の月)と1月(新暦の月)では季節にずれが発生していて、”だいたい1ヶ月~2ヶ月ほど”のずれがあるので注意が必要です。なので睦月の時期は旧暦と新暦における季節のずれを考慮すると、新暦(現在の暦)でいうところの”1月下旬~3月上旬”のことを表していることになります。関連:旧暦の月(睦月、如月、弥生・・・)の意味と読み方、由来とは?関連:なぜ旧暦と新暦にずれが発生するのかを詳しく解説!2.睦月の意味・由来・読み方についてでは睦月の意味・由来・読み方について見ていきましょう。まず睦月は旧暦における1月のことで、読み方は”睦月(むつき)”になります。そして睦月の意味・由来としては諸説ありますが、その中で有力な説としては”陸び月(むつびつき)”から由来したという説があります。お正月に家族や親せきが集まり、仲睦まじく(仲良く・親密に)過ごすことから”睦び月(むつびつき)”と呼ばれ、その”睦び月”が略されて旧暦における1月である”睦月(むつき)”になったとされています。なので睦月(むつき)の由来としては、親戚や知人が集まって仲睦(むつ)まじくする月という意味からきているんですね。また他の説(有力な説ではない)としては、1年の元になる月(初めの月)ということから”元月(もとつき)”が転じて睦月になったとされる説。稲の実を初めて水に浸す月ということから、”実月(むつき)”が転じて睦月になったとされる説もあります。このように旧暦の月名の由来には様々な説があります。3.睦月の別名とは何か?旧暦の月名である睦月(むつき)ですが、実は睦月という名称以外にも別名がたくさんあります。いまだと1月のことは1月としか言わず別名はありませんが、昔は月名に生活や季節に関連する呼び方をしていました。そしてその月を表す名称もひとつやふたつではありません。では睦月の別名には一体どういう名称のものがあるのかを見ていきましょう。初月(しょげつ)睦月が別名で初月(しょげつ)と呼ばれるのは、1年の初めの月という理由からです。睦月は新暦(現在の暦)でいうところの1月にあたる月のことなので、1年間の最初の月になるため別名で初月(しょげつ)と呼ばれます。初春(しょしゅん)睦月が別名で初春(しょしゅん)と呼ばれるのは、その年で初めて春が訪れる月という理由からです。他にも初春(しょしゅん)は、”初春(はつはる)”と呼ばれることも多いです。いま現在では春という季節は3月・4月・5月になりますが、旧暦における春は1月・2月・3月の時期のことを言います。睦月は1月のことを指しているため初めて春が訪れる月ということで、睦月の別名として初春(しょしゅん)と呼ばれています。新春(しんしゅん)睦月が別名で新春(しんしゅん)と呼ばれるのは、新しい春が始まる月という理由からです。初春月のときと同様で旧暦では1月・2月・3月が春とされているので、新しい春が始まる月ということで別名として新春(しんしゅん)と呼ばれています。またお正月(現在の1月)のことを新春と言うことがよくありますが、これは旧暦の季節の名残からきているものです。なので旧暦では1月が新しい春の始まりだったことから、その旧暦のときの名残でいま現在もお正月のことを新春と呼んでいます。他の睦月の別名(箇条書き)”初月(しょげつ)”、”初春(しょしゅん)”、”新春(しんしゅん)”以外にも、睦月の別名として呼ばれている名称について下に箇条書きにしてみました。<睦月の別名の一覧>孟春(もうしゅん)早緑月(さみどりづき)三微月(さんびづき)霞初月(かすみそめづき)太郎月(たろうづき)暮新月(くれしづき)子日月(ねのひづき)初見月(はつみづき)王春(おうしゅん)開歳(かいさい)開春(かいしゅん)嘉月(かげつ)歳始(さいし) などなど※上記以外にも睦月の別名は数多く存在しています。以上が「睦月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?睦月の別名は?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、睦月(むつき)とは、旧暦における1月のこと。睦月と新暦の1月には季節にずれがあり、睦月は現在の1月下旬~3月上旬のことになる。睦月の由来は、お正月に家族や親せきと仲睦まじく過ごすことからきている。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒上旬と下旬と中旬の期間の違いとは?⇒新暦って何?旧暦との違いとは?⇒太陽暦とは?太陰暦と太陰太陽暦との違いって何?⇒ユリウス暦とは?グレゴリオ暦との違いって何?⇒紀元前とは?またBCとADの意味や表を分かりやすくまとめました!⇒今年と今年度の違いとは?年度の期間は目的によって異なるって本当?⇒和暦とは?西暦との違いは何か?⇒西暦とは何か?西暦はいつから使われた?西暦・和暦・干支の早見表!⇒うるう年(閏年)とは?4年に1度だけ366日になる仕組みを解説!⇒如月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?如月の別名は?
-
さてあなたは如月とは何かをご存知でしょうか。いま現在では日本での暦は主に新暦が使われていますが、昔は新暦ではなく旧暦が使用されていました。如月というのは日本での旧暦の時代における月(1月、2月・・・)の名称なのですが、現在ではほとんど使用されることがないので分からない人も多いでしょう。そこでこのページでは如月とは何月のことを指しているのか?また如月の意味・由来・読み方・別名について簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次如月とは何月のことを指しているのか?如月の意味・由来・読み方について如月の別名とは何か?仲春(ちゅうしゅん)初花月(はつはなづき)雪消月(ゆきぎえづき)他の如月の別名(箇条書き)まとめ1.如月とは何月のことを指しているのか?では如月とは何月のことを指しているのか見ていきましょう。如月とは旧暦における月(1月、2月、3月・・・)の名称のことで、新暦(いま現在の暦)でいうところの”2月”のことを指しています。いまだと1年間が365日(うるう年だと366日)というのは一般的ですが、それはいま現在使用されているのが新暦だからです。(いま現在使用されている暦は、太陽暦のひとつであるグレゴリオ暦です)日本における旧暦では天保暦(太陰太陽暦のひとつ)が使用されていましたが、旧暦(天保暦)に従った場合は1年間が354日ということになります。そしてこの旧暦が使用されていたときの月の名称が”如月”であり、暦が新暦に改暦された現在では如月という名称から”2月”に変更されました。ですが如月(旧暦の月)と2月(新暦の月)では季節にずれが発生していて、”だいたい1ヶ月~2ヶ月ほど”のずれがあるので注意が必要です。なので如月の時期は旧暦と新暦における季節のずれを考慮すると、新暦(現在の暦)でいうところの”2月下旬~4月上旬”のことを表していることになります。関連:旧暦の月(睦月、如月、弥生・・・)の意味と読み方、由来とは?関連:なぜ旧暦と新暦にずれが発生するのかを詳しく解説!2.如月の意味・由来・読み方についてでは如月の意味・由来・読み方について見ていきましょう。まず如月は旧暦における2月のことで、読み方は”如月(きさらぎ)”になります。そして如月の意味・由来としては諸説ありますが、その中で有力な説としては”衣更着(きさらぎ)”から由来したという説があります。もともと如月は中国で使用されていた2月の名称のことで、中国では”如月(きさらぎ)”ではなく”如月(にょげつ)”と呼ばれていました。”如”という字には”従う”という意味があってこれは、何かが動き出すと他のものも動き出すという意味で使用されています。冬という季節は植物や動物などの動きが活発でない(冬眠する)時期であり、その冬の後の季節である如月はそれらが徐々に動き始める時期でもあります。そして如月を”にょげつ”ではなく”きさらぎ”と読むようになったのは、以下の説が有力とされています。新暦(現在の暦)では如月は2月下旬から4月上旬のことで、この時期から少しずつ暖かくなり始めますが、そのあと一旦また寒さがぶり返す時期でもあります。このように少しずつ暖かくなる時期ではありますが、再び寒さがぶり返す時期なために、一旦脱いだ衣(服)を更に着るという意味から”衣更着(きさらぎ)”と呼ばれるようになりました。この”衣更着(きさらぎ)”が如月の読み方となり、旧暦における月名の”如月(きさらぎ)”になっています。なので如月(きさらぎ)の由来としては、衣(服)を何枚も重ねて更に着る”衣更着(きさらぎ)”からきているんですね。また他の説(有力な説ではない)としては、草木が生え始める季節という意味から”生更木(きさらぎ)”となり、それが転じて如月になったという説。草木の芽が張り出す月という意味の”草木張り月(くさきはりづき)”が転じたとされる説もあります。このように旧暦の月名の由来には様々な説があります。3.如月の別名とは何か?旧暦の月名である如月(きさらぎ)ですが、実は如月という名称以外にも別名がたくさんあります。いまだと2月のことは2月としか言わず別名はありませんが、昔は月名に生活や季節に関連する呼び方をしていました。そしてその月を表す名称もひとつやふたつではありません。では如月の別名には一体どういう名称のものがあるのかを見ていきましょう。仲春(ちゅうしゅん)如月が別名で仲春(ちゅうしゅん)と呼ばれるのは、春の真ん中という理由からです。旧暦における季節では1月・2月・3月が春となっており、仲春の”仲”という字には”真ん中”という意味があります。ですので仲春は春(1月・2月・3月)の真ん中という意味になるため、旧暦の2月である如月の別名として仲春(ちゅうしゅん)と呼ばれています。ちなみに挨拶などで”仲春の候(ちゅうしゅんのこう)”と使用するときがありますが、だいたい3月初め~4月初めにかけて使われることが多いです。如月は旧暦では2月のことを指していますが、現在の暦では2月下旬から4月上旬ぐらいの時期なのでだいたい合っていますよね。初花月(はつはなづき)如月が別名で初花月(はつはなづき)と呼ばれるのは、季節の中で花が最初に咲く月という理由からです。季節で最初に咲く花のことを”初花”と言い、ここでの初花とは”梅の花”のことを指しています。なので如月(旧暦における2月)は1年間の季節の中で、最初に花が咲く月という意味から”初花月(はつはなづき)”と呼ばれています。また他の花は暖かくなってきてから咲く花がほとんどですが、梅の花は他の花よりもかなり早い時期に咲き始めます。梅の花の時期として現在の暦でいうと2月~3月が開花時期とされ、暖冬の場合では1月ごろに満開になることもあるほどです。雪消月(ゆきぎえづき)如月が別名で雪消月(ゆきぎえづき)と呼ばれるのは、残っていた雪も2月には消えるという理由からです。雪消月(ゆきぎえづき)は、”ゆききえつき”や”ゆきげづき”とも呼ばれます。1月には残っていた雪も2月には消え始めるという意味から、如月の別名として”雪消月(ゆきぎえづき)”と呼ばれています。他の如月の別名(箇条書き)”仲春(ちゅうしゅん)”、”初花月(はつはなづき)”、”雪消月(ゆきぎえづき)”以外にも、如月の別名として呼ばれている名称について下に箇条書きにしてみました。<如月の別名の一覧>衣更着(きさらぎ)梅津早月(うめつさつき)梅津五月(うめつさつき)梅見月(うめみづき)為如(いじょ)木の芽月(このめづき)中の春(なかのはる)殷春(いんしゅん)華朝(かちょう)春分(しゅんぶん)美景(びけい)令節(れいせつ)陽中(ようちゅう)令月(れいげつ) などなど※上記以外にも如月の別名は数多く存在しています。以上が「如月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?如月の別名は?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、如月(きさらぎ)とは、旧暦における2月のこと。如月と新暦の2月には季節にずれがあり、如月は現在の2月下旬~4月上旬のことになる。如月の由来は、衣(服)を何枚も重ねて更に着る”衣更着(きさらぎ)からきている。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒上旬と下旬と中旬の期間の違いとは?⇒新暦って何?旧暦との違いとは?⇒太陽暦とは?太陰暦と太陰太陽暦との違いって何?⇒ユリウス暦とは?グレゴリオ暦との違いって何?⇒紀元前とは?またBCとADの意味や表を分かりやすくまとめました!⇒今年と今年度の違いとは?年度の期間は目的によって異なるって本当?⇒和暦とは?西暦との違いは何か?⇒西暦とは何か?西暦はいつから使われた?西暦・和暦・干支の早見表!⇒うるう年(閏年)とは?4年に1度だけ366日になる仕組みを解説!⇒弥生とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?弥生の別名は?
-
さてあなたは弥生とは何かをご存知でしょうか。いま現在では日本での暦は主に新暦が使われていますが、昔は新暦ではなく旧暦が使用されていました。弥生というのは日本での旧暦の時代における月(1月、2月・・・)の名称なのですが、現在ではほとんど使用されることがないので分からない人も多いでしょう。そこでこのページでは弥生とは何月のことを指しているのか?また弥生の意味・由来・読み方・別名について簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次弥生とは何月のことを指しているのか?弥生の意味・由来・読み方について弥生の別名とは何か?晩春(ばんしゅん)春惜月(はるおしみづき)花見月(はなみづき)他の弥生の別名(箇条書き)まとめ1.弥生とは何月のことを指しているのか?では弥生とは何月のことを指しているのか見ていきましょう。弥生とは旧暦における月(1月、2月、3月・・・)の名称のことで、新暦(いま現在の暦)でいうところの”3月”のことを指しています。いまだと1年間が365日(うるう年だと366日)というのは一般的ですが、それはいま現在使用されているのが新暦だからです。(いま現在使用されている暦は、太陽暦のひとつであるグレゴリオ暦です)日本における旧暦では天保暦(太陰太陽暦のひとつ)が使用されていましたが、旧暦(天保暦)に従った場合は1年間が354日ということになります。そしてこの旧暦が使用されていたときの月の名称が”弥生”であり、暦が新暦に改暦された現在では弥生という名称から”3月”に変更されました。ですが弥生(旧暦の月)と3月(新暦の月)では季節にずれが発生していて、”だいたい1ヶ月~2ヶ月ほど”のずれがあるので注意が必要です。なので弥生の時期は旧暦と新暦における季節のずれを考慮すると、新暦(現在の暦)でいうところの”3月下旬~5月上旬”のことを表していることになります。関連:旧暦の月(睦月、如月、弥生・・・)の意味と読み方、由来とは?関連:なぜ旧暦と新暦にずれが発生するのかを詳しく解説!2.弥生の意味・由来・読み方についてでは弥生の意味・由来・読み方について見ていきましょう。まず弥生は旧暦における3月のことで、読み方は”弥生(やよい)”になります。そして弥生の意味・由来としては諸説ありますが、”弥(いよいよ)”草木が”生い”茂るという意味からきているという説が有力です。如月の頃には草木(植物)はまだ動き始めた段階で活発ではありませんでしたが、弥生になると草木の活動が活発になるので生い茂っていきます。弥生(やよい)はもともと”弥生(いやおい)”が変化したとされるもので、”弥(いや)”は「いよいよ」「ますます」で、”生(おい)”は「生い茂る」の意味となります。このように弥生とは寒い時期(冬)が終わりを迎え、草木が生い茂る時期のことを意味しているんですね。3.弥生の別名とは何か?旧暦の月名である弥生(やよい)ですが、実は弥生という名称以外にも別名がたくさんあります。いまだと3月のことは3月としか言わず別名はありませんが、昔は月名に生活や季節に関連する呼び方をしていました。そしてその月を表す名称もひとつやふたつではありません。では弥生の別名には一体どういう名称のものがあるのかを見ていきましょう。晩春(ばんしゅん)弥生が別名で晩春(ばんしゅん)と呼ばれるのは、春の終わりの方という理由からです。晩春の”晩”には”終わりの方”という意味があるため、晩春というのは春の終わりの方であることを意味しています。現在の季節では3月と言えば春が始まったばかりなのですが、旧暦の季節では春というのは1月・2月・3月なので終わりの方にあたります。ですので晩春は春(1月・2月・3月)の終わりの方を意味しているので、旧暦の3月である弥生の別名として晩春(ばんしゅん)と呼ばれています。春惜月(はるおしみづき)弥生が別名で春惜月(はるおしみづき)と呼ばれるのは、春の終わりを惜しむ月という理由からです。晩春のときにも解説していましたが旧暦における3月は、その年の春という季節が終わってしまう月になります。ですのでその年の春が終わってしまうことを惜しむ月ということで、旧暦の3月である弥生の別名として春惜月(はるおしみづき)と呼ばれています。花見月(はなみづき)弥生が別名で花見月(はなみづき)と呼ばれるのは、花見をする月という理由からです。この時期になると桜の花が咲くので花見をする月ということから、旧暦の3月である弥生の別名として花見月(はなみづき)と呼ばれています。桜の花の開花時期はだいたい3月下旬~4月中旬までが多いので、旧暦の3月は現在の暦だと3月下旬~5月上旬となり時期的に合っています。桜の花ではなく梅の花でも花見とは言えますが、梅の花の開花時期はだいたい2月~3月と時期的に少し早めです。ですので弥生(旧暦の3月)の別名の花見月は、桜の花のことを指していると言えます。他の弥生の別名(箇条書き)”晩春(ばんしゅん)”、”春惜月(はるおしみづき)”、”花見月(はなみづき)”以外にも、弥生の別名として呼ばれている名称について下に箇条書きにしてみました。<弥生の別名の一覧>季春(きしゅん)早花月(さはなつき)花津月(はなつづき)佳月(かげつ)華節(かせつ)花飛(かひ)花老(かろう)穀雨(こくう)桜月(さくらづき)竹秋(ちくしゅう)桃月(とうげつ)祓月(はらえづき)病月(びょうげつ)暮陽(ぼよう) などなど※上記以外にも弥生の別名は数多く存在しています。以上が「弥生とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?弥生の別名は?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、弥生(やよい)とは、旧暦における3月のこと。弥生と新暦の3月には季節にずれがあり、弥生は現在の3月下旬~5月上旬のことになる。弥生の由来は、”弥(いよいよ)”草木が”生い”茂るという意味からきている。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒上旬と下旬と中旬の期間の違いとは?⇒新暦って何?旧暦との違いとは?⇒太陽暦とは?太陰暦と太陰太陽暦との違いって何?⇒ユリウス暦とは?グレゴリオ暦との違いって何?⇒紀元前とは?またBCとADの意味や表を分かりやすくまとめました!⇒今年と今年度の違いとは?年度の期間は目的によって異なるって本当?⇒和暦とは?西暦との違いは何か?⇒西暦とは何か?西暦はいつから使われた?西暦・和暦・干支の早見表!⇒うるう年(閏年)とは?4年に1度だけ366日になる仕組みを解説!⇒卯月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?卯月の別名は?
-
さてあなたは卯月とは何かをご存知でしょうか。いま現在では日本での暦は主に新暦が使われていますが、昔は新暦ではなく旧暦が使用されていました。卯月というのは日本での旧暦の時代における月(1月、2月・・・)の名称なのですが、現在ではほとんど使用されることがないので分からない人も多いでしょう。そこでこのページでは卯月とは何月のことを指しているのか?また卯月の意味・由来・読み方・別名について簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次卯月とは何月のことを指しているのか?卯月の意味・由来・読み方について卯月の別名とは何か?初夏(しょか)夏初月(なつはづき)麦秋(ばくしゅう)他の卯月の別名(箇条書き)まとめ1.卯月とは何月のことを指しているのか?では卯月とは何月のことを指しているのか見ていきましょう。卯月とは旧暦における月(1月、2月、3月・・・)の名称のことで、新暦(いま現在の暦)でいうところの”4月”のことを指しています。いまだと1年間が365日(うるう年だと366日)というのは一般的ですが、それはいま現在使用されているのが新暦だからです。(いま現在使用されている暦は、太陽暦のひとつであるグレゴリオ暦です)日本における旧暦では天保暦(太陰太陽暦のひとつ)が使用されていましたが、旧暦(天保暦)に従った場合は1年間が354日ということになります。そしてこの旧暦が使用されていたときの月の名称が”卯月”であり、暦が新暦に改暦された現在では卯月という名称から”4月”に変更されました。ですが卯月(旧暦の月)と4月(新暦の月)では季節にずれが発生していて、”だいたい1ヶ月~2ヶ月ほど”のずれがあるので注意が必要です。なので卯月の時期は旧暦と新暦における季節のずれを考慮すると、新暦(現在の暦)でいうところの”4月下旬~6月上旬”のことを表していることになります。関連:旧暦の月(睦月、如月、弥生・・・)の意味と読み方、由来とは?関連:なぜ旧暦と新暦にずれが発生するのかを詳しく解説!2.卯月の意味・由来・読み方について※卯の花(ウツギの花)の写真では卯月の意味・由来・読み方について見ていきましょう。まず卯月は旧暦における4月のことで、読み方は”卯月(うづき)”になります。そして卯月の意味・由来としては諸説ありますが、卯の花(ウツギの花)が咲く月という意味の”卯の花月”からきている説が有力です。卯の花はウツギの花とも呼ばれ、卯の花の茎の中が空洞になっていることから、”空木(ウツギ)の花”と呼ばれるようになりました。卯の花(ウツギの花)が開花するのは5月中旬~6月頃になるので、旧暦における4月(現在の4月下旬~6月上旬)は”卯月(うづき)”と呼ばれていたんですね。また他の説(有力な説ではない)としては、1年の最初のことを意味する”初”や”産”の”う”から卯月になったという説。稲を植える月と言う意味かの”植月(うえつき)”から、卯月になったという説もあります。(この説については旧暦の5月である皐月の語源と似ているため薄いです)このように旧暦の月名の由来には様々な説があります。3.卯月の別名とは何か?旧暦の月名である卯月(うづき)ですが、実は卯月という名称以外にも別名がたくさんあります。いまだと4月のことは4月としか言わず別名はありませんが、昔は月名に生活や季節に関連する呼び方をしていました。そしてその月を表す名称もひとつやふたつではありません。では卯月の別名には一体どういう名称のものがあるのかを見ていきましょう。初夏(しょか)卯月が別名で初夏(しょか)と呼ばれるのは、その年で初めて夏が訪れる月という理由からです。現在の暦(新暦)における季節では夏は6月・7月・8月ですが、旧暦における季節では夏というのは4月・5月・6月になります。ですので卯月(旧暦の4月)というのはその年で初めて夏が訪れる月になるため、卯月の別名として初夏(しょか)と呼ばれているんですね。夏初月(なつはづき)卯月が別名で夏初月(なつはづき)と呼ばれるのは、その年で夏が初めて訪れる月という理由からです。これも初夏のときと同様の理由から名称が付けられており、旧暦における季節は4月・5月・6月が夏だったことから卯月の別名になっています。ですので夏初月は夏(4月・5月・6月)が初めて訪れる月のことを意味しているので、旧暦の4月である卯月の別名として夏初月(なつはづき)と呼ばれています。麦秋(ばくしゅう)卯月が別名で麦秋(ばくしゅう)と呼ばれるのは、麦における収穫の秋という理由からです。麦秋は”ばくしゅう”以外の呼び方では、そのまま”むぎあき”とも呼ばれています。旧暦における4月(現在の暦における4月下旬~6月上旬)は、麦を収穫する時期であり、麦にとっての収穫の秋になります。”収穫の秋”と言われるのは昔から作物を収穫する季節には秋が多かったためで、収穫の秋以外でも”実りの秋”のように言うことがあります。ですので実際に麦が収穫されるのは夏なので秋はそこまで関係ないですが、麦にとっては”収穫の秋”だということから卯月の別名とされているようです。他の卯月の別名(箇条書き)”初夏(しょか)”、”夏初月(なつはづき)”、”麦秋(ばくしゅう)”以外にも、卯月の別名として呼ばれている名称について下に箇条書きにしてみました。<卯月の別名の一覧>卯花月(うのはなづき)孟夏(もうか)得鳥羽月(えとりはづき)木葉採月(このはとりづき)花残月(はなのこりづき)維夏(いか)陰月(いんげつ)乾月(けんげつ)乾梅(けんばい)始夏(しか)修景(しゅうけい)新夏(しんか)仲呂(ちゅうりょ)正陽(せいよう) などなど※上記以外にも卯月の別名は数多く存在しています。以上が「卯月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?卯月の別名は?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、卯月(うづき)とは、旧暦における4月のこと。卯月と新暦の4月には季節にずれがあり、卯月は現在の4月下旬~6月上旬のことになる。卯月の由来は、卯の花が咲く月という意味の”卯の花月”からからきている。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒上旬と下旬と中旬の期間の違いとは?⇒新暦って何?旧暦との違いとは?⇒太陽暦とは?太陰暦と太陰太陽暦との違いって何?⇒ユリウス暦とは?グレゴリオ暦との違いって何?⇒紀元前とは?またBCとADの意味や表を分かりやすくまとめました!⇒今年と今年度の違いとは?年度の期間は目的によって異なるって本当?⇒和暦とは?西暦との違いは何か?⇒西暦とは何か?西暦はいつから使われた?西暦・和暦・干支の早見表!⇒うるう年(閏年)とは?4年に1度だけ366日になる仕組みを解説!⇒皐月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?皐月の別名は?
-
さてあなたは皐月とは何かをご存知でしょうか。いま現在では日本での暦は主に新暦が使われていますが、昔は新暦ではなく旧暦が使用されていました。皐月というのは日本での旧暦の時代における月(1月、2月・・・)の名称なのですが、現在ではほとんど使用されることがないので分からない人も多いでしょう。そこでこのページでは皐月とは何月のことを指しているのか?また皐月の意味・由来・読み方・別名について簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次皐月とは何月のことを指しているのか?皐月の意味・由来・読み方について皐月の別名とは何か?仲夏(ちゅうか)早稲月(さいねづき)橘月(たちばなづき)他の皐月の別名(箇条書き)まとめ1.皐月とは何月のことを指しているのか?では皐月とは何月のことを指しているのか見ていきましょう。皐月とは旧暦における月(1月、2月、3月・・・)の名称のことで、新暦(いま現在の暦)でいうところの”5月”のことを指しています。いまだと1年間が365日(うるう年だと366日)というのは一般的ですが、それはいま現在使用されているのが新暦だからです。(いま現在使用されている暦は、太陽暦のひとつであるグレゴリオ暦です)日本における旧暦では天保暦(太陰太陽暦のひとつ)が使用されていましたが、旧暦(天保暦)に従った場合は1年間が354日ということになります。そしてこの旧暦が使用されていたときの月の名称が”皐月”であり、暦が新暦に改暦された現在では皐月という名称から”5月”に変更されました。ですが皐月(旧暦の月)と5月(新暦の月)では季節にずれが発生していて、”だいたい1ヶ月~2ヶ月ほど”のずれがあるので注意が必要です。なので皐月の時期は旧暦と新暦における季節のずれを考慮すると、新暦(現在の暦)でいうところの”5月下旬~7月上旬”のことを表していることになります。関連:旧暦の月(睦月、如月、弥生・・・)の意味と読み方、由来とは?関連:なぜ旧暦と新暦にずれが発生するのかを詳しく解説!2.皐月の意味・由来・読み方について※写真中で植えられているのが早苗(若い稲の苗)では皐月の意味・由来・読み方について見ていきましょう。まず皐月は旧暦における5月のことで、読み方は”皐月(さつき)”になります。そして皐月の意味・由来としては諸説ありますが、田に早苗(若い稲の苗)を植える月という意味の”早苗月(さなえづき)”からきている説が有力です。稲の苗というのは田植えができるようになるまである程度育てる必要があって、田植えを行うことができるまで育った苗のことを”早苗(さなえ)”と言います。そしてこの時期は田んぼに若い稲の苗である早苗を植える月ということから、早苗を植える月なので”早苗月(さなえづき)”となりました。その”早苗月”が略されて旧暦の”皐月(さつき)”になるのですが、もともとさつきの”さ”という字自体に苗植えや耕作の意味があります。さらに皐月の”皐”という漢字があてられているのも、”皐”という字には”神に捧げる稲”という意味があることから皐月となったようです。3.皐月の別名とは何か?旧暦の月名である皐月(さつき)ですが、実は皐月という名称以外にも別名がたくさんあります。いまだと5月のことは5月としか言わず別名はありませんが、昔は月名に生活や季節に関連する呼び方をしていました。そしてその月を表す名称もひとつやふたつではありません。では皐月の別名には一体どういう名称のものがあるのかを見ていきましょう。仲夏(ちゅうか)皐月が別名で仲夏(ちゅうか)と呼ばれるのは、夏の真ん中という理由からです。旧暦における季節では4月・5月・6月が夏となっており、仲夏の”仲”という字には”真ん中”という意味があります。ですので仲夏は夏(4月・5月・6月)の真ん中という意味になるため、旧暦の5月である皐月の別名として仲夏(ちゅうか)と呼ばれています。ちなみに挨拶などで”仲夏の候(ちゅうかのこう)”と使用するときがありますが、だいたい6月初め~7月初めにかけて使われることが多いです。皐月は旧暦では5月のことを指していますが、現在の暦では5月下旬から7月上旬ぐらいの時期なのでだいたい合っていますよね。早稲月(さいねづき)皐月が別名で早稲月(さいねづき)と呼ばれるのは、早熟の稲を植える月という理由からです。早熟の稲というのはつまり早苗(さなえ)のことであり、早苗を植える月である”早苗月(さなえづき)”と語源的にはほとんど同じです。なので”早苗月(さなえづき)”と”早稲月(さいねづき)”で、呼び方が多少異なるだけですね。橘月(たちばなづき)※橘(たちばな)の花の写真皐月が別名で橘月(たちばなづき)と呼ばれるのは、橘の花が咲く月という理由からです。橘の開花時期は現在の季節でいう5月~7月あたりになるので、旧暦の5月である皐月の時期(5月下旬~7月上旬)とだいたい合っています。他の皐月の別名(箇条書き)”仲夏(ちゅうか)”、”早稲月(さいねづき)”、”橘月(たちばなづき)”以外にも、皐月の別名として呼ばれている名称について下に箇条書きにしてみました。<皐月の別名の一覧>早苗月(さなえづき)授雲月(じゅうんづき)田草月(たぐさづき)月不見月(つきみずづき)吹喜月(ふききづき)悪月(あくげつ)雨月(うげつ)開明(かいめい)啓月(けいげつ)写月(しゃげつ)鶉月(うずらづき)梅夏(ばいか)梅月(ばいげつ)長至(ちょうし) などなど※上記以外にも皐月の別名は数多く存在しています。以上が「皐月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?皐月の別名は?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、皐月(さつき)とは、旧暦における5月のこと。皐月と新暦の5月には季節にずれがあり、皐月は現在の5月下旬~7月上旬のことになる。皐月の由来は、田に早苗(若い稲の苗)を植える月という意味の”早苗月(さなえづき)”からきている。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒上旬と下旬と中旬の期間の違いとは?⇒新暦って何?旧暦との違いとは?⇒太陽暦とは?太陰暦と太陰太陽暦との違いって何?⇒ユリウス暦とは?グレゴリオ暦との違いって何?⇒紀元前とは?またBCとADの意味や表を分かりやすくまとめました!⇒今年と今年度の違いとは?年度の期間は目的によって異なるって本当?⇒和暦とは?西暦との違いは何か?⇒西暦とは何か?西暦はいつから使われた?西暦・和暦・干支の早見表!⇒うるう年(閏年)とは?4年に1度だけ366日になる仕組みを解説!⇒水無月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?水無月の別名は?
-
さてあなたは水無月とは何かをご存知でしょうか。いま現在では日本での暦は主に新暦が使われていますが、昔は新暦ではなく旧暦が使用されていました。水無月というのは日本での旧暦の時代における月(1月、2月・・・)の名称なのですが、現在ではほとんど使用されることがないので分からない人も多いでしょう。そこでこのページでは水無月とは何月のことを指しているのか?また水無月の意味・由来・読み方・別名について簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次水無月とは何月のことを指しているのか?水無月の意味・由来・読み方について水無月の別名とは何か?晩夏(ばんか)水張月(みずはりづき)常夏月(とこなつづき)他の水無月の別名(箇条書き)まとめ1.水無月とは何月のことを指しているのか?では睦月とは何月のことを指しているのか見ていきましょう。水無月とは旧暦における月(1月、2月、3月・・・)の名称のことで、新暦(いま現在の暦)でいうところの”6月”のことを指しています。いまだと1年間が365日(うるう年だと366日)というのは一般的ですが、それはいま現在使用されているのが新暦だからです。(いま現在使用されている暦は、太陽暦のひとつであるグレゴリオ暦です)日本における旧暦では天保暦(太陰太陽暦のひとつ)が使用されていましたが、旧暦(天保暦)に従った場合は1年間が354日ということになります。そしてこの旧暦が使用されていたときの月の名称が”水無月”であり、暦が新暦に改暦された現在では水無月という名称から”6月”に変更されました。ですが水無月(旧暦の月)と6月(新暦の月)では季節にずれが発生していて、”だいたい1ヶ月~2ヶ月ほど”のずれがあるので注意が必要です。なので水無月の時期は旧暦と新暦における季節のずれを考慮すると、新暦(現在の暦)でいうところの”6月下旬~8月上旬”のことを表していることになります。関連:旧暦の月(睦月、如月、弥生・・・)の意味と読み方、由来とは?関連:なぜ旧暦と新暦にずれが発生するのかを詳しく解説!2.水無月の意味・由来・読み方についてでは水無月の意味・由来・読み方について見ていきましょう。まず水無月は旧暦における6月のことで、読み方は”水無月(みなづき)”になります。そして水無月の意味・由来としては諸説ありますが、”無”は”の”を意味し、田んぼに再び水を引く月という意味の”水の月”からきている説が有力です。水無月には”無”という漢字があるので”水が無い月”と覚えている人も多いのですが、実は水無月の”無”は”ない(存在しない)”ということを表しているのではありません。これは古い日本語の使い方で、”な”は現在の意味における”の”を意味していることから、水無月は”水の月”を意味していることになるんですね。ではなぜ旧暦における6月(現在の6月下旬~8月上旬)が”水の月”になるのかと言うと、それは水が抜かれた田んぼに再び水を引くための作業が行われるからです。※中干し作業後の田んぼの写真旧暦の前の月である皐月には田んぼに早苗を植えていますが、そのあと水無月になると一旦”中干し”と呼ばれる田んぼの水を抜く作業があります。(田んぼの中干しが行われるのは、現在の暦でいうところの7月下旬あたりです)そして中干し作業が終わると再び田んぼに水が引かれるので、旧暦における6月は”水の月”を意味する水無月になったということです。3.水無月の別名とは何か?旧暦の月名である水無月(みなづき)ですが、実は水無月という名称以外にも別名がたくさんあります。いまだと6月のことは6月としか言わず別名はありませんが、昔は月名に生活や季節に関連する呼び方をしていました。そしてその月を表す名称もひとつやふたつではありません。では水無月の別名には一体どういう名称のものがあるのかを見ていきましょう。晩夏(ばんか)水無月が別名で晩夏(ばんか)と呼ばれるのは、夏の終わりの方という理由からです。晩夏の”晩”には”終わりの方”という意味があるため、晩夏というのは夏の終わりの方であることを意味しています。現在の季節では6月と言えば夏が始まったばかりなのですが、旧暦の季節では夏というのは4月・5月・6月なので終わりの方にあたります。ですので晩夏は夏(4月・5月・6月)の終わりの方を意味しているので、旧暦の6月である水無月の別名として晩夏(ばんか)と呼ばれています。水張月(みずはりづき)水無月が別名で水張月(みずはりづき)と呼ばれるのは、という理由からです。これは水無月の由来のところでも解説したように、旧暦における6月(水無月)は田んぼに水を引く月でした。そして田んぼに水を張る(引く)という意味として、水無月のことを”水張月(みずはりづき)”と呼んでいたそうです。呼び方が違うだけで、基本的には水無月のときの解釈と同じになります。常夏月(とこなつづき)※常夏の花(ナデシコ)の写真水無月が別名で常夏月(とこなつづき)と呼ばれるのは、常夏の花が咲く月という理由からです。常夏の花であるナデシコの開花時期は6月~9月になるので、旧暦における6月である水無月の時期(6月下旬~8月上旬)とだいたい合っています。常夏(とこなつ)という言葉は”ずっと夏のような気候”ということを意味していますが、ナデシコは品種にもよりますが夏~秋にかけて比較的長い時期にわたり咲いています。またナデシコの品種には四季咲きの品種もあるので季節を問わず、何度でも開花する様子から常に夏を感じられるということで”常夏の花”と呼ばれています。他の水無月の別名(箇条書き)”晩夏(ばんか)”、”水張月(みずはりづき)”、”常夏月(とこなつづき)”以外にも、水無月の別名として呼ばれている名称について下に箇条書きにしてみました。<水無月の別名の一覧>季夏(きか)青水無月(あおみなづき)風待月(かぜまちづき)涼暮月(すずくれづき)蝉の羽月(せみのはづき)鳴雷月(なるかみづき)鳴神月(なるかみづき)炎陽(えんよう)松風月(まつかぜづき)極暑(きょくしょ)庚伏(こうふく)鶉火(じゅんか)水月(すいげつ)陽氷(ようひょう) などなど※上記以外にも水無月の別名は数多く存在しています。以上が「水無月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?水無月の別名は?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、水無月(みなづき)とは、旧暦における6月のこと。水無月と新暦の6月には季節にずれがあり、水無月は現在の6月下旬~8月上旬のことになる。水無月の由来は、田んぼに再び水を引く月という意味の”水の月”からきている。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒上旬と下旬と中旬の期間の違いとは?⇒新暦って何?旧暦との違いとは?⇒太陽暦とは?太陰暦と太陰太陽暦との違いって何?⇒ユリウス暦とは?グレゴリオ暦との違いって何?⇒紀元前とは?またBCとADの意味や表を分かりやすくまとめました!⇒今年と今年度の違いとは?年度の期間は目的によって異なるって本当?⇒和暦とは?西暦との違いは何か?⇒西暦とは何か?西暦はいつから使われた?西暦・和暦・干支の早見表!⇒うるう年(閏年)とは?4年に1度だけ366日になる仕組みを解説!⇒文月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?文月の別名は?
-
さてあなたは文月とは何かをご存知でしょうか。いま現在では日本での暦は主に新暦が使われていますが、昔は新暦ではなく旧暦が使用されていました。文月というのは日本での旧暦の時代における月(1月、2月・・・)の名称なのですが、現在ではほとんど使用されることがないので分からない人も多いでしょう。そこでこのページでは文月とは何月のことを指しているのか?また文月の意味・由来・読み方・別名について簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次文月とは何月のことを指しているのか?文月の意味・由来・読み方について文月の別名とは何か?秋初月(あきはづき)初秋(しょしゅう)七夕月(たなばたづき)他の文月の別名(箇条書き)まとめ1.文月とは何月のことを指しているのか?では文月とは何月のことを指しているのか見ていきましょう。文月とは旧暦における月(1月、2月、3月・・・)の名称のことで、新暦(いま現在の暦)でいうところの”7月”のことを指しています。いまだと1年間が365日(うるう年だと366日)というのは一般的ですが、それはいま現在使用されているのが新暦だからです。(いま現在使用されている暦は、太陽暦のひとつであるグレゴリオ暦です)日本における旧暦では天保暦(太陰太陽暦のひとつ)が使用されていましたが、旧暦(天保暦)に従った場合は1年間が354日ということになります。そしてこの旧暦が使用されていたときの月の名称が”文月”であり、暦が新暦に改暦された現在では文月という名称から”7月”に変更されました。ですが文月(旧暦の月)と7月(新暦の月)では季節にずれが発生していて、”だいたい1ヶ月~2ヶ月ほど”のずれがあるので注意が必要です。なので文月の時期は旧暦と新暦における季節のずれを考慮すると、新暦(現在の暦)でいうところの”7月下旬~9月上旬”のことを表していることになります。関連:旧暦の月(睦月、如月、弥生・・・)の意味と読み方、由来とは?関連:なぜ旧暦と新暦にずれが発生するのかを詳しく解説!2.文月の意味・由来・読み方についてでは文月の意味・由来・読み方について見ていきましょう。まず文月は旧暦における7月のことで、読み方は”文月(ふみづき)”になります。そして文月の意味・由来としては諸説ありますが、七夕のとき短冊に歌や字(文)を書いていたことからきている説が有力です。いまでは七夕になると短冊に願い事を書くというのが一般的ですが、昔は願い事ではなく歌や字(文)を書いて、書道の上達を祈っていたそうです。そのような七夕の風習に因(ちな)んで、旧暦の7月は”文披月(ふみひらきづき)”と呼ばれるようになりました。(文披月の読み方については”ふみひろげづき”でも問題ありません)”披(ひら)くは閉じてあるものを開ける”という意味があることから、”文(ふみ)を広げて晒(さら)す月”という意味で”文披月(ふみひらきづき)”です。その文披月がのちに旧暦の月である”文月(ふみづき)”になったとされています。また他の説(有力な説ではない)としては、この時期に稲穂が膨らむ月であることから、”穂含月(ほふみづき)”や”含月(ふくみづき)”となり、それが転じて文月になったとされる説。稲穂の膨らみを見る月であることから”穂見月(ほみづき)”となり、それが転じたという説があります。このように旧暦の月名の由来には様々な説があります。3.文月の別名とは何か?旧暦の月名である文月(ふみづき)ですが、実は文月という名称以外にも別名がたくさんあります。いまだと7月のことは7月としか言わず別名はありませんが、昔は月名に生活や季節に関連する呼び方をしていました。そしてその月を表す名称もひとつやふたつではありません。では文月の別名には一体どういう名称のものがあるのかを見ていきましょう。秋初月(あきはづき)文月が別名で秋初月(あきはづき)と呼ばれるのは、その年で秋が初めて訪れる月という理由からです。秋初月(あきはづき)は他にも、”あきそめづき”や”あきそめつき”と呼ばれています。いま現在の季節だと秋は9月・10月・11月になりますが、旧暦における季節は7月・8月・9月が秋ということになっています。ですので秋初月は秋(7月・8月・9月)が初めて訪れる月のことを意味しているので、旧暦の7月である文月の別名として秋初月(あきはづき)と呼ばれています。初秋(しょしゅう)文月が別名で初秋(しょしゅう)と呼ばれるのは、その年で初めて秋が訪れる月という理由からです。これも秋初月のときと同様の理由から名称が付けられており、旧暦における季節は7月・8月・9月が秋だったことから文月の別名になっています。ですので初秋は秋(7月・8月・9月)が初めて訪れる月のことを意味しているので、旧暦の7月である文月の別名として初秋(しょしゅう)と呼ばれています。七夕月(たなばたづき)文月が別名で七夕月(たなばたづき)と呼ばれるのは、七夕の行事を行う月という理由からです。この七夕月については名称がそのままなので分かりやすいですが、文月(旧暦における7月)に短冊に歌や字(文)を書くという行事を行っていました。これがそのまま文月の別名として、”七夕月(たなばたづき)”と呼ばれていたそうです。他の文月の別名(箇条書き)”秋初月(あきはづき)”、”初秋(しょしゅう)”、”七夕月(たなばたづき)”以外にも、文月の別名として呼ばれている名称について下に箇条書きにしてみました。<文月の別名の一覧>文披月(ふみひらきづき)七夜月(ななよづき)孟秋(もうしゅう)女郎花月(おみなえしづき)愛逢月(めであいづき)夷則(いそく)瓜時(かじ)上秋(じょうしゅう)処暑(しょしょ)親月(しんげつ)新秋(しんしゅう)相月(そうげつ)否月(ひげつ)涼月(りょうげつ) などなど※上記以外にも文月の別名は数多く存在しています。以上が「文月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?文月の別名は?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、文月(ふみづき)とは、旧暦における7月のこと。文月と新暦の7月には季節にずれがあり、文月は現在の7月下旬~9月上旬のことになる。文月の由来は、七夕のとき短冊に歌や字(文)を書いていたことからきている。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒上旬と下旬と中旬の期間の違いとは?⇒新暦って何?旧暦との違いとは?⇒太陽暦とは?太陰暦と太陰太陽暦との違いって何?⇒ユリウス暦とは?グレゴリオ暦との違いって何?⇒紀元前とは?またBCとADの意味や表を分かりやすくまとめました!⇒今年と今年度の違いとは?年度の期間は目的によって異なるって本当?⇒和暦とは?西暦との違いは何か?⇒西暦とは何か?西暦はいつから使われた?西暦・和暦・干支の早見表!⇒うるう年(閏年)とは?4年に1度だけ366日になる仕組みを解説!⇒葉月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?葉月の別名は?
-
さてあなたは葉月とは何かをご存知でしょうか。いま現在では日本での暦は主に新暦が使われていますが、昔は新暦ではなく旧暦が使用されていました。葉月というのは日本での旧暦の時代における月(1月、2月・・・)の名称なのですが、現在ではほとんど使用されることがないので分からない人も多いでしょう。そこでこのページでは葉月とは何月のことを指しているのか?また葉月の意味・由来・読み方・別名について簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次葉月とは何月のことを指しているのか?葉月の意味・由来・読み方について葉月の別名とは何か?仲秋(ちゅうしゅう)雁来月(かりくづき)迎寒(げいかん)他の葉月の別名(箇条書き)まとめ1.葉月とは何月のことを指しているのか?では葉月とは何月のことを指しているのか見ていきましょう。葉月とは旧暦における月(1月、2月、3月・・・)の名称のことで、新暦(いま現在の暦)でいうところの”8月”のことを指しています。いまだと1年間が365日(うるう年だと366日)というのは一般的ですが、それはいま現在使用されているのが新暦だからです。(いま現在使用されている暦は、太陽暦のひとつであるグレゴリオ暦です)日本における旧暦では天保暦(太陰太陽暦のひとつ)が使用されていましたが、旧暦(天保暦)に従った場合は1年間が354日ということになります。そしてこの旧暦が使用されていたときの月の名称が”葉月”であり、暦が新暦に改暦された現在では葉月という名称から”8月”に変更されました。ですが葉月(旧暦の月)と8月(新暦の月)では季節にずれが発生していて、”だいたい1ヶ月~2ヶ月ほど”のずれがあるので注意が必要です。なので葉月の時期は旧暦と新暦における季節のずれを考慮すると、新暦(現在の暦)でいうところの”8月下旬~10月上旬”のことを表していることになります。関連:旧暦の月(睦月、如月、弥生・・・)の意味と読み方、由来とは?関連:なぜ旧暦と新暦にずれが発生するのかを詳しく解説!2.葉月の意味・由来・読み方についてでは葉月の意味・由来・読み方について見ていきましょう。まず葉月は旧暦における8月のことで、読み方は”葉月(はづき)”になります。そして葉月の意味・由来としては諸説ありますが、葉が落ち始める時期という意味の”葉落ち月”からきている説が有力です。葉月は旧暦では8月ですが、新暦(現在の暦)だと8月下旬~10月上旬と秋のことを指します。そして秋になると青々としていた葉の色が黄色や赤色に変化しはじめ、木から葉が落ちてしまう”落葉(らくよう)”が始まる時期です。このように葉が落ち始める月という意味の”葉落ち月”から由来しており、最終的にはその葉落ち月が略されて”葉月”になったとされています。また他の説(有力な説ではない)としては、その年に初めて北の方から雁(かり)が渡って来る月で、”初雁月(はつかりづき)”となってそれが転じたという説。稲の穂が月であることから”穂張り月(ほはりづき)”や”張り月(はりづき)”となり、それが転じて葉月(はづき)になったとされる説があります。このように旧暦の月名の由来には様々な説があります。3.葉月の別名とは何か?旧暦の月名である葉月(はづき)ですが、実は葉月という名称以外にも別名がたくさんあります。いまだと8月のことは8月としか言わず別名はありませんが、昔は月名に生活や季節に関連する呼び方をしていました。そしてその月を表す名称もひとつやふたつではありません。では葉月の別名には一体どういう名称のものがあるのかを見ていきましょう。仲秋(ちゅうしゅう)葉月が別名で仲秋(ちゅうしゅう)と呼ばれるのは、秋の真ん中という理由からです。旧暦における季節では7月・8月・9月が秋となっており、仲秋の”仲”という字には”真ん中”という意味があります。ですので仲秋は秋(7月・8月・9月)の真ん中という意味になるため、旧暦の8月である葉月の別名として仲秋(ちゅうしゅう)と呼ばれています。ちなみに挨拶などで”仲秋の候(ちゅうしゅうのこう)”と使用するときがありますが、だいたい9月初め~10月初めにかけて使われることが多いです。葉月は旧暦では8月のことを指していますが、現在の暦では8月下旬から10月上旬ぐらいの時期なのでだいたい合っていますよね。雁来月(かりくづき)※雁(かり、がん)の写真葉月が別名で雁来月(かりくづき)と呼ばれるのは、北から越冬のために雁が来る月という理由からです。雁来月(かりくづき)は別の読み方として、”がんらいげつ”と呼ばれることもあります。先ほど解説した葉月の由来のひとつに”初雁月(はつかりづき)”とありましたが、”雁来月(かりくづき)”はそれと同様の理由からで呼び方が違うだけです。迎寒(げいかん)葉月が別名で迎寒(げいかん)と呼ばれるのは、少しずつ寒さを迎える季節という理由からです。旧暦における8月は現在における8月下旬~10月上旬のことですので、秋の季節から少しずつ冬を迎える季節でもあります。そして冬に近づくことによって少しずつ寒さを迎えていく季節になるため、葉月(旧暦における8月)は別名として”迎寒(げいかん)”と呼ばれています。他の葉月の別名(箇条書き)”仲秋(ちゅうしゅう)”、”雁来月(かりくづき)”、”迎寒(げいかん)”以外にも、葉月の別名として呼ばれている名称について下に箇条書きにしてみました。<葉月の別名の一覧>葉落月(はおちづき)穂張り月(ほはりづき)秋風月(あきかぜづき)木染月(こぞめづき)染色月(そめいろづき)竹の春(たけのはる)月見月(つきみづき)燕去月(つばめさりづき)紅染月(べにそめづき)観月(かんげつ)寒旦(かんたん)秋半(しゅうはん)盛秋(せいしゅう)白露(はくろ) などなど※上記以外にも葉月の別名は数多く存在しています。以上が「葉月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?葉月の別名は?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、葉月(はづき)とは、旧暦における8月のこと。葉月と新暦の8月には季節にずれがあり、葉月は現在の8月下旬~10月上旬のことになる。葉月の由来は、葉が落ち始める時期という意味の”葉落ち月”からきている。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒上旬と下旬と中旬の期間の違いとは?⇒新暦って何?旧暦との違いとは?⇒太陽暦とは?太陰暦と太陰太陽暦との違いって何?⇒ユリウス暦とは?グレゴリオ暦との違いって何?⇒紀元前とは?またBCとADの意味や表を分かりやすくまとめました!⇒今年と今年度の違いとは?年度の期間は目的によって異なるって本当?⇒和暦とは?西暦との違いは何か?⇒西暦とは何か?西暦はいつから使われた?西暦・和暦・干支の早見表!⇒うるう年(閏年)とは?4年に1度だけ366日になる仕組みを解説!⇒長月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?長月の別名は?
-
さてあなたは長月とは何かをご存知でしょうか。いま現在では日本での暦は主に新暦が使われていますが、昔は新暦ではなく旧暦が使用されていました。長月というのは日本での旧暦の時代における月(1月、2月・・・)の名称なのですが、現在ではほとんど使用されることがないので分からない人も多いでしょう。そこでこのページでは長月とは何月のことを指しているのか?また長月の意味・由来・読み方・別名について簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次長月とは何月のことを指しているのか?長月の意味・由来・読み方について長月の別名とは何か?晩秋(ばんしゅう)菊月(きくづき)寝覚月(ねざめづき)他の長月の別名(箇条書き)まとめ1.長月とは何月のことを指しているのか?では長月とは何月のことを指しているのか見ていきましょう。長月とは旧暦における月(1月、2月、3月・・・)の名称のことで、新暦(いま現在の暦)でいうところの”9月”のことを指しています。いまだと1年間が365日(うるう年だと366日)というのは一般的ですが、それはいま現在使用されているのが新暦だからです。(いま現在使用されている暦は、太陽暦のひとつであるグレゴリオ暦です)日本における旧暦では天保暦(太陰太陽暦のひとつ)が使用されていましたが、旧暦(天保暦)に従った場合は1年間が354日ということになります。そしてこの旧暦が使用されていたときの月の名称が”長月”であり、暦が新暦に改暦された現在では長月という名称から”9月”に変更されました。ですが長月(旧暦の月)と9月(新暦の月)では季節にずれが発生していて、”だいたい1ヶ月~2ヶ月ほど”のずれがあるので注意が必要です。なので長月の時期は旧暦と新暦における季節のずれを考慮すると、新暦(現在の暦)でいうところの”9月下旬~11月上旬”のことを表していることになります。関連:旧暦の月(睦月、如月、弥生・・・)の意味と読み方、由来とは?関連:なぜ旧暦と新暦にずれが発生するのかを詳しく解説!2.長月の意味・由来・読み方についてでは長月の意味・由来・読み方について見ていきましょう。まず長月は旧暦における9月のことで、読み方は”長月(ながつき)”になります。そして長月の意味・由来としては諸説ありますが、夜がだんだんと長くなり始める月という意味の”夜長月”からきている説が有力です。この時期ぐらいになると日が昇っている時間が少しずつ短くなっていき、日が落ちる夜の時間が長くなるため、”夜長月(よながつき)”と呼ばれました。(旧暦における9月は、現在でいうと9月下旬~11月上旬ぐらい)よく聞く言葉に夏至と冬至がありますが、夏至(6月21日前後)は”最も夜が短くなる日”で、冬至(12月21日前後)は”最も夜が長くなる日”だとされています。なので夏至を過ぎて冬至に近づくにつれて少しずつ夜が長くなることを、昔の人もいまと同じように感じていたということです。そしてこの夜長月が略されて、旧暦の月である”長月”となったんですね。また他の説(有力な説ではない)としては、秋の月を見ることができる最後の月になることから、”名残月(なごりづき)”となってそれが転じたとされる説。この時期は雨が多く降る(秋雨のこと)季節だったことから、”長雨月(ながめつき)”が転じて”長月(ながつき)”になったとされる説があります。このように旧暦の月名の由来には様々な説があります。3.長月の別名とは何か?旧暦の月名である長月(ながつき)ですが、実は長月という名称以外にも別名がたくさんあります。いまだと9月のことは9月としか言わず別名はありませんが、昔は月名に生活や季節に関連する呼び方をしていました。そしてその月を表す名称もひとつやふたつではありません。では長月の別名には一体どういう名称のものがあるのかを見ていきましょう。晩秋(ばんしゅう)長月が別名で晩秋(ばんしゅう)と呼ばれるのは、秋の終わりの方という理由からです。晩秋の”晩”には”終わりの方”という意味があるため、晩秋というのは秋の終わりの方であることを意味しています。現在の季節では9月と言えば秋が始まったばかりなのですが、旧暦の季節では秋というのは7月・8月・9月なので終わりの方にあたります。ですので晩秋は秋(7月・8月・9月)の終わりの方を意味しているので、旧暦の9月である長月の別名として晩秋(ばんしゅう)と呼ばれています。菊月(きくづき)※菊(きく)の花の写真長月が別名で菊月(きくづき)と呼ばれるのは、菊の花が咲く月という理由からです。俳句の季語でも”菊”は秋に分類されて秋の花というイメージが強いですが、実は秋以外の季節でも菊の花の品種によって開花時期は異なります。菊の花はその品種によってはだいたい5月~1月の時期まで咲くため、秋だけでなく夏や冬の時期にも咲かせることができます。寝覚月(ねざめづき)長月が別名で寝覚月(ねざめづき)と呼ばれるのは、眠りから覚めることが多くなる月という理由からです。この時期は夜の時間が長くなるためそれに伴って、寝ていても夜に目が覚める回数が多くなるので”寝覚月(ねざめづき)”呼ばれています。他の長月の別名(箇条書き)”晩秋(ばんしゅう)”、”菊月(きくづき)”、”寝覚月(ねざめづき)”以外にも、長月の別名として呼ばれている名称について下に箇条書きにしてみました。<長月の別名の一覧>夜長月(よながつき)名残月(なごりづき)長雨月(ながめつき)色取月(いろどりづき)菊の秋(きくのあき)菊見月(きくみづき)竹酔月(ちくすいづき)紅葉月(もみじづき)祝月(いわいづき)詠月(えいげつ)季秋(きしゅう)季白(きはく)朽月(きゅうげつ)玄月(げんげつ) などなど※上記以外にも長月の別名は数多く存在しています。以上が「長月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?長月の別名は?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、長月(ながつき)とは、旧暦における9月のこと。長月と新暦の9月には季節にずれがあり、長月は現在の9月下旬~11月上旬のことになる。長月の由来は、夜がだんだんと長くなり始める月という意味の”夜長月”からきている。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒上旬と下旬と中旬の期間の違いとは?⇒新暦って何?旧暦との違いとは?⇒太陽暦とは?太陰暦と太陰太陽暦との違いって何?⇒ユリウス暦とは?グレゴリオ暦との違いって何?⇒紀元前とは?またBCとADの意味や表を分かりやすくまとめました!⇒今年と今年度の違いとは?年度の期間は目的によって異なるって本当?⇒和暦とは?西暦との違いは何か?⇒西暦とは何か?西暦はいつから使われた?西暦・和暦・干支の早見表!⇒うるう年(閏年)とは?4年に1度だけ366日になる仕組みを解説!⇒神無月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?神無月の別名は?
-
さてあなたは神無月とは何かをご存知でしょうか。いま現在では日本での暦は主に新暦が使われていますが、昔は新暦ではなく旧暦が使用されていました。神無月というのは日本での旧暦の時代における月(1月、2月・・・)の名称なのですが、現在ではほとんど使用されることがないので分からない人も多いでしょう。そこでこのページでは神無月とは何月のことを指しているのか?また神無月の意味・由来・読み方・別名について簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次神無月とは何月のことを指しているのか?神無月の意味・由来・読み方について神無月の別名とは何か?初冬(しょとう)神去月(かみさりづき)時雨月(しぐれづき)他の神無月の別名(箇条書き)まとめ1.神無月とは何月のことを指しているのか?では神無月とは何月のことを指しているのか見ていきましょう。神無月とは旧暦における月(1月、2月、3月・・・)の名称のことで、新暦(いま現在の暦)でいうところの”10月”のことを指しています。いまだと1年間が365日(うるう年だと366日)というのは一般的ですが、それはいま現在使用されているのが新暦だからです。(いま現在使用されている暦は、太陽暦のひとつであるグレゴリオ暦です)日本における旧暦では天保暦(太陰太陽暦のひとつ)が使用されていましたが、旧暦(天保暦)に従った場合は1年間が354日ということになります。そしてこの旧暦が使用されていたときの月の名称が”神無月”であり、暦が新暦に改暦された現在では神無月という名称から”10月”に変更されました。ですが神無月(旧暦の月)と10月(新暦の月)では季節にずれが発生していて、”だいたい1ヶ月~2ヶ月ほど”のずれがあるので注意が必要です。なので神無月の時期は旧暦と新暦における季節のずれを考慮すると、新暦(現在の暦)でいうところの”10月下旬~12月上旬”のことを表していることになります。関連:旧暦の月(睦月、如月、弥生・・・)の意味と読み方、由来とは?関連:なぜ旧暦と新暦にずれが発生するのかを詳しく解説!2.神無月の意味・由来・読み方についてでは神無月の意味・由来・読み方について見ていきましょう。まず神無月は旧暦における10月のことで、読み方は”神無月(かんなづき)”になります。そして神無月の意味・由来としては諸説ありますが、全国の神々が出雲大社に集まる”神の月”からきている説が有力です。旧暦の10月になると全国の八百万(やおよろず)の神様たちが、島根県にある出雲大社へと会議のために集まるものだと考えられていました。旧暦の6月である水無月と考え方は同じで”無”は”ない”ではなく”の”を意味するので、神無月に関しても”神のいない月”ではなく”神の月”という意味で捉えます。これにより旧暦の10月は全国から神様が集まる月ということから、”神無月(=神の月)”と呼ばれるようになったんですね。また他にも神無月の”無”をそのまま”ない(=存在しない)”という意味で捉えて、神様がいなくなった地域では旧暦の10月を”神無月(かみなしづき)”と呼んでいたり。反対に全国から神様が集まる地域(出雲)では、”神在月(かみありつき)”と呼ばれていたという説もあります。3.神無月の別名とは何か?旧暦の月名である神無月(かんなづき)ですが、実は神無月という名称以外にも別名がたくさんあります。いまだと10月のことは10月としか言わず別名はありませんが、昔は月名に生活や季節に関連する呼び方をしていました。そしてその月を表す名称もひとつやふたつではありません。では神無月の別名には一体どういう名称のものがあるのかを見ていきましょう。初冬(しょとう)神無月が別名で初冬(しょとう)と呼ばれるのは、その年で初めて冬が訪れる月という理由からです。現在の暦(新暦)における季節では冬は12月・1月・2月ですが、旧暦における季節では冬というのは10月・11月・12月になります。ですので神無月(旧暦の10月)というのはその年で初めて冬が訪れる月になるため、神無月の別名として初冬(しょとう)と呼ばれているんですね。神去月(かみさりづき)神無月が別名で神去月(かみさりづき)と呼ばれるのは、出雲に神が集まり各地で神が不在になるという理由からです。旧暦における10月(神無月)は島根県にある出雲大社に、全国の神様たちが集まるとされています。しかし出雲には神様は集まりますが他の地域では神様が去って不在となる月のため、神無月の別名として神去月(かみさりづき)と呼ばれています。時雨月(しぐれづき)神無月が別名で時雨月(しぐれづき)と呼ばれるのは、時雨が起こる月という理由からです。時雨(しぐれ)はだいたい秋から冬にかけて起こる雨のことで、一時的に降ったり止んだりする雨のことを言います。時雨は季語にも用いられることがありますが、そのときは秋ではなく”冬”の季語になるので注意が必要です。他の神無月の別名(箇条書き)”初冬(しょとう)”、”神去月(かみさりづき)”、”時雨月(しぐれづき)”以外にも、神無月の別名として呼ばれている名称について下に箇条書きにしてみました。<神無月の別名の一覧>神在月(かみありづき)←出雲地方での名称神有月(かみありづき)←出雲地方での名称孟冬(もうとう)鏡祭月(きょうさいげつ)小春(こはる)鎮祭月(ちんさいげつ)初霜月(はつしもづき)応章(おうしょう)開冬(かいとう)亥冬(がいとう)吉月(きつげつ)坤月(こんげつ)正陰月(せいいんづき)立冬(りっとう) などなど※上記以外にも神無月の別名は数多く存在しています。以上が「神無月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?神無月の別名は?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、神無月(かんなづき)とは、旧暦における10月のこと。神無月と新暦の10月には季節にずれがあり、神無月は現在の10月下旬~12月上旬のことになる。神無月の由来は、全国の神々が出雲大社に集まる”神の月”からきている。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒上旬と下旬と中旬の期間の違いとは?⇒新暦って何?旧暦との違いとは?⇒太陽暦とは?太陰暦と太陰太陽暦との違いって何?⇒ユリウス暦とは?グレゴリオ暦との違いって何?⇒紀元前とは?またBCとADの意味や表を分かりやすくまとめました!⇒今年と今年度の違いとは?年度の期間は目的によって異なるって本当?⇒和暦とは?西暦との違いは何か?⇒西暦とは何か?西暦はいつから使われた?西暦・和暦・干支の早見表!⇒うるう年(閏年)とは?4年に1度だけ366日になる仕組みを解説!⇒霜月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?霜月の別名は?
-
さてあなたは霜月とは何かをご存知でしょうか。いま現在では日本での暦は主に新暦が使われていますが、昔は新暦ではなく旧暦が使用されていました。霜月というのは日本での旧暦の時代における月(1月、2月・・・)の名称なのですが、現在ではほとんど使用されることがないので分からない人も多いでしょう。そこでこのページでは霜月とは何月のことを指しているのか?また霜月の意味・由来・読み方・別名について簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次霜月とは何月のことを指しているのか?霜月の意味・由来・読み方について霜月の別名とは何か?仲冬(ちゅうとう)神来月(かみきづき)雪待月(ゆきまちづき)他の霜月の別名(箇条書き)まとめ1.霜月とは何月のことを指しているのか?では霜月とは何月のことを指しているのか見ていきましょう。霜月とは旧暦における月(1月、2月、3月・・・)の名称のことで、新暦(いま現在の暦)でいうところの”11月”のことを指しています。いまだと1年間が365日(うるう年だと366日)というのは一般的ですが、それはいま現在使用されているのが新暦だからです。(いま現在使用されている暦は、太陽暦のひとつであるグレゴリオ暦です)日本における旧暦では天保暦(太陰太陽暦のひとつ)が使用されていましたが、旧暦(天保暦)に従った場合は1年間が354日ということになります。そしてこの旧暦が使用されていたときの月の名称が”霜月”であり、暦が新暦に改暦された現在では霜月という名称から”11月”に変更されました。ですが霜月(旧暦の月)と11月(新暦の月)では季節にずれが発生していて、”だいたい1ヶ月~2ヶ月ほど”のずれがあるので注意が必要です。なので霜月の時期は旧暦と新暦における季節のずれを考慮すると、新暦(現在の暦)でいうところの”11月下旬~1月上旬”のことを表していることになります。関連:旧暦の月(睦月、如月、弥生・・・)の意味と読み方、由来とは?関連:なぜ旧暦と新暦にずれが発生するのかを詳しく解説!2.霜月の意味・由来・読み方について※植物に霜(氷の結晶)が付いている写真では霜月の意味・由来・読み方について見ていきましょう。まず霜月は旧暦における11月のことで、読み方は”霜月(しもつき)”になります。そして霜月の意味・由来としては諸説ありますが、霜が降り始める月という意味の”霜降り月”からきている説が有力です。段々と寒くなり霜が降り始める月という意味の”霜降り月・霜降月(しもふりつき)”が、略されて旧暦の11月である”霜月”になったそうです。霜は秋の終わりごろから冬にかけて降り始めるものなので、植物などに霜が降り始めたら「そろそろ冬になるんだなあ」と思って良いでしょう。ちなみに現在の日本における初霜(はつしも)は場所によっても時期は異なりますが、北海道では10月中に降り始めて、東京などでは12月下旬頃になることも多いです。このように場所によって霜が降り始める時期というのは大きく異なります。3.霜月の別名とは何か?旧暦の月名である霜月(しもつき)ですが、実は霜月という名称以外にも別名がたくさんあります。いまだと11月のことは11月としか言わず別名はありませんが、昔は月名に生活や季節に関連する呼び方をしていました。そしてその月を表す名称もひとつやふたつではありません。では霜月の別名には一体どういう名称のものがあるのかを見ていきましょう。仲冬(ちゅうとう)霜月が別名で仲冬(ちゅうとう)と呼ばれるのは、冬の真ん中という理由からです。旧暦における季節では10月・11月・12月が冬となっており、仲冬の”仲”という字には”真ん中”という意味があります。ですので仲冬は冬(10月・11月・12月)の真ん中という意味になるため、旧暦の11月である霜月の別名として仲冬(ちゅうとう)と呼ばれています。挨拶などで”仲冬の候(ちゅうとうのこう)”と使用するときがありますが、だいたい12月初め~1月初めにかけて使われることが多いです。霜月は旧暦では11月のことを指していますが、現在の暦では11月下旬から1月上旬ぐらいの時期なのでだいたい合っていますよね。神来月(かみきづき)霜月が別名で神来月(かみきづき)と呼ばれるのは、出雲大社から神様が帰って来る月という理由からです。神来月(かみきづき)は他にも”神帰月(かみきづき)”という漢字でも表されます。(神来月よりも神帰月のほうが覚えやすいかもしれませんね)霜月前の月である神無月(旧暦における10月)では、島根県にある出雲大社に全国の神様が集まって会議が行われるとされています。そしてその会議が終わって神様たちが出雲体大社から各地へと帰って来る月であることから、霜月の別名として神来月または神帰月(かみきづき)と呼ばれています。雪待月(ゆきまちづき)霜月が別名で雪待月(ゆきまちづき)と呼ばれるのは、雪が降るのを待つ月という理由からです。冬ごもりの支度をして雪が降るのを待っている月ということから、霜月の別名として”雪待月(ゆきまちづき)”と呼ばれています。他の霜月の別名(箇条書き)”仲冬(ちゅうとう)”、”神来月(かみきづき)”、”雪待月(ゆきまちづき)”以外にも、霜月の別名として呼ばれている名称について下に箇条書きにしてみました。<霜月の別名の一覧>霜降月(しもふりづき)神楽月(かぐらづき)顔見月(かおみせづき)雪見月(ゆきみづき)竜潜月(りゅうせんづき)一陽来復(いちようらいふく)天正月(てんしょうづき)黄鐘(おうしょう)広寒(こうかん)朔易(さくえき)章月(しょうげつ)盛冬(せいとう)達月(たつげつ)風寒(ふうかん) などなど※上記以外にも霜月の別名は数多く存在しています。以上が「霜月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?霜月の別名は?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、霜月(しもつき)とは、旧暦における11月のこと。霜月と新暦の11月には季節にずれがあり、霜月は現在の11月下旬~1月上旬のことになる。霜月の由来は、霜が降り始める月という意味の”霜降り月”からきている。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒上旬と下旬と中旬の期間の違いとは?⇒新暦って何?旧暦との違いとは?⇒太陽暦とは?太陰暦と太陰太陽暦との違いって何?⇒ユリウス暦とは?グレゴリオ暦との違いって何?⇒紀元前とは?またBCとADの意味や表を分かりやすくまとめました!⇒今年と今年度の違いとは?年度の期間は目的によって異なるって本当?⇒和暦とは?西暦との違いは何か?⇒西暦とは何か?西暦はいつから使われた?西暦・和暦・干支の早見表!⇒うるう年(閏年)とは?4年に1度だけ366日になる仕組みを解説!⇒師走とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?師走の別名は?
-
さてあなたは師走とは何かをご存知でしょうか。いま現在では日本での暦は主に新暦が使われていますが、昔は新暦ではなく旧暦が使用されていました。師走というのは日本での旧暦の時代における月(1月、2月・・・)の名称なのですが、現在ではほとんど使用されることがないので分からない人も多いでしょう。そこでこのページでは師走とは何月のことを指しているのか?また師走の意味・由来・読み方・別名について簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次師走とは何月のことを指しているのか?師走の意味・由来・読み方について師走の別名とは何か?晩冬(ばんとう)梅初月(うめはつづき)雪月(ゆきづき)他の師走の別名(箇条書き)まとめ1.師走とは何月のことを指しているのか?では師走とは何月のことを指しているのか見ていきましょう。師走とは旧暦における月(1月、2月、3月・・・)の名称のことで、新暦(いま現在の暦)でいうところの”12月”のことを指しています。いまだと1年間が365日(うるう年だと366日)というのは一般的ですが、それはいま現在使用されているのが新暦だからです。(いま現在使用されている暦は、太陽暦のひとつであるグレゴリオ暦です)日本における旧暦では天保暦(太陰太陽暦のひとつ)が使用されていましたが、旧暦(天保暦)に従った場合は1年間が354日ということになります。そしてこの旧暦が使用されていたときの月の名称が”師走”であり、暦が新暦に改暦された現在では葉月という名称から”12月”に変更されました。ですが師走(旧暦の月)と12月(新暦の月)では季節にずれが発生していて、”だいたい1ヶ月~2ヶ月ほど”のずれがあるので注意が必要です。なので師走の時期は旧暦と新暦における季節のずれを考慮すると、新暦(現在の暦)でいうところの”12月下旬~2月上旬”のことを表していることになります。関連:旧暦の月(睦月、如月、弥生・・・)の意味と読み方、由来とは?関連:なぜ旧暦と新暦にずれが発生するのかを詳しく解説!2.師走の意味・由来・読み方についてでは師走の意味・由来・読み方について見ていきましょう。まず師走は旧暦における12月のことで、読み方は”師走(しわす)”になります。そして師走の意味・由来としては諸説ありますが、僧(お坊さん)がお経を唱えるため、各地を忙しく走り回ることからきている説が有力です。師走の”師”というのは師匠のことを意味しているのではなく、僧(お坊さん)のことを意味しており、僧などを敬っていう場合の言い方になります。(他にも師は教師のことを表して、学校の先生も忙しく走り回る月という説もあります)昔から年末にはお坊さん(僧)に自分の家まで来てもらい、お経を唱えてもらうというような風習がありました。いまではこのような風習はあまり残っていませんが、それだけ昔は年末になるとお坊さんにとってとても忙しい時期だったのですね。ちなみに”師走(しわす)”という読み方は当て字で、普通に読むと師走をしわすとは読むことはできません。いまでこそ師走と言えばしわすと読むのが常識となっていますが、師走(しわす)については当て字だということを覚えておきましょう。3.師走の別名とは何か?旧暦の月名である師走(しわす)ですが、実は師走という名称以外にも別名がたくさんあります。いまだと12月のことは12月としか言わず別名はありませんが、昔は月名に生活や季節に関連する呼び方をしていました。そしてその月を表す名称もひとつやふたつではありません。では師走の別名には一体どういう名称のものがあるのかを見ていきましょう。晩冬(ばんとう)師走が別名で晩冬(ばんとう)と呼ばれるのは、冬の終わりの方という理由からです。晩冬の”晩”には”終わりの方”という意味があるため、晩冬というのは冬の終わりの方であることを意味しています。現在の季節では12月と言えば冬が始まったばかりなのですが、旧暦の季節では冬というのは10月・11月・12月なので終わりの方にあたります。ですので晩冬は冬(10月・11月・12月)の終わりの方を意味しているので、旧暦の12月である師走の別名として晩冬(ばんとう)と呼ばれています。梅初月(うめはつづき)師走が別名で梅初月(うめはつづき)と呼ばれるのは、梅の花が咲き始めるころの月という理由からです梅の花の開花時期は他の花と比べてもかなり早く、梅の花はだいたい2月~3月にかけて咲きます。しかし季節が冬でも梅の品種によっては、早咲きの品種で12月下旬~1月に開花するものもあります。雪月(ゆきづき)師走が別名で雪月(ゆきづき)と呼ばれるのは、雪が降る月という理由からです旧暦における12月は現在の暦での12月下旬~2月上旬にあたるので、雪が降る地域ではすでに雪が積もり始めている時期です。地域によっては雪がほとんど降らないところもありますが、冬と言えば雪なので師走の別名として”雪月(ゆきづき)”と呼ばれています。他の師走の別名(箇条書き)”晩冬(ばんとう)”、”梅初月(うめはつづき)”、”雪月(ゆきづき)”以外にも、師走の別名として呼ばれている名称について下に箇条書きにしてみました。<師走の別名の一覧>乙子月(おとごづき)弟子月(おとごづき)親子月(おやこづき)年積月(としつむづき)果ての月(はてのつき)春待月(はるまちづき)黄冬(おうとう)季冬(きとう)窮陰(きゅういん)窮月(きゅうげつ)窮冬(きゅうとう)厳冬(げんげつ)除月(じょげつ)暮歳(ぼさい) などなど※上記以外にも師走の別名は数多く存在しています。以上が「師走とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?師走の別名は?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、師走(しわす)とは、旧暦における12月のこと。師走と新暦の12月には季節にずれがあり、師走は現在の12月下旬~2月上旬のことになる。師走の由来は、僧(お坊さん)がお経を唱えるために各地を忙しく走り回ることからきている。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒上旬と下旬と中旬の期間の違いとは?⇒新暦って何?旧暦との違いとは?⇒太陽暦とは?太陰暦と太陰太陽暦との違いって何?⇒ユリウス暦とは?グレゴリオ暦との違いって何?⇒紀元前とは?またBCとADの意味や表を分かりやすくまとめました!⇒今年と今年度の違いとは?年度の期間は目的によって異なるって本当?⇒和暦とは?西暦との違いは何か?⇒西暦とは何か?西暦はいつから使われた?西暦・和暦・干支の早見表!⇒うるう年(閏年)とは?4年に1度だけ366日になる仕組みを解説!⇒睦月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?睦月の別名は?