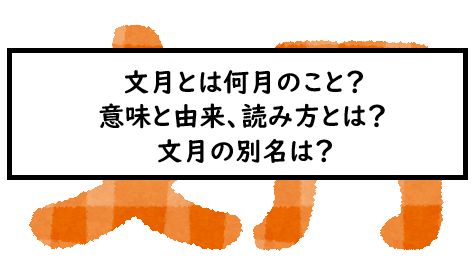
このページでは文月とは何月のことを指しているのか?。また文月の意味・由来・読み方・別名について簡単に解説しています。
目次
1.文月とは何月のことを指しているのか?

文月とは旧暦における月(1月、2月、3月・・・)の名称のことで、
新暦(いま現在の暦)でいうところの”7月”のことを指しています。
いまだと1年間が365日(うるう年だと366日)というのは一般的ですが、
それはいま現在使用されているのが新暦だからです。
(いま現在使用されている暦は、太陽暦のひとつであるグレゴリオ暦です)
日本における旧暦では天保暦(太陰太陽暦のひとつ)が使用されていましたが、
旧暦(天保暦)に従った場合は1年間が354日ということになります。

そしてこの旧暦が使用されていたときの月の名称が”文月”であり、
暦が新暦に改暦された現在では文月という名称から”7月”に変更されました。
ですが文月(旧暦の月)と7月(新暦の月)では季節にずれが発生していて、
”だいたい1ヶ月~2ヶ月ほど”のずれがあるので注意が必要です。
なので文月の時期は旧暦と新暦における季節のずれを考慮すると、
新暦(現在の暦)でいうところの”7月下旬~9月上旬”のことを表していることになります。
2.文月の意味・由来・読み方について

まず文月は旧暦における7月のことで、読み方は”文月(ふみづき)”になります。
そして文月の意味・由来としては諸説ありますが、
七夕のとき短冊に歌や字(文)を書いていたことからきている説が有力です。
いまでは七夕になると短冊に願い事を書くというのが一般的ですが、
昔は願い事ではなく歌や字(文)を書いて、書道の上達を祈っていたそうです。
そのような七夕の風習に因(ちな)んで、旧暦の7月は”文披月(ふみひらきづき)”と呼ばれるようになりました。
(文披月の読み方については”ふみひろげづき”でも問題ありません)
”披(ひら)くは閉じてあるものを開ける”という意味があることから、
”文(ふみ)を広げて晒(さら)す月”という意味で”文披月(ふみひらきづき)”です。
その文披月がのちに旧暦の月である”文月(ふみづき)”になったとされています。
また他の説(有力な説ではない)としては、この時期に稲穂が膨らむ月であることから、
”穂含月(ほふみづき)”や”含月(ふくみづき)”となり、それが転じて文月になったとされる説。
稲穂の膨らみを見る月であることから”穂見月(ほみづき)”となり、それが転じたという説があります。
このように旧暦の月名の由来には様々な説があります。
3.文月の別名とは何か?
旧暦の月名である文月(ふみづき)ですが、実は文月という名称以外にも別名がたくさんあります。
いまだと7月のことは7月としか言わず別名はありませんが、
昔は月名に生活や季節に関連する呼び方をしていました。
そしてその月を表す名称もひとつやふたつではありません。
では文月の別名には一体どういう名称のものがあるのかを見ていきましょう。
秋初月(あきはづき)
文月が別名で秋初月(あきはづき)と呼ばれるのは、その年で秋が初めて訪れる月という理由からです。
秋初月(あきはづき)は他にも、”あきそめづき”や”あきそめつき”と呼ばれています。
いま現在の季節だと秋は9月・10月・11月になりますが、
旧暦における季節は7月・8月・9月が秋ということになっています。
ですので秋初月は秋(7月・8月・9月)が初めて訪れる月のことを意味しているので、
旧暦の7月である文月の別名として秋初月(あきはづき)と呼ばれています。
初秋(しょしゅう)
文月が別名で初秋(しょしゅう)と呼ばれるのは、その年で初めて秋が訪れる月という理由からです。
これも秋初月のときと同様の理由から名称が付けられており、
旧暦における季節は7月・8月・9月が秋だったことから文月の別名になっています。
ですので初秋は秋(7月・8月・9月)が初めて訪れる月のことを意味しているので、
旧暦の7月である文月の別名として初秋(しょしゅう)と呼ばれています。
七夕月(たなばたづき)
文月が別名で七夕月(たなばたづき)と呼ばれるのは、七夕の行事を行う月という理由からです。
この七夕月については名称がそのままなので分かりやすいですが、
文月(旧暦における7月)に短冊に歌や字(文)を書くという行事を行っていました。
これがそのまま文月の別名として、”七夕月(たなばたづき)”と呼ばれていたそうです。
他の文月の別名(箇条書き)
”秋初月(あきはづき)”、”初秋(しょしゅう)”、”七夕月(たなばたづき)”以外にも、
文月の別名として呼ばれている名称について下に箇条書きにしてみました。
<文月の別名の一覧>
- 文披月(ふみひらきづき)
- 七夜月(ななよづき)
- 孟秋(もうしゅう)
- 女郎花月(おみなえしづき)
- 愛逢月(めであいづき)
- 夷則(いそく)
- 瓜時(かじ)
- 上秋(じょうしゅう)
- 処暑(しょしょ)
- 親月(しんげつ)
- 新秋(しんしゅう)
- 相月(そうげつ)
- 否月(ひげつ)
- 涼月(りょうげつ) などなど
※上記以外にも文月の別名は数多く存在しています。
以上が「文月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?文月の別名は?」でした。
4.まとめ
これまで説明したことをまとめますと、
- 文月(ふみづき)とは、旧暦における7月のこと。
- 文月と新暦の7月には季節にずれがあり、文月は現在の7月下旬~9月上旬のことになる。
- 文月の由来は、七夕のとき短冊に歌や字(文)を書いていたことからきている。
関連ページ
<覚えておきたい知識>
鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など
哀悼、重複、出生、集荷など
(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど
(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど
(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など
≪名前は知っているけどわからないもの≫
(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど
(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など
(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど
<豆知識>
(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など
