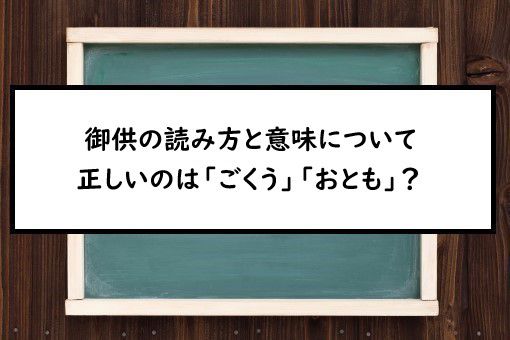1.御供の正しい読み方は「ごくう」「おとも」?
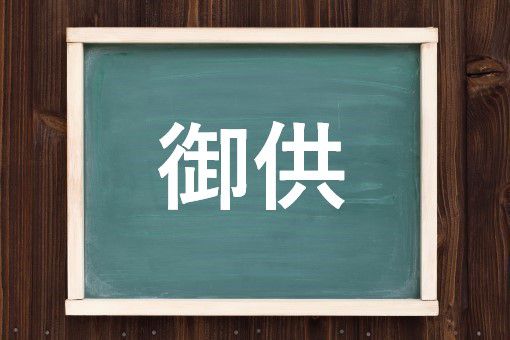
結論から言ってしまうと、御供の正しい読み方は「ごくう」「おとも」「ごく」になります。
御供の”御”は「ご」「お」「み」「ぎょ」、”供”は「そな(える)」「とも」「きょう」「く」と読むことができます。
ただ御供は「ごくう」「おとも」「ごく」のどれで読むかによって、意味が異なるので注意が必要です。
(次の章でそれぞれの意味について解説していきます)
また御供の”供”という字は単体で「くう」と読むことはできませんが、
日本語における音変化によって「ごく」から「ごくう」という読み方に変化しました。
簡単に言うと、”発音しにくい音を発音しやすい音に変化させたもの”です。
この音変化により、通常では読むことができない「ごくう」という読み方になったんですね。
次の章で御供の意味について解説していきます。
2.御供の意味について

御供(ごくう、ごく)は「神仏へ供(そな)えるもの」の意味として用いられています。
御供を「ごくう」「ごく」と読むと上記のような意味になりますが、「おとも」と読むと「目上の人などに付き従って行くこと。また、その人のこと/料理屋などで、客が帰るときに呼ぶ車のこと」の意味となります。
このように御供は「ごくう」「おとも」「ごく」のどれで読むかによって、意味が異なるので覚えておきましょう。
御供を用いた例文としては、「危うく会社の人身御供(ひとみごくう)にされるところだった」や、「彼に御供(おとも)する人」のような使い方で用いられています。
前者の例文は「神仏へ供えるもの」の意味で、後者の例文は「目上の人などに付き従って行くこと」の意味で使用しています。
以上が「御供の読み方と意味、”ごくう”と”おとも”正しいのは?」でした。
3.まとめ
これまで説明したことをまとめますと、
- 御供の正しい読み方は「ごくう」「おとも」「ごく」。
- 御供(ごくう、ごく)は「神仏へ供えるもの」の意味。
- 御供(おとも)は「目上の人などに付き従って行くこと。また、その人のこと/料理屋などで、客が帰るときに呼ぶ車のこと」の意味。
関連ページ
<難読漢字の一覧>
(写真あり)藜、櫛、羆など
(写真あり)竜髭菜、青梗菜、蕗など
(写真あり)岩魚、栄螺、鱧など
(写真あり)海驢、犀、猫鼬など
(写真あり)花鶏、信天翁、杜鵑など
(写真あり)薊、金木犀、百合など
(写真あり)水黽、蟋蟀、蟷螂など
(写真あり)外郎、皮蛋、雲呑など
(写真あり)行灯、暖簾、轆轤など
<読み間違えやすい漢字の一覧>
哀悼、重複、出生、集荷など
依存、過不足、続柄など
<難読漢字の一覧(偏)>
(写真あり)鯆、鰍、鰉など
(写真あり)蝗、蠍、蝮など
(写真あり)梲、栂、樅など
(写真あり)鎹、鍬、釦など
<覚えておきたい知識>
鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など
(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど