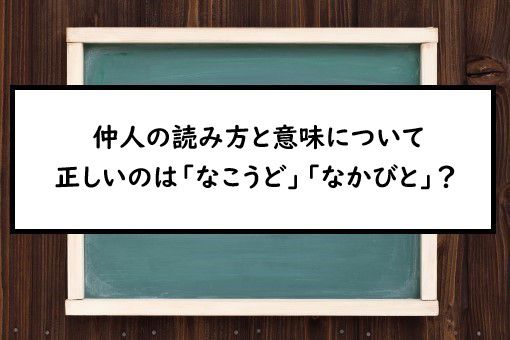1.仲人の正しい読み方は「なこうど」「なかびと」?
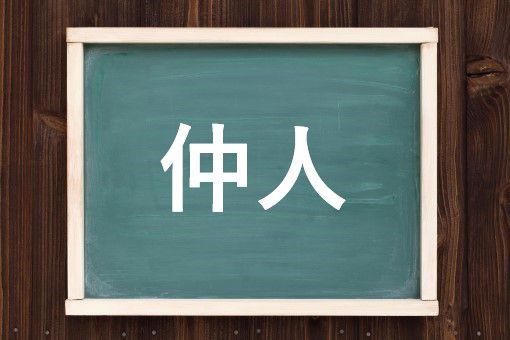
結論から言ってしまうと、仲人の正しい読み方は「なこうど」「なかびと」「なかうど」「ちゅうにん」になります。
仲人の”仲”は「なか」「ちゅう」、”人”は「ひと」「じん」「にん」(連濁により「びと」)と読むことができます。
一般的には仲人は「なこうど」と読むことがほとんどです。
ただ仲人は「なこうど」「なかびと」「なかうど」「ちゅうにん」のどれで読むかによって、意味が少し異なるので注意が必要です。
(次の章でそれぞれの意味について解説していきます)
また仲人の”人”の読み方は連濁により「びと」と読むことはできますが、
もともとそれ単体では”仲”は「なこ」、”人”も「うど」という読み方をすることはできません。
仲人のように「なかびと」ではなく、「なかうど」「なこうど」と変化して読むのは、日本語の音便(おんびん)のひとつである”ウ音便”と呼ばれているものです。
(音便とは、”発音しやすくするために、言い方を変えること”です)
ウ音便とは、”語中・語尾の「く」「ぐ」「ひ」「び」「み」などの音が、「う」の音に変化する現象のこと”を言います。
・仲人(なかびと) → 仲人(なかうど) → 仲人(なこうど)
仲人であれば上記のように、「び」の音が「う」の音に変化して、そこからさらに発音しやすいように変化して「なこうど」と読まれるようになりました。
例えば、ウ音便には他にも「玄人(くろうと)」や「若人(わこうど)」などがあります。
・ 玄人(くろひと) → 玄人(くろうと)
(”玄”という字は「くろ」と読むことができます)
・ 若人(わかびと) → 若人(わかうど) → 若人(わこうど)
玄人(くろうと)のように単純に「う」の音に変化するものだけでなく、
仲人(なこうど)や若人(わこうど)のように「う」の音に変化した後に、さらに発音しやすいように変化するものもあるため注意してください。
次の章で仲人の意味について解説していきます。
2.仲人の意味について

仲人(なこうど、なかびと、なかうど)は「仲立ちをする人。特に、結婚の仲立ちを務める人のこと」の意味として用いられています。
仲立ち(なかだち)というのは、”両者の間に立って関係がうまく行くように引き合わせたり、世話をしたりすること”です。
仲人を「なこうど」「なかびと」「なかうど」と読むと上記のような意味になりますが、「ちゅうにん」と読むと上記の他に、「対立している両者の間に入って仲裁する人」の意味も含まれます。
このように仲人は「なこうど」「なかびと」「なかうど」「ちゅうにん」のどれで読むかによって、意味が少し異なるので覚えておきましょう。
仲人を用いた例文としては、「縁談は彼が仲人を務めてくれたおかげでまとまった」や、「仲人として両社の間を取り持つ」のような使い方で用いられています。
どちらの例文も「仲立ちをする人のこと」の意味で使用しています。
以上が「仲人の読み方と意味、”なこうど”と”なかびと”正しいのは?」でした。
3.まとめ
これまで説明したことをまとめますと、
- 仲人の正しい読み方は「なこうど」「なかびと」「なかうど」「ちゅうにん」。
- 仲人(なこうど、なかびと、なかうど)は「仲立ちをする人。特に、結婚の仲立ちを務める人のこと」の意味。
- 仲人(ちゅうにん)は「仲立ちをする人。特に、結婚の仲立ちを務める人のこと/対立している両者の間に入って仲裁する人」の意味。
関連ページ
<難読漢字の一覧>
(写真あり)藜、櫛、羆など
(写真あり)竜髭菜、青梗菜、蕗など
(写真あり)岩魚、栄螺、鱧など
(写真あり)海驢、犀、猫鼬など
(写真あり)花鶏、信天翁、杜鵑など
(写真あり)薊、金木犀、百合など
(写真あり)水黽、蟋蟀、蟷螂など
(写真あり)外郎、皮蛋、雲呑など
(写真あり)行灯、暖簾、轆轤など
<読み間違えやすい漢字の一覧>
哀悼、重複、出生、集荷など
依存、過不足、続柄など
<難読漢字の一覧(偏)>
(写真あり)鯆、鰍、鰉など
(写真あり)蝗、蠍、蝮など
(写真あり)梲、栂、樅など
(写真あり)鎹、鍬、釦など
<覚えておきたい知識>
鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など
(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど