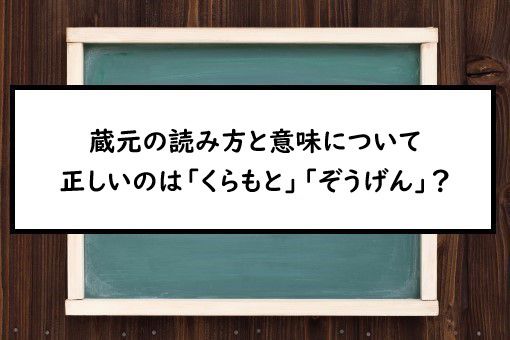1.蔵元の正しい読み方は「くらもと」「ぞうげん」?
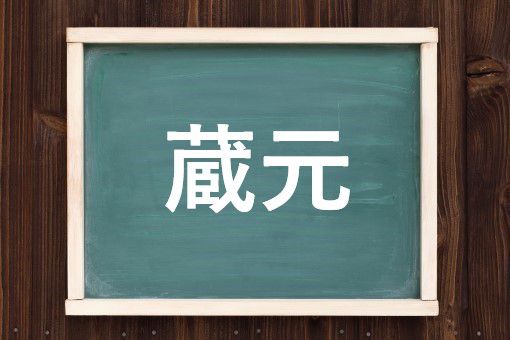
結論から言ってしまうと、蔵元の正しい読み方は「くらもと」になります。
蔵元の”蔵”は「くら」「ぞう」と読むことができますが、蔵元は「くらもと」と読むのが正しく、「ぞうげん」と読むのは間違いです。
次の章で蔵元の意味について解説していきます。
2.蔵元の意味について

※軒先(のきさき)につるされた杉玉(すぎだま)の写真
蔵元は「酒・醤油(しょうゆ)・味噌(みそ)などの醸造元のこと/江戸時代、蔵屋敷で蔵物(くらもの)の出納(すいとう)を担当した商人のこと」の意味として用いられています。
ちなみに日本酒の酒屋・酒蔵の軒先に杉玉(すぎだま)が飾られていることがありますが、これは杉玉を飾ることで”新酒が出来たこと”を知らせています。
(杉玉とは、杉の葉を集めてボール状にしたもの)
杉玉はだいたい2~3月ころに飾られ始め、最初は緑色をしていて、薄い緑色、枯れた茶色と杉玉の色が次第に変化していきます。
以上が「蔵元の読み方と意味、”くらもと”と”ぞうげん”正しいのは?」でした。
3.まとめ
これまで説明したことをまとめますと、
- 蔵元の正しい読み方は「くらもと」で、「ぞうげん」は間違い。
- 蔵元は「酒・醤油・味噌などの醸造元のこと/江戸時代、蔵屋敷で蔵物の出納を担当した商人のこと」の意味。
関連ページ
<難読漢字の一覧>
(写真あり)藜、櫛、羆など
(写真あり)竜髭菜、青梗菜、蕗など
(写真あり)岩魚、栄螺、鱧など
(写真あり)海驢、犀、猫鼬など
(写真あり)花鶏、信天翁、杜鵑など
(写真あり)薊、金木犀、百合など
(写真あり)水黽、蟋蟀、蟷螂など
(写真あり)外郎、皮蛋、雲呑など
(写真あり)行灯、暖簾、轆轤など
<読み間違えやすい漢字の一覧>
哀悼、重複、出生、集荷など
依存、過不足、続柄など
<難読漢字の一覧(偏)>
(写真あり)鯆、鰍、鰉など
(写真あり)蝗、蠍、蝮など
(写真あり)梲、栂、樅など
(写真あり)鎹、鍬、釦など
<覚えておきたい知識>
鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など
(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど