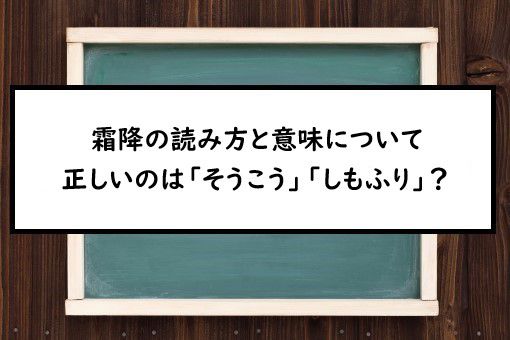1.霜降の正しい読み方は「そうこう」「しもふり」?
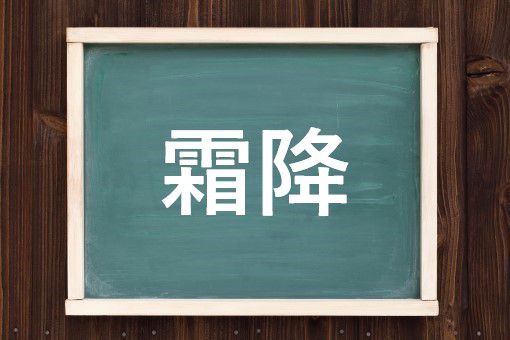
結論から言ってしまうと、霜降の正しい読み方は「そうこう」「しもふり」の両方になります。
霜降の”霜”は「しも」「そう」、”降”は「ふ(る)」「ふ(り)」「お(りる)」「こう」と読むことができます。
一般的には霜降は「そうこう」と読むことが多く、「しもふり」は”霜降り”と送り仮名がある場合が多いです。
ただ霜降は「そうこう」「しもふり」のどちらで読むかによって、意味が異なるので注意が必要です。
次の章で霜降の意味について解説していきます。
2.霜降の意味について

霜降(そうこう)は「二十四節気のひとつ」の意味として用いられています。
霜降(そうこう)は、”現在の暦(太陽暦)の10月23日頃のこと”で、この頃に霜が降り始めるとされています。
霜降を「そうこう」と読むと上記のような意味になりますが、「しもふり」と読むと下記のような意味となります。
- 霜が降りること
- 霜の降りたように、白い斑点が散らばっている文様のこと
- 牛肉の赤身に白い脂が混じっている状態のこと
- 魚肉や鶏肉などを、さっと熱湯にくぐらせたり焼いたりしてから冷水にさらし、表面を白くする調理法のこと
このように霜降は「そうこう」「しもふり」のどちらで読むかによって、意味が異なるので覚えておきましょう。
以上が「霜降の読み方と意味、”そうこう”と”しもふり”正しいのは?」でした。
3.まとめ
これまで説明したことをまとめますと、
- 霜降の正しい読み方は「そうこう」「しもふり」の両方。
- 霜降(そうこう)は「二十四節気のひとつ」の意味。
<霜降(しもふり)の意味>
- 霜が降りること
- 霜の降りたように、白い斑点が散らばっている文様のこと
- 牛肉の赤身に白い脂が混じっている状態のこと
- 魚肉や鶏肉などを、さっと熱湯にくぐらせたり焼いたりしてから冷水にさらし、表面を白くする調理法のこと
関連ページ
<難読漢字の一覧>
(写真あり)藜、櫛、羆など
(写真あり)竜髭菜、青梗菜、蕗など
(写真あり)岩魚、栄螺、鱧など
(写真あり)海驢、犀、猫鼬など
(写真あり)花鶏、信天翁、杜鵑など
(写真あり)薊、金木犀、百合など
(写真あり)水黽、蟋蟀、蟷螂など
(写真あり)外郎、皮蛋、雲呑など
(写真あり)行灯、暖簾、轆轤など
<読み間違えやすい漢字の一覧>
哀悼、重複、出生、集荷など
依存、過不足、続柄など
<難読漢字の一覧(偏)>
(写真あり)鯆、鰍、鰉など
(写真あり)蝗、蠍、蝮など
(写真あり)梲、栂、樅など
(写真あり)鎹、鍬、釦など
<覚えておきたい知識>
鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など
(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど