1.仏桑花の正しい読み方は「ぶっそうげ」「ぶっそうか」?
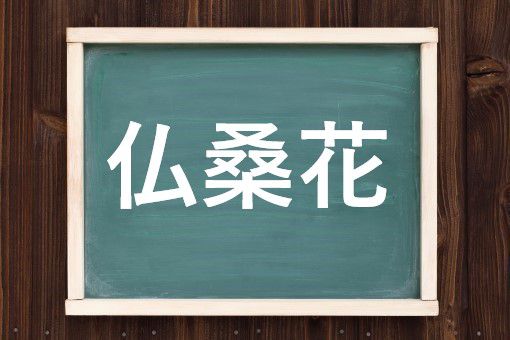
結論から言ってしまうと、仏桑花の正しい読み方は「ぶっそうげ」になります。
仏桑花の”仏”は「ほとけ」「ぶつ」、”桑”は「くわ」「そう」、”花”は「はな」「か」「け」と読むことができますが、仏桑花を「ぶっそうか」と読むのは間違いです。
また仏桑花を「ぶっそうげ」と読むのは、日本語の”促音化(そくおんか)+連濁(れんだく)”によるものです。
仏桑の”仏”の読み方は「ぶつ」と読むことはできますが、
もともとそれ単体では「ぶっ」という読み方をすることはできません。
仏桑のように「ぶつそう」ではなく、「ぶっそう」と変化して読むのは、日本語の「促音化(そくおんか)」と呼ばれているものです。
促音化とは、”2つの語が結びついて1つの語になるときに、発音しやすくするために、後ろの語(カ行・サ行・タ行・パ行)の前に付いた音が「っ」(これを促音という)に変化する現象のこと”を言います。
仏桑であれば、仏(ぶつ)+桑(そう)なので、桑(後ろの語)の前に付いた音である”つ”が促音の”っ”に変化します。
そして”花”の読み方は「け」と読むことはできますが、
もともとそれ単体では「げ」という読み方をすることはできません。
仏桑花のように「ぶっそうけ」ではなく、「ぶっそうげ」と濁って読むのは、日本語の「連濁(れんだく)」と呼ばれているものです。
連濁とは、”2つの語が結びついて1つの語になるときに、発音しやすくするために、後ろの語の語頭が清音から濁音に変化する現象のこと”を言います。
仏桑花であれば、仏桑(ぶっそう)+花(け)なので、花(後ろの語)の語頭である清音の”け”が濁音の”げ”に変化します。
このように日本語の”促音化+連濁”によって仏桑花を「ぶっそうげ」と読んでいます。
次の章で仏桑花の意味について解説していきます。
2.仏桑花の意味について

仏桑花は「アオイ科フヨウ属の常緑低木のこと」の意味として用いられています。
夏から秋頃に、長い柄を持つ赤い大きな5弁花を咲かせ、花の中心から筒状に合体した雄蕊(おしべ)と雌蕊(めしべ)が突き出しています。
また仏桑花(ぶっそうげ)は「ハイビスカス」と呼ばれることもありますが、フヨウ属の学名・英名が”Hibiscus(ハイビスカス)”なので、ハイビスカスという名称はフヨウ属の植物の総称として使われることも多いです。
ですので仏桑花(ぶっそうげ)の類似のフヨウ属植物を指す場合にも使われるため、”仏桑花=ハイビスカスというわけではない”ので覚えておきましょう。
以上が「仏桑花の読み方と意味、”ぶっそうげ”と”ぶっそうか”正しいのは?」でした。
3.まとめ
これまで説明したことをまとめますと、
- 仏桑花の正しい読み方は「ぶっそうげ」で、「ぶっそうか」は間違い。
- 仏桑花は「アオイ科フヨウ属の常緑低木のこと」の意味。
関連ページ
<難読漢字の一覧>
(写真あり)藜、櫛、羆など
(写真あり)竜髭菜、青梗菜、蕗など
(写真あり)岩魚、栄螺、鱧など
(写真あり)海驢、犀、猫鼬など
(写真あり)花鶏、信天翁、杜鵑など
(写真あり)薊、金木犀、百合など
(写真あり)水黽、蟋蟀、蟷螂など
(写真あり)外郎、皮蛋、雲呑など
(写真あり)行灯、暖簾、轆轤など
<読み間違えやすい漢字の一覧>
哀悼、重複、出生、集荷など
依存、過不足、続柄など
<難読漢字の一覧(偏)>
(写真あり)鯆、鰍、鰉など
(写真あり)蝗、蠍、蝮など
(写真あり)梲、栂、樅など
(写真あり)鎹、鍬、釦など
<覚えておきたい知識>
鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など
(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

