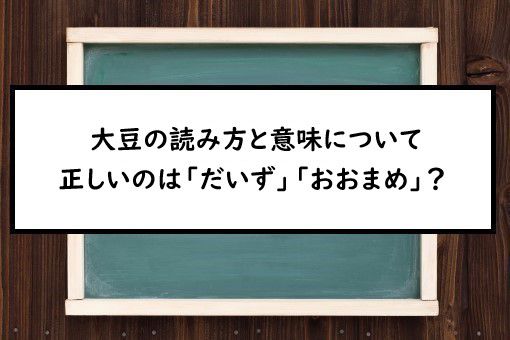1.大豆の正しい読み方は「だいず」「おおまめ」?
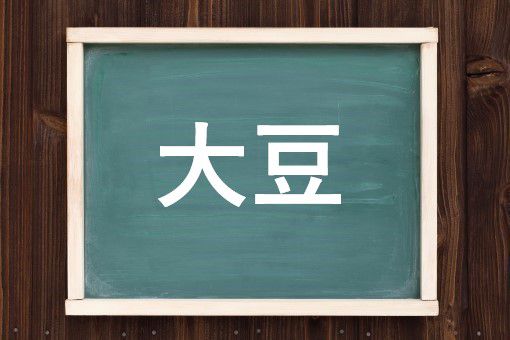
結論から言ってしまうと、大豆の正しい読み方は「だいず」「おおまめ」の両方になります。
大豆の”大”は「おお(きい)」「だい」、”豆”は「まめ」「ず」と読むことができます。
ただ一般的には大豆は「だいず」と読むことがほとんどです。
次の章で大豆の意味について解説していきます。
2.大豆の意味について

大豆は「マメ科の一年草のこと」の意味として用いられています。
「おおまめ」というのは、「だいず」の別名になります。
.jpg)
夏頃に、白色または紫紅色の花を咲かせ、種子は食用で、豆腐・味噌・醤油(しょうゆ)・納豆・きな粉などの原料として用いられます。
ちなみに枝豆(えだまめ)と大豆は収穫時期が違うだけで、もともと同じ植物の種子になります。
未成熟の時期に収穫された緑色の若いものを”枝豆”、
成熟するまで待って茶色く乾燥したものを”大豆”と呼んでいます。
.jpg)
上の写真は枝豆(未成熟)の状態から、さらに成熟するまで待った状態のものです。
この成熟した豆を乾燥させたものが、私たちが普段から目にしている大豆で、大豆を煎(い)って挽(ひ)いて粉にしたものを”黄粉(きなこ)”と言います。
以上が「大豆の読み方と意味、”だいず”と”おおまめ”正しいのは?」でした。
3.まとめ
これまで説明したことをまとめますと、
- 大豆の正しい読み方は「だいず」「おおまめ」の両方。
- 大豆は「マメ科の一年草のこと」の意味。
関連ページ
<難読漢字の一覧>
(写真あり)藜、櫛、羆など
(写真あり)竜髭菜、青梗菜、蕗など
(写真あり)岩魚、栄螺、鱧など
(写真あり)海驢、犀、猫鼬など
(写真あり)花鶏、信天翁、杜鵑など
(写真あり)薊、金木犀、百合など
(写真あり)水黽、蟋蟀、蟷螂など
(写真あり)外郎、皮蛋、雲呑など
(写真あり)行灯、暖簾、轆轤など
<読み間違えやすい漢字の一覧>
哀悼、重複、出生、集荷など
依存、過不足、続柄など
<難読漢字の一覧(偏)>
(写真あり)鯆、鰍、鰉など
(写真あり)蝗、蠍、蝮など
(写真あり)梲、栂、樅など
(写真あり)鎹、鍬、釦など
<覚えておきたい知識>
鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など
(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど