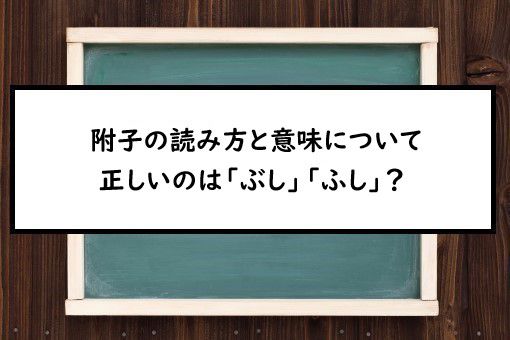1.附子の正しい読み方は「ぶし」「ふし」?

結論から言ってしまうと、附子の正しい読み方は「ぶし」「ふし」「ぶす」になります。
附子の”附”は「ぶ」「ふ」、”子”は「こ」「し」「す」読むことができます。
ただ附子は「ぶし」「ふし」「ぶす」のどれで読むかによって、意味が異なるので注意が必要です。
次の章で附子の意味について解説していきます。
2.附子の意味について

※上は鳥兜(トリカブト)の写真
附子(ぶし)は「鳥兜(トリカブト)の塊根(かいこん)のこと/子根(しこん)をとって乾かした生薬のこと」の意味として用いられています。
トリカブトは全体に毒がありますが、特に根の部分に強い毒性があるとされ、アコニチンなどの毒が含まれています。
附子を「ぶし」と読むと上記のような意味になりますが、
「ふし」「ぶす」と読むとそれぞれ下記のような意味となります。
附子は「ふし」と読むと「白膠木(ぬるで)の葉に五倍子虫(ふしむし)によって生じる瘤(こぶ)のこと」の意味、「ぶす」と読むと「鳥兜の塊根/狂言の曲目のひとつ」の意味になります。
五倍子虫(ふしむし)というのは、”アブラムシ科の昆虫の一種のこと”です。
五倍子虫は白膠木に寄生して葉に虫瘤(むしこぶ)を生じさせ、
虫瘤にはタンニンが多く含まれ、薬用・染料用として使われ、古くにはお歯黒に用いられていました。
このように附子は「ぶし」「ふし」「ぶす」のどれで読むかによって、意味が異なるので覚えておきましょう。
以上が「附子の読み方と意味、”ぶし”と”ふし”正しいのは?」でした。
3.まとめ
これまで説明したことをまとめますと、
- 附子の正しい読み方は「ぶし」「ふし」「ぶす」のすべて。
- 附子(ぶし)は「鳥兜の塊根のこと/子根をとって乾かした生薬のこと」の意味。
- 附子(ふし)は「白膠木の葉に五倍子虫によって生じる瘤のこと」の意味。
- 附子(ぶす)は「鳥兜の塊根のこと/狂言の曲目のひとつ」の意味。
関連ページ
<難読漢字の一覧>
(写真あり)藜、櫛、羆など
(写真あり)竜髭菜、青梗菜、蕗など
(写真あり)岩魚、栄螺、鱧など
(写真あり)海驢、犀、猫鼬など
(写真あり)花鶏、信天翁、杜鵑など
(写真あり)薊、金木犀、百合など
(写真あり)水黽、蟋蟀、蟷螂など
(写真あり)外郎、皮蛋、雲呑など
(写真あり)行灯、暖簾、轆轤など
<読み間違えやすい漢字の一覧>
哀悼、重複、出生、集荷など
依存、過不足、続柄など
<難読漢字の一覧(偏)>
(写真あり)鯆、鰍、鰉など
(写真あり)蝗、蠍、蝮など
(写真あり)梲、栂、樅など
(写真あり)鎹、鍬、釦など
<覚えておきたい知識>
鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など
(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど