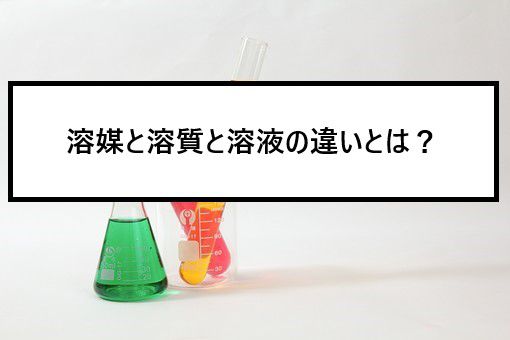1.溶媒と溶質と溶液の違いとは?

溶媒と溶質と溶液はそれぞれ下記のようになります。
・溶媒(ようばい)とは、溶かしている液体のこと。
※溶媒の覚え方については後ほど解説します。
・溶質(ようしつ)とは、溶けている物質のこと。
・溶液(ようえき)とは、溶媒に溶質がとけてできた液体のこと。
なのでこれらを”食塩水”を例にして、簡単な図にしてみると下のようになります。
上図のように、溶媒(水)に溶質(食塩)がとけてできた液体が溶液(食塩水)になります。
水溶液(すいようえき)という言葉も聞いたことがあると思いますが、
水溶液は溶液でも特に水に物質を溶かした場合のみのことを言います。
なので水溶液は溶液の中のひとつの種類と言っても良いでしょう。
さて溶媒の覚え方についてですが、溶質や溶液と違って少し覚えにくいですよね。
溶媒の覚え方としては、”(溶質を)溶かす媒体”と覚えてください。
媒体(ばいたい)というのは”仲立ち”のような意味があり、
言い換えればあるものと他のものを繋ぎ合わせるということです。
例えば物質Aと物質Bを水に溶かすと、
それぞれの物質が水に溶けて○○水みたいになります。
ということは水と物質Aと物質Bが合体してひとつの液体になったということ。
つまりこれは水の働きによって、それぞれの物質が繋ぎ合わされたってことです。
水がなければ物質Aと物質Bは合体せずに別個のままですが、
水のような溶かす媒体が存在すればそれぞれの物質を繋ぐことができます。
このようなことから溶質を溶かす媒体ということで、溶媒という言葉が使われています。
また溶媒は水やアルコールのような液体に限りますが、
溶質については溶ける物質であれば何でも良いので固体である必要はありません。
なので溶質は液体や気体ということもあり得ます。
例えば普通に市販されているチューハイ・ビール・ワインなどについては、
アルコール度数的には低くて3%から高くても20%ぐらいです。
これはビールやワインの全体的な割合から言えば、
多くてもアルコールは全体の5分の1程度しか含まれていません。
アルコール以外にも麦や果実の成分など少なからず含まれてはいますが、
お酒のほとんどを占めているのが水分....つまり水(液体)になります。
そして溶媒と溶質が液体同士のときは、
量が多い液体に量が少ない液体が溶けることになります。
ということでこの場合は溶媒が水で、溶質がアルコールなどの成分になるわけです。
ちなみにスピリタスというアルコール度数96%のお酒がありますが、
これについてはほとんどの成分がアルコールで占められています。
ですのでスピリタスの場合には溶媒がアルコールで、溶質が水などの成分になります。
以上が「溶媒と溶質と溶液の違いとは?」でした。
2.まとめ
これまで説明したことをまとめますと、
- 溶媒とは、溶かす液体のこと(または溶質を溶かす媒体)。
- 溶質とは、溶けている物質のこと。
- 溶液とは、溶媒に溶質がとけてできた液体のこと。
関連ページ
<覚えておきたい知識>
鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など
哀悼、重複、出生、集荷など
(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど
(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど
(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など
<豆知識>
(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など
<名前は知っているけどわからないもの>
(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど
(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など
(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど
<よく使う言葉>
慣習、準拠、言わずもがな、明文化など
慣習的、致命的、便宜的、作為的など
互換性、慢性、普遍性、必然性など
蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など