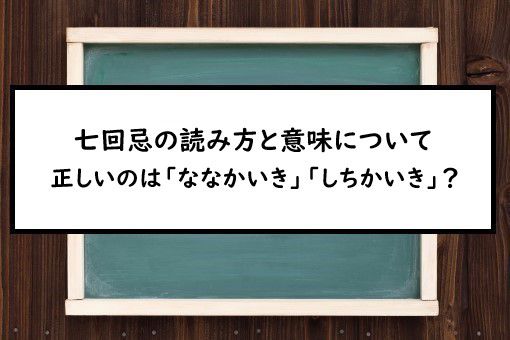ギモン雑学
1.七回忌の正しい読み方は「ななかいき」「しちかいき」?

結論から言ってしまうと、七回忌の本来の読み方は「しちかいき」でしたが、
いま現在では「しちかいき」と「ななかいき」のどちらでも問題はありません。
七回忌の”七”は「なな」「しち」、”忌”は「い(む)」「き」と読むことができます。
ただ一般的には七回忌は「しちかいき」と読むことが多いです。
七回忌を「ななかいき」と読むのは本来の読み方ではなく、
この「ななかいき」は”慣用読み”と呼ばれる読み方になります。
慣用読みというのは、誤った読み方の人が増えて広く定着したことで、
その誤った読み方についても間違いではないとされた読みのことです。
簡単に言えば、七回忌を「ななかいき」と間違って読む人が増えたために、
「しちかいき」でも「ななかいき」でも正しい読み方ということにしよう!となったわけです。
なのでいま現在での七回忌の読み方としては、「しちかいき」と「ななかいき」はどちらも正しい読み方となります。
次の章で七回忌の意味について解説していきます。
2.七回忌の意味について
3.まとめ
これまで説明したことをまとめますと、
- 「しちかいき」が本来の読み方で、「ななかいき」は慣用読み。
- 七回忌の読み方は、「しちかいき」「ななかいき」のどちらでも正しい。
- 七回忌は「死後満6年目の回忌のこと」の意味。
関連ページ
<難読漢字の一覧>
(写真あり)藜、櫛、羆など
(写真あり)竜髭菜、青梗菜、蕗など
(写真あり)岩魚、栄螺、鱧など
(写真あり)海驢、犀、猫鼬など
(写真あり)花鶏、信天翁、杜鵑など
(写真あり)薊、金木犀、百合など
(写真あり)水黽、蟋蟀、蟷螂など
(写真あり)外郎、皮蛋、雲呑など
(写真あり)行灯、暖簾、轆轤など
<読み間違えやすい漢字の一覧>
哀悼、重複、出生、集荷など
依存、過不足、続柄など
<難読漢字の一覧(偏)>
(写真あり)鯆、鰍、鰉など
(写真あり)蝗、蠍、蝮など
(写真あり)梲、栂、樅など
(写真あり)鎹、鍬、釦など
<覚えておきたい知識>
鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など
(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど