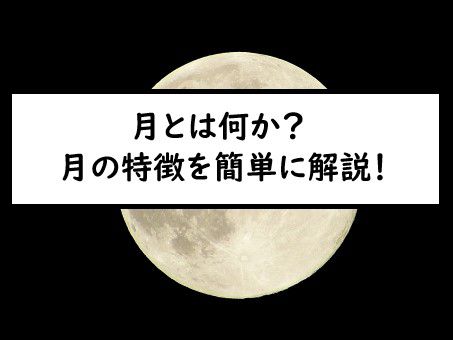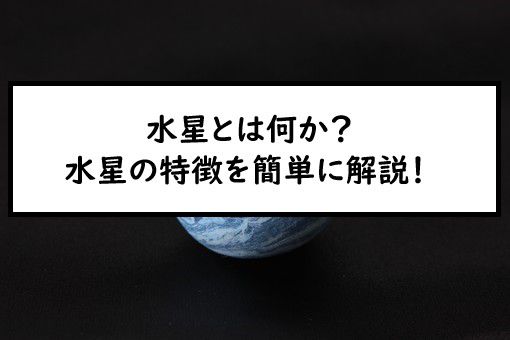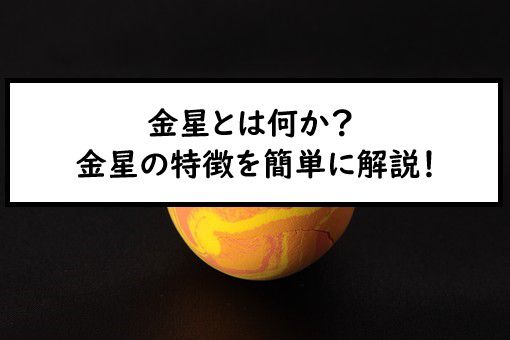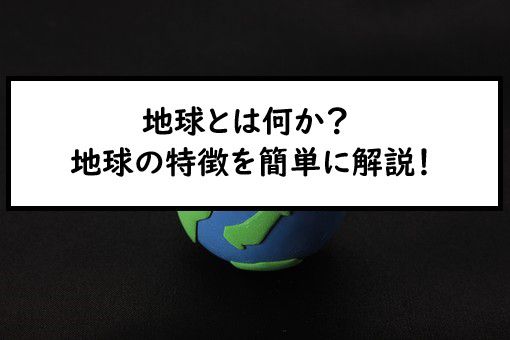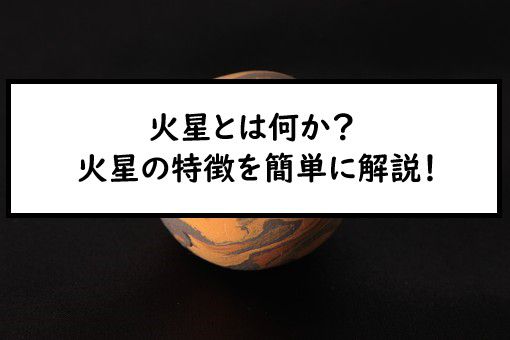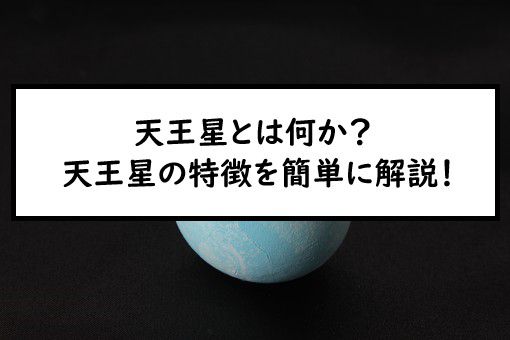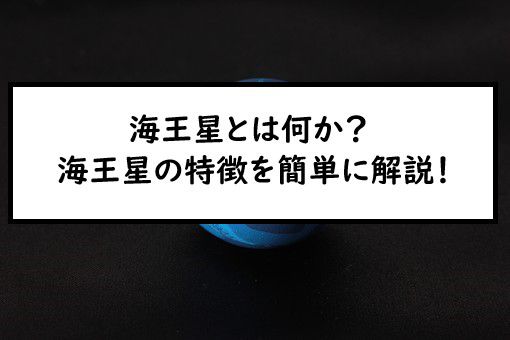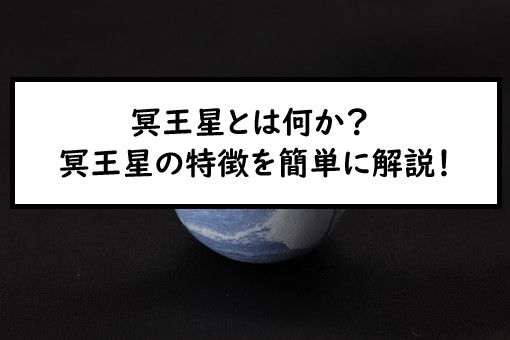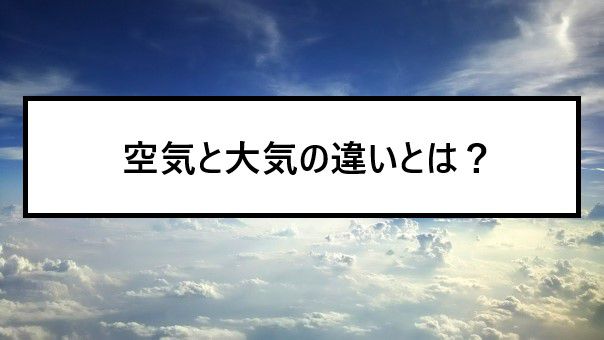さてあなたは月についてどこまでご存知でしょうか。地球から光って見える天体程度にしか思っていない人も多く、月がどのようなものなのか分からないという人もいますよね。そこでこのページでは、月の表面温度・大気・重力などの特徴を解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次月の特徴について構成物質と大気とは?なぜ月の表面温度には差が出る?なぜ月は光っているのか?月は少しずつ地球から離れている重力の大きさは質量と半径から計算するまとめ1.月の特徴についてでは月の特徴について見ていきましょう。月とは地球の周りを公転している唯一の衛星のことです。そんな月の特徴について、それぞれ簡単にまとめたものが下のようになります。項目月の特徴英語名Moon(ムーン)表面温度-233℃~123℃(平均温度-23℃)大気主にナトリウム・カリウム質量0.0123倍(地球を1)大きさ(直径)0.272倍(地球を1)重力0.166倍(地球を1)地球からの平均距離約38万km公転周期約27日項目1項目2)★ -->次の章から月について詳しく解説していきます。2.構成物質と大気とは?では月を構成している物質と大気について見ていきましょう。まず月を構成している物質は下のようになります。上図のように月の地殻・マントル部分については主に岩石で構成されていて、核(外核・内核)部分は鉄・ニッケルなどの金属(液体・固体)で構成されています。また月の大気は主に酸素・ナトリウム・カリウムから構成され、地球の大気と比較すると約10京分の1(10^17分の1)の薄さしかありません。(ナトリウム・カリウム以外にも、わずかですが他の気体が含まれています)ですので月にも大気は存在していますが、地球と比べると大気の量はほとんどないというわけです。当然ですが、月の大気で人間が呼吸することはできません。関連:空気と大気の違いとは?3.なぜ月の表面温度には差が出る?ではなぜ月の表面温度には差が出るのかを見ていきましょう。月の表面温度は-233℃~123℃(平均温度-20℃)の範囲で変化していますが、これは月の大気の薄さにより、大気中の気体による温室効果が起こらないからです。温室効果は地球温暖化の大きな原因とされているもので、温室効果ガスと呼ばれる二酸化炭素などの気体によって起こります。地球の地表における平均温度は2018年で約17℃とされていますが、大気中に温室効果ガスがなくなれば平均は約-19℃まで下がると言われています。地球では約36℃分も温室効果により、地表の温度が上がっていることになります。なので月は大気がかなり薄いためにこのような温室効果がほとんど起こらないので、太陽光が当たる面では温度が上昇し、当たらない面では温度が下降するというわけです。例えば金星の大気は地球よりもかなり多く、その大気中のほとんどの成分が温室効果ガスである二酸化炭素です。ですのでその強い温室効果により金星の平均温度は約463℃まで上がり、太陽光が当たっていない面でも熱が逃げずに金星に留まってしまいます。このように温室効果ガスによって、どれだけ地表温度に影響が出てしまうのかが分かりますよね。4.なぜ月は光っているのか?ではなぜ月が光っているのか見ていきましょう。実は月そのものが光っているのではなく、太陽からの光を月が反射して、その月が反射した太陽光が地球に届くことで、私たちには月が光って見えています。ですので私たちは月に反射した太陽光を目で捉えているんですね。また月は地球の周りを公転していて、地球は太陽の周りを公転しています。これによりそのときの位置関係によって、地球からの月の見え方が異なり、月が満ちたり欠けたりして見えることになります。これを”月の満ち欠け”と呼んでいますが、月の満ち欠けの詳しい仕組みは下記をご覧ください。関連:月の満ち欠けの仕組みとは?月の満ち欠けの名称を簡単に図で解説!関連:月が見える時間帯はなぜ違うのか?月出と月没の時間帯について解説!5.月は少しずつ地球から離れている月は地球の周りを公転しているのは知っていると思いますが、実は毎年4cmずつ月は地球から離れていっています。これは月の引力が潮の満ち引きを起こすことによるもので、満潮や干潮という現象も月の引力によって発生しています。(詳しい仕組みについては他のページで解説します)月は地球の衛星、つまり地球からの引力によって拘束されている天体です。1年間あたりで4cm離れるので、いずれ(数億年後、数十億年後)は地球の引力の拘束から離れて、月が地球の空から見えなくなるという可能性もあるようです。ちなみに月ができたとされているのが約45~46億年前ですので、昔はいまよりもずっと月と地球の距離が近く、月が何倍も大きく見えていたそうです。(地球も月と同じころに誕生したとされています)6.重力の大きさは質量と半径から計算するでは月の重力の大きさについて見ていきましょう。月の重力の大きさは、地球の約0.166倍です。つまり月の重力は、地球の約6分の1ほどになります。この0.166倍というのは地球の質量・半径と、月の質量・半径から計算することができます。計算の手順としては以下の通りです。まず上のように地球と月における質量と半径を比較し、月の質量と半径が地球の何倍なのかをそれぞれ求めていきます。そしてあとは先ほど計算で出した値を上の計算式に入れれば、月の重力は地球の0.166倍ほどだという計算結果が出てきます。このように月と地球の質量・半径がそれぞれ分かっていれば、月の重力が地球のだいたい何倍なのかを計算することができます。関連:重力と重力加速度と重さ(重量)の違いとは?以上が「月とは何か?月の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});7.まとめこれまで説明したことをまとめますと、<月の特徴>英語名は、Moon(ムーン)。表面温度は-233℃~123℃(平均温度-23℃)の範囲で変化する。月は大気が薄く温室効果がほとんど発生しないので、表面温度に大きな差が生じる。大気は主にナトリウム・カリウムで構成され、地球の大気の10京分の1の薄さしかない。月が光って見えるのは月が太陽光を反射して、その反射された光が地球まで届くから。月は毎年だいたい4cmずつ地球から離れている。月の重力は地球と比べると約0.166倍ほど(約6分の1)。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒月はなぜ光るのか?太陽と地球と月の位置関係をわかりやすく図で解説!⇒光年とは何かをわかりやすく解説!1光年の距離はどのくらい?⇒銀河と銀河系と太陽系の違いとは?⇒有明の月とは?どんな形の月なのかを図で解説!⇒なぜ太陽は東から昇って、西に沈むのか?⇒冥王星が惑星から外れた理由を分かりやすく解説!⇒火星の英語名・読み方・由来とは?⇒なぜ太陽と月は地球とぶつからないのか?仕組みを簡単に図で解説!⇒太陽系とは何かをわかりやすく図で解説!⇒重力加速度とは?仕組みを分かりやすく図解!
ギモン雑学
「 大気 」の検索結果
-
-
さて”水星”は私たちが暮らしている地球と同じ惑星の仲間で、太陽系惑星を表す「すいきんちかもくどってんかい」というフレーズにも登場します。水星は太陽系の惑星だということは多くの人が知っていますが、一体どのような惑星なのか、その特徴について知っている人は少ないです。そこでこのページでは、水星の表面温度・大気・重力などの特徴を解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次水星の特徴について構成物質と大気とは?水星と呼ばれる由来とは?なぜ表面温度には差が出る?水星における1日は1年よりも長い?重力の大きさは質量と半径から計算するまとめ1.水星の特徴について※上は水星の写真では水星の特徴について見ていきましょう。水星とは太陽系惑星の中で太陽に1番近い惑星で、月と見た目が似ています。そんな水星の特徴について、それぞれ簡単にまとめたものが下のようになります。項目水星の特徴英語名Mercury(マーキュリー)表面温度-183℃~427℃(平均温度167℃)大気主に酸素・ナトリウム・水素・ヘリウム・カリウム質量0.055倍(地球を1)大きさ(直径)0.38倍(地球を1)重力0.38倍(地球を1)太陽からの平均距離5800万km自転周期約59日公転周期約88日項目1項目2)★ -->次の章から水星について詳しく解説していきます。2.構成物質と大気とは?では水星を構成している物質と大気について見ていきましょう。まず水星を構成している物質は下のようになります。上図のように水星の約70%を占める核の部分は鉄・ニッケルなどの金属で、他の約30%の部分である地殻やマントルは岩石で構成されています。また水星の大気は主に酸素・ナトリウム・水素・ヘリウム・カリウムなどから構成され、地球の大気と比較すると約1兆分の1の薄さしかありません。(上記で挙げた気体以外にも、わずかですが他の気体が含まれています)当然ですが、水星の大気で人間が呼吸することはできません。水星の大気が薄くなってしまうのは水星が持っている重力が小さいという理由と、あとは太陽からの距離が近く、温度がかなり高くなってしまう(最大427℃)という点からです。温度が高くなるということは物質の分子が激しく運動するということなので、大気を構成する気体の分子の運動が激しくなり、水星の重力から逃れてしまうんですね。だから水星の大気はかなり薄くなってしまいます。関連:温度とは何か?物体の状態変化と温度の関係について解説!関連:空気と大気の違いとは?3.水星と呼ばれる由来とは?では水星と呼ばれている由来について簡単に見ていきましょう。なぜ水星と呼ばれているのかと言うと、それは五行思想(または五行説)という思想が由来になっているからです。五行思想とは古代中国における自然哲学の思想のことで、万物は”火・水・木・金・土”の5種類の元素から構成されるという思想です。五行思想の概念は曜日を表すのに使われていますよね。(火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日)水星は地球と同じように太陽の周りを移動(公転という)していますが、太陽の周りを1周するのに地球は約365日、水星は約88日しかかかりません。この様子から水のように流れるように速く動くということで”水星”と名付けられました。この五行思想が主だった時代には、8つの太陽系惑星のうち天王星と海王星の存在は知られておらず、地球を除くとちょうど5つの惑星になるため、五行思想から他の惑星の名前も付けられています。このように水星という名前の由来は、五行思想から来ているんですね。水星の英語名(マーキュリー)の由来について、詳しくは下記をご覧ください。関連:水星の英語名・読み方・由来とは?また実際に五行思想によって水星と名称が付けられしばらくしてから、水星で調査を行ったところ水星には水(液体)がありませんでした。水星には液体状態の水は存在しませんが、水の気体状態である水蒸気と、水の固体状態である氷は存在しています。なぜかというと、水星の温度が-183℃~427℃と変化することによって、水が液体の状態を保つことができないからなんですね。ですので水星では、水は液体の状態で存在し続けることはできません。関連:氷とドライアイスと液体窒素の違いとは?最も温度が低いのはどれ?4.なぜ表面温度には差が出る?ではなぜ水星の表面温度には差が出るのかを見ていきましょう。先ほども少し触れていましたが、水星の表面温度は-183℃~427℃とかなり差があります。これは水星が太陽からの光を受けている面(つまり昼)では最大427℃まで上昇し、太陽からの光を受けていない面では最低-183℃まで下がるということです。水星における平均の表面温度は約167℃と言われています。(ある観測地点で観測された表面温度を平均したもの)水星は太陽系惑星の中でも太陽からの距離が最も近い惑星で、太陽からの光を最も強く受けています。ですので太陽からの光を受けた水星の面では急激に温度が上昇します。また水星自体が回っている(自転)ので、水星には太陽からの光が届いていない面もあります。その太陽からの光が届いていない水星の面(つまり夜)では、温度は-183℃にまで急激に下がることになります。もし地球のようにある程度の厚さの大気(温室効果ガス)が存在していれば、このような急激な温度変化は起こらなかったはずです。温室効果ガスには大気中に熱を留めておく働きがあるため、温室効果ガスが少ない水星では熱を留めておくことができません。なので太陽からの光を受けて水星の表面温度が上がっても、熱を留めておけないので水星からすぐに熱が出ていき、-183℃まで下がってしまうんですね。5.水星における1日は1年よりも長い?では水星の1日と1年の長さについて見ていきましょう。実は水星は太陽系惑星の中でも”1年よりも1日の方が長い”とされる珍しい惑星で、水星では1年が約88日なのに対して、1日は約176日もかかってしまいます。つまり地球では1年間は365日で、夜→昼→夜の周期は1日(24時間)ですが、水星における1年間は約88日で、夜→昼→夜の周期は約176日かかるということです。少しややこしいので、簡単に解説していきます。まず地球における1日というのは、夜が来てまた次の夜が来るまでの時間のことで、1年間は地球が太陽の周りを1周する時間のことを指しています。(時間帯の周期が1周することを1日としているので、朝から朝でも問題なし)地球が夜→昼→夜のように変化するのは地球自身が回っているからで、地球自身が回ることを”地球の自転”、地球が太陽の周りを移動することを”地球の公転”と言います。そして水星も地球と同じように自転と公転をしていますが、その早さは異なります。地球の自転では1日1回転し、地球の公転は365日かかりますが、水星の自転では約59日で1回転し、水星の公転は約88日しかかかりません。見ての通り、水星における1年が約88日間なのは、水星が太陽の周りを1周(公転)する時間が約88日かかるからです。では水星における1日は水星が59日で1回転(自転)するのだから、水星の1日=59日だと覚えてしまうとそれは違います。水星における1日というのは水星が自転していること以外に、水星が太陽の周りを公転していることも考えなければいけません。というのは、もし水星が公転をしておらず、自転だけしているのであれば、”水星における夜→昼→夜の周期=水星の自転周期(約59日)”と同じになります。ですが実際には水星は太陽の周りを公転しているので、”水星の自転によって動いた分”と”公転によって動いた分”の太陽光の当たり方を考えなければいけません。上図のように水星が公転していない場合は夜→昼→夜の周期は約59日ですが、実際には水星は公転しているので夜→昼→夜の周期は約176日になってしまいます。地球の場合は自転と公転の日数が離れているためにそれほど影響はないですが、水星のように自転(約59日)と公転(約88日)の日数が近いので、1年よりも1日の方が長くなるということが起こるんですね。より分かりやすく仕組みを知りたい人は、下記の関連ページで解説しています。関連:なぜ水星の1日は1年よりも長くなるのかをわかりやすく解説!関連:なぜ金星の1日の長さは自転周期に比べて短くなるのか?6.重力の大きさは質量と半径から計算するでは水星の重力の大きさについて見ていきましょう。水星の重力の大きさは、地球の約0.38倍です。つまり水星の重力は、地球の半分以下ということになります。この0.38倍というのは地球の質量・半径と、水星の質量・半径から計算することができます。計算の手順としては以下の通りです。まず上のように地球と水星における質量と半径を比較し、水星の質量と半径が地球の何倍なのかをそれぞれ求めていきます。そしてあとは先ほど計算で出した値を上の計算式に入れれば、水星の重力は地球の0.38倍ほどだという計算結果が出てきます。このように水星と地球の質量・半径がそれぞれ分かっていれば、水星の重力が地球のだいたい何倍なのかを計算することができます。関連:重力と重力加速度と重さ(重量)の違いとは?以上が「水星とは?水星の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});7.まとめこれまで説明したことをまとめますと、<水星の特徴>英語名は、Mercury(マーキュリー)。水星の由来は、五行思想(火・水・木・金・土)から来ている。表面温度は-183℃~427℃の範囲で変化する。大気は水素・へリウム・酸素・ナトリウム・カリウムなどで構成され、地球の大気の1兆分の1ほどの薄さしかない。水星の1年は約88日だが、1日は1年の2倍の約176日ほど。水星の重力は地球と比べると約0.38倍ほど。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒金星とは?金星の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!⇒光年とは何かをわかりやすく解説!1光年の距離はどのくらい?⇒銀河と銀河系と太陽系の違いとは?⇒月はなぜ光るのか?太陽と地球と月の位置関係をわかりやすく図で解説!⇒なぜ太陽は東から昇って、西に沈むのか?⇒冥王星が惑星から外れた理由を分かりやすく解説!⇒火星の英語名・読み方・由来とは?⇒なぜ太陽と月は地球とぶつからないのか?仕組みを簡単に図で解説!⇒太陽系とは何かをわかりやすく図で解説!⇒重力加速度とは?仕組みを分かりやすく図解!
-
さて”金星”は私たちが暮らしている地球と同じ惑星の仲間で、太陽系惑星を表す「すいきんちかもくどってんかい」というフレーズにも登場します。金星は太陽系の惑星だということは多くの人が知っていますが、一体どのような惑星なのか、その特徴について知っている人は少ないです。そこでこのページでは、金星の表面温度・大気・重力などの特徴を解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次金星の特徴について構成物質と大気とは?金星と呼ばれる由来とは?なぜ平均温度は463℃と高いのか?金星における1日と1年について重力の大きさは質量と半径から計算するまとめ1.金星の特徴について※上は金星の写真では金星の特徴について見ていきましょう。金星とは太陽系の惑星において、2番目に太陽に近い惑星のことです。そんな金星の特徴について、それぞれ簡単にまとめたものが下のようになります。項目金星の特徴英語名Venus(ヴィーナス)表面温度-46℃~500℃(平均温度463℃)大気主に二酸化炭素・窒素質量0.815倍(地球を1)大きさ(直径)0.950倍(地球を1)重力0.9倍(地球を1)太陽からの平均距離1億820万km自転周期約243日公転周期約225日項目1項目2)★ -->次の章から金星について詳しく解説していきます。2.構成物質と大気とは?では金星を構成している物質と大気について見ていきましょう。まず金星を構成している物質は下のようになります。上図のように金星の地殻とマントル部分は岩石で構成され、中心である核部分については鉄やニッケルなどの金属で構成されています。そして金星と地球の内部構造はほぼ同じであると考えられています。また金星の大気は主に二酸化炭素・窒素から構成されており、それ以外にもわずかに二酸化硫黄・水蒸気なども含まれています。当然ですが、金星の大気では人間は呼吸することはできません。関連:空気と大気の違いとは?3.金星と呼ばれる由来とは?では金星と呼ばれている由来について簡単に見ていきましょう。なぜ金星と呼ばれているのかと言うと、それは五行思想(または五行説)という思想が由来になっているからです。五行思想とは古代中国における自然哲学の思想のことで、万物は”火・水・木・金・土”の5種類の元素から構成されるという思想です。五行思想の概念は曜日を表すのに使われていますよね。(火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日)金星は明けの明星・宵の明星というように太陽と月に次いで明るく輝いており、このことから金のように輝いている星ということで”金星”となりました。(太陽系惑星の中では最も明るく輝いている)この五行思想が主だった時代には、8つの太陽系惑星のうち天王星と海王星の存在は知られておらず、地球を除くとちょうど5つの惑星になるため、五行思想から他の惑星の名前も付けられています。このように金星という名前の由来は、五行思想から来ているんですね。金星の英語名(ヴィーナス)の由来について、詳しくは下記をご覧ください。関連:金星の英語名・読み方・由来とは?4.なぜ平均温度は463℃と高いのか?最初の方の金星の特徴でも示していましたが、金星の温度の範囲は-46℃~500℃で平均温度が463℃です。ではなぜこんなに金星の平均温度が高いのかと言うと、それは金星の大気を構成している大量の二酸化炭素の温室効果によるものです。金星は地球よりも太陽に近い位置に存在していますが、実は金星へと届く太陽光は地球と比べると10分の1程度しかありません。これは金星の上空に存在している雲が太陽からの光をほとんど反射するため、太陽からの光は10分の1程度しか金星の地表まで届くことはないんですね。また金星の大気は約96%が温室効果ガスである二酸化炭素で構成され、大気自体の量も地球と比較すると数十倍と多いです。その数十倍についても地球の大気の主成分である窒素・酸素ではなく、ほぼ二酸化炭素が代わりになっているため温室効果がかなり高いです。先ほどの-46℃というのは大気による影響がない場合の金星の温度のことで、二酸化炭素の影響で500℃近くの温室効果がもたらされています。地球へと届く10分の1ほどの太陽光で、金星の平均温度は463℃まで達するのですから、二酸化炭素が生み出す温室効果がどれほどすごいのかが分かりますよね。5.金星における1日と1年についてでは金星における1日と1年について見ていきましょう。私たちが暮らしている地球では1日の長さは24時間で、1年の長さは365日というのは常識ですよね。ですが金星における1日と1年の長さは地球とは異なり、金星の1日の長さは約116日と18時間で、1年は約225日ほどになります。つまり地球では1年間は365日で、夜→昼→夜の周期は1日(24時間)ですが、金星における1年間は約225日で、夜→昼→夜の周期は約116日と18時間分かかるということです。少しややこしいので、簡単に解説していきます。まず地球における1日というのは、夜が来てまた次の夜が来るまでの時間のことで、1年間は地球が太陽の周りを1周する時間のことを指しています。(時間帯の周期が1周することを1日としているので、朝から朝でも問題なし)地球が夜→昼→夜のように変化するのは地球自身が回っているからで、地球自身が回ることを”地球の自転”、地球が太陽の周りを移動することを”地球の公転”と言います。そして金星も地球と同じように自転と公転をしていますが、その早さは異なります。地球の自転では1日1回転し、地球の公転は365日かかりますが、金星の自転では約243日で1回転し、金星の公転は約225日しかかかりません。見ての通り、金星における1年が約225日間なのは、金星が太陽の周りを1周(公転)する時間が約225日かかるからです。では金星も地球と同じように自転の周期と夜→昼→夜(1日)の周期が同じなのかと言うと、そうではありません。金星における夜→昼→夜(1日)というのは自転していること以外に、金星が太陽の周りを公転しているということも考えなければいけないからです。(金星の1日の長さについての詳しい仕組みは別のページで解説します)また金星の回転する(自転する)方向は他の惑星とは違って、”時計回り”に自転しています。金星以外の太陽系惑星(地球を含む)の自転は”反時計回り”なので、金星だけ太陽や星の動き方が”西から東”に動いているように見えます。関連:なぜ金星の1日の長さは自転周期に比べて短くなるのか?関連:なぜ水星の1日は1年よりも長くなるのかをわかりやすく解説!6.重力の大きさは質量と半径から計算するでは金星の重力の大きさについて見ていきましょう。金星の重力の大きさは、地球の約0.9倍です。つまり金星の重力は、地球よりも少し程度ということになります。この0.9倍というのは地球の質量・半径と、金星の質量・半径から計算することができます。計算の手順としては以下の通りです。まず上のように地球と金星における質量と半径を比較し、金星の質量と半径が地球の何倍なのかをそれぞれ求めていきます。そしてあとは先ほど計算で出した値を上の計算式に入れれば、金星の重力は地球の0.9倍ほどだという計算結果が出てきます。このように金星と地球の質量・半径がそれぞれ分かっていれば、金星の重力が地球のだいたい何倍なのかを計算することができます。関連:重力と重力加速度と重さ(重量)の違いとは?以上が「金星とは?金星の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});7.まとめこれまで説明したことをまとめますと、<金星の特徴>英語名は、Venus(ヴィーナス)。金星の由来は、五行思想(火・水・木・金・土)から来ている。表面温度は-46℃~500℃(平均温度は463℃)。金星の平均温度が463℃と高いのは、大気中の二酸化炭素(温室効果ガス)によるもの。大気は主に二酸化炭素・窒素で構成されている。金星の1日の長さは約116日で、1年は約225日。金星の重力は地球と比べると約0.9倍ほど。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒火星とは?火星の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!⇒光年とは何かをわかりやすく解説!1光年の距離はどのくらい?⇒銀河と銀河系と太陽系の違いとは?⇒月はなぜ光るのか?太陽と地球と月の位置関係をわかりやすく図で解説!⇒月齢とは?月齢と月の満ち欠けの関係をわかりやすく図で解説!⇒天王星とは?天王星の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!⇒冥王星が惑星から外れた理由を分かりやすく解説!⇒なぜ太陽と月は地球とぶつからないのか?仕組みを簡単に図で解説!⇒太陽系とは何かをわかりやすく図で解説!⇒なぜ太陽は東から昇って、西に沈むのか?
-
さて”地球”とは私たち人間が暮らしている天体のことで、太陽系惑星を表す「すいきんちかもくどってんかい」というフレーズにも出てきます。私たちは当然のように地球で日常生活を送っていますが、地球とはどのような天体なのかを知らない人も多いですよね。そこでこのページでは、地球の表面温度・大気・重力などの特徴を解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次地球の特徴について構成物質と大気とは?地球ができたのはいつごろ?地球と呼ばれる由来とは?地球における1日と1年についてなぜ自転しているのか?地球の衛星についてまとめ1.地球の特徴についてでは地球の特徴について見ていきましょう。地球とは太陽系の惑星において、3番目に太陽に近い惑星のことです。そんな地球の特徴について、それぞれ簡単にまとめたものが下のようになります。項目地球の特徴英語名Earth(アース)表面温度-90℃~70℃(平均温度15℃)大気空気(主に窒素・酸素)質量5.976×10^24 kg大きさ(半径)6.378×10^3 km気圧1気圧地球1周の長さ約4万km太陽からの平均距離1億4960万km自転周期約1日(約24時間)公転周期約365日項目1項目2)★ -->次の章から地球について詳しく解説していきます。2.構成物質と大気とは?では地球を構成している物質と大気について見ていきましょう。まず地球を構成している物質は下のようになります。上図のように地球の地殻・マントル部分は主に岩石で構成され、核の部分には鉄・ニッケルなどの金属で構成されています。上に宇宙から見たときの地球の写真がありますが、青く見える部分は”水”で、白く見える部分は”雲や雪(氷)”になります。また地球の大気は主に窒素・酸素から構成され、それ以外にもわずかにアルゴン・二酸化炭素・水蒸気などの物質が含まれています。地球の大気は別名で”空気”と呼ばれており、私たちが地球で生活するためにかかせないものとなっています。そして地球以外の惑星で、空気のように人間が呼吸できる大気は確認されていません。ちなみに空気に含まれる水蒸気と言うのは、日常的に湿度[%]として表されていて、湿度については下記で詳しく解説しているので、どうぞご覧ください。関連:空気とは何か?高い場所ほど空気が薄くなる理由とは?関連:湿度とは何か?湿度100パーセントとはどんな状態のこと?3.地球ができたのはいつごろ?地球が誕生したのはいまから約46億年前だとされています。(宇宙が始まったとされているのは約100億年ほど前)他の小さな天体が何度も衝突することで合体して地球は誕生しており、それから長い期間を経て、いま現在における地球となっています。衝突した天体の中には金属・岩石・水・二酸化炭素など様々な物質が含まれ、衝突したときに発生した熱によって水は水蒸気に変化しました。地球が誕生したときの頃の大気はメタン・アンモニア・二酸化炭素などで構成され、人間が生きるために必要な酸素は含まれていませんでした。天体との衝突によって発生した熱はこの厚い大気のせいで内部にたまり、地表の温度は1000℃以上に達してしまいます。(温度上昇は二酸化炭素などの温室効果によるもの)それからしばらくして天体との衝突の回数も少なくなってきて、地表の温度が下がり始めたことで、大気中の水蒸気が雲になりました。その雲から激しい雨が何万年も降り続けて、その雨水が海になったと言われています。そして海の中に生物が誕生して、その生物が大気中の二酸化炭素を取り込み酸素を作り出すようになったことで、地上にも植物が誕生しました。さらに地上で植物が光合成を行い、地球内部で酸素を生成してくれていたことで、地球の大気は私たちが呼吸できる”空気”として存在しているわけなんですね。関連:雪と雨とは?雪と雨が降る仕組みを分かりやすく図解!4.地球と呼ばれる由来とは?では地球と呼ばれる由来について見ていきましょう。地球と呼ばれている由来は、大地という概念と地球が球体(丸い)であることからきています。地球はかなり昔から「球体ではないのか?」と推測はされていましたが、地球が球体であるということは証明されていませんでした。実際に地球が球体であることが証明されたのは1520年頃で、マゼランとエルカーノが世界一周したことによって証明されています。その後に”大地”と”球体”という概念から、”地球”と名付けられました。そして実は”地球”という言葉は日本で誕生した言葉ではなく、中国で誕生した言葉で、中国から伝わってそれが日本でも使われるようになりました。幕末から明治あたりに中国から日本へと伝わり、それから少しずつ”地球”という言葉が定着していきます。なので中国語でも同じ意味で”地球”という単語は使われています。また地球を英語で読む場合は”Earth(アース)”ですが、これはドイツ語の”Erde(エルデ)”からきています。ドイツ語の”Erde(エルデ)”から古代中世英語の”Erthe(エルセ)”ときて、そのあとに英語で”Earth(アース)”と読まれるようになりました。なので”Erde(エルデ)⇒Erthe(エルセ)⇒Earth(アース)”となったんですね。ドイツ語の”Erde(エルデ)”にはもともと”大地”の意味があり、いまでは地球の意味としても使われています。5.地球における1日と1年についてでは地球における1日と1年について見ていきましょう。地球における1日というのは地球が自転することで太陽光の当たり方が変わり、それにより地球における時間帯(朝・昼・夜)が変化することで起こります。上図のように地球は自転と言って反時計回りに回転しているので、時間が経過すると太陽光が当たる地球の面も変化していきます。これが地球における1日(時間帯の変化)が起こる簡単な仕組みです。関連:なぜ太陽は東から昇って、西に沈むのか?そして地球における1年というのは、地球が太陽の周りを1周する時間のことを指しています。そしてうるう年という1年が366日になる年が存在していますが、あれは地球が太陽の周りを1周する時間がぴったり365日ではないために設けられています。うるう年の詳しい仕組みや細かいルールについては下記をご覧ください。関連:うるう年(閏年)とは?4年に1度だけ366日になる仕組みを解説!6.なぜ自転しているのか?では地球はなぜ反時計回りに自転しているのか見ていきましょう。これはなぜかというと、地球が誕生したときに発生した運動エネルギーが残っているからです。地球が誕生したときというのは、他の天体が衝突し合って集まったことでできているため、そのときに他の天体がぶつかった衝撃で地球に回転する力が働いています。上図のように天体がぶつかるときは同じ速度、同じ質量のものがぶつかるわけではないので、ぶつかったときには必ずどちらかに力の偏りができてしまいます。その力の偏りがいまでも地球の自転(回転)と言う形で残っているんですね。またなぜ地球の回転速度が時間を経過してもほとんど変わらないのかと言うと、それは宇宙には地球内部と違って抵抗となるものがないからです。地球の中でボールを投げて時間が経つと動きが遅くなったり、地面に落下します。これは地球内部ではそのボールに地球からの重力が働いていたり、空気が存在しているので空気抵抗があるために動きが遅くなってしまいます。ですが宇宙にはそのような物質はほとんどないので、抵抗もほとんど発生しません。太陽からの引力によって引き寄せられはしますが、それは地球の公転という形で保っています。(詳しい仕組みは下記の関連ページからご覧ください)ですので地球の自転の速度がほとんど変わらないんですね。関連:空気抵抗とは?なぜ物体の速度が上がると空気抵抗は大きくなるのか?関連:なぜ太陽と月は地球とぶつからないのか?仕組みを簡単に図で解説!7.地球の衛星についてでは地球の衛星について見ていきましょう。衛星(えいせい)とは、惑星の周りを公転している天体のことで、地球の衛星と言えば誰もが知っている”月”のことを指しています。月は地球の唯一の衛星で、地球からの引力によって拘束されています。月の重力の大きさは地球と比べて6分の1ほどの大きさで、地球で体重が60kgの人は、月では体重が10kgほどになってしまいます。なので月に行くと体が軽く感じてしまうんですね。また太陽からの引力によって地球が太陽の周りを公転しているように、月もまた地球からの引力によって地球の周りを公転しています。地球が太陽の周りを1周するのにかかる時間は約365日で、月が地球の周りを1周するのにかかる時間は約27日かかります。地球が太陽の周りを回ることを”地球の公転”、月が地球の周りを回ることを”月の公転”と言います。ちなみに地球から月が満ちたり、欠けたりして見えるのは、月と地球と太陽の位置関係が大きく関係しています。月の満ち欠けが起こる仕組みについて、詳しくは下記をご覧ください。関連:月の満ち欠けの仕組みとは?月の満ち欠けの名称を簡単に図で解説!以上が「地球とは?地球の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});8.まとめこれまで説明したことをまとめますと、<地球の特徴>英語名は、Earth(アース)。地球の由来は、”大地”という概念と”球体”であることからきている。地球の英語名(アース)の由来は、ドイツ語の”Erde(エルデ)”からきている。表面温度は-90℃~70℃(平均温度15℃)。大気は主に窒素・酸素で構成されている(空気のこと)。地球の1日の長さは約24時間で、1年は約365日ほど。”月”は地球における唯一の衛星。月の重力は地球の約6分の1(言い換えれば、地球の重力は月の6倍ほど)。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒水星とは?水星の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!⇒月とは何か?月の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!⇒銀河と銀河系と太陽系の違いとは?⇒月はなぜ光るのか?太陽と地球と月の位置関係をわかりやすく図で解説!⇒「すいきんちかもくどってんかい」とは何の順番を表している?⇒なぜ太陽は東から昇って、西に沈むのか?⇒光年とは何かをわかりやすく解説!1光年の距離はどのくらい?⇒なぜ太陽と月は地球とぶつからないのか?仕組みを簡単に図で解説!⇒太陽系とは何かをわかりやすく図で解説!⇒重力加速度とは?仕組みを分かりやすく図解!
-
さて”火星”は私たちが暮らしている地球と同じ惑星の仲間で、太陽系惑星を表す「すいきんちかもくどってんかい」というフレーズにも登場します。火星は太陽系の惑星だということは多くの人が知っていますが、一体どのような惑星なのか、その特徴について知っている人は少ないです。そこでこのページでは、火星の表面温度・大気・重力などの特徴を解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次火星の特徴について構成物質と大気とは?火星と呼ばれる由来とは?火星における1日と1年について重力の大きさは質量と半径から計算するまとめ1.火星の特徴について※上は火星の写真では火星の特徴について見ていきましょう。火星とは太陽系の惑星において、4番目に太陽に近い惑星のことです。そんな火星の特徴について、それぞれ簡単にまとめたものが下のようになります。項目火星の特徴英語名Mars(マーズ)表面温度-140℃~20℃(平均温度-63℃)大気主に二酸化炭素・窒素・アルゴン質量0.107倍(地球を1)大きさ(直径)0.532倍(地球を1)重力0.38倍(地球を1)太陽からの平均距離2億2790万km自転周期約1日公転周期約687日項目1項目2)★ -->次の章から火星について詳しく解説していきます。2.構成物質と大気とは?では火星を構成している物質と大気について見ていきましょう。まず火星を構成している物質は下のようになります。上図のように火星の地殻・マントル部分は岩石・鉄で構成され、核の部分には鉄・ニッケルなどの金属で構成されています。そして火星の表面が赤褐色に見えるのは、地殻・マントルを構成している岩石に、酸化鉄が多く含まれているために赤褐色に見えるんですね。酸化鉄とはつまり鉄が錆びた状態のもので、日常的には”赤さび”などと呼ばれることも多いです。また火星の大気は主に二酸化炭素・窒素・アルゴンから構成され、それ以外にもわずかに酸素・一酸化炭素・水蒸気などが含まれています。当然ですが、火星の大気では人間は呼吸することはできません。関連:空気と大気の違いとは?3.火星と呼ばれる由来とは?では火星と呼ばれている由来について簡単に見ていきましょう。なぜ火星と呼ばれているのかと言うと、それは五行思想(または五行説)という思想が由来になっているからです。五行思想とは古代中国における自然哲学の思想のことで、万物は”火・水・木・金・土”の5種類の元素から構成されるという思想です。五行思想の概念は曜日を表すのに使われていますよね。(火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日)五行思想では火は赤色とされており、火星はその赤っぽい色の見た目から”火星”と名付けられました。この五行思想が主だった時代には、8つの太陽系惑星のうち天王星と海王星の存在は知られておらず、地球を除くとちょうど5つの惑星になるため、五行思想から惑星の名前が付けられました。このように火星という名前の由来は、五行思想から来ているんですね。火星の英語名(マーズ)の由来について、詳しくは下記をご覧ください。関連:火星の英語名・読み方・由来とは?4.火星における1日と1年についてでは火星における1日と1年について見ていきましょう。私たちが暮らしている地球では1日の長さは24時間で、1年の長さは365日というのは常識ですよね。実は火星における1日の長さは地球とだいたい同じで約1日(24時間40分)なのですが、火星の1年の長さは地球と異なり約687日もかかってしまいます。つまり地球では1年間は365日で、夜→昼→夜の周期は1日(24時間)ですが、火星における1年間は約687日で、夜→昼→夜の周期は約1日(24時間40分)です。少しややこしいので、簡単に解説していきます。まず地球における1日というのは、夜が来てまた次の夜が来るまでの時間のことで、1年間は地球が太陽の周りを1周する時間のことを指しています。(時間帯の周期が1周することを1日としているので、朝から朝でも問題なし)地球が夜→昼→夜のように変化するのは地球自身が回っているからで、地球自身が回ることを”地球の自転”、地球が太陽の周りを移動することを”地球の公転”と言います。そして火星も地球と同じように自転と公転をしていて、その早さは異なります。地球の自転では1日1回転し、地球の公転は365日かかりますが、火星の自転では約1日で1回転し、火星の公転は約687日かかります。火星における1日の長さは約1日、1年の長さは約687日なので、火星の自転と公転からそれぞれ1日と1年の長さを知ることができます。ですが水星や金星のように、”自転にかかる時間=1日の長さ”とならない惑星もあるので注意しましょう。関連:なぜ金星の1日の長さは自転周期に比べて短くなるのか?関連:なぜ水星の1日は1年よりも長くなるのかをわかりやすく解説!5.重力の大きさは質量と半径から計算するでは火星の重力の大きさについて見ていきましょう。火星の重力の大きさは、地球の約0.38倍です。つまり火星の重力は、地球の半分以下ということになります。この0.38倍というのは地球の質量・半径と、火星の質量・半径から計算することができます。計算の手順としては以下の通りです。まず上のように地球と火星における質量と半径を比較し、火星の質量と半径が地球の何倍なのかをそれぞれ求めていきます。そしてあとは先ほど計算で出した値を上の計算式に入れれば、火星の重力は地球の0.38倍ほどだという計算結果が出てきます。このように火星と地球の質量・半径がそれぞれ分かっていれば、火星の重力が地球のだいたい何倍なのかを計算することができます。関連:重力と重力加速度と重さ(重量)の違いとは?以上が「火星とは?火星の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});6.まとめこれまで説明したことをまとめますと、<火星の特徴>英語名は、Mars(マーズ)。火星の由来は、五行思想(火・水・木・金・土)から来ている。火星が赤褐色に見えるのは、表面部分に酸化鉄(赤さび)を含んでいるから。表面温度は-140℃~20℃(平均温度-63℃)の範囲で変化する。大気は主に二酸化炭素・窒素で構成されている。火星の1日の長さは約1日(24時間40分)で、1年は約687日。火星の重力は地球と比べると約0.38倍ほど。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒木星とは?木星の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!⇒光年とは何かをわかりやすく解説!1光年の距離はどのくらい?⇒銀河と銀河系と太陽系の違いとは?⇒冥王星の英語名・読み方・由来とは?⇒月齢とは?月齢と月の満ち欠けの関係をわかりやすく図で解説!⇒なぜ太陽は東から昇って、西に沈むのか?⇒冥王星が惑星から外れた理由を分かりやすく解説!⇒なぜ太陽と月は地球とぶつからないのか?仕組みを簡単に図で解説!⇒太陽系とは何かをわかりやすく図で解説!⇒重力加速度とは?仕組みを分かりやすく図解!
-
さて”木星”は私たちが暮らしている地球と同じ惑星の仲間で、太陽系惑星を表す「すいきんちかもくどってんかい」というフレーズにも登場します。木星は太陽系の惑星だということは多くの人が知っていますが、一体どのような惑星なのか、その特徴について知っている人は少ないです。そこでこのページでは、木星の表面温度・大気・重力などの特徴を解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次木星の特徴について構成物質と大気とは?木星と呼ばれる由来とは?木星における1日と1年について重力の大きさは質量と半径から計算するまとめ1.木星の特徴について※上は木星の写真では木星の特徴について見ていきましょう。木星とは太陽系の惑星において、5番目に太陽に近い惑星のことです。そんな木星の特徴について、それぞれ簡単にまとめたものが下のようになります。項目木星の特徴英語名Jupiter(ジュピター)表面温度平均温度-121℃大気主に水素・ヘリウム質量317.7倍(地球を1)大きさ(直径)10.96倍(地球を1)重力2.64倍(地球を1)太陽からの平均距離7億7830万km自転周期約9.8時間公転周期約11.86年(4329日)項目1項目2)★ -->次の章から木星について詳しく解説していきます。2.構成物質と大気とは?では木星を構成している物質と大気について見ていきましょう。まず木星を構成している物質は下のようになります。上図のように木星は外層が液体水素・ヘリウム、内層が金属水素・ヘリウムで構成され、核となる部分の物質は岩石と鉄・ニッケルなどの金属で構成されています。液体水素とは気体の水素が高い圧力で圧縮されたもので、その液体水素をさらに高い圧力で圧縮させると金属水素となります。木星の大部分が水素で構成されているため、木星は水素から形成されている惑星と言っても過言ではありません。そして木星が縞模様に見えるのは、木星の上層部分に形成されている雲によるもので、木星の上層部分の雲の主成分はアンモニアで構成されています。なので地球から木星を観測したときに見えているのは、木星の上層部分に形成されているアンモニアの雲なんですね。また木星の大気は主に水素・ヘリウムから構成されていて、それ以外にもわずかにメタン・水蒸気・アンモニアなどの物質も含まれています。当然ですが、木星の大気では人間は呼吸することはできません。関連:空気と大気の違いとは?3.木星と呼ばれる由来とは?では木星と呼ばれている由来について簡単に見ていきましょう。なぜ木星と呼ばれているのかと言うと、それは五行思想(または五行説)という思想が由来になっているからです。五行思想とは古代中国における自然哲学の思想のことで、万物は”火・水・木・金・土”の5種類の元素から構成されるという思想です。五行思想の概念は曜日を表すのに使われていますよね。(火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日)この五行思想が主だった時代には、8つの太陽系惑星のうち天王星と海王星の存在は知られておらず、地球を除くとちょうど5つの惑星になるため、五行思想から惑星の名前が付けられました。先に他の惑星(水星・金星・火星・土星)が見た目の色やその様子から、五行思想に当てはめられて名付けられていますが、木星については最後に余った”木”を当てはめられただけなんです。なので木星は他の4つの惑星とは違い、少しだけ適当に名付けられた感があります。木星の英語名(ジュピター)の由来について、詳しくは下記をご覧ください。関連:木星の英語名・読み方・由来とは?4.木星における1日と1年についてでは木星における1日と1年について見ていきましょう。私たちが暮らしている地球では1日の長さは24時間で、1年の長さは365日というのは常識ですよね。ですが木星における1日と1年の長さは地球とは異なり、木星の1日の長さは約9.8時間で、1年は約11.86年ほどになります。つまり地球では1年間は365日で、夜→昼→夜の周期は1日(24時間)ですが、木星における1年間は約11.86年で、夜→昼→夜の周期は約9.8時間かかるということです。少しややこしいので、簡単に解説していきます。まず地球における1日というのは、夜が来てまた次の夜が来るまでの時間のことで、1年間は地球が太陽の周りを1周する時間のことを指しています。(時間帯の周期が1周することを1日としているので、朝から朝でも問題なし)地球が夜→昼→夜のように変化するのは地球自身が回っているからで、地球自身が回ることを”地球の自転”、地球が太陽の周りを移動することを”地球の公転”と言います。そして木星も地球と同じように自転と公転をしていますが、その早さは異なります。地球の自転では1日1回転し、地球の公転は365日かかりますが、木星の自転では約9.8時間で1回転し、木星の公転は約11.86年もかかります。木星における1日の長さは約9.8時間、1年の長さは約11.86年なので、木星の自転と公転からそれぞれ1日と1年の長さを知ることができます。ですが水星や金星のように、”自転にかかる時間=1日の長さ”とならない惑星もあるので注意しましょう。関連:なぜ金星の1日の長さは自転周期に比べて短くなるのか?関連:なぜ水星の1日は1年よりも長くなるのかをわかりやすく解説!5.重力の大きさは質量と半径から計算するでは木星の重力の大きさについて見ていきましょう。木星の重力の大きさは、地球の約2.64倍です。つまり木星の重力は、地球よりもかなり大きいことになります。この2.64倍というのは地球の質量・半径と、木星の質量・半径から計算することができます。計算の手順としては以下の通りです。まず上のように地球と木星における質量と半径を比較し、木星の質量と半径が地球の何倍なのかをそれぞれ求めていきます。そしてあとは先ほど計算で出した値を上の計算式に入れれば、木星の重力は地球の2.64倍ほどだという計算結果が出てきます。このように木星と地球の質量・半径がそれぞれ分かっていれば、木星の重力が地球のだいたい何倍なのかを計算することができます。関連:重力と重力加速度と重さ(重量)の違いとは?以上が「木星とは?木星の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});6.まとめこれまで説明したことをまとめますと、<木星の特徴>英語名は、Jupiter(ジュピター)。木星の由来は、五行思想(火・水・木・金・土)から来ている。木星の表面が縞模様に見えるのは、木星の上層部分に形成されたアンモニアの雲によるもの。平均温度は-121℃ほど。大気は主に水素・ヘリウムで構成されている。木星の1日の長さは約9.8時間で、1年は約11.86年ほど。木星の重力は地球と比べると約2.64倍ほど。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒土星とは?土星の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!⇒光年とは何かをわかりやすく解説!1光年の距離はどのくらい?⇒銀河と銀河系と太陽系の違いとは?⇒月はなぜ光るのか?太陽と地球と月の位置関係をわかりやすく図で解説!⇒月齢とは?月齢と月の満ち欠けの関係をわかりやすく図で解説!⇒冥王星が惑星から外れた理由を分かりやすく解説!⇒冥王星が惑星から外れた理由を分かりやすく解説!⇒なぜ太陽と月は地球とぶつからないのか?仕組みを簡単に図で解説!⇒太陽系とは何かをわかりやすく図で解説!⇒重力加速度とは?仕組みを分かりやすく図解!
-
さて”土星”は私たちが暮らしている地球と同じ惑星の仲間で、太陽系惑星を表す「すいきんちかもくどってんかい」というフレーズにも登場します。土星は太陽系の惑星だということは多くの人が知っていますが、一体どのような惑星なのか、その特徴について知っている人は少ないです。そこでこのページでは、土星の表面温度・大気・重力などの特徴を解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次土星の特徴について構成物質と大気とは?土星と呼ばれる由来とは?土星に付いているリング状のものって何?土星における1日と1年について重力の大きさは質量と半径から計算するまとめ1.土星の特徴について※上は土星の写真では土星の特徴について見ていきましょう。土星とは太陽系の惑星において、6番目に太陽に近い惑星のことです。そんな土星の特徴について、それぞれ簡単にまとめたものが下のようになります。項目土星の特徴英語名Saturn(サターン)表面温度平均温度-130℃大気主に水素・ヘリウム質量95.124倍(地球を1)大きさ(直径)9.45倍(地球を1)重力1.07倍(地球を1)太陽からの平均距離14億2940万km自転周期約10.2時間公転周期約29.46年(10752日)項目1項目2)★ -->次の章から土星について詳しく解説していきます。2.構成物質と大気とは?では土星を構成している物質と大気について見ていきましょう。まず土星を構成している物質は下のようになります。上図のように土星は外層が液体水素・ヘリウム、内層が金属水素・ヘリウムで構成され、核となる部分の物質は岩石と鉄・ニッケルなどの金属で構成されています。液体水素とは気体の水素が高い圧力で圧縮されたもので、その液体水素をさらに高い圧力で圧縮させると金属水素となります。土星の大部分が木星と同じように水素で構成されているため、土星は水素から形成されている惑星と言っても過言ではありません。土星の表面が黄色味がかって見えるのは、土星の上層部分に形成されているアンモニアなどからできた雲によるものです。木星よりも土星の方が黄色味がかって見えるのは、土星の方が木星よりも厚いアンモニアの雲で覆われているからです。また土星の大気は主に水素・ヘリウムから構成されていて、それ以外にもわずかにメタンやアンモニアなどの物質が含まれています。当然ですが、土星の大気では人間は呼吸することはできません。関連:空気と大気の違いとは?3.土星と呼ばれる由来とは?では土星と呼ばれている由来について簡単に見ていきましょう。なぜ土星と呼ばれているのかと言うと、それは五行思想(または五行説)という思想が由来になっているからです。五行思想とは古代中国における自然哲学の思想のことで、万物は”火・水・木・金・土”の5種類の元素から構成されるという思想です。五行思想の概念は曜日を表すのに使われていますよね。(火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日)五行思想では土は黄色とされており、土星のその黄色っぽい見た目から”土星”と名付けられました。この五行思想が主だった時代には、8つの太陽系惑星のうち天王星と海王星の存在は知られておらず、地球を除くとちょうど5つの惑星になるため、五行思想から惑星の名前が付けられました。このように土星という名前の由来は、五行思想から来ているんですね。土星の英語名(サターン)の由来について、詳しくは下記をご覧ください。関連:土星の英語名・読み方・由来とは?4.土星に付いているリング状のものって何?では土星に付いているリング状のものについて見ていきましょう。土星に付いているリング状のものは”環(わ)”と呼ばれており、一般的には”輪(わ)”という漢字が使われることも多いです。(正確には”環”という漢字の方が正しい)ではなぜ土星にはこのような環が付いているのかと言うと、それは他の星が土星とぶつかって破壊され粉々になり、その破片が土星の重力に捉えられているからです。土星の環は数十億に及ぶ氷と岩石が集まって形成されていて、大きいもので直径数mとされ、土星の環の様子を表したものが下の図です。このように数多くの氷と岩石が集合して形成されているものが”土星の環”になります。また土星の環はいくつかの層(アルファベット)に分けられており、その中の細かい環の数を数えていくと6000本以上にもなるそうです。上の画像をよく見てみると線が数えきれないほど、重なっているのが分かると思います。ちなみに太陽系惑星の中で環と言えば”土星の環”が有名ですが、実は木星・天王星・海王星にも環は存在しています。ただしそれぞれの環自体は土星のものと比べると規模が小さく、観測するのが難しいためにあまり有名にはなっていません。5.土星における1日と1年についてでは土星における1日と1年について見ていきましょう。私たちが暮らしている地球では1日の長さは24時間で、1年の長さは365日というのは常識ですよね。ですが土星における1日と1年の長さは地球とは異なり、土星の1日の長さは約10.2時間で、1年は約29.46年ほどになります。つまり地球では1年間は365日で、夜→昼→夜の周期は1日(24時間)ですが、土星における1年間は約29.46年で、夜→昼→夜の周期は約10.2時間かかるということです。少しややこしいので、簡単に解説していきます。まず地球における1日というのは、夜が来てまた次の夜が来るまでの時間のことで、1年間は地球が太陽の周りを1周する時間のことを指しています。(時間帯の周期が1周することを1日としているので、朝から朝でも問題なし)地球が夜→昼→夜のように変化するのは地球自身が回っているからで、地球自身が回ることを”地球の自転”、地球が太陽の周りを移動することを”地球の公転”と言います。そして土星も地球と同じように自転と公転をしていますが、その早さは異なります。地球の自転では1日1回転し、地球の公転は365日かかりますが、土星の自転では約10.2時間で1回転し、土星の公転は約29.46年もかかります。土星における1日の長さは約10.2時間、1年の長さは約29.46年なので、土星の自転と公転からそれぞれ1日と1年の長さを知ることができます。ですが水星や金星のように、”自転にかかる時間=1日の長さ”とならない惑星もあるので注意しましょう。関連:なぜ金星の1日の長さは自転周期に比べて短くなるのか?関連:なぜ水星の1日は1年よりも長くなるのかをわかりやすく解説!6.重力の大きさは質量と半径から計算するでは土星の重力の大きさについて見ていきましょう。土星の重力の大きさは、地球の約1.07倍です。つまり土星の重力は、地球よりも少し大きい程度ということになります。この1.07倍というのは地球の質量・半径と、土星の質量・半径から計算することができます。計算の手順としては以下の通りです。まず上のように地球と土星における質量と半径を比較し、土星の質量と半径が地球の何倍なのかをそれぞれ求めていきます。そしてあとは先ほど計算で出した値を上の計算式に入れれば、土星の重力は地球の1.07倍ほどだという計算結果が出てきます。このように土星と地球の質量・半径がそれぞれ分かっていれば、土星の重力が地球のだいたい何倍なのかを計算することができます。関連:重力と重力加速度と重さ(重量)の違いとは?以上が「土星とは?土星の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});7.まとめこれまで説明したことをまとめますと、<土星の特徴>英語名は、Saturn(サターン)。土星の由来は、五行思想(火・水・木・金・土)から来ている。平均温度は-130℃ほど。大気は主に水素・ヘリウムで構成されている。リング状のものは”環(わ)”と呼ばれ、他の星が粉々になった破片(主に氷と岩石)で形成されている。土星の1日の長さは約10.2時間で、1年は約29.46年ほど。土星の重力は地球と比べると約1.07倍ほど。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒天王星とは?天王星の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!⇒光年とは何かをわかりやすく解説!1光年の距離はどのくらい?⇒銀河と銀河系と太陽系の違いとは?⇒月はなぜ光るのか?太陽と地球と月の位置関係をわかりやすく図で解説!⇒月齢とは?月齢と月の満ち欠けの関係をわかりやすく図で解説!⇒冥王星が惑星から外れた理由を分かりやすく解説!⇒なぜ太陽は東から昇って、西に沈むのか?⇒なぜ太陽と月は地球とぶつからないのか?仕組みを簡単に図で解説!⇒太陽系とは何かをわかりやすく図で解説!⇒重力加速度とは?仕組みを分かりやすく図解!
-
さて”天王星”は私たちが暮らしている地球と同じ惑星の仲間で、太陽系惑星を表す「すいきんちかもくどってんかい」というフレーズにも登場します。天王星は太陽系の惑星だということは多くの人が知っていますが、一体どのような惑星なのか、その特徴について知っている人は少ないです。そこでこのページでは、天王星の表面温度・大気・重力などの特徴を解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次天王星の特徴について構成物質と大気とは?天王星と呼ばれる由来とは?天王星における1日と1年について重力の大きさは質量と半径から計算するまとめ1.天王星の特徴について※上は天王星の写真では天王星の特徴について見ていきましょう。天王星とは太陽系の惑星において、7番目に太陽に近い惑星のことです。そんな天王星の特徴について、それぞれ簡単にまとめたものが下のようになります。項目天王星の特徴英語名Uranus(ユラナス)表面温度平均温度-205℃大気主に水素・ヘリウム・メタン質量14.53倍(地球を1)大きさ(直径)4.01倍(地球を1)重力0.9倍(地球を1)太陽からの平均距離28億7500万km自転周期約17.9時間公転周期約84年(30660日)項目1項目2)★ -->次の章から天王星について詳しく解説していきます。2.構成物質と大気とは?では天王星を構成している物質と大気について見ていきましょう。まず天王星を構成している物質は下のようになります。上図のように天王星の外層には水素ガスを主成分として、ヘリウム・メタンを含んだ層が存在します。そして内層には水・メタン・アンモニアなどからできている氷で構成され、天王星の核の部分は、岩石や鉄・ニッケルなどの金属で構成されていると考えられています。天王星が青緑色に見えるのは、上層部分の大気に含まれるメタンによるものです。また天王星の大気は主に水素・ヘリウム・メタンから構成され、それ以外にもわずかにアンモニア・エタン・アセチレンなどの物質が含まれています。当然ですが、天王星の大気では人間は呼吸することはできません。関連:空気と大気の違いとは?3.天王星と呼ばれる由来とは?では天王星と呼ばれる由来について見ていきましょう。天王星と呼ばれる由来としては、ローマ神話における天空神である”Uranus(ウラヌス)”からきています。天王星はきれいな水色の見た目をしており、その青空のような見た目から、ローマ神話における天空の神であるウラヌス(ラテン語)と名付けられました。”Uranus(ウラヌス)”はラテン語(ローマでの言語)で、それを英語にした場合に”Uranus(ユラナス)”となります。なので天王星の英語名である”Uranus(ユラナス)”は、ローマ神話における天空神の”Uranus(ウラヌス)”からきているんですね。そして日本語名での”天王星”の由来についても、ローマ神話における天空神ウラヌスからきています。”天空の神=天空の王様”とされ、そこから”天空の王様の星”なので略して”天王星”です。どの言語で表すかによって言葉が違うのでややこしいですが、簡単にまとめると、天王星(日本語)=ユラナス(英語)=ウラヌス(ラテン語)となります。4.天王星における1日と1年についてでは天王星における1日と1年について見ていきましょう。私たちが暮らしている地球では1日の長さは24時間で、1年の長さは365日というのは常識ですよね。ですが天王星における1日と1年の長さは地球とは異なり、天王星の1日の長さは約17.9時間で、1年は約84年ほどになります。つまり地球では1年間は365日で、夜→昼→夜の周期は1日(24時間)ですが、天王星における1年間は約84年で、夜→昼→夜の周期は約17.9時間かかるということです。少しややこしいので、簡単に解説していきます。まず地球における1日というのは、夜が来てまた次の夜が来るまでの時間のことで、1年間は地球が太陽の周りを1周する時間のことを指しています。(時間帯の周期が1周することを1日としているので、朝から朝でも問題なし)地球が夜→昼→夜のように変化するのは地球自身が回っているからで、地球自身が回ることを”地球の自転”、地球が太陽の周りを移動することを”地球の公転”と言います。そして天王星も地球と同じように自転と公転をしていますが、その早さは異なります。地球の自転では1日1回転し、地球の公転は365日かかりますが、天王星の自転では約17.9時間で1回転し、天王星の公転は約84年もかかります。天王星における1日の長さは約17.9時間、1年の長さは約84年なので、天王星の自転と公転からそれぞれ1日と1年の長さを知ることができます。ですが水星や金星のように、”自転にかかる時間=1日の長さ”とならない惑星もあるので注意しましょう。関連:なぜ金星の1日の長さは自転周期に比べて短くなるのか?関連:なぜ水星の1日は1年よりも長くなるのかをわかりやすく解説!5.重力の大きさは質量と半径から計算するでは天王星の重力の大きさについて見ていきましょう。天王星の重力の大きさは、地球の約0.9倍です。つまり天王星の重力は、地球よりも少し小さい程度ということになります。この0.9倍というのは地球の質量・半径と、天王星の質量・半径から計算することができます。計算の手順としては以下の通りです。まず上のように地球と天王星における質量と半径を比較し、天王星の質量と半径が地球の何倍なのかをそれぞれ求めていきます。そしてあとは先ほど計算で出した値を上の計算式に入れれば、天王星の重力は地球の0.9倍ほどだという計算結果が出てきます。このように天王星と地球の質量・半径がそれぞれ分かっていれば、天王星の重力が地球のだいたい何倍なのかを計算することができます。関連:重力と重力加速度と重さ(重量)の違いとは?以上が「天王星とは?天王星の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});6.まとめこれまで説明したことをまとめますと、<天王星の特徴>英語名は、Uranus(ユラナス)。天王星の由来は、ローマ神話における天空の神が元になっていて、”天空の王様(神様)の星”という意味からきている。平均温度は-205℃。大気は主に水素・ヘリウム・メタンで構成されている。天王星の1日の長さは約17.9時間で、1年は約84年ほど。天王星の重力は地球と比べると約0.9倍ほど。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒海王星とは?海王星の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!⇒光年とは何かをわかりやすく解説!1光年の距離はどのくらい?⇒銀河と銀河系と太陽系の違いとは?⇒月はなぜ光るのか?太陽と地球と月の位置関係をわかりやすく図で解説!⇒月齢とは?月齢と月の満ち欠けの関係をわかりやすく図で解説!⇒なぜ金星の1日の長さは自転周期に比べて短くなるのか?⇒なぜ太陽は東から昇って、西に沈むのか?⇒なぜ太陽と月は地球とぶつからないのか?仕組みを簡単に図で解説!⇒太陽系とは何かをわかりやすく図で解説!⇒重力加速度とは?仕組みを分かりやすく図解!
-
さて”海王星”は私たちが暮らしている地球と同じ惑星の仲間で、太陽系惑星を表す「すいきんちかもくどってんかい」というフレーズにも登場します。海王星は太陽系の惑星だということは多くの人が知っていますが、一体どのような惑星なのか、その特徴について知っている人は少ないです。そこでこのページでは、海王星の表面温度・大気・重力などの特徴を解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次海王星の特徴について構成物質と大気とは?海王星と呼ばれる由来とは?海王星における1日と1年について重力の大きさは質量と半径から計算するまとめ1.海王星の特徴について※上は海王星の写真では海王星の特徴について見ていきましょう。海王星とは太陽系の惑星において、8番目(最も遠い)に太陽に近い惑星のことです。そんな海王星の特徴について、それぞれ簡単にまとめたものが下のようになります。項目海王星の特徴英語名Neptune(ネプチューン)表面温度平均温度-220℃大気主に水素・ヘリウム・メタン質量17.14倍(地球を1)大きさ(直径)3.88倍(地球を1)重力1.14倍(地球を1)太陽からの平均距離45億440万km自転周期約19.1時間公転周期約164.8年(60152日)項目1項目2)★ -->次の章から海王星について詳しく解説していきます。2.構成物質と大気とは?では海王星を構成している物質と大気について見ていきましょう。まず海王星を構成している物質は下のようになります。上図のように海王星の外層には水素ガスを主成分として、ヘリウム・メタンを含んだ層が存在します。そして内層には水・メタン・アンモニアなどからできている氷で構成され、海王星の核の部分は、岩石や鉄・ニッケルなどの金属で構成されていると考えられています。海王星の色は上層部分の大気に含まれるメタンによるものですが、天王星と海王星のメタン含有率はあまり変わらないのに、海王星の方が濃い青色をしています。この海王星と天王星の色が異なる理由としては、海王星に存在する未知の化合物によるものだとされています。また海王星の大気は主に水素・ヘリウム・メタンから構成され、それ以外にもわずかに重水素化水素・エタンなどの物質が含まれています。当然ですが、海王星の大気では人間は呼吸することはできません。関連:空気と大気の違いとは?3.海王星と呼ばれる由来とは?では海王星と呼ばれる由来について見ていきましょう。海王星と呼ばれる由来としては、ローマ神話における海の神である”Neptunus(ネプトゥーヌス)”からきています。海王星はきれいな青色の見た目をしており、その海のような見た目から、ローマ神話における海の神であるネプトゥーヌス(ラテン語)と名付けられました。”Neptunus(ネプトゥーヌス)”はラテン語(ローマでの言語)で、それを英語にした場合に”Neptune(ネプチューン)”となります。なので海王星の英語名である”Neptune(ネプチューン)”は、ローマ神話における海の神の”Neptunus(ネプトゥーヌス)”からきているんですね。そして日本語名での”海王星”の由来についても、ローマ神話における海の神ネプトゥーヌスからきています。”海の神=海の王様”とされ、そこから”海の王様の星”なので略して”海王星”です。どの言語で表すかによって言葉が違うのでややこしいですが、簡単にまとめると、海王星(日本語)=ネプチューン(英語)=ネプトゥーヌス(ラテン語)となります。4.海王星における1日と1年についてでは海王星における1日と1年について見ていきましょう。私たちが暮らしている地球では1日の長さは24時間で、1年の長さは365日というのは常識ですよね。ですが海王星における1日と1年の長さは地球とは異なり、海王星の1日の長さは約19.1時間で、1年は約164.8年ほどになります。つまり地球では1年間は365日で、夜→昼→夜の周期は1日(24時間)ですが、海王星における1年間は約164.8年で、夜→昼→夜の周期は約19.1時間かかるということです。少しややこしいので、簡単に解説していきます。まず地球における1日というのは、夜が来てまた次の夜が来るまでの時間のことで、1年間は地球が太陽の周りを1周する時間のことを指しています。(時間帯の周期が1周することを1日としているので、朝から朝でも問題なし)地球が夜→昼→夜のように変化するのは地球自身が回っているからで、地球自身が回ることを”地球の自転”、地球が太陽の周りを移動することを”地球の公転”と言います。そして海王星も地球と同じように自転と公転をしていますが、その早さは異なります。地球の自転では1日1回転し、地球の公転は365日かかりますが、海王星の自転では約19.1時間で1回転し、海王星の公転は約164.8年もかかります。海王星における1日の長さは約19.1時間、1年の長さは約164.8年なので、海王星の自転と公転からそれぞれ1日と1年の長さを知ることができます。ですが水星や金星のように、”自転にかかる時間=1日の長さ”とならない惑星もあるので注意しましょう。関連:なぜ金星の1日の長さは自転周期に比べて短くなるのか?関連:なぜ水星の1日は1年よりも長くなるのかをわかりやすく解説!5.重力の大きさは質量と半径から計算するでは海王星の重力の大きさについて見ていきましょう。海王星の重力の大きさは、地球の約1.14倍です。つまり海王星の重力は、地球よりも少し大きい程度ということになります。この1.14倍というのは地球の質量・半径と、海王星の質量・半径から計算することができます。計算の手順としては以下の通りです。まず上のように地球と海王星における質量と半径を比較し、海王星の質量と半径が地球の何倍なのかをそれぞれ求めていきます。そしてあとは先ほど計算で出した値を上の計算式に入れれば、海王星の重力は地球の1.14倍ほどだという計算結果が出てきます。このように海王星と地球の質量・半径がそれぞれ分かっていれば、海王星の重力が地球のだいたい何倍なのかを計算することができます。関連:重力と重力加速度と重さ(重量)の違いとは?以上が「海王星とは?海王星の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});6.まとめこれまで説明したことをまとめますと、<海王星の特徴>英語名は、Neptune(ネプチューン)。海王星の由来は、ローマ神話における海の神が元になっていて、”海の王様(神様)の星”という意味からきている。平均温度は-220℃。大気は主に水素・ヘリウム・メタンで構成されている。海王星の1日の長さは約19.1時間で、1年は約164.8年ほど。海王星の重力は地球と比べると約1.14倍ほど。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒冥王星とは?冥王星の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!⇒光年とは何かをわかりやすく解説!1光年の距離はどのくらい?⇒銀河と銀河系と太陽系の違いとは?⇒月はなぜ光るのか?太陽と地球と月の位置関係をわかりやすく図で解説!⇒月齢とは?月齢と月の満ち欠けの関係をわかりやすく図で解説!⇒水星とは?水星の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!⇒なぜ太陽は東から昇って、西に沈むのか?⇒なぜ太陽と月は地球とぶつからないのか?仕組みを簡単に図で解説!⇒太陽系とは何かをわかりやすく図で解説!⇒重力加速度とは?仕組みを分かりやすく図解!
-
さて冥王星は2006年までは太陽系における”惑星”でしたが、2006年以降からは”準惑星”という分類に変わってしまいました。冥王星の分類が準惑星に変わったことは多くの人が知っていますが、冥王星にはどのような特徴があるのかを知っている人は意外と少ないです。そこでこのページでは、冥王星の表面温度・大気・重力などの特徴を解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次冥王星の特徴について構成物質と大気とは?冥王星と呼ばれる由来とは?なぜ冥王星は”準惑星”になってしまったのか?冥王星における1日と1年について重力の大きさは質量と半径から計算するまとめ1.冥王星の特徴について※上の画像は冥王星の写真では冥王星の特徴について見ていきましょう。冥王星とは太陽系における準惑星のことで、海王星の外側を移動している星のことです。そんな冥王星の特徴について、それぞれ簡単にまとめたものが下のようになります。項目冥王星の特徴英語名Pluto(プルートゥ)表面温度-240℃~-218℃(平均温度-223℃)大気主に窒素・メタン・一酸化炭素質量0.0022倍(地球を1)大きさ(直径)0.186倍(地球を1)重力0.06倍(地球を1)太陽からの平均距離59億100万km自転周期約6日と9時間公転周期約247.69年項目1項目2)★ -->次の章から冥王星について詳しく解説していきます。2.構成物質と大気とは?では冥王星を構成している物質と大気について見ていきましょう。まず冥王星を構成している物質は下のようになります。上図のように冥王星の外層は窒素・メタン・一酸化炭素の氷で構成され、内層は主に水の氷、核については岩石と鉄などの金属で構成されていると考えられています。冥王星の表面が少し黄色みがかっている理由は、太陽から届く紫外線によって冥王星の表面に存在する窒素・メタンが分解・再結合され、”ソリン”と呼ばれる物質を作ることによるものです。ソリンは大気中の有機化合物が紫外線によって化学変化することで生成される物質で、炭化水素類の総称のこと指しています。そしてソリンはその成分によって茶色から黄色まで多くの色になるため、冥王星の表面の色が黄色がかっているというわけです。また冥王星の大気は主に窒素・メタン・一酸化炭素から構成されています。ただし2000年に冥王星の大気の観測を行ったときよりも、約10年後に再び大気の観測を行ったときの方が、一酸化炭素の量が2倍以上も増えていることが判明しています。大気中の一酸化炭素が増加している理由については、はっきりとしたことはまだ分かっていないそうです。ちなみに当然ですが、冥王星の大気では人間は呼吸することはできません。関連:空気と大気の違いとは?関連:一酸化炭素中毒とは?発生する原因と仕組みについて簡単に解説!3.冥王星と呼ばれる由来とは?では冥王星と呼ばれる由来について見ていきましょう。冥王星と呼ばれる由来としては、ローマ神話における冥界の神である”Pluto(プルートー)”からきています。冥王星は太陽系惑星(2006年まで)の中で最も薄暗い外側を移動していたことから、ローマ神話における冥界を司る神であるプルートー(ラテン語)と名付けられました。冥界(めいかい)とは死後の世界のことなので、プルートーは死後の世界を支配しているということです。”Pluto(プルートー)”はラテン語(ローマでの言語)で、それを英語にした場合に”Pluto(プルートゥ)”となります。なので冥王星の英語名である”Pluto(プルートゥ)”は、ローマ神話における冥界の神の”Pluto(プルートー)”からきているんですね。そして日本語名での”冥王星”の由来についても、ローマ神話における冥界の神プルートーからきています。”冥界の神=冥界の王様”とされ、そこから”冥界の王様の星”なので略して”冥王星”です。どの言語で表すかによって言葉が違うのでややこしいですが、簡単にまとめると、冥王星(日本語)=プルートゥ(英語)=プルートー(ラテン語)となります。4.なぜ冥王星は”準惑星”になってしまったのか?ではなぜ冥王星は”惑星”から”準惑星”という分類に変わったのかを見ていきましょう。冥王星が”準惑星”という分類に変更された理由は、冥王星の近くに冥王星と同程度の大きさの天体”エリス”が発見されたからです。冥王星は1930年にその存在が明らかにされており、当時は地球の質量と同等であると考えられていました。ですが近年の技術の発展により、冥王星が地球よりも明らかに小さいことが判明しました。(地球と比べると質量は0.0022倍、直径は0.186倍ほど)冥王星は地球の衛星である月よりも小さいです。そして1992年以降に冥王星に似た1000を超える天体が発見され、冥王星が本当に惑星の分類で良いのか、惑星の定義を明確に決めることにしました。そこで2006年8月にチェコのプラハで国際天文学連合(IAU)総会が開かれ、以下の3つの条件すべてに当てはまった天体が”惑星”であると定義されました。太陽の周りを公転していること。十分に大きな質量を持ち、自身の重力により球状(丸く)になっていること。軌道上の天体を排除していること。3つ目の条件は、自身の重力で他の天体を引き寄せて吸収したり、自身とぶつからせることで、その軌道上から他の天体を排除していることを条件としています。つまり冥王星の場合は、自身の重力で他の天体を排除しているとは言い切れず、”惑星”から”準惑星”という分類に格下げされたということになりますね。これにより2006年8月以降からは、冥王星は”準惑星”という分類になってしまいました。5.冥王星における1日と1年についてでは冥王星における1日と1年について見ていきましょう。私たちが暮らしている地球では1日の長さは24時間で、1年の長さは365日というのは常識ですよね。ですが冥王星における1日と1年の長さは地球とは異なり、冥王星の1日の長さは約6日と9時間で、1年は約247.69年ほどになります。つまり地球では1年間は365日で、夜→昼→夜の周期は1日(24時間)ですが、冥王星における1年間は約247.69年で、夜→昼→夜の周期は約6日と9時間かかるということです。少しややこしいので、簡単に解説していきます。まず地球における1日というのは、夜が来てまた次の夜が来るまでの時間のことで、1年間は地球が太陽の周りを1周する時間のことを指しています。(時間帯の周期が1周することを1日としているので、朝から朝でも問題なし)地球が夜→昼→夜のように変化するのは地球自身が回っているからで、地球自身が回ることを”地球の自転”、地球が太陽の周りを移動することを”地球の公転”と言います。そして冥王星も地球と同じように自転と公転をしていますが、その早さは異なります。地球の自転では1日1回転し、地球の公転は365日かかりますが、冥王星の自転では約6日と9時間で1回転し、冥王星の公転は約247.69年もかかります。冥王星における1日の長さは約6日と9時間、1年の長さは約247.69年なので、冥王星の自転と公転からそれぞれ1日と1年の長さを知ることができます。ですが水星や金星のように、”自転にかかる時間=1日の長さ”とならない惑星もあるので注意しましょう。関連:なぜ金星の1日の長さは自転周期に比べて短くなるのか?関連:なぜ水星の1日は1年よりも長くなるのかをわかりやすく解説!6.重力の大きさは質量と半径から計算するでは冥王星の重力の大きさについて見ていきましょう。冥王星の重力の大きさは、地球の約0.06倍です。つまり冥王星の重力は、地球よりもかなり小さいということになります。この0.06倍というのは地球の質量・半径と、冥王星の質量・半径から計算することができます。計算の手順としては以下の通りです。まず上のように地球と冥王星における質量と半径を比較し、冥王星の質量と半径が地球の何倍なのかをそれぞれ求めていきます。そしてあとは先ほど計算で出した値を上の計算式に入れれば、冥王星の重力は地球の0.06倍ほどだという計算結果が出てきます。このように冥王星と地球の質量・半径がそれぞれ分かっていれば、冥王星の重力が地球のだいたい何倍なのかを計算することができます。関連:重力と重力加速度と重さ(重量)の違いとは?以上が「冥王星とは?冥王星の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});7.まとめこれまで説明したことをまとめますと、<冥王星の特徴>英語名は、Pluto(プルートゥ)。冥王星の由来は、ローマ神話における冥界の神が元になっていて、”冥界の王様(神様)の星”という意味からきている。表面温度は-240℃~-218℃(平均温度223℃)。大気は主に窒素・メタン・一酸化炭素で構成されている。冥王星の1日の長さは約6日と9時間で、1年は約247.69年ほど。冥王星の重力は地球と比べると約0.06倍ほど。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒水星とは?水星の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!⇒光年とは何かをわかりやすく解説!1光年の距離はどのくらい?⇒銀河と銀河系と太陽系の違いとは?⇒月はなぜ光るのか?太陽と地球と月の位置関係をわかりやすく図で解説!⇒「すいきんちかもくどってんかい」とは何の順番を表している?⇒なぜ太陽は東から昇って、西に沈むのか?⇒天王星とは?天王星の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!⇒なぜ太陽と月は地球とぶつからないのか?仕組みを簡単に図で解説!⇒太陽系とは何かをわかりやすく図で解説!⇒重力加速度とは?仕組みを分かりやすく図解!
-
さて天気予報で大気という言葉がよく出てきますね。でも大気って何なのだろうと疑問に思ったことはありませんか?そして大気と空気の意味の違いについて理解しないまま、混同させて覚えてしまっている人も多いように感じます。そこでこのページでは、空気と大気の違いについて簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次空気とは?大気とは?空気と大気の違いについて違いその1:”地球と惑星”における捉え方の場合違いその2:”地球のみ”における捉え方の場合まとめ1.空気とは?まず空気とは何なのか見ていきましょう。空気(くうき)とは、地球の表面部分を覆っている混合気体のことを言います。例えば窒素・酸素・アルゴン・二酸化炭素・ネオン・ヘリウムなど、空気は他にもたくさんの種類の気体によって混合されてできています。空気が多くの種類の気体によって混合されているといっても、空気を占める割合のほとんどが窒素(約8割)と酸素(約2割)です。なので空気は主に窒素と酸素で構成されているといっても過言ではありません。また空気は混合気体ですが、基本的に人間が呼吸することができるものを空気と呼んでいます。関連:空気とは何か?また高い場所ほど空気が薄くなる理由とは?2.大気とは?次に大気とはどのようなものなのか見ていきましょう。大気(たいき)とは、惑星の表面を覆っている気体のことを言います。惑星と言うのは、水星・金星・地球・火星・木星・土星・天王星・海王星などのことです。そしてこれらの惑星自体それぞれが重力を持っていて、惑星周辺に存在していた気体がその重力に捕まります。大気を図にしてみるとこんな感じです。上の図のように惑星の持つ重力に引き寄せられた気体が、その惑星の周りを覆うようになります。この惑星の表面を覆う気体(気体なら何でも構いません)こそが大気です。気体は目で捉えることができない無色透明なものが多いので、重力がかからないと思っている人がいますがそれは違います。たとえ無色透明な気体であったとしても、その気体にも質量があるため重力はかかります。なので惑星の重力に捕まった気体は、惑星の表面を覆う気体である大気になってしまうんですね。惑星の表面を覆っている気体であればその気体の種類によらずそれは大気になります。また天気予報などで大気という言葉がよく使われていますが、そのときは地球の大気のことを指している場合が多いです。しかし基本的には地球の大気を指していることが多いですが、大気は地球に限らず他の惑星にも存在するということを覚えておきましょう。関連:太陽系とは何かをわかりやすく図で解説!関連:気圧と大気圧の違いとは?3.空気と大気の違いについて空気と大気の違いは、どのような視点で捉えるかによっても異なります。というのは下記の2つの場合で空気と大気の違いが変わるからです。違いその1:”地球と惑星”における捉え方の場合違いその2:”地球のみ”における捉え方の場合では空気と大気の違いについてそれぞれ見ていきましょう。違いその1:”地球と惑星”における捉え方の場合1つ目の空気と大気の違いは、”地球と惑星”における捉え方の場合です。”地球と惑星”における視点で捉えた場合の空気と大気の違いは、地球を覆っている気体なのか惑星を覆っている気体なのかです。空気は地球の表面を覆っている気体のことで、大気は惑星の表面を覆っている気体になります。地球も惑星の種類の中のひとつなので、地球の大気は空気だと言えます。ただ地球の大気=空気ですが、どこの惑星でも大気=空気とは言えません。ちなみに金星や木星にも大気はありますが、その大気は空気ではありません。金星や木星の大気は地球の空気のように窒素や酸素で構成されているわけではないです。そしていまのところ地球以外の惑星で空気と呼べるものは発見できていません。空気と大気の違いについてイメージしやすいように簡単に図にしましたのでご覧ください。あくまで人間が呼吸することができる混合気体のことを空気と言っているだけです。大気だけなら金星や木星にも存在していますが、地球の大気(空気)と構成している気体が異なるため人間の呼吸に使用することができません。だから大気自体は地球以外の惑星(金星や木星など)にも存在しますが、空気という形で存在している大気は地球にしかないものになります。関連:銀河と銀河系と太陽系の違いとは?違いその2:”地球のみ”における捉え方の場合2つ目の空気と大気の違いは、”地球のみ”における捉え方の場合です。”地球のみ”の視点で捉えた場合の空気と大気の違いは、大気のほんの一部分なのか大気全てなのかです。地球の大気圏(大気が存在する範囲)は地表から約500km上空までありますが、その大気圏の中で空気と呼べるものは下層にしか存在しません。人間が呼吸できる限界が約8000mと言われているので、それよりも高度が高くなると人体は順応できなくなります。ただこの限界というのは低酸素の状態に慣れている人(登山家など)の限界ですので、普通の人の高度限界はもっと下がります。低酸素の状態に慣れていない人だと約2500mぐらいから低酸素状態になり、頭痛・めまい・呼吸困難などに陥ってしまう可能性があるので注意が必要です。なので地球で人間が呼吸できる空気があるのは、高度約8000mまでになります。以上のことを簡単に表すと下図のようになります。ですので”地球のみ”における空気は高度8000mまでの大気のことを指していて、大気は高度500kmまでに存在する気体のこと(空気を含む)を指しています。このように”地球と惑星”で捉えるのか”地球のみ”で捉えるのかによって、空気と大気の違いが少し異なるということを覚えておきましょう。以上が「空気と大気の違いとは?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、空気とは、地球の表面部分を覆っている混合気体のこと。大気とは、惑星の表面を覆っている気体のこと。違いは、地球を覆っている気体なのか惑星を覆っている気体なのか。地球だけでみたときの違いは、大気のほんの一部分なのか大気全てなのか。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒気圧とは何かをわかりやすく解説!なぜ気圧で人はつぶされないのか?⇒煙とは?黒い煙や白い煙の正体って何?⇒気圧と沸点の関係について。気圧によって沸点が変化する仕組みとは?⇒山でお菓子の袋が膨らむ仕組みとは?分かりやすく図で解説!⇒風の正体とは?どんな原理で吹いているのか?⇒熱気球とは?また熱気球はどんな原理で空中に浮いているのか?⇒空気の膨張とは何か?空気の温度によって体積が変化する仕組みとは?⇒一酸化炭素中毒とは?発生する原因と仕組みについて簡単に解説!⇒空気抵抗とは?なぜ物体の速度が上がると空気抵抗は大きくなるのか?⇒植物の光合成と呼吸の違いとは?植物は二酸化炭素を排出するのか?