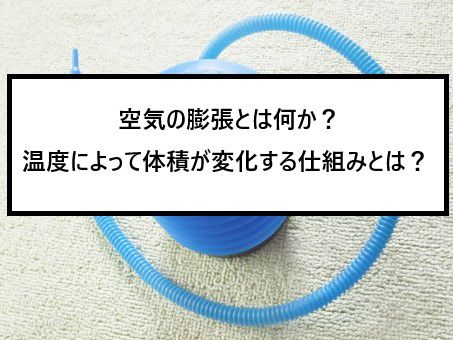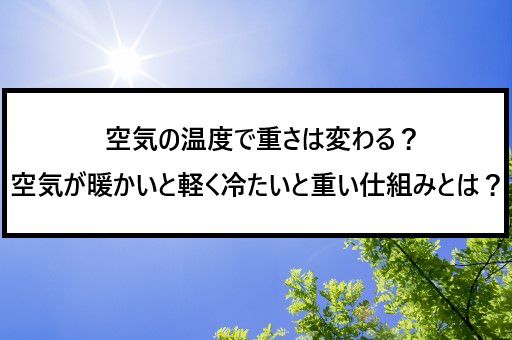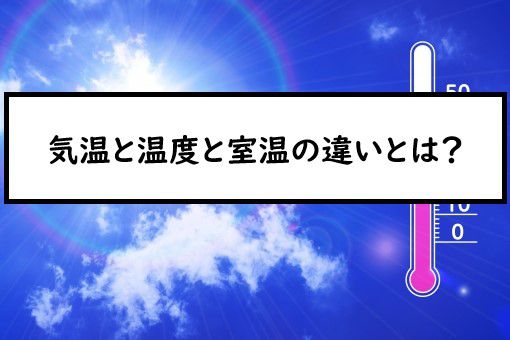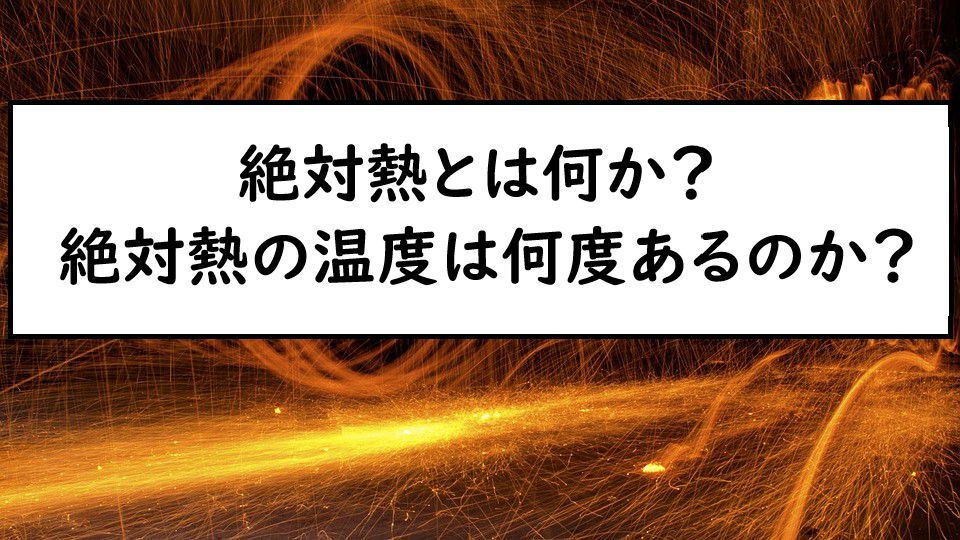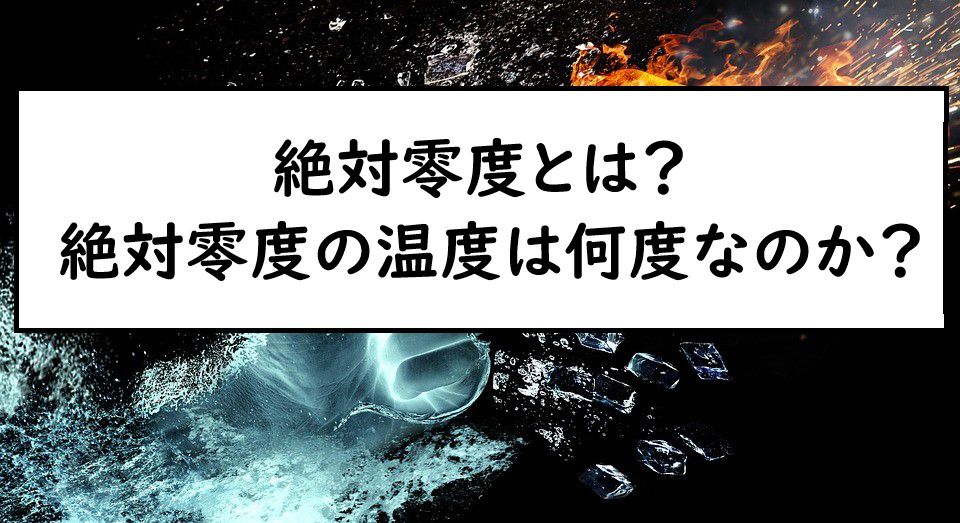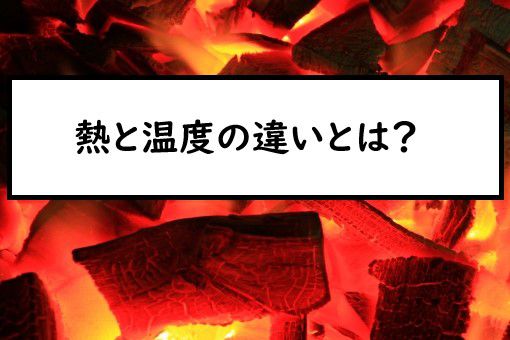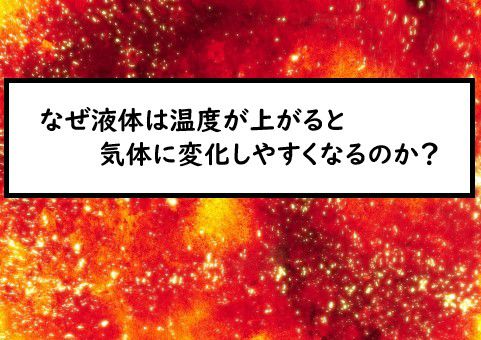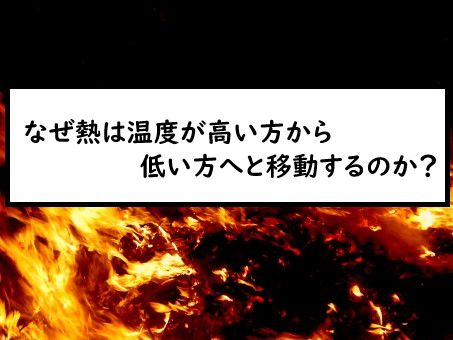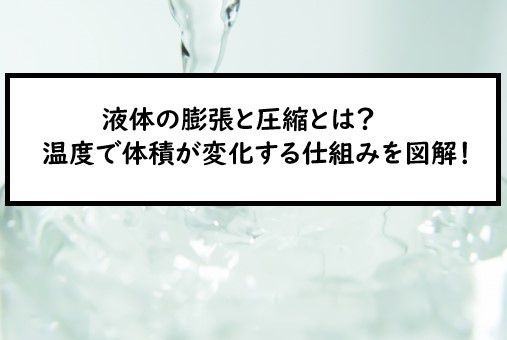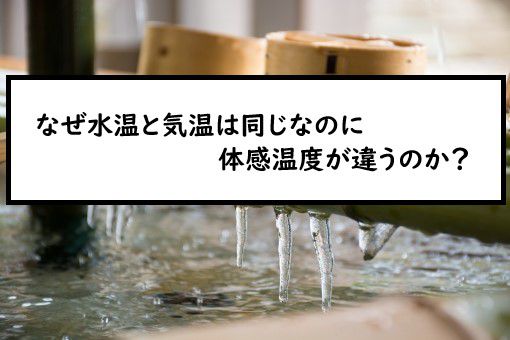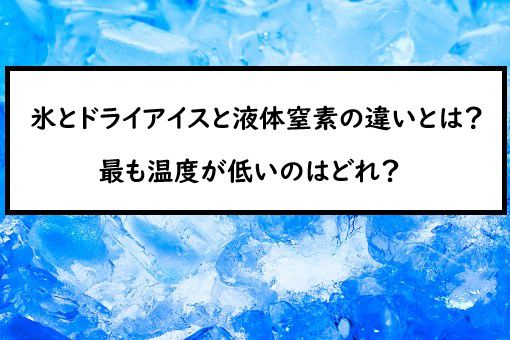さてあなたは空気の膨張という言葉を聞いたことがあるでしょうか。空気自体が無色透明で目には見えないため、膨張するといってもイメージするのが難しいです。そして空気というのはその温度によって体積が変化します。しかしなぜ空気の体積が変化するのかその仕組みを理解している人は少ないです。そこでこのページでは空気の膨張とは何か?また空気の温度によって体積が変化する仕組みを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次空気の膨張とは何か?空気の温度によって体積が変化する仕組みについて空気の温度を変化させない場合(通常時)空気の温度を上げた場合空気の温度を下げた場合まとめ1.空気の膨張とは何か?では空気の膨張とは何か見ていきましょう。空気の膨張(ぼうちょう)とは、空気が熱によって暖められることで体積が大きくなることを言います。また熱で暖めることで空気が膨張するのですから、反対に冷やすことで空気は圧縮します。空気が圧縮すると体積は小さくなります。そして暖めたり冷やしたりすることで体積が変化するのは空気だけではありません。例えば鉄などの金属や他の物体に対しても言えることです。基本的に膨張するか圧縮するかは、その物体の状態(気体・液体・固体)に関係なく起こります。このように暖めたり冷やしたりすることで膨張・圧縮するのは、空気だけでなく他の多くの物体にも当てはまる性質なんですね。空気の膨張 → 体積が大きくなる空気の圧縮 → 体積が小さくなるちなみに空気は暖めたり冷やしたりする以外でも体積が変化することがあり、熱を加えないで膨張したり圧縮することを断熱膨張・断熱圧縮と言います。関連:断熱膨張と断熱圧縮とは?これらによって温度が変化する仕組みとは?なので空気の体積を変化させる方法には、熱を加える方法と熱を加えない方法の2通りがあるということになります。このページでは主に熱を加えたときの空気の体積変化の仕組みを説明しています。ではなぜ空気は暖めれば膨張し、冷やされれば圧縮するのでしょうか?次の章で空気の温度によって体積が変化する仕組みを見ていきましょう。関連:空気の温度で重さは変わる?暖かい空気は軽く冷たい空気が重い仕組みとは?関連:熱気球とは?また熱気球はどんな原理で空中に浮いているのか?2.空気の温度によって体積が変化する仕組みについてさて空気の温度によって体積が変化する仕組みを説明していきます。まず前提として空気だけでなくどんな物体においても温度というのは、その物体の分子の運動によって決まっているということを知っておかなければなりません。分子が激しく動いていればその物体の温度は高くなり、分子の動きが穏やかであればその物体の温度は低くなります。このように物体の温度を決めているのは、その物体を構成している分子の運動になります。空気にも空気分子というものが存在しています。空気というのは下の図のようなものだとイメージしてください。このイメージで空気の温度が高い状態と低い状態を表すと下図のようになります。あくまでもこの図は空気の一部をイメージしたものなので、この空気の塊以外にも周囲に空気はたくさん存在しています。なのでこの周囲にも同じような空気の塊がぎゅうぎゅうに詰まっているとイメージしてください。さて本題に入って空気の温度によって体積が変化する理由は、空気分子が空気の壁(図の中だと○のこと)を押す力が変化するからです。空気の温度が変化すると、空気分子の動きも変化します。そして空気分子の動きが激しくなれば空気の壁を押す力も強くなり、空気分子の動きが穏やかであれば空気の壁を押す力も弱くなります。つまり空気の体積の大小というのは、空気分子が空気の壁を押す力によって決まります。それでは以上のことを踏まえて空気の温度を上げた場合と下げた場合で、空気の体積が変化する仕組みについて詳しく説明していきます。関連:温度とは何か?物体の状態変化と温度の関係について解説!空気の温度を変化させない場合(通常時)まずは温度を変化させないときは空気の体積が、どのような状態になっているのかを説明していきます。空気の温度を変化させなければ、空気の体積はほぼ一定のままキープされるので変化しません。では空気の体積がキープされているときはどのような状態なのか下図をご覧ください。空気はお互いを押し合ってぎゅうぎゅうに詰まっているため、周囲を他の空気に取り囲まれているので他の空気分子の力を受けます。そして空気の体積が一定にキープされている状態というのは上図のように、内側の空気分子と外側の空気分子の空気の壁を押す力が釣り合っているということを意味します。なので簡単に言えば、内側と外側の空気分子の押す力が釣り合っていなければ空気の体積は変化することになります。空気の温度を上げた場合空気を暖めて空気の温度を上げると体積は大きくなります(空気の膨張)。そして空気を暖めるということは、空気分子の動きを激しくさせ空気の壁を押す力を強くするということです。暖められた空気分子の動きは激しくなって壁を押す力は強くなりますが、外側の暖められていない空気分子の動きは変わらないのでそのままの状態です。そうすると内側と外側の空気の壁を押す釣り合っていた力が崩れます。なので暖められた空気分子によって空気の壁を押す力が、周囲の空気分子の力(外側)よりも強くなるからその空気の体積は大きくなるんですね。これが空気を暖めて温度を上げた場合に起こる空気の膨張の仕組みです。関連:ピンポン玉のへこみの直し方とは?またへこみが直る仕組みについて空気の温度を下げた場合空気を冷やして空気の温度を下げると体積は小さくなります(空気の圧縮)。そして空気を冷やすということは、空気分子の動きを穏やかにさせ空気の壁を押す力を弱くするということです。基本的に考え方は空気の温度を上げたときと同じです。空気を冷やすことによって空気分子の動きが穏やかになるため、内側から空気の壁を押す力は弱くなります。しかし冷やされた空気分子の押す力は弱くなりますが、その周辺に存在する空気分子は温度が変化しないのでそのままです。なので冷やされた空気分子の押す力の方が、外側の空気分子(外側)よりも弱くなってしまうため空気の体積は小さくなるんですね。これが空気を冷やして温度を下げた場合に起こる空気の圧縮の仕組みです。関連:絶対零度とは?また絶対零度の温度は何度なのか?以上が「空気の膨張とは何か?空気の温度によって体積が変化する仕組みとは?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、空気の膨張とは、空気が熱によって暖められることで体積が大きくなること。空気を膨張させるには熱による方法と、断熱膨張の2通りがある。空気の温度によって体積が変化するのは、空気分子が空気の壁を押す力が変化するから。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒山でお菓子の袋が膨らむ仕組みとは?分かりやすく図で解説!⇒空気と大気の違いとは?⇒断熱膨張とは?また断熱圧縮とは?どんな原理で温度変化するのか?⇒気圧と大気圧の違いとは?⇒風の正体とは?風はどんな原理で吹いているのか?⇒風船にヘリウムガスを入れると空中に浮く理由とは?⇒マシュマロを電子レンジでチンすると膨らむ仕組みを簡単に解説!⇒ドライアイスを密閉した容器に入れると爆発する仕組みとは?⇒粉塵爆発とは何か?粉塵爆発の原理をわかりやすく図で解説!⇒真空とは何か?分かりやすく図で解説!
ギモン雑学
「 温度 」の検索結果
-
-
さて暖かい空気が軽くなって、冷たい空気は重くなるという話を聞いたことがないでしょうか。これが本当なら空気は温度によって重さが変化することになりますが、本当に空気は温度で重さが変わるのでしょうか?そしてなぜ暖かい空気が軽くなって冷たい空気は重くなるのか、その仕組みを知りたいと疑問に感じている人も多いはずです。そこでこのページでは空気の温度で重さは変わるのか?また暖かい空気が軽くなり、冷たい空気が重くなる仕組みを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次空気の温度で重さは変わるのか?どちらが重いのかは密度で判断する暖かい空気が上昇して空気が下降する仕組みまとめ1.空気の温度で重さは変わるのか?では空気の温度で重さは変わるのかどうか見ていきましょう。結論から言ってしまうと、空気の温度が変化しても空気自体の重さは変わりません。まず空気というのは温度によって膨張・圧縮します。空気が膨張・圧縮するということは簡単に言えば、空気の体積が大きくなったり(膨張)小さくなったり(圧縮)するということです。上の図は空気の温度と体積・重さの関係をそれぞれ表したものです。このように空気を冷やしたり暖めたりすることで、空気自体の体積は変化しますが重さは変わりません。なので空気の体積が大きくなっても小さくなっても、もとの空気の重さと同じままなんですね。暖かい空気は軽くなるから上昇して、冷たい空気は重くなるから下降するというような話をよく聞きますよね。確かに暖かい空気は上昇して、冷たい空気が下降するというのは事実です。しかし空気を暖めても冷やしても空気自体の重さは変わりません。では空気を暖めると上昇して、冷やすと下降する理由は何なのでしょうか?それは、空気の温度が変化することで、その空気の密度が変わるからです。関連:密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?次の章でどちらが重いのかは密度で判断するについて解説していきますね。2.どちらが重いのかは密度で判断するではどちらが重いのかを考えるときに密度が重要になる理由を説明していきます。まず密度(みつど)というのは、体積当たりの重さのことを言います。例えば1kgの金と1kgの綿(わた)があります。この金と綿を比較したときどちらの方が重さがあるでしょうか?正解は、金も綿も同じ重さです。どちらも1kgなのですから重さは同じに決まっています。ですが綿よりも金の方が重いイメージってありますよね。そしてこれについて考えるうえで重要になってくるのが”密度”です。この例みたいに綿のようにどんなに軽いものでも、量を積み重ねていけばいくらでも重さを増やすことが可能です。そうすれば何が軽くて何が重いのか判断することが難しくなりますよね?だから重さを比較するときはそれぞれの物体の密度、つまり同じ体積当たりの重さで考えなければならないということです。このようにそれぞれの物体の密度で考えることでどちらが重いのかが判断できるようになります。軽い重いというのはその時点で何かを基準にしていて、その基準と比較することで軽いか重いかを判断しています。体重が軽くなったというときは以前の体重と比較していて、空気を暖めたら軽くなったというときは暖める前の状態の空気と比較しています。空気自体の重さは変わっていないのに軽くなった重くなったと表現することで、その物体の重さが変化したんだなと勘違いしてしまうこともよくあります。なのでそこには物体の重さが関係しているようにも思えるのですが、実際にどちらが重いのかを比較する場合は物体の重さよりも密度が重要になるので覚えておきましょう。関連:質量とは?重量(重さ)との違いと単位についてまた暖かい空気は上昇して冷たい空気は下降していきますが、空気自体が無色透明の気体なのでイメージするのが難しいですよね。そこで次の章で図を用いてその仕組みを分かりやすく解説していきます。3.暖かい空気が上昇して冷たい空気が下降する仕組みまず暖かい空気は重さは変わらず膨張するので密度は大きくなり、冷たい空気は重さは変わらず圧縮するので密度は小さくなります。暖かい空気のほうが通常の空気よりも密度が小さくなるから軽くなって、冷たい空気のほうが通常の空気よりも密度が大きくなるから重くなります。これは先ほど説明した内容です。では暖かい空気が上昇して、冷たい空気が下降する仕組みについて図を用いて解説していきます。さっそく結論から言ってしまうと、暖かい空気が上昇して冷たい空気が下降する仕組みは、冷たくて重い空気が暖かくて軽い空気を押しのけるからなんですね。これは水の中にモノを沈めたときのことを考えるとイメージしやすくなります。水も空気と同じように流体です。関連:流体とは何かをわかりやすく解説!圧力はどんなかかり方なのか?モノには水に沈むモノと水に沈まないモノがあります。水に沈むモノと沈まないモノの違いは密度の大きさです。上の図のように水よりも密度が大きいものであれば沈み、水よりも密度の小さいものであれば水の上に浮かびます。そして暖かく軽い空気が上昇して、冷たく重い空気が下降する仕組みも水と同じように考えてみてください。冷たい空気の方が暖かい空気よりも密度が大きくて重いので、上に存在していた冷たい空気が暖かい空気を押しのけて下降していきます。なので暖かい空気と冷たい空気を簡単に表すのなら、冷たい空気の上に暖かい空気が乗っかっているような状態です。このようにイメージしてみると、暖かい空気が上昇して冷たい空気が下降する仕組みが理解しやすくなるのではないでしょうか。ちなみに空中に風船が浮かぶのもこれと同じ仕組みです。風船の中に入っている気体が空気よりも密度の小さい気体なので、空気のほうが密度が大きく重いため風船を押しのけて空気がどんどん下へ下へと入っていきます。これによって風船が浮かんでいます。なので風船が空中に浮かんでいるというのは、風船が空気の上に乗っかっているようなイメージになります。関連:熱気球とは?また熱気球はどんな原理で空中に浮いているのか?関連:暖かい水と冷たい水で重さが変わる仕組みとは?以上が「空気の温度で重さは変わる?暖かい空気は軽く冷たい空気が重い仕組みとは?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、温度によって空気の重さ自体は変化しないが、空気の密度については変化する。どちらが重いのか軽いのかは、それぞれの物体の密度で判断すること。冷たい空気は密度が大きく重いため、暖かい空気を押しのけて下に入り込んでいく。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒空気の膨張とは何か?空気の温度によって体積が変化する仕組みとは?⇒断熱膨張とは?また断熱圧縮とは?どんな原理で温度変化するのか?⇒結露とは何か?仕組みを分かりやすく図解!⇒気温と温度と室温の違いとは?⇒熱と温度の違いとは?⇒絶対熱とは何か?絶対熱の温度は何度あるのか?⇒自由落下とは?空気抵抗・重さ・質量は関係ないのかを簡単に解説!⇒真空とは何か?分かりやすく図で解説!⇒なぜ標高が高い所は寒いのか?太陽との距離は関係ないって本当?⇒熱の伝わり方の3種類(伝導・対流・放射)を分かりやすく図で解説!
-
さて日常的によく”気温”と”温度”と”室温”という言葉を聞きます。普段から何気なく使用している言葉で文字的に似ていますが、実はそれぞれの言葉が表しているものは違います。そしてこれらの言葉の違いをあまり理解せずに、普段から使用している人も中にはいるのではないでしょうか?そこでこのページでは、気温と温度と室温の違いについて簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次気温と温度と室温の違いとは?厳密には気温というのは室温を含んでいるまとめ1.気温と温度と室温の違いとは?では気温と温度と室温の違いとは何か見ていきましょう。結論から言ってしまうと気温と温度と室温の違いとしては、温度の種類の中に気温と室温があるということです。温度(おんど)というのは、熱さ・冷たさ(暖かさ・寒さ)などその度合いを表したものです。そして気温(きおん)は大気の温度のことで、外に百葉箱を設置することによって測定されます。大気とは地球における空気のことですので、気温というのは空気の温度と覚えてもらって問題ありません。百葉箱の中には、温度計・湿度計が地面から高さ1.5mになるように設置されている。また室温(しつおん)は室内の温度のことで、室内に温度計を設置して測定されます。なので一般的に室内は室温、外は気温で表されます。ちなみに鉄と水がどれくらいの熱さ・冷たさなのか温度を測定したとき、鉄はそのまま鉄の温度と表され、水なら水温と略して表されることが多いですよね。このように物体によって○温と略されるものと略されないものがあるので覚えておきましょう。(日常的によく使用されているものが略されている傾向にある)関連:空気と大気の違いとは?関連:熱と温度の違いとは?2.厳密には気温というのは室温を含んでいる厳密には気温というのは室温のことも含んでいます。どういうことかというと室温は室内に設置してある温度計を使って、室内の空気の温度を測定しているからです。なので室温というのは、室内における大気(空気)の温度のことなんですね。これは気温という言葉をどのように捉えるかによって、少し意味が違ってきます。気温のことを”百葉箱で測定した大気(空気)の温度”として捉えた場合は、一般的な意味である室外の大気(空気)の温度と捉えることができます。ですが気温のことを”大気(空気)の温度”のみとして捉えた場合は、気温には”室内の気温”と”外の気温”の2つの捉え方ができてしまいます。室内で測定しているのも外で測定してるのについても両方とも、大気(空気)の温度を測定しているということには変わりありません。なのでこのように気温という言葉の捉え方次第では室温を含んでしまいます。ただし、一般的には気温という場合には外の温度のことを表しており、室温という場合には室内の温度のことを表しているので覚えておきましょう。関連:液体温度計の仕組みを簡単に図解!なぜ水銀は使われなくなったのか?関連:室内と屋内の違いとは?以上が「気温と温度と室温の違いとは?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、温度とは、熱さ・冷たさ(暖かさ・寒さ)などその度合いを表したもの。気温とは、大気(地球の場合は空気)の温度のこと。室温とは、室内の温度のこと。これらの違いとしては、温度の種類の中に気温と室温が存在するということ。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒温度とは何か?物体の状態変化と温度の関係について解説!⇒絶対零度とは?また絶対零度の温度は何度なのか?⇒絶対熱とは何か?絶対熱の温度は何度あるのか?⇒ドライアイスとは?ドライアイスから発生する白い煙の正体って何?⇒シンクに熱湯を流すとボコッと音がする理由とは?熱湯は流さない方が良いのか?⇒水が100度に達していないのに蒸発する仕組みとは?⇒熱対流とは何か?熱対流の仕組みをわかりやすく図で解説!⇒なぜ氷は空気中よりも水中の方が溶けやすいのか?⇒なぜ水温と気温は同じなのに体感温度が違うのか?⇒水を沸騰させると発生する泡の正体とは?またなぜ泡は発生するのか?
-
さてあなたは温度というものをご存知でしょうか。私たちの身の回りでは理解しているようで、実はそのことについてほとんど理解していないものがたくさん存在します。温度もその中のひとつで意味は知っていても、温度について詳しく理解している人は少ないように感じます。そこでこのページでは温度とは何か?また物体の状態変化と温度の関係について簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次温度とは何か?温度の高さは何で決まるのか?物体の状態変化と温度の関係について分子運動における物体の温度変化の仕組み容器に入った水を火で暖めた場合容器に入った水を氷で冷やした場合まとめ1.温度とは何か?では温度とは何か見ていきましょう。温度(おんど)とは、物体の熱さ・冷たさ(暖かさ・寒さ)という度合いを表したものです。人によって熱い・冷たいと感じる基準が違うので、ただ単に熱い・冷たいだけでは正しく測定することはできません。そこで物体の熱さ・冷たさを誰でも同じく捉えることができるように、温度という物体の熱さ・冷たさの度合いを表す指標が生まれました。また温度といっても種類はいくつもあり、絶対温度・摂氏・華氏・列氏・蘭氏などが挙げられます。上記の種類の中で私たちが日常的に使用している温度の種類が、摂氏(セルシウス度)で、[℃]という単位で物体の温度が表されます。世界的に広く普及している温度の指標は摂氏ですが、地域によっては摂氏以外の種類が使用されている場所もあります。関連:摂氏と華氏とは何か?また摂氏と華氏の変換方法と違いについて次の章では温度の高さは何で決まるのかを解説します。2.温度の高さは何で決まるのか?では温度の高さは何で決まるのか見ていきましょう。結論から述べると物体の温度の高さは、その物体を構成している原子・分子の運動の大きさで決まります。物体は何でも原子・分子という目に見えない小さな粒で構成されていて、その原子・分子が運動することでその物体の温度の高さが決まります。簡単に言えば、その物体の原子・分子の運動が激しい(動きが速い)ほど温度は高くなり、反対に運動が穏やか(動きが遅い)であればその物体の温度は低くなります。水(液体)を例にして見てみましょう。まず水は水分子という小さな粒がいくつも集まることで構成されています。そして水の温度が低いとき・高いときを表すと下図のようになります。このようにその物体の温度の高さは分子の運動の大きさで決まっています。そして一般的に物体の温度が異なるのは、その物体の持っている熱の大きさが異なるからです。その物体の持っている熱が大きければ温度は高くなり、その物体の持っている熱が小さければ温度は低くなります。実はこの物体の持っている熱の大きさと分子運動というのは同じことを指しています。物体の温度の高さが原子・分子の運動の大きさで決まるのですから、原子・分子の運動の大きさ=その物体の持っている熱エネルギーということになります。簡単に関係をまとめると下記のようになります。原子・分子の運動が激しい(速い)=熱エネルギーが大きい⇒物体の温度が高くなる原子・分子の運動が穏やか(遅い)=熱エネルギーが小さい⇒物体の温度が低くなるなので温度を別の言葉で言い換えると、その物体がどのぐらいの熱エネルギーを持っているかを表す指標ということです。ちなみに注意してもらいたいこととして、物体の温度が高くなるのは先に物体の運動が激しくなるからです。物体の温度が高くなるから分子の運動が激しくなるのではなく、あくまでも分子の運動が先にあっての温度変化になりますので注意してください。関連:熱と温度の違いとは?次の章で物体の状態と温度変化の関係について解説します。3.物体の状態変化と温度の関係についてでは物体の状態変化と温度の関係について見ていきましょう。物体には固体・液体・気体の3つの状態が存在していて、その物体の温度が変化することで物体の状態も変化します。例えば氷(固体)を熱していけば水(液体)になり、その水(液体)をさらに熱していくといずれ水蒸気(気体)に変化します。このように物体の状態が変化することを状態変化と言います。この物体の状態変化を分子の運動という観点から解説していきます。下図は固体・液体・気体それぞれの状態における分子の運動の様子を表したものです。このそれぞれの状態と物体の温度の高さは大きく関係しています。はじめの方でも言いましたが、物体の温度の高さを決めるのは、その物体を構成している原子・分子の運動の大きさです。物体の温度の高さ=原子・分子の運動の大きさということを理解したうえで、それぞれの状態変化について見ていくと分かりやすいです。一般的に状態変化はその物体の温度が高くなっていくと、固体→液体→気体の順番で変化していきますよね。このとき物体の状態変化に必要なのは表面的に見れば温度を上げていくことですが、状態変化の本質は分子の運動を大きくさせて分子同士の繋がりを切ることにあります。なので物体が状態変化するのは温度を高くしていくことで、分子の運動が大きくなり分子同士の繋がりが切れるからなんですね。そして氷(固体)が溶けて水(液体)になり始める温度は0度で、水(液体)が水蒸気(気体)になる温度は100度です。これはあくまでも水分子同士の繋がりが切れ始める温度なわけで、その分子の種類によって繋がりの切れやすさ(状態変化のしやすさ)が異なります。ただ単に物体の温度が高くなるから固体が液体になるという覚え方でも良いですが、このように分子同士の考え方を知っていた方が何かと便利なので覚えておきましょう。関連:状態変化とは何か?物質が状態変化する仕組みを簡単に図解!4.分子運動における物体の温度変化の仕組み物体が温度変化するのは、物体の持っている熱が他の物体に移動するからです。温度の高い物体に温度の低い物体を当てると、温度の高い物体は少しずつ温度が下がっていきますよね。これは温度が高い物体から低い物体に熱が移動しているからです。このように熱というのは温度の高い物体から、低い物体に移動していきます。そして物体の持っている熱が他の物体に移動するということは、物体を構成している分子運動の大きさが他の物体の分子に働くということ。なので簡単に言うと、分子運動における物体の温度変化の仕組みは、動きの激しい分子が動きの穏やかな分子にぶつかっていくことで起こります。動きの激しい分子(温度が高い)が動きの穏やかな分子(温度が低い)にぶつかると、ぶつかった衝撃で穏やかな分子は少し動きが激しくなりますよね。反対に動きの激しい分子はぶつかったことで、その動きが少し穏やかになります。これが温度変化(熱の移動)の仕組みになります。具体的な例として容器内に水を入れて熱したときと冷やしたときについて、分子の運動を見ていきながらどのように温度変化するのかを解説していきます。では分子運動の様子からそれぞれの場合で、容器内の水が温度変化する仕組みを見ていきましょう。容器に入った水を火で暖めた場合まず容器内の水を容器の外から火で暖めた場合です。上図右は容器内の水と容器(ガラス)を分子で見た場合で、小さい分子の粒でそれぞれが構成されてることが分かると思います。そして火は分子で構成されている物体ではなく現象のことで、火からは物体の分子の運動を激しくさせる赤外線が放出されています。火に物体を近づけていきその物体が暖かくなっていくのは、火から赤外線が放出され物体の分子の運動を激しくさせているからなんですね。これを先ほどの例で見ていくと下図のようになります。火から放出された赤外線によって容器のガラス分子の運動が激しくなり、その運動がガラス分子を伝わり容器内の水分子にまで到達します。このまま火で熱し続けていくと水分子の動きがどんどん激しくなり、水分子の運動の激しさが水分子同士の繋がりを切るほど強くなると水が水蒸気に変化します。関連:湯気と水蒸気の違いとは?容器に入った水を氷で冷やした場合次は容器内の水を容器の外から氷で冷やした場合です。上図は先ほどと同じように分子で見た場合で表しています。物体の温度の高さは分子の運動の大きさによるので、容器の外にある氷の分子運動が1番小さい(温度が低い)です。つまり氷を構成している分子の動きが最も穏やかだということ。熱の移動は温度の高い物体から低い物体に起こるので、まずはガラス分子から氷の分子に熱の移動が起こります。そしてガラス分子から氷の分子に熱の移動が起こったことで、ガラス分子の動きが穏やか(温度が低く)になります。最後に容器内の水分子からガラス分子に熱の移動が起こります。これが容器内の水を氷で冷やした場合における、分子運動から見た温度変化の様子になります。関連:氷とドライアイスと液体窒素の違いとは?最も温度が低いのはどれ?以上が「温度とは何か?物体の状態変化と温度の関係について解説!」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});5.まとめこれまで説明したことをまとめますと、温度とは、物体の熱さ・冷たさ(暖かさ・寒さ)という度合いを表したもの。温度は、その物体がどのぐらいの熱エネルギーを持っているかを表す指標とも言うことができる。温度の高さは、物体を構成している分子の運動の大きさ(激しさ)によるもの。物体の状態変化は、分子の運動を激しくする(温度を高くする)ことで分子同士の繋がりが切れるので起こる。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒絶対零度とは?また絶対零度の温度は何度なのか?⇒凝結と結露の違いとは?⇒気温と温度と室温の違いとは?⇒⇒シンクに熱湯を流すとボコッと音がする理由とは?熱湯は流さない方が良いのか?⇒熱気球とは?また熱気球はどんな原理で空中に浮いているのか?⇒熱の伝わり方の3種類(伝導・対流・放射)を分かりやすく図で解説!⇒なぜ熱は必ず温度が高い方から低い方へと移動するのか?⇒なぜ液体は温度が上がると気体に変化しやすくなるのか?⇒熱伝導率とは何かをわかりやすく解説!熱伝導率が高い・低いとは?
-
さてあなたは”絶対熱”という言葉をご存知でしょうか。最も物体の温度が低くなる”絶対零度(ぜったいれいど)”については、多くの人がその存在を知っているはずです。しかし絶対零度の反対とも言える絶対熱については、どんなものなのか知っている人はほとんどいないのではないでしょうか。そこでこのページでは絶対熱とは何か?また絶対熱の温度は何度あるのかを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次絶対熱とは何か?絶対熱の温度は何度あるのか?なぜ爆発する瞬間に最も温度が高くなるのか?まとめ1.絶対熱とは何か?では絶対熱とその温度について見ていきましょう。まず絶対熱(ぜったいねつ)とは、宇宙の中で最高の温度のことを言います。つまり絶対熱よりも高い温度は存在しないということです。絶対熱は最も高い温度のことを指していますがその反対に、最も低い温度のことを指す絶対零度というものも存在します。関連:絶対零度とは?また絶対零度の温度は何度なのか?では絶対熱まで温度が高くなるのは一体どんなときなのかというと、それはビックバンが発生して1プランク時間が経過したときになります。ビックバンとは英語で大爆発のことを意味していて、一般的には”宇宙が生まれるきっかけとなった大爆発のこと”を言います。そしてこのビックバンという大爆発が起こることによって飛び散ったかけらが、宇宙に存在している星や天体のこと(地球もそのうちのひとつ)なんです。宇宙を誕生させるほどの大爆発なのですから、私たちが想像もできないほど大きなエネルギーの爆発だということは確かです。ちなみに1プランク時間というのは時間における最小単位のことで、1秒よりもとんでもなく短い時間だと認識しておいてください。(厳密には、1プランク時間=5.391×10^-44[秒]です)なのでビックバンという大爆発が起こった直後の温度が、宇宙の中で最も高い温度である”絶対熱”ということになるんですね。関連:太陽系とは何かをわかりやすく図で解説!2.絶対熱の温度は何度あるのか?では絶対熱の温度は何度あるのか見ていきましょう。結論から言ってしまうと、絶対熱の温度は142×10^31[℃]です。温度の桁は間違いではありません。絶対熱とは私たちの想像をはるかに超えている温度なんですね。絶対熱の温度を数字だけで表してみると......1,420,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000[℃]もう数字が大きすぎて何て読むのかさえも難しいですが、読み方としては14溝(こう)2千穣(じょう)[℃]になります。数字の大きさ目安一(いち)万(まん)垓(がい)十(じゅう)億(おく)杼(じょ)百(ひゃく)兆(ちょう)穣(じょう)千(せん)京(けい)溝(こう)項目1項目2項目3)★ -->数字の大きさの参考にどうぞ(この表では溝までしか書いていません)。また人類によって生み出された最高温度は約4兆度にまで達し、”クォーク・グルーオン・プラズマ”という物質でギネスブックにも登録されています。この物質は原子核どうしをぶつけることによって作られ、ビックバンから数マイクロ秒後の宇宙での温度と考えられています。4兆度でも考えられないほど高い温度ですが、絶対熱の温度には遠く及びません。関連:熱と温度の違いとは?3.なぜ爆発する瞬間に最も温度が高くなるのか?ではなぜ爆発する瞬間が最も温度が高くなるのか見ていきましょう。さっそくですが爆発する瞬間に最も温度が高くなるのは、爆発した瞬間に最もエネルギーが集中しているからです。爆発した瞬間が最もエネルギーが集中しているときで、爆発から時間が経つごとに少しずつ爆発のエネルギーが周囲に拡散されていきます。上図のように同じ大きさのエネルギーを持っているのなら、より小さい範囲にエネルギーを集中させた方がその力は強くなりますよね。拡散されればそれだけエネルギーが周囲に分散されるので、同じ範囲に働くエネルギーの大きさは弱くなります。爆発のエネルギーというのは熱や光のことで、そのエネルギーが爆発物から拡散されることで広範囲で被害を受けることになります。実際に爆発に巻き込まれたことがある人は少ないかもしれませんが、爆発物の近くにあるものほど被害が大きくなるのはなんとなくイメージできますよね。爆発物からの距離が近ければエネルギーは集中しているので、それだけ爆発による被害は大きくなります。なのでビックバンという大爆発が起こった直後には、私たちが想像できない大きな熱エネルギーが集中している状態なわけです。そして爆発した瞬間に熱エネルギーが集中するため、ビックバン直後には絶対熱といわれる温度まで達するんですね。関連:粉塵爆発とは何か?粉塵爆発の原理をわかりやすく図で解説!以上が「絶対熱とは何か?絶対熱の温度は何度あるのか?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、絶対熱とは、宇宙の中で最高の温度のこと。絶対熱の温度 = 142×10^31[℃]爆発した瞬間に最も温度が高くなるのは、エネルギーが集中しているから。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒絶対零度とは?また絶対零度の温度は何度なのか?⇒温度とは何か?物体の状態変化と温度の関係について解説!⇒気温と温度と室温の違いとは?⇒摂氏と華氏とは何か?また摂氏と華氏の変換方法と違いについて⇒結露とは何か?仕組みを分かりやすく図解!⇒熱気球とは?また熱気球はどんな原理で空中に浮いているのか?⇒熱の伝わり方の3種類(伝導・対流・放射)を分かりやすく図で解説!⇒空気は太陽光で直接暖められないって本当?空気が暖まる仕組みとは?⇒なぜ氷は空気中よりも水中の方が溶けやすいのか?
-
さてあなたは”絶対零度”という言葉をご存知でしょうか。ドラマの名前や何かのキャラクターの技名にもなっていますが、一体どんなことを表しているのでしょうか。絶対零度という言葉自体を知っている人は意外と多いですが、その言葉の意味をしっかりと理解している人は少ないはずです。そこでこのページでは絶対零度とは?また絶対零度の温度は何度なのかを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次絶対零度とその温度について絶対零度とは分子の運動が停止した状態まとめ1.絶対零度とその温度についてでは絶対零度とその温度について見ていきましょう。まず絶対零度(ぜったいれいど)とは、宇宙の中で最も低い温度のことを言います。そして絶対零度の温度が一体何度なのかというと、摂氏(せっし)温度で-273.15[℃]になります。摂氏というのは温度を表す尺度のことで、私たちが温度を表すときによく使用している尺度です。なので物体が絶対零度(-273.15[℃])よりも温度が下がることはありません。また絶対零度の名前の由来としては、絶対温度(ぜったいおんど)という摂氏温度とは別の尺度が元になっています。絶対温度の単位にはケルビン[K]が用いられており、この絶対温度という尺度における最も最低の温度が0[K]で表されます。つまり絶対温度において最低の温度が0度(0[K])なので、絶対(温度の)零度(0度)という名称になったわけです。ちなみに絶対零度という宇宙で最低の温度があるのですから、反対の”宇宙で最高の温度”を表す言葉もしっかりと存在しています。関連:絶対熱とは何か?絶対熱の温度は何度あるのか?関連:なぜ単位は大文字と小文字で区別しなければいけなのか?2.絶対零度とは分子の運動が停止した状態では絶対零度とは分子の運動が停止した状態について見ていきましょう。さっそくですが結論から言ってしまうと絶対零度というのは、物体の原子・分子の運動が完全に停止した状態の温度を表しています。まず物体の温度の高い低いというのは、その物体を構成している原子・分子の運動によって決まります。簡単に言えば、原子・分子の運動が激しければ物体の温度が高くなり、原子・分子の運動が穏やかであれば物体の温度は低くなります。温度はその物体の原子・分子の運動で決まっているのですから、原子・分子の運動が完全に停止した状態が温度が最も低くなる状態ということになります。なので運動が停止した状態こそが絶対零度(摂氏-273.15[℃])になるわけです。このように原子・分子の運動によってその物体の温度は決まります。関連:温度とは何か?物体の状態変化と温度の関係について解説!以上が「絶対零度とは?また絶対零度の温度は何度なのか?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、絶対零度とは、宇宙の中で最も低い温度のこと。絶対零度の温度は、摂氏温度で-273.15[℃]。絶対零度は、物体の原子・分子の運動が完全に停止したときの状態の温度である。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒液体温度計の仕組みを簡単に図解!なぜ水銀は使われなくなったのか?⇒マシュマロを電子レンジでチンすると膨らむ仕組みを簡単に解説!⇒気温と温度と室温の違いとは?⇒摂氏と華氏とは何か?また摂氏と華氏の変換方法と違いについて⇒熱と温度の違いとは?⇒氷とドライアイスと液体窒素の違いとは?最も温度が低いのはどれ?⇒水が100度に達していないのに蒸発する仕組みとは?⇒なぜ熱は必ず温度が高い方から低い方へと移動するのか?⇒なぜ水の中にドライアイスを入れるとブクブクと泡立つのか?⇒熱伝導とは何か?熱伝導の仕組みをわかりやすく図で解説!
-
さて熱と温度という2つの言葉を聞いたことはありますよね。熱と温度は意味が少し似ている言葉なので、意外と多くの人が同じような意味で使っているかもしれません。しかし熱と温度には決定的に違う点があります。そこでこのページでは、熱と温度の違いについて簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次熱と温度の違いについて熱とは?温度とは?まとめ1.熱と温度の違いについてでは熱と温度の違いについて見ていきましょう。結論から言ってしまうと熱と温度の違いは、物体の持っているエネルギーなのか、そのエネルギー量を数値で表したものなのかです。上図のように熱というのは物体が持っているエネルギーのことを指し、温度というのはその物体が持つ熱量を分かりやすく数値で表したものです。なのでその物体がどのくらい熱を持っているかを表したものが温度になります。さて熱と温度についてそれぞれ解説していきます。関連:気温と温度と室温の違いとは?熱とは?熱(ねつ)とは、物体の持っているエネルギーのことです。また熱というのは物体を構成している原子・分子の運動のことを表しています。例えば水(液体)の場合では、水分子という小さな粒が集まることで液体の水を構成しています。水だけに限らずすべてのものは原子・分子によって構成されていて、その物体を構成している原子・分子の運動の激しさが熱になります。簡単に図にすると下のようになります。上図のように水分子の運動が激しくなれば熱エネルギーが大きくなり、反対に水分子の運動が穏やかになれば熱エネルギーは小さくなります。そして物体の熱エネルギーが大きいとそれだけ物体の温度が高く、熱エネルギーが小さければその物体の温度も低くなるということです。ちなみに熱というのは温度の高い物体だけでなく、温度の低い物体についても同じように持っています。”熱を持っている”という表現を使うときは温度の高い物体を指すことが多いですが、温度の低い物体も少なからず熱を持っているということは覚えておいてください。温度とは?温度(おんど)とは、物体がどのくらい熱を持っているのかを数値で表したもので、物体の熱さや冷たさを表すための尺度になります。先ほど温度というのは物体が持っている熱エネルギーの大きさのことで、その熱エネルギーの大きさは物体の原子・分子の運動の激しさで決まると説明しました。そして物体の温度が高くったり低くなったりするのは、その物体が持っている熱エネルギーが他の物体に伝わるからです。基本的に熱は温度が高い物体から低い物体へと伝わります。つまり熱が伝わるということは簡単に言えば、物体の原子・分子の運動が他の物体に伝わるということです。上図のように運動が激しい原子・分子から穏やかな原子・分子へとぶつかり、その衝撃が伝わることで他の物体に熱として伝わっていくんですね。詳しい仕組みについては、下記で簡単に図解しているのでぜひご覧ください。関連:温度とは何か?物体の状態変化と温度の関係について解説!そして単に温度と言っても摂氏温度や華氏温度など様々な種類があります。私たちが日常的によく使用している温度の種類は、摂氏温度(セルシウス度)のことで単位は”℃”で表されます。世界的にも摂氏温度が標準となってはいますが、地域によっては摂氏温度以外の種類も使われていますので注意してください。関連:摂氏と華氏とは何か?また摂氏と華氏の変換方法と違いについて以上が「熱と温度の違いとは?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、熱とは、物体の持っているエネルギーのこと。温度とは、その物体がどのくらい熱を持っているのかを数値で表したもの。違いとしては物体の持っているエネルギーなのか、そのエネルギー量を数値で表したものなのか。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒絶対熱とは何か?絶対熱の温度は何度あるのか?⇒絶対零度とは?また絶対零度の温度は何度なのか?⇒状態変化とは何か?物質が状態変化する仕組みを簡単に図解!⇒ドライアイスとは?ドライアイスから発生する白い煙の正体って何?⇒シンクに熱湯を流すとボコッと音がする理由とは?熱湯は流さない方が良いのか?⇒熱気球とは?また熱気球はどんな原理で空中に浮いているのか?⇒植物の光合成と呼吸の違いとは?植物は二酸化炭素を排出するのか?⇒粉塵爆発とは何か?粉塵爆発の原理をわかりやすく図で解説!⇒なぜ熱は必ず温度が高い方から低い方へと移動するのか?⇒熱の伝わり方の3種類(伝導・対流・放射)を分かりやすく図で解説!
-
さて水などの液体は火などで加熱したりすると少しずつ液体の温度が上がっていき、しばらくすると液体が気体に変化するということは知っていますよね。ですが意外と温度を上げることで液体が気体に変化しやすくなるのかを、しっかりと理解して解説できる人は少ないです。そこでこのページでは、なぜ液体は温度が上がると気体に変化しやすくなるのかを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次なぜ液体は温度が上がると気体に変化しやすくなるのか?(1)液体は分子という小さな粒で構成されている(2)液体の温度が変化すると分子の動きも変化する(3)液体が気体に変化するというのは分子が飛び出すということまとめ1.なぜ液体は温度が上がると気体に変化しやすくなるのか?ではなぜ液体は温度が上がると気体に変化しやすくなるのかを解説していきます。結論から言ってしまうと温度が上がることで液体が気体に変化しやすくなる理由は、液体の分子の動きが激しくなり、分子同士の繋がり(液体)から分子が飛び出しやすくなるからです。これだけでは何を言っているのか分からないと思うので、順を追って下の通りに少しずつ簡単に解説していきます。(1)液体は分子という小さな粒で構成されている(2)液体の温度が変化すると分子の動きも変化する(3)液体が気体に変化するというのは分子が飛び出すということでは順を追ってそれぞれを見ていきましょう。(1)液体は分子という小さな粒で構成されているまず液体は分子という小さな粒が集まって構成されています。分子の粒が集まって構成されているのは液体だけでなく、すべての物質(固体や気体)に対して言えることです。例えば上図のように水(液体)なら水分子が集まって構成されていて、空気(気体)なら空気分子が集まって構成されています。(2)液体の温度が変化すると分子の動きも変化する液体を構成している分子というのは常に動いて(振動して)いて、その分子の動きの激しさは温度が変化することで共に変化していきます。上図のように物質の分子の動きと温度の関係は、物質の温度が上がると分子の動きが激しくなり、反対に物質の温度が下がると分子の動きが穏やかになります。ちなみに厳密に言えば先に物質の温度が変化することで分子の動きが変わるのではなく、先に分子の動きが変わることでそれに伴いその物質の温度も変化していきます。関連:温度とは何か?物体の状態変化と温度の関係について解説!(3)液体が気体に変化するというのは分子が飛び出すということ液体が気体に変化するということは液体を構成する分子同士の繋がりから、その液体の分子が飛び出すということを意味しています。水(液体)が水蒸気(気体)に変化するのであれば、上図のように水を構成している水分子が水分子同士の繋がりから飛び出すということです。なので飛び出している水分子が水蒸気(気体)になるわけです。関連:状態変化とは何か?物質が状態変化する仕組みを簡単に図解!またイメージしてみて欲しいのですが、水分子同士の繋がりから飛び出すということは、その繋がりを切り離すためのエネルギー(力)が必要だということになります。例えば自分の身体が拘束されている状態だとして、その拘束から脱出するためには力で振りほどこうとしますよね。しかし力がなければその拘束を振りほどくことはできません。つまり簡単に言えば、分子同士の繋がりである液体から分子を飛び出させるには、分子に分子同士の繋がりを振りほどくための力が必要になります。そしてこの分子同士の繋がりから振りほどくための力というのが、液体の温度を上げて分子の動きを激しくさせるということなんですね。液体の温度が低い状態であれば分子の動きが穏やかなので、分子同士の繋がりから分子が飛び出すだけの力がありません。ですが液体の温度を上げていくことによって液体を構成する分子の動きが激しくなるので、分子同士の繋がりから分子が飛び出していくことが可能になります。ちなみに水(液体)は加熱したりすることで温度を上げなくても、少しずつ蒸発しているのはご存知でしょうか。(これは水以外の液体でも起こることです)なぜ温度を上げなくても水は蒸発するのか、その仕組みについては下記をご覧ください。関連:水が100度に達していないのに蒸発する仕組みとは?以上が「なぜ液体は温度が上がると気体に変化しやすくなるのか?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、温度を上げると液体が気体に変化しやすくなるのは、分子の動きを激しくなり、分子同士の繋がりから飛び出しやすくなるから。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒水を沸騰させると発生する泡の正体とは?またなぜ泡は発生するのか?⇒絶対熱とは何か?絶対熱の温度は何度あるのか?⇒流体とは何かをわかりやすく解説!圧力はどんなかかり方なのか?⇒なぜ熱は必ず温度が高い方から低い方へと移動するのか?⇒水垢とは何か?水道周りに白い塊ができる仕組みについて図解!⇒浮力とは何か?浮力の原理を簡単に図で解説!⇒熱対流とは何か?熱対流の仕組みをわかりやすく図で解説!⇒密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?⇒気圧とは何かをわかりやすく解説!なぜ気圧で人はつぶされないのか?⇒気圧と沸点の関係について。気圧によって沸点が変化する仕組みとは?
-
さて何かモノを触ったときに温度が高い・低いと感じるように、その物質が持っている熱の量によって私たちが感じる温度が異なります。例えば冷たいモノに触っていれば人間の体温は下がっていき、反対に熱いモノに触っていれば人間の体温は上がっていきます。このように熱は温度が高いモノから低いモノへと移動していきますが、なぜ熱が温度の高い方から低い方へ移動するのか理解している人は少ないです。そこでこのページでは、物質の熱が温度の高い方から低い方へと移動する仕組みを解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次物質の熱が温度の高い方から低い方へ移動する理由(1)物質の温度は分子の運動で決まっている(2)熱=分子の運動の激しさ(3)熱が移動するというのは他の分子に衝突することまとめ1.物質の熱が温度の高い方から低い方へ移動する理由では物質の熱が温度の高い方から、低い方へと移動する理由を見ていきましょう。結論から言ってしまうと、物質を構成している分子の運動が激しい方(温度が高い)から、他の分子の運動が穏やかな方(温度が低い)へと伝わるからです。さて分子という少し難しい話が出てきましたが、簡単なので順序立てて解説していきます。(1)物質の温度は分子の運動で決まっているまず物質は分子と言われるたくさんの小さな粒で構成されていて、物質の温度はその物質を構成している分子の運動の激しさによって決まります。液体の水を例にして見ていくと下図のようになります。上図の黒い丸枠が水(液体)のことを表していて、水は水分子と言われる小さな粒がたくさん集まって構成されています。そして上図のように水を構成する水分子の運動によってその水の温度が決まり、水分子の運動が激しければ温度が高くなり、運動が穏やかであれば温度は低くなります。ここでは水を例にして解説していますが、基本的にはどんな物質も小さな粒である分子などから構成されているので、ここで解説した水のときと同様に考えることができます。関連:温度とは何か?物体の状態変化と温度の関係について解説!関連:絶対熱とは何か?絶対熱の温度は何度あるのか?(2)熱=分子の運動の激しさ次に温度はその物質を構成している分子の運動によって決まり、物質の温度はその物質の持っている熱の量によって高いか低いかが決まります。つまり物質の持っている熱というのは、その物質を構成している分子の運動そのものなんですね。この関係を簡単にまとめると下のようになります。温度が高い=分子の運動が激しい=物質の持つ熱の量が多い温度が低い=分子の運動が穏やか=物質の持つ熱の量が少ないでは次の章で本題の熱が移動することについて見ていきましょう。関連:熱と温度の違いとは?(3)熱が移動するというのは他の分子に衝突することここからが物質の熱が温度の高い方から低い方へ移動する理由についての本題です。物質の熱は温度の高い方から温度の低い方へと移動しますが、熱が移動するということは分子同士が衝突することを意味しています。例えば”温度の高い物質A”から”温度の低い物質B”へと、熱が移動する場合は下図のようになります。上図のように”温度の高いAという物質(分子の動きが激しい)”から、”温度の低いBという物質(分子の動きが穏やか)”へと熱(分子の運動)が移動しています。このとき温度の高い物質Aの分子の運動は少し穏やか(温度は低く)になり、温度の低い物質Bの分子の運動は少し激しく(温度は高く)なります。ではなぜ物質の熱は温度の高い方から低い方へしか移動しないのかというと、それは2つのボールが衝突したときのことを考えてみると分かるはずです。動きの速い(激しい)ボールを動きの遅い(穏やかな)ボールにぶつけてみると、ぶつかった衝撃で動きの速いボールは少し動きが遅くなります。反対に動きの遅いボールは動きの速いボールとぶつかった衝撃で、動きが速くなります。温度の高い物質から温度の低い物質へと熱が移動するのも、この異なる速さのボールがぶつかったときと同じような考え方をすれば良いわけです。そしてたとえボールがどちらからぶつかっていったかが違っても、結果は同じで動きの速いボールから遅いボールへと運動が大きくなります。これが熱が必ず温度の高い物質から温度の低い物質へと移動する理由になります。関連:熱の伝わり方の3種類(伝導・対流・放射)を分かりやすく図で解説!以上が「なぜ熱は温度が高い方から低い方へと移動するのか?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、熱が温度の高い方から低い方へと移動するのは、物質の分子の運動が激しい方から穏やかな方へと伝わるから。温度が高い=分子の運動が激しい=物質の持つ熱の量が多い温度が低い=分子の運動が穏やか=物質の持つ熱の量が少ない (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒状態変化とは何か?物質が状態変化する仕組みを簡単に図解!⇒絶対零度とは?また絶対零度の温度は何度なのか?⇒植物の光合成と呼吸の違いとは?植物は二酸化炭素を排出するのか?⇒熱気球とは?また熱気球はどんな原理で空中に浮いているのか?⇒熱伝導率とは何かをわかりやすく解説!熱伝導率が高い・低いとは?⇒空気は太陽光で直接暖められないって本当?空気が暖まる仕組みとは?⇒粉塵爆発とは何か?粉塵爆発の原理をわかりやすく図で解説!⇒マシュマロを電子レンジでチンすると膨らむ仕組みを簡単に解説!⇒液体温度計の仕組みを簡単に図解!なぜ水銀は使われなくなったのか?
-
さてあなたは液体の膨張と圧縮についてご存知でしょうか。液体は温度が変化するとそれに伴って体積も変化するのですが、理解せずにただ暗記しているだけではすぐに忘れてしまいますよね。そこでこのページでは液体の膨張と圧縮とは何か?また温度によって液体の体積が変化する仕組みを図で解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次液体の膨張と圧縮とは?温度によって液体の体積が変化する仕組みについて(1)温度によって分子の運動の激しさが変化する(2)分子の運動の激しさで動く範囲(体積)が変化するまとめ1.液体の膨張と圧縮とは?では液体の膨張と圧縮とは何かを見ていきましょう。さっそくですが、液体の膨張とは液体の温度が上がることで体積が大きくなることで、液体の圧縮とは液体の温度が下がることで体積が小さくなることを言います。温度によって体積が変化(膨張・圧縮)するのは液体だけでなく、他の状態である気体や固体でも同じことが言えます。ただ温度によって体積が変化する程度にはその状態(気体・液体・固体)で差があり、体積変化(膨張・圧縮)が小さい順番に並べると”固体 < 液体 < 気体”のようになります。つまり温度変化によって最も体積が変化しやすい状態は”気体”ということです。また液体(気体・固体も)は温度変化によって体積が変化したとしても、その液体の質量は変わりません。質量が変わらずに体積だけが変化するため、”質量÷体積”で算出される密度が変化します。例えば冷たい水が重くなって、暖かい水が軽くなるというのは、水の温度が変化したことによってその水の密度も変化するから起こることなんですね。温度によって水の重さが変化する詳しい仕組みは下記をご覧ください。関連:暖かい水と冷たい水で重さが変わる仕組みとは?関連:密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?次の章でなぜ温度によって液体の膨張・圧縮が起こるのかを簡単に解説していきます。2.温度によって液体の体積が変化する仕組みについて結論から言ってしまうと温度によって液体の体積が変化するのは、液体の分子運動の激しさが変わることで、その分子の移動する範囲も変わるからです。まずどんな物質でも分子と呼ばれる小さな粒が集まって構成されていて、水であれば下のように水分子と呼ばれる小さな粒が集まって構成されています。ではこのことを踏まえたうえで、温度によって液体の体積が変化する仕組みを順番に解説していきます。(1)温度によって分子の運動の激しさが変化する液体はその液体分子が集まることで構成されていますが、その液体分子は常に動き回っています。そして液体分子の動きの激しさでその液体の温度が決まっており、液体分子の運動が激しければ温度が高く、液体分子の運動が穏やかであれば温度は低くなります。その液体が水であれば上図のようになります。ですので液体の温度が上がるということは液体分子の動きが激しく、反対に液体の温度が下がるということは液体分子の動きが穏やかだということになります。厳密に言えば物質の温度というのは、その物質を構成する分子運動によって決まるものなので注意してください。(このページでは関係なく記していますが特に気にしないでください)これは気体や固体の物質にも共通することなので、ぜひ覚えておいてください。関連:温度とは何か?物体の状態変化と温度の関係について解説!関連:絶対零度とは?また絶対零度の温度は何度なのか?(2)分子の運動の激しさで動く範囲(体積)が変化する液体の温度が上がれば分子の運動が激しくなり、反対に液体の温度が下がれば分子の運動が穏やかになります。そしてその液体の分子運動の激しさが変化することで、その分子が移動できる範囲も変わります。液体の温度が上がることで液体分子の動きが激しくなれば、エネルギーが大きくなるのでより広範囲に移動できるようになります。反対に液体の温度が下がることで液体分子の動きが穏やかになれば、エネルギーが小さくなるので動ける範囲は狭くなります。つまりこれが液体の温度が上がれば体積が大きく(膨張)なり、液体の温度が下がれば体積は小さく(圧縮)なるということです。ちなみに日常的に見かけることも多い液体温度計なんかは、液体の温度によって体積が変化する性質を利用して作られています。関連:液体温度計の仕組みを簡単に図解!なぜ水銀は使われなくなったのか?以上が「液体の膨張と圧縮とは?温度によって液体の体積が変化する仕組みを図解!」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、液体の膨張とは、液体の温度が上がることで体積が大きくなること。液体の圧縮とは、液体の温度が下がることで体積が小さくなること。温度によって液体の体積が変化するのは、液体の分子運動の激しさが変わることで、その分子の移動できる範囲も変わるから。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒熱と温度の違いとは?⇒なぜ熱は必ず温度が高い方から低い方へと移動するのか?⇒絶対熱とは何か?絶対熱の温度は何度あるのか?⇒なぜ標高が高い所は寒いのか?太陽との距離は関係ないって本当?⇒水が100度に達していないのに蒸発する仕組みとは?⇒流体とは何かをわかりやすく解説!圧力はどんなかかり方なのか?⇒熱対流とは何か?熱対流の仕組みをわかりやすく図で解説!⇒なぜ氷は空気中よりも水中の方が溶けやすいのか?⇒状態変化とは何か?物質が状態変化する仕組みを簡単に図解!⇒暖かい水と冷たい水で重さが変わる仕組みとは?
-
気温30℃だと暑いと感じて、水温30℃の水に触ると冷たく感じますが、同じ30℃なのにどうして体感温度が違うのかをあなたはご存知でしょうか。別に理由が分からず「そういうもんだ」と思っていても特に問題はありませんが、知っていたほうが何かと役に立つときが来るので得をするはずです。そこでこのページでは、なぜ水温と気温は同じなのに体感温度が違うのかを簡単に解説します。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次なぜ水温と気温は同じなのに体感温度が違うのか?まとめ1.なぜ水温と気温は同じなのに体感温度が違うのか?ではなぜ水温と気温は同じなのに体感温度が違うのかを見ていきましょう。まず水温は”水の温度”で、気温は”空気の温度”のことを表しており、水温30℃の水は冷たく感じて、気温30℃の空気は暑いと感じますよね。結論から言って、水と空気は同じ30℃なのになぜ体感温度が違うのかと言うと、それは水と空気における熱伝導率(熱の伝わりやすさ)が異なるからです。水は空気に比べて熱伝導率が高いため熱が伝わりやすく、反対に空気は水よりも熱伝導率が低いため熱が伝わりにくいです。(水は空気に比べると20倍以上も熱が伝わりやすい物質になります)この水と空気の熱伝導率(熱の伝わりやすさ)の違いにより、それぞれに触れたときの体感温度が異なるんですね。さて以上のことを踏まえて、もう少し詳しく体感温度が異なる仕組みを解説していきます。私たち人間は普通であれば36℃~37℃ほどの体温を持っていて、何かに触れて冷たいと感じるのは、触れたモノに熱が移動している(奪われている)からです。そして自分の体から移動する(奪われる)熱の量が多いほど冷たいと感じます。ですので30℃の水(熱が伝わりやすい)と空気(熱が伝わりにくい)であれば、体温の方が36℃~37℃ほどで高いので、触れれば水と空気に熱が移動していきます。(熱は温度の高い方から低い方へと移動していくため)このときに同じ温度でも水と空気であれば、水の方が熱が伝わりやすい物質になるため、自分の体からより多くの熱が移動してしまうので水の方が冷たいと感じてしまうんですね。また水と空気の温度が体温よりも高かった場合についても同様の考え方になります。例えばそれぞれ100℃の水と空気(100℃の空気はサウナ内ぐらいの気温)があった場合には、100℃の水は熱すぎてずっと触っているのはまず無理ですが、100℃の空気であれば比較的長い時間触っていられますよね。100℃ということは自分の体温よりも温度が上になるので、触れていればその温度の高い物質から自分の体へと熱が移動してきます。上図のように100℃の水にずっと触れていることができないのは、水の熱伝導率が高いために自分の体に熱が大量に移動してくるからです。反対に100℃の空気に長いあいだ体が触れていても平気なのは、空気の熱伝導率が低いために空気から体に熱があまり移動してこないからです。(それでも息苦しかったり、暑い感じはします)水と空気の温度が同じなのに、体感温度が違うのにはこのような理由があったというわけです。関連:熱と温度の違いとは?関連:熱伝導率とは何かをわかりやすく解説!熱伝導率が高い・低いとは?以上が「なぜ水温と気温は同じなのに体感温度が違うのか?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、水温と気温が同じなのに体感温度が違うのは、水と空気における熱伝導率の違いによるもの。水の方が空気よりも熱伝導率が高いので、触れたときに移動する熱の量が多くなる。熱は必ず温度が高いモノから温度が低いモノへと移動する。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒温度とは何か?物体の状態変化と温度の関係について解説!⇒絶対零度とは?また絶対零度の温度は何度なのか?⇒質量とは?重量(重さ)との違いと単位について⇒コップに水滴がつく理由とは?分かりやすく仕組みを図で解説!⇒熱伝導とは何か?熱伝導の仕組みをわかりやすく図で解説!⇒なぜ氷は空気中よりも水中の方が溶けやすいのか?⇒流体とは何かをわかりやすく解説!圧力はどんなかかり方なのか?⇒なぜ液体は温度が上がると気体に変化しやすくなるのか?⇒粉塵爆発とは何か?粉塵爆発の原理をわかりやすく図で解説!⇒シンクに熱湯を流すとボコッと音がする理由とは?熱湯は流さない方が良いのか?
-
さてあなたは氷とドライアイスと液体窒素についてご存知でしょうか。私たちは日常的に氷とドライアイスを利用することはありますが、液体窒素を利用することは実験以外ではほとんどないですよね。これらが利用される目的は主に他のモノを冷やすためですが、一体どんな物質から出来ているのか疑問に感じる人も多いですよね。そこでこのページでは氷とドライアイスと液体窒素の違いとは何か?またこれらの中で最も温度が低いのはどれなのかを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次氷とドライアイスと液体窒素の違いについて氷とは?ドライアイスとは?液体窒素とは?まとめ1.氷とドライアイスと液体窒素の違いとは?では氷とドライアイスと液体窒素の違いを見ていきましょう。結論から言ってしまうと氷とドライアイスと液体窒素の違いとして、それぞれを構成している物質が異なります。簡単にまとめると、氷(固体)⇒水(液体)が固体に変化したものドライアイス(固体)⇒二酸化炭素(気体)が固体に変化したもの液体窒素(液体)⇒窒素(気体)が液体に変化したものこのように氷とドライアイスと液体窒素では、それぞれを構成している物質が違います。関連:状態変化とは何か?物質が状態変化する仕組みを簡単に図解!さて氷とドライアイスと液体窒素について詳しく解説していきますね。氷とは?氷とは、水(液体)が固体に変化したものです。私たちが日常的に他のモノを冷やすときに使用しているのが”氷”です。例えば飲み物を冷やす目的でコップの中に入れたり、食材の周囲に氷を置いておき一時的に温度を保たせるようなときに利用されていますよね。液体である水が固体(氷)に変化し始めるのは(このときの温度を凝固点)、ほとんどの人が知っている通り水の温度が0℃になったとき(1気圧の場合)です。氷の温度は通常であれば冷凍庫から取り出したときで約-15℃から-20℃になります。しかし氷自体の温度は周囲の環境によっても大きく変化するので、冷凍庫よりも温度が低い環境であれば氷の温度はより低くなります。その方法によっては物質の最低温度である約-273℃近くまで下がるので、氷の温度は一定でなく周囲の環境で変化するということは覚えておきましょう。関連:1気圧とは?また何ヘクトパスカル(hPa)なのか?関連:絶対零度とは?また絶対零度の温度は何度なのか?ドライアイスとは?ドライアイスとは、二酸化炭素(気体)が固体に変化したものです。私たちに馴染みのある二酸化炭素というのは空気中に存在する気体の状態のもので、その気体の二酸化炭素の温度がある温度以下にまで下がると固体(ドライアイス)に変化します。二酸化炭素は状態によってそれぞれ名称があって”気体は炭酸ガス”、”液体は液体二酸化炭素”、”固体はドライアイス”と呼ばれています。ドライアイスの見た目は白い塊(固体)で、ドライアイス自体の温度は-79℃以下とかなりの低温です。(氷と同様に一定の温度ではなく、方法によっては約-273℃付近まで下がる)二酸化炭素が固体になったドライアイスは特殊な性質があって、氷のように溶けると液体にはならずに気体の二酸化炭素に変化していきます。(液体にはならずに固体から気体に状態が変化することを”昇華”と言います)このような性質からドライアイスは液体にならずに他のモノを冷やすことができるので、溶けると水になってしまう氷と比べてとても便利です。(便利な反面、氷よりも温度がかなり低く危険でもあります)ただドライアイスが昇華するのは周囲の気圧の大きさが常圧の場合で、二酸化炭素にかかる周囲の圧力が大きくなれば液体に変化することになります。実際に深海では水によってかかる圧力(水圧)がとても大きいため、液体の二酸化炭素が溜まっている場所があるということも分かっています。関連:ドライアイスとは?ドライアイスから発生する白い煙の正体って何?液体窒素とは?液体窒素とは、窒素(気体)が液体に変化したものです。液体窒素は日常的に使用されることはほとんどありませんが、テレビなどの実験で使用されているのを見たことがあるという人は多いと思います。容器の中に液体窒素を入れて、その中にモノを入れると瞬時に凍るというような実験です。液体窒素の中にバラを入れ取り出して握るとパリパリと音がして粉々になったり、液体窒素にバナナを入れて凍らせるとバナナで釘が打てるようになるといったものです。また液体窒素の見た目は無色透明の液体(水みたい)で、温度は-196℃以下とドライアイスよりも低温です。液体窒素が-210℃に達すると、液体から固体の窒素に変化します。なので方法によっては氷やドライアイスと同様に温度が下がり、-196℃から-210℃になるまで温度を下げることは可能です。よく液体窒素が-196℃と言われるのは私たちが生活している空間(気温・圧力)では、-196℃以下を維持できないのですぐに気体の窒素に変化してしまうからです。(液体窒素の状態を維持できず、少しずつ気体に変化していきます)氷とドライアイスと液体窒素の温度とその状態について、少しややこしく感じてしまうと思うので簡単に下の図でまとめます。このようにまとめて図にしてみるとイメージしやすいですね。関連:気圧と沸点の関係について。気圧によって沸点が変化する仕組みとは?以上が「氷とドライアイスと液体窒素の違いとは?最も温度が低いのはどれ?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、氷とは、水が氷に変化したもの。ドライアイスとは、二酸化炭素が固体に変化したもの。液体窒素とは、窒素が液体に変化したもの。温度が低い順に並べると、”液体窒素(-196℃以下)<ドライアイス(-79℃以下)<氷(0℃以下)”となる。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒ドライアイスとは?ドライアイスから発生する白い煙の正体って何?⇒沸騰したお湯にドライアイスを入れると爆発するのか?⇒なぜ水の中にドライアイスを入れるとブクブクと泡立つのか?⇒スプーンをドライアイスに付けると音がする仕組みとは?⇒ドライアイスの安全な処理方法とは?またどういう処理が危険なのか?⇒ドライアイスを密閉した容器に入れると爆発する仕組みとは?⇒一酸化炭素中毒とは?発生する原因と仕組みについて簡単に解説!⇒凝結と結露の違いとは?⇒煙とは?黒い煙や白い煙の正体って何?⇒熱と温度の違いとは?