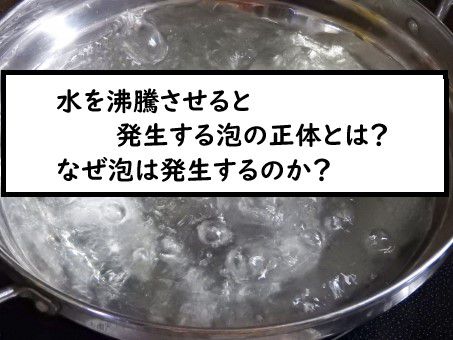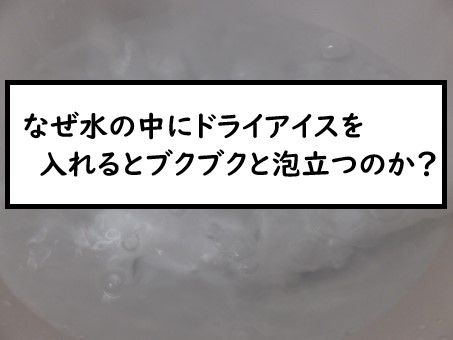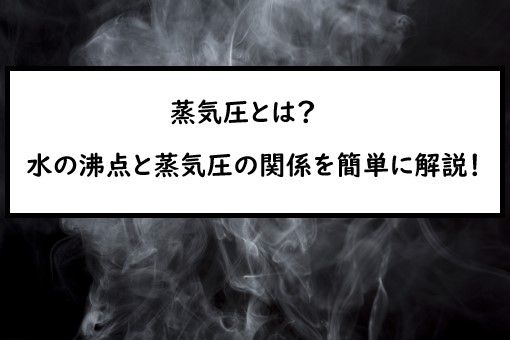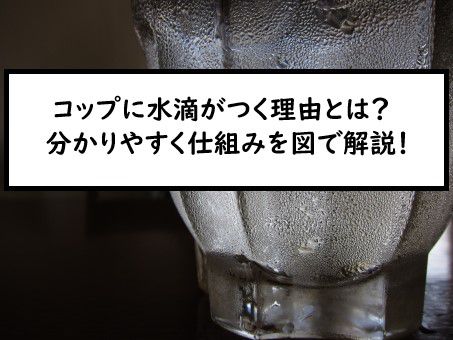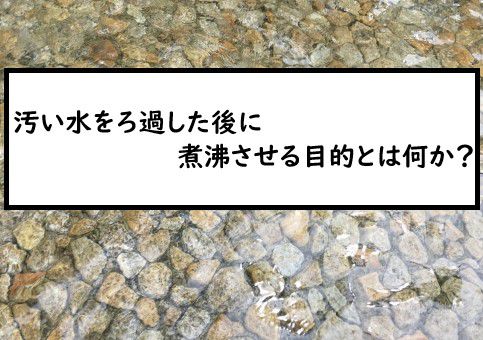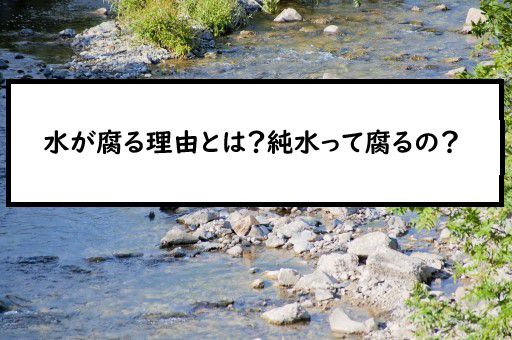さて水は100度になったら沸騰して気体になるということは、普通に生活していればほとんどの人が知っていることだと思います。ですが洗濯物や食器などを洗った後に放置していると、知らない間に水滴が乾いていますよね。この現象の正体こそが蒸発なのですが、なぜ100度に達していないのに水は蒸発するのでしょうか?そこでこのページでは、水が100度に達していないのに蒸発する仕組みを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次水が100度に達していないのに蒸発する仕組み蒸発することは分子との繋がりが切れること物質の温度は分子運動の大きさ(速さ)によって決まる同じ物質の分子でも運動の大きさが異なる分子が存在するまとめ1.水が100度に達していないのに蒸発する仕組みでは水が100度に達していないのに蒸発する仕組みについて見ていきましょう。結論から言ってしまうと水が100度に達していなくても蒸発するのは、水の温度が低くても運動が大きくなる(速くなる)水分子が存在するからです。どういうことなのか順番に詳しく解説していきます。蒸発することは分子との繋がりが切れることまずは水が蒸発するということが、どういうことなのかを理解する必要があります。私たちが普段から見ている液体の水というのは、水分子といわれる目に見えない小さな粒が集まって構成されています。それらの水分子はお互いが繋がり合うことで液体の水になっています。なので水が蒸発するということは簡単に言えば、水(水分子が繋がり合っている状態)から水分子の繋がりが切れるということなんですね。そしてその水分子同士の繋がりから切れることで、水(液体)は水蒸気(気体)に変化します(この現象が蒸発)。つまり水蒸気というのは、水分子同士の繋がりから切れた水分子のことなんですね。関連:状態変化とは何か?物質が状態変化する仕組みを簡単に図解!関連:湯気と水蒸気の違いとは?物質の温度は分子運動の大きさ(速さ)によって決まる物質の温度というのは構成している分子の運動によって決まり、分子の運動が激しい(速い)ほどその物質の温度は高くなります。つまり水は水分子の動きが速いほど温度は高くなり、反対に水分子の動きが遅ければそれだけ温度は低くなるということです。水だけに限らず液体は温度が高くなればなるほど、その状態が液体から気体に変化しやすくなります。これは簡単に言えば、液体を構成している分子の運動が大きくなる(速く)ことで、それだけ分子の力が大きくなるので繋がりが切れやすくなるんですね。同じ重さのモノで動きの速いモノと遅いモノを比べた場合なら、動きの速いモノの方が自然と力は強くなります。これと同じで分子も動きの速いほうが力が強くなり、温度が高くなることで気体に変化しやすく(繋がりが切れやすく)なるということになります。関連:温度とは何か?物体の状態変化と温度の関係について解説!関連:絶対零度とは?また絶対零度の温度は何度なのか?同じ物質の分子でも運動の大きさが異なる分子が存在する先ほど物質の温度は分子の運動の大きさ(速さ)によって決まると解説しました。ここが今回で最も重要なポイントで物質の分子というのは、すべての分子が同じ動きをしているわけではありません。つまり温度が低い物質の分子の動きを見た場合は、動きの遅い分子だけではなく、動きの速い分子も一定数存在するということです。物質の温度は構成している分子の運動の大きさで決まっていますが、厳密に言えば動きの速い分子と遅い分子の平均によって決まります。イメージすると下図のようになります。温度が高い物質は動きが速い分子が全体的に多いけれど、少なからず動きの遅い分子も混ざっているということです。なので水の温度が100度に達していなくても少しずつ蒸発していくのは、水の温度が低くてもその中の分子には一定数動きの速い分子が混ざっているからなんですね。このとき動きの速い分子が、水の温度が100度のときの分子の動きと同等以上の速さになるので蒸発します。ではなぜこのように動きの速い分子が一定数できるのかというと、分子同士が衝突し合うことで運動エネルギーを交換しているからです。ボールとボールが衝突した様子をイメージしてみてください。ボールが衝突すればどちらか一方が速くなったり、遅くなったりすると思いますが、このようなことが分子同士でも常に起きているということになります。上図のように水分子同士でぶつかり合って運動エネルギーを交換することで、中には空気中に飛び出すだけのエネルギーを得る水分子も出てきます。そして水の温度が高くなればそれだけ水分子の運動も大きくなるので、空気中に水分子がより多く飛び出しやすくなります(蒸発しやすくなる)。このようなことが水分子同士で起こっているため、温度が100度にならなくても水は蒸発するんですね。(水以外の液体が沸点に達していないのに蒸発するのも仕組みは同じ)関連:気圧と沸点の関係について。気圧によって沸点が変化する仕組みとは?以上が「水が100度に達していないのに蒸発する仕組みとは?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、水が100度に達していないのに蒸発するのは、水の温度が低くても運動が大きくなる(速くなる)水分子が存在するから。分子同士が衝突し合うことで運動エネルギーを交換しているので、一定数動きの速い分子が生まれる。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒絶対熱とは何か?絶対熱の温度は何度あるのか?⇒なぜ風が吹くと洗濯物は乾きやすくなるのか?⇒湿度とは何か?湿度100パーセントとはどんな状態のこと?⇒水を沸騰させると発生する泡の正体とは?またなぜ泡は発生するのか?⇒結露とは何か?仕組みを分かりやすく図解!⇒ドライアイスとは?ドライアイスから発生する白い煙の正体って何?⇒氷とドライアイスと液体窒素の違いとは?最も温度が低いのはどれ?⇒蒸気圧とは?水の沸点と蒸気圧の関係についてわかりやすく解説!⇒揮発とは?蒸発との違いと意味は何か?なぜ揮発は起こる?⇒揮発性とは?揮発性が高い・低いとはどういう意味なのか?
ギモン雑学
「 水 」の検索結果
-
-
さてあなたは水を鍋などの容器に入れて沸騰させたことがあるでしょうか。容器の中に水を入れ、火にかけてから少し時間が経つと、水の中からボコボコッと泡が発生する現象が起こります。普段から料理をする人はこの光景をよく目にしているかもしれませんが、あらためて考えてみると泡の正体って何なんだろうと疑問に思う人も多いはずです。そこでこのページでは水を沸騰させると発生する泡の正体とは何なのか?またなぜ沸騰させると水の中から泡が発生するのかを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次水を沸騰させたときに発生する泡の正体とは?なぜ水の中から泡が発生するのか?まとめ1.水を沸騰させたときに発生する泡の正体とは?では水を沸騰させたときに発生する泡の正体とは何か見ていきましょう。さっそくですが水を沸騰させたときに発生する泡の正体は、水蒸気(すいじょうき)になります。水蒸気というのは水(液体)の状態が気体に変化したもので、水蒸気は無色透明なので目で見ることはできません。そして水(液体)から水蒸気(気体)に変化することで、水のときよりも体積が約1700倍も大きくなります。水が火で熱せられたことで液体である水が気体の水蒸気に変化して体積が大きくなるため、水の中で発生した水蒸気が周囲の水を押しのけて泡が発生しているんですね。(泡が発生する詳しい仕組みは次の章で解説します)また泡の正体についてよく誤解してしまうのが、水に溶けていた空気が出てきて泡として発生したというものです。何度も言いますが、泡の正体は空気ではなく”水蒸気”です。意外と間違えやすいとこなのでしっかりと覚えておきましょう。さて泡の正体が水蒸気ということは理解することができたと思いますが、次の章でなぜ水を沸騰させると泡(水蒸気)が発生するのかその仕組みを解説していきますね。関連:なぜ液体は温度が上がると気体に変化しやすくなるのか?関連:湯気と水蒸気の違いとは?2.なぜ水の中から泡が発生するのか?ではなぜ水の中から泡が発生するのか仕組みを簡単に見ていきましょう。結論から言ってしまうと水の中から泡が発生する仕組みは、水を火にかけることで水を構成している水分子の動きが激しくなるからです。これだけでは分からないと思うので、順番に解説していきますね。まず水は水分子といわれる小さな粒が集まって構成されていて、水の温度はその水分子の動きの激しさによって決まっています。水分子の動きが激しければ水の温度が高くなり、反対に水分子の動きが穏やかであれば水の温度は低くなります。そして水分子の動きが激しくなるということは、水分子が動くことのできる範囲が広くなるということでもあります。つまり水分子の動きが激しくなって動ける範囲が広くなるということが、水から水蒸気に変化したときに体積が急激に大きくなることと同じことを意味しています。水だけでなく物質には固体・液体・気体の3つの状態が存在しますが、この物質の状態というのはその物質を構成している分子の動きの激しさのことを表しています。なので水が沸騰するときの温度である100℃というのは、水が水蒸気に変化するときに必要な水分子の動きの激しさのことを表しているんですね。物質の状態変化について詳しくは下記をご覧ください。関連:状態変化とは何か?物質が状態変化する仕組みを簡単に図解!いままでのことが理解できればあとは簡単です。水は水分子が集まって構成されているので、容器の中に水を入れると下図のようなイメージです。水を沸騰させるときは水を入れている容器の底に火をかけていきますから、火が当たっている容器の底付近に存在する水から少しずつ熱せられていきます。上図のように容器の底付近に存在していた水分子は火によって動きが激しくなり(温度が上がり)、水分子の動きが激しくなっていくと最終的には水(液体)から水蒸気(気体)に変化することになります。それにより容器の底付近で水が水蒸気に変化すると、水(液体)よりも水蒸気(気体)の方が軽いので上昇していきます。(水蒸気の方が水よりも密度が小さい)この容器の底付近から上昇してきた水蒸気が、水が沸騰したときに発生していた泡の正体なんですね。関連:水が100度に達していないのに蒸発する仕組みとは?以上が「水を沸騰させると発生する泡の正体とは?またなぜ泡は発生するのか?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、水を沸騰させると発生する泡の正体は、水蒸気(水が気体に変化したもの)。水を沸騰させると泡が発生するのは、水を火にかけることで水を構成している水分子の動きが激しくなるから。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒温度とは何か?物体の状態変化と温度の関係について解説!⇒熱と温度の違いとは?⇒シンクに熱湯を流すとボコッと音がする理由とは?熱湯は流さない方が良いのか?⇒ドライアイスとは?ドライアイスから発生する白い煙の正体って何?⇒気温と温度と室温の違いとは?⇒なぜ熱は必ず温度が高い方から低い方へと移動するのか?⇒氷とドライアイスと液体窒素の違いとは?最も温度が低いのはどれ?⇒凝結と結露の違いとは?⇒なぜ氷は空気中よりも水中の方が溶けやすいのか?⇒液体の膨張と圧縮とは?温度によって液体の体積が変化する仕組みを図解!
-
さてあなたは水の中にドライアイスを入れたところを見たことがありますか?水の中にドライアイスを入れると水の中からブクブクと泡が出てきますが、なにやら水を加熱したときに水が沸騰している様子と少し似ています。しかし加熱しているわけでもないのに、なぜ沸騰したようになるのか疑問に思いますよね。そこでこのページでは、なぜ水の中にドライアイスを入れるとブクブクと泡立つのかを解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次なぜ水の中にドライアイスを入れるとブクブクと泡立つのか?まとめ1.なぜ水の中にドライアイスを入れるとブクブクと泡立つのか?ではなぜ水の中にドライアイスを入れるとブクブクと泡立つのかを見ていきましょう。結論から言ってしまうと水の中にドライアイスを入れると泡立つ理由は、水の中でドライアイスの表面から気化した二酸化炭素が発生するからです。まずドライアイスは二酸化炭素が固体になったもので、その温度は-79℃以下と低温です。そしてドライアイスは温度が-79℃よりも高くなると、固体からそのまま液体にならずに気体の二酸化炭素に変化します。(固体から液体にならずに気体に変化することを昇華と言います)水の中にドライアイスを入れることでブクブクと泡立つので、「もしかして水が沸騰してるのではないか?」と思う人もいるかもしれません。しかしそれは間違いで、ただ水の中で気体の二酸化炭素が発生しているだけです。普通の冷凍庫の中の温度が-20℃ほどなので、温度が-79℃以下の状況は特殊な設備がなければ作れません。ですのでドライアイスはほとんどの場合で、空気中でも水中でも暖められていることに変わりはないので少しずつ気体に変化していきます。上図のように水の中にドライアイスを入れると水によって暖められるので、それにより昇華し始めるためドライアイスの表面から気体の二酸化炭素が発生します。二酸化炭素は固体(ドライアイス)から気体に変化することで、体積が約800倍に膨れ上がります。これにより体積が大きくなる現象が水(液体)の中で起こるから、体積が膨れ上がった気体が泡として発生するんですね。ちなみに固体の二酸化炭素であるドライアイスは白い塊をしていますが、気体の二酸化炭素の色は無色透明なので注意してくださいね。関連:ドライアイスとは?ドライアイスから発生する白い煙の正体って何?また水の中にドライアイスを入れるとブクブクと泡立つ現象は、水を入れた鍋を加熱して沸騰させたときの様子に似ています。水の入った鍋を加熱して少し経過すると、鍋の底からボコボコッと泡が発生しますよね。この場合は鍋底の水が暖められたことで気体の水蒸気に変化したことによるものですが、水の中にドライアイスを入れたときに泡立つのも考え方は似たようなものです。泡が発生する理由が”水が沸点に達したことで水蒸気に変化するのか”、”水の中でドライアイスが昇華して気体の二酸化炭素に変化するのか”ってだけです。水は水蒸気に変化すると体積が約1700倍に膨れ上がり、ドライアイスは気体の二酸化炭素に変化すると約800倍に膨れ上がります。なので液体(水)の中で泡が発生する原理としては、二酸化炭素も水蒸気もほとんど変わらないというわけです。関連:空気の膨張とは何か?空気の温度によって体積が変化する仕組みとは?関連:気圧と沸点の関係について。気圧によって沸点が変化する仕組みとは?以上が「なぜ水の中にドライアイスを入れるとブクブクと泡立つのか?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、水の中にドライアイスを入れると泡立つ理由は、水中でドライアイスから気体の二酸化炭素が発生するから。固体の二酸化炭素(ドライアイス)から気体に変化すると、体積が約800倍に膨れ上がる。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒氷とドライアイスと液体窒素の違いとは?最も温度が低いのはどれ?⇒ドライアイスの安全な処理方法とは?またどういう処理が危険なのか?⇒沸騰したお湯にドライアイスを入れると爆発するのか?⇒ドライアイスを密閉した容器に入れると爆発する仕組みとは?⇒スプーンをドライアイスに付けると音がする仕組みとは?⇒粉塵爆発とは何か?粉塵爆発の原理をわかりやすく図で解説!⇒質量とは?重量(重さ)との違いと単位について⇒一酸化炭素中毒とは?発生する原因と仕組みについて簡単に解説!⇒水を沸騰させると発生する泡の正体とは?またなぜ泡は発生するのか?⇒なぜ氷は空気中よりも水中の方が溶けやすいのか?
-
さてあなたは蒸気圧という言葉を聞いたことがあるでしょうか。蒸気機関車や蒸気船という乗り物を知っていると思いますが、これらの乗り物の動力源として主に蒸気圧が利用されています。そこまで私たちは日常的に蒸気圧という言葉を使用することはありませんが、中には蒸気圧とはどういうものなのか疑問に感じる人も多いはずです。そこでこのページでは蒸気圧とは何か?また水の沸点と蒸気圧の関係についてわかりやすく解説しています。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次蒸気圧とは何か?水の沸点と蒸気圧の関係について水が蒸発した場合(表面から気体に変化)水が沸騰した場合(内部から気体に変化)まとめ1.蒸気圧とは何か?では蒸気圧とは何か見ていきましょう。蒸気圧(じょうきあつ)とは、蒸気によって発生する圧力のことを言います。蒸気というのは液体や固体が気体に変化したもので、液体が気体に変化することは蒸発、固体が気体に変化することを昇華と言います。関連:状態変化とは何か?物質が状態変化する仕組みを簡単に図解!蒸気圧について私たちの身近なもので例にすると、ヤカンに水を入れて沸騰させた場合です。水を入れたヤカンを加熱していくと次第に中の水は温度を上げていきますが、しばらくするとヤカンのふたがカタカタと音を立てて動きますよね。あのヤカンのふたを動かす現象こそまさに、蒸気圧によるものです。水の温度が100度に達すると沸騰し、水(液体)は水蒸気(気体)に変化します。そして水蒸気は水のときよりも体積が約1700倍大きくなります。そしてヤカンの中では体積が大きくなった水蒸気が、中から外に出ようとするためにヤカンのふたを持ち上げるんですね。このときの水蒸気がヤカンのふたを持ち上げる力が蒸気圧です。ちなみに水蒸気は無色透明な気体で実際に目で見ることはできず、もし目で見ることができたのならそれは水蒸気ではないので注意してください。関連:湯気と水蒸気の違いとは?また蒸気圧自体は水のみに限らず液体や固体が気体に変化することで発生するものですが、一般的にただ蒸気圧と言う場合には水蒸気による圧力のことを指していることが多いです。このページの冒頭でも少し触れていた蒸気機関車や蒸気船などは、水(液体)が水蒸気(気体)に変化したことで発生する圧力を動力源にしています。だから蒸気圧を動力源としてその乗り物の機関に利用しているため、蒸気機関車や蒸気船のように蒸気という言葉が名前に入っています。(機関とは、水力・火力・電力などを力学的エネルギーに変換する装置のこと)次の章で水の沸点と蒸気圧の関係について解説していきますね。2.水の沸点と蒸気圧の関係についてでは水の沸点と蒸気圧の関係について見ていきましょう。結論から言ってしまうと水の沸点というのは、蒸気圧が大気圧よりも大きくなったときの温度のことを表しています。大気圧(たいきあつ)とは、空気によって発生する圧力のことです。(圧力の考え方としては蒸気圧と同じで、違いはそれが蒸気なのか空気なのかってだけ)大気圧はただ単に気圧と呼ばれることも多いです。関連:気圧とは何かをわかりやすく解説!なぜ気圧で人はつぶされないのか?関連:気圧と大気圧の違いとは?どういうことなのか、まずは水が水蒸気に変化することについて理解する必要があります。水は水分子という小さな粒がお互いに繋がり合い集まることで構成されていて、その水を構成している水分子が空気中に飛び出すことで水が水蒸気に変化します。なので水を構成している水分子という小さな粒が水蒸気ということになります。(それが集まることで水という液体を作りだしています)ではどんなときに水を構成している水分子が空気中に飛び出すのかと言うと、それは水を構成している水分子の力が大気圧を超えたときです。水だけに限ったことではありませんが物質を構成している分子は常に運動していて、温度というのはその物質を構成している分子の運動の大きさで決まります。簡単に言えば、分子の運動が激しいほどその物質の温度が高くなり、分子の運動が穏やかなほどその物質の温度は低くなります。水などの液体は温度を上げていくことで気体に変化しやすくなりますが、その理由は分子の運動が激しくなることによって空気中に飛び出しやすくなるからなんですね。分子の運動が激しくなるということは分子の持つ力が大きくなるということになり、水を構成している水分子同士の繋がりから切れやすくなります。関連:温度とは何か?物体の状態変化と温度の関係について解説!もうお分かりかと思いますが蒸気圧(水蒸気による圧力)と言うのは、水分子が運動することによって他の物質に水分子が衝突してかかる力のことです。前の章でヤカンのふたがカタカタと動くのは蒸気圧によるものだと解説しましたが、それをヤカンの中における水分子の運動という観点から見ていきましょう。上図のようにヤカンのふたがカタカタと動くのは、ヤカンの中で水分子が激しく運動していてふたに衝突しているからです。(つまりヤカンのふたには中から蒸気圧がかかっているから)もしもその蒸気圧がアルコールが気体に変化したことで発生するものであれば、その場合の蒸気圧は水分子ではなくアルコール分子の衝突による力のことになります。さてここからが本題です。先ほど水の沸点は、蒸気圧が大気圧よりも大きくなったときの温度のことだと言いました。水が水蒸気に変化するのは空気中に水分子が飛び出すことによるものですが、その際には空気中に存在する大気圧のことも考えなければなりません。水蒸気における蒸気圧であれば水分子が衝突する力のことを表していて、それが大気圧の場合であれば空気分子が衝突する力のことを表しています。そして水が水蒸気に変化するときは水分子の衝突する力(蒸気圧)が、空気分子の衝突する力(大気圧)を超えなければ水蒸気に変化することができません。上図のように大気圧(空気分子)によって水分子が上から押さえつけられている状態なので、空気中に飛び出すためには水分子に大気圧を超える力が必要です。だから水の温度を上げていけば水分子の運動が激しくなり、水分子の持つエネルギーも大きくなるので水蒸気に変化しやすくなるんですね。なので水の沸点が100度なのは蒸気圧の関係から言ってしまうと、水分子の運動の大きさが大気圧を超えるのが100度だからということになりますね。また細かく言えば蒸発と沸騰は違うもので、蒸発は液体の表面から気体に変化して、沸騰は液体の内部から気体に変化します。沸点というのは蒸発するときの温度ではなく、沸騰するときの温度を表しています。水が蒸発しても沸騰しても水蒸気に変化するという点では変わりませんが、変化するのが表面からなのか内部からなのかで蒸気圧と大気圧の関係が少しだけ異なります。では蒸発と沸騰の場合についてそれぞれ解説していきます。水が蒸発した場合(表面から気体に変化)水が蒸発する場合の蒸気圧と大気圧の関係について言えば、蒸気圧が大気圧以上になれば水は水蒸気に変化することができます。何が違うのかというと水を沸騰させる場合は蒸気圧が大気圧を超える必要がありますが、水を蒸発させる場合は蒸気圧が大気圧と同じでも構わないということです。蒸発するということは水の表面から水蒸気に変化することなので、水の表面から水分子が空気中に飛び出すことができれば良いわけです。なので水の表面から空気中に水分子を飛び出させるためには、水の表面に対してかかっている大気圧と同じ以上の力が必要になります。蒸気圧(水分子の力)と大気圧(空気分子の力)の強さが同じであれば、どちらか一方が抑えられるということもなくなりますからね。ちなみに水の蒸発は、沸騰とは違い水の温度に関係なく起こります。食器を洗ったあとや洗濯物を干したあとにそれをしばらく放置してみると、何もしなくても水が乾いていますよね(場合によっては乾きにくいこともありますが)。このように蒸発という現象は水の温度に関係なく起こることが分かります。関連:水が100度に達していないのに蒸発する仕組みとは?水が沸騰した場合(内部から気体に変化)水が蒸発する場合の蒸気圧と大気圧の関係について言えば、蒸気圧が大気圧を超えていれば水は水蒸気に変化することができます。蒸発のときは蒸気圧と大気圧が同じでも気体に変化することができましたが、沸騰の場合は水の内部から気体に変化するため大気圧と同じではダメです。それはなぜかというと、水の内部では大気圧だけでなく水圧もかかってしまうからです。上図ではイメージしやすいように水圧は下向きの力しか書いていませんが、実際に水圧(気圧についても)は下向きだけでなくあらゆる方向にかかるので注意してください。関連:水圧とは何か?わかりやすく図を用いて解説!火で加熱していくことで水の温度を少しずつ上げていき、容器の底部分に火が当たっているため、底に存在している水から徐々に温度が上がっていきます。ということは底に存在している水分子の運動が激しくなるということです。そして容器の底付近に存在する水分子の運動が、大気圧+水圧以上になれば内部で水蒸気に変化することができます。液体の内部から気体に変化.....つまり沸騰するということですね。液体の内部から気体に変化するイメージは少し難しいですが、このように考えてみてはいかがでしょうか。加熱されて水の温度が上がることで水分子の運動は激しくなり、ある一定以上の激しさになると他の水分子を押しのけることができます。他の水分子を押しのけることができる激しさを得ることができるのは、水が沸点に達したとき(水分子が大気圧と水圧以上の力になったとき)です。水分子の運動の大きさ(蒸気圧)が大気圧と水圧の力よりも弱ければ、それらの圧力に押しつぶされることになるので水蒸気に変化することができなくなります。水蒸気は水分子の運動が激しくなることで持っている力が大きくなり、それにより動ける範囲が広くなるので水よりも体積が大きくなります。そして容器の底で発生した水蒸気は最終的に、上昇していきボコボコと泡となります。ちなみに一般的に水が沸騰するのは100度と知られていますが、水が100度で沸騰するのはあくまでも1気圧における場合です。1気圧というのは簡単に言えば地上での気圧の大きさのことで、気圧の低い場所に行くほど水が沸騰する温度は下がります。例えば富士山の山頂付近(高度3776m)であれば、周囲の気圧は約0.6気圧で、温度が約87度になると水は沸騰します。水だけでなく液体が沸騰する温度には、周囲の気圧が大きく関係しています。なぜ気圧によって沸点が変化するのか、詳しくは下記の関連リンクをご覧ください。関連:気圧と沸点の関係について。気圧によって沸点が変化する仕組みとは?関連:1気圧とは?1気圧って何ヘクトパスカル(hPa)?以上が「蒸気圧とは?水の沸点と蒸気圧の関係についてわかりやすく解説!」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、蒸気圧とは、蒸気によって発生する圧力のことで一般的には水蒸気圧を指すことが多い。蒸気圧は、水分子が運動することで他の物質に衝突したときにかかる力のこと。水の沸点は、蒸気圧が大気圧よりも大きくなったとき(厳密に言えば大気圧+水圧)の温度のこと。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒気化と蒸発と沸騰の違いとは何か?⇒空気の膨張とは何か?空気の温度によって体積が変化する仕組みとは?⇒真空とは何か?分かりやすく図で解説!⇒結露とは何か?仕組みを分かりやすく図解!⇒流体とは何かをわかりやすく解説!圧力はどんなかかり方なのか?⇒圧力鍋とは何か?圧力鍋の仕組みをわかりやすく図解!⇒ストローで飲み物を吸うことができる仕組みとは?⇒寒いと息が白くなる理由とは?南極では息が白くならないって本当?⇒コップに水滴がつく理由とは?分かりやすく仕組みを図で解説!⇒揮発とは?蒸発との違いと意味は何か?なぜ揮発は起こる?
-
さて夏になるとコップの中に飲み物と氷を入れて冷やして飲むことがあるかと思います。そして氷を入れた飲み物を少し放置していると、コップの表面に水滴がついてしまうことがよくあります。飲み物をこぼしたわけでもないのに「なぜコップに水滴がつくのだろうか?」と、中には疑問に思った人も多いのではないでしょうか。そこでこのページではコップに水滴がつく理由とは何か?またコップに水滴がつく仕組みを図で分かりやすく解説しています。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次コップに水滴がつく理由とは?分かりやすく仕組みを図で解説!まとめ1.コップに水滴がつく理由とは?ではコップに水滴がつく理由について見ていきましょう。結論から言ってしまうとコップに水滴がつく理由は、飲み物を入れた後にコップの表面で結露(けつろ)という現象が起こるからです。結露というのは、空気中の水蒸気が水になって物体の表面に付着する現象のことです。ちなみに水蒸気は水が気体になったものの名称で、目で見ることはできませんので注意してください。私たちの周りには空気が存在していますが、その空気には水蒸気が含まれています。空気によってどのくらいの水蒸気が含まれているのかは異なりますが、空気中にどのくらい水蒸気が含まれているかを表す指標として湿度(しつど)が使われます。普段からよく聞く言葉なので知っていますよね。また空気中にどのくらい水蒸気を含むことができるかは空気の温度によっても変化します。空気の温度が高ければそれだけ多くの水蒸気を含むことができ、反対に空気の温度が低ければ少ない水蒸気しか空気中に含むことができません。このように空気が含むことができる限界の水蒸気量を”飽和水蒸気量”と言います。そして冷たい飲み物を入れるとコップ周辺に存在する空気が冷やされ、空気中に含むことができる水蒸気の量が減るためその限界を超えた分が水滴になります。なのでコップ表面についてしまう水滴の正体というのは、コップ周辺に存在していた空気が元から含んでいた水蒸気が水になったものです。コップに入れるはずの飲み物がこぼれたとか、飲み物がコップの中から浸透したわけではありません。さて水滴がつく理由について言葉だけで解説しましたが、いまいちイメージできないという人のために次の章で図を用いて分かりやすく解説していきます。関連:結露とは何か?分かりやすく結露の仕組みを図解!関連:飽和水蒸気量とは?露点との違いは何か?2.分かりやすく仕組みを図で解説!ではコップに水滴がつく仕組みを図を用いて分かりやすく解説していきます。コップに水滴がつく理由は、冷たい飲み物を入れることでコップ表面に飲み物の冷たさが伝わり、コップ周辺の空気が冷やされるため空気中に含むことができなくなった水蒸気が水として現れるからです。まずこの仕組みを理解するうえで重要なポイントが、空気の温度によって空気中に含むことができる水蒸気の量が変化するということです。上図のようなイメージをしていただければ良いです。温度の高い空気の方が容量...つまり含むことができる水蒸気量が多くなり、温度の低い空気は高い空気よりもその容量が少なくなります。では次にコップに冷たい飲み物を入れたときの様子を図で見てみましょう。冷たい飲み物を入れることで飲み物の冷たさがコップ表面まで伝わり、表面周辺の温度の高い空気が温度の低い空気に変化します。そして温度の低い空気というのは温度の高い空気に比べて、空気中に含むことができる水蒸気量が少ないです。もしこのときに温度の高い空気が水蒸気を多く含んでいたら、空気の温度が低くなることによって空気中から追い出される水蒸気が発生します。これによって空気中から追い出された水蒸気というのが、コップの表面に付着する水滴のことなんです。だからコップに冷たい飲み物を入れると、よく水滴が発生するんですね。関連:湿度とは何か?湿度100パーセントとはどんな状態のこと?関連:湿気るとはどういう状態?お菓子が湿気る理由と元に戻す方法とは?以上が「コップに水滴がつく理由とは?分かりやすく仕組みを図で解説!」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、コップに水滴がつく理由は、飲み物を入れた後にコップの表面で結露(けつろ)という現象が起こるから。水蒸気は空気中に潜んでいるもので、目で見ることはできない。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒結露とは何か?分かりやすく結露の仕組みを例とともに解説!⇒揮発とは?蒸発との違いと意味は何か?なぜ揮発は起こる?⇒なぜ風が吹くと洗濯物は乾きやすくなるのか?⇒水が100度に達していないのに蒸発する仕組みとは?⇒気化と蒸発と沸騰の違いとは何か?⇒相対湿度と絶対湿度の違いとは?⇒蒸気圧とは?水の沸点と蒸気圧の関係についてわかりやすく解説!⇒湯気と水蒸気の違いとは?⇒なぜ同じ湿度(%)なのに季節によって水分量が異なるのか?⇒なぜ水の中にドライアイスを入れるとブクブクと泡立つのか?
-
さて何かしら災害などの緊急時に飲み水が足りなくなることがありますが、汚れた水をろ過して飲み水にするのを見たことがあるでしょうか。ペットボトルなどに様々な材料を敷き詰めていき、その上から汚い水を流していくと汚れの取れた水が出てきます。しかし飲み水として利用するときはろ過後の水をそのまま飲むのではなく、どういうわけか一度煮沸させてから飲むことが勧められています。そこでこのページでは、汚い水をろ過した後に煮沸させる目的を簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次なぜ汚い水はろ過した後に煮沸させるのか?まとめ1.なぜ汚い水はろ過した後に煮沸させるのか?ではなぜ汚い水はろ過した後に煮沸(しゃふつ)させるのか見ていきましょう。結論から言ってしまうとろ過した後の水を煮沸させる理由は、ろ過によって不純物は取り除けますが、細菌などの微生物は存在しているからです。ろ過によってある程度の大きさの汚れ(砂・粘土・葉・枝など様々)は水から取り除けますが、細菌などの微生物は小さいのでろ過では取り除くことができません。たとえろ過した後の水が透明であったとしても、透明な水がイコール清潔な水(健康に害のない水)である保証はありません。なので水をろ過した後に、ろ過後の水を煮沸して殺菌しなければなりません。(細菌などの微生物を体内に入れることは、食中毒の原因になります)簡単にまとめると、汚い水をろ過する目的は比較的大きな不純物を取り除くためで、ろ過した後の水を煮沸する目的は細菌などの微生物を殺すためになります。私たちは普段から何かしら食べ物を食べていますが、食べ物によっては焼かないと食べられないようなものも存在しますよね。例えばよく「豚肉や鶏肉はしっかり焼かないとダメ!」ということを聞きます。あれは”焼いた方が生の状態よりも美味しいから焼かないとダメ”と言っているのではなく、”肉に付いている菌を殺菌できないので焼かないとダメ”と言っているんですね。細菌などの微生物は食べ物や飲み物に付着することで繁殖していき、食べ物を腐らせたり、人間が食中毒になったりする主な原因でもあります。これと同様の理由から、ろ過して不純物を取り除いた後の水を煮沸させます。関連:酸化と腐るの違いとは?酸化した食品は食べたらダメなの?以上が「汚い水をろ過した後に煮沸させる目的とは何か?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、汚い水をろ過する目的は、砂などの不純物を取り除くため。ろ過した後の水を煮沸する目的は、細菌などの微生物を殺すため(殺菌して安全性を高める)。たとえろ過した後の水が透明でも、細菌などが繁殖していることも多いため注意が必要。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒水が腐る理由とは?また純水って腐るの?⇒浄水器とは?また浄水器ってどんな仕組みなの?⇒蒸留とは何か?簡単に仕組みを図解!⇒水垢とは何か?水道周りに白い塊ができる仕組みについて図解!⇒希釈の意味とは?計算方法と対義語について簡単に解説!⇒暖かい水と冷たい水で重さが変わる仕組みとは?⇒溶媒と溶質と溶液の違いとは?⇒海水と淡水と真水の違いとは?⇒結露とは何か?仕組みを分かりやすく図解!⇒氷とドライアイスと液体窒素の違いとは?最も温度が低いのはどれ?
-
さて暖かい水と冷たい水では重さが異なるという話を聞いたことはないでしょうか。実際に暖かい水は上に冷たい水は下にたまるので、お風呂で冷たい水が下の方にたまっていたという経験がある人も多いはずです。暖かい水は軽くて冷たい水は重くなると覚えておくだけでも特に問題ありませんが、なぜ温度によって水の重さが変化するのか疑問に感じる人もいますよね。そこでこのページでは、暖かい水と冷たい水で重さが変わる仕組みを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次水の温度が変わることで密度が変化する暖かい水が軽く、冷たい水が重くなる仕組みなぜ同じ体積の水なのに重さが異なるのか?まとめ1.水の温度が変わることで密度が変化するでは水の温度が変わることで密度が変化することについて見ていきましょう。結論から言ってしまうと、水の温度によって変化するのは重さではなく密度になります。密度というのは体積1[cm^3]当たりに何[g]の質量があるのかを表しているもので、密度の単位として[g/cm^3]が使用されています。密度は簡単に言えば、物質がどれだけ密に詰まっているのかその度合いを表したものです。関連:密度と比重の違いとは?また密度と比重の単位って何?そして重要なポイントなので何度も言いますが、温度によって変化するのは水の重さではなく水の密度です。たとえ温度が変化しても水の重さ自体は変わらず、密度だけが変化することになります。水は温度が変化することで体積が膨張したり圧縮したりしますが、そのときに水の重さは変化せず、体積変化に伴い水の密度だけが変化します。上図のように水を暖めると体積が膨張して大きくなり、水を冷やすと体積は圧縮されて小さくなります(このとき重さは変化せず)。密度はその物質がどれだけ密に詰まっているのかを表す度合いなので、密度が小さければあまり詰まっておらず、密度が大きければよく詰まっているということになります。これが水の温度変化によって、水の密度だけが変化するということです。ちなみに水の体積が温度によって膨張・圧縮する仕組みは、基本的に空気が膨張・圧縮するのと同じものです。なぜ体積が変化するのか、詳しい仕組みは下記の関連リンクからご覧ください。関連:空気の膨張とは何か?空気の温度によって体積が変化する仕組みとは?2.暖かい水が軽く、冷たい水が重くなる仕組みでは暖かい水が軽く、冷たい水が重くなる仕組みを見ていきましょう。まず私たちは普段から重い軽いと様々なモノの重さを比較していると思いますが、モノの重さを比較する場合はそのモノの重さではなく密度で比べなければなりません。例えば金と綿がそれぞれ1kgずつあったとします。では上図の1kgの金と1kgの綿ではどちらの方が重いでしょうか?正解は、どちらも同じ重さです。普通であれば綿よりも金の方が圧倒的に重いはずですが、上の図ではなぜ金と綿が同じ重さになったのでしょうか。それは比較するときに同じ体積当たりの質量(つまり密度)で比べていないからです。綿のようにどんなに軽いものであったとしても数を積み上げていけば、どんなに重い物質にも匹敵する以上の重さにすることができます。なのでモノの重さを比較する場合は、それぞれの密度で比べなければなりません。さて今までの解説ですでに理解されているとは思いますが、暖かい水が軽くなり、冷たい水が重くなる仕組みについて見ていきましょう。暖かい水は温度が上がることで膨張して密度が小さくなり、冷たい水は温度が下がることで圧縮して密度が大きくなります。そして温度が変化してもそれぞれの水の重さ自体は変わらないため、体積当たりの質量の大きさによってその物質の重い・軽いが決まります。体積当たりの質量が大きくなることでより地球からの重力がかかりやすくなるので、それにより密度の大きい方がより地球の中心に引き寄せられやすくなります。つまり密度が大きいモノの方が重いということです。なので冷たい水の方が密度が大きくなるため、暖かい水に比べて重くなるんですね。また暖かい水は軽くて、冷たい水が重いのは簡単に下図のようなイメージです。暖かい水は軽くなって冷たい水が重くなるというのは上図のように、暖かい水(密度が小さい)が冷たい水(密度が大きい)の上に乗っているイメージになります。例えば極端ですが豆腐(密度が小さい)の上に鉄の塊(密度が大きい)を乗せようとすれば、鉄の塊は豆腐よりも密度が大きいので重力によって下に行こうとして豆腐はつぶれます。反対に鉄の塊の上に豆腐を乗せるのであれば、特に問題なく鉄の塊の上に豆腐を乗せることができますよね。暖かい水が上にたまって、冷たい水が下にたまるのはこれと同じです。このように暖かい水と冷たい水をそれぞれ別のモノであると捉えれば、簡単にイメージできるようになります。関連:重力と重力加速度と重さ(重量)の違いとは?次の章では容器の中に同じ体積で温度が違う水を入れた場合の重さについて解説します。3.なぜ同じ体積の水なのに重さが異なるのか?ではなぜ同じ体積の水なのに重さが異なるのかを見ていきましょう。これは先ほどまでの解説をしっかりと理解していればすぐに分かります。例えば同じ体積の容器を2つ用意して、暖かい水と冷たい水をそれぞれの容器にギリギリまで入れます。このときに暖かい水と冷たい水ではどちらが重くなるでしょうか?「どちらもの水も体積が同じなんだから同じ重さになるに決まってる」と思う人も多いでしょう。ですが正解は同じ重さではなく、冷たい水が入った容器の方が重くなります。なぜ同じ体積なのに冷たい水の方が重くなるのかというと、それは冷たい水の方が暖かい水よりも密度が大きいからになります。これだけでは少し分かりにくいため、もう少し簡単に解説していきますねまず水は温度が上がると膨張し温度が下がると圧縮するので、なので暖かい水は体積が大きくなり冷たい水は体積が小さくなります。このときに重さ自体は変わらないので、水の密度だけが変化します。ではこれを簡単に数値にして表してみましょう。上図のように暖かい水と冷たい水では重さは数値10で同じですが、体積は暖かい水が15、冷たい水が5と異なります(数値は適当に付けています)。そしてそれぞれの水を体積60まで入れることができる容器に流していき、水位がギリギリになったところでそれぞれの重さを測るとどうなるでしょうか?(このとき水をまとまった液体ではなく、ひとつひとつ個別のものとしてみていきます)暖かい水の方は体積60まで入る容器に4個分、冷たい水の方は体積60まで入る容器に12個分収めることができます。そうすると暖かい水は体積60に対して重さが40(=4個分×10)となりますが、冷たい水は同じ体積60でも重さが120(=12個分×10)となりますよね。なので同じ体積でも冷たい水のほうが暖かい水よりも重くなるんですね。以上が「暖かい水と冷たい水で重さが変わる仕組みとは?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、水の温度が変化することで重さではなく、水の密度が変化する。どちらが重いかを判断するときは、それぞれの密度(同じ体積当たりの質量)で比べること。冷たい水は暖かい水よりも密度が大きくなるため重くなる(地球の中心に引き寄せられやすくなる)。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒水圧とは何か?わかりやすく図を用いて解説!⇒密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?⇒重力加速度とは?仕組みを分かりやすく図解!⇒水垢とは何か?水道周りに白い塊ができる仕組みについて図解!⇒蒸留とは何か?簡単に仕組みを図解!⇒溶媒と溶質と溶液の違いとは?⇒海水と淡水と真水の違いとは?⇒水道水のカルキとは?また塩素とカルキは何が違うのか?⇒浄水器とは?また浄水器ってどんな仕組みなの?⇒汚い水をろ過した後に煮沸させる目的とは何か?
-
さて私たちが普段から飲んでいる水ですが、食べ物と同様に腐ることがあるのは知っていましたか?私たちがいつも使用している水は消毒されていてきれいなので、水が腐るってあまりイメージできないですよね。なのでここでは水が腐るとはどういうことなのか?また純水の場合も腐ることはあるのかを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次水が腐る理由とは?純水って腐るの?まとめ1.水が腐る理由とは?まず水が腐る理由の前にどういう状態の水が腐っていると言えるのでしょうか。水が腐っている状態の基準としては、水から異臭がする水が濁っているこのような状態の場合は水が腐っている状態と言えます。では本題に入ります。水が腐る理由とは何なのか。それは、水の中に含まれているミネラルなどの有機物を微生物が栄養として増殖していくからです。水の中にはミネラルなどの有機物が含まれています。また空気中には菌などの微生物がそこらじゅうに漂っています。水が腐る仕組みを順番に説明していくと以下の通りになります。<水が腐る仕組み>①水が空気に触れることで水の中に微生物が混じる。②微生物が水に混じると水の中に含まれている有機物を栄養として、微生物がどんどん増殖していく。③微生物によって栄養となった有機物が分解され、その分解作用によって様々な物質が生成される。④分解作用によって生成された物質や増殖した微生物によって、水が濁ったり異臭を放ったりするいわゆる水が腐るという現象になる。ちなみに水が腐っている状態を細かく言ってしまえば、水そのものが腐っているわけではなく、水の中に微生物が繁殖してしまい飲めなくなるということです。なのでたとえ腐っていると言われている水であったとしても、しっかりと滅菌して身体に悪い影響をもたらす微生物さえ除去してしまえば再び飲めるようになるんです。次の章では純水の場合だとどうなるのか見ていきましょう。2.純水って腐るの?では純水(じゅんすい)は腐ってしまうのかについて見ていきましょう。まず純水というのは、ミネラルなどの不純物がほとんど含まれていない純粋な水になります。水道水なんかはミネラルやカルキなどの不純物が入っているので純水とは呼ばないです。純水は人工的に作るもので自然の水ではないのでご注意を。先ほど説明した通り水が腐ってしまう理由は、微生物が水の中に含まれているミネラルなどの有機物を栄養として増殖し、微生物の分解作用によって悪い物質が生成されてしまうことが原因ですよね。もうピン!ときたのではないでしょうか。純水には微生物の栄養となるミネラルなどの有機物がほとんど含まれていないため、増殖することができないので腐ることはありません。何度も言いますが、微生物は有機物を栄養に増殖していきます。単純に水そのものは無機物なので純水の場合だと微生物の栄養とするものがないんですね。ですので純水の場合は腐ることはないということです。ですが純水の場合でもしっかり管理がされていなければ、外部から不純物が混じってしまい腐るということは十分考えられます。そうなってしまったら、純水ではなくなるので腐ってしまいます。簡単に説明すると純水を腐らないようにするには、純水を無菌で保存できる環境と空気に触れないように完全に密封した状態を保つ必要があります。空気中には菌などの微生物がウヨウヨしていますので、空気に触れるだけでも菌が混じってしまいます。以上が「水が腐る理由とは?また純水って腐るの?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、水が腐る理由は、水の中に含まれているミネラルなどの有機物を微生物が栄養として増殖していくから。水が濁ったり異臭を放つのは、微生物の増殖や微生物によって有機物が分解されその分解作用によって生成される物質が原因。純水とは、ミネラルなどの不純物をほとんど含まれていない純粋な水のこと。純水にはミネラルなど微生物の栄養となるものがほとんど含まれていないため、増殖できないので腐らない。純水は腐らないが、保存方法が悪ければ不純物が混じってしまうため純水ではなくなり腐ってしまう可能性も十分ある。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒コップに水滴がつく理由とは?分かりやすく仕組みを図で解説!⇒浄水器とは?また浄水器ってどんな仕組みなの?⇒汚い水をろ過した後に煮沸させる目的とは何か?⇒水垢とは何か?水道周りに白い塊ができる仕組みについて図解!⇒希釈の意味とは?計算方法と対義語について簡単に解説!⇒暖かい水と冷たい水で重さが変わる仕組みとは?⇒蒸留水と純水の違いとは?⇒海水と淡水と真水の違いとは?⇒結露とは何か?仕組みを分かりやすく図解!⇒氷とドライアイスと液体窒素の違いとは?最も温度が低いのはどれ?