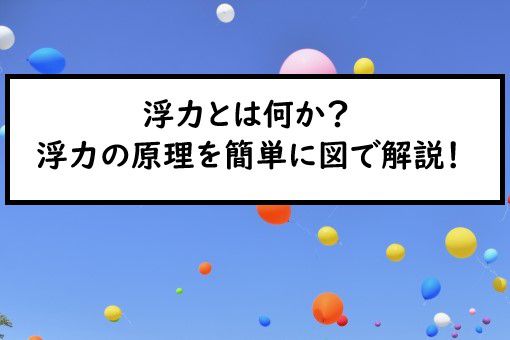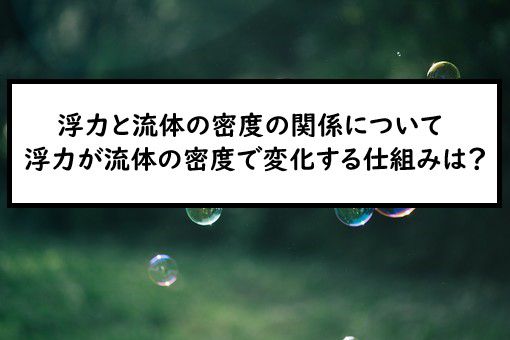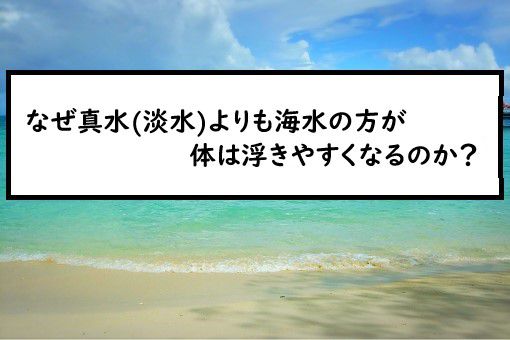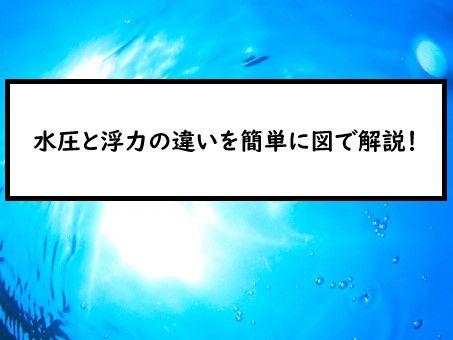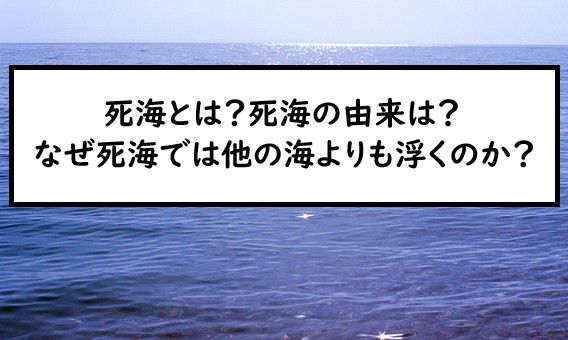さてあなたは浮力という言葉をご存知でしょうか。水の上に浮くことができるのはその物体に浮力が働いているからですが、実際に浮力がどのような力なのかをしっかりと理解している人は少ないように感じます。そこでこのページでは浮力とは何か?また浮力の原理を簡単に図を用いて解説していきます。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次浮力とは何か?浮力の原理について詳しく解説!流体中ではあらゆる方向から圧力がかかる流体中でかかる圧力のイメージ浮力は流体によって発生する下方向からの圧力のこと重い(密度が大きい)流体ほど浮力は大きくなるまとめ1.浮力とは何か?では浮力とは何かを簡単に見ていきましょう。結論から言ってしまうと浮力(ふりょく)とは、流体中において物体に対して、流体から上向きに働く力のことを言います。流体というのは水や空気のことを言い、水の上に物体が浮くのはその物体に水からの浮力が働いているからで、空気中に物体が浮くのはその物体に空気からの浮力が働いているからになります。浮力はどういうものかをイメージするのが難しいと感じている人は、重いボールの上に軽いボールが乗ったときに、重いボールが反発する力だと思ってみてください。つまり浮力(上向きの力)が働くというのは、上図のようなイメージです。関連:流体とは何かをわかりやすく解説!圧力はどんなかかり方なのか?例えば水に沈むモノと浮くモノが存在すると思いますが、これは水よりもそのモノが重いのか軽いのかということが大きく関係しています。水よりも密度が大きい(重い)モノは水に沈むことになり、水よりも密度が小さい(軽い)モノは水の上に浮くことになります。重いということはそれだけ地球の中心に引っ張られやすいということなので、水よりも重いモノであれば水を押しのけてしまうため水に沈むことになります。ここで先ほど解説した重いボールと軽いボールのことを思い出してみてください。水の上にモノが浮くということは”水が重いボール”で、”浮くモノが軽いボール”だと置き換えることができます。上図のように水の上にモノが浮くということは、水からの浮力(反発する力)の方がモノにかかる重力よりも大きいということです。反対に水にモノが沈むということは”沈むモノが重いボール”で、”水が軽いボール”と置き換えられます。この場合は沈むモノには水からの浮力(上向きの力)はかかってはいるのですが、水からの浮力よりもモノにかかる重力の方が大きいため他の水は押しのけられます。そして結果として水よりも密度の大きい(重い)モノは、水に浮かずに沈んでしまうんですね。関連:密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?関連:暖かい水と冷たい水で重さが変わる仕組みとは?ここでは浮力についてイメージできるよう簡単に解説しましたが、次の章では浮力の原理について詳しく解説していきます。2.浮力の原理について詳しく解説!前の章では浮力についてイメージするのが難しいと感じている人のために、浮力の詳しい原理ではなく、浮力とはどのようなものかを簡単に解説をしていきました。しかしここでは先ほどよりも浮力の原理について詳しく解説していきます。そして下の3つを理解できれば、浮力の原理について理解できるでしょう。流体中ではあらゆる方向から圧力がかかる流体中でかかる圧力のイメージ浮力は流体によって発生する下方向からの圧力のことでは浮力の原理を詳しく理解していただくために、上記について順番に解説していきますね。流体中ではあらゆる方向から圧力がかかる”流体中ではあらゆる方向から圧力がかかる”ということで、これが指している圧力とは”水であれば水圧”、”空気であれば気圧”のことを指しています。流体(水・空気など)であれば圧力のかかり方はほとんど変わらないので、ここでは水を例として流体中における圧力の解説をしていきます。まず水の中では、”水圧”という水の重さによる圧力が発生します。ここで注意して欲しいことは水圧は下方向だけにかかる力ではなく、あらゆる方向からかかっているということです。例えば風船に重りなどを付けて水に沈めていくと、水深が深くなるほど風船にかかる水圧が大きくなるため、風船が小さくなっていきます。このとき上図のように風船は一定方向につぶされていくのではなく、あらゆる方向から水圧がかかることによって、全体的に小さくなっていきます。関連:水圧とは何か?わかりやすく図を用いて解説!流体中でかかる圧力のイメージ次に流体中でかかる圧力のイメージを軟らかいボールを用いた例で解説していきます。(ボールを水だと仮定してイメージしてみてください)流体中にかかる圧力というのは、その流体の重さによってかかっているので、容器内のボールの上層から順番にどのような向きの力がかかっているのかを見ていきます。まずは上から1層目に存在するボールの重さによって、2層目に存在するボールに力が加わります。次に2層目のボールは横方向に力が流れ(1層目のボールの重さ分の力)、下方向(3層目)に1層目と2層目のボールの重さによる力が加えられます。また各方向へと力が流れていきますが、作用反作用の法則によってそれらの力とは逆向きの力も加わります。最終的に水圧の関係は上図のようになります。下方向だけではなくあらゆる方向から水圧がかかっているのが分かりますよね。そして深い層になるにつれてボール同士に働く圧力は大きくなっています。膨らませた風船を水中に沈ませれば全体的に水圧がかかることで小さくなりますが、正確には風船全体に等しい水圧がかかるというわけではありません。水深が深いほど風船には大きな水圧がかかるので、正しい水圧のかかり方は下図のようになります。水深が深くなるほど水圧を表している矢印が大きくなっていますよね。これが流体中(水圧だけでなく)における圧力のかかるイメージになります。浮力は流体によって発生する下方向からの圧力のこと最後ですが結論から言ってしまうと浮力というのは、流体によって発生する下方向からの圧力のことを指しています。先ほど解説した図に力の大きさを加えてみたので、まずは下を見てください。(数字は水圧の大きさになりますが、適当に付けたものです)上図では風船に上からかかる圧力、下からかかる圧力、左右横からかかる圧力で分けています。水深が深くなるほど風船にかかる圧力は大きくなっていくので、この中だと風船に下からかかる圧力が最も大きくなります。そして浮力というのは流体によって発生する下方向からの圧力のことで、この場合だと”浮力=風船の下からかかる圧力-風船の上から掛かる圧力”のことを言います。ですので数字で言うと、”浮力=7(下からの圧力)-3(上からの圧力)=4”ということになります。(左右横からかかる圧力は同じ大きさなので、横からの圧力は打ち消し合います)このとき水の上に物体が浮かぶのは”浮力>物体にかかる重力”となるからで、反対に”浮力<物体にかかる重力”となれば水の上には浮かばずに物体が沈んでいくことになります。また浮力は流体の重さによって発生する下方向からの圧力のことなので、無重力状態の空間では物体に浮力は発生しないので覚えておいてくださいね。関連:重力加速度とは?仕組みを分かりやすく図解!関連:重力と重力加速度と重さ(重量)の違いとは?3.重い(密度が大きい)流体ほど浮力は大きくなるでは重い(密度が大きい)流体ほど浮力が大きい理由を見ていきましょう。浮力というのは流体の重さによって発生する下方向からの圧力のことで、浮力の大きさはその流体の重さが重いほど大きくなると言えます。なので流体の重さが軽いほど(密度が小さいほど)、浮力も小さくなるということです。上図の2層目と3層目ではそれよりも上層にある水(流体)の重さが基準となって、周囲へと発生する流体の圧力の大きさが決まっています。例えば上層にある流体が軽ければ”1”の圧力しか下層へとかかっていきませんが、上層にある流体が重いのであれば”10”の圧力が下層へとかかってしまいます。そして浮力はその流体の重さによって発生する下方向からの圧力のことなので、上層から下層へかかる流体による圧力が大きくなるほど、下方向からの力である浮力も大きくなります。このようにその流体が重い(密度が大きい)ほど、浮力というのは大きくなるんですね。以上が「浮力とは何か?浮力の原理を簡単に図で解説!」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、浮力とは流体中において物体に対して、流体から上向きに働く力のこと。流体によって発生する圧力(水圧・気圧など)は、一定方向ではなくあらゆる方向からかかっている。浮力と言うのは、流体によって発生する下方向からの圧力のこと。重い(密度が大きい)流体ほど、浮力は大きくなる。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒なぜ真水(淡水)よりも海水の方が体がよく浮くのか?⇒浮力と流体の密度の関係について。流体の密度で浮力が変化する仕組みとは?⇒死海とは?死海の由来は?なぜ死海は他の海よりも浮くことができるのか?⇒水温と浮力の関係について。水温によって浮力が変化する仕組みとは?⇒水圧と浮力の違いについて簡単に図で解説!⇒なぜ氷は空気中よりも水中の方が溶けやすいのか?⇒熱気球とは?また熱気球はどんな原理で空中に浮いているのか?⇒気圧と大気圧の違いとは?⇒海水と淡水と真水の違いとは?⇒自由落下とは?空気抵抗・重さ・質量は関係ないのかを簡単に解説!
ギモン雑学
「 浮力 」の検索結果
-
-
さて水の中に空のペットボトルを入れると、そのペットボトルは沈まずに水の上に浮かんできます。このときペットボトルに対して水から働いている力を”浮力”と言います。そして流体(水など)の密度によって、浮力の大きさは変化するのはご存知でしょうか。そこでこのページでは浮力と流体の密度の関係について。また流体の密度によって浮力が変化する仕組みを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次浮力と流体の密度の関係について流体の密度によって浮力が変化する仕組みとは?浮力とは流体の重さによって発生する圧力流体が重い(密度が大きい)ほど浮力は大きくなるまとめ1.浮力と流体の密度の関係についてでは浮力と流体の密度の関係について見ていきましょう。結論から言ってしまうと、浮力と流体の密度の関係は下のようになります。流体の密度が小さい(軽い) ⇒ 浮力は小さくなる流体の密度が大きい(重い) ⇒ 浮力は大きくなる流体というのは”液体と気体の総称のこと”で、空気や水も流体であると言えます。なかには浮力は水のときにだけ働く力だと思っている人も多いですが、実は空中にゴム風船が浮かぶのも空気による浮力が働いているからなんですね。流体(液体・気体)であれば水や空気以外でも浮力は働きます。関連:風船にヘリウムガスを入れると空中に浮く理由とは?関連:なぜ空中に浮く風船と浮かない風船があるのか?また上記の浮力と流体の密度の関係で”流体の密度が小さい・大きい”とあります。密度はどれだけ密に詰まっているかの度合いを表しているので、”密度が小さい”なら密に詰まっていない、”密度が大きい”なら密に詰まっているということです。つまり密度が小さい物質なら中身が密に詰まっていないので”軽く”、反対に密度が大きい物質なら中身が密に詰まっているので”重く”なります。そして流体の密度が小さければ(軽ければ)浮力は小さくなり、流体の密度が大きければ(重ければ)浮力は大きくなります。関連:浮力とは何か?浮力の原理を簡単に図で解説!関連:密度とは?比重との違いと単位について次の章で流体の密度によって浮力が変化する仕組みについて解説していきます。2.流体の密度によって浮力が変化する仕組みとは?では流体の密度によって浮力が変化する仕組みを見ていきましょう。さっそくですが流体の密度によって浮力が変化するのは、浮力そのものが流体の重さによって発生している力だからです。なので無重力の空間では浮力は発生しません。浮力とは流体の重さによって発生する圧力流体が重い(密度が大きい)ほど浮力は大きくなるさてこれだけでは理解するのが難しいと思うので、上記について順番に解説していきます。関連:重力と重力加速度と重さ(重量)の違いとは?浮力とは流体の重さによって発生する圧力浮力とは流体中において物体に対して、流体から上向きに働く力のことです。流体中においてどのように力がかかっているのかを図で示すと下のようになります。(容器内の丸いボールを流体だと仮定してください)流体中にかかる圧力というのは、その流体の重さによってかかっているので、容器内のボールの上層から順番にどのような向きの力がかかっているのかを見ていきます。まず上から1層目に存在するボールの重さによって、2層目に存在するボールに力が加わります。次に2層目のボールは横方向に力が流れ(1層目のボールの重さ分の力)、下方向(3層目)に1層目と2層目のボールの重さによる力が加えられます。また各方向へと力が流れていきますが、作用反作用の法則によってそれらの力とは逆向きの力も加わります。最終的に流体の重さによって発生する圧力の関係は上図のようになりますが、下方向だけではなく、あらゆる方向から流体による圧力がかかっているのが分かりますよね。このことから深い層になるにつれてボール同士に働く圧力は大きくなっていきます。例えば空気を入れて膨らませた風船を水中(流体中)に沈めていくと、風船に対して水から下図のような向きと強さの圧力がかかることになります。上図では風船に上からかかる圧力、下からかかる圧力、左右横からかかる圧力で分けています。水深が深くなるほど風船にかかる水からの圧力は大きくなっていくので、この中だと風船に下からかかる圧力が最も大きくなります。そして浮力というのは流体の重さによって発生する下方向からの圧力(つまり上向きの力)のことなので、この場合だと”浮力=風船の下からかかる圧力-風船の上から掛かる圧力”のことを指します。ですので数字で言うと、”浮力=7(下からの圧力)-3(上からの圧力)=4”ということになります。(左右横からかかる圧力は同じ大きさなので、横からの圧力は打ち消し合います)このとき水の上に物体が浮かぶのは”浮力>物体にかかる重力”となるからで、反対に”浮力<物体にかかる重力”となれば水の上には浮かばずに物体が沈んでいくことになります。関連:水圧とは何か?わかりやすく図を用いて解説!流体が重い(密度が大きい)ほど浮力は大きくなる流体が重い(密度が大きい)ほど浮力は大きくなり、反対に流体が軽い(密度が小さい)ほど浮力は小さくなります。先ほどの容器内にボールを積み上げた図を用いて解説していきます。上図の2層目と3層目ではそれよりも上層にある流体の重さが基準となって、周囲へと発生する流体による圧力の大きさが決まることになります。例えば上層にある流体が軽ければ”1”の圧力しか下層へとかかっていきませんが、上層にある流体が重いのであれば”10”の圧力が下層へとかかってしまいます。これを先ほどみたいな水の中に沈めた風船の図で表すと下のようになります。上図のように浮力はその流体の重さによって発生する下方向からの圧力のことなので、上層から下層へかかる流体による圧力が大きくなるほど、下方向からの力である浮力も大きくなります。だから流体が重い(密度が大きい)ほど、浮力というのは大きくなるんですね。ちなみにプールと海では海の方が体が浮きやすくなるというのがまさにこの理由からで、プールの水と海の水では海水の方が重い(密度が大きい)ために体が浮きやすくなっています。関連:なぜ真水(淡水)よりも海水の方が体がよく浮くのか?関連:暖かい水と冷たい水で重さが変わる仕組みとは?以上が「浮力と流体の密度の関係について。浮力が流体の密度で変化する仕組みとは?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、流体が軽い(密度が小さい)ほど、浮力は小さくなる。流体が重い(密度が大きい)ほど、浮力は大きくなる。流体の重さで浮力が変化するのは、浮力そのものが流体の重さによって発生している力だから。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒水圧と浮力の違いについて簡単に図で解説!⇒死海とは?死海の由来は?なぜ死海は他の海よりも浮くことができるのか?⇒密度が大きい(高い)・密度が小さい(低い)の意味を簡単に図解!⇒水温と浮力の関係について。水温によって浮力が変化する仕組みとは?⇒なぜ真水(淡水)よりも海水の方が体がよく浮くのか?⇒蒸気圧とは?水の沸点と蒸気圧の関係についてわかりやすく解説!⇒相対湿度と絶対湿度の違いとは?⇒結露とは何か?仕組みを分かりやすく図解!⇒熱気球とは?また熱気球はどんな原理で空中に浮いているのか?⇒水圧とは何か?わかりやすく図を用いて解説!
-
さてあなたは海の水のほうがプールの水よりも、体が浮きやすいというのはご存知でしょうか。これには”水の重さ”が大きく関係しているのですが、この原理をしっかりと理解している人は意外と少ないように感じます。そこでこのページでは、なぜ真水(淡水)よりも海水の方が体がよく浮くのかを簡単に解説します。どうぞごご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次なぜ真水(淡水)よりも海水の方が体がよく浮くのか?まとめ1.なぜ真水(淡水)よりも海水の方が体がよく浮くのか?ではなぜ真水(淡水)よりも海水の方が体がよく浮くのかを見ていきましょう。(真水と淡水は同じものを表しています)結論から言ってしまうと、真水よりも海水の方が体が浮きやすくなる理由は、海水の方が塩が含まれている分だけ重いため、その分だけ真水よりも浮力が大きくなるからです。まず海水における平均的な塩分濃度は約3.5パーセントほどで、比重はだいたい1.025ほどになります。(水温によっても比重は変化するので注意してください)海水の比重1.025というのは真水と比べたときの比重なので、同じ体積で比べると真水よりも2.5パーセントの差があることを意味します。つまり海水の方が真水よりも2.5パーセントほど、密度が大きい(重い)ということです。関連:密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?そして水の上にモノが浮かぶのは、水の中でそのモノに対して”浮力”という力が働いているからです。”浮力は流体(水や空気など)の重さによって発生する力のこと”を言い、その流体の密度が大きい(重い)ほど発生する浮力は大きくなります。ここでの流体とは”真水”と”海水”のことを指していて、真水よりも海水の方が重いので海水の方が浮力は大きくなります。例えば空気で膨らませた風船を水の中に沈めていき、水から風船にかかる浮力を図で表したものが下になります。上図のように水中の風船には”水圧”があらゆる方向からかけられることになり、水深が深くなるほど大きな水圧が風船に対してかかっていきます。その風船にかけられた”上向きの水圧”から”下向きの水圧”を引いたものが、”浮力”となります。これが分かればなぜ流体の重さによって浮力が変化するのかは簡単です。それぞれ重さが異なる流体の浮力の大きさがどうなるのかを下に表します。上図のように浮力というのは流体の重さによって発生している力なので、その流体が軽ければ浮力は小さくなり、その流体が重ければ浮力は大きくなります。この例では風船でしたが、人間も同様に水から浮力がかかるので考え方は同じです。なので海の水は塩が含まれている分だけ真水(淡水)よりも重くなるため、海水の方が浮力が大きくなって、プールの水よりも体が浮きやすくなるというわけです。この解説だけではいまいち浮力について理解するのが難しいと感じた人は、下記の関連ページで分かりやすく解説しているのでそちらをどうぞご覧ください。関連:浮力とは何か?浮力の原理を簡単に図で解説!関連:浮力と流体の密度の関係について。流体の密度で浮力が変化する仕組みとは?以上が「なぜ真水(淡水)よりも海水の方が体がよく浮くのか?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、海水の方が体が浮きやすくなるのは、海水の方が塩が含まれている分だけ重いため、その分だけ真水よりも浮力が大きくなるから。浮力は流体の重さによって発生している力なので、その流体が重さいほど浮力は大きくなる。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒水圧とは何か?わかりやすく図を用いて解説!⇒水圧と浮力の違いについて簡単に図で解説!⇒絶対零度とは?また絶対零度の温度は何度なのか?⇒水温と浮力の関係について。水温によって浮力が変化する仕組みとは?⇒なぜ水温と気温は同じなのに体感温度が違うのか?⇒死海とは?死海の由来は?なぜ死海は他の海よりも浮くことができるのか?⇒流体とは何かをわかりやすく解説!圧力はどんなかかり方なのか?⇒海水と淡水と真水の違いとは?⇒圧力鍋とは何か?圧力鍋の仕組みをわかりやすく図解!⇒揮発とは?蒸発との違いと意味は何か?なぜ揮発は起こる?
-
さてあなたは水温と浮力が関係しているということはご存知でしょうか。つまり水温が上がったり下がったりすることで、水から受ける浮力も変化するということです。そして水温によって浮力が変化する仕組みを知っている人は意外と少ないです。そこでこのページでは水温と浮力の関係について。また水温によって浮力が変化する仕組みを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次水温と浮力の関係について水温によって浮力が変化する仕組みとは?水温によって水の密度が変化する水の密度が変化すると浮力も変化するまとめ1.水温と浮力の関係についてでは水温と浮力の関係について見ていきましょう。結論から言ってしまうと、水温と浮力の関係は下のようになります。水温が4℃より高い ⇒ 水温が高いほど浮力は小さくなる(最高100℃まで)水温が4℃ ⇒ 浮力は最も大きくなる水温が4℃より低い ⇒ 水温が低いほど浮力は小さくなる(最低0℃まで)水温4℃のときが最も水から受ける浮力は大きくなり、水温4℃を境界として4℃より高くても低くなっても水からの浮力は小さくなります。水温が4℃よりも高い場合は100℃のときが最も浮力が小さくなり、水温が4℃よりも低い場合は0℃のときが最も浮力が小さくなります。これは水温が100℃以上になると水が沸騰して水蒸気(気体)に変化し、水温が0℃以下になると水が氷(固体)に変化し始めるからです。ちなみに水が100℃のとき沸騰して気体である水蒸気に変化し、0℃のとき固体である氷に変化し始めるというのは周囲の気圧が”1気圧”だからです。1気圧とは簡単に言えば、私たちが住んでいる地上における気圧の大きさのことで、周囲の気圧が1気圧でなければ水が水蒸気や氷に変化する温度も変わります。富士山などの頂上で水を沸騰させると、80℃~90℃ぐらいで沸騰する理由がまさにこれです。(1気圧では100℃で沸騰するが、富士山頂上の気圧は1気圧よりも低いため)関連:1気圧とは?また何ヘクトパスカル(hPa)なのか?関連:気圧と沸点の関係について。気圧によって沸点が変化する仕組みとは?次の章では水温によって浮力が変化する仕組みについて解説していきます。2.水温によって浮力が変化する仕組みとは?では水温によって浮力が変化する仕組みを見ていきましょう。さっそくですが水温によって浮力が変化する理由は、水温が変化することで水の密度が変化して、その水の密度変化に伴い浮力が変化するからです。浮力というのは流体(水や空気など)の重さによって発生している力なので、水温が変化して水の密度が変われば、それに伴って水からの浮力も変化することになります。簡単に水温によって浮力が変化する仕組みを解説しましたが、まだ分かりにくいだろうと思うので下記の2点について順番に詳しく解説していきます。水温によって水の密度が変化する水の密度が変化すると浮力も変化するさてそれぞれについて見ていきましょう。関連:流体とは何かをわかりやすく解説!圧力はどんなかかり方なのか?水温によって水の密度が変化する水の温度が上がるとその水の体積が大きく(膨張)なり、反対に水の温度が下がるとその水の体積は小さく(圧縮)なります。(このときその水の質量は変化せずに、体積だけが変化します)この水の体積変化に伴い、水の密度が変化します。(”密度[g/cm^3]=質量[g]/体積[cm^3]”なので、体積が変わると密度は変化します)上図のように水の温度が上がって体積が大きくなると密度は小さくなり、水の温度が下がって体積が小さくなると密度は大きくなります。関連:質量とは?重量(重さ)との違いと単位についてまた水の密度が大きくなるということはその水が”重くなる”ことと同じで、反対に水の密度が小さくなれば”軽くなる”ことと同じになります。普段から私たちが複数のモノの重さを判断するときには密度を用いています。例えばどんなに軽いモノでもそれをたくさん積み上げていくと、重いモノと同じ重さになるのでどちらが重いのか正確に判断ができなくなります。ですので軽いモノと重いモノを”同じ体積[cm^3]あたりの質量[g](つまり密度[g/cm^3])”で判断し、どちらのモノが重いのかを判断しています。水の質量が変化していないのにも関わらず、水の重さが変わるように感じるのは密度が変化したからです。このとき密度が大きいモノの方が重いモノで、密度が小さいモノの方が軽いモノとなります。関連:密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?関連:密度が大きい(高い)・密度が小さい(低い)の意味を簡単に図解!水の密度が変化すると浮力も変化する水温が上がると体積が膨張して密度が小さくなるのでその水は軽くなり、水温が下がると体積が圧縮して密度が大きくなるのでその水は重くなります。そして浮力はその流体の重さによって発生している力のことなので、水の密度が変化することによって浮力も変化していきます。まず水中の物体にかかる浮力のイメージは下図のようになります。上図のように流体中の物体には流体の重さによって発生した圧力があらゆる方向からかかり、その物体にかかる力の大きさは、流体中の深い場所ほど大きな力がかかります。(流体が水なら”水圧”がかかり、流体が空気なら”気圧”がかかる)上図でもあるように流体における浮力というのは、物体へとかかっている”下からかかる力ー上からかかる力”のことです。そうすると物体に下からかかる力の方が残るため、水などの流体に物体を沈めようとしても浮かんでくるんですね。(上からかかる力を引いたあとに残った物体に下からかかる力が”浮力”)なので浮力とは流体によって発生するあらゆる方向からかかる圧力のうち、下方向からかかっている圧力に限定したものを指しているんですね。では本題に入りますが、水温で水の密度が変化して重さが変わると、その変化した水の重さによって水中で物体にかかる力も変化していきます。水の重さが変化するということは”水によって下へとかかる力”が変化するということで、水の重さによって発生している浮力はその影響をそのまま受けることになります。つまりはこういうことです。上図のように水温が上がって軽くなった水は下へとかかる力(図では上)が弱くなり、反対に水温が下がって重くなった水は下へとかかる力が強くなります。(上図の数字は適当な値です)その水の重さによって発生した下へとかかる力が浮力にも影響するので、水温が上がると浮力は小さくなり、水温が下がると浮力は大きくなるというわけです。ただし水温が下がると浮力は大きくなると解説しましたが、水温4℃になると密度が最も大きく(重く)なるため、4℃より下がると浮力は小さくなっていきます。他の物質は温度が高くなるほど密度が小さくなっていき、温度が低くなるほど密度が大きくなっていくため、水は少し特殊な性質の物質です。上図のように水温4℃を境にして水温が上下するほど、浮力は小さくなります。浮力のイメージがまだ難しいと感じる人は、少し詳しく解説しているので下記をご覧ください。関連:浮力と流体の密度の関係について。流体の密度で浮力が変化する仕組みとは?以上が「水温と浮力の関係について。水温によって浮力が変化する仕組みとは?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、水温4℃のときが最も水の浮力は大きく、水温4℃を境にして浮力は小さくなっていく。水温4℃のときが水の密度が最も大きくなる(水は特殊な性質を持つ物質)。水温によって浮力が変化する仕組みは、水温が変化することで水の密度が変わるから。浮力は流体の重さによって発生する力なので、水の密度が大きく(重く)なると浮力も大きくなる。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒浮力とは何か?浮力の原理を簡単に図で解説!⇒単位の接頭語とは何か?単位の接頭語の種類について⇒なぜ氷は空気中よりも水中の方が溶けやすいのか?⇒水圧と浮力の違いについて簡単に図で解説!⇒液体の膨張と圧縮とは?温度によって液体の体積が変化する仕組みを図解!⇒氷とドライアイスと液体窒素の違いとは?最も温度が低いのはどれ?⇒なぜ真水(淡水)よりも海水の方が体がよく浮くのか?⇒死海とは?死海の由来は?なぜ死海は他の海よりも浮くことができるのか?⇒蒸気圧とは?水の沸点と蒸気圧の関係についてわかりやすく解説!⇒蒸気と水蒸気の違いとは?
-
さてあなたは”水圧”と”浮力”という言葉をご存知でしょうか。これらはよく物理学などで用いられている言葉ですが、イメージするのが難しいと感じている人もいますよね。そしてどちらも水によって発生している力ということから、水圧と浮力の違いがよく分からないという人も多いです。そこでこのページでは、水圧と浮力の違いについて簡単に図で解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次水圧と浮力の違いについて水圧とは?浮力とは?まとめ1.水圧と浮力の違いについてでは水圧と浮力の違いについて簡単に見ていきましょう。結論から言ってしまうと水圧と浮力の違いは、物体に対して”あらゆる方向からかかるのか”、”下方向だけからかかるのか”になります。水圧は水中の物体に対してあらゆる方向から力がかかり、浮力は水中の物体に対して下方向だけから力がかかります。(浮力自体は水だけでなく、それが流体であれば発生します)上図を見ていただければ分かるかと思いますが、浮力というのは水圧による力のうち、下方向からかかる力のみのことを指します。なので浮力とは、水圧と言われている力の一部のことなんですね。さて水圧と浮力が発生する原理などについて、それぞれ詳しく解説していきます。関連:流体とは何かをわかりやすく解説!圧力はどんなかかり方なのか?水圧とは?まず水圧とは、水の重さによって発生する圧力のことです。水の中に物体を入れると、その物体に水による圧力(水圧)が”あらゆる方向”からかかり、水深が深くなるほど物体に対してかかる水圧も大きくなっていきます。水圧は水の重さによってかかる力だと言いましたが、簡単にイメージできるように下図のような容器とボールを用いて解説していきます。(ボールが水だと思ってください)水圧というのは上の層に存在するボールから下の層に存在するボールに対して、その重さがかかっていくことで発生するので下図のように順番に力がかかっていきます。まずは上から1層目に存在するボールの重さによって、2層目に存在するボールに力が加わります。次に2層目のボールは横方向に力が流れ(1層目のボールの重さ分の力)、下方向(3層目)に1層目と2層目のボールの重さによる力が加えられます。横方向にも力が流れていくのは上から力がかけられたときに、ボールがつぶされることで横方向に力が逃げていくために起こります。また各方向へと力が流れていきますが、作用反作用の法則によってそれらの力とは逆向きの力も加わります。最終的に水圧の関係は上図のようになります。下方向だけではなくあらゆる方向から水圧がかかっているのと、深い層になるにつれてボール同士に働く圧力は大きくなっているのが分かりますよね。これが水圧のかかり方のイメージとなります。関連:水圧とは何か?わかりやすく図を用いて解説!浮力とは?次に浮力とは、流体中において物体に対して下方向からかかる力のことを言います。浮力は水だけに働く力だと思っている人も多いようですが、水だけでなくそれが流体(気体と液体)であれば働く力になります。水圧はあらゆる方向からかかる力でしたが、浮力は下方向からかかっている力です。そして浮力というのは、水圧(あらゆる方向からかかる力)のうち”下方向からかかる力に限定した呼び方”です。なので浮力は水圧の一部ということになりますね。浮力について最初の方で使用していた図を用いて解説していきます。まず水深が深いほど物体にかかる水圧が大きくなるため、水深が深い位置に存在する物体ほど大きな水圧がかかっています。そして上図のように物体に対してかかる横方向(左右)からの水圧は同じ大きさなので、左右の力は相殺されて、浮力のときに考えるべき力は上下の力のみになります。上下の力だけで考えた場合に水深が深いほど力は大きくなるため、上からかかる力よりも下からかかる力の方が大きく、それらを差し引いた力が浮力になります。またどんな物体にも流体中であれば流体からの浮力は働いていますが、流体からの浮力よりもその物体の重さのほうが大きければ物体は沈みます。(沈もうとする物体にも浮力自体は働いています)反対に流体からの浮力のほうが物体の重さよりも大きければ、その物体は流体中に沈まずに浮かぶことになるので覚えておきましょう。関連:浮力とは何か?浮力の原理を簡単に図で解説!関連:なぜ真水(淡水)よりも海水の方が体がよく浮くのか?以上が「水圧と浮力の違いについて簡単に図で解説!」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、水圧とは、水の重さによって発生する圧力であらゆる方向からかかる。浮力とは、流体中において物体に対して下方向からかかる力のこと。水圧と浮力の違いは力のかかる方向と、浮力が水圧のうちの一部だということ。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒浮力と流体の密度の関係について。流体の密度で浮力が変化する仕組みとは?⇒なぜ水温と気温は同じなのに体感温度が違うのか?⇒気圧と沸点の関係について。気圧によって沸点が変化する仕組みとは?⇒揮発とは?蒸発との違いと意味は何か?なぜ揮発は起こる?⇒死海とは?死海の由来は?なぜ死海は他の海よりも浮くことができるのか?⇒密度が大きい(高い)・密度が小さい(低い)の意味を簡単に図解!⇒揮発性とは?揮発性が高い・低いとはどういう意味なのか?⇒水温と浮力の関係について。水温によって浮力が変化する仕組みとは?⇒吸盤が壁にくっつく仕組みとは?⇒気圧と大気圧の違いとは?
-
さてあなたは死海という言葉を聞いたことがあるでしょうか。名称だけを見るととてもこわい場所なんだと感じるかと思いますが、実は死海というのはリゾート地としても知られています。ではどうして”死海”のようなこわい名称が付いたのか疑問に感じますよね。そこでこのページでは死海とは何か?死海の由来は?またなぜ死海では他の海よりも体が浮くのかを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次死海とは?死海の由来とは?なぜ死海では他の海よりも体が浮くのか?まとめ1.死海とは?では死海とは何かを見ていきましょう。まず死海(しかい)とは、ヨルダンとイスラエルとの国境に存在する塩湖のことを言います。死海のことを海だと思っている人も多いですが、実は死海というのは湖なんですね。塩湖(えんこ)というのは水1L中に0.5g以上の塩類を含む湖のことで、死海における塩分濃度は約27%なので、水1L中に塩類が270g含まれることになります。ただの海水だと平均的な塩分濃度は約3.0%~3.5%ほどですので、死海の約27%という塩分濃度はかなり高いのが分かりますよね。(死海の湖底だと塩分濃度は約40%ほどです)また死海の海抜はマイナス400mほどで、かなり低い場所に存在しています。死海には6つの川から水が流入してきますが、周辺で死海よりも低い場所がないため、死海の水が他へと流出することはありません。そうなると死海へと水が流入するばかりで水位が増えていくと考えますが、死海は年間を通して気温が高く、さらに降水量も少ないために水が蒸発しやすくなります。この水の蒸発が多く起こることにより他から水が流入してきても、水の流入量と蒸発量が釣り合うことで死海の水位は保たれています。ただ最近では死海の主な水源であったヨルダン川付近において住民が増えたので、ヨルダン川の水の消費量が増加したために、死海へと流入する水の量が減っているそうです。そして死海へと流入する水の量が減少しても、蒸発する死海の水の量は変化しないため、流入と蒸発の釣り合いが取れなくなり、死海の水位は少しずつ低下していきます。このような事情もあり、死海の水位は年間平均で約1mずつ低下しています。関連:水が100度に達していないのに蒸発する仕組みとは?2.死海の由来とは?では名称が”死海”となった由来について見ていきましょう。さっそくですが”死海”という名称が付けられている由来としては、塩分濃度が高く(約27%)、生物が生きられない環境という意味からきています。実際に死海では湧水の発生している1か所を除いて、魚類の生息は確認されていません。湧水の発生している場所では、小さな魚がわずかながら存在するようです。そして湧水の発生していない塩分濃度が高い場所でも、高い塩分濃度を好む”高度好塩菌”などの生息は確認されています。また魚類が死海のような塩分濃度が高い場所で生息できない理由は、浸透圧の関係によって魚類が脱水状態を引き起こしてしまうからです。魚類の体液の塩分濃度は約0.9%ほどで人間などと変わらなく、それに比べて死海の水の塩分濃度は約27%です。液体には濃度の低い方から濃度の高い方へと移動して、液体の濃度を同じにしようとする性質があります。つまり死海では上図のように魚類の体液の方が塩分濃度が低いために、死海の水の塩分濃度と同じにしようとして、魚類の体液中の水分が死海へと放出されてしまいます。そして水分が放出された魚類の体内では強い脱水症状が引き起こされるので、死海だと魚類は生息することができないんですね。このように濃度を同じにしようと液体が移動することを”浸透(しんとう)”と言い、その浸透によって発生する圧力のことを”浸透圧(しんとうあつ)”と言います。ただし海水魚はもともと自身の体液の塩分濃度よりも高い海で生息していますが、普通の海ぐらいの塩分濃度(約3.0%~3.5%)なら体液の塩分濃度を調節できます。(海水魚には海水を飲んだとしても、エラから塩分を放出する機能などがあります)海水の場合でも浸透圧の関係によって魚から水分は少しずつ放出はされていきますが、海水魚には塩分調節機能があることで必要な水分を体内へと取り込むことができます。ですが死海の場合は塩分濃度が高すぎて、海水魚の塩分調節機能では調節が難しいのです。なので上手く塩分濃度の調節ができないために、脱水症状が起こり死海では魚類が生息というわけです。関連:海水と淡水と真水の違いとは?2.なぜ死海では他の海よりも体が浮くのか?では死海だと他の海よりも体が浮きやすいという話は有名ですが、なぜ死海だと他の海よりも体が浮きやすくなるのかを解説していきます。結論から言ってしまうと死海では体が浮きやすくなる理由は、死海の塩分濃度が他の海よりも高いことによって、その分だけ比重が大きくなるからです。つまり他の海よりも死海の水の方が塩分が多く含まれている分だけ、その水は重くなるので重く(密度が大きく)なっただけ、浮力も大きくなるからなんですね。塩の比重は水と比較した場合には2.16となっており、これは塩が水よりも2.16倍重い(密度が大きい)物質だということを表しています。例えば同じ100gの水でも、塩分濃度が高い水と低い水では、溶けている塩の量だけ重さに差が生じることになります。これにより塩分濃度が高い水ほど、重くなるということは分かりますよね。そして水の上に体が浮くのは、体に対して水から”浮力”が働いているからです。浮力と言うのは、その水(流体)の重さによって発生している力のため、その水が重ければ重いほど水から体に対して働く浮力も大きくなります。ですので他の海よりも塩分濃度がかなり高い死海の水の方が重くなり、それによって水から体が受ける浮力が大きくなったというわけなんですね。浮力と流体の密度(重さ)の関係について、詳しい仕組みは下記をご覧ください。関連:密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?関連:浮力と流体の密度の関係について。流体の密度で浮力が変化する仕組みとは?以上が「死海とは?死海の由来は?なぜ死海は他の海よりも浮くことができるのか?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、死海とは、ヨルダンとイスラエルとの国境に存在する塩湖のこと(死海は海ではなく湖)。”死海”という名称の由来は、その塩分濃度の高さゆえに魚類などの生物が生息できないことからきている。死海が他の海よりも体が浮くのは、死海の水が他の海よりも塩分濃度が高いことで、水から受ける浮力が大きくなるから。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒浮力とは何か?浮力の原理を簡単に図で解説!⇒水温と浮力の関係について。水温によって浮力が変化する仕組みとは?⇒水圧と浮力の違いについて簡単に図で解説!⇒氷とドライアイスと液体窒素の違いとは?最も温度が低いのはどれ?⇒密度が大きい(高い)・密度が小さい(低い)の意味を簡単に図解!⇒なぜ氷は空気中よりも水中の方が溶けやすいのか?⇒なぜ真水(淡水)よりも海水の方が体がよく浮くのか?⇒ドライアイスとは?ドライアイスから発生する白い煙の正体って何?⇒ストローで飲み物を吸うことができる仕組みとは?⇒圧力鍋とは何か?圧力鍋の仕組みをわかりやすく図解!