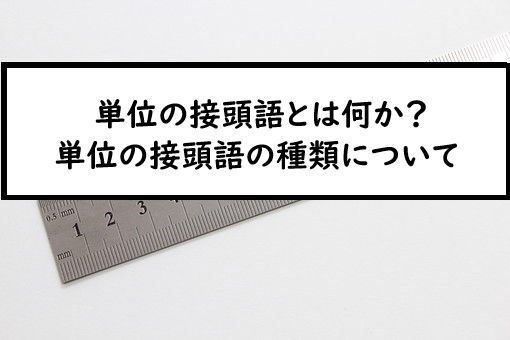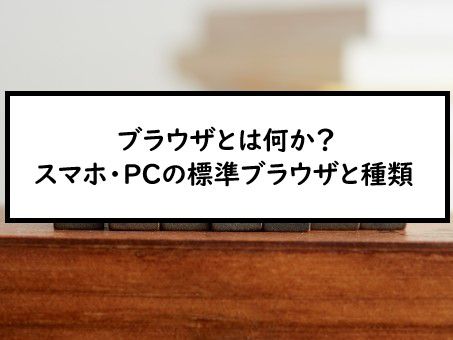さて熱には3種類の伝わり方があるのはご存知でしょうか。日常生活で何かしらモノに触れると”熱い・冷たい”というように、その触れたモノから直接熱を感じることってありますよね。これがそのモノから自分へと熱が伝わっているということなのですが、このように熱が伝わる(移動する)方法には全部で3種類存在します。そこでこのページでは、3種類の熱の伝わり方(伝導・対流・放射)をわかりやすく図で解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次熱というのは分子の運動のこと熱には3種類の伝わり方が存在する伝導とは?対流とは?放射(輻射)とは?まとめ1.熱というのは分子の運動のことまず3種類の熱の伝わり方の前に、熱とは一体どのようなものなのかを簡単に見ていきましょう。さっそくですが、熱というのは物質を構成している分子の運動のことを言います。あらゆる物質(気体・液体・固体)は分子(または原子)と呼ばれる小さな粒で構成されていて、物質を構成しているその分子は常に運動(振動)しています。そしてその物質を構成する分子の運動が激しければ熱エネルギーが大きく(温度が高く)、反対にその物質の分子の運動が穏やかであれば熱エネルギーが小さく(温度が低く)なります。上図のように絶対零度というのは物質の分子の運動が完全に止まっている状態のことで、物質における最低の温度となり、この状態は熱エネルギーが何もないことを意味しています。では水(液体)を例にして見てみましょう。水は水分子という小さな粒がたくさん集合しすることで構成されています。上図のように水分子の運動が激しければ熱エネルギーが大きく(水の温度が高く)、水分子の運動が穏やかであれば熱エネルギーが小さく(水の温度が低く)なります。このように熱というのはその物質を構成する分子の運動の激しさのことで、次の章で解説する3種類の熱の伝わり方を理解するときにも必要なためぜひ覚えておきましょう。関連:熱と温度の違いとは?関連:状態変化とは何か?物質が状態変化する仕組みを簡単に図解!2.熱には3種類の伝わり方が存在する熱の伝わり方は全部で3種類存在しますが、それが下記の3種類になります。伝導(でんどう)対流(たいりゅう)放射(ほうしゃ)、輻射(ふくしゃ)上記の名称の他に熱伝導・熱対流・熱放射(熱輻射)とも呼ばれており、日常的に起こる熱の伝わり方はすべてこの3種類(伝導・対流・放射)に分けられます。さて3種類の熱の伝わり方(伝導・対流・放射)について、それぞれ詳しく解説していきますね。関連:なぜ熱は必ず温度が高い方から低い方へと移動するのか?伝導とは?伝導(でんどう)とは、物質から他の物質(または同じ物質)へと熱が伝えられる方法で、これは物質を構成する分子から他の物質(または同じ物質)の分子に運動が伝わることによるものです。ここでいう物質とは状態(気体・液体・固体)に関係なく、すべての物質のことを指します。熱の伝わり方で多くの人がイメージするのが、この”伝導”ではないでしょうか。例えば金属の棒の端を熱すると、次第にもう片方の端の方まで熱くなっていきますよね。上図のように火によって熱せられている金属部分が熱くなっていき、その部分の熱が少しずつ他の金属部分へと移動して伝わっていきます。そして熱というのは、”物質を構成する分子の運動の激しさ”のことです。これを考慮して金属の棒の端を熱した様子を見てみると下のようになります。火はガスを構成する分子(ロウソクであればロウ分子)と空気中の酸素分子が反応して、とても激しく運動しているのでとても熱く(温度が高く)なっています。その火(とても激しく運動している分子)で金属を熱することによって、火を構成する分子の激しい運動が金属の分子へと伝わっていきます。これにより金属の棒は少しずつ熱せられていきます。火から金属へと熱が伝わっていくのも伝導ですし、金属から金属へと熱が伝わっていくのも伝導です。(後で解説しますが、火には他にも”放射”という熱の伝え方も存在します)このように物質を構成する分子同士がぶつかることによって、熱が伝えられるのが”伝導”になります。関連:熱伝導とは何か?熱伝導の仕組みをわかりやすく図で解説!関連:金属に触ると冷たく感じる理由とは?なぜガラスと木材ではガラスの方が冷たい?対流とは?対流(たいりゅう)とは、流体(気体と液体)が移動することで熱が伝わる方法で、これは流体の密度の変化によって流体が移動して熱が伝わることによるものです。対流については伝導とは異なり、物質を構成する分子の運動は特に考える必要はありません。対流で考える必要があるのは、流体(気体と液体)の温度変化による密度の変化についてです。「暖かい空気(水)は上に行き、冷たい空気(水)は下に行く」という話はご存知でしょうか。これは本当のことで、流体の温度が上がると重さは変わらずに体積だけが大きく(膨張)なり、反対に流体の温度が下がると重さは変わらず体積だけが小さく(圧縮)なります。(気体や液体のような流体だけでなく、固体でも同様の変化は起こります)これを密度という言葉で置き換えると、流体の温度が上がるとその流体の密度が小さく(軽く)なり、反対に流体の温度が下がるとその流体の密度が大きく(重く)なります。関連:空気の温度で重さは変わる?暖かい空気は軽く冷たい空気が重い仕組みとは?関連:空気の膨張とは何か?空気の温度によって体積が変化する仕組みとは?そして物質の重さはその物質の密度の大きさによって重い・軽いが決まるため、空気や水のような流体の温度が変化して密度が変われば、その流体の中で移動が起こります。上図のように温度が上がって密度が大きく(軽く)なった流体については上へと移動し、温度が下がって密度が小さく(重く)なった流体については下へと移動します。(火からの熱の伝わり方については”伝導”です)つまり流体自体が移動することによって、流体と一緒に熱も移動することになるわけです。このように流体の密度が変化して、流体自体が移動することによる熱の伝わり方が”対流”になります。また”伝導”と”対流”における決定的な違いは、熱を伝えるときにその物質が移動するかどうかの違いです。伝導であればその物質の分子がぶつかることで熱が伝わっていくので物質は移動しませんが、対流は熱を持っている物質(流体)そのものが移動して熱を伝えます。伝導と対流にはこのような違いがあるので、覚えておきましょう。関連:熱対流とは何か?熱対流の仕組みをわかりやすく図で解説!関連:密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?放射(輻射)とは?放射(ほうしゃ)とは、赤外線などの電磁波によって熱が伝わる方法で、これは赤外線などの電磁波が物質を構成する分子を振動させる働きによるものです。放射は別名として”輻射(ふくしゃ)”とも呼ばれます。熱は物質を構成する分子の運動で、その分子の運動をより激しくさせるのが赤外線などの電磁波になります。電磁波の中でも赤外線が最も物質を暖める(分子を振動させる)働きがあり、赤外線を利用している身近な例としてはオーブンやストーブなどの器具がそうです。オーブンは赤外線を放出することで食材の表面を焼いていますし、ストーブは赤外線を放出して周囲を暖めています。そして放射には他の熱の伝え方(伝導・対流)にはない特徴があります。それは周囲が真空状態であっても他の物質に熱を伝えることができるというものです。例えば太陽から太陽光(赤外線などの電磁波)が放出されて地球にまで届いていますが、地球に届くまでに真空である宇宙を必ず通ってから来ますよね。なので太陽から地球に熱が伝えられるのは、伝導でも対流でもなく”放射”になります。このように赤外線などの電磁波による熱の伝え方は、熱を伝えるために仲立ちとなる物質(分子)が必要ありません。また先ほど火による熱の伝え方には、伝導の他に放射もあると言っていたのを覚えているでしょうか。実は温度を持っている物質ならどんな物質からでも赤外線は放出されていて、放出されている赤外線の強さはその物質の温度によります。その物質の温度が高ければ放出される赤外線も強くなり、反対にその物質の温度が低ければ放出される赤外線は弱くなります。ですので火からはその温度に応じた赤外線が放出されてるので、火の熱の伝え方には伝導以外にも放射が存在するというわけなんですね。関連:熱放射とは何か?熱放射の仕組みをわかりやすく図で解説!関連:真空とは何か?分かりやすく図で解説!以上が「熱の伝わり方の3種類(伝導・対流・放射)を分かりやすく図で解説!」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、熱というのは、物質を構成している分子の運動のこと。分子の運動が激しければ温度が高く、分子の運動が穏やかであれば温度が低い。<3種類の熱の伝え方についてのまとめ>伝導とは、物質の分子から他の物質(または同じ物質)の分子に運動が伝わること。対流とは、流体の密度の変化によって流体が移動して熱が伝わること。放射(輻射)とは、電磁波の働きによって物質の分子の運動が大きくなること。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒水を沸騰させると発生する泡の正体とは?またなぜ泡は発生するのか?⇒空気は太陽光で直接暖められないって本当?空気が暖まる仕組みとは?⇒絶対熱とは何か?絶対熱の温度は何度あるのか?⇒なぜ標高が高い所は寒いのか?太陽との距離は関係ないって本当?⇒熱伝導率とは何かをわかりやすく解説!熱伝導率が高い・低いとは?⇒なぜ水温と気温は同じなのに体感温度が違うのか?⇒結露とは何か?仕組みを分かりやすく図解!⇒氷とドライアイスと液体窒素の違いとは?最も温度が低いのはどれ?
ギモン雑学
「 種類 」の検索結果
-
-
さてあなたは単位の接頭語についてご存知でしょうか。”単位”についてはほとんどの人が聞いたことがあると思いますが、”単位の接頭語”と言われると分からない人も多いですよね。実は単位の接頭語について知らない人も多いですが、私たちは普段の生活で単位の接頭語をよく使用しています。そこでこのページでは単位の接頭語とは何か?また単位の接頭語の種類について簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次単位の接頭語とは何か?いつも1kgが何gなのか分からなくなる人はこれを見れば解決!単位の接頭語の種類についてまとめ1.単位の接頭語とは何か?では単位の接頭語とは何か見ていきましょう。結論から言ってしまうと単位の接頭語(せっとうご)とは、量の大きさを簡単に表すために単位の前に付けられる記号のことです。接頭語ではなく、”接頭辞(せっとうじ)”と言うこともあります。上のようにkm(キロメートル)は長さを表す単位のm(メートル)の前に、単位の接頭語であるk(キロ)という記号が付けられたものです。(mgもkgと考え方は同じです)ちなみにg(グラム)という単位は”重さ”ではなく、”質量”を表している単位になるので覚えておいてくださいね。関連:質量とは?重量(重さ)との違いと単位について単位の前には必ず接頭語を付けなければならないのかと言えば、そうではありません。単位の前に接頭語を付けるのはその量(長さや重さなど)の大きさを簡単に表すためなので、別に必ず接頭語を用いなければいけないわけではありません。上のように”0(ゼロ)”が何個も付いているといちいち数えるのがめんどくさいですよね。単位の前に接頭語を付けることで0が何個か数える必要がなくなり、簡単に表すことができます。また単位の接頭語は特定の単位だけに付く記号ではありません。k(キロ)であればkm(キロメートル)のような長さの単位だけではなく、kg(キログラム)やkW(キロワット)のように使用されることもありますよね。m(ミリ)についても同様でmg(ミリグラム)のような重さの単位だけではなく、mm(ミリメートル)やmW(ミリワット)のように使用されるときもあります。このように接頭語であるk(キロ)やm(ミリ)は重さや長さを表しているものではありません。(接頭語だけでは何を表しているのかが分からない)日常生活でよくあるのが「このダンベル何キロ?」とか、「この靴(くつ)何センチ?」というような質問です。(センチも単位の接頭語になります)厳密に言えば正しくはないですが、ダンベルであれば「何kgか知りたいんだなあ」とか、靴であれば「サイズのことだから長さであるcmを答えれば良い」のだと何となく分かると思います。なのでテストとかではない限り相手に内容がしっかりと伝わりさえすれば、それはそれで特に問題にはならないので気にする必要はないです。ただ知識として接頭語単体では、何かの単位そのものを表しているわけではないので覚えておきましょう。また単位というのは接頭語も含めて大文字で表すのか、小文字で表すのかによって示している意味が異なるので注意が必要です。関連:なぜ単位は大文字と小文字で区別しなければいけなのか?2.いつも1kgが何gなのか分からなくなる人はこれを見れば解決!ではいつも1kgが何gなのか分からなくなる人は以下の解説を見てください。(この覚え方はgだけでなく全ての単位変換で有効です)まずいつも1kgが何gなのか分からなくなる人というのは、単位の接頭語の意味を特に理解しないで使用している人が多いです。なので単位の接頭語をしっかりと理解していればすぐに分かるようになります。上のような覚え方は単位がg(グラム)でなかったとしても、接頭語がk(キロ)やm(ミリ)でなくても使用することができます。(その接頭語の数値を覚えていればですが)kg(キログラム)やkm(キロメートル)って結局のところ、基本の単位であるg(グラム)やm(メートル)の前に接頭語を付けただけです。なので1kg=1000gや1km=1000mとただ暗記するのではなく、その接頭語が何を意味しているのかを理解した方が効率よく覚えることができます。接頭語を覚えることで「k(キロ)は1000(10^3)を表している接頭語だから、kg=1000gでkm=1000mなんだな」とすぐに分かりますよね。私は接頭語について理解する方が分かりやすかったので、このような覚え方をしています。ただどちらの覚え方が良いかはその人次第なので単純に暗記するのか、接頭語を理解する覚え方にするのかはお任せします。関連:単位変換にはコツが必要?単位変換の簡単な考え方について3.単位の接頭語の種類についてでは単位の接頭語にはどのような種類があるのか見ていきましょう。先ほどのk(キロ)やm(ミリ)を含めて単位の接頭語は全部で20種類存在しており、それらを簡単に表にしたものが以下になります。※単位の接頭語の名称をクリックすると、それぞれの個別ページへと移動します乗数記号名称10^24Yヨタ10^21Zゼタ10^18Eエクサ10^15Pペタ10^12Tテラ10^9Gギガ10^6Mメガ10^3kキロ10^2hヘクト10^1daデカ010^-1dデシ10^-2cセンチ10^-3mミリ10^-6μマイクロ10^-9nナノ10^-12pピコ10^-15fフェムト10^-18aアト10^-21zゼプト10^-24yヨクト項目1項目2項目3)★ -->以上が「単位の接頭語とは何か?単位の接頭語の種類について」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、単位の接頭語とは、量の大きさを簡単に表すために単位の前に付けられる記号のこと。ミリやキロのような接頭語単体では、何を表しているのかが分からない。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?⇒1気圧とは?また何ヘクトパスカル(hPa)なのか?⇒加速度とは何か?単位の意味とともにわかりやすく解説!⇒密度が大きい(高い)・密度が小さい(低い)の意味を簡単に図解!⇒何桁の数字の意味とは?7桁の収入や3桁の収入はいくらを表している?⇒単位変換にはコツが必要?単位変換の簡単な考え方について⇒1時間は何秒?1時間は何分?単位(時間)の簡単な覚え方について⇒1リットルは何ミリリットル?1リットルは何デシリットル?単位(体積)の覚え方について⇒1グラムは何ミリグラム?1グラムは何キログラム?単位(質量)の覚え方について⇒1センチは何メートル?1センチは何ミリ?単位(長さ)の覚え方について
-
さてパソコンやスマホなどを操作していると、かなりの頻度で出てくるのがブラウザという言葉です。私はいつもパソコンやスマホを使用しているので分かりますが、パソコンなどに慣れていないときはよく理解していませんでした。どちらかというとパソコンを使用していると出てくることが多いのですが、ネット関連の知識がない人であれば分からないですよね。そこでこのページではブラウザとは何か?またブラウザの種類とそれぞれの特徴について解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次ブラウザとは何か?OSの種類によって標準ブラウザは異なるブラウザは端末に複数インストールしても良いブラウザの種類とそれぞれの特徴についてGoogle Chrome(グーグル クローム)IE(インターネット・エクスプローラー)Firefox(ファイアーフォックス)Safari(サファリ)まとめ1.ブラウザとは何か?ではブラウザとは何か見ていきましょう。結論から言ってしまうとブラウザとは、インターネットでWebサイトを閲覧するためのアプリケーションのことです。もし端末(PCやスマホ)がインターネットに繋がっていたとしても、その端末にブラウザがインストールされていないのであればWebサイトを見ることはできません。つまりインターネットで検索することができなくなるということです。単にブラウザと呼ばれることが多いですが、Webブラウザやインターネットブラウザと呼ばれることもあります。呼び方は違いますがこれらはブラウザと同じ意味です。ちなみにブラウザという名前の由来は、「browse(ブラウズ):閲覧する」という単語から来ています。そして元々の「browse(ブラウズ):閲覧する」から、「browser(ブラウザー):閲覧するための設備」という言葉が生まれました。読み方はブラウザーでもブラウザでもどちらについても正しいです。では次に標準ブラウザについて説明していきますね。2.OSの種類によって標準ブラウザは異なるでは標準ブラウザはOSによって異なるということについて見ていきましょう。まず標準ブラウザというのは、PCやスマホにはじめから標準装備されているブラウザのことです。そして標準ブラウザはそのPCやスマホに入っているOSの種類によって、どのブラウザがインストールされているのか異なります。ここではOSについて詳しく説明しませんが、私たちのよく知っているWindowsもOSのひとつです。他にもiPhoneなどApple社製のモバイル端末には、iOSというOSが搭載されています。OSの種類による標準ブラウザの違いは下記のとおりです。OSの名称標準ブラウザの名称WindowsIE(インターネット・エクスプローラー)iOSSafari(サファリ)AndroidGoogle Chrome(グーグル クローム)項目1項目2)★ -->誰でも聞いたことがあるようなものについて挙げていくと、こんな感じではないでしょうか。またAndroidのブラウザに関していえば、昔のAndroidだと標準ブラウザはGoogle Chromeではありません。昔のAndroidには、「ブラウザ」という名前の標準ブラウザがインストールされていました。端末にははじめからブラウザが標準搭載されているため、インターネットにさえ繋がっていればWebサイトを見ることができないということはありません。標準搭載されているブラウザ以外を使用したいのであれば、他のブラウザをインターネットからインストールすることができます。そのときはOSとブラウザに相性があるためOSの種類によっては、ブラウザに対応していないことがあるので注意が必要です。3.ブラウザは端末に複数インストールしても良いたまに間違えて覚えてしまっている人がいるので説明しますが、ブラウザはスマホやPCなどひとつの端末に対して複数インストールしてもかまいません。ブラウザというのはアプリケーションですので、ひとつの端末に対してひとつだけしかインストールできないということはないです。例えばOSがWindowsのPCを持っていたとします。Windowsの標準ブラウザはIE(インターネット・エクスプローラー)ですが、同じPCに新しく別のブラウザ(Google Chromeなど)をインストールしても問題ないということです。そして同じPCに複数のブラウザがインストールされている場合でも、それぞれのブラウザからWebサイトを閲覧できるので安心してください。またほとんどの人はブラウザが1つインストールされていれば十分ですが、中には複数のブラウザを使い分けている人も存在します。ブラウザの種類によって仕様や性能が異なるため、様々なブラウザを試して自分の好みのブラウザを選びましょう。次の章ではシェア率が高い4つのブラウザについて、それぞれにどのような特徴があるのか説明していきます。4.ブラウザの種類とそれぞれの特徴についてさてブラウザの種類について少し触れていましたが、ひと口にブラウザと言っても多くの種類が存在します。そのブラウザの種類の中で一般的に多く使用されている4つのブラウザについて、それぞれ説明していきたいと思います。Google Chrome(グーグル クローム)IE(インターネット・エクスプローラー)Firefox(ファイア-フォックス)Safari(サファリ)ブラウザごとの特徴を知ることで自分の持っている端末のOSと相性の良いブラウザや、自分が使いやすいと感じるものを探すことができるため覚えておいて損はないです。ではブラウザの種類とそれぞれの特徴について簡単に見ていきましょう。Google Chrome(グーグル クローム)Google ChromeはGoogle社によって開発されたブラウザです。最近ではAndroidに標準搭載されているブラウザ。Google Chromeの特徴としては、拡張機能とWebページの表示速度が早いということです。拡張機能によって自分が欲しい機能があれば、Web上で探してカスタマイズしていくことが可能になります。表示速度や処理能力が速いというのも大きなメリットのひとつですね。IE(インターネット・エクスプローラー)IEはMicrosoft(マイクロソフト)社によって開発されたブラウザです。Windows(OS)に標準搭載されているブラウザです。パソコンを購入すると大体WindowsがOSとして入っているので、他のブラウザをインストールしていなければIEを使用している人が多いはずです。また他のブラウザで閲覧することのできないWebページでも、IEからなら閲覧できないページはほとんどないことがメリットとして挙げられます。しかし、他のブラウザと比較すると起動や動作がやや遅いというのが難点です。Firefox(ファイアーフォックス)FirefoxはMozilla Foundationによって開発されたブラウザです。FirefoxにもGoogle Chromeと同様に拡張機能が備わっている。Google Chromeよりも起動や動作はやや劣るものの、拡張機能に関してはFirefoxが一歩リードしているように感じます。ブラウザで細かいカスタマイズを楽しみたいのであれば、Firefoxを使用してみることをおすすめします。Safari(サファリ)SafariはApple(アップル)社によって開発されたブラウザです。SafariはMac PCやiPhoneなど、Apple社製の端末に標準搭載されているブラウザになります。Safariの特徴としてはとてもシンプルなデザインということです。デザインに無駄なものを省いているため、Web上のコンテンツが画面いっぱいに表示されるので見やすいです。そしてWebページの表示速度や処理能力が速く、Google Chromeとほとんど変わらない速さと言われています。5.まとめこれまで説明したことをまとめますと、ブラウザとは、Webサイトを閲覧するためのアプリケーションのこと。端末のOSの種類によって標準ブラウザは異なる。OSとブラウザにも相性があるため注意が必要。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒「iPhone」と「スマホ」と「Android」の違いとは?⇒強制終了とは?シャットダウンの方が良い理由って何?⇒再起動とは?またシャットダウンと再起動との違いって何?⇒LANとは?無線LANと有線LANの違いって何?⇒ハードウェアとソフトウェアの違いとは?ハード面、ソフト面の意味って?⇒コンピューターとは?パソコンとコンピューターの違いって何?⇒なぜインストールやアップデート後には再起動が必要なのか?⇒Wi-Fiとは?無線LANとWi-Fiの違いって何?