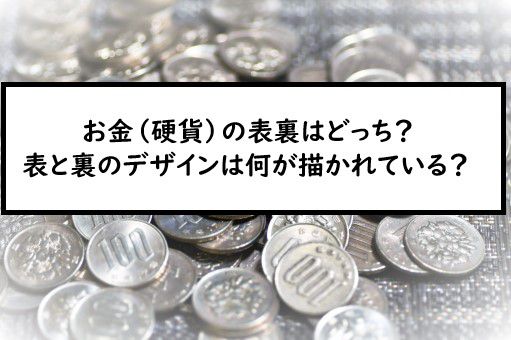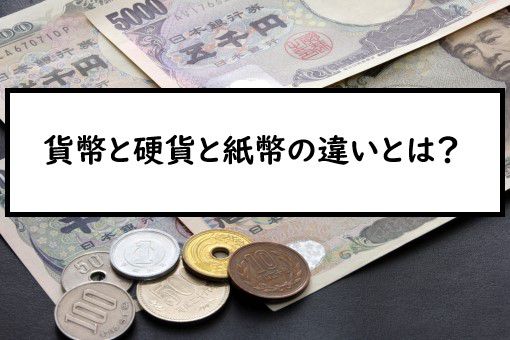さて私たちが日頃からよく目にしているものにお金(硬貨)があります。硬貨の種類には、1円玉・5円玉・10円玉・50円玉・100円玉・500円玉があります。お財布の小銭入れの中に硬貨が入っていない人はほとんどいないでしょう。日本に住んでいる人ならほぼ全ての人が例外なく硬貨を使っています。そんな日頃から使用している硬貨ですが、硬貨の表裏には何かしらのデザインが施されているのをご存知でしょうか。そして多くの人はその硬貨のどちら側が表でどちら側が裏なのか分からないのではないでしょうか。そこでこのページでは、お金(硬貨)の表裏とデザインについて簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次お金(硬貨)の表と裏はどっち?1円玉の表裏とデザイン5円玉の表裏とデザイン10円玉の表裏とデザイン50円玉の表裏とデザイン100円玉の表裏とデザイン500円玉の表裏とデザインまとめ1.お金(硬貨)の表と裏はどっち?ではお金(硬貨)の表と裏はどっちなのかを簡単に解説していきます。お金(硬貨)のどっちが表でどっちが裏なのか、下に簡単にまとめてみました。上のようにお金(硬貨)は”植物や建物などが描かれている面が表”で、”数字が書かれている面が裏”になります(5円玉のみ例外)。数字が書かれている面が硬貨の表だと思っていた人も多いですよね。ただし5円玉だけ他の硬貨と違って裏に数字が書かれていないので注意が必要ですが、判別するのにより確実なのは何円玉なのかが漢数字で表されているかどうかです。上のように何円なのかが漢数字(算用数字ではない)で表されていれば、その面が硬貨の表になりますのでぜひ覚えておいてください。さて次の章から硬貨の表裏にそれぞれ何が描かれているのかを解説していきますね。1円玉の表裏とデザインでは1円玉の表裏とデザインについて見ていきましょう。1円玉の表には若木、裏には1という数字が描かれています。また1円玉の素材はアルミニウムでできています。1円玉の表裏のデザインは一般公募で選出されたものです。1円玉の表に描かれている若木は特定の植物をデザインしたものではありません。若木は伸びゆく日本という意味で1円玉に描かれています。5円玉の表裏とデザインでは5円玉の表裏とデザインについて見ていきましょう。5円玉の表には稲穂と水と歯車が、裏には双葉(ふたば)が描かれています。また5円玉の素材は黄銅でできています。表のデザインは当時の日本の主な産業を表していて、稲穂は農業、水が水産業、歯車は工業を表しています。そして裏面の双葉は、民主主義に向かって伸びていく日本を表しています。双葉とは植物が芽を出したときに見られる2つの葉のことなので、特定の植物のことではありません。10円玉の表裏とデザインでは10円玉の表裏とデザインについて見ていきましょう。10円玉の表には平等院鳳凰堂と唐草模様が、裏には常盤木(ときわぎ)が描かれています。また10円玉の素材は青銅でできています。常盤木というのは特定の植物のことではなく、主に広葉樹からなる森林のことを表しています。50円玉の表裏とデザインでは50円玉の表裏とデザインについて見ていきましょう。50円玉の表には菊が、裏には50という数字が描かれています。また50円玉の素材は白銅でできています。50円玉のデザインは1円玉のデザインと同様に、一般公募で選出されたものです。100円玉の表裏とデザインでは100円玉の表裏とデザインについて見ていきましょう。100円玉の表には桜が、裏には100という数字が描かれています。また100円玉の素材は、50円玉と同じ白銅でできています。100円玉は最初から桜が描かれていたわけではありません。最初のデザインは鳳凰、次が稲穂で現在は桜が描かれるようになりました。500円玉の表裏とデザインでは500円玉の表裏とデザインについて見ていきましょう。500円玉の表には桐(きり)が、裏には竹と橘(たちばな)が描かれています。500円玉の素材はニッケル黄銅でできています。ちなみに500円玉は硬貨としては価値が高いため、様々な偽造防止の技術が施されています。以上が「お金(硬貨)の表裏はどっち?表と裏のデザインは何が描かれている?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、お金(硬貨)は何円玉なのかが漢数字で書かれている面が表になる。<日本の硬貨(お金)の表裏とデザイン>1円玉の表には若木、裏には1という数字。5円玉の表には稲穂と水と歯車、裏には双葉。10円玉の表には平等院鳳凰堂と唐草模様、裏には常盤木。50円玉の表には菊、裏には50という数字。100円玉の表には桜、裏には100という数字。500円玉の表には桐、裏には竹と橘。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒貨幣と硬貨と紙幣の違いとは?⇒支払いを硬貨20枚以上で行うと拒否されるって本当?⇒元請けと下請けと孫請けの違いとは?状況によって呼び名は異なる?⇒5円玉と50円玉に穴が開いている理由とは?⇒元本と元金と元利金の違いとは?⇒以下・以上・未満・超えるの違いとは?簡単な覚え方について
ギモン雑学
「 硬貨 」の検索結果
-
-
さてあなたは「貨幣・硬貨・紙幣」という言葉をご存知でしょうか。これらは私たちが日常的に使用しているお金のことを指していますが、一体どのような違いがあるのかを知らないという人も多いと思います。そこでこのページでは、貨幣と硬貨と紙幣の違いを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次貨幣と硬貨と紙幣の違いとは?実は造幣局で製造されているのは”硬貨だけ”まとめ1.貨幣と硬貨と紙幣の違いとは?では貨幣と硬貨と紙幣の違いについて見ていきましょう。結論から言ってしまうと、貨幣と硬貨と紙幣の違いは下のようになります。上図のように、貨幣とは”硬貨と紙幣の総称のこと”を指していて、(硬)貨と(紙)幣を合わせたものなので貨幣と呼びます。そして硬貨とは”1円玉・5円玉・10円玉・50円玉・100円玉・500円玉”を指し、紙幣とは”千円札・二千円札・五千円札・一万円札”のことを言います。ただし日本における硬貨や紙幣は上記を指しますが、様々な硬貨や紙幣が存在するので注意が必要です。また硬貨と紙幣には「どこが発行しているのか」という違いもあり、硬貨は政府が発行していて、紙幣は日本銀行が発行しています。これはそれぞれの硬貨や紙幣を見ればすぐに分かるのですが、硬貨には”日本国”と表記され、紙幣には”日本銀行”との表記があります。このことから”硬貨→日本政府が発行”し、”紙幣→日本銀行が発行”しているとすぐに分かります。ちなみに一般的に貨幣と言えば、硬貨と紙幣のことを指していますが、硬貨の正式名称は貨幣で、紙幣の正式名称は日本銀行券となっています。(紙幣にはそれぞれ日本銀行券と表記されています)ただ法律の中でも硬貨のことは「貨幣」と規定されていますが、あくまでも一般的には貨幣と言えば、硬貨と紙幣の両方を指しているので覚えておいてください。2.実は造幣局で製造されているのは”硬貨だけ”実は多くの人が誤解していることなのですが、造幣局(ぞうへいきょく)で製造されているのは”硬貨だけ”なんです。これは前章で解説していましたが、硬貨の正式名称は”貨幣”と言うので、「造幣局では貨幣が製造されている」という言葉から、紙幣も一緒に製造されていると誤解する人が増えたのでしょう。なので造幣局で製造されているのは”硬貨だけ”で、紙幣は造幣局ではなく、国立印刷局という場所で製造されています。そして造幣局に硬貨を発行させているのが日本政府で、国立印刷局に紙幣を発行させているのが日本銀行というわけです。ちなみに造幣局の本局は大阪府大阪市、国立印刷局の本局は東京都港区に存在します。(他にもそれぞれいくつか支店があります)以上が「貨幣と硬貨と紙幣の違いとは?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、貨幣とは、硬貨と紙幣の総称のことを言う。硬貨とは、”1円玉・5円玉・10円玉・50円玉・100円玉・500円玉”のこと。紙幣とは、”千円札・二千円札・五千円札・一万円札”のこと。硬貨の正式名称は”貨幣”で、紙幣の正式名称は”日本銀行券”となる。硬貨は造幣局で製造され、紙幣は国立印刷局で製造されている。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒一次請けと一次下請けの違いとは?⇒お金(硬貨)の表裏はどっち?表と裏のデザインは何が描かれている?⇒5円玉と50円玉に穴が開いている理由とは?⇒支払いを硬貨20枚以上で行うと拒否されるって本当?⇒元請けと下請けと孫請けの違いとは?状況によって呼び名は異なる?⇒元本と元金と元利金の違いとは?⇒以下・以上・未満・超えるの違いとは?簡単な覚え方について
-
さて何かしらの商品を購入するときにはお金を使用しますが、支払いの際に硬貨を何枚以上出すと拒否されるという話を聞いたことがないでしょうか。支払いの際に硬貨を大量に出している人を見る機会はほとんどないので、実際に本当のことなのかどうか疑問に感じる人も多いですよね。そこでこのページでは、支払いを硬貨20枚以上で行うと拒否されるのは本当なのかを解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次支払いを硬貨20枚以上で行うと拒否される?まとめ1.支払いを硬貨20枚以上で行うと拒否される?では支払いを硬貨20枚以上で行うと拒否されるのかを見ていきましょう。結論から言ってしまうと、支払いの際に同じ額面の硬貨を21枚以上用いると、相手側に拒否される可能性があります。これは”通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律”の第7条で定められており、内容は以下の通りです。貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。ここでの貨幣とは硬貨(1円玉・5円玉・10円玉・50円玉・100円玉・500円玉)を指し、上記は「1度の支払いで同じ額面の硬貨は20枚までなら通用します」という意味です。上図のように210円の支払いの場合、10円玉を21枚で支払うのであれば、お金を受け取る側はその支払いを拒否することができます。ただしお金(硬貨)を受け取る側さえ良ければ、同じ額面の硬貨は21枚以上使用しても問題なく支払いを行うことはできます。あくまでもお金(硬貨)を受け取る側にその支払いの拒否権が与えられるだけで、お金(硬貨)を受け取る側は必ずしも拒否しないといけないわけではありません。このような法律が定められているのは、お金(硬貨)を受け取る側の面倒を減らすためです。例えばスーパーなどで974円の支払いを1円玉のみでされると、店員さんはその1円玉が974枚あるかを数える手間が発生するわけです。そうなると店員さんがその1円玉を数えてる間にレジに行列ができてしまいます。そして何人も同じように大量の硬貨で支払いをしてしまえば、それだけで店員さんの業務が滞ってしまいますよね。こんな事態になることを防ぐためにこの法律が存在するわけです。ちなみに紙幣に関しては硬貨とは異なり支払いの際の枚数制限はなく、1度の支払いで何枚使用しても特に問題はありません。これについても”日本銀行法”第46条第2項で定められており、その内容は以下の通りです。日本銀行が発行する銀行券は、法貨として無制限に通用する。日本銀行が発行する銀行券とは紙幣(千円札・二千円札・五千円札・一万円札)を指し、「1度の支払いで日本銀行券(紙幣)は何枚使用しても良い」という意味になります。なので100万円の支払いを千円札1000枚で行ったとしても、お金を受け取る側からは嫌がられはしますが、法的には特に問題はないわけです。以上が「支払いを硬貨20枚以上で行うと拒否されるって本当?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、1度の支払いで同じ額面の硬貨を21枚以上使用すると、支払いを拒否される可能性がある。紙幣(日本銀行券)には、1度の支払いにおける枚数制限はない。お金(硬貨)を受け取る側の面倒を減らすために、1度の支払いにおける硬貨の枚数制限がされている。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒貨幣と硬貨と紙幣の違いとは?⇒一次請けと一次下請けの違いとは?⇒お金(硬貨)の表裏はどっち?表と裏のデザインは何が描かれている?⇒5円玉と50円玉に穴が開いている理由とは?⇒元請けと下請けと孫請けの違いとは?状況によって呼び名は異なる?⇒元本と元金と元利金の違いとは?⇒以下・以上・未満・超えるの違いとは?簡単な覚え方について