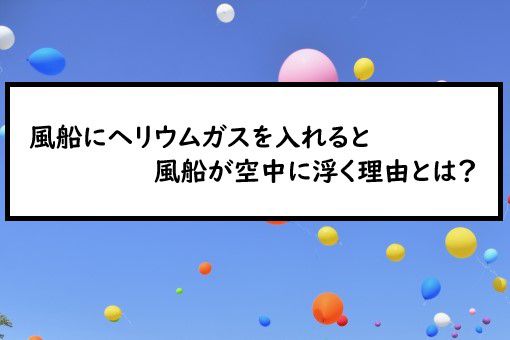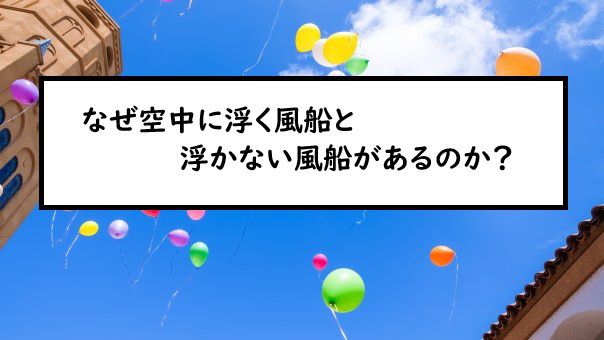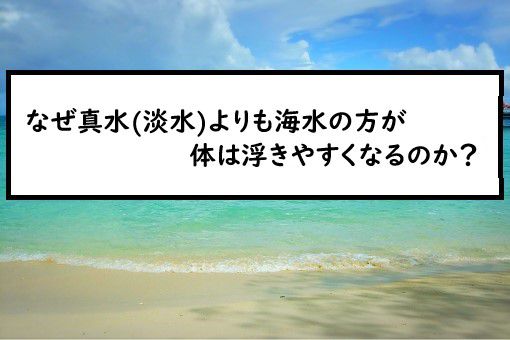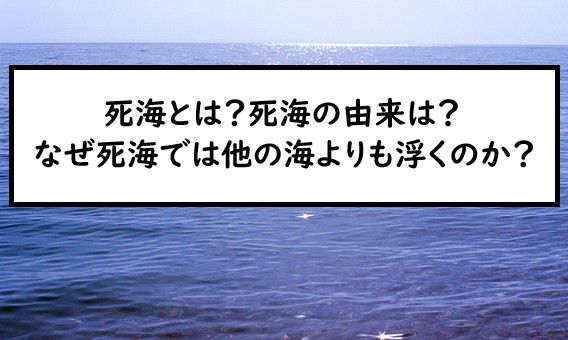さて風船にはヘリウムガスが入れられているものがありますが、風船にヘリウムガスを入れるとその風船は空中に浮きます。ですがなぜヘリウムガスを風船に入れると空中に浮くのか、疑問に感じている人もいるのではないでしょうか。そこでこのページでは、風船にヘリウムガスを入れると空中に浮く理由を簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次風船にヘリウムガスを入れると空中に浮く理由とは?昔は風船にヘリウムガスではなく水素が入れられていたまとめ1.風船にヘリウムガスを入れると空中に浮く理由とは?では風船にヘリウムガスを入れると空中に浮く理由とは何か見ていきましょう。結論から言ってしまうと風船にヘリウムガスを入れると空中に浮く理由は、ヘリウムガスが空気よりも軽い物質だからです。ヘリウムガスの比重は0.14(空気を1としたとき)で、これはヘリウムガスが空気より約7倍軽い物質であることを意味しています。このヘリウムガスを風船の中に入れることでその風船は周囲の空気よりも軽くなるので、どんどん上へ上へと上昇しようとして空中に浮くことになるんですね。風船の中にヘリウムガスを入れて空中に浮くようになるのは、ヘリウムガスによって得られた浮力(ふりょく)が風船自体の重さよりも大きくなったときになります。ヘリウムガスも何も入れていない風船(しぼんだ状態)は、当然ですが周囲の空気よりも重いため空中に浮くことはできません。そして風船の中にヘリウムガスを入れたとしても、入れるヘリウムガスの量が少なければ風船は空中に浮きません。(ヘリウムガスによって得られる浮力が風船自体の重さより小さいため)これを簡単に図でまとめると下のようになります。風船自体(気体が入っていない状態)が周囲の空気よりも重いので、風船自体を持ち上げるためにその重さよりも大きな浮力を作らなければなりません。だから十分な量のヘリウムガスが風船の中に入っていなければ、風船自体の重さより浮力が小さくなってしまうため空中に浮かなくなるんですね。関連:密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?2.昔は風船にヘリウムガスではなく水素が入れられていたいまでこそ空中に浮く風船の中にはヘリウムガスが入れられていますが、昔は風船の中にヘリウムガスではなく”水素”が入れられていました。ではなぜ水素からヘリウムガスに代えられたのかと言うと、それは水素自体が燃える物質でとても危険だからです。水素爆発という言葉をご存知の人も多いかと思いますが、空気中における水素濃度が高い状態でその近くに火気があると引火して爆発します。昔は水素が飛行船に使用されており、爆発事故が発生したことがあります。このような事故が起こったことからいまでは、爆発や燃える危険性のないヘリウムガスが使用されるようになりました。またヘリウムガス自体は無色・無味・無臭・無毒の気体なのですが、ヘリウムガスを大量に吸い込むと酸欠状態となり呼吸困難に陥ることがあります。(過去には実際にヘリウムガスによる事故が起こっています)空中に浮かすように風船の中にヘリウムガスが入れられている場合には、それを大量に吸い込んでしまうと呼吸困難となる危険性があります。(風船の中にはほぼ純粋なヘリウムガスしか入っていない)そしてヘリウムガスと言えば、声が高音になるジョークグッズとして用いられることも多いですが、ジョークグッズとして使用されるヘリウムガスには酸素が20%ほど含まれています。なのでジョークグッズとして用いられるヘリウムガスは吸い込んでも問題はありません。呼吸困難に陥る恐れがあるのは、風船の中に入れられているヘリウムガスになりますので、風船の中に入れられているヘリウムガスは吸い込まないように注意してください。関連:一酸化炭素中毒とは?発生する原因と仕組みについて簡単に解説!以上が「風船にヘリウムガスを入れると空中に浮く理由とは?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、風船にヘリウムガスを入れると空中に浮く理由は、ヘリウムガスが空気よりも軽い物質だから(浮力が働く)。水素からヘリウムガスに代わったのは、水素自体が燃える物質でとても危険だから。風船の中のヘリウムガスは吸い込むと、呼吸困難になる危険性があるので吸い込まないこと。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒なぜ空中に浮く風船と浮かない風船があるのか?⇒熱気球とは?また熱気球はどんな原理で空中に浮いているのか?⇒質量とは?重量(重さ)との違いと単位について⇒真空とは何か?分かりやすく図で解説!⇒1気圧とは?また何ヘクトパスカル(hPa)なのか?⇒風の正体とは?どんな原理で吹いているのか?⇒自由落下とは?空気抵抗・重さ・質量は関係ないのかを簡単に解説!⇒空気の膨張とは何か?空気の温度によって体積が変化する仕組みとは?⇒空気の温度で重さは変わる?暖かい空気は軽く冷たい空気が重い仕組みとは?⇒空気とは何か?高い場所ほど空気が薄くなる理由とは?
ギモン雑学
「 浮く 」の検索結果
-
-
さて風船には空中に浮く風船と浮かない風船の2種類が存在します。風船の見た目は変わらないのに、なぜ空中に浮く風船があって、中には空中に浮かない風船があるのか疑問に感じている人もいますよね。そこでこのページでは、空中に浮く風船と浮かない風船がある理由を解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次なぜ空中に浮く風船と浮かない風船があるのか?まとめ1.なぜ空中に浮く風船と浮かない風船があるのか?ではなぜ空中に浮く風船と浮かない風船があるのかを見ていきましょう。結論から言ってしまうと空中に浮く風船と浮かない風船があるのは、風船の中に入っている気体(ヘリウムガスまたは空気)が異なるからです。上図のように空中に浮く風船の中にはヘリウムガスが入っていて、空中に浮かない風船の中には空気が入っています。ヘリウムガスは空気よりも約7倍ほど軽い物質になるため、周囲に存在する空気よりも上へ上へと上昇しようとします。(空気の比重=1とすると、ヘリウムガスの比重=0.14となる)なので風船を自分の息で膨らませようとすると、風船の中に入る気体は空気になるのでその風船は空中に浮かなくなります。このようにヘリウムガス(浮く)なのか空気(浮かない)なのか、風船の中にある気体の種類によって空中に浮くかどうかが決まります。関連:風船にヘリウムガスを入れると空中に浮く理由とは?関連:密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?以上が「なぜ空中に浮く風船と浮かない風船があるのか?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、空中に”浮く”風船の中には、ヘリウムガス(空気より約7倍軽い物質)が入っている。空中に”浮かない”風船の中には、空気が入っている。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒自由落下とは?空気抵抗・重さ・質量は関係ないのかを簡単に解説!⇒風の正体とは?どんな原理で吹いているのか?⇒空気とは何か?高い場所ほど空気が薄くなる理由とは?⇒真空とは何か?分かりやすく図で解説!⇒一酸化炭素中毒とは?発生する原因と仕組みについて簡単に解説!⇒重力加速度とは?仕組みを分かりやすく図解!⇒空気抵抗とは?なぜ物体の速度が上がると空気抵抗は大きくなるのか?⇒山でお菓子の袋が膨らむ仕組みとは?分かりやすく図で解説!⇒空気の膨張とは何か?空気の温度によって体積が変化する仕組みとは?⇒熱気球とは?また熱気球はどんな原理で空中に浮いているのか?
-
さてあなたは海の水のほうがプールの水よりも、体が浮きやすいというのはご存知でしょうか。これには”水の重さ”が大きく関係しているのですが、この原理をしっかりと理解している人は意外と少ないように感じます。そこでこのページでは、なぜ真水(淡水)よりも海水の方が体がよく浮くのかを簡単に解説します。どうぞごご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次なぜ真水(淡水)よりも海水の方が体がよく浮くのか?まとめ1.なぜ真水(淡水)よりも海水の方が体がよく浮くのか?ではなぜ真水(淡水)よりも海水の方が体がよく浮くのかを見ていきましょう。(真水と淡水は同じものを表しています)結論から言ってしまうと、真水よりも海水の方が体が浮きやすくなる理由は、海水の方が塩が含まれている分だけ重いため、その分だけ真水よりも浮力が大きくなるからです。まず海水における平均的な塩分濃度は約3.5パーセントほどで、比重はだいたい1.025ほどになります。(水温によっても比重は変化するので注意してください)海水の比重1.025というのは真水と比べたときの比重なので、同じ体積で比べると真水よりも2.5パーセントの差があることを意味します。つまり海水の方が真水よりも2.5パーセントほど、密度が大きい(重い)ということです。関連:密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?そして水の上にモノが浮かぶのは、水の中でそのモノに対して”浮力”という力が働いているからです。”浮力は流体(水や空気など)の重さによって発生する力のこと”を言い、その流体の密度が大きい(重い)ほど発生する浮力は大きくなります。ここでの流体とは”真水”と”海水”のことを指していて、真水よりも海水の方が重いので海水の方が浮力は大きくなります。例えば空気で膨らませた風船を水の中に沈めていき、水から風船にかかる浮力を図で表したものが下になります。上図のように水中の風船には”水圧”があらゆる方向からかけられることになり、水深が深くなるほど大きな水圧が風船に対してかかっていきます。その風船にかけられた”上向きの水圧”から”下向きの水圧”を引いたものが、”浮力”となります。これが分かればなぜ流体の重さによって浮力が変化するのかは簡単です。それぞれ重さが異なる流体の浮力の大きさがどうなるのかを下に表します。上図のように浮力というのは流体の重さによって発生している力なので、その流体が軽ければ浮力は小さくなり、その流体が重ければ浮力は大きくなります。この例では風船でしたが、人間も同様に水から浮力がかかるので考え方は同じです。なので海の水は塩が含まれている分だけ真水(淡水)よりも重くなるため、海水の方が浮力が大きくなって、プールの水よりも体が浮きやすくなるというわけです。この解説だけではいまいち浮力について理解するのが難しいと感じた人は、下記の関連ページで分かりやすく解説しているのでそちらをどうぞご覧ください。関連:浮力とは何か?浮力の原理を簡単に図で解説!関連:浮力と流体の密度の関係について。流体の密度で浮力が変化する仕組みとは?以上が「なぜ真水(淡水)よりも海水の方が体がよく浮くのか?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、海水の方が体が浮きやすくなるのは、海水の方が塩が含まれている分だけ重いため、その分だけ真水よりも浮力が大きくなるから。浮力は流体の重さによって発生している力なので、その流体が重さいほど浮力は大きくなる。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒水圧とは何か?わかりやすく図を用いて解説!⇒水圧と浮力の違いについて簡単に図で解説!⇒絶対零度とは?また絶対零度の温度は何度なのか?⇒水温と浮力の関係について。水温によって浮力が変化する仕組みとは?⇒なぜ水温と気温は同じなのに体感温度が違うのか?⇒死海とは?死海の由来は?なぜ死海は他の海よりも浮くことができるのか?⇒流体とは何かをわかりやすく解説!圧力はどんなかかり方なのか?⇒海水と淡水と真水の違いとは?⇒圧力鍋とは何か?圧力鍋の仕組みをわかりやすく図解!⇒揮発とは?蒸発との違いと意味は何か?なぜ揮発は起こる?
-
さてあなたは死海という言葉を聞いたことがあるでしょうか。名称だけを見るととてもこわい場所なんだと感じるかと思いますが、実は死海というのはリゾート地としても知られています。ではどうして”死海”のようなこわい名称が付いたのか疑問に感じますよね。そこでこのページでは死海とは何か?死海の由来は?またなぜ死海では他の海よりも体が浮くのかを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次死海とは?死海の由来とは?なぜ死海では他の海よりも体が浮くのか?まとめ1.死海とは?では死海とは何かを見ていきましょう。まず死海(しかい)とは、ヨルダンとイスラエルとの国境に存在する塩湖のことを言います。死海のことを海だと思っている人も多いですが、実は死海というのは湖なんですね。塩湖(えんこ)というのは水1L中に0.5g以上の塩類を含む湖のことで、死海における塩分濃度は約27%なので、水1L中に塩類が270g含まれることになります。ただの海水だと平均的な塩分濃度は約3.0%~3.5%ほどですので、死海の約27%という塩分濃度はかなり高いのが分かりますよね。(死海の湖底だと塩分濃度は約40%ほどです)また死海の海抜はマイナス400mほどで、かなり低い場所に存在しています。死海には6つの川から水が流入してきますが、周辺で死海よりも低い場所がないため、死海の水が他へと流出することはありません。そうなると死海へと水が流入するばかりで水位が増えていくと考えますが、死海は年間を通して気温が高く、さらに降水量も少ないために水が蒸発しやすくなります。この水の蒸発が多く起こることにより他から水が流入してきても、水の流入量と蒸発量が釣り合うことで死海の水位は保たれています。ただ最近では死海の主な水源であったヨルダン川付近において住民が増えたので、ヨルダン川の水の消費量が増加したために、死海へと流入する水の量が減っているそうです。そして死海へと流入する水の量が減少しても、蒸発する死海の水の量は変化しないため、流入と蒸発の釣り合いが取れなくなり、死海の水位は少しずつ低下していきます。このような事情もあり、死海の水位は年間平均で約1mずつ低下しています。関連:水が100度に達していないのに蒸発する仕組みとは?2.死海の由来とは?では名称が”死海”となった由来について見ていきましょう。さっそくですが”死海”という名称が付けられている由来としては、塩分濃度が高く(約27%)、生物が生きられない環境という意味からきています。実際に死海では湧水の発生している1か所を除いて、魚類の生息は確認されていません。湧水の発生している場所では、小さな魚がわずかながら存在するようです。そして湧水の発生していない塩分濃度が高い場所でも、高い塩分濃度を好む”高度好塩菌”などの生息は確認されています。また魚類が死海のような塩分濃度が高い場所で生息できない理由は、浸透圧の関係によって魚類が脱水状態を引き起こしてしまうからです。魚類の体液の塩分濃度は約0.9%ほどで人間などと変わらなく、それに比べて死海の水の塩分濃度は約27%です。液体には濃度の低い方から濃度の高い方へと移動して、液体の濃度を同じにしようとする性質があります。つまり死海では上図のように魚類の体液の方が塩分濃度が低いために、死海の水の塩分濃度と同じにしようとして、魚類の体液中の水分が死海へと放出されてしまいます。そして水分が放出された魚類の体内では強い脱水症状が引き起こされるので、死海だと魚類は生息することができないんですね。このように濃度を同じにしようと液体が移動することを”浸透(しんとう)”と言い、その浸透によって発生する圧力のことを”浸透圧(しんとうあつ)”と言います。ただし海水魚はもともと自身の体液の塩分濃度よりも高い海で生息していますが、普通の海ぐらいの塩分濃度(約3.0%~3.5%)なら体液の塩分濃度を調節できます。(海水魚には海水を飲んだとしても、エラから塩分を放出する機能などがあります)海水の場合でも浸透圧の関係によって魚から水分は少しずつ放出はされていきますが、海水魚には塩分調節機能があることで必要な水分を体内へと取り込むことができます。ですが死海の場合は塩分濃度が高すぎて、海水魚の塩分調節機能では調節が難しいのです。なので上手く塩分濃度の調節ができないために、脱水症状が起こり死海では魚類が生息というわけです。関連:海水と淡水と真水の違いとは?2.なぜ死海では他の海よりも体が浮くのか?では死海だと他の海よりも体が浮きやすいという話は有名ですが、なぜ死海だと他の海よりも体が浮きやすくなるのかを解説していきます。結論から言ってしまうと死海では体が浮きやすくなる理由は、死海の塩分濃度が他の海よりも高いことによって、その分だけ比重が大きくなるからです。つまり他の海よりも死海の水の方が塩分が多く含まれている分だけ、その水は重くなるので重く(密度が大きく)なっただけ、浮力も大きくなるからなんですね。塩の比重は水と比較した場合には2.16となっており、これは塩が水よりも2.16倍重い(密度が大きい)物質だということを表しています。例えば同じ100gの水でも、塩分濃度が高い水と低い水では、溶けている塩の量だけ重さに差が生じることになります。これにより塩分濃度が高い水ほど、重くなるということは分かりますよね。そして水の上に体が浮くのは、体に対して水から”浮力”が働いているからです。浮力と言うのは、その水(流体)の重さによって発生している力のため、その水が重ければ重いほど水から体に対して働く浮力も大きくなります。ですので他の海よりも塩分濃度がかなり高い死海の水の方が重くなり、それによって水から体が受ける浮力が大きくなったというわけなんですね。浮力と流体の密度(重さ)の関係について、詳しい仕組みは下記をご覧ください。関連:密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?関連:浮力と流体の密度の関係について。流体の密度で浮力が変化する仕組みとは?以上が「死海とは?死海の由来は?なぜ死海は他の海よりも浮くことができるのか?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、死海とは、ヨルダンとイスラエルとの国境に存在する塩湖のこと(死海は海ではなく湖)。”死海”という名称の由来は、その塩分濃度の高さゆえに魚類などの生物が生息できないことからきている。死海が他の海よりも体が浮くのは、死海の水が他の海よりも塩分濃度が高いことで、水から受ける浮力が大きくなるから。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒浮力とは何か?浮力の原理を簡単に図で解説!⇒水温と浮力の関係について。水温によって浮力が変化する仕組みとは?⇒水圧と浮力の違いについて簡単に図で解説!⇒氷とドライアイスと液体窒素の違いとは?最も温度が低いのはどれ?⇒密度が大きい(高い)・密度が小さい(低い)の意味を簡単に図解!⇒なぜ氷は空気中よりも水中の方が溶けやすいのか?⇒なぜ真水(淡水)よりも海水の方が体がよく浮くのか?⇒ドライアイスとは?ドライアイスから発生する白い煙の正体って何?⇒ストローで飲み物を吸うことができる仕組みとは?⇒圧力鍋とは何か?圧力鍋の仕組みをわかりやすく図解!