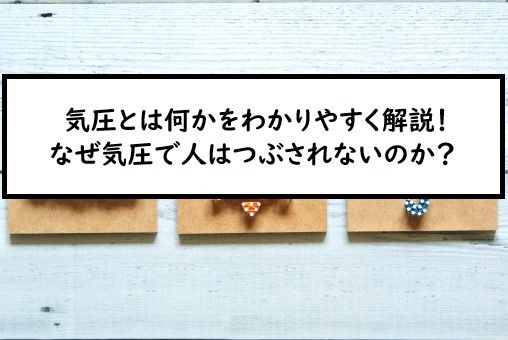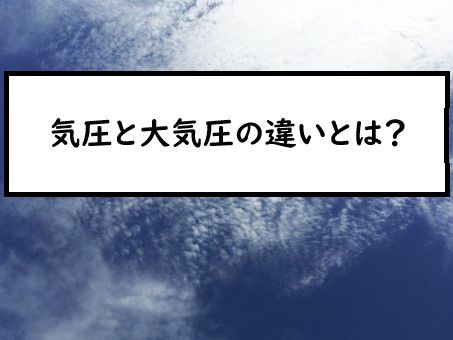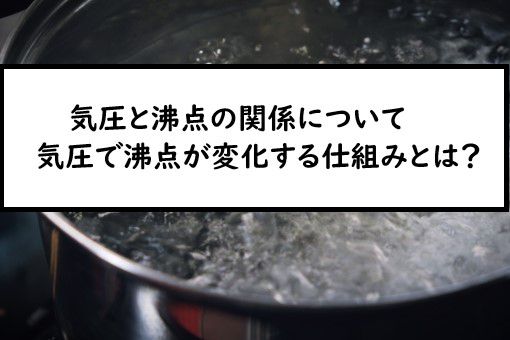さて天気予報などで気圧という言葉をよく聞くことがありますよね。あなたはこの気圧についてしっかりと理解できていますか?気圧は実際に目に見えるものではないのであまり理解できず、うまくイメージできていないという人も多いのではないでしょうか。そこでこのページでは気圧とは何かをわかりやすく解説。またなぜ気圧によって人はつぶされないのかを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次気圧とは何か?気圧について分かりやすく解説!空気の量と気圧の大きさの関係について気圧が働く力の方向についてなぜ人や物は気圧によってつぶされないのか?まとめ1.気圧とは何か?では気圧とは何か見ていきましょう。気圧(きあつ)とは、大気によって発生する圧力のことです。大気というのは地球のような惑星を包んでいる気体のことで、”地球の大気=空気”のことなので空気によって発生する圧力だと考えてください。空気は無色透明の気体なので目で見ることはできませんが、目で見えないからといってそこに空気が存在していないわけではありません。空気は見えないだけで私たちの周りに常に存在していて、その空気にも質量があって、地球からの重力がかかっています。つまり空気にも他のモノと同様に重さがあるということです。関連:太陽系とは何かをわかりやすく図で解説!そして気圧というのは空気に重さがあるからこそ発生するもので、空気に重さがなければ気圧は発生しません。(詳しい仕組みは次の章で解説していきます)例えばあなたの手の上にペンを乗せてみると、手の上にペンの重さを感じることができると思います。ペンに対して地球からの重力がかかることによって、下向きの圧力(つまり重さ)がかかるためにその力を手で感じることになります。(厳密に言えば、ペンの上から空気の重さもかかっています)これがペンの重さではなく、空気の重さによって発生した圧力であれば”気圧”ということです。関連:気圧と大気圧の違いとは?さて以上の解説だけでは気圧についてイメージするのが難しいと思うので、次の章で気圧について図を用いてわかりやすく解説していきますね。2.気圧について分かりやすく解説!では気圧について図を用いて分かりやすく解説していきます。まず気圧というのは空気の重さによって発生する圧力のことです。気圧について簡単にイメージできるように、容器内で重ねたボールを例にして解説していきます。(容器内のボールを空気だと思ってください)気圧は上の層に存在するボールから下の層に存在するボールに対して、その重さがかかっていくことで発生するので下図のように順番に力がかかっていきます。まずは上から1層目に存在するボールの重さによって、2層目に存在するボールに力が加わります。次に2層目のボールは横方向に力が流れ(1層目のボールの重さ分の力)、下方向(3層目)に1層目と2層目のボールの重さによる力が加えられます。横方向にも力が流れていくのは上から力がかけられたときに、ボールがつぶされることで横方向に力が逃げていくために起こります。また各方向へと力が流れていきますが、作用反作用の法則によってそれらの力とは逆向きの力も加わります。最終的に気圧の関係は上図のようになります。気圧が空気の重さによって発生する力だということは分かってもらえたと思うので、次は”空気の量と気圧の大きさの関係について”、”気圧が働く方向について”解説していきます。空気の量と気圧の大きさの関係についてでは空気の量と気圧の大きさの関係について解説します。まず空気の量と気圧の大きさの関係を簡単にまとめると下のようになります。存在する空気の量が少ない ⇒ 気圧は小さくなる存在する空気の量が多い ⇒ 気圧は大きくなる分かりやすい例としては山などの標高が高い所では、地上に比べて気圧が低いです。それはなぜかというと、標高が高くなるにつれて空気の量が少なくなる(空気が薄くなる)からです。上図のように地上は空気の存在する量が多いので気圧が高く、反対に高度が高くなるほど空気の量が少なくなるため気圧が低くなります。空気の量が多くなれば気圧が高くなる理由については、容器の中に軟らかいボールを詰め込んだときのことをイメージしてみてください。(ボール=空気だと仮定しています)上図ではボールによって発生する圧力を矢印で表していますが、ボールを詰め込めばボール同士でお互いに圧力を掛け合うことになりますよね。逆に容器内に物を詰め込まないで余裕を持たせてやれば、ボール同士であまり圧力を掛け合わないで済みます。空気もボールと同じように、詰まっていれば(量が多ければ)それだけ周りへの圧力が強くなり、詰まっていなければ(量が少なければ)それだけ周りへの圧力は弱くなります。これがつまり空気の量が多ければ気圧が高くなり、空気の量が少なければ気圧が低くなるということです。関連:空気とは何か?高い場所ほど空気が薄くなる理由とは?関連:なぜ標高が高い所は寒いのか?太陽との距離は関係ないって本当?そして地上の気圧が上空に比べて大きいのは、地上の空気にはその上に存在する空気の重さ分もかかっているためです。地上の空気にその上に存在する空気の重さ分もかかることで、地上の空気はぎゅうぎゅうに詰められた状態となり、上空よりも気圧が大きくなります。ぎゅうぎゅうに詰められるということは詰められていない状態に比べて、同じ体積あたりに存在する空気の量が多いということです。これにより地上では気圧が大きく、上空では気圧が小さくなるんですね。ちなみに地上における気圧の大きさを”1気圧”と表しますが、詳しくは下記をご覧ください。関連:1気圧とは?また何ヘクトパスカル(hPa)なのか?気圧が働く力の方向について次に気圧が働く力の方向について解説します。気圧が働く力の方向は、気圧の大きさをボールで表した図を見ればすぐに分かります。上図のように気圧というのは、”あらゆる方向”に対して働きます。最も上の層(図では1層目)の空気の場合については、自身の重さによる下向きの力とそれに反発する上向きの力しかかかりません。ですがよほど上空(宇宙に近い)に存在する空気ではない限り、ほとんどの空気にはその周囲に別の空気が隣接して存在しています。なので図における1層目のような状態には、日常ではまずならないでしょう。基本的に気圧は物体に対して、”あらゆる方向からかかる”ので覚えておきましょう。また気圧だけでなく、水の重さによって発生する”水圧”についても同じ考え方です。関連:水圧とは何か?わかりやすく図を用いて解説!関連:浮力とは何か?浮力の原理を簡単に図で解説!3.なぜ人や物は気圧でつぶされないのか?ではなぜ人や物は気圧でつぶされないのか、その理由を見ていきましょう。結論から言ってしまうと気圧によって人や物がつぶされない理由は、外側からだけでなく内側からも空気による圧力(気圧)がかかっているからです。私たち人間や地上に存在する全てのものには、例外なく気圧がかかっています。気圧というのは空気の重さによるものなので、地上にいればその上に存在する空気の重さを受けていることになります。この気圧の大きさはどのくらいなのかというと、1[m^2](平方メートル)当たり約10t(トン)の力がかかっているのと同じなんです。1平方メートル当たり約10トンの気圧がかかるということは、縦1メートル横1メートルの面積に対して約10トンの力がかかるということです。この大きさの気圧が地上にいる私たち人間や物に対して、上からだけでなく四方八方から常にかかっているんですね。そして、ここで重要なポイントが人間や物の内部にも空気が含まれていて、外側からかかる気圧と同じように内側からも気圧がかかっているということです。このように空気を含んでいれば内側からも外側と同じだけの気圧が働くので、人間や物が気圧によってつぶされてしまうということもなくなるんですね。例えば袋の中に空気を入れて膨らませると、その袋は膨らんだままの状態になります。なぜ袋がこのような状態になるのかというと、袋の内側と外側で気圧がかかっているからです。では袋の中の空気だけを抜いてみるとどうなるでしょうか?答えは簡単ですよね。袋の中の空気を抜いたらその袋は外側からの気圧によって、ペシャンコにつぶれてしまいます。袋の中の空気を抜けば袋の内側から気圧がかからなくなるので、袋の外側からかかる気圧を押し返すことができなくなりつぶされてしまいます。袋の中の空気を抜くということはつまり、袋の中が真空状態になるということです。この真空を利用したものに真空パックというものがありますが、食品を長期保存させたいときによく使用されますよね。真空パックで食品が保存されているものを見たことがあれば分かると思いますが、パックの中を真空状態にしているので食品とパックがほとんど密着しています。あれはパックの中の空気を抜いているため、パックの外側からの気圧につぶされているから起こることなんですね。関連:山でお菓子の袋が膨らむ仕組みとは?分かりやすく図で解説!関連:真空とは何か?分かりやすく図で解説!以上が「気圧とは何かをわかりやすく解説!なぜ気圧で人はつぶされないのか?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、気圧とは、空気の重さによって発生する圧力のこと。気圧の強さは空気の量に比例して大きくなる。気圧が働く力の向きは、下向きだけではなく”あらゆる方向から”働く。人や物が気圧でつぶされないのは、内側からも気圧がかかっているから。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒空気の膨張とは何か?空気の温度によって体積が変化する仕組みとは?⇒気圧と沸点の関係について。気圧によって沸点が変化する仕組みとは?⇒圧力鍋とは何か?圧力鍋の仕組みをわかりやすく図解!⇒空気と大気の違いとは?⇒断熱膨張とは?また断熱圧縮とは?どんな原理で温度変化するのか?⇒蒸気圧とは?水の沸点と蒸気圧の関係についてわかりやすく解説!⇒吸盤が壁にくっつく仕組みとは?⇒水圧と浮力の違いについて簡単に図で解説!⇒死海とは?死海の由来は?なぜ死海は他の海よりも浮くことができるのか?⇒なぜ真水(淡水)よりも海水の方が体がよく浮くのか?
ギモン雑学
「 気圧 」の検索結果
-
-
テレビを見ていると「気圧」と「大気圧」という2つの言葉を聞くことがあります。そして「気圧」と「大気圧」という言葉はよく混同されがちです。しっかりとこれらの違いを説明できる人は少ないのではないでしょうか。このページを訪れたということはこれらの言葉の意味について、何が違うんだろうと疑問に感じたからでしょう。そこでこのページでは気圧と大気圧とは何か?また気圧と大気圧の違いについて簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次気圧とは?大気圧とは?気圧と大気圧の違いについてまとめ1.気圧とは?ではまず気圧とは何なのか見ていきましょう。気圧(きあつ)とは、気体によって発生する圧力のことです。気体によって発生する圧力だから気圧です。圧力とはある物体の面を押す力のことなので、気圧とは気体によって押される力とも言えますね。無色透明で目に見えない気体も多いですが、その無色透明な気体でもしっかりと質量があって地球からの重力がかかっています。なので地上で生活している人間やあらゆる物体には、常に空気(気体)による圧力である気圧がかかっているということです。では次の章で大気圧とは何なのか説明していきますね。関連:気圧とは何かをわかりやすく解説!なぜ気圧で人はつぶされないのか?2.大気圧とは?では大気圧とは何なのか見ていきましょう。大気圧(たいきあつ)とは、大気によって発生する圧力のことです。大気とは惑星の周りに存在する気体の層のことです。大気は地球の場合なら空気のことを指しています。つまり大気圧とは、惑星の周りに存在する気体の層(地球なら空気)によって発生する圧力のことを言います。ただ天気予報など一般的に言われる大気圧の意味は、地上における空気による圧力のことを指す場合がほとんどです。地球以外の惑星の話題となったときに大気圧と言った場合であれば、それはその惑星の大気(空気かどうかは分からない)による圧力を指すので注意してください。関連:太陽系とは何かをわかりやすく図で解説!それではこれらを踏まえて、次の章では気圧と大気圧の違いについて説明していきますね3.気圧と大気圧の違いについてでは気圧と大気圧の違いとは何なのか見ていきましょう。結論から言ってしまうと気圧と大気圧の違いは、それぞれの圧力が指している範囲です。どういうことなのか説明していきますね。大気圧とは重力を持っている惑星の周りに集まっている気体の層、つまり大気によって発生する圧力のことです。そして気圧とは、ただ単に気体の圧力のことのみを指しています。地球の場合を例にして見ていきましょう。地球の大気とは空気のことです。なので空気によって発生した圧力なら、それは気圧でもあり大気圧でもあります。ですが空気以外の気体によって発生した圧力なら、それは気圧ではありますが大気圧ではありません。以上のことから大気圧は重力を持っている天体の周りの大気による圧力のみを示し、気圧は大気圧も含めて気体による圧力すべてのことを指しています。つまりは大気圧よりも気圧のほうが示している範囲は広いってことですね。関連:流体とは何かをわかりやすく解説!圧力はどんなかかり方なのか?以上が「気圧と大気圧の違いとは?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、気圧とは、気体の圧力のこと。大気圧とは、大気による圧力のこと。大気とは、地球に限らず重力のある天体の表面に存在する気体の層のこと。大気圧は大気による圧力のみを指し、気圧は大気圧も含めた気体による圧力すべてを指す。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒空気と大気の違いとは?⇒粉塵爆発とは何か?粉塵爆発の原理をわかりやすく図で解説!⇒空気の膨張とは何か?空気の温度によって体積が変化する仕組みとは?⇒空気とは何か?また高い場所ほど空気が薄くなる理由とは?⇒気圧と沸点の関係について。気圧によって沸点が変化する仕組みとは?⇒空気の温度で重さは変わる?暖かい空気は軽く冷たい空気が重い仕組みとは?⇒圧力鍋とは何か?圧力鍋の仕組みをわかりやすく図解!⇒浮力とは何か?浮力の原理を簡単に図で解説!⇒ストローで飲み物を吸うことができる仕組みとは?⇒吸盤が壁にくっつく仕組みとは?
-
さて気圧と沸点にはとても密接な関係があるのを知っていますか?そして周囲の気圧が変化することで液体の沸点も変化しますが、なぜ気圧が変化すると沸点も変化するのでしょうか。意外に気圧と沸点の仕組みを理解できていない人も多いように感じます。そこでこのページでは気圧と沸点の関係について。また気圧によって沸点が変化する仕組みを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次気圧と沸点の関係について気圧によって沸点が変化する仕組みとは?水の温度は水分子の動きで決まる水から水蒸気に変わるときの分子の動き方気圧で水分子の出やすさが左右されるまとめ1.気圧と沸点の関係についてでは気圧と沸点の関係について見ていきましょう。まず結論から言うと気圧と沸点の関係は下記のようになります。周囲の気圧が低くなる ⇒ 沸点が低くなる周囲の気圧が高くなる ⇒ 沸点が高くなる沸点(ふってん)とは液体が沸騰するときの温度で、水の沸点が約100度というのはご存知だと思います。しかし水の沸点が100度というのは、あくまでも周囲の気圧の大きさが1気圧における場合です。1気圧というのは地上における気圧の大きさを表していて、高度が高くなればなるほど1気圧よりも低くなっていきます。目安として富士山(3776m)だと周囲の気圧の大きさは約0.6気圧になり、気圧の大きさが0.6気圧における水の沸点は約87度にまで下がります。なので水を熱して100度で沸騰するのは地上(1気圧)における場合のみで、周囲の気圧の大きさによって水(液体)が沸騰する温度は異なります。関連:1気圧とは?また何ヘクトパスカル(hPa)なのか?そして日常的に気圧と沸点の関係を利用したものに圧力鍋(圧力釜)があります。簡単に言えば圧力鍋というのは鍋の中の圧力を調整することで、より高温で食材を煮込んだりすることができる調理器具のことです。なぜ圧力鍋を使用すればより高温で食材を煮込むことができるのか?それは圧力鍋の中の気圧(圧力)が高くなるので、水が沸騰する温度が上がるため通常よりも高温で煮込むことが可能になるからです。水の沸点というのは周囲の気圧の大きさが1気圧であれば100度です。ということは周囲の気圧が1気圧なら水(液体)が100度で水蒸気(気体)になってしまうということです。加熱して煮込んでいくと少しずつ沸点に達した水分が水蒸気に変化していき、普通の鍋であればその水蒸気は鍋のふたの隙間から外へと出ていきますよね。ですが圧力鍋の場合は沸騰した水が水蒸気になっても、鍋の中がある程度の高圧にならない限り水蒸気が漏れない造りになっています。なので水蒸気がどんどんたまっていくことで鍋の中が水蒸気による気圧で圧力が高くなるため、沸騰しにくくなるので水の沸点が上がり通常よりも高温で煮込むことができるというわけです。このように気圧と沸点には密接な関係があるんですね。では気圧と沸点の関係についてはどういうものなのか理解していただけたかと思いますので、次の章で仕組みについて図を用いていきながら分かりやすく解説していきます。関連:圧力鍋とは何か?圧力鍋の仕組みをわかりやすく図解!2.気圧によって沸点が変化する仕組みとは?気圧によって沸点が変化する仕組みについて見ていきましょう。気圧によって沸点が変化するのは液体すべてに言えることですが、ここでは私たちに馴染みがある液体の水で解説していきます。結論から言ってしまうと気圧によって沸点が変化する仕組みは、空気中に存在する空気分子の量で、空気中への水分子の出やすさが変わるからです。どういうことなのか順番に解説していきます。水の温度は水分子の動きで決まるまず気圧によって沸点が変化する仕組みを理解するためには、物質(空気や水)が分子という小さい粒で構成されていると認識する必要があります。これによって水や空気は下図のようなイメージになります。上図のように枠の中に水分子や空気分子がたくさん存在することで、水(液体)や空気(気体)ができていると考えてください。そして分子というのは常に動いていて、分子の動きはその物質の温度に大きく関係しています。分子の動きが激しければその物質の温度は高くなり、分子の動きが穏やかであればその物質の温度は低くなります。このように物質の温度を決めているのは、その物質を構成している分子の動きによるものになります。関連:温度とは何か?物体の状態変化と温度の関係について解説!水(液体)から水蒸気(気体)に変わるときの分子の動き方次は水を加熱して沸騰させることで、水(液体)が水蒸気(気体)に変化するイメージについて見ていきましょう。水を加熱していくと少しずつ水の温度が上がっていきますが、それは水を構成している水分子の動きが激しくなっているということを意味します。また水(液体)でいる状態というのは、水分子が集合してお互いが繋がり合っている状態になります。そして加熱され水の温度が上がることで水分子の動きが激しくなってくると、その水分子同士の繋がりから外れる水分子が出てきます。上図のように加熱して水の温度を上げていくと水分子の動きが激しくなり、水分子同士の繋がりから外れるので空気中に水分子が飛び出てしまいます。簡単に言えば、水分子同士の繋がりから水分子が外れるということが、水(液体)から水蒸気(気体)に変化するってことなんですね。なので沸点というのは水だけに限らず液体がその液体分子の繋がりから、液体分子を空気中に放つために必要な動きの激しさを表している温度になります。関連:湯気と水蒸気の違いとは?気圧で水分子の出やすさが左右されるさてここが最も重要なポイントになります。まず物質の分子という観点から見てみると、周囲の気圧が変化することで一体何が変わるのでしょうか?それは空気中に存在している空気分子の量が変わります。一般的に周囲の気圧が高い状態というのは空気分子が多く存在している状態で、反対に気圧が低い状態というのは空気分子が少ない状態になります。だから山など高度の高いところでは、空気分子の量が少ない(空気が薄い)ので気圧が低くなるんですね。この空気中に存在している空気分子の量が変化することによって、水(液体)が水蒸気(気体)に変化し始める温度も変わるのです。では空気中に存在する空気分子の量が変化することで、水分子の出やすさにどのような違いがあるのか下図をご覧ください。このように存在する空気分子が少なければ簡単に水分子は飛び出せますが、空気中に存在する空気分子が多ければ水分子が空気中に出にくくなります。なので空気中に空気分子が多く存在しているほど、水分子が空気中に出るには大きなエネルギーが必要になります。そしてその大きなエネルギーというのが、加熱することで水分子の動きを激しくすることです。だから気圧が高い(空気分子が多い)ほど大きなエネルギーが必要になるので、水分子の動きを激しくするために液体の沸点が高くなります。関連:気圧とは何かをわかりやすく解説!なぜ気圧で人はつぶされないのか?以上が「気圧と沸点の関係について。気圧によって沸点が変化する仕組みとは?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、周囲の気圧が高ければ沸点も高くなり、気圧が低ければ沸点も低くなる。仕組みとしては、空気中の空気分子の量で水分子の出やすさが左右されるから。空気分子が多ければ、空気中に水分子が出やすくなる(水蒸気になりやすくなる)。空気分子が少なければ、空気中に水分子が出にくくなる(水蒸気になりにくくなる)。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒真空とは何か?分かりやすく図で解説!⇒状態変化とは何か?物質が状態変化する仕組みを簡単に図解!⇒山でお菓子の袋が膨らむ仕組みとは?分かりやすく図で解説!⇒空気の膨張とは何か?空気の温度によって体積が変化する仕組みとは?⇒気圧と大気圧の違いとは?⇒流体とは何かをわかりやすく解説!圧力はどんなかかり方なのか?⇒ピンポン玉のへこみの直し方とは?またへこみが直る仕組みについて⇒浮力とは何か?浮力の原理を簡単に図で解説!⇒ストローで飲み物を吸うことができる仕組みとは?⇒吸盤が壁にくっつく仕組みとは?
-
さてあなたは1気圧という言葉を聞いたことがあるでしょうか。1気圧とは日常的にあまり聞かない言葉ですが、私たちが生活するうえで大きく関係しているものになります。1気圧について理解していなくても困ることはないと思いますが、理解していないよりは理解していたほうが良いのは間違いありません。そこでこのページでは1気圧とは何か?また1気圧は何ヘクトパスカル(hPa)なのかを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次1気圧とは何か?1気圧は何ヘクトパスカル(hPa)?具体的に1気圧(1013hPa)はどのくらいの力なのか?なぜ人間は1気圧でつぶされないのか?1気圧=760mmHgと言われている理由についてまとめ1.1気圧とは何か?では1気圧とは何か見ていきましょう。1気圧とは、ふつう地上において大気によって発生する圧力の大きさのことを言います。簡単に言えば、私たちが普段から住んでいる場所における気圧の強さを表したものです。(上空や穴の深い場所でなければ、その場所での気圧の大きさは1気圧になります)1気圧は地上における大気によって発生する圧力の大きさのことで、大気とは空気のことなので空気によって発生する圧力の大きさになります。ではなぜ気圧が発生するのかというと空気は無色透明な気体ですが、空気自体には質量があってそこに存在しないわけではないからです。何もないところで(実際には空気がある)腕を回すと、腕に何かが当たる感覚がありますよね。あれは腕に空気が当たっている感覚になります。このように空気は目に見えないだけで、存在しています。そして気圧の大きさは上に乗っかっている空気の量で変化します。何にでも言えることですがモノを積み上げていくと上に存在しているモノには、あまり圧力はかかりませんが下に存在しているモノには大きな圧力がかかります。気圧もこれと同じで、地上における気圧の大きさである1気圧というのは、地上から上空までの空気が積み重なり、その重さによって発生した圧力のことなんですね。なので地上(1気圧)と比べると上空の気圧は小さくなります。上図のように上空では上に乗っかっている空気の量が少ないので気圧は小さくなり、穴が開いているような場所では空気の量が多くなるので気圧は1気圧よりも大きくなります。例えば富士山の頂上付近(3776m)では、気圧の大きさは約0.6気圧です。そして富士山よりさらに上に行くとどんどん空気が少なくなり、最終的には空気がない(真空状態)宇宙空間まで到達します。宇宙空間のように空気の存在しないところでは気圧は発生しないので、当然ですが気圧の大きさは0気圧になります。関連:気圧とは何かをわかりやすく解説!なぜ気圧で人はつぶされないのか?関連:空気とは何か?また高い場所ほど空気が薄くなる理由とは?2.1気圧は何ヘクトパスカル(hPa)?では1気圧は何ヘクトパスカル(hPa)なのか見ていきましょう。結論から言ってしまうと、1気圧=1013.25ヘクトパスカル(hPa)になります。ヘクト(h)というのは接頭語で、10の2乗(10^2)つまり100倍を表します。なので1気圧=1013.25[hPa]=101325[Pa]ということです。また1気圧の単位として”atm(アトム)”が使用されており、1気圧=1[atm]=1013.25[hPa]になるので覚えておきましょう。さて1気圧の強さが1013.25ヘクトパスカルということは分かりましたが、具体的にはどのくらいの力の大きさなのか解説していきますね。関連:単位の接頭語とは何か?単位の接頭語の種類について関連:なぜ単位は大文字と小文字で区別しなければいけなのか?具体的に1気圧(1013hPa)はどのくらいの力なのか?さて1気圧(約1013hPa)がどのくらいの力の大きさなのか見ていきましょう。まずパスカル(Pa)は圧力の単位のことで、以下のように単位変換することができます。<パスカル(Pa)の単位変換>1 [Pa] = 1 [N/m^2] = 1 [kg/m・s^2]※[N] = [kg/m・s^2]簡単に言えば圧力[Pa]とは単位面積[m^2]当たりにかかる力[N]のことで、1[m^2]の面積に対して1[N]の力がかかった場合の圧力が1[Pa]になります。1[N]の力がどのぐらいの大きさなのかは下図をご覧ください。上図のように1[N]は面積1[m^2]に対して102[g]の質量の物体に、地球の重力がかかった場合の重量(重さ)のことを表しています。(なぜ102[g]の質量の物体なのかは、長くなるので別の記事で詳しく解説します。)なので1気圧である101325[Pa](1013.25[hPa])の場合だと、面積1[m^2]に対して10335150[g]の質量の物体に重力がかかったときの力のことです。数字がとても大きいのでより簡単に直すと、1気圧は面積1[m^2]に対して、約10.34[t](トン)の質量の物体に重力がかかったときの力(重量)になるということ。1気圧がどれだけ大きな力なのか理解していただけたでしょうか。関連:重力加速度とは?仕組みを分かりやすく図解!関連:重力と重力加速度と重さ(重量)の違いとは?なぜ人間は1気圧でつぶされないのか?ではなぜ人間は気圧によってつぶされることはないのかというとそれは、人間の内部(体内)からも同じ大きさの気圧が外側に対して働いているからです。1気圧の大きさは面積1[m^2]に対して約10.34[t]の重量がかかります。そして成人における人間の体の平均の表面積は約1.6[m^2]です。ですので1.6[m^2]×10.34[t/m^2]=16.544[t]もの重量が体にかかっている計算になります。このままだと少しイメージしにくいと思うので、面積1[cm^2]当たりにかかる重量に直していきます。16544[kg] ÷ 16000[cm^2] = 1.034[kg/cm^2]16.544[t] = 16544[kg]1.6[m^2] = 16000[cm^2]面積1[cm^2]当たりに直すと、約1[kg]の重量がかかるわけです。しかし人間は呼吸などにより空気を体内に取り込むことで、内部からも外部と同じように1気圧がかかっています。これにより内部(体内)から外側に働く気圧と、外部(体外)から内側に働く気圧がお互いを打ち消しています。人間だけでなく地球上に存在しているモノが気圧につぶされることがないのは、そのモノの内部に空気が含まれていて外部からかかる気圧を打ち消しているからです。もし人間や他のモノの内部に空気が含まれていなければ、外部からかかる気圧(1気圧)につぶされてしまいます。3.1気圧=760mmHgと言われている理由についてではなぜ1気圧=760mmHgと言われるのか見ていきましょう。結論から言ってしまうと1気圧(1013hPa)の大きさが、水銀(液体)を上に760mm持ち上げるときの力の大きさと同じだからです。760mmHgの”Hg”は水銀の元素記号のことで読み方としては、「ミリメートルエイチジー」や「水銀柱ミリメートル」と呼ばれています。さて1気圧の大きさが水銀760mmを持ち上げる力の大きさと同じとは、いったいどういうことなのか下の図で解説していきます。上図のように水銀の表面には上から1気圧もの力がかけられていて、1気圧に押された水銀は容器の中で760mmの高さまで持ち上げられます。容器の中は真空(0気圧)なので水銀を持ち上げた力は、外の1気圧のみです。これにより1気圧=水銀を760mmの高さまで持ち上げる力ということが分かります。また容器の中が真空ではなく、元から空気が入っていれば水銀は持ち上がりません。(水銀の表面にただ空の容器をかぶせたのと同じ)上図のように容器の中には空気が入っているので、持ち上げようとする力と等しい力が容器の中からかかっている状態です。じゃあどうすれば水銀を気圧によって容器の中で持ち上げさせるのかというと、それは水銀の中に容器を沈めてその容器の中に空気が入らないように立たせます。容器が760mmよりも長ければ、水銀の位置は760mmのところまで下がり、その上部は真空となります。ちなみになぜ水銀なのかと言うと水銀(液体)の密度は常温・常圧で約13.6[g/cm^2]あり、水の密度が約1[g/cm^2]なので水銀は水の13.6倍も密度が大きいです。これは単純に水よりも水銀の方が13.6倍も重い液体ということになります。水銀は液体の中で最も密度の大きい液体として知られていて、水銀を使用することで持ち上がる高さをより抑えることができるんですね。これを水銀ではなく水で行えば密度が13.6倍も小さくなる(軽くなる)ので、水の高さが10m以上(760[mm]×13.6)になってしまいます。なので持ち上がる高さを抑えるために、水銀という密度の大きい物質が使用されています。関連:真空とは何か?分かりやすく図で解説!関連:密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?以上が「1気圧とは?また何ヘクトパスカル(hPa)なのか?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、1気圧とは、ふつう地上において大気(空気)によって発生する圧力の大きさのこと。1気圧は、1013.25ヘクトパスカル(hPa)のこと。1気圧は面積1[m^2]当たりに約10.34[t]もの力が働いている。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒気圧と大気圧の違いとは?⇒重力加速度とは?仕組みを分かりやすく図解!⇒気圧と沸点の関係について。気圧によって沸点が変化する仕組みとは?⇒加速度とは何か?単位の意味とともにわかりやすく解説!⇒質量とは?重量(重さ)との違いと単位について⇒密度が大きい(高い)・密度が小さい(低い)の意味を簡単に図解!⇒何桁の数字の意味とは?7桁の収入や3桁の収入はいくらを表している?⇒単位変換にはコツが必要?単位変換の簡単な考え方について⇒1リットルは何ミリリットル?1リットルは何デシリットル?単位(体積)の覚え方について⇒氷とドライアイスと液体窒素の違いとは?最も温度が低いのはどれ?