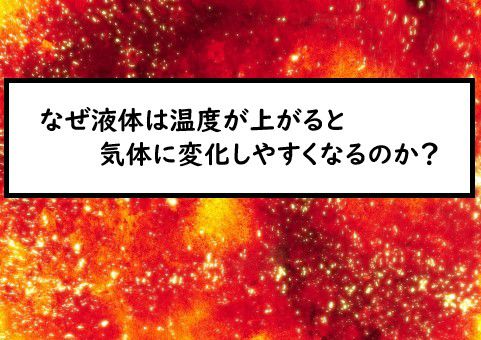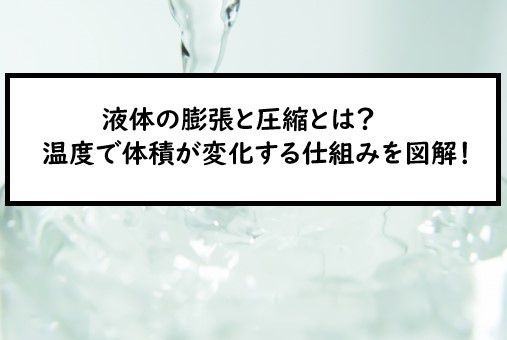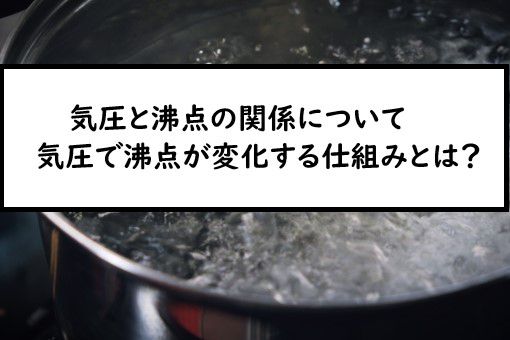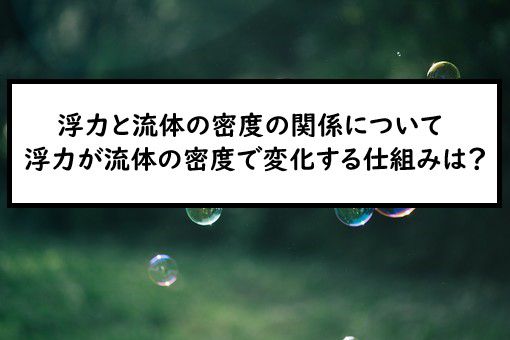さて水などの液体は火などで加熱したりすると少しずつ液体の温度が上がっていき、しばらくすると液体が気体に変化するということは知っていますよね。ですが意外と温度を上げることで液体が気体に変化しやすくなるのかを、しっかりと理解して解説できる人は少ないです。そこでこのページでは、なぜ液体は温度が上がると気体に変化しやすくなるのかを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次なぜ液体は温度が上がると気体に変化しやすくなるのか?(1)液体は分子という小さな粒で構成されている(2)液体の温度が変化すると分子の動きも変化する(3)液体が気体に変化するというのは分子が飛び出すということまとめ1.なぜ液体は温度が上がると気体に変化しやすくなるのか?ではなぜ液体は温度が上がると気体に変化しやすくなるのかを解説していきます。結論から言ってしまうと温度が上がることで液体が気体に変化しやすくなる理由は、液体の分子の動きが激しくなり、分子同士の繋がり(液体)から分子が飛び出しやすくなるからです。これだけでは何を言っているのか分からないと思うので、順を追って下の通りに少しずつ簡単に解説していきます。(1)液体は分子という小さな粒で構成されている(2)液体の温度が変化すると分子の動きも変化する(3)液体が気体に変化するというのは分子が飛び出すということでは順を追ってそれぞれを見ていきましょう。(1)液体は分子という小さな粒で構成されているまず液体は分子という小さな粒が集まって構成されています。分子の粒が集まって構成されているのは液体だけでなく、すべての物質(固体や気体)に対して言えることです。例えば上図のように水(液体)なら水分子が集まって構成されていて、空気(気体)なら空気分子が集まって構成されています。(2)液体の温度が変化すると分子の動きも変化する液体を構成している分子というのは常に動いて(振動して)いて、その分子の動きの激しさは温度が変化することで共に変化していきます。上図のように物質の分子の動きと温度の関係は、物質の温度が上がると分子の動きが激しくなり、反対に物質の温度が下がると分子の動きが穏やかになります。ちなみに厳密に言えば先に物質の温度が変化することで分子の動きが変わるのではなく、先に分子の動きが変わることでそれに伴いその物質の温度も変化していきます。関連:温度とは何か?物体の状態変化と温度の関係について解説!(3)液体が気体に変化するというのは分子が飛び出すということ液体が気体に変化するということは液体を構成する分子同士の繋がりから、その液体の分子が飛び出すということを意味しています。水(液体)が水蒸気(気体)に変化するのであれば、上図のように水を構成している水分子が水分子同士の繋がりから飛び出すということです。なので飛び出している水分子が水蒸気(気体)になるわけです。関連:状態変化とは何か?物質が状態変化する仕組みを簡単に図解!またイメージしてみて欲しいのですが、水分子同士の繋がりから飛び出すということは、その繋がりを切り離すためのエネルギー(力)が必要だということになります。例えば自分の身体が拘束されている状態だとして、その拘束から脱出するためには力で振りほどこうとしますよね。しかし力がなければその拘束を振りほどくことはできません。つまり簡単に言えば、分子同士の繋がりである液体から分子を飛び出させるには、分子に分子同士の繋がりを振りほどくための力が必要になります。そしてこの分子同士の繋がりから振りほどくための力というのが、液体の温度を上げて分子の動きを激しくさせるということなんですね。液体の温度が低い状態であれば分子の動きが穏やかなので、分子同士の繋がりから分子が飛び出すだけの力がありません。ですが液体の温度を上げていくことによって液体を構成する分子の動きが激しくなるので、分子同士の繋がりから分子が飛び出していくことが可能になります。ちなみに水(液体)は加熱したりすることで温度を上げなくても、少しずつ蒸発しているのはご存知でしょうか。(これは水以外の液体でも起こることです)なぜ温度を上げなくても水は蒸発するのか、その仕組みについては下記をご覧ください。関連:水が100度に達していないのに蒸発する仕組みとは?以上が「なぜ液体は温度が上がると気体に変化しやすくなるのか?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、温度を上げると液体が気体に変化しやすくなるのは、分子の動きを激しくなり、分子同士の繋がりから飛び出しやすくなるから。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒水を沸騰させると発生する泡の正体とは?またなぜ泡は発生するのか?⇒絶対熱とは何か?絶対熱の温度は何度あるのか?⇒流体とは何かをわかりやすく解説!圧力はどんなかかり方なのか?⇒なぜ熱は必ず温度が高い方から低い方へと移動するのか?⇒水垢とは何か?水道周りに白い塊ができる仕組みについて図解!⇒浮力とは何か?浮力の原理を簡単に図で解説!⇒熱対流とは何か?熱対流の仕組みをわかりやすく図で解説!⇒密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?⇒気圧とは何かをわかりやすく解説!なぜ気圧で人はつぶされないのか?⇒気圧と沸点の関係について。気圧によって沸点が変化する仕組みとは?
ギモン雑学
「 変化 」の検索結果
-
-
さてあなたは液体の膨張と圧縮についてご存知でしょうか。液体は温度が変化するとそれに伴って体積も変化するのですが、理解せずにただ暗記しているだけではすぐに忘れてしまいますよね。そこでこのページでは液体の膨張と圧縮とは何か?また温度によって液体の体積が変化する仕組みを図で解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次液体の膨張と圧縮とは?温度によって液体の体積が変化する仕組みについて(1)温度によって分子の運動の激しさが変化する(2)分子の運動の激しさで動く範囲(体積)が変化するまとめ1.液体の膨張と圧縮とは?では液体の膨張と圧縮とは何かを見ていきましょう。さっそくですが、液体の膨張とは液体の温度が上がることで体積が大きくなることで、液体の圧縮とは液体の温度が下がることで体積が小さくなることを言います。温度によって体積が変化(膨張・圧縮)するのは液体だけでなく、他の状態である気体や固体でも同じことが言えます。ただ温度によって体積が変化する程度にはその状態(気体・液体・固体)で差があり、体積変化(膨張・圧縮)が小さい順番に並べると”固体 < 液体 < 気体”のようになります。つまり温度変化によって最も体積が変化しやすい状態は”気体”ということです。また液体(気体・固体も)は温度変化によって体積が変化したとしても、その液体の質量は変わりません。質量が変わらずに体積だけが変化するため、”質量÷体積”で算出される密度が変化します。例えば冷たい水が重くなって、暖かい水が軽くなるというのは、水の温度が変化したことによってその水の密度も変化するから起こることなんですね。温度によって水の重さが変化する詳しい仕組みは下記をご覧ください。関連:暖かい水と冷たい水で重さが変わる仕組みとは?関連:密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?次の章でなぜ温度によって液体の膨張・圧縮が起こるのかを簡単に解説していきます。2.温度によって液体の体積が変化する仕組みについて結論から言ってしまうと温度によって液体の体積が変化するのは、液体の分子運動の激しさが変わることで、その分子の移動する範囲も変わるからです。まずどんな物質でも分子と呼ばれる小さな粒が集まって構成されていて、水であれば下のように水分子と呼ばれる小さな粒が集まって構成されています。ではこのことを踏まえたうえで、温度によって液体の体積が変化する仕組みを順番に解説していきます。(1)温度によって分子の運動の激しさが変化する液体はその液体分子が集まることで構成されていますが、その液体分子は常に動き回っています。そして液体分子の動きの激しさでその液体の温度が決まっており、液体分子の運動が激しければ温度が高く、液体分子の運動が穏やかであれば温度は低くなります。その液体が水であれば上図のようになります。ですので液体の温度が上がるということは液体分子の動きが激しく、反対に液体の温度が下がるということは液体分子の動きが穏やかだということになります。厳密に言えば物質の温度というのは、その物質を構成する分子運動によって決まるものなので注意してください。(このページでは関係なく記していますが特に気にしないでください)これは気体や固体の物質にも共通することなので、ぜひ覚えておいてください。関連:温度とは何か?物体の状態変化と温度の関係について解説!関連:絶対零度とは?また絶対零度の温度は何度なのか?(2)分子の運動の激しさで動く範囲(体積)が変化する液体の温度が上がれば分子の運動が激しくなり、反対に液体の温度が下がれば分子の運動が穏やかになります。そしてその液体の分子運動の激しさが変化することで、その分子が移動できる範囲も変わります。液体の温度が上がることで液体分子の動きが激しくなれば、エネルギーが大きくなるのでより広範囲に移動できるようになります。反対に液体の温度が下がることで液体分子の動きが穏やかになれば、エネルギーが小さくなるので動ける範囲は狭くなります。つまりこれが液体の温度が上がれば体積が大きく(膨張)なり、液体の温度が下がれば体積は小さく(圧縮)なるということです。ちなみに日常的に見かけることも多い液体温度計なんかは、液体の温度によって体積が変化する性質を利用して作られています。関連:液体温度計の仕組みを簡単に図解!なぜ水銀は使われなくなったのか?以上が「液体の膨張と圧縮とは?温度によって液体の体積が変化する仕組みを図解!」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、液体の膨張とは、液体の温度が上がることで体積が大きくなること。液体の圧縮とは、液体の温度が下がることで体積が小さくなること。温度によって液体の体積が変化するのは、液体の分子運動の激しさが変わることで、その分子の移動できる範囲も変わるから。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒熱と温度の違いとは?⇒なぜ熱は必ず温度が高い方から低い方へと移動するのか?⇒絶対熱とは何か?絶対熱の温度は何度あるのか?⇒なぜ標高が高い所は寒いのか?太陽との距離は関係ないって本当?⇒水が100度に達していないのに蒸発する仕組みとは?⇒流体とは何かをわかりやすく解説!圧力はどんなかかり方なのか?⇒熱対流とは何か?熱対流の仕組みをわかりやすく図で解説!⇒なぜ氷は空気中よりも水中の方が溶けやすいのか?⇒状態変化とは何か?物質が状態変化する仕組みを簡単に図解!⇒暖かい水と冷たい水で重さが変わる仕組みとは?
-
さて気圧と沸点にはとても密接な関係があるのを知っていますか?そして周囲の気圧が変化することで液体の沸点も変化しますが、なぜ気圧が変化すると沸点も変化するのでしょうか。意外に気圧と沸点の仕組みを理解できていない人も多いように感じます。そこでこのページでは気圧と沸点の関係について。また気圧によって沸点が変化する仕組みを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次気圧と沸点の関係について気圧によって沸点が変化する仕組みとは?水の温度は水分子の動きで決まる水から水蒸気に変わるときの分子の動き方気圧で水分子の出やすさが左右されるまとめ1.気圧と沸点の関係についてでは気圧と沸点の関係について見ていきましょう。まず結論から言うと気圧と沸点の関係は下記のようになります。周囲の気圧が低くなる ⇒ 沸点が低くなる周囲の気圧が高くなる ⇒ 沸点が高くなる沸点(ふってん)とは液体が沸騰するときの温度で、水の沸点が約100度というのはご存知だと思います。しかし水の沸点が100度というのは、あくまでも周囲の気圧の大きさが1気圧における場合です。1気圧というのは地上における気圧の大きさを表していて、高度が高くなればなるほど1気圧よりも低くなっていきます。目安として富士山(3776m)だと周囲の気圧の大きさは約0.6気圧になり、気圧の大きさが0.6気圧における水の沸点は約87度にまで下がります。なので水を熱して100度で沸騰するのは地上(1気圧)における場合のみで、周囲の気圧の大きさによって水(液体)が沸騰する温度は異なります。関連:1気圧とは?また何ヘクトパスカル(hPa)なのか?そして日常的に気圧と沸点の関係を利用したものに圧力鍋(圧力釜)があります。簡単に言えば圧力鍋というのは鍋の中の圧力を調整することで、より高温で食材を煮込んだりすることができる調理器具のことです。なぜ圧力鍋を使用すればより高温で食材を煮込むことができるのか?それは圧力鍋の中の気圧(圧力)が高くなるので、水が沸騰する温度が上がるため通常よりも高温で煮込むことが可能になるからです。水の沸点というのは周囲の気圧の大きさが1気圧であれば100度です。ということは周囲の気圧が1気圧なら水(液体)が100度で水蒸気(気体)になってしまうということです。加熱して煮込んでいくと少しずつ沸点に達した水分が水蒸気に変化していき、普通の鍋であればその水蒸気は鍋のふたの隙間から外へと出ていきますよね。ですが圧力鍋の場合は沸騰した水が水蒸気になっても、鍋の中がある程度の高圧にならない限り水蒸気が漏れない造りになっています。なので水蒸気がどんどんたまっていくことで鍋の中が水蒸気による気圧で圧力が高くなるため、沸騰しにくくなるので水の沸点が上がり通常よりも高温で煮込むことができるというわけです。このように気圧と沸点には密接な関係があるんですね。では気圧と沸点の関係についてはどういうものなのか理解していただけたかと思いますので、次の章で仕組みについて図を用いていきながら分かりやすく解説していきます。関連:圧力鍋とは何か?圧力鍋の仕組みをわかりやすく図解!2.気圧によって沸点が変化する仕組みとは?気圧によって沸点が変化する仕組みについて見ていきましょう。気圧によって沸点が変化するのは液体すべてに言えることですが、ここでは私たちに馴染みがある液体の水で解説していきます。結論から言ってしまうと気圧によって沸点が変化する仕組みは、空気中に存在する空気分子の量で、空気中への水分子の出やすさが変わるからです。どういうことなのか順番に解説していきます。水の温度は水分子の動きで決まるまず気圧によって沸点が変化する仕組みを理解するためには、物質(空気や水)が分子という小さい粒で構成されていると認識する必要があります。これによって水や空気は下図のようなイメージになります。上図のように枠の中に水分子や空気分子がたくさん存在することで、水(液体)や空気(気体)ができていると考えてください。そして分子というのは常に動いていて、分子の動きはその物質の温度に大きく関係しています。分子の動きが激しければその物質の温度は高くなり、分子の動きが穏やかであればその物質の温度は低くなります。このように物質の温度を決めているのは、その物質を構成している分子の動きによるものになります。関連:温度とは何か?物体の状態変化と温度の関係について解説!水(液体)から水蒸気(気体)に変わるときの分子の動き方次は水を加熱して沸騰させることで、水(液体)が水蒸気(気体)に変化するイメージについて見ていきましょう。水を加熱していくと少しずつ水の温度が上がっていきますが、それは水を構成している水分子の動きが激しくなっているということを意味します。また水(液体)でいる状態というのは、水分子が集合してお互いが繋がり合っている状態になります。そして加熱され水の温度が上がることで水分子の動きが激しくなってくると、その水分子同士の繋がりから外れる水分子が出てきます。上図のように加熱して水の温度を上げていくと水分子の動きが激しくなり、水分子同士の繋がりから外れるので空気中に水分子が飛び出てしまいます。簡単に言えば、水分子同士の繋がりから水分子が外れるということが、水(液体)から水蒸気(気体)に変化するってことなんですね。なので沸点というのは水だけに限らず液体がその液体分子の繋がりから、液体分子を空気中に放つために必要な動きの激しさを表している温度になります。関連:湯気と水蒸気の違いとは?気圧で水分子の出やすさが左右されるさてここが最も重要なポイントになります。まず物質の分子という観点から見てみると、周囲の気圧が変化することで一体何が変わるのでしょうか?それは空気中に存在している空気分子の量が変わります。一般的に周囲の気圧が高い状態というのは空気分子が多く存在している状態で、反対に気圧が低い状態というのは空気分子が少ない状態になります。だから山など高度の高いところでは、空気分子の量が少ない(空気が薄い)ので気圧が低くなるんですね。この空気中に存在している空気分子の量が変化することによって、水(液体)が水蒸気(気体)に変化し始める温度も変わるのです。では空気中に存在する空気分子の量が変化することで、水分子の出やすさにどのような違いがあるのか下図をご覧ください。このように存在する空気分子が少なければ簡単に水分子は飛び出せますが、空気中に存在する空気分子が多ければ水分子が空気中に出にくくなります。なので空気中に空気分子が多く存在しているほど、水分子が空気中に出るには大きなエネルギーが必要になります。そしてその大きなエネルギーというのが、加熱することで水分子の動きを激しくすることです。だから気圧が高い(空気分子が多い)ほど大きなエネルギーが必要になるので、水分子の動きを激しくするために液体の沸点が高くなります。関連:気圧とは何かをわかりやすく解説!なぜ気圧で人はつぶされないのか?以上が「気圧と沸点の関係について。気圧によって沸点が変化する仕組みとは?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、周囲の気圧が高ければ沸点も高くなり、気圧が低ければ沸点も低くなる。仕組みとしては、空気中の空気分子の量で水分子の出やすさが左右されるから。空気分子が多ければ、空気中に水分子が出やすくなる(水蒸気になりやすくなる)。空気分子が少なければ、空気中に水分子が出にくくなる(水蒸気になりにくくなる)。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒真空とは何か?分かりやすく図で解説!⇒状態変化とは何か?物質が状態変化する仕組みを簡単に図解!⇒山でお菓子の袋が膨らむ仕組みとは?分かりやすく図で解説!⇒空気の膨張とは何か?空気の温度によって体積が変化する仕組みとは?⇒気圧と大気圧の違いとは?⇒流体とは何かをわかりやすく解説!圧力はどんなかかり方なのか?⇒ピンポン玉のへこみの直し方とは?またへこみが直る仕組みについて⇒浮力とは何か?浮力の原理を簡単に図で解説!⇒ストローで飲み物を吸うことができる仕組みとは?⇒吸盤が壁にくっつく仕組みとは?
-
さて水の中に空のペットボトルを入れると、そのペットボトルは沈まずに水の上に浮かんできます。このときペットボトルに対して水から働いている力を”浮力”と言います。そして流体(水など)の密度によって、浮力の大きさは変化するのはご存知でしょうか。そこでこのページでは浮力と流体の密度の関係について。また流体の密度によって浮力が変化する仕組みを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次浮力と流体の密度の関係について流体の密度によって浮力が変化する仕組みとは?浮力とは流体の重さによって発生する圧力流体が重い(密度が大きい)ほど浮力は大きくなるまとめ1.浮力と流体の密度の関係についてでは浮力と流体の密度の関係について見ていきましょう。結論から言ってしまうと、浮力と流体の密度の関係は下のようになります。流体の密度が小さい(軽い) ⇒ 浮力は小さくなる流体の密度が大きい(重い) ⇒ 浮力は大きくなる流体というのは”液体と気体の総称のこと”で、空気や水も流体であると言えます。なかには浮力は水のときにだけ働く力だと思っている人も多いですが、実は空中にゴム風船が浮かぶのも空気による浮力が働いているからなんですね。流体(液体・気体)であれば水や空気以外でも浮力は働きます。関連:風船にヘリウムガスを入れると空中に浮く理由とは?関連:なぜ空中に浮く風船と浮かない風船があるのか?また上記の浮力と流体の密度の関係で”流体の密度が小さい・大きい”とあります。密度はどれだけ密に詰まっているかの度合いを表しているので、”密度が小さい”なら密に詰まっていない、”密度が大きい”なら密に詰まっているということです。つまり密度が小さい物質なら中身が密に詰まっていないので”軽く”、反対に密度が大きい物質なら中身が密に詰まっているので”重く”なります。そして流体の密度が小さければ(軽ければ)浮力は小さくなり、流体の密度が大きければ(重ければ)浮力は大きくなります。関連:浮力とは何か?浮力の原理を簡単に図で解説!関連:密度とは?比重との違いと単位について次の章で流体の密度によって浮力が変化する仕組みについて解説していきます。2.流体の密度によって浮力が変化する仕組みとは?では流体の密度によって浮力が変化する仕組みを見ていきましょう。さっそくですが流体の密度によって浮力が変化するのは、浮力そのものが流体の重さによって発生している力だからです。なので無重力の空間では浮力は発生しません。浮力とは流体の重さによって発生する圧力流体が重い(密度が大きい)ほど浮力は大きくなるさてこれだけでは理解するのが難しいと思うので、上記について順番に解説していきます。関連:重力と重力加速度と重さ(重量)の違いとは?浮力とは流体の重さによって発生する圧力浮力とは流体中において物体に対して、流体から上向きに働く力のことです。流体中においてどのように力がかかっているのかを図で示すと下のようになります。(容器内の丸いボールを流体だと仮定してください)流体中にかかる圧力というのは、その流体の重さによってかかっているので、容器内のボールの上層から順番にどのような向きの力がかかっているのかを見ていきます。まず上から1層目に存在するボールの重さによって、2層目に存在するボールに力が加わります。次に2層目のボールは横方向に力が流れ(1層目のボールの重さ分の力)、下方向(3層目)に1層目と2層目のボールの重さによる力が加えられます。また各方向へと力が流れていきますが、作用反作用の法則によってそれらの力とは逆向きの力も加わります。最終的に流体の重さによって発生する圧力の関係は上図のようになりますが、下方向だけではなく、あらゆる方向から流体による圧力がかかっているのが分かりますよね。このことから深い層になるにつれてボール同士に働く圧力は大きくなっていきます。例えば空気を入れて膨らませた風船を水中(流体中)に沈めていくと、風船に対して水から下図のような向きと強さの圧力がかかることになります。上図では風船に上からかかる圧力、下からかかる圧力、左右横からかかる圧力で分けています。水深が深くなるほど風船にかかる水からの圧力は大きくなっていくので、この中だと風船に下からかかる圧力が最も大きくなります。そして浮力というのは流体の重さによって発生する下方向からの圧力(つまり上向きの力)のことなので、この場合だと”浮力=風船の下からかかる圧力-風船の上から掛かる圧力”のことを指します。ですので数字で言うと、”浮力=7(下からの圧力)-3(上からの圧力)=4”ということになります。(左右横からかかる圧力は同じ大きさなので、横からの圧力は打ち消し合います)このとき水の上に物体が浮かぶのは”浮力>物体にかかる重力”となるからで、反対に”浮力<物体にかかる重力”となれば水の上には浮かばずに物体が沈んでいくことになります。関連:水圧とは何か?わかりやすく図を用いて解説!流体が重い(密度が大きい)ほど浮力は大きくなる流体が重い(密度が大きい)ほど浮力は大きくなり、反対に流体が軽い(密度が小さい)ほど浮力は小さくなります。先ほどの容器内にボールを積み上げた図を用いて解説していきます。上図の2層目と3層目ではそれよりも上層にある流体の重さが基準となって、周囲へと発生する流体による圧力の大きさが決まることになります。例えば上層にある流体が軽ければ”1”の圧力しか下層へとかかっていきませんが、上層にある流体が重いのであれば”10”の圧力が下層へとかかってしまいます。これを先ほどみたいな水の中に沈めた風船の図で表すと下のようになります。上図のように浮力はその流体の重さによって発生する下方向からの圧力のことなので、上層から下層へかかる流体による圧力が大きくなるほど、下方向からの力である浮力も大きくなります。だから流体が重い(密度が大きい)ほど、浮力というのは大きくなるんですね。ちなみにプールと海では海の方が体が浮きやすくなるというのがまさにこの理由からで、プールの水と海の水では海水の方が重い(密度が大きい)ために体が浮きやすくなっています。関連:なぜ真水(淡水)よりも海水の方が体がよく浮くのか?関連:暖かい水と冷たい水で重さが変わる仕組みとは?以上が「浮力と流体の密度の関係について。浮力が流体の密度で変化する仕組みとは?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、流体が軽い(密度が小さい)ほど、浮力は小さくなる。流体が重い(密度が大きい)ほど、浮力は大きくなる。流体の重さで浮力が変化するのは、浮力そのものが流体の重さによって発生している力だから。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒水圧と浮力の違いについて簡単に図で解説!⇒死海とは?死海の由来は?なぜ死海は他の海よりも浮くことができるのか?⇒密度が大きい(高い)・密度が小さい(低い)の意味を簡単に図解!⇒水温と浮力の関係について。水温によって浮力が変化する仕組みとは?⇒なぜ真水(淡水)よりも海水の方が体がよく浮くのか?⇒蒸気圧とは?水の沸点と蒸気圧の関係についてわかりやすく解説!⇒相対湿度と絶対湿度の違いとは?⇒結露とは何か?仕組みを分かりやすく図解!⇒熱気球とは?また熱気球はどんな原理で空中に浮いているのか?⇒水圧とは何か?わかりやすく図を用いて解説!
-
さてあなたは水温と浮力が関係しているということはご存知でしょうか。つまり水温が上がったり下がったりすることで、水から受ける浮力も変化するということです。そして水温によって浮力が変化する仕組みを知っている人は意外と少ないです。そこでこのページでは水温と浮力の関係について。また水温によって浮力が変化する仕組みを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次水温と浮力の関係について水温によって浮力が変化する仕組みとは?水温によって水の密度が変化する水の密度が変化すると浮力も変化するまとめ1.水温と浮力の関係についてでは水温と浮力の関係について見ていきましょう。結論から言ってしまうと、水温と浮力の関係は下のようになります。水温が4℃より高い ⇒ 水温が高いほど浮力は小さくなる(最高100℃まで)水温が4℃ ⇒ 浮力は最も大きくなる水温が4℃より低い ⇒ 水温が低いほど浮力は小さくなる(最低0℃まで)水温4℃のときが最も水から受ける浮力は大きくなり、水温4℃を境界として4℃より高くても低くなっても水からの浮力は小さくなります。水温が4℃よりも高い場合は100℃のときが最も浮力が小さくなり、水温が4℃よりも低い場合は0℃のときが最も浮力が小さくなります。これは水温が100℃以上になると水が沸騰して水蒸気(気体)に変化し、水温が0℃以下になると水が氷(固体)に変化し始めるからです。ちなみに水が100℃のとき沸騰して気体である水蒸気に変化し、0℃のとき固体である氷に変化し始めるというのは周囲の気圧が”1気圧”だからです。1気圧とは簡単に言えば、私たちが住んでいる地上における気圧の大きさのことで、周囲の気圧が1気圧でなければ水が水蒸気や氷に変化する温度も変わります。富士山などの頂上で水を沸騰させると、80℃~90℃ぐらいで沸騰する理由がまさにこれです。(1気圧では100℃で沸騰するが、富士山頂上の気圧は1気圧よりも低いため)関連:1気圧とは?また何ヘクトパスカル(hPa)なのか?関連:気圧と沸点の関係について。気圧によって沸点が変化する仕組みとは?次の章では水温によって浮力が変化する仕組みについて解説していきます。2.水温によって浮力が変化する仕組みとは?では水温によって浮力が変化する仕組みを見ていきましょう。さっそくですが水温によって浮力が変化する理由は、水温が変化することで水の密度が変化して、その水の密度変化に伴い浮力が変化するからです。浮力というのは流体(水や空気など)の重さによって発生している力なので、水温が変化して水の密度が変われば、それに伴って水からの浮力も変化することになります。簡単に水温によって浮力が変化する仕組みを解説しましたが、まだ分かりにくいだろうと思うので下記の2点について順番に詳しく解説していきます。水温によって水の密度が変化する水の密度が変化すると浮力も変化するさてそれぞれについて見ていきましょう。関連:流体とは何かをわかりやすく解説!圧力はどんなかかり方なのか?水温によって水の密度が変化する水の温度が上がるとその水の体積が大きく(膨張)なり、反対に水の温度が下がるとその水の体積は小さく(圧縮)なります。(このときその水の質量は変化せずに、体積だけが変化します)この水の体積変化に伴い、水の密度が変化します。(”密度[g/cm^3]=質量[g]/体積[cm^3]”なので、体積が変わると密度は変化します)上図のように水の温度が上がって体積が大きくなると密度は小さくなり、水の温度が下がって体積が小さくなると密度は大きくなります。関連:質量とは?重量(重さ)との違いと単位についてまた水の密度が大きくなるということはその水が”重くなる”ことと同じで、反対に水の密度が小さくなれば”軽くなる”ことと同じになります。普段から私たちが複数のモノの重さを判断するときには密度を用いています。例えばどんなに軽いモノでもそれをたくさん積み上げていくと、重いモノと同じ重さになるのでどちらが重いのか正確に判断ができなくなります。ですので軽いモノと重いモノを”同じ体積[cm^3]あたりの質量[g](つまり密度[g/cm^3])”で判断し、どちらのモノが重いのかを判断しています。水の質量が変化していないのにも関わらず、水の重さが変わるように感じるのは密度が変化したからです。このとき密度が大きいモノの方が重いモノで、密度が小さいモノの方が軽いモノとなります。関連:密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?関連:密度が大きい(高い)・密度が小さい(低い)の意味を簡単に図解!水の密度が変化すると浮力も変化する水温が上がると体積が膨張して密度が小さくなるのでその水は軽くなり、水温が下がると体積が圧縮して密度が大きくなるのでその水は重くなります。そして浮力はその流体の重さによって発生している力のことなので、水の密度が変化することによって浮力も変化していきます。まず水中の物体にかかる浮力のイメージは下図のようになります。上図のように流体中の物体には流体の重さによって発生した圧力があらゆる方向からかかり、その物体にかかる力の大きさは、流体中の深い場所ほど大きな力がかかります。(流体が水なら”水圧”がかかり、流体が空気なら”気圧”がかかる)上図でもあるように流体における浮力というのは、物体へとかかっている”下からかかる力ー上からかかる力”のことです。そうすると物体に下からかかる力の方が残るため、水などの流体に物体を沈めようとしても浮かんでくるんですね。(上からかかる力を引いたあとに残った物体に下からかかる力が”浮力”)なので浮力とは流体によって発生するあらゆる方向からかかる圧力のうち、下方向からかかっている圧力に限定したものを指しているんですね。では本題に入りますが、水温で水の密度が変化して重さが変わると、その変化した水の重さによって水中で物体にかかる力も変化していきます。水の重さが変化するということは”水によって下へとかかる力”が変化するということで、水の重さによって発生している浮力はその影響をそのまま受けることになります。つまりはこういうことです。上図のように水温が上がって軽くなった水は下へとかかる力(図では上)が弱くなり、反対に水温が下がって重くなった水は下へとかかる力が強くなります。(上図の数字は適当な値です)その水の重さによって発生した下へとかかる力が浮力にも影響するので、水温が上がると浮力は小さくなり、水温が下がると浮力は大きくなるというわけです。ただし水温が下がると浮力は大きくなると解説しましたが、水温4℃になると密度が最も大きく(重く)なるため、4℃より下がると浮力は小さくなっていきます。他の物質は温度が高くなるほど密度が小さくなっていき、温度が低くなるほど密度が大きくなっていくため、水は少し特殊な性質の物質です。上図のように水温4℃を境にして水温が上下するほど、浮力は小さくなります。浮力のイメージがまだ難しいと感じる人は、少し詳しく解説しているので下記をご覧ください。関連:浮力と流体の密度の関係について。流体の密度で浮力が変化する仕組みとは?以上が「水温と浮力の関係について。水温によって浮力が変化する仕組みとは?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、水温4℃のときが最も水の浮力は大きく、水温4℃を境にして浮力は小さくなっていく。水温4℃のときが水の密度が最も大きくなる(水は特殊な性質を持つ物質)。水温によって浮力が変化する仕組みは、水温が変化することで水の密度が変わるから。浮力は流体の重さによって発生する力なので、水の密度が大きく(重く)なると浮力も大きくなる。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒浮力とは何か?浮力の原理を簡単に図で解説!⇒単位の接頭語とは何か?単位の接頭語の種類について⇒なぜ氷は空気中よりも水中の方が溶けやすいのか?⇒水圧と浮力の違いについて簡単に図で解説!⇒液体の膨張と圧縮とは?温度によって液体の体積が変化する仕組みを図解!⇒氷とドライアイスと液体窒素の違いとは?最も温度が低いのはどれ?⇒なぜ真水(淡水)よりも海水の方が体がよく浮くのか?⇒死海とは?死海の由来は?なぜ死海は他の海よりも浮くことができるのか?⇒蒸気圧とは?水の沸点と蒸気圧の関係についてわかりやすく解説!⇒蒸気と水蒸気の違いとは?