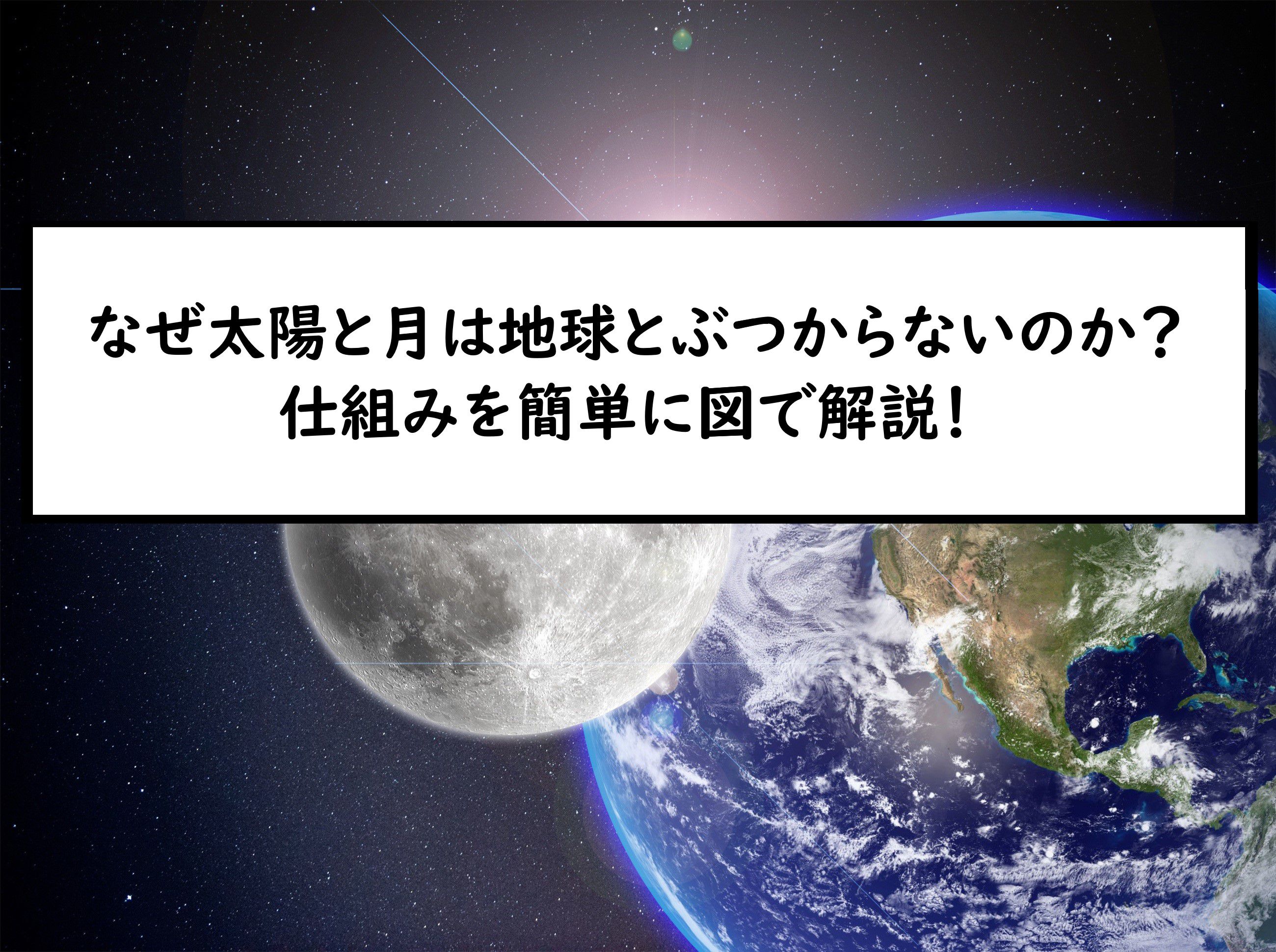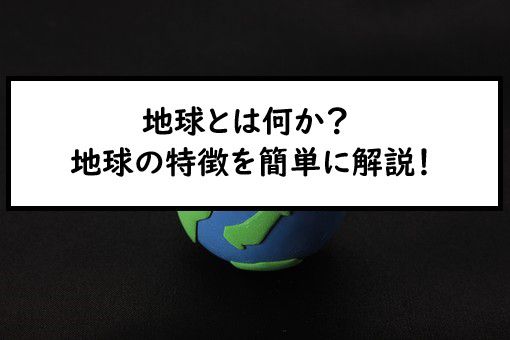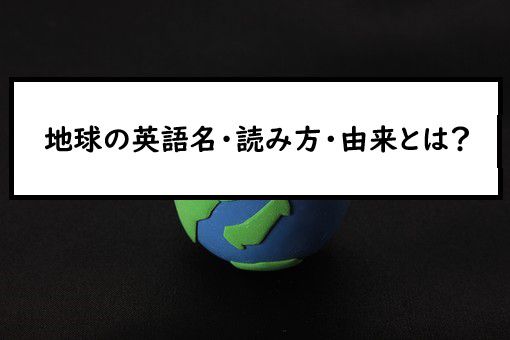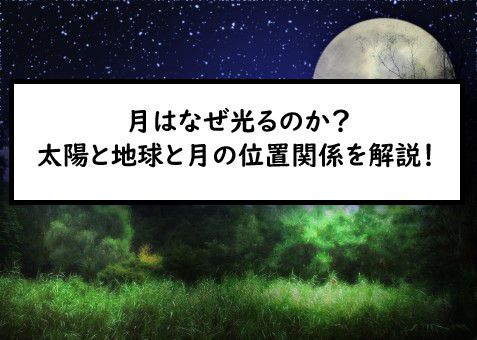さて「なぜ太陽と月は地球とぶつからないんだろう?」と思ったことはないでしょうか。太陽は地球よりも引力が大きく、月は地球よりも引力が小さいので、地球が太陽に引き寄せられたり、月を引き寄せたりすることも考えられますよね。しかし現実にそのようなことは起こっていません。そこでこのページでは、太陽と月が地球とぶつからない仕組みを簡単に図で解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次太陽と月が地球とぶつからない仕組みとは?太陽と地球の場合(太陽の引力のほうが大きい)月と地球の場合(地球の引力のほうが大きい)まとめ1.太陽と月が地球とぶつからない仕組みとは?では太陽と月がぶつからない仕組みについて見ていきましょう。結論から簡単に言ってしまうと、太陽と月が地球にぶつからないのは、”太陽の引力”と”地球の移動する力”、”月の移動する力”と”地球の引力”が釣り合っているからです。まず引力というのはその物体の質量が大きいほど比例して大きくなるので、太陽と月と地球における引力の関係を表すと下のようになります。太陽(地球の約28倍) > 地球 > 月(地球の1/6)上のようにこの中では太陽の質量が最も大きいため、太陽の引力が最も大きくなり、反対にこの中では月の質量が最も小さくなるため、月の引力が最も小さくなります。そうすると太陽は引力によって地球を吸い寄せてしまい、地球は引力によって月を引き寄せてしまうと考えてしまいますよね。ですが実は地球も月も(太陽も)移動しているので、その移動する力と引力がバランスを取っているためにぶつかりません。さて太陽と月と地球が移動している理由も含めて、ぶつからない仕組みをそれぞれ図で解説していきます。太陽と地球の場合(太陽の引力のほうが大きい)太陽と地球で考えた場合は、太陽の方が地球よりも約28倍引力が大きいので、太陽に地球が引き寄せられてぶつかってしまうと考えがちです。ですが地球が太陽に引き寄せられることはありません。それはなぜかというと、地球そのものに移動しようとする力が働いていて、その地球が移動しようとする力と太陽からの引力が釣り合っているからです。”地球の公転(こうてん)”というのは上図のような仕組みで起こっています。地球などの惑星というのは誕生するときにガスや固体状の物質が衝突して、集まることで誕生します。この惑星が誕生するときに物質同士が衝突した衝撃で、その惑星が移動する力が発生することになります。上図のように地球はたくさんの物質がぶつかり合って誕生し、そのぶつかったときの衝撃が移動する力として地球には残っています。地球上であれば地球からの重力や空気抵抗などがモノに働くことで、そのモノの速度が減速したり、止まったりすることになりますよね。ですが宇宙空間ではその移動する力を止める力が外部から働かないため、地球などの惑星が移動しようとすれば、ずっと同じ速度で移動し続けます。そして地球のその移動し続ける力は、太陽の引力の影響によって拘束されることになります。(太陽の引力で拘束されはしますが、移動する力と釣り合うため完全には引き寄せられない)これはちょうど下図のようにボールにひもを付けて、投げて回したときのイメージです。地球上であれば地球からの重力や空気抵抗で少しずつ減速していきますが、宇宙空間であれば減速せずに進んでいくため、そのようにイメージしてください。上図のようにボールを投げたとしても、ひもから引っ張られる力があることで、ボールは拘束されてしまい重りの周囲を回転することになります。ただしボールを投げる力が強すぎれば、ひもからボールが離れて飛んでいき、反対にボールを投げる力が弱すぎれば、少しずつ重りの方へとボールが近づいていきますよね。太陽と地球の関係も同じで、地球が移動する力が強すぎれば太陽の引力から解放され飛んでいき、反対に地球の移動する力が弱くなれば太陽の引力によって引き寄せられてしまいます。実際にはこのようなことは起こらないとは思いますが、太陽と地球がぶつからない仕組みはこんな感じになります。関連:空気抵抗とは?なぜ物体の速度が上がると空気抵抗は大きくなるのか?月と地球の場合(地球の引力のほうが大きい)月と地球の場合も太陽と地球の場合と考え方は同じです。月と地球の場合では地球の方が引力が大きくなるので、”太陽と地球の場合”で解説したときの太陽の役割が地球に代わるだけです。また月は平均して1年あたり4cmずつ、地球から離れていることが分かっています。これは月の引力が潮の満ち引きを起こすことによるもので、満潮や干潮という現象も月の引力によって発生しています。(詳しい仕組みについては他のページで解説します)1年間あたりで4cm離れるので、いずれ((数億年後、数十億年後))は地球の引力の拘束から離れて、月が地球の空から見えなくなるという可能性もあるようです。以上が「なぜ太陽と月は地球とぶつからないのか?仕組みを簡単に図で解説!」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、太陽と地球がぶつからないのは、”太陽の引力”と”地球が移動する力”がバランスをとっているから。月と地球がぶつからないのは、”月が移動する力”と”地球の引力”がバランスをとっているから。”月が移動する力”と”地球の引力”はピッタリ釣り合っているわけではなく、1年間あたり約3cmずつ地球から月が遠ざかっている。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒銀河と銀河系と太陽系の違いとは?⇒光年とは何かをわかりやすく解説!1光年の距離はどのくらい?⇒新月と満月の違いとは?なぜ新月は昼に、満月は夜にしか出ないの?⇒月はなぜ光るのか?太陽と地球と月の位置関係をわかりやすく図で解説!⇒太陽系とは何かをわかりやすく図で解説!⇒なぜ月の公転周期と月の満ち欠けの周期がずれるのかを簡単に図で解説!⇒なぜ朝が来ると明るくなって、夜が来ると暗くなるのか?⇒なぜ太陽は東から昇って、西に沈むのか?⇒なぜ赤道では重力が小さく、北極・南極では重力が大きくなるのか?⇒月の満ち欠けの仕組みとは?月の満ち欠けの名称を簡単に図で解説!
ギモン雑学
「 地球 」の検索結果
-
-
さて”地球”とは私たち人間が暮らしている天体のことで、太陽系惑星を表す「すいきんちかもくどってんかい」というフレーズにも出てきます。私たちは当然のように地球で日常生活を送っていますが、地球とはどのような天体なのかを知らない人も多いですよね。そこでこのページでは、地球の表面温度・大気・重力などの特徴を解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次地球の特徴について構成物質と大気とは?地球ができたのはいつごろ?地球と呼ばれる由来とは?地球における1日と1年についてなぜ自転しているのか?地球の衛星についてまとめ1.地球の特徴についてでは地球の特徴について見ていきましょう。地球とは太陽系の惑星において、3番目に太陽に近い惑星のことです。そんな地球の特徴について、それぞれ簡単にまとめたものが下のようになります。項目地球の特徴英語名Earth(アース)表面温度-90℃~70℃(平均温度15℃)大気空気(主に窒素・酸素)質量5.976×10^24 kg大きさ(半径)6.378×10^3 km気圧1気圧地球1周の長さ約4万km太陽からの平均距離1億4960万km自転周期約1日(約24時間)公転周期約365日項目1項目2)★ -->次の章から地球について詳しく解説していきます。2.構成物質と大気とは?では地球を構成している物質と大気について見ていきましょう。まず地球を構成している物質は下のようになります。上図のように地球の地殻・マントル部分は主に岩石で構成され、核の部分には鉄・ニッケルなどの金属で構成されています。上に宇宙から見たときの地球の写真がありますが、青く見える部分は”水”で、白く見える部分は”雲や雪(氷)”になります。また地球の大気は主に窒素・酸素から構成され、それ以外にもわずかにアルゴン・二酸化炭素・水蒸気などの物質が含まれています。地球の大気は別名で”空気”と呼ばれており、私たちが地球で生活するためにかかせないものとなっています。そして地球以外の惑星で、空気のように人間が呼吸できる大気は確認されていません。ちなみに空気に含まれる水蒸気と言うのは、日常的に湿度[%]として表されていて、湿度については下記で詳しく解説しているので、どうぞご覧ください。関連:空気とは何か?高い場所ほど空気が薄くなる理由とは?関連:湿度とは何か?湿度100パーセントとはどんな状態のこと?3.地球ができたのはいつごろ?地球が誕生したのはいまから約46億年前だとされています。(宇宙が始まったとされているのは約100億年ほど前)他の小さな天体が何度も衝突することで合体して地球は誕生しており、それから長い期間を経て、いま現在における地球となっています。衝突した天体の中には金属・岩石・水・二酸化炭素など様々な物質が含まれ、衝突したときに発生した熱によって水は水蒸気に変化しました。地球が誕生したときの頃の大気はメタン・アンモニア・二酸化炭素などで構成され、人間が生きるために必要な酸素は含まれていませんでした。天体との衝突によって発生した熱はこの厚い大気のせいで内部にたまり、地表の温度は1000℃以上に達してしまいます。(温度上昇は二酸化炭素などの温室効果によるもの)それからしばらくして天体との衝突の回数も少なくなってきて、地表の温度が下がり始めたことで、大気中の水蒸気が雲になりました。その雲から激しい雨が何万年も降り続けて、その雨水が海になったと言われています。そして海の中に生物が誕生して、その生物が大気中の二酸化炭素を取り込み酸素を作り出すようになったことで、地上にも植物が誕生しました。さらに地上で植物が光合成を行い、地球内部で酸素を生成してくれていたことで、地球の大気は私たちが呼吸できる”空気”として存在しているわけなんですね。関連:雪と雨とは?雪と雨が降る仕組みを分かりやすく図解!4.地球と呼ばれる由来とは?では地球と呼ばれる由来について見ていきましょう。地球と呼ばれている由来は、大地という概念と地球が球体(丸い)であることからきています。地球はかなり昔から「球体ではないのか?」と推測はされていましたが、地球が球体であるということは証明されていませんでした。実際に地球が球体であることが証明されたのは1520年頃で、マゼランとエルカーノが世界一周したことによって証明されています。その後に”大地”と”球体”という概念から、”地球”と名付けられました。そして実は”地球”という言葉は日本で誕生した言葉ではなく、中国で誕生した言葉で、中国から伝わってそれが日本でも使われるようになりました。幕末から明治あたりに中国から日本へと伝わり、それから少しずつ”地球”という言葉が定着していきます。なので中国語でも同じ意味で”地球”という単語は使われています。また地球を英語で読む場合は”Earth(アース)”ですが、これはドイツ語の”Erde(エルデ)”からきています。ドイツ語の”Erde(エルデ)”から古代中世英語の”Erthe(エルセ)”ときて、そのあとに英語で”Earth(アース)”と読まれるようになりました。なので”Erde(エルデ)⇒Erthe(エルセ)⇒Earth(アース)”となったんですね。ドイツ語の”Erde(エルデ)”にはもともと”大地”の意味があり、いまでは地球の意味としても使われています。5.地球における1日と1年についてでは地球における1日と1年について見ていきましょう。地球における1日というのは地球が自転することで太陽光の当たり方が変わり、それにより地球における時間帯(朝・昼・夜)が変化することで起こります。上図のように地球は自転と言って反時計回りに回転しているので、時間が経過すると太陽光が当たる地球の面も変化していきます。これが地球における1日(時間帯の変化)が起こる簡単な仕組みです。関連:なぜ太陽は東から昇って、西に沈むのか?そして地球における1年というのは、地球が太陽の周りを1周する時間のことを指しています。そしてうるう年という1年が366日になる年が存在していますが、あれは地球が太陽の周りを1周する時間がぴったり365日ではないために設けられています。うるう年の詳しい仕組みや細かいルールについては下記をご覧ください。関連:うるう年(閏年)とは?4年に1度だけ366日になる仕組みを解説!6.なぜ自転しているのか?では地球はなぜ反時計回りに自転しているのか見ていきましょう。これはなぜかというと、地球が誕生したときに発生した運動エネルギーが残っているからです。地球が誕生したときというのは、他の天体が衝突し合って集まったことでできているため、そのときに他の天体がぶつかった衝撃で地球に回転する力が働いています。上図のように天体がぶつかるときは同じ速度、同じ質量のものがぶつかるわけではないので、ぶつかったときには必ずどちらかに力の偏りができてしまいます。その力の偏りがいまでも地球の自転(回転)と言う形で残っているんですね。またなぜ地球の回転速度が時間を経過してもほとんど変わらないのかと言うと、それは宇宙には地球内部と違って抵抗となるものがないからです。地球の中でボールを投げて時間が経つと動きが遅くなったり、地面に落下します。これは地球内部ではそのボールに地球からの重力が働いていたり、空気が存在しているので空気抵抗があるために動きが遅くなってしまいます。ですが宇宙にはそのような物質はほとんどないので、抵抗もほとんど発生しません。太陽からの引力によって引き寄せられはしますが、それは地球の公転という形で保っています。(詳しい仕組みは下記の関連ページからご覧ください)ですので地球の自転の速度がほとんど変わらないんですね。関連:空気抵抗とは?なぜ物体の速度が上がると空気抵抗は大きくなるのか?関連:なぜ太陽と月は地球とぶつからないのか?仕組みを簡単に図で解説!7.地球の衛星についてでは地球の衛星について見ていきましょう。衛星(えいせい)とは、惑星の周りを公転している天体のことで、地球の衛星と言えば誰もが知っている”月”のことを指しています。月は地球の唯一の衛星で、地球からの引力によって拘束されています。月の重力の大きさは地球と比べて6分の1ほどの大きさで、地球で体重が60kgの人は、月では体重が10kgほどになってしまいます。なので月に行くと体が軽く感じてしまうんですね。また太陽からの引力によって地球が太陽の周りを公転しているように、月もまた地球からの引力によって地球の周りを公転しています。地球が太陽の周りを1周するのにかかる時間は約365日で、月が地球の周りを1周するのにかかる時間は約27日かかります。地球が太陽の周りを回ることを”地球の公転”、月が地球の周りを回ることを”月の公転”と言います。ちなみに地球から月が満ちたり、欠けたりして見えるのは、月と地球と太陽の位置関係が大きく関係しています。月の満ち欠けが起こる仕組みについて、詳しくは下記をご覧ください。関連:月の満ち欠けの仕組みとは?月の満ち欠けの名称を簡単に図で解説!以上が「地球とは?地球の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});8.まとめこれまで説明したことをまとめますと、<地球の特徴>英語名は、Earth(アース)。地球の由来は、”大地”という概念と”球体”であることからきている。地球の英語名(アース)の由来は、ドイツ語の”Erde(エルデ)”からきている。表面温度は-90℃~70℃(平均温度15℃)。大気は主に窒素・酸素で構成されている(空気のこと)。地球の1日の長さは約24時間で、1年は約365日ほど。”月”は地球における唯一の衛星。月の重力は地球の約6分の1(言い換えれば、地球の重力は月の6倍ほど)。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒水星とは?水星の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!⇒月とは何か?月の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!⇒銀河と銀河系と太陽系の違いとは?⇒月はなぜ光るのか?太陽と地球と月の位置関係をわかりやすく図で解説!⇒「すいきんちかもくどってんかい」とは何の順番を表している?⇒なぜ太陽は東から昇って、西に沈むのか?⇒光年とは何かをわかりやすく解説!1光年の距離はどのくらい?⇒なぜ太陽と月は地球とぶつからないのか?仕組みを簡単に図で解説!⇒太陽系とは何かをわかりやすく図で解説!⇒重力加速度とは?仕組みを分かりやすく図解!
-
さて私たちは地球で生活しているということは誰でも知っています。地球は太陽系に属している8つの惑星のうちのひとつですが、実際に地球の英語名やその由来を知らない人も多いですよね。そこでこのページでは、地球の英語名・読み方・由来について簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次地球の英語名・読み方・由来とは?まとめ1.地球の英語名・読み方・由来とは?では地球の英語名・読み方・由来について見ていきましょう。まず地球(ちきゅう)の英語名は”Earth(アース)”と言い、由来は大地という概念と地球が球体(丸い)であることからきています。地球はかなり昔から「球体ではないのか?」と推測はされていましたが、地球が球体であるということは証明されていませんでした。実際に地球が球体であることが証明されたのは1520年頃で、マゼランとエルカーノが世界一周したことによって証明されています。その後に”大地”と”球体”という概念から、”地球”と名付けられました。そして実は”地球”という言葉は日本で誕生した言葉ではなく、中国で誕生した言葉で、中国から伝わってそれが日本でも使われるようになりました。幕末から明治あたりに中国から日本へと伝わり、それから少しずつ”地球”という言葉が日本で定着していきます。なので中国語でも同じ意味で”地球”という単語は使われています。また地球を英語で読む場合は”Earth(アース)”ですが、これはドイツ語の”Erde(エルデ)”からきています。ドイツ語の”Erde(エルデ)”から古代中世英語の”Erthe(エルセ)”ときて、そのあとに英語で”Earth(アース)”と読まれるようになりました。なので”Erde(エルデ)⇒Erthe(エルセ)⇒Earth(アース)”となったんですね。ドイツ語の”Erde(エルデ)”にはもともと”大地”の意味があり、いまでは地球の意味としても使われています。ちなみに太陽系惑星の中において、英語名で神の名前が由来とされていないのは”地球だけ”です。関連:地球とは?地球の表面温度・大気・衛星などの特徴を簡単に解説!以上が「地球の英語名・読み方・由来とは?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、地球の英語名・読み方は、”Earth(アース)”。地球の由来は、”大地”という概念と”球体”であることからきている。地球の英語名が”Earth(アース)”なのは、ドイツ語の”Erde(エルデ)”からきている。太陽系惑星の中において、英語名で神の名前が由来とされていないのは”地球だけ”。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒太陽系惑星の英語名・読み方・由来の簡単なまとめ!⇒光年とは何かをわかりやすく解説!1光年の距離はどのくらい?⇒銀河と銀河系と太陽系の違いとは?⇒月はなぜ光るのか?太陽と地球と月の位置関係をわかりやすく図で解説!⇒月齢とは?月齢と月の満ち欠けの関係をわかりやすく図で解説!⇒なぜ太陽は東から昇って、西に沈むのか?⇒土星とは?土星の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!⇒なぜ太陽と月は地球とぶつからないのか?仕組みを簡単に図で解説!⇒太陽系とは何かをわかりやすく図で解説!⇒重力加速度とは?仕組みを分かりやすく図解!
-
さてあなたは月がなぜ光るのか、その理由をご存知でしょうか。月が光るのは太陽と地球と月の位置が大きく関係していますが、これをしっかりと理解している人は少ないように感じます。そこでこのページでは月はなぜ光るのか?また太陽と地球と月の位置関係をわかりやすく図で解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次月はなぜ光るのか?太陽と地球と月の位置関係をわかりやすく図で解説!まとめ1.月はなぜ光るのか?では月はなぜ光るのかを見ていきましょう。結論から言って、月はなぜ光るのかというと、月が太陽の光を反射して、その反射した光が地球へと届いているからです。なので月そのものが光を発しているわけではなくて、月が太陽の光を反射することで月が光っているように見えるというわけです。月の光はもともとは太陽の光なんですね。関連:新月と満月の違いとは?なぜ新月は昼に、満月は夜にしか出ないの?2.太陽と地球と月の位置関係をわかりやすく図で解説!前の章で月がなぜ光るのか、その仕組みについては簡単に解説しましたが、太陽と地球と月がどのような位置関係にあるのか分からないといまいちイメージしにくいですよね。さっそくですが、太陽と地球と月の位置関係を下図に表します。上図のように地球は太陽の周りを約365日かけて1周(地球の公転)して、月は地球の周りを約27日かけて1周(月の公転)しています。ですので上図では月と太陽に地球が挟まれているようにはなっていますが、月は地球の周りを移動しているため、そのときによって月と地球の位置関係は変わります。月と太陽で地球を挟む位置に来るときもあれば、上図のように月と地球の位置関係が反対になることもあります。またこのように月が地球の周りを移動することによって起こるのが、”月の満ち欠け”です。月が地球の周りを移動すれば当然ですが、地球から見える月の部分も変わり、それによって地球から月が光って見える部分も変わるので月の満ち欠けは起こります。月の満ち欠けの仕組みについて詳しくは下記をご覧ください。関連:月の満ち欠けの仕組みとは?月の満ち欠けの名称を簡単に図で解説!以上が「月はなぜ光るのか?太陽と地球と月の位置関係をわかりやすく図で解説!」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、月が光る理由は、月が太陽の光を反射して、その反射した光が地球へと届いているから。太陽と地球と月の位置関係は、月が地球の周りを移動しているので変化する。月が地球の周りを移動することによって起こるのが、”月の満ち欠け”である。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒銀河と銀河系と太陽系の違いとは?⇒なぜ三日月は夜に見えないのか?その仕組みを簡単に図で解説!⇒朔と新月の違いとは何か?⇒新月と満月の違いとは?なぜ新月は昼に、満月は夜にしか出ないの?⇒月齢とは?月齢と月の満ち欠けの関係をわかりやすく図で解説!⇒なぜ月の公転周期と月の満ち欠けの周期がずれるのかを簡単に図で解説!⇒なぜ朝が来ると明るくなって、夜が来ると暗くなるのか?⇒なぜ太陽は東から昇って、西に沈むのか?⇒太陽系とは何かをわかりやすく図で解説!⇒上弦の月と下弦の月の違いと見分け方とは?どんな形の月をしている?