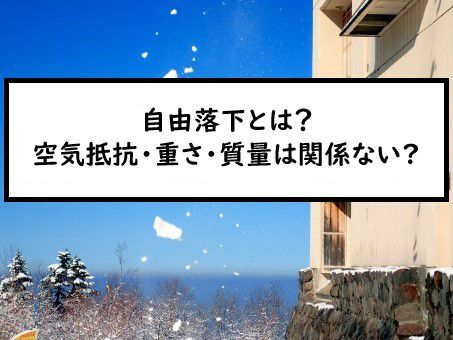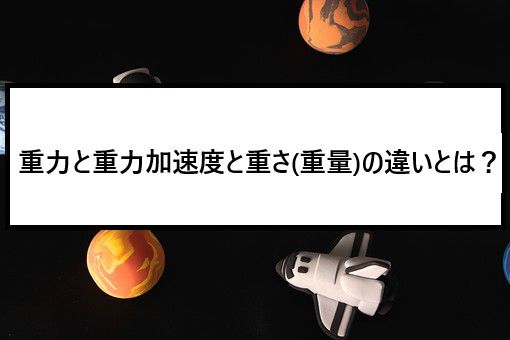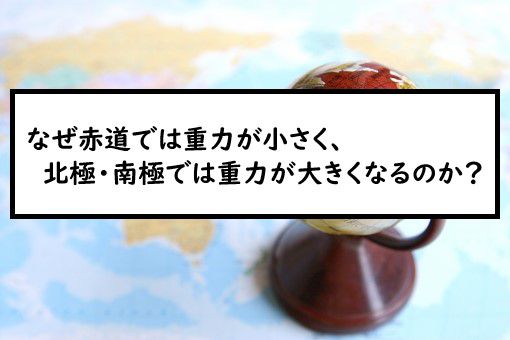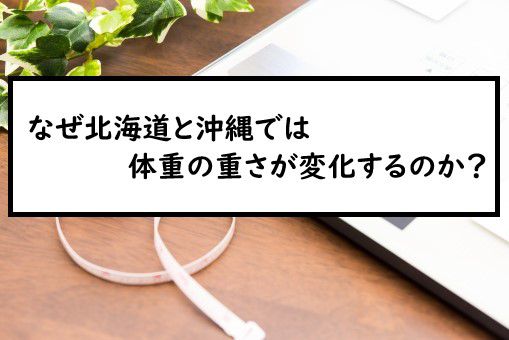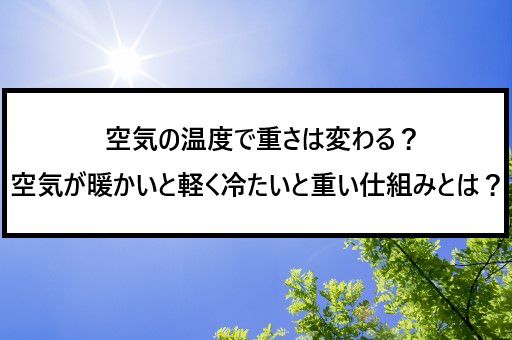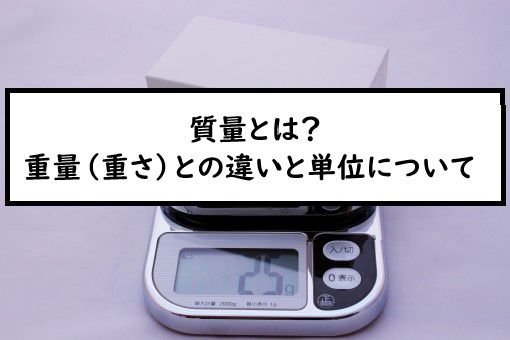さてあなたは物体の”自由落下”とは何かをご存知でしょうか。自由落下という言葉からも何となく分かりますが、この言葉は物体が落下するときのある条件を示している言葉になります。物理を勉強している人ならどういうものなのか分かるかもしれませんが、過去に勉強していてもすでに忘れてしまっている人もいますよね。そこでこのページでは自由落下とは何か?また物体の空気抵抗・重さ・質量は関係ないのかを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次自由落下とは何か?自由落下に物体の空気抵抗・重さ・質量は関係ないのか?真空中では物体の質量に関係なく落下速度は同じ空気抵抗があると質量によって落下速度が変化するまとめ1.自由落下とは何か?では自由落下とは何かを見ていきましょう。結論から言ってしまうと自由落下(じゆうらっか)とは、物体が空気抵抗などの影響を受けずに、重力の働きのみで落下する現象のことです。ですので物体が落下するその周囲に空気が存在していれば、物体に空気抵抗や空気による摩擦が発生することになるため自由落下にはなりません。つまり自由落下とは、真空中において物体が落下する現象と言えます。落下する物体の周囲に空気などの物質が存在していれば、それだけで落下する物体に少なからず影響が生じてしまいます。また自由落下させるときは落下させる物体に重力以外の力を加えてはいけないので、手で投げたりして物体に力を加えてしまうと自由落下ではなくなるので注意が必要です。ちなみに厳密に言えば真空は空気だけでなく、物質(空気も含む)がほとんど存在しない空間のことで、その空間に空気だけがなければ真空になると思っている人も多いので覚えておいてください。(このサイトでは簡単に”真空=空気がない空間”と書いているので注意してください)関連:真空とは何か?分かりやすく図で解説!関連:空気抵抗とは?なぜ物体の速度が上がると空気抵抗は大きくなるのか?次の章で自由落下に物体の空気抵抗・重さ・質量は関係ないのかを解説していきます。2.自由落下に物体の空気抵抗・重さ・質量は関係ないのか?では自由落下に物体の空気抵抗・重さ・質量は関係ない(影響しない)のかを見ていきましょう。結論から言うと、自由落下において空気抵抗・重さ・質量はどれも関係ありません。先ほども解説しているように、空気抵抗については初めから除外されます。(そもそも空気抵抗があれば、”自由落下”ということにはならないからです)そして自由落下において物体の重さと質量に違いがあっても、その物体が落下する速度に影響が生じることはありません。つまり自由落下では、重い物体と軽い物体はどちらも同じ速度で落下するということになります。質量と重さの違いについて詳しくは下記をご覧ください。関連:質量とは?重量(重さ)との違いと単位について真空中では物体の質量に関係なく落下速度は同じ真空中では物体の質量に関係なく、自由落下する物体の速度は同じになります。(ここでは簡単に”真空=空気がない空間”としています)例えば真空中で質量10[kg]の物体と質量1[g]の物体の落下速度を比較した場合、これら異なる質量の2つの物体を自由落下させるとどっちが速く落ちるでしょうか。普通の感覚で言えば、質量10[kg]の物体のほうが速く落ちると思いますよね。しかし正解は、”これら2つの物体は同じ速度で落下する”になります。上図のように質量10[kg]の物体と質量1[g]の物体は、落下速度が同じなので同時に底に着きます。このように自由落下(真空中における物体の落下現象)では、その物体の質量に関係なく落下する際の物体の速度は同じになります。空気抵抗があると質量によって落下速度が変化する空気抵抗が発生する(空気がある)ので自由落下とは関係ありませんが、空気抵抗があると質量によって物体の落下速度が変化することについて解説していきます。まず私たちが日常的に感じている重い物体ほど速く落下して、軽い物体ほど遅く落下するというのは空気抵抗が主な原因になります。様々な物体に質量があるように、空気にも質量が存在します。空気抵抗というのは簡単に言えば、他の物体が空気にぶつかることで、その物体の進行方向と逆向きの力が働くことを言います。イメージするなら自分が大きなボールに突っ込んで行ったとして、自分がボールとぶつかるとその衝撃でボールに押し返されます。このときボールを空気とした場合、ボールから押し返される力(進行方向と逆向きの力)がいわば空気抵抗になります。ですので落下する物体にはこの進行方向と逆向きに働く力である空気抵抗が働くため、落下する物体の進行方向(下向き)と空気抵抗は逆向き(上向き)に働きます。そして質量が大きい(重い)物体ほど空気抵抗によって受ける影響が少なくなり、反対に質量が小さい(軽い)物体ほど空気抵抗による影響を受けやすくなります。なので上図のように空気抵抗があるときは質量が大きい(重い)物体は落下速度が速くなり、反対に質量が小さい(軽い)物体は落下速度が遅くなってしまうんですね。これが私たちが日常的に感じている物体の落下速度に違いが生じる仕組みになります。何度も言いますが、自由落下(真空中)だと異なる質量の物体が落下しても、途中で落下する物体に反発する空気が存在しない(空気抵抗がない)ので落下速度は変化しません。このように自由落下でない場合は空気抵抗を受けるため質量によって落下速度が変化しますが、自由落下の場合であれば空気抵抗・重さ・質量は落下速度に関係ないので覚えておきましょう。以上が「自由落下とは?空気抵抗・重さ・質量は関係ないのかを簡単に解説!」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、自由落下とは、重力の働きだけで物体が落下する現象のことを指す(つまり真空中における場合のこと)。自由落下の場合、空気抵抗・重さ・質量は落下速度に関係ない。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒震源と震央の違いとは?簡単に図で解説!⇒加速度とは何か?単位の意味とともにわかりやすく解説!⇒地表と地面と地上の違いとは?⇒重力加速度とは?仕組みを分かりやすく図解!⇒路面と地面の違いとは?⇒重力と重力加速度と重さ(重量)の違いとは?⇒なぜ太陽と月は地球とぶつからないのか?仕組みを簡単に図で解説!
ギモン雑学
「 重さ 」の検索結果
-
-
さて重力と重力加速度と重さ(重量)についてご存知でしょうか。これらは地球上で暮らしている私たちにとって密接に関係しているものですが、どういうものなのかを質問されると答えられないですよね。このように世の中には私たちの生活に大きく関係しているけれど、実は違いについて答えられないようなことがとても多く存在しています。そこでこのページでは、重力と重力加速度と重さ(重量)の違いについて簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次重力と重力加速度と重さ(重量)の違いについて重力とは?重力加速度とは?重さ(重量)とは?まとめ1.重力と重力加速度と重さ(重量)の違いについてでは重力と重力加速度と重さ(重量)の違いについて見ていきましょう。まずそれぞれについて簡単に見ていきましょう。重力とは、地球上の物体が地球の中心に引っ張られる力のこと。重力加速度とは、物体に重力がかかることによって発生する加速度のこと。重さ(重量)とは、物体に働く重力の大きさのこと。さて重力と重力加速度と重さ(重量)について詳しく解説していきます。重力とは?重力(じゅうりょく)とは、地球上の物体が地球の中心に引っ張られる力のことです。重力は地球上に存在している物体には必ず働く力で、物体だけでなく私たち人間に対しても重力が働いています。上図のように地球の中心に引き寄せられる力が働くので、丸い形をしている地球の上でも立っていられるんですね。無重力空間という言葉を聞いたことがある人も多いと思いますが、宇宙のような重力が存在しない空間のことを指しています。宇宙のような無重力空間では重力が存在していないので、引き寄せられる力が働かず一回ジャンプするとそのまま上へと飛んでいってしまいます。地球ではジャンプしてもすぐに地面へと落ちていきますが、それは地球からの重力が働いているからです。ジャンプだけでなくボールを投げたり、雲から雨が降ってきたりするのも、すべては物体に重力という地球の中心に引き寄せられる力が働いているからになります。関連:なぜ太陽と月は地球とぶつからないのか?仕組みを簡単に図で解説!重力加速度とは?重力加速度とは、物体に重力がかかることによって発生する加速度のことです。例えば高いところから物体を落下させると(重力以外の力を加えない)、落下し始めた直後よりも少し時間が経過してからの方が物体の落下速度は上がります。つまり重力によって引き寄せられた(落下した)物体が加速していくということです。このように重力が働くことで物体が加速する度合いのことを重力加速度と言います。(地球の重力加速度=9.8[m/s^2]になります)重力加速度の詳しい解説については下記をご覧ください。関連:重力加速度とは?仕組みを分かりやすく図解!重さ(重量)とは?重さ(重量)とは、物体に働く重力の大きさのことです。重さ(重量)[N]=質量[kg]×重力加速度[m/s^2]上のように重さ(重量)は質量と重力加速度を掛けることで求めることができ、重さの単位には[N](ニュートン)が使われています。重さ[N]と質量[kg]を混同している人も多いので注意してください。関連:質量とは?重量(重さ)との違いと単位についてまた中には重力=重さ(重量)だと誤解している人もいるため、有名な実験を元に重力と重さが同じではないということを解説していきます。まずもし重力=重さであるなら質量が大きい物体ほど速く落下することになります。(重さ[N]を求める式に、質量の大きい物体と小さい物体で計算すると分かります)重さ[N]が大きければそれだけ物体の落下速度が上がるのは普通だと思っている人も多いでしょう。そこでこの実験です。実験の内容としては大きな容器内を真空(空気がない状態)にして、上から質量の異なる2つの物体を同時に落下させるというものです。なぜ容器内を真空状態にするのかというと、落下させるときに物体に働く力を重力のみにしなければいけないからです。容器内に空気が存在していれば空気抵抗が発生するので、物体に重力以外の力が発生してしまい重力と重さの関係が調べられなくなります。さてそれぞれの物体を同時に落下させると一体どうなるでしょうか?正解は、どちらも同じ速度で落ちて同時に底に着きます。この実験には物体の質量と重力による影響しか与えられていないため、もし重力=重さになるのであれば単純に質量10[kg]のほうが速く落下するはずですよね。ですが実際は重さが異なるそれぞれの物体は同じ速度で落下して同時に底に着いたので、この実験から重力が重さと同じではないということが証明されました。ちなみに地球上で重いものほど速く落下し、軽いものほど遅く落下するのは、地球に空気が存在していて落下するものに対して空気抵抗が発生しているからです。関連:真空とは何か?分かりやすく図で解説!関連:空気抵抗とは?なぜ物体の速度が上がると空気抵抗は大きくなるのか?以上が「重力と重力加速度と重さ(重量)の違いとは?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、重力とは、地球上の物体が地球の中心に引っ張られる力のこと。重力加速度とは、物体に重力がかかることによって発生する加速度のこと。重さ(重量)とは物体に働く重力の大きさのことで、質量に重力加速度を掛けることで求められる。重力と重さ(重量)は同じものではない。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒引力と重力の違いとは?⇒なぜ赤道では重力が小さく、北極・南極では重力が大きくなるのか?⇒なぜ北海道と沖縄では体重の重さが変化するのか?⇒マグニチュードと震度の違いとは?分かりやすく図を用いて解説!⇒震源と震央の違いとは?簡単に図で解説!⇒密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?⇒自由落下とは?空気抵抗・重さ・質量は関係ないのかを簡単に解説!⇒空気の温度で重さは変わる?暖かい空気は軽く冷たい空気が重い仕組みとは?⇒浮力とは何か?浮力の原理を簡単に図で解説!⇒加速度とは何か?単位の意味とともにわかりやすく解説!
-
さてあなたは同じ地球上でも場所によっては、物体に働く重力が少し異なってしまうということはご存知でしょうか。赤道と北極・南極ではだいたい0.5%ほどの違いがあって、赤道付近の方が重力が小さくなり、北極・南極付近の方が重力が小さくなります。そこでこのページでは、なぜ赤道では重力が小さく、北極・南極では重力が大きくなるのかを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次なぜ赤道では重力が小さく、北極・南極では重力が大きくなるのか?赤道と北極・南極で体重を比べると変化する?まとめ1.なぜ赤道では重力が小さく、北極・南極では重力が大きくなるのか?ではなぜ赤道付近では重力が小さく、北極・南極付近では重力が大きくなるのかを見ていきましょう。理由を結論から言ってしまうと、赤道の方が北極・南極よりも物体にかかる遠心力が大きいからです。どういうことなのか、順番に詳しく解説していきますね。まず地球は反時計回りに自転(1日に1回転)していて、地球上に存在している物体には外側へと遠心力が働くことになります。上図のように重力と言うのは引力と遠心力を合わせた力のことなので、引力が10で、遠心力が1だとすると”引力10-遠心力1=重力9”となります。引力と重力の違いについて詳しくは下記をご覧ください。関連:引力と重力の違いとは?そして遠心力は回転の中心(軸)から距離が遠いほど大きくなり、反対に回転する中心から距離が近ければ遠心力は小さくなります。例えば遊びで使うコマを回してみると、遠心力の大きさは下のようになります。上図のようにコマの回転の中心(軸)から遠いほど遠心力は大きくなり、反対に回転の中心に近いほど遠心力が小さくなっているのが分かりますよね。地球における重力をコマと同様に考えていくと分かりやすいです。地球は北極から南極を結んだ直線を回転(自転)の軸にしていて、その直線と直角な平面になるものが”赤道”と呼ばれています。コマと同様に考え地球における①・②・③の地点それぞれの遠心力を見てみると、北極(回転の中心)に近いほど遠心力は小さくなり、反対に北極から遠くなれば遠心力は大きくなります。南極の場合も北極と同じで、南極(回転の中心)に近い地点ほど遠心力は小さくなります。また引力・遠心力・重力の大きさを適当な数字で見てみると下のようになります。上図のように回転の中心である北極(または南極)に近づくにつれて、遠心力は小さくなっていくため、それにより引力から差し引かれる値が小さくなり重力は大きくなります。その地点が北極・南極にピンポイントな地点であれば、回転の中心に存在するということになり、その地点で働く遠心力はゼロです。なので北極・南極では引力の大きさが、そのまま重力の大きさになります。これが赤道では重力が小さくなり、北極・南極では重力が大きくなる理由です。ちなみに上で表している数字で引力の大きさを”すべて10”としていますが、実際には引力の大きさは地球の中心からの距離で変化します。例えば高地や低地のように地球の中心からの距離が変わる場所もあるので、引力の大きさには多少の誤差があり、地球上であれば引力がすべて同じになるわけではありません。2.赤道と北極・南極で体重を比べると変化する?では赤道と北極・南極では体重が変化するのかを解説します。結論から言ってしまうと、赤道と北極・南極ではそれぞれ体重が約0.5%ほど変化します。冒頭でも触れていましたが、赤道と北極・南極では重力の大きさが約0.5%ほど異なります。北極・南極の方が赤道よりも重力が大きいので、北極・南極の方が約0.5%ほど重力が大きいことになります。重さは”その物体が持っている質量に重力がかけられたときの値”で、体重というのはその人間の持っている質量に重力がかけられた値です。なので重力が変化すれば、当然ですが体重も同じように変化することになります。上図のように北極・南極で体重が60kgだった人は、赤道で体重を測ると約59.7kgに減ってしまうんですね。(60kgの0.5%だと、300gしか重さは変わらない)このように赤道か北極・南極かで体重は変化します。日本でも北海道と沖縄で体重を測ると、重力の違いで異なる値になるとされていますが、体重計によってその地域の重力の設定がされているので変わらない場合も多いです。北極・南極に距離的に近いのは北海道の方なので、同じ体重計であれば北海道の方が体重は重くなります。関連:重力と重力加速度と重さ(重量)の違いとは?以上が「なぜ赤道では重力が小さく、北極・南極では重力が大きくなるのか?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、赤道では重力が小さく、北極・南極では重力が大きい理由は、赤道の方が北極・南極よりも物体にかかる遠心力が大きいから。北極・南極の方が赤道よりも重力が約0.5%大きくなり、北極・南極で体重を測る方が赤道よりも約0.5%分増える。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒重力加速度とは?仕組みを分かりやすく図解!⇒光年とは何かをわかりやすく解説!1光年の距離はどのくらい?⇒なぜ北海道と沖縄では体重の重さが変化するのか?⇒水星とは?水星の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!⇒銀河と銀河系と太陽系の違いとは?⇒なぜ金星の1日の長さは自転周期に比べて短くなるのか?⇒「すいきんちかもくどってんかい」とは何の順番を表している?⇒なぜ朝が来ると明るくなって、夜が来ると暗くなるのか?⇒太陽系とは何かをわかりやすく図で解説!⇒なぜ太陽と月は地球とぶつからないのか?仕組みを簡単に図で解説!
-
さてあなたは北海道と沖縄で体重を測ると、北海道の方が体重が重くなるという話を聞いたことがないでしょうか。そこまで大きく体重が変化するわけではないですが、この話については事実です。そこでこのページでは、なぜ北海道と沖縄では体重の重さが変化するのかを解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次なぜ北海道と沖縄では体重の重さが変化するのか?なぜ場所によって重力の大きさは変わる?北海道と沖縄ではどのくらい重さは変わる?まとめ1.なぜ北海道と沖縄では体重の重さが変化するのか?ではなぜ北海道と沖縄では体重の重さが変化するのかを解説します。結論から言ってしまうと、北海道と沖縄で体重が変化するのは、北海道と沖縄では重力の大きさがわずかに異なるからです。体重はその人が持っている質量に重力がかけられた値のことを表し、その人が受ける重力の大きさが変化すれば、体重の値も変化することになります。北海道では沖縄よりも重力が少し大きいために体重が重くなり、沖縄では北海道よりも重力が少し小さいために体重が軽くなります。また日本では北海道が最も重力が大きく、沖縄に向かうほど重力は小さくなっていきます。ではそもそもなぜ場所によって重力の大きさが変わるのか、その仕組みを簡単に解説していきます。関連:質量とは?重量(重さ)との違いと単位についてなぜ場所によって重力の大きさは変わる?場所によって重力の大きさが変わってしまう理由は、地球の自転で発生する遠心力の大きさが場所によって異なるからです。まず重力というのは、引力と地球の自転によって発生した遠心力を合わせた力のことで、引力と重力と遠心力の関係を簡単に図で表すと下のようになります。上図のように地球の自転によって発生する遠心力の大きさが1だとして、引力を10とすると引力から遠心力を差し引いた値9が重力の大きさとなります。そして遠心力の大きさはどの場所でも同じというわけではなく、この遠心力の大きさの違いが北海道や沖縄の重力の違いに繋がっています。遠心力と言うのは回転の中心から距離が遠いほど大きくなり、回転の中心から距離が近ければそれだけ小さくなります。地球で言えば下のようになります。上図のように遠心力は回転の中心(北極)から遠いほど大きくなり、反対に回転の中心に近づくほど小さくなっていることが分かりますよね。つまり北極・南極(回転の中心)に近い地域ほど重力は大きくなり、赤道に近い地域ほど重力は小さくなるということです。上図は適当な数字で引力・重力・遠心力を表したもので、北極(回転の中心)に近いほど重力は大きくなり、遠いほど重力は小さくなっています。もうお分かりかと思いますが、北海道と沖縄で重力に違いが生じるのはこれによるもので、北海道の方が沖縄よりも北極(回転の中心)に近いです。ですので北海道の方が重力は大きく(遠心力は小さく)なり、沖縄の方が重力は小さく(遠心力は大きい)なるというわけなんですね。さて北海道と沖縄で重力が変化する仕組みは解説しましたが、次の章で北海道と沖縄ではどのくらい重さが変化するのかを解説していきます。2.北海道と沖縄ではどのくらい重さは変わる?では北海道と沖縄でどのくらい重さは変化するのかを見ていきましょう。まず北海道の札幌での重力加速度は9.805[m/s^2]で、沖縄の那覇での重力加速度は9.791[m/s^2]となります。重力加速度とは重力がかかったときの物体の加速度のことで、よく重力の大きさを判断するのに用いられています。重力加速度の値が大きいほど、重力が大きいということを意味しているので、北海道と沖縄の場合は、北海道の方が重力は大きいということが分かります。この北海道と沖縄の重力加速度から、それぞれでかかる重力がどのくらい異なるのかを計算します。上のように北海道を基準とした場合には”0.9986倍”で、沖縄を基準とした場合には”1.0014倍”ということになりました。あとは先ほど求めた値を用いて、どのくらい重さが変化するのかを計算していきます。例えば北海道で100[kg]のモノだと沖縄では99.86[kg](140[g]減る)で、沖縄で100[kg]のモノだと北海道では100.14[kg](140[g]増える)になります。北海道と沖縄における重力の差によって、物体の重さには上のような差が生じます。関連:重力加速度とは?仕組みを分かりやすく図解!以上が「なぜ北海道と沖縄では体重の重さが変化するのか?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、北海道と沖縄では遠心力の大きさが異なるため、それにより重力に差が生じる。この重力の差によって北海道と沖縄では体重の重さが変化する。北海道で100[kg]のモノは沖縄では99.86[kg]に減り、沖縄で100[kg]のモノは北海道では100.14[kg]に増える。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒引力と重力の違いとは?⇒重力と重力加速度と重さ(重量)の違いとは?⇒光年とは何かをわかりやすく解説!1光年の距離はどのくらい?⇒なぜ赤道では重力が小さく、北極・南極では重力が大きくなるのか?⇒銀河と銀河系と太陽系の違いとは?⇒なぜ金星の1日の長さは自転周期に比べて短くなるのか?⇒「すいきんちかもくどってんかい」とは何の順番を表している?⇒なぜ朝が来ると明るくなって、夜が来ると暗くなるのか?⇒太陽系とは何かをわかりやすく図で解説!⇒なぜ太陽と月は地球とぶつからないのか?仕組みを簡単に図で解説!
-
さて暖かい空気が軽くなって、冷たい空気は重くなるという話を聞いたことがないでしょうか。これが本当なら空気は温度によって重さが変化することになりますが、本当に空気は温度で重さが変わるのでしょうか?そしてなぜ暖かい空気が軽くなって冷たい空気は重くなるのか、その仕組みを知りたいと疑問に感じている人も多いはずです。そこでこのページでは空気の温度で重さは変わるのか?また暖かい空気が軽くなり、冷たい空気が重くなる仕組みを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次空気の温度で重さは変わるのか?どちらが重いのかは密度で判断する暖かい空気が上昇して空気が下降する仕組みまとめ1.空気の温度で重さは変わるのか?では空気の温度で重さは変わるのかどうか見ていきましょう。結論から言ってしまうと、空気の温度が変化しても空気自体の重さは変わりません。まず空気というのは温度によって膨張・圧縮します。空気が膨張・圧縮するということは簡単に言えば、空気の体積が大きくなったり(膨張)小さくなったり(圧縮)するということです。上の図は空気の温度と体積・重さの関係をそれぞれ表したものです。このように空気を冷やしたり暖めたりすることで、空気自体の体積は変化しますが重さは変わりません。なので空気の体積が大きくなっても小さくなっても、もとの空気の重さと同じままなんですね。暖かい空気は軽くなるから上昇して、冷たい空気は重くなるから下降するというような話をよく聞きますよね。確かに暖かい空気は上昇して、冷たい空気が下降するというのは事実です。しかし空気を暖めても冷やしても空気自体の重さは変わりません。では空気を暖めると上昇して、冷やすと下降する理由は何なのでしょうか?それは、空気の温度が変化することで、その空気の密度が変わるからです。関連:密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?次の章でどちらが重いのかは密度で判断するについて解説していきますね。2.どちらが重いのかは密度で判断するではどちらが重いのかを考えるときに密度が重要になる理由を説明していきます。まず密度(みつど)というのは、体積当たりの重さのことを言います。例えば1kgの金と1kgの綿(わた)があります。この金と綿を比較したときどちらの方が重さがあるでしょうか?正解は、金も綿も同じ重さです。どちらも1kgなのですから重さは同じに決まっています。ですが綿よりも金の方が重いイメージってありますよね。そしてこれについて考えるうえで重要になってくるのが”密度”です。この例みたいに綿のようにどんなに軽いものでも、量を積み重ねていけばいくらでも重さを増やすことが可能です。そうすれば何が軽くて何が重いのか判断することが難しくなりますよね?だから重さを比較するときはそれぞれの物体の密度、つまり同じ体積当たりの重さで考えなければならないということです。このようにそれぞれの物体の密度で考えることでどちらが重いのかが判断できるようになります。軽い重いというのはその時点で何かを基準にしていて、その基準と比較することで軽いか重いかを判断しています。体重が軽くなったというときは以前の体重と比較していて、空気を暖めたら軽くなったというときは暖める前の状態の空気と比較しています。空気自体の重さは変わっていないのに軽くなった重くなったと表現することで、その物体の重さが変化したんだなと勘違いしてしまうこともよくあります。なのでそこには物体の重さが関係しているようにも思えるのですが、実際にどちらが重いのかを比較する場合は物体の重さよりも密度が重要になるので覚えておきましょう。関連:質量とは?重量(重さ)との違いと単位についてまた暖かい空気は上昇して冷たい空気は下降していきますが、空気自体が無色透明の気体なのでイメージするのが難しいですよね。そこで次の章で図を用いてその仕組みを分かりやすく解説していきます。3.暖かい空気が上昇して冷たい空気が下降する仕組みまず暖かい空気は重さは変わらず膨張するので密度は大きくなり、冷たい空気は重さは変わらず圧縮するので密度は小さくなります。暖かい空気のほうが通常の空気よりも密度が小さくなるから軽くなって、冷たい空気のほうが通常の空気よりも密度が大きくなるから重くなります。これは先ほど説明した内容です。では暖かい空気が上昇して、冷たい空気が下降する仕組みについて図を用いて解説していきます。さっそく結論から言ってしまうと、暖かい空気が上昇して冷たい空気が下降する仕組みは、冷たくて重い空気が暖かくて軽い空気を押しのけるからなんですね。これは水の中にモノを沈めたときのことを考えるとイメージしやすくなります。水も空気と同じように流体です。関連:流体とは何かをわかりやすく解説!圧力はどんなかかり方なのか?モノには水に沈むモノと水に沈まないモノがあります。水に沈むモノと沈まないモノの違いは密度の大きさです。上の図のように水よりも密度が大きいものであれば沈み、水よりも密度の小さいものであれば水の上に浮かびます。そして暖かく軽い空気が上昇して、冷たく重い空気が下降する仕組みも水と同じように考えてみてください。冷たい空気の方が暖かい空気よりも密度が大きくて重いので、上に存在していた冷たい空気が暖かい空気を押しのけて下降していきます。なので暖かい空気と冷たい空気を簡単に表すのなら、冷たい空気の上に暖かい空気が乗っかっているような状態です。このようにイメージしてみると、暖かい空気が上昇して冷たい空気が下降する仕組みが理解しやすくなるのではないでしょうか。ちなみに空中に風船が浮かぶのもこれと同じ仕組みです。風船の中に入っている気体が空気よりも密度の小さい気体なので、空気のほうが密度が大きく重いため風船を押しのけて空気がどんどん下へ下へと入っていきます。これによって風船が浮かんでいます。なので風船が空中に浮かんでいるというのは、風船が空気の上に乗っかっているようなイメージになります。関連:熱気球とは?また熱気球はどんな原理で空中に浮いているのか?関連:暖かい水と冷たい水で重さが変わる仕組みとは?以上が「空気の温度で重さは変わる?暖かい空気は軽く冷たい空気が重い仕組みとは?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、温度によって空気の重さ自体は変化しないが、空気の密度については変化する。どちらが重いのか軽いのかは、それぞれの物体の密度で判断すること。冷たい空気は密度が大きく重いため、暖かい空気を押しのけて下に入り込んでいく。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒空気の膨張とは何か?空気の温度によって体積が変化する仕組みとは?⇒断熱膨張とは?また断熱圧縮とは?どんな原理で温度変化するのか?⇒結露とは何か?仕組みを分かりやすく図解!⇒気温と温度と室温の違いとは?⇒熱と温度の違いとは?⇒絶対熱とは何か?絶対熱の温度は何度あるのか?⇒自由落下とは?空気抵抗・重さ・質量は関係ないのかを簡単に解説!⇒真空とは何か?分かりやすく図で解説!⇒なぜ標高が高い所は寒いのか?太陽との距離は関係ないって本当?⇒熱の伝わり方の3種類(伝導・対流・放射)を分かりやすく図で解説!
-
さて質量と重量という言葉をご存知でしょうか。質量と重量はほとんど同じ意味として使用されていますが、実はこれらの言葉は意味が似ているようで違います。そしてほとんどの人は質量と重量の違いを理解していないように感じます。そこでこのページでは、質量と重量の違いと単位について簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次質量と重量の違いについて質量とは?重量とは?まとめ1.質量と重量の違いについてでは質量と重量の違いについて見ていきましょう。結論から言ってしまうと質量と重量の違いは、物体そのものの量なのか、物体に働く重力の大きさなのかです。質量は物体そのものの量のことなので重力によって値が変化することはないですが、重量は物体に働く重力の大きさのことなので重力の大きさによって値が変化します。そして質量の単位には[g]や[kg]が使用され、重量の単位には[N](ニュートン)が使われます。また”質量=m”、”地球の重力=g”とした場合、”重量=mg”で表されます(単位ではなく記号です)。さて質量と重量それぞれについて詳しく解説していきますね。関連:単位の接頭語とは何か?単位の接頭語の種類について関連:なぜ単位は大文字と小文字で区別しなければいけなのか?質量とは?質量(しつりょう)とは、物体そのものの量のことです。質量は物体そのものの量のことなので、重力の大きさが変わっても質量が変化することはありません。質量の単位には[g]や[kg]が使用されています。私たちは普段から体重計で自分の体重を測定していますが、そもそも体重というのは体の重さではなく体の質量のことです。体重計に表示されている単位は[kg]ですよね(質量の単位は[g]や[kg])。なので体重計で測定しているのは体の質量なんですね。(つまり重力がかかっていない体そのものの量のこと)普通に測定すれば体の質量ではなく重量(重力がかかった値)が出てくるはずですが、一体どのようにして体重計では質量の値を出しているのでしょうか。それは簡単なことで、体の重量を測定してから質量に戻して表示しているんですね。上図のように体重計の中では体の重量を一旦測定したあとに、測定した体の重量から地球の重力gを割ることで質量に戻して表示しています。だから普段から私たちが見ている体重計に表示される値は質量[kg]になります。また学生の頃に実験をしていると思いますが、分銅(ふんどう)と上皿天秤を用いることで物体の質量を測定することができます。分銅には1[g]・2[g]・10[g]・50[g]・100[g]のように様々なものがありますが、分銅の何[g]が示しているのは重量ではなく質量のことです。ですので分銅に書かれている何[g]という値は、重力がかかっていない値になります。例えば600[g]の分銅を上皿天秤の片方の皿の上に置いて、別の皿の上に何かしらの物体を置いて釣り合えばその物体の質量は600[g]ということです。上図のように物体と分銅それぞれに地球からの重力はかかりますが、両方の質量が同じであれば重力がかかっていても関係ありません。初めから分銅の質量が分かっているため同じだけの重力がかかっても、もう片方の天秤の皿と釣り合えば質量は同じになるということです。ちなみに上皿天秤と分銅を用いれば、地球以外の重力のところでも物体の質量を測定することができます。よく例として挙げられるのは月ですね。月は地球に比べて重力の大きさが約1/6です。質量は重量とは違って重力による影響を受けないので、先ほどの質量が600[g]の物体も地球のときと同じように600[g]の分銅と釣り合います。なので質量600[g]の物体は地球でも月でも重力が変わろうと、質量が600[g]ということは変わらないというわけです。関連:重力加速度とは?仕組みを分かりやすく図解!重量とは?重量(じゅうりょう)とは、物体に働く重力の大きさのことです。(重さという言葉も重量と同じ意味です。)重量は物体に働く重力の大きさのことで、重力の大きさが変われば重量もそれに伴い変化します。重量の単位には[N](ニュートン)が使用されています。以前は重量の単位に[kgf]や[kgw]が使用されていましたが、いま現在では重量の単位には[N]を使用するよう決められています。先ほど地球と月で重力の大きさが変わっても物体の質量は変化しないと言いましたが、物体の重量(重さ)についてはその場所の重力の影響を受けます。なので地球ではある物体の重量が600[N]であったとしても、月では地球の重力の約1/6しかないのでその物体の重量は100[N]になってしまいます。このように重量[N]はその場所における重力の大きさによって変化するんですね。また体重計は重量を測定してから内部で重力を割る計算が行われていますが、あくまでも内部で行われる計算は地球の重力の大きさに設定されています。ですので地球の重力の大きさに設定されている体重計を月で使用すると、正しい計算が行われません(地球の重力の大きさで割られるから)。上図のように体重計は地球の重力が割られるように設定されているので、地球の重力の約1/6である月では実際の質量の1/6に減ったように表示されます。なので正しい計算が行われません。関連:重力と重力加速度と重さ(重量)の違いとは?以上が「質量とは?重量(重さ)との違いと単位について」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、質量とは物体そのものの量のことで、単位は[g]や[kg]が用いられる。重量(重さ)とは物体に働く重力の大きさのことで、単位は[N]が用いられる。これらの違いは、その場所における重力の大きさによって変化するかどうか。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?⇒1気圧とは?また何ヘクトパスカル(hPa)なのか?⇒空気の温度で重さは変わる?暖かい空気は軽く冷たい空気が重い仕組みとは?⇒空気の膨張とは何か?空気の温度によって体積が変化する仕組みとは?⇒空気抵抗とは?なぜ物体の速度が上がると空気抵抗は大きくなるのか?⇒加速度とは何か?単位の意味とともにわかりやすく解説!⇒何桁の数字の意味とは?7桁の収入や3桁の収入はいくらを表している?⇒密度が大きい(高い)・密度が小さい(低い)の意味を簡単に図解!⇒単位変換にはコツが必要?単位変換の簡単な考え方について⇒1グラムは何ミリグラム?1グラムは何キログラム?単位(質量)の覚え方について
-
さて1グラムをミリグラム(またはキログラム)に変換するときがありますが、あなたはしっかりとそれらの意味を理解して変換できているでしょうか。ミリなどの意味を理解せずに1グラムは何ミリグラムというように覚えても、それはただ暗記しただけで時間が経てばすぐに忘れてしまいます。そこでこのページでは1グラムは何ミリグラム(または何キログラム)なのか?また単位(質量)を変換する簡単な覚え方について解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次1グラムは何ミリグラム(または何キログラム)?単位(質量)を変換する簡単な覚え方についてまとめ1.1グラムは何ミリグラム(または何キログラム)?では1グラムは何ミリグラム(または何キログラム)なのか見ていきましょう。結論から言ってしまうと、1グラムは1000ミリグラムで、キログラムに変換する場合だと1グラムは0.001キログラム(1/1000キログラム)になります。(ちなみに1キログラム=1000グラムで、1キログラム=1000000(=100万)ミリグラムです)これで終わってしまえば、ただ答えを暗記するだけになってしまうので、次の章で変換方法の簡単な覚え方について解説していきますね。関連:質量とは?重量(重さ)との違いと単位について2.単位(質量)を変換する簡単な覚え方についてでは単位(質量)を変換する簡単な覚え方について見ていきましょう。さっそくですがグラムからキログラムなどに変換するときの簡単な覚え方としては、ミリやキロという言葉の意味を理解して覚えることです。まず私たちが普段から質量を表すのに使用しているミリグラムやキログラムは、[mg](ミリグラム)と[kg](キログラム)のことを指しています。[m](ミリ)や[k](キロ)というのは”単位の接頭語”と呼ばれるもので、単位である[g](グラム)などの前に付けられることで意味をなします。(単位の接頭語の”ミリ”と単位の”メートル”は同じ小文字の”m”なので注意してください)そして単位の接頭語である”[m](ミリ)は1000分の1”を表していて、”[k](キロ)は1000倍”のことを表しています。例えば[g](グラム)から[mg](ミリグラム)と[kg](キログラム)への変換であれば、下のように考えていきます。また[g](グラム)からの変換ではなく、[mg](ミリグラム)から[kg](キログラム)への変換や、[kg](キログラム)から[mg](ミリグラム)への変換の場合も先ほどと同じように考えていきます。上のように[m](ミリ)は”1000分の1”で[k](キロ)は”1000倍”だから、それぞれの単位に変換するとこうなるんだなと理解できれば忘れることは少なくなりますよね。m(ミリ)やk(キロ)以外の単位の接頭語が付いている場合でも、同じように考えれば頭の中だけで変換することができるようになります。[m](ミリ)や[k](キロ)など単位の接頭語について詳しくは下記をご覧ください。関連:単位の接頭語とは何か?単位の接頭語の種類について以上が「1グラムは何ミリグラム?1グラムは何キログラム?単位(質量)の覚え方について」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、1[g](グラム) = 1000[mg](ミリグラム)、1[g] = 0.001[kg](キログラム)[m](ミリ)は”1000分の1”で、[k](キロ)は”1000倍”の意味を持っている。[m](ミリ)や[k](キロ)の意味を理解すれば、簡単に覚えることができる。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒1センチは何メートル?1センチは何ミリ?単位(長さ)の覚え方について⇒1リットルは何ミリリットル?1リットルは何デシリットル?単位(体積)の覚え方について⇒1時間は何秒?1時間は何分?単位(時間)の簡単な覚え方について⇒なぜ単位は大文字と小文字で区別しなければいけないのか?⇒ミクロン(μ)とは何か?マイクロとの違いは?⇒密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?⇒加速度とは何か?単位の意味とともにわかりやすく解説!⇒密度が大きい(高い)・密度が小さい(低い)の意味を簡単に図解!⇒光年とは何かをわかりやすく解説!1光年の距離はどのくらい?⇒単位変換にはコツが必要?単位変換の簡単な考え方について
-
さて暖かい水と冷たい水では重さが異なるという話を聞いたことはないでしょうか。実際に暖かい水は上に冷たい水は下にたまるので、お風呂で冷たい水が下の方にたまっていたという経験がある人も多いはずです。暖かい水は軽くて冷たい水は重くなると覚えておくだけでも特に問題ありませんが、なぜ温度によって水の重さが変化するのか疑問に感じる人もいますよね。そこでこのページでは、暖かい水と冷たい水で重さが変わる仕組みを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次水の温度が変わることで密度が変化する暖かい水が軽く、冷たい水が重くなる仕組みなぜ同じ体積の水なのに重さが異なるのか?まとめ1.水の温度が変わることで密度が変化するでは水の温度が変わることで密度が変化することについて見ていきましょう。結論から言ってしまうと、水の温度によって変化するのは重さではなく密度になります。密度というのは体積1[cm^3]当たりに何[g]の質量があるのかを表しているもので、密度の単位として[g/cm^3]が使用されています。密度は簡単に言えば、物質がどれだけ密に詰まっているのかその度合いを表したものです。関連:密度と比重の違いとは?また密度と比重の単位って何?そして重要なポイントなので何度も言いますが、温度によって変化するのは水の重さではなく水の密度です。たとえ温度が変化しても水の重さ自体は変わらず、密度だけが変化することになります。水は温度が変化することで体積が膨張したり圧縮したりしますが、そのときに水の重さは変化せず、体積変化に伴い水の密度だけが変化します。上図のように水を暖めると体積が膨張して大きくなり、水を冷やすと体積は圧縮されて小さくなります(このとき重さは変化せず)。密度はその物質がどれだけ密に詰まっているのかを表す度合いなので、密度が小さければあまり詰まっておらず、密度が大きければよく詰まっているということになります。これが水の温度変化によって、水の密度だけが変化するということです。ちなみに水の体積が温度によって膨張・圧縮する仕組みは、基本的に空気が膨張・圧縮するのと同じものです。なぜ体積が変化するのか、詳しい仕組みは下記の関連リンクからご覧ください。関連:空気の膨張とは何か?空気の温度によって体積が変化する仕組みとは?2.暖かい水が軽く、冷たい水が重くなる仕組みでは暖かい水が軽く、冷たい水が重くなる仕組みを見ていきましょう。まず私たちは普段から重い軽いと様々なモノの重さを比較していると思いますが、モノの重さを比較する場合はそのモノの重さではなく密度で比べなければなりません。例えば金と綿がそれぞれ1kgずつあったとします。では上図の1kgの金と1kgの綿ではどちらの方が重いでしょうか?正解は、どちらも同じ重さです。普通であれば綿よりも金の方が圧倒的に重いはずですが、上の図ではなぜ金と綿が同じ重さになったのでしょうか。それは比較するときに同じ体積当たりの質量(つまり密度)で比べていないからです。綿のようにどんなに軽いものであったとしても数を積み上げていけば、どんなに重い物質にも匹敵する以上の重さにすることができます。なのでモノの重さを比較する場合は、それぞれの密度で比べなければなりません。さて今までの解説ですでに理解されているとは思いますが、暖かい水が軽くなり、冷たい水が重くなる仕組みについて見ていきましょう。暖かい水は温度が上がることで膨張して密度が小さくなり、冷たい水は温度が下がることで圧縮して密度が大きくなります。そして温度が変化してもそれぞれの水の重さ自体は変わらないため、体積当たりの質量の大きさによってその物質の重い・軽いが決まります。体積当たりの質量が大きくなることでより地球からの重力がかかりやすくなるので、それにより密度の大きい方がより地球の中心に引き寄せられやすくなります。つまり密度が大きいモノの方が重いということです。なので冷たい水の方が密度が大きくなるため、暖かい水に比べて重くなるんですね。また暖かい水は軽くて、冷たい水が重いのは簡単に下図のようなイメージです。暖かい水は軽くなって冷たい水が重くなるというのは上図のように、暖かい水(密度が小さい)が冷たい水(密度が大きい)の上に乗っているイメージになります。例えば極端ですが豆腐(密度が小さい)の上に鉄の塊(密度が大きい)を乗せようとすれば、鉄の塊は豆腐よりも密度が大きいので重力によって下に行こうとして豆腐はつぶれます。反対に鉄の塊の上に豆腐を乗せるのであれば、特に問題なく鉄の塊の上に豆腐を乗せることができますよね。暖かい水が上にたまって、冷たい水が下にたまるのはこれと同じです。このように暖かい水と冷たい水をそれぞれ別のモノであると捉えれば、簡単にイメージできるようになります。関連:重力と重力加速度と重さ(重量)の違いとは?次の章では容器の中に同じ体積で温度が違う水を入れた場合の重さについて解説します。3.なぜ同じ体積の水なのに重さが異なるのか?ではなぜ同じ体積の水なのに重さが異なるのかを見ていきましょう。これは先ほどまでの解説をしっかりと理解していればすぐに分かります。例えば同じ体積の容器を2つ用意して、暖かい水と冷たい水をそれぞれの容器にギリギリまで入れます。このときに暖かい水と冷たい水ではどちらが重くなるでしょうか?「どちらもの水も体積が同じなんだから同じ重さになるに決まってる」と思う人も多いでしょう。ですが正解は同じ重さではなく、冷たい水が入った容器の方が重くなります。なぜ同じ体積なのに冷たい水の方が重くなるのかというと、それは冷たい水の方が暖かい水よりも密度が大きいからになります。これだけでは少し分かりにくいため、もう少し簡単に解説していきますねまず水は温度が上がると膨張し温度が下がると圧縮するので、なので暖かい水は体積が大きくなり冷たい水は体積が小さくなります。このときに重さ自体は変わらないので、水の密度だけが変化します。ではこれを簡単に数値にして表してみましょう。上図のように暖かい水と冷たい水では重さは数値10で同じですが、体積は暖かい水が15、冷たい水が5と異なります(数値は適当に付けています)。そしてそれぞれの水を体積60まで入れることができる容器に流していき、水位がギリギリになったところでそれぞれの重さを測るとどうなるでしょうか?(このとき水をまとまった液体ではなく、ひとつひとつ個別のものとしてみていきます)暖かい水の方は体積60まで入る容器に4個分、冷たい水の方は体積60まで入る容器に12個分収めることができます。そうすると暖かい水は体積60に対して重さが40(=4個分×10)となりますが、冷たい水は同じ体積60でも重さが120(=12個分×10)となりますよね。なので同じ体積でも冷たい水のほうが暖かい水よりも重くなるんですね。以上が「暖かい水と冷たい水で重さが変わる仕組みとは?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、水の温度が変化することで重さではなく、水の密度が変化する。どちらが重いかを判断するときは、それぞれの密度(同じ体積当たりの質量)で比べること。冷たい水は暖かい水よりも密度が大きくなるため重くなる(地球の中心に引き寄せられやすくなる)。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒水圧とは何か?わかりやすく図を用いて解説!⇒密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?⇒重力加速度とは?仕組みを分かりやすく図解!⇒水垢とは何か?水道周りに白い塊ができる仕組みについて図解!⇒蒸留とは何か?簡単に仕組みを図解!⇒溶媒と溶質と溶液の違いとは?⇒海水と淡水と真水の違いとは?⇒水道水のカルキとは?また塩素とカルキは何が違うのか?⇒浄水器とは?また浄水器ってどんな仕組みなの?⇒汚い水をろ過した後に煮沸させる目的とは何か?