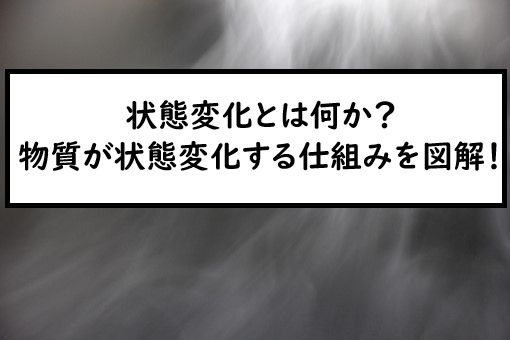さてあなたは温度というものをご存知でしょうか。私たちの身の回りでは理解しているようで、実はそのことについてほとんど理解していないものがたくさん存在します。温度もその中のひとつで意味は知っていても、温度について詳しく理解している人は少ないように感じます。そこでこのページでは温度とは何か?また物体の状態変化と温度の関係について簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次温度とは何か?温度の高さは何で決まるのか?物体の状態変化と温度の関係について分子運動における物体の温度変化の仕組み容器に入った水を火で暖めた場合容器に入った水を氷で冷やした場合まとめ1.温度とは何か?では温度とは何か見ていきましょう。温度(おんど)とは、物体の熱さ・冷たさ(暖かさ・寒さ)という度合いを表したものです。人によって熱い・冷たいと感じる基準が違うので、ただ単に熱い・冷たいだけでは正しく測定することはできません。そこで物体の熱さ・冷たさを誰でも同じく捉えることができるように、温度という物体の熱さ・冷たさの度合いを表す指標が生まれました。また温度といっても種類はいくつもあり、絶対温度・摂氏・華氏・列氏・蘭氏などが挙げられます。上記の種類の中で私たちが日常的に使用している温度の種類が、摂氏(セルシウス度)で、[℃]という単位で物体の温度が表されます。世界的に広く普及している温度の指標は摂氏ですが、地域によっては摂氏以外の種類が使用されている場所もあります。関連:摂氏と華氏とは何か?また摂氏と華氏の変換方法と違いについて次の章では温度の高さは何で決まるのかを解説します。2.温度の高さは何で決まるのか?では温度の高さは何で決まるのか見ていきましょう。結論から述べると物体の温度の高さは、その物体を構成している原子・分子の運動の大きさで決まります。物体は何でも原子・分子という目に見えない小さな粒で構成されていて、その原子・分子が運動することでその物体の温度の高さが決まります。簡単に言えば、その物体の原子・分子の運動が激しい(動きが速い)ほど温度は高くなり、反対に運動が穏やか(動きが遅い)であればその物体の温度は低くなります。水(液体)を例にして見てみましょう。まず水は水分子という小さな粒がいくつも集まることで構成されています。そして水の温度が低いとき・高いときを表すと下図のようになります。このようにその物体の温度の高さは分子の運動の大きさで決まっています。そして一般的に物体の温度が異なるのは、その物体の持っている熱の大きさが異なるからです。その物体の持っている熱が大きければ温度は高くなり、その物体の持っている熱が小さければ温度は低くなります。実はこの物体の持っている熱の大きさと分子運動というのは同じことを指しています。物体の温度の高さが原子・分子の運動の大きさで決まるのですから、原子・分子の運動の大きさ=その物体の持っている熱エネルギーということになります。簡単に関係をまとめると下記のようになります。原子・分子の運動が激しい(速い)=熱エネルギーが大きい⇒物体の温度が高くなる原子・分子の運動が穏やか(遅い)=熱エネルギーが小さい⇒物体の温度が低くなるなので温度を別の言葉で言い換えると、その物体がどのぐらいの熱エネルギーを持っているかを表す指標ということです。ちなみに注意してもらいたいこととして、物体の温度が高くなるのは先に物体の運動が激しくなるからです。物体の温度が高くなるから分子の運動が激しくなるのではなく、あくまでも分子の運動が先にあっての温度変化になりますので注意してください。関連:熱と温度の違いとは?次の章で物体の状態と温度変化の関係について解説します。3.物体の状態変化と温度の関係についてでは物体の状態変化と温度の関係について見ていきましょう。物体には固体・液体・気体の3つの状態が存在していて、その物体の温度が変化することで物体の状態も変化します。例えば氷(固体)を熱していけば水(液体)になり、その水(液体)をさらに熱していくといずれ水蒸気(気体)に変化します。このように物体の状態が変化することを状態変化と言います。この物体の状態変化を分子の運動という観点から解説していきます。下図は固体・液体・気体それぞれの状態における分子の運動の様子を表したものです。このそれぞれの状態と物体の温度の高さは大きく関係しています。はじめの方でも言いましたが、物体の温度の高さを決めるのは、その物体を構成している原子・分子の運動の大きさです。物体の温度の高さ=原子・分子の運動の大きさということを理解したうえで、それぞれの状態変化について見ていくと分かりやすいです。一般的に状態変化はその物体の温度が高くなっていくと、固体→液体→気体の順番で変化していきますよね。このとき物体の状態変化に必要なのは表面的に見れば温度を上げていくことですが、状態変化の本質は分子の運動を大きくさせて分子同士の繋がりを切ることにあります。なので物体が状態変化するのは温度を高くしていくことで、分子の運動が大きくなり分子同士の繋がりが切れるからなんですね。そして氷(固体)が溶けて水(液体)になり始める温度は0度で、水(液体)が水蒸気(気体)になる温度は100度です。これはあくまでも水分子同士の繋がりが切れ始める温度なわけで、その分子の種類によって繋がりの切れやすさ(状態変化のしやすさ)が異なります。ただ単に物体の温度が高くなるから固体が液体になるという覚え方でも良いですが、このように分子同士の考え方を知っていた方が何かと便利なので覚えておきましょう。関連:状態変化とは何か?物質が状態変化する仕組みを簡単に図解!4.分子運動における物体の温度変化の仕組み物体が温度変化するのは、物体の持っている熱が他の物体に移動するからです。温度の高い物体に温度の低い物体を当てると、温度の高い物体は少しずつ温度が下がっていきますよね。これは温度が高い物体から低い物体に熱が移動しているからです。このように熱というのは温度の高い物体から、低い物体に移動していきます。そして物体の持っている熱が他の物体に移動するということは、物体を構成している分子運動の大きさが他の物体の分子に働くということ。なので簡単に言うと、分子運動における物体の温度変化の仕組みは、動きの激しい分子が動きの穏やかな分子にぶつかっていくことで起こります。動きの激しい分子(温度が高い)が動きの穏やかな分子(温度が低い)にぶつかると、ぶつかった衝撃で穏やかな分子は少し動きが激しくなりますよね。反対に動きの激しい分子はぶつかったことで、その動きが少し穏やかになります。これが温度変化(熱の移動)の仕組みになります。具体的な例として容器内に水を入れて熱したときと冷やしたときについて、分子の運動を見ていきながらどのように温度変化するのかを解説していきます。では分子運動の様子からそれぞれの場合で、容器内の水が温度変化する仕組みを見ていきましょう。容器に入った水を火で暖めた場合まず容器内の水を容器の外から火で暖めた場合です。上図右は容器内の水と容器(ガラス)を分子で見た場合で、小さい分子の粒でそれぞれが構成されてることが分かると思います。そして火は分子で構成されている物体ではなく現象のことで、火からは物体の分子の運動を激しくさせる赤外線が放出されています。火に物体を近づけていきその物体が暖かくなっていくのは、火から赤外線が放出され物体の分子の運動を激しくさせているからなんですね。これを先ほどの例で見ていくと下図のようになります。火から放出された赤外線によって容器のガラス分子の運動が激しくなり、その運動がガラス分子を伝わり容器内の水分子にまで到達します。このまま火で熱し続けていくと水分子の動きがどんどん激しくなり、水分子の運動の激しさが水分子同士の繋がりを切るほど強くなると水が水蒸気に変化します。関連:湯気と水蒸気の違いとは?容器に入った水を氷で冷やした場合次は容器内の水を容器の外から氷で冷やした場合です。上図は先ほどと同じように分子で見た場合で表しています。物体の温度の高さは分子の運動の大きさによるので、容器の外にある氷の分子運動が1番小さい(温度が低い)です。つまり氷を構成している分子の動きが最も穏やかだということ。熱の移動は温度の高い物体から低い物体に起こるので、まずはガラス分子から氷の分子に熱の移動が起こります。そしてガラス分子から氷の分子に熱の移動が起こったことで、ガラス分子の動きが穏やか(温度が低く)になります。最後に容器内の水分子からガラス分子に熱の移動が起こります。これが容器内の水を氷で冷やした場合における、分子運動から見た温度変化の様子になります。関連:氷とドライアイスと液体窒素の違いとは?最も温度が低いのはどれ?以上が「温度とは何か?物体の状態変化と温度の関係について解説!」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});5.まとめこれまで説明したことをまとめますと、温度とは、物体の熱さ・冷たさ(暖かさ・寒さ)という度合いを表したもの。温度は、その物体がどのぐらいの熱エネルギーを持っているかを表す指標とも言うことができる。温度の高さは、物体を構成している分子の運動の大きさ(激しさ)によるもの。物体の状態変化は、分子の運動を激しくする(温度を高くする)ことで分子同士の繋がりが切れるので起こる。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒絶対零度とは?また絶対零度の温度は何度なのか?⇒凝結と結露の違いとは?⇒気温と温度と室温の違いとは?⇒⇒シンクに熱湯を流すとボコッと音がする理由とは?熱湯は流さない方が良いのか?⇒熱気球とは?また熱気球はどんな原理で空中に浮いているのか?⇒熱の伝わり方の3種類(伝導・対流・放射)を分かりやすく図で解説!⇒なぜ熱は必ず温度が高い方から低い方へと移動するのか?⇒なぜ液体は温度が上がると気体に変化しやすくなるのか?⇒熱伝導率とは何かをわかりやすく解説!熱伝導率が高い・低いとは?
ギモン雑学
「 状態 」の検索結果
-
-
さてあなたは物質の状態変化という言葉をご存知でしょうか。いま現在社会人の人でも学生の頃には勉強しているはずの言葉で、理科や化学などの分野でよく使用されています。物質の状態変化は私たちの日常生活においても、普段から周囲でよく起こっている現象になります。そこでこのページでは物質の状態変化とは何か?また物質が状態変化する仕組みを簡単に図で解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次物質の状態変化とは何か?状態変化の各名称について物質が状態変化する仕組みを簡単に図解!まとめ1.物質の状態変化とは何か?では物質の状態変化とは何か見ていきましょう。結論から言ってしまうと物質の状態変化とは、温度によって物質の状態(固体・液体・気体)が変化することを言います。そして固体・液体・気体の物質の3つの状態のことを”物質の三態”と呼びます。上図のように物質には固体・液体・気体の3つの状態が存在していますが、それらの状態はその物質の温度によって変化します。例えば水を0℃まで冷やすと少しずつ氷始めたり、反対に水を熱して100℃に達すると沸騰して水蒸気に変化します。このように物質は温度が変化することで、その状態も変化するんですね。関連:湯気と水蒸気の違いとは?関連:気化と蒸発と沸騰の違いとは何か?そして物質によって状態が変化する温度というのは異なります。水(液体)は0℃で氷(固体)に100℃で水蒸気(気体)に変化しますが、純アルコール(液体)は-114℃で固体に78℃で気体に変化します。なので一口に物質といっても、状態変化に必要な温度はそれぞれ異なるんですね。このときに物質が液体から固体に変化する温度のことを凝固点(ぎょうこてん)、液体から気体に変化する温度のことを沸点(ふってん)と言います。ちなみに一般的に知られている物質が状態変化する温度というのは、あくまでも周囲の気圧の大きさが1気圧の場合によるものなので注意してください。関連:1気圧とは?また何ヘクトパスカル(hPa)なのか?関連:気圧と沸点の関係について。気圧によって沸点が変化する仕組みとは?さて次の章で物質の状態変化の各名称について解説していきますね。2.状態変化の各名称についてでは物質の状態変化の各名称について見ていきましょう。物質の状態には固体・液体・気体の3つの状態(物質の三態)が存在しており、物質が各状態へと変化する際にそれぞれ異なる名称が付けられています。上図では気体から固体に変化する状態変化のことを”凝結”と示していますが、”凝結”の箇所を”昇華”と表しても構いません。以前までは気体→固体と固体→気体の変化のどちらとも昇華と示していましたが、最近ではそれぞれ分けられて気体→固体は凝結、固体→気体は昇華とすることが多いです。ただ凝結の箇所を昇華と書いても特に間違いではありませんが、もし授業で習った内容が凝結であるならばそのまま凝結と書いた方が良いでしょう。関連:凝結と結露の違いとは?また物質の状態が変化することでその物質の体積は変化していき、ほとんどの物質は固体→液体→気体になるにつれて体積が大きくなります。このときに物質の体積は変化しますが、質量については変化しないので覚えておきましょう。(この法則のことを”質量保存の法則”と言います)しかし私たちがよく知っている物質で、上のような体積変化とは少し異なる物質があります。その物質が何かというと、水になります。普通の物質であれば液体から固体に変化すると体積は小さくなりますが、水に限っては氷(固体)に変化したときの方が体積が大きくなるんですね。水(液体)の中に氷(固体)を入れると氷が浮くのは、氷の密度が水よりも小さいので氷が水の上に浮きます。もし他の物質と同様に固体である氷が液体の水よりも体積が小さければ、水の中に氷を入れても氷の方が水よりも密度が大きくなるために沈んでしまいます。関連:密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?関連:コップに水滴がつく理由とは?分かりやすく仕組みを図で解説!次の章で物質が状態変化する仕組みを簡単に図解していきますね。3.物質が状態変化する仕組みを簡単に図解!では物質が状態変化する仕組みを簡単に図解していきます。物質の状態には固体・液体・気体の3つの状態がありますが、物質の状態はそれぞれ温度が変化することで異なる状態に変化します。そして物質の温度が変化することが一体どういうことなのかを理解できれば、物質が状態変化する仕組みは簡単に理解することができます。まず物質の温度が変化するということは簡単に言えば、物質を構成している原子・分子の動きの激しさが変化するということです。上図のように物質を構成している原子・分子の動きが激しいほど温度は高く、反対に原子・分子の動きが穏やかであればその物質の温度は低くなります。物質のそれぞれの状態(固体・液体・気体)というのは、物質を構成している原子・分子同士による繋がり方で決まっています。上図のように物質の原子・分子は、それぞれ繋がり合うことで状態を形成しています。なので物質が状態変化する仕組みはその物質の温度を変化させることにより、原子・分子の動きの激しさが変わるため繋がり方も変わってしまうからなんですね。物質の温度が高くなるほど原子・分子の動きが激しくなるので繋がりが切れやすくなり、反対に物質の温度が低くなると動きが穏やかになるのでそれぞれが繋がりやすくなります。だから物質は熱していくと原子・分子同士の繋がりがほとんど切れた状態の気体に変化し、冷やしていくと原子・分子同士の繋がりが強い固体に変化するんですね。また物質が状態変化することで体積が変化しても質量が変化しないのは、単純に物質を構成している原子・分子の動きの激しさが変わっただけだからです。例えばA君を物質を構成している原子・分子だと考えてみましょう。A君が歩いたり走ったりすることで動きが変化したところで、A君の動ける範囲(体積)は変わりますがA君の体重(質量[kg])は特に変化しませんよね?これと同じで物質の状態によって変化するのは、その物質の体積だけになります。関連:熱と温度の違いとは?関連:絶対熱とは何か?絶対熱の温度は何度あるのか?以上が「状態変化とは何か?物質が状態変化する仕組みを簡単に図解!」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、物質の状態変化とは、温度によって物質の状態(固体・液体・気体)が変化すること。状態変化する仕組みは、原子・分子の動きが変化することでそれぞれの繋がり方が変化するから。物質が状態変化しても質量は変わらない(変化するのは体積のみ)。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒気温と温度と室温の違いとは?⇒摂氏と華氏とは何か?また摂氏と華氏の変換方法と違いについて⇒絶対零度とは?また絶対零度の温度は何度なのか?⇒水が100度に達していないのに蒸発する仕組みとは?⇒ドライアイスとは?ドライアイスから発生する白い煙の正体って何?⇒固体と個体の違いとは?⇒流体とは何かをわかりやすく解説!圧力はどんなかかり方なのか?⇒なぜ熱は必ず温度が高い方から低い方へと移動するのか?⇒シンクに熱湯を流すとボコッと音がする理由とは?熱湯は流さない方が良いのか?⇒熱の伝わり方の3種類(伝導・対流・放射)を分かりやすく図で解説!