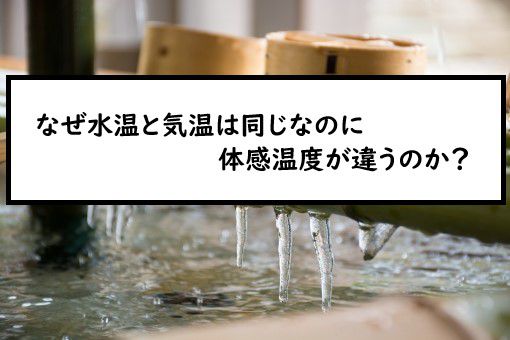気温30℃だと暑いと感じて、水温30℃の水に触ると冷たく感じますが、同じ30℃なのにどうして体感温度が違うのかをあなたはご存知でしょうか。別に理由が分からず「そういうもんだ」と思っていても特に問題はありませんが、知っていたほうが何かと役に立つときが来るので得をするはずです。そこでこのページでは、なぜ水温と気温は同じなのに体感温度が違うのかを簡単に解説します。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次なぜ水温と気温は同じなのに体感温度が違うのか?まとめ1.なぜ水温と気温は同じなのに体感温度が違うのか?ではなぜ水温と気温は同じなのに体感温度が違うのかを見ていきましょう。まず水温は”水の温度”で、気温は”空気の温度”のことを表しており、水温30℃の水は冷たく感じて、気温30℃の空気は暑いと感じますよね。結論から言って、水と空気は同じ30℃なのになぜ体感温度が違うのかと言うと、それは水と空気における熱伝導率(熱の伝わりやすさ)が異なるからです。水は空気に比べて熱伝導率が高いため熱が伝わりやすく、反対に空気は水よりも熱伝導率が低いため熱が伝わりにくいです。(水は空気に比べると20倍以上も熱が伝わりやすい物質になります)この水と空気の熱伝導率(熱の伝わりやすさ)の違いにより、それぞれに触れたときの体感温度が異なるんですね。さて以上のことを踏まえて、もう少し詳しく体感温度が異なる仕組みを解説していきます。私たち人間は普通であれば36℃~37℃ほどの体温を持っていて、何かに触れて冷たいと感じるのは、触れたモノに熱が移動している(奪われている)からです。そして自分の体から移動する(奪われる)熱の量が多いほど冷たいと感じます。ですので30℃の水(熱が伝わりやすい)と空気(熱が伝わりにくい)であれば、体温の方が36℃~37℃ほどで高いので、触れれば水と空気に熱が移動していきます。(熱は温度の高い方から低い方へと移動していくため)このときに同じ温度でも水と空気であれば、水の方が熱が伝わりやすい物質になるため、自分の体からより多くの熱が移動してしまうので水の方が冷たいと感じてしまうんですね。また水と空気の温度が体温よりも高かった場合についても同様の考え方になります。例えばそれぞれ100℃の水と空気(100℃の空気はサウナ内ぐらいの気温)があった場合には、100℃の水は熱すぎてずっと触っているのはまず無理ですが、100℃の空気であれば比較的長い時間触っていられますよね。100℃ということは自分の体温よりも温度が上になるので、触れていればその温度の高い物質から自分の体へと熱が移動してきます。上図のように100℃の水にずっと触れていることができないのは、水の熱伝導率が高いために自分の体に熱が大量に移動してくるからです。反対に100℃の空気に長いあいだ体が触れていても平気なのは、空気の熱伝導率が低いために空気から体に熱があまり移動してこないからです。(それでも息苦しかったり、暑い感じはします)水と空気の温度が同じなのに、体感温度が違うのにはこのような理由があったというわけです。関連:熱と温度の違いとは?関連:熱伝導率とは何かをわかりやすく解説!熱伝導率が高い・低いとは?以上が「なぜ水温と気温は同じなのに体感温度が違うのか?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、水温と気温が同じなのに体感温度が違うのは、水と空気における熱伝導率の違いによるもの。水の方が空気よりも熱伝導率が高いので、触れたときに移動する熱の量が多くなる。熱は必ず温度が高いモノから温度が低いモノへと移動する。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒温度とは何か?物体の状態変化と温度の関係について解説!⇒絶対零度とは?また絶対零度の温度は何度なのか?⇒質量とは?重量(重さ)との違いと単位について⇒コップに水滴がつく理由とは?分かりやすく仕組みを図で解説!⇒熱伝導とは何か?熱伝導の仕組みをわかりやすく図で解説!⇒なぜ氷は空気中よりも水中の方が溶けやすいのか?⇒流体とは何かをわかりやすく解説!圧力はどんなかかり方なのか?⇒なぜ液体は温度が上がると気体に変化しやすくなるのか?⇒粉塵爆発とは何か?粉塵爆発の原理をわかりやすく図で解説!⇒シンクに熱湯を流すとボコッと音がする理由とは?熱湯は流さない方が良いのか?
ギモン雑学
「 水温 」の検索結果
-
-
さてあなたは水温と浮力が関係しているということはご存知でしょうか。つまり水温が上がったり下がったりすることで、水から受ける浮力も変化するということです。そして水温によって浮力が変化する仕組みを知っている人は意外と少ないです。そこでこのページでは水温と浮力の関係について。また水温によって浮力が変化する仕組みを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次水温と浮力の関係について水温によって浮力が変化する仕組みとは?水温によって水の密度が変化する水の密度が変化すると浮力も変化するまとめ1.水温と浮力の関係についてでは水温と浮力の関係について見ていきましょう。結論から言ってしまうと、水温と浮力の関係は下のようになります。水温が4℃より高い ⇒ 水温が高いほど浮力は小さくなる(最高100℃まで)水温が4℃ ⇒ 浮力は最も大きくなる水温が4℃より低い ⇒ 水温が低いほど浮力は小さくなる(最低0℃まで)水温4℃のときが最も水から受ける浮力は大きくなり、水温4℃を境界として4℃より高くても低くなっても水からの浮力は小さくなります。水温が4℃よりも高い場合は100℃のときが最も浮力が小さくなり、水温が4℃よりも低い場合は0℃のときが最も浮力が小さくなります。これは水温が100℃以上になると水が沸騰して水蒸気(気体)に変化し、水温が0℃以下になると水が氷(固体)に変化し始めるからです。ちなみに水が100℃のとき沸騰して気体である水蒸気に変化し、0℃のとき固体である氷に変化し始めるというのは周囲の気圧が”1気圧”だからです。1気圧とは簡単に言えば、私たちが住んでいる地上における気圧の大きさのことで、周囲の気圧が1気圧でなければ水が水蒸気や氷に変化する温度も変わります。富士山などの頂上で水を沸騰させると、80℃~90℃ぐらいで沸騰する理由がまさにこれです。(1気圧では100℃で沸騰するが、富士山頂上の気圧は1気圧よりも低いため)関連:1気圧とは?また何ヘクトパスカル(hPa)なのか?関連:気圧と沸点の関係について。気圧によって沸点が変化する仕組みとは?次の章では水温によって浮力が変化する仕組みについて解説していきます。2.水温によって浮力が変化する仕組みとは?では水温によって浮力が変化する仕組みを見ていきましょう。さっそくですが水温によって浮力が変化する理由は、水温が変化することで水の密度が変化して、その水の密度変化に伴い浮力が変化するからです。浮力というのは流体(水や空気など)の重さによって発生している力なので、水温が変化して水の密度が変われば、それに伴って水からの浮力も変化することになります。簡単に水温によって浮力が変化する仕組みを解説しましたが、まだ分かりにくいだろうと思うので下記の2点について順番に詳しく解説していきます。水温によって水の密度が変化する水の密度が変化すると浮力も変化するさてそれぞれについて見ていきましょう。関連:流体とは何かをわかりやすく解説!圧力はどんなかかり方なのか?水温によって水の密度が変化する水の温度が上がるとその水の体積が大きく(膨張)なり、反対に水の温度が下がるとその水の体積は小さく(圧縮)なります。(このときその水の質量は変化せずに、体積だけが変化します)この水の体積変化に伴い、水の密度が変化します。(”密度[g/cm^3]=質量[g]/体積[cm^3]”なので、体積が変わると密度は変化します)上図のように水の温度が上がって体積が大きくなると密度は小さくなり、水の温度が下がって体積が小さくなると密度は大きくなります。関連:質量とは?重量(重さ)との違いと単位についてまた水の密度が大きくなるということはその水が”重くなる”ことと同じで、反対に水の密度が小さくなれば”軽くなる”ことと同じになります。普段から私たちが複数のモノの重さを判断するときには密度を用いています。例えばどんなに軽いモノでもそれをたくさん積み上げていくと、重いモノと同じ重さになるのでどちらが重いのか正確に判断ができなくなります。ですので軽いモノと重いモノを”同じ体積[cm^3]あたりの質量[g](つまり密度[g/cm^3])”で判断し、どちらのモノが重いのかを判断しています。水の質量が変化していないのにも関わらず、水の重さが変わるように感じるのは密度が変化したからです。このとき密度が大きいモノの方が重いモノで、密度が小さいモノの方が軽いモノとなります。関連:密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?関連:密度が大きい(高い)・密度が小さい(低い)の意味を簡単に図解!水の密度が変化すると浮力も変化する水温が上がると体積が膨張して密度が小さくなるのでその水は軽くなり、水温が下がると体積が圧縮して密度が大きくなるのでその水は重くなります。そして浮力はその流体の重さによって発生している力のことなので、水の密度が変化することによって浮力も変化していきます。まず水中の物体にかかる浮力のイメージは下図のようになります。上図のように流体中の物体には流体の重さによって発生した圧力があらゆる方向からかかり、その物体にかかる力の大きさは、流体中の深い場所ほど大きな力がかかります。(流体が水なら”水圧”がかかり、流体が空気なら”気圧”がかかる)上図でもあるように流体における浮力というのは、物体へとかかっている”下からかかる力ー上からかかる力”のことです。そうすると物体に下からかかる力の方が残るため、水などの流体に物体を沈めようとしても浮かんでくるんですね。(上からかかる力を引いたあとに残った物体に下からかかる力が”浮力”)なので浮力とは流体によって発生するあらゆる方向からかかる圧力のうち、下方向からかかっている圧力に限定したものを指しているんですね。では本題に入りますが、水温で水の密度が変化して重さが変わると、その変化した水の重さによって水中で物体にかかる力も変化していきます。水の重さが変化するということは”水によって下へとかかる力”が変化するということで、水の重さによって発生している浮力はその影響をそのまま受けることになります。つまりはこういうことです。上図のように水温が上がって軽くなった水は下へとかかる力(図では上)が弱くなり、反対に水温が下がって重くなった水は下へとかかる力が強くなります。(上図の数字は適当な値です)その水の重さによって発生した下へとかかる力が浮力にも影響するので、水温が上がると浮力は小さくなり、水温が下がると浮力は大きくなるというわけです。ただし水温が下がると浮力は大きくなると解説しましたが、水温4℃になると密度が最も大きく(重く)なるため、4℃より下がると浮力は小さくなっていきます。他の物質は温度が高くなるほど密度が小さくなっていき、温度が低くなるほど密度が大きくなっていくため、水は少し特殊な性質の物質です。上図のように水温4℃を境にして水温が上下するほど、浮力は小さくなります。浮力のイメージがまだ難しいと感じる人は、少し詳しく解説しているので下記をご覧ください。関連:浮力と流体の密度の関係について。流体の密度で浮力が変化する仕組みとは?以上が「水温と浮力の関係について。水温によって浮力が変化する仕組みとは?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、水温4℃のときが最も水の浮力は大きく、水温4℃を境にして浮力は小さくなっていく。水温4℃のときが水の密度が最も大きくなる(水は特殊な性質を持つ物質)。水温によって浮力が変化する仕組みは、水温が変化することで水の密度が変わるから。浮力は流体の重さによって発生する力なので、水の密度が大きく(重く)なると浮力も大きくなる。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒浮力とは何か?浮力の原理を簡単に図で解説!⇒単位の接頭語とは何か?単位の接頭語の種類について⇒なぜ氷は空気中よりも水中の方が溶けやすいのか?⇒水圧と浮力の違いについて簡単に図で解説!⇒液体の膨張と圧縮とは?温度によって液体の体積が変化する仕組みを図解!⇒氷とドライアイスと液体窒素の違いとは?最も温度が低いのはどれ?⇒なぜ真水(淡水)よりも海水の方が体がよく浮くのか?⇒死海とは?死海の由来は?なぜ死海は他の海よりも浮くことができるのか?⇒蒸気圧とは?水の沸点と蒸気圧の関係についてわかりやすく解説!⇒蒸気と水蒸気の違いとは?