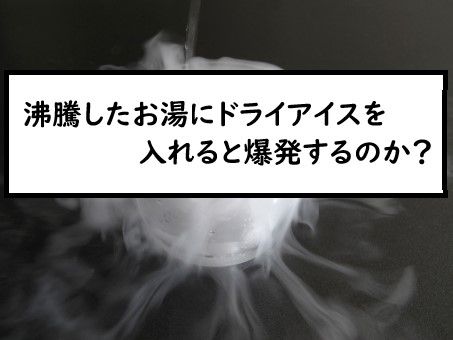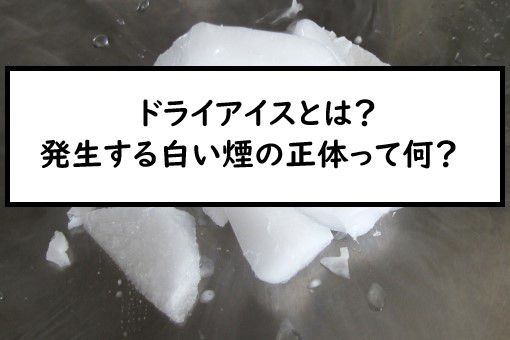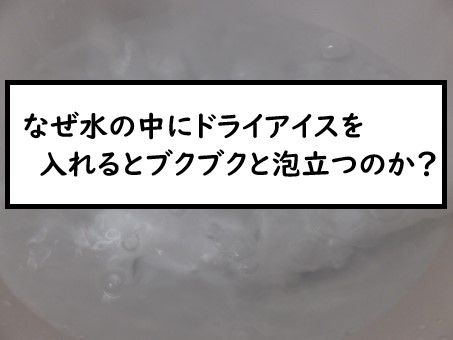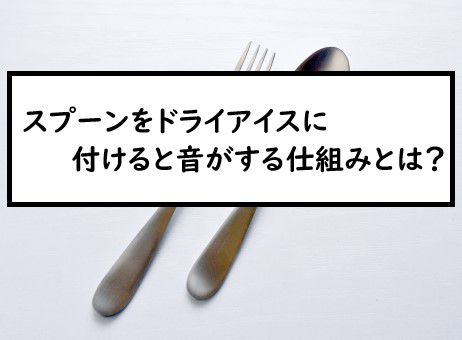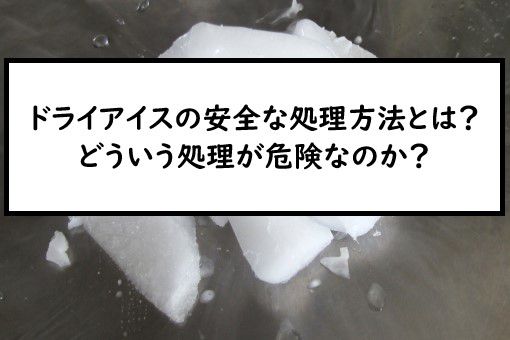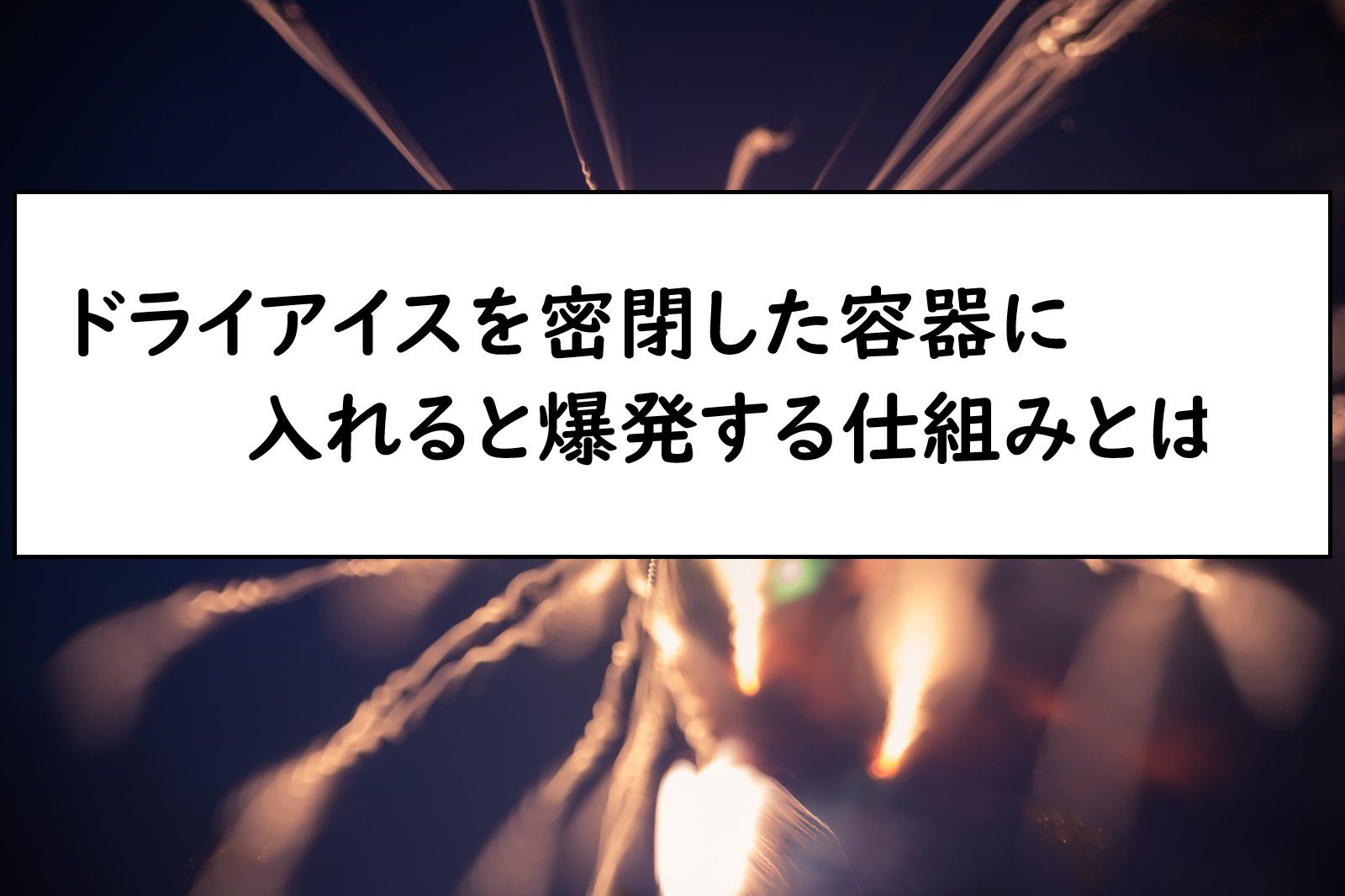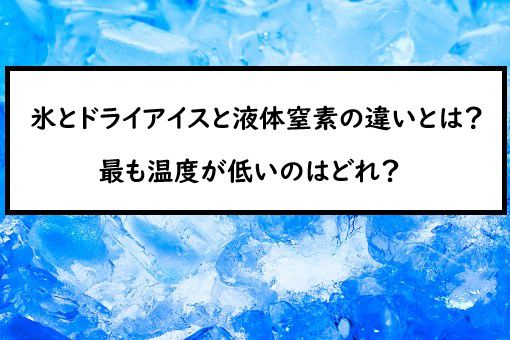さてあなたはドライアイスを沸騰したお湯の中に入れた経験はありますか?ドライアイスを水の中に入れたことがある人は多くても、沸騰したお湯の中に入れたことがある人はあまりいないのではないでしょうか。中には「沸騰したお湯の中にドライアイスを入れると爆発した!」というような噂もありますが、「本当に爆発するの?」と疑問に思いますよね。そこでこのページでは、沸騰したお湯にドライアイスを入れると爆発するのかどうかを解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次沸騰したお湯にドライアイスを入れると爆発するのか?まとめ1.沸騰したお湯にドライアイスを入れると爆発するのか?では沸騰したお湯にドライアイスを入れると爆発するのかどうか見ていきましょう。結論から言ってしまうと、沸騰したお湯にドライアイスを入れても爆発はしません。まずドライアイスと言うのは二酸化炭素が固体になったもので、ドライアイスの温度は-79℃以下という低温の物体になります。実際に経験している人もいると思いますが上の写真のように、ドライアイスを水の中に入れるとモクモクと白い煙が発生します。さてこのように水の中にドライアイスを入れるとモクモクと白い煙が発生しますが、沸騰したお湯の中にドライアイスを入れると一体どうなるのでしょうか?簡単に言えば沸騰したお湯にドライアイスを入れると、ドライアイスを水に入れたときよりも白い煙が勢いよく発生します。この”白い煙が勢いよく発生”という部分が、爆発したようにも見えるんですね。ドライアイスは-79℃以下の固体の二酸化炭素ですが、温度が-79℃よりも高くなると気体の二酸化炭素に変化します。(液体にならずに固体から気体に変化することを昇華と言います)二酸化炭素が固体から気体に変化すると、その体積は約800倍にも膨れ上がります。そして水よりも沸騰したお湯の中に入れる方が白い煙が勢いよく発生するのは、沸騰したお湯の方が水よりも温度が高いので気体の二酸化炭素に変化しやすくなるからです。水を加熱していくと次第に気体である水蒸気に変化していくのと同じで、水の温度が上がるほどドライアイスは気体の二酸化炭素に変化しやすくなります。さらにドライアイスを小さく砕いてから入れると、白い煙が勢いよく発生しやすくなるので注意が必要です。なぜドライアイスを砕いてからの方が白い煙が勢いよく発生するのかと言うと、それはドライアイスの表面積が大きくなることで発生する二酸化炭素の量が増えるからです。上図のようにドライアイスを細かく砕くことで、水に接触しているドライアイスの表面積が増えますよね。水によって暖められている表面からドライアイスは気化していくので、単純にドライアイスの表面積が増えるほど気体の二酸化炭素は発生しやすくなります。そして気体に変化して膨張した二酸化炭素が多ければ、気体の二酸化炭素による圧力も大きくなるのでそれだけ勢いよく噴き出すというわけです。またお湯の中でドライアイスから気化した二酸化炭素は一気に膨張するため、その二酸化炭素が膨張した勢いで熱湯が周囲に飛び散る可能性があります。他にも細かく砕いたドライアイスが二酸化炭素の膨張によって、熱湯と同時に飛び散ることも十分に考えられます。このように沸騰したお湯にドライアイスを入れる行為は、とても危険なので真似しないでくださいね。ちなみにドライアイスから発生する白い煙は、気体の二酸化炭素ではないので注意してください。関連:ドライアイスとは?ドライアイスから発生する白い煙の正体って何?以上が「沸騰したお湯にドライアイスを入れると爆発するのか?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、沸騰したお湯にドライアイスを入れても、爆発は起こらない。場合によっては白い煙が勢いよく発生することもあるので、爆発のように見えることもある。熱湯などが飛び散る可能性があり危険なため、真似しないこと。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒氷とドライアイスと液体窒素の違いとは?最も温度が低いのはどれ?⇒なぜ水の中にドライアイスを入れるとブクブクと泡立つのか?⇒ドライアイスを密閉した容器に入れると爆発する仕組みとは?⇒シンクに熱湯を流すとボコッと音がする理由とは?熱湯は流さない方が良いのか?⇒スプーンをドライアイスに付けると音がする仕組みとは?⇒ドライアイスの安全な処理方法とは?またどういう処理が危険なのか?⇒一酸化炭素中毒とは?発生する原因と仕組みについて簡単に解説!⇒揮発とは?蒸発との違いと意味は何か?なぜ揮発は起こる?⇒気化と蒸発と沸騰の違いとは何か?⇒粉塵爆発とは何か?粉塵爆発の原理をわかりやすく図で解説!
ギモン雑学
「 ドライアイス 」の検索結果
-
-
さてあなたはドライアイスとは何かをご存知でしょうか。食品などを冷やして保存するためによく一緒に入れられている白い塊のことですが、パッと見てもドライアイスがどんなものからできているのか分かりませんよね。普段からドライアイスをよく使用している人についても、実はドライアイスが何からできているのか知らないってことも割と多いです。そこでこのページではドライアイスとは何か?またドライアイスから発生する白い煙の正体について簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次ドライアイスとは何か?ドライアイスから発生している白い煙の正体とは?なぜドライアイスから発生した白い煙は下に溜まるのか?まとめ1.ドライアイスとは何か?ではドライアイスとは何か見ていきましょう。結論から言ってしまうとドライアイスとは、固体の二酸化炭素(CO2)のことです。私たちがよく知る二酸化炭素とは空気中に含まれている気体のことですが、ドライアイスはその気体の二酸化炭素が固体に変化したものです。ちなみに二酸化炭素はその状態(固体・液体・気体)によって名称が変化します。固体は”ドライアイス”、液体は”液体二酸化炭素”、気体は”炭酸ガス”となり、気体の二酸化炭素(炭酸ガス)が含まれた水は”炭酸水”とも言われています。(ここでは酸化炭素の状態によって、特に名称は変えていません)さて本題に戻りますが、ドライアイスの温度は-79℃”以下”の低温です。(ドライアイスの温度が-79℃”以下”と具体的な温度を示していないのは、ドライアイスも水や氷に決まった温度がないのと同じで、温度にある程度の範囲があるからです)なのでドライアイスに触るときは厚手の手袋などを装着して、絶対に素手で触れないようにしましょう(凍傷になる可能性もあります)。二酸化炭素(ドライアイス)は他の物質とは異なり少し特殊で、周囲が常圧(約1気圧のこと)の場合では固体からそのまま気体に変化します。(固体から液体にならずに気体に変化することを昇華と言います)ドライアイスの温度が79℃より高くなると昇華してしまうので、ドライアイスを保存しておくのは難しいです(普通の冷凍庫で-20℃ほど)。また常圧下ではドライアイスは昇華するため、液体にはなりません。ということは普通の氷であれば次第に水(液体)に変化していきますが、ドライアイスは液体にならずに気体になるので触れているものは濡れることがありません。ドライアイスによって冷やしているものが濡れないのでとても便利ですよね。このようなことから”ドライ(乾いた)アイス(氷)”という名称になっています。関連:1気圧とは?また何ヘクトパスカル(hPa)なのか?関連:状態変化とは何か?物質が状態変化する仕組みを簡単に図解!さて次の章でドライアイスから発生している白い煙の正体を解説していきますね。2.ドライアイスから発生している白い煙の正体とは?ではドライアイスから発生している白い煙の正体について見ていきましょう。さっそくですがドライアイスから発生している白い煙の正体は、空気中に含まれていた水蒸気がドライアイスによって冷やされて小さな水や氷の粒になったものです。ドライアイスを置いておくとその周囲に存在する空気や、ドライアイスから昇華して発生した気体の二酸化炭素によって空気が冷やされます。そして空気が冷やされることでその空気の飽和水蒸気量が少なくなり、空気中に含まれていた水蒸気が小さな水や氷の粒に変化するんですね。関連:湯気と水蒸気の違いとは?関連:飽和水蒸気量とは?露点との違いは何か?ドライアイス自体が白い塊なのでドライアイスから発生する白い煙の正体は、ドライアイスが気化したもの(二酸化炭素)だと思っていた人も多いはずです。ですがよく考えてみてください。空気は酸素・窒素・二酸化炭素などの気体が混合されていますが、空気の色は無色透明です。なぜかというと、空気を構成している気体の色が無色透明だからです。固体の二酸化炭素(ドライアイス)は白い色をしていますが、気体の二酸化炭素の色は無色透明になります。だからドライアイスから発生している白い煙の正体は、気体の二酸化炭素(無色透明)ではなく液体の水や固体の氷ということになります。またドライアイスによって白い煙が発生するのは、雲や霧が発生する仕組みと同じです。雲が発生する詳しい仕組みについては下記をご覧ください。関連:雲とは何か?雲ができる仕組みをわかりやすく図で解説!3.なぜドライアイスから発生した白い煙は下に溜まるのか?ではなぜドライアイスから発生した白い煙は下に溜まるのかを見ていきましょう。簡単に言えばドライアイスから発生した白い煙が下に溜まる理由は、気体の二酸化炭素が空気より重い物質だからです。二酸化炭素の比重は約1.5で、空気よりも1.5倍ほど重いということです。ですのでドライアイスから気体の二酸化炭素が発生すれば、付近に上昇気流などの流れがない限りは自然に下に溜まっていくことになります。そして白い煙の正体は気体の二酸化炭素(無色透明)ではなく、ドライアイスとそこから気化した二酸化炭素によって冷やされて小さな水や氷の粒になったものです。上図のようにドライアイスから発生した気体の二酸化炭素が下に流れることによって、気体の二酸化炭素の流れる方向にある空気中の水蒸気が冷やされて小さな水や氷の粒になります。なので自然と下の方に白い煙(水や氷の粒)が溜まるというわけです。またしばらくすると白い煙が消えて見えなくなってしまうのは、白い煙(水や氷の粒)が周囲に存在する空気に暖められるからです。空気は冷やされることで飽和水蒸気量が少なくなり、反対に暖められることで飽和水蒸気量が多くなります。空気は暖められると水蒸気をより多く含むことができるので、目に見えていた白い煙(水や氷の粒)が水蒸気に変化して見えなくなったということです。つまりドライアイスから白い煙が発生したときと反対の現象が起きています。ドライアイスから白い煙が発生するときは空気が冷やされることで起こりますが、反対に白い煙が消えるときは空気が暖められることで起こります。最初の内は理解するのが難しいかもしれませんが、慣れていけば簡単に理解できるので少しずつ学んでいきましょう。関連:密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?以上が「ドライアイスとは?ドライアイスから発生する白い煙の正体って何?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、ドライアイスとは、固体の二酸化炭素(CO2)のこと。ドライアイスの温度は-79℃ほど(素手で触れると凍傷になる危険がある)。白い煙の正体は気体の二酸化炭素ではなく、液体の水。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒氷とドライアイスと液体窒素の違いとは?最も温度が低いのはどれ?⇒なぜ水の中にドライアイスを入れるとブクブクと泡立つのか?⇒ドライアイスを密閉した容器に入れると爆発する仕組みとは?⇒シンクに熱湯を流すとボコッと音がする理由とは?熱湯は流さない方が良いのか?⇒スプーンをドライアイスに付けると音がする仕組みとは?⇒ドライアイスの安全な処理方法とは?またどういう処理が危険なのか?⇒一酸化炭素中毒とは?発生する原因と仕組みについて簡単に解説!⇒煙とは?黒い煙や白い煙の正体って何?⇒風の正体とは?風はどんな原理で吹いているのか?⇒結露とは何か?仕組みを分かりやすく図解!
-
さてあなたは水の中にドライアイスを入れたところを見たことがありますか?水の中にドライアイスを入れると水の中からブクブクと泡が出てきますが、なにやら水を加熱したときに水が沸騰している様子と少し似ています。しかし加熱しているわけでもないのに、なぜ沸騰したようになるのか疑問に思いますよね。そこでこのページでは、なぜ水の中にドライアイスを入れるとブクブクと泡立つのかを解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次なぜ水の中にドライアイスを入れるとブクブクと泡立つのか?まとめ1.なぜ水の中にドライアイスを入れるとブクブクと泡立つのか?ではなぜ水の中にドライアイスを入れるとブクブクと泡立つのかを見ていきましょう。結論から言ってしまうと水の中にドライアイスを入れると泡立つ理由は、水の中でドライアイスの表面から気化した二酸化炭素が発生するからです。まずドライアイスは二酸化炭素が固体になったもので、その温度は-79℃以下と低温です。そしてドライアイスは温度が-79℃よりも高くなると、固体からそのまま液体にならずに気体の二酸化炭素に変化します。(固体から液体にならずに気体に変化することを昇華と言います)水の中にドライアイスを入れることでブクブクと泡立つので、「もしかして水が沸騰してるのではないか?」と思う人もいるかもしれません。しかしそれは間違いで、ただ水の中で気体の二酸化炭素が発生しているだけです。普通の冷凍庫の中の温度が-20℃ほどなので、温度が-79℃以下の状況は特殊な設備がなければ作れません。ですのでドライアイスはほとんどの場合で、空気中でも水中でも暖められていることに変わりはないので少しずつ気体に変化していきます。上図のように水の中にドライアイスを入れると水によって暖められるので、それにより昇華し始めるためドライアイスの表面から気体の二酸化炭素が発生します。二酸化炭素は固体(ドライアイス)から気体に変化することで、体積が約800倍に膨れ上がります。これにより体積が大きくなる現象が水(液体)の中で起こるから、体積が膨れ上がった気体が泡として発生するんですね。ちなみに固体の二酸化炭素であるドライアイスは白い塊をしていますが、気体の二酸化炭素の色は無色透明なので注意してくださいね。関連:ドライアイスとは?ドライアイスから発生する白い煙の正体って何?また水の中にドライアイスを入れるとブクブクと泡立つ現象は、水を入れた鍋を加熱して沸騰させたときの様子に似ています。水の入った鍋を加熱して少し経過すると、鍋の底からボコボコッと泡が発生しますよね。この場合は鍋底の水が暖められたことで気体の水蒸気に変化したことによるものですが、水の中にドライアイスを入れたときに泡立つのも考え方は似たようなものです。泡が発生する理由が”水が沸点に達したことで水蒸気に変化するのか”、”水の中でドライアイスが昇華して気体の二酸化炭素に変化するのか”ってだけです。水は水蒸気に変化すると体積が約1700倍に膨れ上がり、ドライアイスは気体の二酸化炭素に変化すると約800倍に膨れ上がります。なので液体(水)の中で泡が発生する原理としては、二酸化炭素も水蒸気もほとんど変わらないというわけです。関連:空気の膨張とは何か?空気の温度によって体積が変化する仕組みとは?関連:気圧と沸点の関係について。気圧によって沸点が変化する仕組みとは?以上が「なぜ水の中にドライアイスを入れるとブクブクと泡立つのか?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、水の中にドライアイスを入れると泡立つ理由は、水中でドライアイスから気体の二酸化炭素が発生するから。固体の二酸化炭素(ドライアイス)から気体に変化すると、体積が約800倍に膨れ上がる。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒氷とドライアイスと液体窒素の違いとは?最も温度が低いのはどれ?⇒ドライアイスの安全な処理方法とは?またどういう処理が危険なのか?⇒沸騰したお湯にドライアイスを入れると爆発するのか?⇒ドライアイスを密閉した容器に入れると爆発する仕組みとは?⇒スプーンをドライアイスに付けると音がする仕組みとは?⇒粉塵爆発とは何か?粉塵爆発の原理をわかりやすく図で解説!⇒質量とは?重量(重さ)との違いと単位について⇒一酸化炭素中毒とは?発生する原因と仕組みについて簡単に解説!⇒水を沸騰させると発生する泡の正体とは?またなぜ泡は発生するのか?⇒なぜ氷は空気中よりも水中の方が溶けやすいのか?
-
さてスプーンをドライアイスに付けると、”ギギギ”というような音がするのをご存知でしょうか。実際にドライアイスの実験で、過去に経験している人もいるはずです。このような現象が発生するのはドライアイスの性質によるものなのですが、なぜドライアイスにスプーンを付けると音がするのか疑問に思いますよね。そこでこのページでは、スプーンをドライアイスに付けると音がする仕組みを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次スプーンをドライアイスに付けると音がする仕組みとは?まとめ1.スプーンをドライアイスに付けると音がする仕組みとは?ではスプーンをドライアイスに付けると音がする仕組みを見ていきましょう。結論から言ってしまうとスプーンをドライアイスに付けると音がするのは、ドライアイスが気化してスプーンを振動させ、ドライアイスとスプーンが接触することによるものです。さてなぜスプーンが振動して音がするのかを詳しく解説していきますね。まずドライアイスは二酸化炭素が固体になったもので、-79℃以下の低温の物体です。ドライアイスの温度がー79℃よりも高くなると、気体の二酸化炭素に変化していきます。(固体から液体にならずに気体に変化することを昇華と言います)普通の環境ではドライアイスを-79℃以下に保つことは難しいので、ドライアイスを放置していれば勝手に気体の二酸化炭素に変化していきます。関連:ドライアイスとは?ドライアイスから発生する白い煙の正体って何?そしてスプーンというのはたいてい素材が金属で作られていて、最もスプーンに使われている金属で多いのがステンレスです。(ステンレスは台所のシンクにも多く使用されている金属になります)ご存知かもしれませんがほとんどの金属は熱伝導率が高く、熱伝導率が高いということは自身が持っている熱を他の物質に伝えやすいということです。これによりスプーンをドライアイスに付けるとスプーンの持っている熱がドライアイスに伝達され、ドライアイスのその部分の温度が上昇するので気体の二酸化炭素に変わります。二酸化炭素は固体から気体に変化すると体積が約800倍も大きくなるので、約800倍に大きくなった気体の二酸化炭素は発生すると同時にスプーンを持ち上げます。しかし気体の二酸化炭素は一瞬だけスプーンを持ち上げることはできますが、スプーンの重さには勝てないので気体の二酸化炭素は周囲に分散していきます。そうすると持ち上がっていたスプーンは落ちて再びドライアイスと接触することになるため、ドライアイスが気体の二酸化炭素に変化してスプーンを持ち上げます。(このときスプーンが落ちてドライアイスと接触することで音が鳴ります)このような現象が短時間に何度も繰り返し発生しているので、スプーンをドライアイスに付けると”ギギギ”というような音がするんですね。ちなみにドライアイスに付けると音がする話で重要なのは、”スプーン”ということではなく”金属”だからなのでそこだけは誤解しないようにしてください。熱伝導率の低い物質をドライアイスに付けても、今回と同じような現象は起こらないので覚えておきましょう。関連:シンクに熱湯を流すとボコッと音がする理由とは?熱湯は流さない方が良いのか?以上が「スプーンをドライアイスに付けると音がする仕組みとは?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、スプーンをドライアイスに付けると音がするのは、ドライアイスが気化してスプーンを振動させるから。スプーンの素材が金属製だと音が鳴る(熱伝導率が高いから) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒氷とドライアイスと液体窒素の違いとは?最も温度が低いのはどれ?⇒沸騰したお湯にドライアイスを入れると爆発するのか?⇒なぜ水の中にドライアイスを入れるとブクブクと泡立つのか?⇒ドライアイスを密閉した容器に入れると爆発する仕組みとは?⇒ドライアイスの安全な処理方法とは?またどういう処理が危険なのか?⇒ドライアイスとは?ドライアイスから発生する白い煙の正体って何?⇒一酸化炭素中毒とは?発生する原因と仕組みについて簡単に解説!⇒粉塵爆発とは何か?粉塵爆発の原理をわかりやすく図で解説!⇒真空とは何か?分かりやすく図で解説!⇒金属に触ると冷たく感じる理由とは?なぜガラスと木材ではガラスの方が冷たい?
-
さてケーキやアイスクリームを買うとドライアイスが一緒に付いてくることがありますよね。ドライアイスは氷よりも温度が低いので冷却剤としての性能が高く、さらには液体にならないので食材が濡れることもありません。そんな冷却剤として便利なドライアイスですが、とても危険な物質でもあります。実際にドライアイスによって大ケガをした人も多いです。そこでこのページではドライアイスの安全な処理方法とは?またドライアイスを処理するときにどのような処理が危険なのかを解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次ドライアイスの安全な処理方法とは?風通しの良い場所で放置する水の中に入れる小さく砕いてから放置または水の中に入れるドライアイスを処理するときに危険な行為!濡れている手などで触る空気が換気されない場所で放置する密閉した容器に入れて放置するまとめ1.ドライアイスの安全な処理方法とは?まず基本的な知識としてドライアイスは二酸化炭素が固体になったもので、ドライアイス自体の温度は-79℃以下の低温の物体になります。そしてドライアイスの温度が-79℃よりも高くなると、固体から気体の二酸化炭素に変化していきます。(固体から液体にならずに気体に変化することを昇華と言います)関連:状態変化とは何か?物質が状態変化する仕組みを簡単に図解!ではドライアイスの安全な処理方法について詳しく解説していきますね。風通しの良い場所で放置するドライアイスを処理するときに最も簡単で安全なのは、風通しの良い場所や換気している部屋内で放置することです。先ほども少し触れていましたがドライアイスは-79℃よりも温度が高くなると、固体から気体の二酸化炭素(無色透明)に少しずつ変化していきます。ただ放置しているだけでもドライアイスよりも温度の高い空気に触れているので、ドライアイスは少しずつ昇華していきます。なのでただ放置しているだけで、自然とドライアイスは消えてなくなります。(正確には気体の二酸化炭素に変化していきます)しかし、ただ放置するだけと言っても注意しなければいけないことがあります。それは”ドライアイスの温度が-79℃以下の低温”だということと、”ドライアイスから気化した二酸化炭素は空気よりも重いため下に溜まる”ということです。ドライアイスは大人でも日頃から触れていることが少ないので、面白がってついつい手を出したくなりますよね。ですがドライアイスの温度は-79℃以下とかなりの低温なので、素手で触れていると触れた部分が凍傷になる可能性があります。(触れるときは手袋や軍手を使用するようにしてください)そのドライアイスをどこにでも放置していると子供やペット、さらにはその危険性を知らない大人でも素手で触れてしまう可能性が高いです。なので子供などの手で簡単には触れることができない場所に放置してくださいね。また気体の二酸化炭素は空気よりも約1.5倍重い物質で、換気などがされていないと気体の二酸化炭素が下に溜まってしまうことが多いです。ドライアイスから発生する白い煙自体は気体の二酸化炭素(無色透明)ではないですが、白い煙と同様に二酸化炭素も下に溜まるので、白い煙と同じ場所に溜まります。二酸化炭素が下に溜まってその二酸化炭素濃度が高い空気を吸うと、二酸化炭素中毒や酸欠状態になることも十分に考えられます。ですので必ず換気などで空気を入れ替えるようにしてください。換気扇が上部に付いている場合でも空気の入れ替えによって流れができ、下に溜まっていた気体の二酸化炭素もかき混ぜられるので問題はありません。(人が移動するだけでも下に溜まった二酸化炭素はかくはんされます)もし小さな子供やペットがいて不安なら、室内ではなくベランダなどの外に置いておきましょう。室内よりは外でドライアイスを放置したほうがより安全だと言えます。(外で放置する場合でも、自分の家の敷地内で他の人が触れられない場所にしてください)関連:ドライアイスとは?ドライアイスから発生する白い煙の正体って何?関連:風の正体とは?風はどんな原理で吹いているのか?水の中に入れるドライアイスを水の中に入れて処理するという人も多いです。なぜただ放置するだけではなく水の中で処理するのかというと、空気よりも水の中に入れた方が時間的に早くドライアイスが気化するからです。水の方が空気よりも熱を伝達しやすい物質なので、ドライアイスに熱がより伝わりやすくなり早く気化することができます。さらにドライアイスを水の中に入れると白い煙がモクモクと発生するので、遊びでドライアイスを水の中に入れていたという人も多いのではないでしょうか。またお湯に入れると水のときよりも温度差が大きくなるため、水のときよりもさらに早くドライアイスが気化します。そして水(お湯)の中に入れてドライアイスを処理する場合についても、気体の二酸化炭素が発生する点では同じなのでしっかりと空気は入れ替えてくださいね。関連:なぜ水の中にドライアイスを入れるとブクブクと泡立つのか?関連:沸騰したお湯にドライアイスを入れると爆発するのか?小さく砕いてから放置または水の中に入れる最後はドライアイスを小さく砕いてから放置または水(お湯)の中に入れるになります。基本的なことは”風通しの良い場所で放置する”と”水の中に入れる”のときに、解説した内容や注意点とほとんど同じになります。ただ違うのは”ドライアイスを小さく砕く”という点です。ドライアイスを小さく砕くことで何が変わるのかと言うと、それはドライアイスの表面積が増えることによって気化しやすくなるということです。ドライアイスが空気中や水中に入れて放置すると気化していくのは、空気や水に触れているドライアイスの表面部分が暖められるからです。空気や水もドライアイスからすると温度の低い物質であることには変わりないので、たとえ私たちが冷たいと思っているものでもドライアイスを気化させてしまいます。そしてドライアイスを小さく砕くことで砕く前よりも表面積が増えるので、空気や水などに暖められる部分が増えてより気化しやすくなるということになります。関連:気化と蒸発と沸騰の違いとは何か?またドライアイスを細かく砕いて水やお湯の中に入れると、砕かないで入れるよりも白い煙が勢いよく噴き出すことがあるので注意してください。2.ドライアイスを処理するときに危険な行為!まずドライアイスを処理する際に注意する点は下記の通りです。ドライアイスの温度は-79℃以下と低温である気体の二酸化炭素は空気より重いので、下に溜まりやすい気体の二酸化炭素に変化すると、体積が約800倍も大きくなる以上の点を踏まえたうえで、ドライアイスを処理するときの危険な行為について解説していきますね。濡れている手などで触るドライアイスを処理する際に濡れている手などで触れるのはとても危険です。水で濡れているだけでなく汗などで湿っている場合にも注意が必要で、さらに素手で触るときだけに関わらず軍手が濡れているときも注意が必要になります。なぜ危険なのかというとドライアイスによって冷やされることで、手などに付着している水分が凍ってしまい容易に取れなくなるからです。冷凍庫の中で氷に触るとその部分が体温で暖められて水になりますが、冷凍庫の中は気温がとても低いので変化した水が再び氷に戻ってしまいます。このときに水が氷に変化したものが接着剤のような働きをするため、手で触れている部分と氷がくっついて容易に取れなくなる現象が起こるんですね。もし手が濡れたまま(汗などで湿っていても)ドライアイスに触れることで、ドライアイスによってその水分が冷やされて氷になります。そうすると先ほどの解説のように氷が接着剤みたいに働くことによって、手がドライアイスとくっついて簡単には取れなくなってしまいます。これによりドライアイスに触れている部分が凍傷になってしまう危険があるんですね。乾いた手で一瞬触れるぐらいであればそこまで問題にはならないでしょうが、危険な行為であることに変わりはないので素手でドライアイスに触るのは控えてください。軍手でドライアイスに触るときももし軍手が濡れていれば、軍手の中に水分が浸透するので軍手を通して素手まで凍ってしまいます。(軍手は通気性が良いので、水分を中まで通す)なのでドライアイスに触るのであれば、乾いた軍手や手袋で触るようにしてください。(ドライアイスに素手で触るのは、乾いていてもやめてください)空気が換気されない場所で放置する空気が喚起されない場所でドライアイスを放置するのは危険です。ドライアイスは二酸化炭素が固体になったもので、何もしていなければ自然と気体の二酸化炭素に変化していきます。少しずつドライアイスが気体の二酸化炭素に変化していくことで、換気されていない部屋なら空気中の二酸化炭素濃度がどんどん高くなりますよね。これにより呼吸するとき体内に普段より多くの二酸化炭素を取り込むことになるので、二酸化炭素中毒や酸欠に陥りやすくなってしまいます。なのでドライアイスを部屋の中で放置するときは、必ず窓を開けたり換気扇を回して空気の換気を行ってください。密閉した容器に入れて放置する最後はドライアイスを密閉した容器に入れて放置することです。ドライアイスは気体の二酸化炭素に変化することで、固体のときよりも体積は約800倍にも膨れ上がります。なので容器の中でドライアイスから気化した二酸化炭素が、容器の中で膨れ上がることで容器が内部の圧力に耐えられなくなるんですね。危険なので絶対に真似しないでもらいたいのですが、ペットボトルの中にドライアイスを入れてふたを閉めて少し待つと爆発します。(このときにペットボトルの破片が飛散してとても危険です)例えば風船の中に空気を入れていくと少しずつ風船は膨らんでいきますが、空気がパンパンの状態からさらに空気を入れようとすると最後には風船が破裂しますよね。要はこれと同じで容器の中でドライアイスから気体の二酸化炭素が発生して、容器が耐えられなくなると最終的には容器が破裂します。またペットボトルだけでなく密閉された容器の中なら起こる現象です。ゴミ袋の中に入れても結び目をきつく縛ると密閉されている状態と同じで、ゴミ袋が破裂して中のゴミが飛散することもあるので注意してください。ですのでドライアイスを安全に処理するなら屋外などの喚起されている場所に放置するのが安全です。(他の人やペットが簡単に触れないような場所にしてくださいね)関連:ドライアイスを密閉した容器に入れると爆発する仕組みとは?以上が「ドライアイスの安全な処理方法とは?またどういう処理が危険なのか?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、ドライアイスの安全な処理方法は、風通しの良い場所や換気されている場所で放置すること。ドライアイスを濡れている手や軍手で触るのは危険(乾いていても素手では触らないこと)。空気が喚起されていない場所では、二酸化炭素中毒や酸欠になる危険性がある。ドライアイスは密閉されている容器の中には爆発するので入れないこと。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒ドライアイスとは?ドライアイスから発生する白い煙の正体って何?⇒スプーンをドライアイスに付けると音がする仕組みとは?⇒結露とは何か?仕組みを分かりやすく図解!⇒粉塵爆発とは何か?粉塵爆発の原理をわかりやすく図で解説!⇒なぜ熱は必ず温度が高い方から低い方へと移動するのか?⇒煙とは?黒い煙や白い煙の正体って何?⇒一酸化炭素中毒とは?発生する原因と仕組みについて簡単に解説!⇒熱伝導率とは何かをわかりやすく解説!熱伝導率が高い・低いとは?⇒氷とドライアイスと液体窒素の違いとは?最も温度が低いのはどれ?⇒絶対零度とは?また絶対零度の温度は何度なのか?
-
さてドライアイスをペットボトルなどの容器に入れてから密閉して、少し時間が経つとその容器が爆発するというのをご存知でしょうか。中にはドライアイスで爆発させる遊びをしている話を聞きますがとても危険な行為で、実際に爆発した容器の欠片が飛んできて大ケガをした人もたくさんいます。そして遊びではなくただの興味本位で試してしまう人も多いです。そこでこのページでは、ドライアイスを密閉した容器に入れると爆発する仕組みを解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次ドライアイスを密閉した容器に入れると爆発する仕組みとは?まとめ1.ドライアイスを密閉した容器に入れると爆発する仕組みとは?ではドライアイスを密閉した容器に入れると爆発する仕組みを見ていきましょう。結論から言ってしまうと密閉した容器にドライアイスを入れることで爆発するのは、ドライアイスが気体の二酸化炭素に変化することで容器内の圧力が大きくなるからです。まずドライアイスというのは簡単に言えば、二酸化炭素が固体になったものです。ドライアイスは-79℃以下の低温の物体で、-79℃よりも温度が高くなると固体から気体の二酸化炭素に変化していきます。(固体から液体にならずに気体に変化することを昇華と言います)ですので特殊な設備がない限り、ドライアイスは固体から気体に変化していきます。さらにドライアイスが固体から気体の二酸化炭素に変化することで、二酸化炭素の体積は固体の状態よりも約800倍にも膨れ上がります。以上を踏まえて、ドライアイスが爆発する仕組みを簡単に図にすると下のようになります。上図のように密閉された容器内にドライアイスを入れることで容器内の空気に暖められ、次第に気化して体積が膨張した二酸化炭素が増えるのでパンパンになっていきます。そしてドライアイスから気化して体積が膨張した二酸化炭素により、容器内部の圧力が大きくなるので最後には容器が耐えられなくなり爆発が起こるんですね。ドライアイスによるこのような爆発は、”密閉された容器でのみ”発生する可能性があります。密閉されていない容器であれば気体になった二酸化炭素も、容器の外へと逃げていくため容器内で圧力がたまって爆発することはなくなります。ペットボトルだけでなくビンやごみ袋などでも、密閉されていれば十分に爆発する危険性があるので注意が必要です。(爆発の衝撃によって飛び散った欠片で大ケガを伴います)また容器内に水を入れた状態でドライアイスを入れると、水は空気よりも熱を伝達しやすいのでドライアイスがより早く気化してしまいます。つまり何も入っていない状態の容器にドライアイスを入れたときよりも、水などの飲料が入っている方が爆発する時間が早くなります(密閉していればの話です)。暑い時期になると飲み物を冷やすためにドライアイスを入れたり、炭酸水を作れるかどうかを調べるためにドライアイスを入れる人が多いです。実際に事故も発生しているので、密閉した状態では真似しないでください。(密閉されていない状態でも、ドライアイス自体が不衛生な場合もあるのであまりお勧めはしません)関連:ドライアイスとは?ドライアイスから発生する白い煙の正体って何?関連:なぜ水の中にドライアイスを入れるとブクブクと泡立つのか?以上が「ドライアイスを密閉した容器に入れると爆発する仕組みとは?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、密閉した容器内でドライアイスを入れると爆発するのは、ドライアイスが気体の二酸化炭素に変化することで容器内の圧力が大きくなるから。水(飲み物)にドライアイスを入れると気化しやすくなるので、早く爆発する。爆発の衝撃によって、容器の欠片が飛び散って危険なので真似しないこと。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒沸騰したお湯にドライアイスを入れると爆発するのか?⇒スプーンをドライアイスに付けると音がする仕組みとは?⇒ドライアイスの安全な処理方法とは?またどういう処理が危険なのか?⇒密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?⇒一酸化炭素中毒とは?発生する原因と仕組みについて簡単に解説!⇒流体とは何かをわかりやすく解説!圧力はどんなかかり方なのか?⇒粉塵爆発とは何か?粉塵爆発の原理をわかりやすく図で解説!⇒なぜ水温と気温は同じなのに体感温度が違うのか?⇒氷とドライアイスと液体窒素の違いとは?最も温度が低いのはどれ?⇒液体の膨張と圧縮とは?温度によって液体の体積が変化する仕組みを図解!
-
さてあなたは氷とドライアイスと液体窒素についてご存知でしょうか。私たちは日常的に氷とドライアイスを利用することはありますが、液体窒素を利用することは実験以外ではほとんどないですよね。これらが利用される目的は主に他のモノを冷やすためですが、一体どんな物質から出来ているのか疑問に感じる人も多いですよね。そこでこのページでは氷とドライアイスと液体窒素の違いとは何か?またこれらの中で最も温度が低いのはどれなのかを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次氷とドライアイスと液体窒素の違いについて氷とは?ドライアイスとは?液体窒素とは?まとめ1.氷とドライアイスと液体窒素の違いとは?では氷とドライアイスと液体窒素の違いを見ていきましょう。結論から言ってしまうと氷とドライアイスと液体窒素の違いとして、それぞれを構成している物質が異なります。簡単にまとめると、氷(固体)⇒水(液体)が固体に変化したものドライアイス(固体)⇒二酸化炭素(気体)が固体に変化したもの液体窒素(液体)⇒窒素(気体)が液体に変化したものこのように氷とドライアイスと液体窒素では、それぞれを構成している物質が違います。関連:状態変化とは何か?物質が状態変化する仕組みを簡単に図解!さて氷とドライアイスと液体窒素について詳しく解説していきますね。氷とは?氷とは、水(液体)が固体に変化したものです。私たちが日常的に他のモノを冷やすときに使用しているのが”氷”です。例えば飲み物を冷やす目的でコップの中に入れたり、食材の周囲に氷を置いておき一時的に温度を保たせるようなときに利用されていますよね。液体である水が固体(氷)に変化し始めるのは(このときの温度を凝固点)、ほとんどの人が知っている通り水の温度が0℃になったとき(1気圧の場合)です。氷の温度は通常であれば冷凍庫から取り出したときで約-15℃から-20℃になります。しかし氷自体の温度は周囲の環境によっても大きく変化するので、冷凍庫よりも温度が低い環境であれば氷の温度はより低くなります。その方法によっては物質の最低温度である約-273℃近くまで下がるので、氷の温度は一定でなく周囲の環境で変化するということは覚えておきましょう。関連:1気圧とは?また何ヘクトパスカル(hPa)なのか?関連:絶対零度とは?また絶対零度の温度は何度なのか?ドライアイスとは?ドライアイスとは、二酸化炭素(気体)が固体に変化したものです。私たちに馴染みのある二酸化炭素というのは空気中に存在する気体の状態のもので、その気体の二酸化炭素の温度がある温度以下にまで下がると固体(ドライアイス)に変化します。二酸化炭素は状態によってそれぞれ名称があって”気体は炭酸ガス”、”液体は液体二酸化炭素”、”固体はドライアイス”と呼ばれています。ドライアイスの見た目は白い塊(固体)で、ドライアイス自体の温度は-79℃以下とかなりの低温です。(氷と同様に一定の温度ではなく、方法によっては約-273℃付近まで下がる)二酸化炭素が固体になったドライアイスは特殊な性質があって、氷のように溶けると液体にはならずに気体の二酸化炭素に変化していきます。(液体にはならずに固体から気体に状態が変化することを”昇華”と言います)このような性質からドライアイスは液体にならずに他のモノを冷やすことができるので、溶けると水になってしまう氷と比べてとても便利です。(便利な反面、氷よりも温度がかなり低く危険でもあります)ただドライアイスが昇華するのは周囲の気圧の大きさが常圧の場合で、二酸化炭素にかかる周囲の圧力が大きくなれば液体に変化することになります。実際に深海では水によってかかる圧力(水圧)がとても大きいため、液体の二酸化炭素が溜まっている場所があるということも分かっています。関連:ドライアイスとは?ドライアイスから発生する白い煙の正体って何?液体窒素とは?液体窒素とは、窒素(気体)が液体に変化したものです。液体窒素は日常的に使用されることはほとんどありませんが、テレビなどの実験で使用されているのを見たことがあるという人は多いと思います。容器の中に液体窒素を入れて、その中にモノを入れると瞬時に凍るというような実験です。液体窒素の中にバラを入れ取り出して握るとパリパリと音がして粉々になったり、液体窒素にバナナを入れて凍らせるとバナナで釘が打てるようになるといったものです。また液体窒素の見た目は無色透明の液体(水みたい)で、温度は-196℃以下とドライアイスよりも低温です。液体窒素が-210℃に達すると、液体から固体の窒素に変化します。なので方法によっては氷やドライアイスと同様に温度が下がり、-196℃から-210℃になるまで温度を下げることは可能です。よく液体窒素が-196℃と言われるのは私たちが生活している空間(気温・圧力)では、-196℃以下を維持できないのですぐに気体の窒素に変化してしまうからです。(液体窒素の状態を維持できず、少しずつ気体に変化していきます)氷とドライアイスと液体窒素の温度とその状態について、少しややこしく感じてしまうと思うので簡単に下の図でまとめます。このようにまとめて図にしてみるとイメージしやすいですね。関連:気圧と沸点の関係について。気圧によって沸点が変化する仕組みとは?以上が「氷とドライアイスと液体窒素の違いとは?最も温度が低いのはどれ?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、氷とは、水が氷に変化したもの。ドライアイスとは、二酸化炭素が固体に変化したもの。液体窒素とは、窒素が液体に変化したもの。温度が低い順に並べると、”液体窒素(-196℃以下)<ドライアイス(-79℃以下)<氷(0℃以下)”となる。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒ドライアイスとは?ドライアイスから発生する白い煙の正体って何?⇒沸騰したお湯にドライアイスを入れると爆発するのか?⇒なぜ水の中にドライアイスを入れるとブクブクと泡立つのか?⇒スプーンをドライアイスに付けると音がする仕組みとは?⇒ドライアイスの安全な処理方法とは?またどういう処理が危険なのか?⇒ドライアイスを密閉した容器に入れると爆発する仕組みとは?⇒一酸化炭素中毒とは?発生する原因と仕組みについて簡単に解説!⇒凝結と結露の違いとは?⇒煙とは?黒い煙や白い煙の正体って何?⇒熱と温度の違いとは?