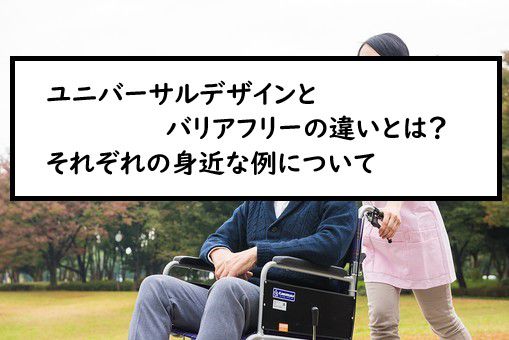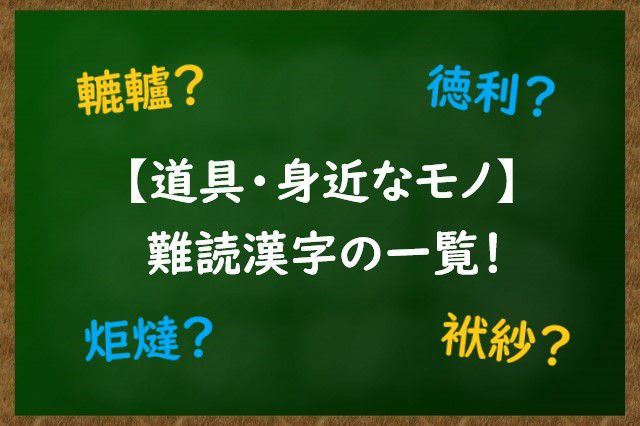さてあなたはユニバーサルデザインとバリアフリーという言葉をご存知でしょうか。これらはよく似ている言葉として意味が混同されて覚えられていますが、ユニバーサルデザインとバリアフリーには明確な違いがあります。違いを理解していなくても日常生活で困ることはないですが、疑問に思ってしまったら答えを知るまでモヤモヤしてしまいますよね。そこでこのページではユニバーサルデザインとバリアフリーの違いとは?またそれぞれの身近な例について簡単に解説しています。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次ユニバーサルデザインとバリアフリーの違いについてユニバーサルデザインとは?バリアフリーとは?それぞれ身近な例としてはどんなものがある?ユニバーサルデザインの例バリアフリーの例まとめ1.ユニバーサルデザインとバリアフリーの違いについてではユニバーサルデザインとバリアフリーの違いを見ていきましょう。結論から言ってしまうとユニバーサルデザインとバリアフリーの大きな違いは、誰が使いやすいように設計されたものなのかです。ユニバーサルデザインは”すべての人に使いやすいように設計されたもの”で、バリアフリーは”高齢者・障害者に使いやすいように設計されたもの”になります。どちらも使いやすいように設計されているという点では同じですが、上記のように誰を対象として設計されているかが違います。またユニバーサルデザインの”すべての人”というのは、もちろん高齢者・障害者の人も含まれています。なのでバリアフリーよりもユニバーサルデザインの方が、誰を対象としているものなのか、その範囲が広いということですね。さてユニバーサルデザインとバリアフリーそれぞれについて解説していきます。ユニバーサルデザインとは?ユニバーサルデザインとは、すべての人に使いやすいように設計されたものを言います。ユニバーサルデザインは英語にすると、”Universal(すべてに共通) Design(設計)”という意味です。すべての人に使いやすいように共通して設計されているから、ユニバーサルデザインと言うんですね。ユニバーサルデザインで指している”すべての人”というのは、文字通り年齢・性別・国籍・障害などに関係なくすべての人のことです。ただすべての人といっても意味合い的には、ほとんどの人と言った方が合っているかもしれません。ユニバーサルデザインとして設計されているものでも、特定の障害を持った人には役に立たないデザインのものも存在します。ですのでユニバーサルデザインが対象としているのはすべての人ではなく、ほとんどの人・多くの人という意味合いで認識していてください。またユニバーサルデザインには7つの原則が存在していて、それは下記の通りです。①公平な実用性②柔軟性③簡単で直感的に理解して使える④感覚的に簡単に理解できる情報⑤エラーへの対応⑥身体的負担を少なくする⑦利用しやすい大きさと空間ユニバーサルデザインはこの7つの原則(考え方)を元に設計されています。バリアフリーとは?バリアフリーとは、高齢者・障害者に使いやすいように設計されたものやその考え方を言います。バリアフリーは英語にすると、”Barrier(障壁) free(自由)”という意味です。つまり障壁を取り除いて自由に生活するという意味から、バリアフリーという言葉が使用されているんですね。ちなみにバリアフリーは先に障害となるものがすでに存在していて、その障害を取り除いて生活を良くするために様々なものが設計されています。なのでユニバーサルデザインは最初からすべての人に使いやすいように設計されていますが、バリアフリーは後から高齢者・障害者に使いやすいように設計されているという違いもあります。さて次の章では実際に身近な例としてどのようなものがユニバーサルデザインやバリアフリーとされているのか解説していきます。2.それぞれ身近な例としてはどんなものがある?ではユニバーサルデザインとバリアフリーの身近な例ではどんなものがあるのか見ていきましょう。ユニバーサルデザインの例バリアフリーの例自動ドア点字ブロックセンサー式の蛇口駐車場のスペースシャンプー容器の凸凹ノンステップバス様々なマークスロープ段差を設けない項目1項目2)★ -->まずそれぞれの身近な例を挙げると上記のようなものがありますが、聞いただけでは分からないという人もいると思うので簡単に見ていきましょう。ユニバーサルデザインの例自動ドア自動ドアは人の出入りを感知して、自動で開閉する扉のことです。普通の扉であれば両手に荷物を持っている状態で開けるのは大変ですが、自動ドアの場合は荷物を持っていようと自動で開閉してくれます。このように誰にでも使用しやすいように設計されているので、自動ドアはユニバーサルデザインの例として分かりやすいでしょう。センサー式の蛇口センサー式の蛇口もユニバーサルデザインの良い例です。センサー式の蛇口でなければハンドルをひねったりすると水が出てきますが、ときには固く閉められているときもあります。これによって手の力が弱い人や手に障害を持っている人は、固く閉められた蛇口のハンドルをひねることができません。ですがセンサー式の蛇口であれば誰でも簡単に水を出すことが可能です。さらにセンサー式の蛇口はどこにも汚れた手で触れることなく、自動で水が出て手を洗うことができるのでとても衛生的です。シャンプー容器のギザギザシャンプーの容器にギザギザが付けられているのはご存知でしょうか。髪を洗っているときはシャンプーなどが目に入って来るかもしれないので、目を閉じたままシャンプーやリンスのボトルのポンプを押すことも多いですよね。目が見えていない状態だと「どっちがシャンプー?どっちがリンス?」と、分からなくなってしまうことも多いと思います。ですがシャンプーの容器にギザギザが付いていることで、「ボトルにギザギザが付いている方がシャンプー!」と判断することができます。(ボトルにギザギザがないものはリンスかコンディショナーになります)これも数多くあるユニバーサルデザインのひとつで、簡単にシャンプーかどうかを判断できるようにするために考えられたものです。また容器によってはボトルの側面以外に付いている場合も多いので、自分が使用しているシャンプーはどこにギザギザが付いているのか確認してみてくださいね。様々なマークよく街中や施設の中で上のようなマークを見ることってありますよね。この様々なマークもユニバーサルデザインのひとつです。例えば外国人が日本に遊びに来ているときに、トイレに行きたくなったら周囲にトイレがないか探しますよね。ですが上のようなマークではなく日本語で「トイレはあっち!」と示されていても、その外国人が日本語を読めなければ意味がありません。なので誰にでも簡単に伝わるように上のようなマークにして知らせているんですね。このように一目見て簡単に意味が分かるようなマークが、ユニバーサルデザインとして使用されています。段差を設けない段差を設けないのもユニバーサルデザインによるものです。車いすの人にとって段差はとても嫌なもので、その段差が大きければ一人で行きたい場所に行くことができません。車いす以外の人にとっても急に段差があるような場所では、歩いている途中でその段差につまづいて転倒する原因にもなります。ですがはじめから段差を設けなければこんなことは起こりません。なので段差がないというのもユニバーサルデザインに当てはまるんですね。バリアフリーの例点字ブロック点字ブロックというのは歩道や公共の建物や、駅のホームなどに敷設されている視覚障害者誘導用のブロックです。上の写真のように黄色いブロックに突起が付いているもので、足裏の感覚で突起の種類を認識することで視覚障害者を誘導します。線状になっているブロックは進行方向を表していて、点状になっているブロックは危険位置などを表しているものになります。点状ブロックは、階段の前・横断歩道の前・線状ブロックが交差する分岐点などに敷設されます。視覚障害者にとっては歩行する際になくてはならない設備です。駐車場のスペース駐車場に車を止めておくときに、車いすマークのスペースを見たことがあると思います。これは車いすの人が乗っている車だけ止めて良いというマークではなく、障害者が乗っている車であればどんな障害を持っているかに関係なく止めても良いことを意味します。その障害がたとえ体を動かすことに不自由がない人でも、障害を持っていればこのマークの場所に駐車することは問題ないんですね。他にも妊婦・高齢者・ケガ人は車いすマークの駐車場を使用して良い場合がありますが、これはその駐車場を管理している側の決め方によって違います。なので車いすマークであれば絶対にどの駐車場でも、妊婦・高齢者・ケガ人が使用しても良いというわけではありません。(もともと車いすのマークには”障害者”という意味しかない)ただし中には車いすマークの他に妊婦・高齢者・ケガ人のマークが表示している駐車場もあるので、そのような表示がされていれば駐車することができるので覚えておきましょう。関連:駐車場の車椅子マークの意味とは?また駐車しても良いのはどんな人?ノンステップバスノンステップバスというのは、出入口の段差を無くしたバスのことです。(低床バスとも呼ばれています)出入り口の段差を無くして乗降性を高めることで、お客さんへの負担を少なからず軽減することができます。若い人にとってはこのぐらいの段差は大したことないですが、高齢者にとって段差を上がるのはなかなか苦労しますよね。中には車いすの人用にドアの前にスロープが設置されるバスもあります。スロープスロープは斜面や勾配を意味している言葉です。車いすの人は大きな段差があると車いすでは移動できないので、車いすで移動するための道として上の写真のようなスロープが設けられます。またスロープと言っても上の写真のような大きなものではなく、施設の中のちょっとした段差をなくすために小さなスロープを設けることもあります。その際は車いすだけでなく高齢者のつまづき防止としての役割も含んでいます。他にもユニバーサルデザインとバリアフリーの考え方で設計されたものは多いので、時間があるときにどのようなものがあるのか探してみてはいかがでしょうか。以上が「ユニバーサルデザインとバリアフリーの違いとは?身近な例について」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、ユニバーサルデザインとは、すべての人(年齢・性別・国籍・障害に関係なく)に使いやすいように設計されたもの。バリアフリーとは、高齢者・障害者に使いやすいように設計されたものやその考え方のこと。これらの違いは、誰に使いやすいように設計されたものなのか。ユニバーサルデザインは最初から使いやすいように設計されているが、バリアフリーは後から障害を取り除くように設計されている。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒駐車場の車椅子マークの意味とは?駐車しても良いのはどんな人?⇒室内と屋内の違いとは?⇒野外と屋外と戸外の違いとは?⇒地平線と水平線の違いとは?⇒物理的とは?意味や対義語と”物理的に無理”って何?⇒和英辞典と英和辞典の違いとは?⇒借りると貸すの違いとは?貸りると借すは間違いなのか?⇒上り坂と下り坂の数はどちらが多いのか知ってる?⇒当て字とは何か?かっこいい当て字・日常で使用される当て字の一覧!⇒箱入り娘と箱入り息子の意味とは?良い意味なのか悪い意味なのか?
ギモン雑学
「 身近 」の検索結果
-
-
このページでは道具・身近なモノの難読漢字について簡単に一覧にしてまとめています。(道具・身近なモノの難読漢字を新しく見つけ次第、追記していきます)どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次↓道具・身近なモノの難読漢字の読み方や説明、写真などを載せています◆【ア行~】◇【カ行~】◆【サ行~】◇【タ行~】◆【ナ行~】◇【ハ行~】◆【マ行~】◇【ヤ行~】◆【ラ行~】◇【ワ行~】↓道具・身近なモノの難読漢字とその読み方だけをザっと見たい方はこちら(同ページのリンクへ移動します)●道具・身近なモノの難読漢字(一覧表)↓関連ページはこちら(同ページのリンクへ移動します)★関連ページ道具・身近なモノの難読漢字※1:漢字表記が複数ある場合は、一般的に使われることが多いほうの漢字表記を優先しています。例 【行灯(行燈)】 ⇒ 【一般的に使われることが多い漢字表記(比較して一般的に使われることが少ない漢字表記)】※2:読み方が複数ある場合は、一般的に読まれることが多い読み方を優先し、どちらも一般的に読まれることが多い場合は五十音順に表記しています。例 【風車】 読み方:かざぐるま、ふうしゃ (どちらも一般的に読まれることが多いため五十音順で表記)↓ア行~【痣】読み方:あざ痣は”(色素の増加や内出血などによって)皮膚の一部にできる赤・紫・青色などの変色箇所のこと”の意味。【足枷】読み方:あしかせ足枷は”罪人の足にはめて歩行の自由を奪う刑具のこと/(転じて)生活や行動の自由を妨(さまた)げるもの”の意味。後者の意味は例えば、「家族が行動の足枷になっている」や「彼の人生の足枷になってしまうことを恐れた」のように用いられます。【畦道】読み方:あぜみち※上は畦道の写真※上は農道の写真畦道は”田と田の間の細い道のこと”の意味。農道とは「農業用道路」を略したもので、”農作業のために設けられた道のこと”です。農道も田と田の間に作られていることが多く、畦道と少し似ていますが、畦道と間違えないように注意が必要です。【鐙】読み方:あぶみ鐙は”馬具のひとつで、鞍(くら)の両脇(りょうわき)に垂らして、乗り手が足をのせるもの”の意味。【行灯(行燈)】読み方:あんどん※上は行灯(あんどん)の写真行灯(行燈)は”木や竹などの枠に紙を貼り、その中に油皿を置いて火をともす照明具のこと”の意味。現在では中に火をともすのではなく、電球を入れたりすることも多いです。※上は提灯(ちょうちん)の写真もともと持ち運ぶためのものであったため、「行灯」という字が当てられていました。ですがその後に持ち運びやすいように進化した「提灯(ちょうちん)」ができたので、行灯は”据置(すえおき)用”、提灯は”携行(けいこう)用”として使用されるようになりました。【庵(廬)】読み方:いおり庵(廬)は”草木などを材料として作った粗末な家・小屋のこと”の意味。【筏】読み方:いかだ筏は”木材・竹などを並べてつなぎ合わせ、水に浮かべるもの”の意味。木材の運搬や舟(ふね)の代わりに用いられます。(舟というのは、手で漕ぐ小型のものを指します)【鋳型】読み方:いがた鋳型は”鋳物(いもの)を作るために、溶かした金属を流し込む型のこと”の意味。鋳物というのは、”溶かした金属を鋳型に流し込んで製造された器物のこと”です。【錨(碇)】読み方:いかり錨(碇)は”船を一定の場所に留めておくために、綱(つな)や鎖をつけて海底に沈めるおもり。アンカーのこと”の意味。【生け簀(生簀)】読み方:いけす生け簀(生簀)は”魚介類を生きたままにしておくための水槽や施設のこと”の意味。漁獲(ぎょかく)した魚介類を料理・販売などに使用するまでの間、一時的に飼育するための水槽・施設などのことを指します。【衣桁】読み方:いこう衣桁は”室内で衣類などを掛けておく道具のこと”の意味。木を鳥居のような形に組んで台の上に立てたもので、衝立(ついたて)式のものと、2枚に折れる屏風(びょうぶ)式のものがあります。【漁火】読み方:いさりび漁火は”夜に魚を誘うために漁船で焚(た)く火のこと”の意味。【椅子】読み方:いす椅子は”腰を掛ける道具のこと/官職・役職などの地位のこと”の意味。後者の意味は例えば、「彼は幹部の椅子を狙っている」や「社長の椅子には興味がない」のように用いられます。【疣】読み方:いぼ疣は”皮膚上に盛り上がってできる小さなできもののこと/物の表面にある小さな突起のこと”の意味。前者の疣はヒトパピローマウイルスが皮膚表面の傷から感染して生じるもので、人から人への直接接触だけでなく、プール・ジムなどの間接接触でも感染します。【鋳物】読み方:いもの鋳物は”溶かした金属を鋳型(いがた)に流し込んで製造された器物のこと”の意味。鋳型というのは、”鋳物を作るために、溶かした金属を流し込む型のこと”の意味。【甍】読み方:いらか※上は前者の意味の甍甍は”屋根の背。屋根の頂上の部分のこと/屋根瓦(やねがわら)。また、瓦葺(かわらぶ)きの屋根のこと”の意味。【刺青】読み方:いれずみ(しせい)「いれずみ」は、一般的には「入れ墨」と表記されることが多いです。刺青は”皮膚に針や小刀などで傷をつけて墨などを入れ、文字・絵・模様などを描くこと。また、その彫り物のこと”の意味。刺青は「入れ墨」や「タトゥー」と呼ばれることもありますが、刺青・入れ墨・タトゥーはどれも指している意味は同じです。タトゥー(Tattoo)は、刺青(または入れ墨)を英語表記したものになります。【囲炉裏】読み方:いろり囲炉裏は”室内の床の一部を四角に切り抜いて、火をたくようにした場所のこと”の意味。囲炉裏は、主に暖房・煮炊きに用いられます。【岩室】読み方:いわむろ岩室は”岩壁(がんぺき)に自然にできた洞窟(どうくつ)のこと/岩に横穴を掘って住居にしたもの”の意味。【臼】読み方:うす※上は挽き臼(ひきうす)の写真※上は搗き臼(つきうす)と杵(きね)の写真臼は”穀物や豆類などを粉にしたり、餅(もち)をついたりする道具のこと”の意味。臼には「挽き臼(ひきうす)」と「搗き臼(つきうす)」があり、挽き臼で穀物や豆類などを粉にし、搗き臼(と杵)で餅をついたりします。【団扇】読み方:うちわ団扇は”あおいで風を起こす道具のこと”の意味。【畝(畦)】読み方:うね”畦”は「うね」と読むこともできますが、一般的に”畦”は「あぜ」と読まれることがほとんどです。畝は”作物を植えつけたり種を蒔(ま)いたりするために、一定の幅で土を盛り上げたところのこと”の意味。【産衣】読み方:うぶぎ産衣は”生まれたばかりの赤子に着せる衣服のこと”の意味。【産毛】読み方:うぶげ産毛は”生まれた時にすでに生えている細く柔らかい毛のこと。また、そのような細く柔らかい毛のこと”の意味。【雲母】読み方:うんも(きらら)雲母は”単斜晶系、六角板状の結晶をしているケイ酸塩の鉱物のこと”の意味。「きらら」は、「うんも」の別名。雲母は薄く剥(は)がれやすく、光沢があり、耐火性が強く、熱・電気の絶縁に利用されます。雲母の種類には、白雲母(しろうんも)・黒雲母(くろうんも)などの種類が存在します。【烏帽子】読み方:えぼし烏帽子は”昔、成人した男子がつけた被り物のひとつ”の意味。いま現在では、烏帽子は儀式などにおける被り物として用いられることが多いです。烏帽子は布や紙で作られたものがあり、立(たて)烏帽子・風折(かざおり)烏帽子・侍(さむらい)烏帽子などの種類があります。【襟】読み方:えり襟は”衣服の、首の周りの部分。また、そこにつける縁取(ふちど)りの布のこと”の意味。【縁石】読み方:えんせき縁石は”歩道と車道、または歩道と私有地などの境界に置くコンクリート製のブロックのこと”の意味。【縁台】読み方:えんだい縁台は”庭や露地などに置く、木などで作られた細長い腰掛けのこと”の意味。【大鋸屑】読み方:おがくず大鋸屑は”鋸(のこぎり)で木材を切るときに出る木屑(きくず)のこと”の意味。【桶】読み方:おけ桶は”細長い板を縦に円筒形(えんとうけい)に並べて底をつけ、箍(たが)で締めた容器のこと”の意味。箍というのは、”桶・樽(たる)などの周りに巻いて、締めつけるための竹や金属製の輪のこと”です。【白粉】読み方:おしろい白粉は”顔などに塗り、色を白く見せるための化粧品のこと”の意味。ファンデーションなどの化粧品が一般的になる前は普及していましたが、いま現在では舞台俳優・芸者・舞妓が化粧に使用するぐらいです。白粉の種類には粉おしろい・水おしろい・練りおしろい・紙おしろいなどの種類が存在します。ちなみに昔の白粉には「鉛(なまり)」などの毒性の強い物質が含まれていて、それにより中毒にかかり、様々な病気になってしまい死に至ることも多かったです。(いま現在では無鉛の白粉が使用されています)【御虎子】読み方:おまる御虎子は”病人や小児(しょうに)が使用する、持ち運びのできる便器のこと”の意味。【重石】読み方:おもし重石は”物を押さえるのに用いる石のこと”の意味。【玩具】読み方:おもちゃ(がんぐ)玩具は”子供が持って遊ぶ道具のこと”の意味。【自鳴琴】読み方:オルゴール(じめいきん)自鳴琴は”短い楽曲を自動的に演奏する装置を小箱などに組み込んだもの”の意味。「じめいきん」は、「オルゴール」の別名。表面にトゲを付けた円筒や円盤がぜんまい仕掛けなどで回転し、順番にトゲが音階板に触れていき音を出す仕組みになります。【音叉】読み方:おんさ音叉は”音響測定、楽器の調律などに用いる道具のこと”の意味。音叉はU字型の鋼鉄棒に柄を付けた道具のことで、軽く打って一定の振動数の音を発生させ、音の実験や調律などに用いられます。↓カ行~【櫂】読み方:かい櫂は”手に持って水をかくことで生じる抵抗を利用して船を進める船具のこと”の意味。ちなみに櫂には「オール(oar)」と「パドル(paddle)」があり、これらの違いは”櫂が船体に固定されているかどうか”になります。オールは”器具などで船体に櫂が固定されたまま使用”し、パドルは”船体に櫂が固定されず漕(こ)ぎ手が支えながら使用”します。※上はボートでオール(固定されている)を使用している写真※上はカヌーでパドル(固定されていない)を使用している写真なのでボートではオール(固定されている)、カヌー・カヤックなどではパドル(固定されていない)を使用しているというわけです。(必ずしもボートだからオールというわけではなく、ボートによっては船体に固定されていないパドルを使用することもあります)【碍子】読み方:がいし碍子は”電線を絶縁し支持するために鉄塔や電柱などに取り付ける器具のこと”の意味。碍子は、陶磁器やプラスチックなどで作られています。【外套】読み方:がいとう外套は”防寒などのために衣服の上に着る上着のこと”の意味。【懐炉】読み方:かいろ懐炉は”懐(ふところ)や衣服の内側に入れて体を温める道具のこと”の意味。【案山子(鹿驚)】読み方:かかし案山子(鹿驚)は”田畑の作物を荒らす鳥獣を防ぐために立てる人形や似たような仕掛けのこと”の意味。人間が田畑で農作業していると鳥などが近寄らないことから、人間の形を模(も)した案山子を置くことにより、鳥獣除けとして用いられています。【篝】読み方:かがり篝は”篝火(かがりび)を焚(た)く鉄製の籠(かご)のこと”の意味。篝火というのは、”夜間の警護・照明、漁をするためなどに鉄製の籠の中で焚く火のこと”です。【垣根】読み方:かきね垣根は”家の周囲や庭などの囲いや仕切りのこと/他との間を隔(へだ)てるもの”の意味。垣根(前者の意味)は、一般的には植木(うえき)や竹で作ったものが多いです。「生垣(いけがき)」は”植木で仕切りを作ったもの”を指し、「竹垣(たけがき)」は”竹で仕切りを作ったもの”を指します。なので簡単に言うと、「生垣・竹垣・石垣など」は垣根の種類のひとつになります。後者の意味の垣根は例えば、「両者の垣根を取り払う」や「国の垣根を超えた友情だ」のように用いられます。【額縁】読み方:がくぶち額縁は”絵画などをはめて飾るための枠(わく)のこと”の意味。【画材】読み方:がざい画材は”絵になる材料。絵の題材のこと/絵を描くときに使う材料のこと”の意味。後者の意味は、絵の具・筆・キャンバスなどのことを指します。【風車】読み方:かざぐるま、ふうしゃ※上は風車(かざぐるま)の写真※上は風車(ふうしゃ)の写真「かざぐるま」と読むと”紙などで作られた羽根車に柄を付け、風を受けて回る玩具(おもちゃ)のこと”の意味。「ふうしゃ」と読むと”羽根車を風の力で回転させ、動力を得る装置のこと”の意味。【瘡蓋(痂)】読み方:かさぶた瘡蓋(痂)は”傷などの表面から出た分泌物が乾いて固まってできる皮のこと”の意味。傷ができると瘡蓋が形成されるのは、傷の中に細菌や汚れなどが入るのを防ぐためなので、痒(かゆ)くても瘡蓋を剝がすのは良くないです。瘡蓋は血液中の血小板(けっしょうばん)・赤血球、血液を固めるタンパク質であるフィブリンなどにより形成されています。【風見鶏】読み方:かざみどり風見鶏は”鶏(にわとり)をかたどった風見(かざみ)のこと”の意味。風見というのは”風の吹く方向を知る道具のこと”で、建物の屋根などに取り付けられます。【瓦斯】読み方:ガス瓦斯は”気体/燃料用の気体/毒ガス/海上や山に発生する濃霧/ガソリン/おなら”の意味。【鎹】読み方:かすがい鎹は”材木と材木とを繋ぎとめるために打ち込む、両端の曲がった大釘(おおくぎ)のこと”の意味。【絣(飛白)】読み方:かすり絣(飛白)は”所々かすったような模様を規則的に配した模様。また、その織物(おりもの)のこと”の意味。【帷子】読み方:かたびら帷子は”裏地を付けない衣服のこと”の意味。【滑車】読み方:かっしゃ滑車は”周りに溝(みぞ)のある車に綱(つな)をかけて回転させる装置のこと”の意味。滑車は”力の方向や大きさを変えるためのもの”で、複数の滑車を組み合わせることでより大きな効果が得られます。【合羽】読み方:かっぱ合羽は”雨のときに着る防水性の上着のこと”の意味。【割烹着】読み方:かっぽうぎ割烹着は”家事や料理をするときに着る上っ張り(うわっぱり)のこと”の意味。上っ張りというのは、”衣服の汚れを防ぐためなどに、上に羽織(はお)って着るもの”を指します。【鬘】読み方:かつら鬘は”(毛髪を補う目的で)頭髪のように作って、頭に被(かぶ)ったり付けたりするもの”の意味。【門松】読み方:かどまつ門松は”正月に、家の門口(かどぐち)に立てる飾りの松のこと”の意味。門口というのは”家や門の出入口のこと”で、門口に飾る松なので「門松(かどまつ)」と言い、竹を添える場合が多いです。門松は、年神(としがみ)を家に迎えるための依り代(よりしろ)であるとされています。【鼎】読み方:かなえ鼎は”古代中国で使われた、食物を煮るのに用いる(普通は3本脚の)金属製の器のこと”の意味。【曲尺(矩尺)】読み方:かねじゃく曲尺(矩尺)は”大工などが使う、直角に曲がった金属製のものさしのこと”の意味。【鞄】読み方:かばん鞄は”革・布などで作り、中に物を入れて持ち歩く用具のこと”の意味。【黴】読み方:かび※上は黴(白い毛のような部分)のついた苺の写真黴は”生物体・有機物の表面に生じる菌類またはその菌糸の集まりのこと”の意味。黴には有害なものと、発酵などに必要な有用なものがあります。(上の写真の苺に生えた黴は、有害なものなので食べないようにしましょう)例えば発酵に必要な有用なもので言えば、アオカビを用いて製造されるブルーチーズや、コウジカビを用いて製造される日本酒・醤油(しょうゆ)などが有名です。【画鋲】読み方:がびょう※上は画鋲と画鋲抜きの写真画鋲は”紙などを壁や板などに留めるための鋲(びょう)のこと”の意味。【蝦蟇口】読み方:がまぐち蝦蟇口は”(開いた口が蝦蟇(がま)の口に似ていることから)口金のついた小銭入れのこと”の意味。蝦蟇は”ヒキガエルの俗称のこと”で、口金(くちがね)は”器物の口につける金具のこと”を指します。【兜】読み方:かぶと兜は”頭部を守るための被(かぶ)り物のこと”の意味。【釜】読み方:かま釜は”飯を炊いたり湯を沸かしたりするのに用いる金属製の器のこと”の意味。円形で鍋よりも底が深く、普通は胴の周りに竈(かまど)にかけるための鍔(つば)があり、蓋(ふた)は木製です。釜の鍔を羽根に例えて「羽釜(はがま)」と呼ぶこともあります。【竈】読み方:かまど竈は”上に鍋・釜(かま)をかけて煮炊きするための設備のこと”の意味。【裃】読み方:かみしも裃は”江戸時代の武士の礼服で、肩衣(かたぎぬ)と袴(はかま)を同じ色に染めたもの”の意味。肩衣というのは、”上代、庶民(しょみん)の着た衣で、袖(そで)がなく肩と胴だけをおおう上着のこと”を指します。【剃刀】読み方:かみそり剃刀は”髪やひげを剃(そ)るのに使う、鋭利な刃物のこと”の意味。【蚊帳】読み方:かや蚊帳は”麻(あさ)・木綿(もめん)などで網状に作り、蚊を防ぐために吊って寝床を覆(おお)うもの”の意味。「蚊帳の外」という慣用句がありますが、これは蚊帳の外に居ることで、蚊帳の外にいる者だけが蚊に刺されてしまうことからきている言葉です。「蚊帳の外」は”無視され、不利な扱いを受けること”や、”事情を知らされず、内情が分からない立場に置かれること”の意味として用いられます。蚊帳の外は例えば、「自分だけ蚊帳の外で面白くない」や「彼を蚊帳の外に置いて話し合いが進む」のように用いられます。【唐獅子】読み方:からじし唐獅子は”獅子(しし)を美術的に装飾化したもの”の意味。獅子というのは、”ライオンのこと”を指します。【硝子】読み方:ガラス硝子は”石英・石灰石・炭酸ナトリウムなどを高温で溶かし、冷却して作った透明な物質のこと”の意味。硬くて表面が滑らかであることから、表面に付いた汚れなどを落としやすく、窓ガラスなど様々なところで利用されています。硝子の表面にわざと細かな凹凸を付けた「磨(す)りガラス」という種類もあり、磨りガラスは「曇りガラス」や「つや消しガラス」とも呼ばれています。【歌留多(骨牌)】読み方:かるた歌留多(骨牌)は”遊びや博打(ばくち)に使う、絵や文字の書かれた長方形の小さい厚紙の札。また、それを使った遊びのこと”の意味。【枯山水】読み方:かれさんすい枯山水は”水を用いずに、石や砂によって山水を表現する庭園様式のこと”の意味。【画廊】読み方:がろう画廊は”絵画などの美術品を陳列(ちんれつ)・展示する場所。ギャラリーのこと”の意味。【簪】読み方:かんざし簪は”女性の頭髪に挿(さ)す髪飾りのひとつ”の意味。【鉗子】読み方:かんし鉗子は”主に外科(げか)手術用の、器官・組織などを挟んだりするために用いられる、鋏(はさみ)形の金属器具のこと”の意味。【橇】読み方:かんじき、そり※上は橇(かんじき)の写真※上は橇(そり)の写真「かんじき」と読むと”雪の上などを歩くとき、深く踏み込んだり滑ったりしないように、靴(くつ)などの下につけるもの”の意味。橇(かんじき)を靴などに装着することで、接地面積を大きくし、体重が分散されることで雪の上などを歩いたときに足が沈みにくくなったりします。「そり」と読むと”雪や氷の上を滑らせて走る乗り物または運搬具のこと”の意味。【岩礁】読み方:がんしょう岩礁は”海で水中に隠れている大きな岩。また、水面上にわずかに出ている岩のこと”の意味。【鉋】読み方:かんな鉋は”材木の表面を削ってなめらかにする大工道具のこと”の意味。【閂】読み方:かんぬき閂は”門の扉が開かないようにするための横木のこと”の意味。門扉(もんぴ)の左右にある金具に差し通して用いられます。【甲板】読み方:かんぱん甲板は”船の上部の、木や鉄板などを張り詰めた広く平らな床。船のデッキのこと”の意味。【甘味処】読み方:かんみどころ(あまみどころ)甘味処は”餡蜜(あんみつ)やお汁粉(おしるこ)など、甘い味の菓子を提供する飲食店のこと”の意味。【生糸】読み方:きいと※上は蚕の繭の写真生糸は”蚕(かいこ)の繭(まゆ)から取った、まだ精練していない糸のこと”の意味。【煙管】読み方:きせる(えんかん)※上は煙管(きせる)の写真「きせる」と読むと”刻みタバコを吸う道具のこと”の意味。「えんかん」と読むと”煙を通すための管のこと/きせるの別名のこと”の意味。【牛車】読み方:ぎっしゃ牛車は”主に平安時代に、牛にひかせた、貴人(きじん)を乗せるための屋形車(やかたぐるま)のこと”の意味。貴人というのは、”地位・身分の高い人のこと”です。【衣笠(絹傘)】読み方:きぬがさ衣笠(絹傘)は”絹を張った柄(え)の長い傘のこと/仏像などの頭上に吊るす絹張りの傘のこと”の意味。【杵】読み方:きね杵は”臼(うす)に入れた穀物などをつくための木製の道具のこと”の意味。【脚立】読み方:きゃたつ脚立は”2つの短い梯子(はしご)の上端を蝶番(ちょうつがい)などで繋いで板を取り付けた、八の字形に開いて用いる踏み台のこと”の意味。【脚絆】読み方:きゃはん脚絆は”旅や作業をするとき、動きやすくするために脛(すね)に巻く布のこと”の意味。【急須】読み方:きゅうす急須は”茶葉(ちゃば)を入れ、湯をさして茶を煎(せん)じ出すのに用いる、注ぎ口と取っ手のある小さな土瓶(どびん)のこと”の意味。【経木】読み方:きょうぎ経木は”杉・檜(ひのき)などの木材を紙のように薄く削ったもの”の意味。お菓子・料理の包装、たこ焼きなどで、お皿の代わりに用いられることが多いです。【香車】読み方:きょうしゃ香車は”将棋の駒(こま)のひとつ”の意味。香車は前方へだけ進むことができ、後ろへ下がることはできませんが、成(な)ると金将と同じ動き方をすることができます。【錐】読み方:きり錐は”板などに小さな穴をあけるための先の尖(とが)った工具のこと”の意味。【巾着】読み方:きんちゃく巾着は”布や革(かわ)などで作った、口をひもで締める小さな袋のこと”の意味。【楔】読み方:くさび楔は”堅い木材または金属で、一端が厚く、もう一方の端にいくにつれて薄くなるように作ったもの”の意味。楔は薄くなっている方を対象物に当てたり、隙間(すきま)などに差し込み、そのまま厚い端の方をハンマーで打ち込み使用します。木材・石材を割るとき、重いものを押し上げたり、差し込んだ材が抜け落ちるのを防ぐためなどに用いられます。【櫛】読み方:くし櫛は”髪の毛を梳(す)いたり、髪に挿(さ)して飾りに使ったりする道具のこと”の意味。【薬玉】読み方:くすだま薬玉は”式典・祝い事などで用いられる、割ると紙吹雪などが出る飾り物の玉のこと”の意味。【嘴(喙・觜)】読み方:くちばし嘴(喙・觜)は”鳥類の口の部分に突き出ている、上下の顎(あご)の骨の表面が角質化したもの”の意味。【靴】読み方:くつ靴は”足を覆うように作った履物の総称のこと”の意味。【沓石】読み方:くついし沓石は”礎石などの上にあって、柱などの下に据(す)える石のこと”の意味。【轡】読み方:くつわ轡は”手綱(たづな)をつけるために、馬の口にかませる金具のこと”の意味。【鞍】読み方:くら鞍は”牛・馬の背に置き、人や荷物を乗せやすくなるようにする木製または革製の道具のこと”の意味。【曲輪(郭・廓)】読み方:くるわ曲輪(郭・廓)は”城・砦(とりで)などの周囲に築いた囲いのこと。また、その囲いの内側の地域のこと”の意味。【鍬】読み方:くわ鍬は”薄い鉄の板に柄(え)をつけた農具のこと”の意味。土を掘り起こしたり、均(なら)したりします。【懸魚】読み方:げぎょ懸魚は”屋根の破風(はふ)の中央および左右に下げて、棟木(むなぎ)や桁(けた)の先端を隠す装飾板のこと”の意味。【袈裟】読み方:けさ袈裟は”僧侶が、衣の上に左肩から右脇(わき)下にかけて身に着ける長方形の布のこと”の意味。【下駄】読み方:げた下駄は”木の板の下面をくり抜いて歯をつけ、鼻緒(はなお)をすげた履物(はきもの)のこと”の意味。鼻緒というのは、”下駄・草履(ぞうり)などの、足の指で挟む部分。また、履物の緒(お)の全体のこと”を指します。【玄翁(玄能)】読み方:げんのう玄翁(玄能)は”頭の両端に尖(とが)った部分のない金槌(かなづち)のこと”の意味。石を割ったり、鑿(のみ)の頭を叩いたりするのに用いられます。【碁石】読み方:ごいし碁石は”囲碁に用いる円形の小さい石のこと”の意味。碁石は白色と黒色の2種類があり、正式には白石が180個、黒石が181個あります。黒石の方が白石よりも1個多いのは、黒石を打つ側が先手となるからで、碁盤の升目(ますめ)は全部で(19×19=)361あるため、黒石が白石よりも1個だけ多くなっています。【鯉幟】読み方:こいのぼり鯉幟は”布または紙で作った、鯉(こい)の形の幟(のぼり)のこと”の意味。幟というのは”細長い布の端に小さな輪をつけ、竿(さお)に通して立てるもの”で、鯉幟は端午(たんご)の節句に男児の誕生と成長を祝って立てられます。【格子】読み方:こうし格子は”細い木や竹などを、碁盤(ごばん)の目のように組み合わせて作った建具(たてぐ)のこと”の意味。格子は、主に戸や窓などに用いられます。【香典】読み方:こうでん香典は”死者の霊前に香の代わりとして供(そな)える金銭のこと”の意味。【格天井】読み方:ごうてんじょう格天井は”木を格子(こうし)のように組んで、それに板を張った天井のこと”の意味。【行李】読み方:こうり行李は”竹・柳(やなぎ)などを編んで作った、衣類などの収納や運搬に用いる箱形の入れ物のこと”の意味。【炬燵(火燵)】読み方:こたつ炬燵(火燵)は”木で組んだ枠の中に熱源を入れ、布団(ふとん)をかけて暖をとる器具のこと”の意味。【小鼓】読み方:こつづみ小鼓は”小さな鼓(つづみ)のこと”の意味。鼓というのは、”木製で中央部のくびれている胴の両端に革(かわ)を張った楽器のこと”を言います。小鼓は左手で調(しらべ)と呼ばれる紐(ひも)を持ち右肩にのせ、右手で革が張られている部分を叩いて音を出します。【小包】読み方:こづつみ小包は”小さな包みのこと”の意味。【鏝】読み方:こて鏝は”壁土(かべつち)・漆喰(しっくい)・セメントなどを塗るときに使う、鉄の平たい板に柄(え)をつけた道具のこと”の意味。【籠手(小手・篭手)】読み方:こて※上は剣道の防具の写真籠手(小手・篭手)は”剣道で、手先・腕先を覆(おお)う防具。また、その部分を打つわざのこと/鎧の付属具で、肩先から腕を覆うもの/弓を射るとき、左の肘(ひじ)を保護するために掛ける革製の覆いのこと”の意味。【瘤】読み方:こぶ瘤は”病気や打撲(だぼく)のために、皮膚の一部が盛り上がったもの/ものの表面に盛り上がったもの”の意味。【独楽】読み方:こま独楽は”木や金属などでできた、厚みのある円形の胴の中心に心棒を通した玩具(おもちゃ)のこと”の意味。独楽は心棒の部分を指でつまんで回したり、ひもで巻いて回して遊ぶ玩具です。【塵箱(芥箱)】読み方:ごみばこ塵箱(芥箱)は”ごみを入れるための箱のこと”の意味。【紙縒り(紙縒)】読み方:こより紙縒り(紙縒)は”細く切った紙をひねって紐(ひも)状にしたもの”の意味。【混凝土】読み方:コンクリート※上は混凝土(固まったもの)の写真混凝土は”セメントに砂・砂利などの骨材と水を適当な割合で混ぜ、こねたもの。また、それを固めたもの”の意味。一般的には固まったものを「混凝土(コンクリート)」、固まっていないものは「生(なま)コン」(生コンクリート)と呼ぶことが多いです。混凝土は建築土木工事の材料として多く利用され、セメントを水で溶かして混ぜたものを「セメントペースト」、細骨材の砂を練り混ぜたものを「モルタル」と呼んでいます。※上はモルタルの写真セメントは”石灰石・粘土などを焼いて粉砕した灰白色の粉状のもの”で、モルタルや混凝土を作るためのつなぎの役割を持っています。モルタルは「セメント + 砂 + 水」を混ぜ合わせたもので、混凝土は「セメント + 砂 + 砂利 + 水」を混ぜ合わせて作ったものを言います。モルタルと混凝土の違いは、セメントと混ぜるものの中に「砂利」があるかどうかで、砂利が入ることでモルタルよりも強度がかなり上がります。なので混凝土とモルタルの使われる箇所は異なり、混凝土は構造物の基礎部分に、モルタルは混凝土表面の凸凹を均(なら)すために上から塗って使われます。↓サ行~【賽子(骰子)】読み方:サイコロ賽子(骰子)は”双六(すごろく)・博打(ばくち)などで用いられ、小さい立方体の各面に1から6までの目を記したもの”の意味。ちなみに賽子の目の数は、必ず反対側の面に記されている目と合わせて「7」になるように記されています。なので1の目の反対側の面には6の目が記されていて、3の目の反対側の面には4の目が記されています。【菜箸】読み方:さいばし菜箸は”料理を作るときや盛りつけるときに用いる箸(はし)のこと”の意味。【財布】読み方:さいふ財布は”金銭を入れて持ち歩く袋のこと”の意味。【酒蔵】読み方:さかぐら「しゅぞう」というのは、「酒造(しゅぞう)」と表記されるため注意が必要です。酒蔵は”酒を醸造(じょうぞう)、また貯蔵しておくための蔵のこと”の意味。【盃(杯)】読み方:さかずき盃(杯)は”酒を飲むのに使う小さな器のこと”の意味。【酒樽】読み方:さかだる酒樽は”酒を入れておくための樽(たる)のこと”の意味。【匙】読み方:さじ匙は”液体・粉末などを掬(すく)い取る道具のこと”の意味。「匙を投げる」という慣用句がありますが、これは医者が薬を調合するための匙を投げ出す意から、”医者が治療の方法がないと診断すること/物事に救済や解決の見込みがないとして、手を引くこと”の意味で用いられます。例えば「医者に回復の見込みがないと匙を投げられたが、まだ諦めるつもりはない」や「彼に勉強するように何度も言っていたが、ついには匙を投げてしまった」のように用いられます。前者の例文は”医者が治療の方法がないと診断すること”、後者の例文は”物事に救済や解決の見込みがないとして、手を引くこと”の意味で使用しています。【桟敷】読み方:さじき桟敷は”祭りなどを見るため、地面よりも高く作った見物席のこと”の意味。【刺子】読み方:さしこ刺子は”綿布を重ね合わせ、一面に細かく刺し縫(ぬ)いをすること。また、そのようにして縫われたもの”の意味。刺子は非常に丈夫で、柔道着・剣道着・消防服などに用いられています。【砂州(砂洲)】読み方:さす砂州(砂洲)は”沿岸流によって運ばれた砂礫(されき)が、湾口(わんこう)の一方の端から対岸まで細長く堆積(たいせき)してできた地形のこと”の意味。砂礫というのは”砂と小石のこと”で、”砂州によって隔(へだ)たれた水域のこと”を「潟湖(せきこ)」または「ラグーン」と呼びます。【刺股】読み方:さすまた刺股は”長い棒の先に二股(ふたまた)に分かれた鉄製の頭部をつけたもの”の意味。相手の動きを封じたり、捕らえたりするために用いられます。※上は消防署の地図記号ちなみに刺股は消防署の地図記号にもなっていて、これは江戸時代に火事が起きたときに刺股で家を壊していき、火が燃え移るのを防いでいたことからきています。【早苗】読み方:さなえ早苗は”稲の若い苗(なえ)のこと”の意味。早苗は”苗代(なわしろ)から田んぼへ移し植える頃の若い苗のこと”を指し、苗代というのは”田植えができる大きさまで苗を育てるための場所”になります。【錆】読み方:さび錆は”金属の表面が空気や水に触れて生じた酸化物のこと/悪い結果のこと”の意味。後者の意味は「身から出た錆」ということわざによく使われ、これは”自分の犯した悪行の結果として自分自身が苦しむこと”の意味になります。例えば「日頃の彼の態度が原因なのだから、身から出た錆だろう」や「身から出た錆とはいえ、彼女を少しかわいそうに感じる」のように用いられます。【座布団】読み方:ざぶとん座布団は”座るとき下に敷く布団(ふとん)のこと”の意味。【作務衣】読み方:さむえ作務衣は”寺院の僧侶が作務(さむ)と呼ばれる日常の労務(薪割り、掃除など)を行うときに着る衣のこと”の意味。作務(さむ)のときに着る衣(ころも)なので、「作務衣(さむえ)」と言います。ただし、いま現在では作務衣は特に僧侶だけが着ている服というわけではなく、居酒屋・焼き鳥屋などでも店員さんが着ているのをよく見かけます。ですので単純に作業着として使用されている場合も多いです。【鞘】読み方:さや鞘は”刀剣の刀身(とうしん)の部分や、筆の先などを納めておく筒(つつ)のこと”の意味。【笊】読み方:ざる笊は”細く割った竹などで編んだ器のこと/漏れや抜けが多いさま/非常に酒に強い人のこと”の意味。水を注いでも笊(器)の編み目から水が漏れてしまうことから、転じて”漏れや抜けが多いさま”と”非常に酒に強い人のこと”の意味となっています。後者は水と同様に酒をいくら笊(器)に注いでも編み目からそのまま出ていくため、いくら飲んでも酔わない(=酒に強い)というたとえからきています。”漏れや抜けが多いさま”は、例えば「あのチームの守備は笊だ」や「ここの警備は笊だから簡単に侵入できる」のように用いられます。【三叉路】読み方:さんさろ三叉路は”道が3つに分かれている所のこと”の意味。【三線】読み方:さんしん※上は三線の写真三線は”沖縄・奄美(あまみ)で用いられる弦楽器のこと”の意味。※上は三味線のイラスト三線は三味線(しゃみせん)に似ていますが、胴が丸くて全体的にやや小さく、胴の表裏に蛇(へび)の皮が張られています。胴の表裏に蛇の皮が張られていることから、「蛇皮線(じゃびせん)」とも呼ばれています。【桟橋】読み方:さんばし桟橋は”貨物の積み下ろし、船客の乗降のために水上に突き出した構造物のこと”の意味。【栞(枝折)】読み方:しおり栞(枝折)は”読みかけの書物の間に挟んで目印とするもの/簡単な手引書。案内書のこと”の意味。【枝折戸】読み方:しおりど枝折戸は”竹や折った枝などをそのまま使った簡単な開き戸のこと”の意味。片開きで、庭の出入り口などに設けられることが多いです。【敷居(閾)】読み方:しきい敷居(閾)は”門や出入口、また部屋のしきりに敷く横木のこと”の意味。部屋のしきりに敷く横木には、戸・障子(しょうじ)・襖(ふすま)などを開けたてするための溝(みぞ)があります。「敷居が高い」という慣用句がありますが、この慣用句の本来の意味は”不義理・面目のないことをして、その人の家に行きにくいこと”になります。簡単にいうと、”過去に相手に対して失礼をしてしまったことなどが原因で、その人に会いにくい(家に行きにくい)こと”を意味しています。現在では”高級すぎたり、上品すぎたりして、行きにくいこと”の意味で使われることも多く、本来の意味とは異なりますが、多くの人が誤った使い方をしていたことでそれが定着しつつあります。”高級すぎたり、上品すぎたりして、行きにくいこと”も正式な意味として認められつつありますが、あくまでも本来の意味ではなく元々は誤用だったということは覚えておきましょう。【鹿威し】読み方:ししおどし鹿威しは”支点で支えた竹筒の切り口に水を落とすと、溜まった水の重みで傾き、水が流れ出ると、その反動で跳ね返って他方の端が下の石などに当たって音を出す装置のこと”の意味。元は田畑を荒らす鳥獣を音で脅す仕掛けでしたが、現在では庭園などに音を楽しんだり風情(ふぜい)を演出するために設けられています。【雫(滴)】読み方:しずく雫(滴)は”滴(したた)り落ちる液体の粒のこと”の意味。【竹刀】読み方:しない竹刀は”剣道で用いられる、四つ割りの竹を束ね合わせて作った刀のこと”の意味。【鎬】読み方:しのぎ鎬は”刀剣で、刃(やいば)と峰(みね)との間の盛り上がっている部分。鎬筋(しのぎすじ)のこと”の意味。峰というのは、”刀身の刃の背のこと”を指します。「鎬を削る」(「凌ぎを削る」は誤り)という慣用句がありますが、これは日本刀同士が勢いよくぶつかると鎬の部分が削れることから、”激しく争う様子のこと”の意味で用いられます。例えば「覇権を狙って各国と鎬を削る」や「決勝は鎬を削る大接戦だった」のように用いられます。【芝生】読み方:しばふ芝生は”芝(しば)が一面に生えている所のこと”の意味。芝生は植物(イネ科の多年草)が用いられていますが、人工芝(じんこうしば)の場合は芝に似た形状を化合物で作っていて、プラスチック素材が多いです。【注連縄】読み方:しめなわ注連縄は”神聖な場所に不浄なものの侵入を防ぐために張る縄のこと”の意味。※上は注連飾りの写真正月には玄関先などに注連縄が飾られますが、この注連縄のことを「注連飾り(しめかざり)」と言います。【赤銅】読み方:しゃくどう赤銅は”銅に、少量の金・銀を加えた赤黒い色の合金のこと”の意味。赤銅は、仏像・装飾など工芸品などによく用いられます。【車窓】読み方:しゃそう車窓は”列車・電車・自動車などの窓のこと”の意味。【鯱(鯱鉾)】読み方:しゃちほこ※上は「しゃちほこ」(後者の意味)の写真鯱(鯱鉾)は”頭が虎のようで、背にとげのある想像上の海獣のこと/想像上の海獣をかたどった魔除(まよ)けの飾り物のこと”の意味。後者の意味は、城などの屋根の大棟(おおむね)の両端につけ、木・石・金属・瓦(かわら)などで作られます。※上は鯱(しゃち)の写真鯱は「しゃちほこ」の他に「しゃち」と読むことができ、「しゃち」と読むと”マイルカ科の哺乳類のこと”の意味になります。【三味線】読み方:しゃみせん三味線は”日本の弦楽器のこと”の意味。犬や猫の皮を張った胴の部分に棹(さお)を付けて、張っている弦(げん)を「撥(ばち)」という道具を用いて演奏します。【杓文字】読み方:しゃもじ杓文字は”ご飯を盛るための道具のこと”の意味。【砂利】読み方:じゃり砂利は”小石。また、小石に砂の混じったもの”の意味。【絨毯】読み方:じゅうたん絨毯は”床の敷物にする厚い毛織物のこと”の意味。【十二単】読み方:じゅうにひとえ十二単は”平安時代などの女官の正装に対する後世での俗称のこと”の意味。十二単と呼ばれているのは、中着を12枚も重ねて着ていたことに由来しています。【数珠】読み方:じゅず数珠は”仏を拝むときや念仏の回数を数えるときに手にかける、小さな珠(たま)に糸を通して輪にしたもの”の意味。【襦袢】読み方:じゅばん襦袢は”和服用の肌着(はだぎ)のこと”の意味。【背負子】読み方:しょいこ背負子は”荷物をくくりつけて背に負う、木製の長方形の枠(わく)のこと”の意味。【定規】読み方:じょうぎ定規は”物を裁断したり、線を引いたりするのにあてがう器具のこと/物事を判断するもとになる目安のこと”の意味。後者の意味は例えば、「自分の定規で他人を測るな」や「どうしてお前は杓子定規にしか物事を考えられないんだ」のように用いられます。「杓子定規(しゃくしじょうぎ)」というのは四字熟語で、これは曲がっている杓子の柄(え)を定規として使うことから、”何事にも同じ基準で決めようとする、応用や融通(ゆうずう)の利かないやり方や態度。また、そのさま”の意味で用いられます。杓子というのは”ご飯を盛ったり、汁を掬(すく)うための道具のこと”で、現在の杓子の柄はまっすぐなものが多いですが、昔の杓子の柄は曲がっているものが多かったです。【漏斗】読み方:じょうご(ろうと)漏斗は”液体を口の小さな容器に注ぎ入れるときに用いる道具のこと”の意味。上が円形で広く、下がすぼまった形をしていて、すぼまった形の部分を容器の口部分に挿して、上の円形部分から液体を注ぎ込みます。漏斗を「じょうご」「ろうと」と読んでも意味的には同じですが、理科の実験で使われるときは「ろうと」、それ以外で使われるときは「じょうご」と読むことが多いです。【障子】読み方:しょうじ障子は”仕切りなどに用いる建具(たてぐ)のひとつ”の意味。格子(こうし)に組んだ木の枠の片面に、薄い白紙を貼ったものを指します。【装束】読み方:しょうぞく装束は”衣服・着物。特に儀式に用いる礼服・式服などのこと”の意味。【如雨露】読み方:じょうろ如雨露は”草木に水をかけるのに使う道具のこと”の意味。【燭台】読み方:しょくだい燭台は”蝋燭(ろうそく)を立てて火を灯(とも)すための台のこと”の意味。【寝具】読み方:しんぐ寝具は”寝るときに使用する用具のこと”の意味。主に「枕(まくら)・布団・寝巻き」などが挙げられます。【真珠】読み方:しんじゅ真珠は”貝類の殻の中にできる光沢のある玉のこと”の意味。真珠は炭酸カルシウムが主成分となっており、貝の体内に侵入した砂粒などの異物を外套膜(がいとうまく)から分泌された真珠質が包んで真珠が形成されます。特にアコヤガイを使って人工的に作る養殖法が有名で、真珠は宝石として珍重されています。【真鍮】読み方:しんちゅう真鍮は”亜鉛と銅を混ぜて作られる合金のこと”の意味。見た目は黄色で、別名で「黄銅(おうどう)」と呼ばれ、五円玉の原料として知られています。真鍮は”亜鉛35%+銅65%”の配分が一般的で、電気や熱が伝導しやすく、曲げる・伸ばす・削るなどの加工が比較的容易です。【水筒】読み方:すいとう水筒は”飲料水などを入れて持ち歩くことができるようにした筒型(つつがた)の容器のこと”の意味。【鋤】読み方:すき鋤は”手に持って土を掘り起こす農具のこと”の意味。【頭巾】読み方:ずきん頭巾は”頭や顔を覆(おお)う、布製の被り物のこと”の意味。【双六】読み方:すごろく双六は”サイコロを振り、出た目の数で振り出しから駒を進めていき、あがりの早さを競う遊びのこと”の意味。【生絹】読み方:すずし(きぎぬ)生絹は”生糸(きいと)で織った絹織物(きぬおりもの)のこと”の意味。【硯】読み方:すずり硯は”石または瓦(かわら)で作られ、墨を水で磨(す)りおろすために用いる道具のこと”の意味。【裾】読み方:すそ裾は”衣服の下の縁(ふち)のこと”の意味。裾上げなど、一般的に裾はズボンの下の縁を指すことが多いですが、シャツなど上半身に着る衣服の下の縁のことも指しているため覚えておきましょう。【簾】読み方:すだれ※上は簾の写真簾は”細く削った竹や葦(あし)などを並べて糸で編んだもの”の意味。簾は、日除(ひよ)けや部屋の仕切りなどの目的で用いられます。※上は葦簀の写真簾と混同されがちなものに「葦簀(よしず)」というものがありますが、これらの違いは”上から垂らすもの”なのか”立て掛けるもの”なのかです。(葦簀は、日除けや目隠しなどの目的で用いられます)簾の場合は上から垂らして使い、葦簀は比較的大きなサイズで立て掛けて使用します。【磨硝子】読み方:すりガラス磨硝子は”金剛砂(こんごうしゃ)などで表面を磨(す)り、わざと細かな凹凸を付けて不透明にした硝子(がらす)のこと”の意味。磨硝子は、「曇りガラス」や「つや消しガラス」とも呼ばれています。金剛砂というのは”石榴石(ざくろいし)を粉末にしたもの”で、黒みを帯びた粒状をしていて、ダイヤモンドに次(つ)いで硬いとされ、研磨剤に用いられます。【擂粉木】読み方:すりこぎ擂粉木は”擂鉢(すりばち)で物をすりつぶすのに用いる棒のこと”の意味。【擂鉢】読み方:すりばち擂鉢は”味噌(みそ)や胡麻(ごま)などを入れて、擂粉木(すりこぎ)ですりつぶすのに用いる鉢のこと”の意味。【寸胴】読み方:ずんどう※上は寸胴鍋(ずんどうなべ)の写真寸胴は”上から下まで同じ太さであること。また、そのさま”の意味。【正鵠】読み方:せいこく正鵠は”弓の的(まと)の中心にある黒点のこと”の意味。【生石灰】読み方:せいせっかい「しょうせっかい」というのは、「消石灰(しょうせっかい)」と表記されるため注意が必要です。生石灰は”酸化カルシウムの俗称のこと”の意味。【歳暮】読み方:せいぼ歳暮は”1年の感謝を込めて年末におくる贈り物のこと”の意味。【井目】読み方:せいもく井目は”囲碁で、盤面に記された9つの黒点のこと”の意味。【蒸籠】読み方:せいろ(せいろう)蒸籠は”食べ物を蒸すための、底がすのこ状になっている木や竹製の道具のこと”の意味。「すのこ」は”角材の上に薄い板材を間をあけて並べて打ち付けたもの”で、蒸籠は上にある食べ物に、すのこの間から蒸気を通す仕組みになっています。なので沸騰したお湯の入った鍋などの上に蒸籠を置いて使用します。つまり蒸気を食べ物に通すことによって、加熱調理するための道具が蒸籠になります。【石鹸】読み方:せっけん石鹸は”垢(あか)や汚れを落とすために使う、水に溶けやすい洗剤の一種のこと”の意味。【雪駄】読み方:せった雪駄は”竹の皮の草履(ぞうり)の裏に牛革をはった履物(はきもの)のこと”の意味。【雪隠】読み方:せっちん雪隠は”便所のこと”の意味。雪竇(せっとう)という名の禅師が霊隠寺(れいいんじ)の便所掃除の役割をしていたことから、「雪隠」という漢字が当てられています。【雪庇】読み方:せっぴ雪庇は”雪が積もって庇(ひさし)のように突き出たもの”の意味。【千社札】読み方:せんじゃふだ千社札は”千社(せんじゃ)参りの人が参詣(さんけい)のしるしに、社殿の柱や天井などに貼り付ける紙の札のこと”の意味。千社というのは”多くの社(やしろ)のこと”を意味し、千社参りは”多くの神社やお寺にお参りすること”という意味になります。【扇子】読み方:せんす扇子は”折り畳み式の、あおいで風を起こし涼をとるための道具のこと”の意味。【発条】読み方:ぜんまい(ばね)「ぜんまい」と読むと”弾性(だんせい)に富む鋼などを薄く細長くして、渦巻状に巻いたもの”の意味。弾性というのは、”物体に外から力を加えると変形し、その力を取り除けば元の形に戻ろうとする性質のこと”です。この元に戻ろうとする性質を利用して、時計や玩具(おもちゃ)などの動力にしています。「ばね」と読むと”弾性に富む鋼などを薄く細長くして、渦巻状に巻いたもの/足腰の弾力性のこと/飛躍・発展などのきっかけのこと”の意味。”足腰の弾力性”は例えば「足の発条を鍛えるトレーニングをする」、”飛躍・発展などのきっかけ”は例えば「彼は失敗を発条(ばね)に成長した」のように用いられます。【雑巾】読み方:ぞうきん雑巾は”汚れを拭き取るための布のこと”の意味。【象牙】読み方:ぞうげ象牙は”象の牙のこと”の意味。象牙は適度な硬さをもつため、彫刻や工芸の材として重宝(ちょうほう)されています。【草履】読み方:ぞうり※上は草履の写真※上は下駄の鼻緒の写真草履は”鼻緒(はなお)がある底が平たい履物(はきもの)のこと”の意味。藁(わら)・竹皮(たけかわ)などで編んだものや、ビニール・ゴム製のものなどがあります。鼻緒というのは、”下駄(げた)・草履などの、足の指で挟む部分。また、履物の緒(お)の全体のこと”を指します。【粗品】読み方:そしな粗品は”他人に贈る物を遜(へりくだ)っていう語のこと/粗悪な品物のこと”の意味。遜るというのは、”相手に敬意を示すために、自分を低いところに置いた表現のこと”です。【袖】読み方:そで袖は”衣服の腕を覆(おお)う部分のこと”の意味。【算盤】読み方:そろばん算盤は”枠の中の珠(たま)を上下させて計算する道具のこと”の意味。↓タ行~【松明】読み方:たいまつ松明は”長い棒の先端に、松脂(まつやに)など燃えやすいものを浸した布切れを巻き付けたもの”の意味。長い棒の先端にある燃えやすいものが浸された布の部分に、火を点じることで松明は照明具として利用されます。【箍】読み方:たが箍は”桶(おけ)・樽(たる)などの周りに巻いて、締めつけるための竹や金属製の輪のこと”の意味。「箍が外れる」という慣用句がありますが、これは桶・樽などの周りを締めつけている輪(箍)を外すと構成している板がバラバラになることから、”緊張や束縛がとれて、締まりのない状態になること”の意味として用いられます。簡単にいうと、”自分の行動を抑制していたもの(緊張や束縛)がなくなることで、自分自身を制御できなくなったり羽目(はめ)を外してしまったりすること”です。例えば「彼は箍が外れたように愚痴を言い始めた」や「彼女は箍が外れたかのように突然号泣してしまった」のように用いられます。【鏨(鑽)】読み方:たがね鏨(鑽)は”金属で作られた鑿(のみ)のこと”の意味。鑿(のみ)は木材・石材に穴や溝(みぞ)を掘るために用いられ、鏨(たがね)は主に金属・石材を削ったり切ったりするために用いられます。鑿(のみ)は刃が鋭く、鏨(たがね)の先端は鑿(のみ)ほど鋭利ではなく、鈍(にぶ)く作られています。【凧】読み方:たこ凧は”竹などの骨組みに紙やビニールを張り、糸を付け、風を利用して空高く飛ばして遊ぶ玩具のこと”の意味。【胼胝(胝)】読み方:たこ胼胝(胝)は”皮膚の一部が繰り返し圧迫されることで、硬く厚くなったもの”の意味。【山車】読み方:だし山車は”祭りのときに、飾り物などをして引いたり担いだりする屋台(やたい)のこと”の意味。【襷】読み方:たすき※上は襷(前者の意味)の写真※上は襷(後者の意味)の写真襷は”和服の袖(そで)が邪魔にならないようにたくし上げるため、肩から脇(わき)の下へ通し、背中で交差させて結ぶひものこと/一方の肩から他方の腰のあたりに斜めにかける、輪にした細長い布のこと”の意味。【三和土】読み方:たたき三和土は”赤土・石灰・砂などを混ぜて突き固めた、台所や玄関などの土間(どま)。また、コンクリートで固めた土間のこと”の意味。三和土は主に3種類(赤土・石灰・砂)の材料を用いることから付けられた名称です。土間というのは、”家の中において床を張っていない部分のこと”を言います。【太刀】読み方:たち太刀は”日本刀のうち、刃渡りが60cm以上の刀のこと”の意味。「大刀(たち)」と表記されることもありますが、古墳時代から奈良時代までに見られる直刀を「大刀」、平安時代以降の反り刀を「太刀」と書き分けます。【鬣】読み方:たてがみ鬣は”首の背側に生えている長い毛のこと”の意味。【炭団】読み方:たどん炭団は”粉炭(こなずみ)に布海苔(ふのり)を加えて練り、丸くして乾燥した燃料のこと”の意味。粉炭というのは”木炭が砕けて細かくなったもの”で、布海苔というのは”フノリ科の紅藻の総称のこと”です。【煙草】読み方:たばこ煙草は”ナス科の1年草のこと/タバコ(植物)の葉を乾かして作った嗜好品(しこうひん)のこと”の意味。一般的に煙草というと喫煙などで知られる嗜好品のことを指しますが、他にも嗜好品の原材料となっている植物のことも煙草と呼びます。※煙草(植物)畑の写真煙草(植物)の葉には強い依存性を持つニコチンが含まれており、その葉を乾燥させて紙などで巻いたものがよく見る嗜好品の煙草になります。煙草(嗜好品)に依存してしまう人が多いのは、依存性の強いニコチンを含んだ葉を原材料としているからなんですね。【足袋】読み方:たび足袋は”足に履く、爪先(つまさき)が2つに分かれた袋状の履物(はきもの)のこと”の意味。足袋は下駄(げた)や草履(ぞうり)などを履くときに、鼻緒の部分を親指と他の4本の指で挟めるように2つに分かれています。【袂】読み方:たもと袂は”和服の袖(そで)の下方の、袋のように垂れた部分のこと”の意味。「袂を分かつ」という慣用句がありますが、これは”今まで一緒に行動していた人と別れること。絶交すること”の意味で用いられます。”共通の目標・目的を持っていた人が、価値観や意見が違ってきたことによって別れてしまう状況”で使用される言葉になります。例えば「いつからかお互いの価値観が異なり、彼とは袂を分かつことを決意した」や「彼らと袂を分かつ覚悟で正直に話した」のように用いられます。【盥】読み方:たらい盥は”湯水を入れて顔や手足を洗ったり、洗濯したりするときに用いられる丸く平たい容器のこと”の意味。【達磨】読み方:だるま達磨は”中国禅宗(ぜんしゅう)の開祖のこと/達磨(人物)の座禅姿をかたどった置物のこと”の意味。子供のときに「だるまさんがころんだ」で遊んだ人も多いと思いますが、この「だるまさん」というのが中国禅宗の開祖である達磨のことなんですね。【束子】読み方:たわし束子は”器物の汚れをこすって落とす用具のこと”の意味。【短冊】読み方:たんざく短冊は”字を書いたり、しるしとして物に貼る細長い紙のこと/和歌・俳句などを書き記すための細長い厚紙のこと”の意味。【楽車】読み方:だんじり楽車は”主に関西・西日本で、祭礼に引いて歩く屋台(やたい)のこと”の意味。楽車には太鼓をのせ、車輪を付けて引いたり、大勢で担いだりして練り歩きます。【箪笥】読み方:たんす箪笥は”衣服・小道具などを整理・保管するのに用いる家具の総称のこと”の意味。【卓袱台】読み方:ちゃぶだい卓袱台は”短い脚(あし)の付いた食事用の台のこと”の意味。【手水鉢】読み方:ちょうずばち手水鉢は”手を洗う水を入れておく鉢(はち)のこと”の意味。鉢というのは、”上部のあいた容器のこと”を指します。【提灯】読み方:ちょうちん※上は提灯(ちょうちん)の写真提灯は”細い割り竹を円形などにしたものを骨とし、紙や布を貼り、中に蝋燭(ろうそく)を灯せるようにした照明具のこと”の意味。現在では中に蝋燭ではなく、電球を入れたりすることも多いです。※上は行灯(あんどん)の写真似ている照明具に「行灯(あんどん)」がありますが、これはもともと持ち運ぶためのものであったため、「行灯」という字が当てられていました。ですがその後に持ち運びやすいように進化した「提灯(ちょうちん)」ができたので、行灯は”据置(すえおき)用”、提灯は”携行(けいこう)用”として使用されるようになりました。【蝶番】読み方:ちょうつがい蝶番は”開き戸・蓋(ふた)などを支え、自由に開閉できるように取り付ける金具。ヒンジのこと”の意味。【手斧】読み方:ちょうな(ておの)手斧は”大具道具のひとつで、主に片手で振る小型の斧(おの)のこと”の意味。薪(まき)の小割りや枝払いなど、普通の斧よりも細かい作業に用いられます。【猪口】読み方:ちょこ猪口は”酒を注(つ)いで飲む陶製の小さな器のこと”の意味。【衝立】読み方:ついたて衝立は”室内で立てて、仕切りや外からの目隠しにする家具のこと”の意味。【槌】読み方:つち槌は”物を打ち叩くのに用いられる工具のこと”の意味。槌の頭の部分または全部を鉄で作ったものを「金槌(かなづち)」、木製の槌のことを「木槌(きづち)」と言います。【葛籠(葛篭)】読み方:つづら葛籠(葛篭)は”葛藤(つづらふじ)の蔓(つる)で編んだ、衣服などを入れる蓋(ふた)付きの箱形の籠(かご)のこと”の意味。のちには竹や檜(ひのき)の薄板で編み、その上に紙を貼って漆(うるし)などを塗ったものも「葛籠(つづら)」と呼びます。【角笛】読み方:つのぶえ角笛は”動物の角(つの)で作った笛のこと”の意味。角笛は、牧童(ぼくどう)などが牛や羊を追うのに用いられます。牧童というのは、”牧場で家畜の世話をする者のこと”を意味します。【鍔(鐔)】読み方:つば※上は刀剣の鍔(鐔)の写真※上は釜の鍔(鐔)の写真※上は帽子の鍔(鐔)の写真鍔(鐔)は”刀剣の柄(つか)と刀身との間に挟み、柄を握る手を防護する金具のこと/釜(かま)の胴の周りに庇(ひさし)のように出ている部分のこと/帽子の周り、または前部に庇のように出ている部分のこと”の意味。【蕾】読み方:つぼみ蕾は”花が咲く前の、ふくらんだ状態のもの”の意味。【爪楊枝】読み方:つまようじ爪楊枝は”歯に挟まったものを取ったり、食べ物に刺したりするための小さい楊枝(ようじ)のこと”の意味。【氷柱】読み方:つらら氷柱は”軒(のき)などから滴(したた)る水滴が凍って、棒状に垂れ下がったもの”の意味。【鶴嘴】読み方:つるはし鶴嘴は”土砂・岩石などを掘り起こすときに用いる鉄製の工具のこと”の意味。鶴(つる)の嘴(くちばし)のように両端を尖(とが)らせ、それに木の柄(え)を付けたものになります。【釣瓶】読み方:つるべ釣瓶は”縄や竿(さお)の先につけて井戸の水を汲(く)み上げる桶(おけ)のこと”の意味。【天蚕糸】読み方:てぐす天蚕糸は”山繭(やままゆ)の幼虫の絹糸腺(けんしせん)から作った白色透明の糸のこと”の意味。山繭というのは、”鱗翅(りんし)目ヤママユガ科の蛾(が)のこと”を指します。【梃子】読み方:てこ※上は梃子の原理を利用したもの梃子は”棒の途中に置いた支点を中心に棒が自由に回転して、小さい力を大きい力に変える仕組み。また、それに用いる棒のこと”の意味。「梃子でも動かない」ということわざがありますが、これは”どんな手段を用いても、その場から絶対に動かないこと/(転じて)どんなことがあっても決意・信念を変えないこと”の意味になります。例えば「息子はお菓子を買ってもらうまで梃子でも動かないつもりだ」や「彼は一度決めたら梃子でも動かない人だ」のように用いられます。前者は”どんな手段を用いても、その場から絶対に動かないこと”の意味で、後者は”どんなことがあっても決意・信念を変えないこと”の意味で使用しています。【手錠】読み方:てじょう手錠は”罪人の手首にはめて腕の自由を奪う、錠(じょう)のついた鉄製の輪のこと”の意味。【天蓋】読み方:てんがい※上は天蓋(後者の意味)の写真天蓋は”仏像などの上にかざす笠状の装飾物のこと/祭壇やベッドなどの上に付けた覆いのこと”の意味。【天井】読み方:てんじょう天井は”部屋上部の仕切りのこと”の意味。【天袋】読み方:てんぶくろ天袋は”押し入れや違い棚(ちがいだな)の上部に設けた戸棚のこと”の意味。【伝馬船】読み方:てんません伝馬船は”木造の小型和船(わせん)のこと”の意味。伝馬船は、本船と岸との間を往復して、荷物などの積み下ろしを行うために用いられます。【投網】読み方:とあみ投網は”円錐(えんすい)形の網の上部に手綱(たづな)、下部に重りを付け、船上などから水面に投げ広げ、被せて引き上げる漁法。また、その網のこと”の意味。投網は、主に浅い場所で行われます。【樋】読み方:とい樋は”屋根を流れる雨水を受けて、地上に流すための装置のこと”の意味。軒に横に渡して取りつける樋のことを「軒樋(のきどい)」、軒樋を通った水を下に落とすため、縦に渡した樋のことを「竪樋(たてどい)」と呼びます。なので軒樋と竪樋というのは、「雨樋(あまどい)」を構成しているものになります。【砥石】読み方:といし砥石は”刃物などを研(と)ぐのに用いる石のこと”の意味。【灯籠】読み方:とうろう灯籠は”石や金属などで作られた、中にあかりをともす灯火用具のこと”の意味。【徳俵】読み方:とくだわら徳俵は”相撲(すもう)の土俵で、東西南北の中央に切れ目を作り、円の外側に一俵ずつずらして置いてある俵のこと”の意味。もともと相撲は外で行われていて、雨が降ると土俵上に水がたまったり、砂が泥になったりするため、”土俵上の水や泥を外に出す目的”で徳俵が作られました。【髑髏】読み方:どくろ(しゃれこうべ)髑髏は”風雨に晒(さら)され、まわりの肉が落ちてしまった頭の骨のこと”の意味。「しゃれこうべ」というのは、「どくろ」の別名です。【時計】読み方:とけい時計は”時刻を示し、時間を測る器械のこと”の意味。【徳利】読み方:とっくり徳利は”酒などを入れる陶製・金属製などの、細長くて口のすぼまった容器のこと”の意味。【土嚢】読み方:どのう土嚢は”土を入れた袋のこと”の意味。土嚢は、陣地や堤防を築くのに用いられます。【登坂車線】読み方:とはんしゃせん登坂車線は”道路の上り坂において、速度の遅くなる車両のために設けられている車線のこと”の意味。【銅鑼】読み方:ドラ銅鑼は”青銅・鉄などで作られた金属製の円盤を枠に吊(つ)り下げて、桴(ばち)で打ち鳴らす打楽器のひとつ”の意味。銅鑼は、合図などに用いられます。↓ナ行~【渚(汀)】読み方:なぎさ渚(汀)は”波の打ち寄せる所。波打ち際(ぎわ)のこと”の意味。【薙刀(長刀)】読み方:なぎなた薙刀(長刀)は”長い柄(え)の先に幅の広い反った刃を付けた武器のこと”の意味。【長押】読み方:なげし長押は”柱と柱を繋ぐための水平材で、鴨居(かもい)の上部に取り付けた建材のこと”の意味。長押はもともと構造材として使用されていましたが、「貫(ぬき)」が用いられるようになってから、長押は装飾材として用いられることも多くなりました。【鉈】読み方:なた鉈は”厚くて幅が広い刃に、短い柄(え)のついた片手持ちの刃物のこと”の意味。主に薪(まき)割りなどに用いられます。【納屋】読み方:なや納屋は”屋外に設けた物置用の小屋のこと”の意味。【鳴子】読み方:なるこ※上は鳴子(後者の意味)の写真鳴子は”田畑から鳥獣を追い払う道具のこと/よさこい祭りなどで手に持つ楽器のこと”の意味。鳥獣を追い払う道具としての鳴子は、数本の竹筒を板に並べて、縄に吊(つ)るして、遠くからその縄をひき鳴らし、その音で鳥獣が驚いて逃げていきます。【納戸】読み方:なんど納戸は”衣類・家財・道具類などをしまっておく部屋。屋内にある物置部屋のこと”の意味。【膠】読み方:にかわ膠は”獣・魚の骨・皮などを水で煮詰めて、その液を冷やして固めたもの”の意味。膠は接着剤・絵の具などに用いられます。【肉球】読み方:にくきゅう肉球は”犬や猫などの足の裏にある肉質の塊のこと”の意味。肉球は正式には「蹠球(しょきゅう)」と言いますが、肉球の一部を指す「掌球(しょうきゅう)」との混同を避けるために一般的に肉球と呼ばれています。肉球は皮膚が厚く進化したもので、プニプニと柔らかくクッションの働きをしていて、”衝撃や圧力から動物の足を守る役割”があります。クッションの役割の他にも、”獲物に接近する際に気付かれないように足音を消す役割”や、”熱さや冷たさが伝わりにくく、火傷(やけど)や凍傷から足を守る”といった役割があります。【仮漆】読み方:ニス仮漆は”ワニスの略(一般的には「ニス」と呼ぶことがほとんど)のこと”の意味。ワニスというのは、”樹脂を溶かした塗料で、顔料は含まず、光沢(こうたく)のある透明な薄膜を形成するもの”です。仮漆は木材の表面に塗ることでつやのある塗膜(とまく)を作ることができ、さらに塗膜を作ることで水分・空気などによる木材の劣化を防ぐ(防腐)効果もあります。【螺子(捻子・捩子)】読み方:ねじ※上は螺子(前者の意味)の写真※上は螺子(後者の意味)のイラスト螺子(捻子・捩子)は”物を締め付けるための螺旋(らせん)状の溝(みぞ)のある用具のこと/発条(ぜんまい)を巻く装置のこと”の意味。前者の意味の螺子は、棒状のものの側面に溝のある「雄螺子(おねじ)」と、これにはめるものの「雌螺子(めねじ)」から構成されています。後者の意味の発条というのは”弾性(だんせい)に富む鋼などを薄く細長くして、渦巻状に巻いたもの”で、螺子を巻き締めて、その戻ろうとする力を動力として利用します。弾性というのは、”物体に外から力を加えると変形し、その力を取り除けば元の形に戻ろうとする性質のこと”です。この元に戻ろうとする性質を利用して、時計や玩具(おもちゃ)などの動力にしています。【軒】読み方:のき軒は”屋根の下端で、建物の壁面より外に出ている部分のこと”の意味。似ているものに庇(ひさし)がありますが、庇は”建物の窓・出入口・縁側(えんがわ)などの上部に出ている小屋根のこと”を指します。ちなみに縁側は、庇だけでなく軒を屋根代わりにしているものも多いため覚えておきましょう。【鋸】読み方:のこぎり鋸は”木材などを切るのに用いる工具のこと”の意味。薄い鋼板(こうはん)の縁(ふち)に多くの歯をつけ、それに柄(え)をつけた工具になります。ちなみに鋸は、押すときに力を抜いて、引くときに力を入れるのが正しい使い方です。【熨斗】読み方:のし熨斗は”喜び祝う気持ちを表すために、贈答品(ぞうとうひん)に添えるもの”の意味。熨斗は”四角い色紙を細長い六角形に折ったもののこと”を呼び、熨斗が書かれた(印刷された)紙のことを「熨斗紙(のしがみ)」と呼びます。ですので贈り物に熨斗を付けて贈るというよりは、熨斗が印刷された熨斗紙を贈り物に付けて贈る、といった方が正しいです。ちなみにお祝いに金銭を贈るときは、「熨斗袋(のしぶくろ)」と呼ばれる”熨斗が印刷された紙の袋”の中に金銭を入れて贈るのが一般的です。※上は熨斗袋の写真なのでお祝い事で金銭以外の贈り物であれば「熨斗紙」を添えて贈り、金銭を贈るのであれば「熨斗袋」の中に金銭を入れて贈りましょう。【鑿】読み方:のみ鑿は”木材・石材に穴や溝(みぞ)を掘るための工具のこと”の意味。似ているものに鏨(たがね)がありますが、鑿(のみ)は木材・石材に穴や溝(みぞ)を掘るために用いられ、鏨(たがね)は主に金属・石材を削ったり切ったりするために用いられます。鑿(のみ)は刃が鋭く、鏨(たがね)の先端は鑿(のみ)ほど鋭利ではなく、鈍(にぶ)く作られています。【暖簾】読み方:のれん暖簾は”店先に垂らす店名を記した布のこと/部屋の入り口や仕切りに垂らす布のこと/店の信用・格式のこと”の意味。”店の信用・格式のこと”は例えば、「店の暖簾を守るために尽力する」のように用いられます。【狼煙(烽火)】読み方:のろし狼煙(烽火)は”昔、戦争や事件を知らせるために合図として上げた煙のこと/事を起こすための合図や信号のこと”の意味。狼煙は煙だけでなく、夜間などで煙が見えにくい場合には火そのものが使われます。ちなみに狼煙は字の通り「狼(おおかみ)の煙」と書きますが、昔の中国では狼の糞(ふん)を燃やして煙を上げていたそうです。これが「狼煙」という字になった由来とされています。↓ハ行~【袴】読み方:はかま袴は”和服で、着物を着た上からつけて、腰から下を覆(おお)う襞(ひだ)のある緩やかな衣服のこと”の意味。【刷毛】読み方:はけ刷毛は”動物の毛などを束ねて柄(え)を付けたもの”の意味。刷毛はちりを払い落としたり、塗料などを塗ったりするのに使われます。刷毛の毛は主に豚・山羊(やぎ)・人の毛・アクリル樹脂などが使われ、柄の部分には主に木・プラスチックなどが使用されています。【馬穴】読み方:バケツ馬穴は”金属やプラスチックなどで作った、水などを汲(く)んだり運んだりする桶(おけ)形の容器のこと”の意味。【羽子板】読み方:はごいた羽子板は”羽根(羽子とも呼ぶ)をつくための柄(え)のある長方形の板のこと”の意味。羽子板の片面には絵を描いたり、押し絵を付けたりします。羽根(羽子)というのは、”ムクロジ(木の名称)の種に穴を開け、鳥の小羽を数枚差し込んだもの”です。”羽子板で羽根をついて遊ぶこと。また、その遊びのこと”を「羽根突き(はねつき)」と言います。羽根突きにおける主な遊び方は2つで、1つの羽根を2人以上で突く「追羽根(おいばね)」、数をかぞえながら1人で羽根を突く「揚羽根(あげばね)」があります。【羽衣】読み方:はごろも羽衣は”天人が着て空を飛ぶという、鳥の羽で作られている薄くて軽い伝説上の布のこと”の意味。【端材】読み方:はざい端材は”木材などを切り出したときに生じる、余分な切れ端(はし)。半端な材料のこと”の意味。【鋏】読み方:はさみ鋏は”2枚の刃で挟むようにして物を切る道具のこと”の意味。【艀】読み方:はしけ艀は”底が浅く平らになっていて、重い荷物などを運ぶために用いられる船舶のこと”の意味。艀の多くにはエンジンが積まれていないため自走することができず、タグボートにより牽引(けんいん)されながら航行します。【梯子】読み方:はしご梯子は”高い所へ登るための道具のこと/梯子酒(はしござけ)の略のこと”の意味。梯子酒というのは、”次から次へと場所を変えて酒を飲み歩くこと”を指します。【法被】読み方:はっぴ法被は”職人などが着用する印半纏(しるしばんてん)のこと”の意味。印半纏というのは”襟(えり)・背などに屋号・氏名などを染めだした半纏(はんてん)のこと”で、法被は祭りなどの際に着用されていることも多いです。【波止場】読み方:はとば波止場は”港で陸から海へ細長く突き出した築造物のこと”の意味。波止場は、波をよけ、船をつなぎ、船客の乗降や荷物のあげおろしなどに使用されます。【鼻緒】読み方:はなお鼻緒は”下駄(げた)・草履(ぞうり)などの、足の指で挟む部分。また、履物(はきもの)の緒(お)の全体のこと”の意味。【埴輪】読み方:はにわ埴輪は”古墳時代、古墳の周囲に埋めた素焼きの焼き物のこと”の意味。人・動物・家など、様々な形をした埴輪が存在します。【飯盒】読み方:はんごう飯盒は”底の深い、炊飯(すいはん)もできる弁当箱のこと”の意味。主にアルミニウム製で、もともとは軍隊用に作られましたが、現在ではキャンプなどによく用いられます。【干潟】読み方:ひがた干潟は”海岸で潮(しお)が引いて、現れるところのこと”の意味。潮干狩りは干潟で行われ、春の大潮(おおしお)のときが最適とされています。【抽斗】読み方:ひきだし抽斗は”机や箪笥(たんす)などに物を入れるように取り付けた、抜き差しのできる箱のこと”の意味。【魚籠】読み方:びく魚籠は”獲(と)った魚を入れる籠(かご)のこと”の意味。【庇】読み方:ひさし庇は”建物の窓・出入口・縁側(えんがわ)などの上部に出ている小屋根のこと”の意味。似ているものに軒(のき)がありますが、軒は”屋根の下端で、建物の壁面より外に出ている部分のこと”を指します。ちなみに縁側は、庇だけでなく軒(のき)を屋根代わりにしているものも多いため覚えておきましょう。【柄杓】読み方:ひしゃく柄杓は”器状の容器に長い柄(え)を付けた、水などを汲(く)む道具のこと”の意味。【櫃】読み方:ひつ櫃は”蓋(ふた)が上に向かって開く大形の箱のこと/(御櫃(おひつ)の形で)飯を入れる器のこと”の意味。【棺】読み方:ひつぎ棺は”死体を納めて葬(ほうむ)る木製の箱のこと”の意味。【火鉢】読み方:ひばち火鉢は”炭を入れた上に炭火を置いて、手や室内を温める道具のこと”の意味。【屏風】読み方:びょうぶ屏風は”部屋に立てて風を遮(さえぎ)り、仕切りや装飾に用いる家具のこと”の意味。縦長の木の枠の上に紙や布を貼ったものを、2枚(または4枚、6枚)繋ぎ合わせ、折り畳めるようにしたものです。表面に絵などが描かれている場合が多いです。【鞴(吹子)】読み方:ふいご鞴(吹子)は”火をおこしたり強めたりするのに用いる送風装置のこと”の意味。鞴は鍛冶屋(かじや)などが金属の精錬・加工に使用し、箱の中のピストンを手や足で動かして風を送ります。【布巾】読み方:ふきん布巾は”食器類を拭く布のこと”の意味。【袱紗】読み方:ふくさ※上はポケット型の袱紗の写真袱紗は”絹・縮緬(ちりめん)などで作られ、ご祝儀や香典などを包むための方形の布のこと”の意味。もともとは一枚布でできていましたが、現在ではポケット型になっている二つ折りタイプも多く、ご祝儀や香典だけでなく小物入れとしても用いられます。【不織布】読み方:ふしょくふ不織布は”糸の形態を経(へ)ずに、繊維を合成樹脂その他の接着剤で接合して布状にしたもの”の意味。不織布は、弾性(だんせい)・強度・通気性に優れています。【襖】読み方:ふすま襖は”木で骨組みを作り、その両面に紙または布を張った建具(たてぐ)のこと”の意味。引き戸の一種で、部屋と部屋の仕切りや、押入れ(おしいれ)などに用いられます。【文机】読み方:ふづくえ(ふみづくえ)文机は”読み書きをする机のこと”の意味。【布団(蒲団)】読み方:ふとん布団(蒲団)は”布で作った袋の中に、綿や羽毛などを入れたもの”の意味。【文箱】読み方:ふばこ(ふみばこ)文箱は”手紙などを入れておく手箱(てばこ)。また、手紙を入れて先方に届けるために持ち歩いた箱のこと”の意味。【麓】読み方:ふもと麓は”山の下あたりの部分。山の裾(すそ)のこと”の意味。【篩】読み方:ふるい篩は”円形の枠の底に網(あみ)を張った道具のこと”の意味。粉または粒状のものを中に入れて、振り動かすことによって細かいものと粗いものを分けるために用いられます。「篩に掛ける」という慣用句がありますが、これは粒または粒状のものを篩を使って分けることから、”多くの中から良いものだけを選別すること”の意味となっています。例えば「希望者が多いため、試験で篩に掛けて優秀な者を選別する」や「ここに置いているのは、篩に掛けられた良い商品になります」のように用いられます。【文鎮】読み方:ぶんちん文鎮は”紙や書類が風などで飛んだり動いたりしないように、重しとして載せる文房具のこと”の意味。金属・玉石(ぎょくせき)などの材料で作られ、形状も様々で、一般的には習字で使われることが多いです。【分銅】読み方:ふんどう分銅は”秤(はかり)で重さを量るとき、標準とする金属のおもりのこと”の意味。【褌】読み方:ふんどし褌は”男子が陰部を覆(おお)い隠すために用いる布。また、相撲(すもう)のまわしのこと”の意味。「人の褌で相撲を取る」ということわざがありますが、これは相撲を取るには褌がなければいけないが、自分の褌がないからと他の人の褌を身に付けて土俵に上がったことからきていて、”他人の物を利用して自分の役に立てること”の意味になります。例えば「彼のアイデアのおかげで成功したのに、それをすべて自分の実力だと思っているなんて、人の褌で相撲を取ったようなもんだよ」のように用いられます。【貝独楽】読み方:べいごま貝独楽は”巻き貝であるバイの殻(から)に、鉛を溶かしてそれを詰めて作った独楽。また、これを真似て鉄や鉛などで作った独楽のこと”の意味。本体にひもを巻きつけて、その巻きつけたひもを一気に引いて台の上に投げ入れます。複数人が貝独楽を一気に台の上に投げ入れ、台の上で最も長く回転していたものが勝ち(他の貝独楽に台から弾き出されたら負け)になります。【兵児帯】読み方:へこおび兵児帯は”男性または子供が締めるしごき帯のこと”の意味。もともとは薩摩(さつま)の兵児(へこ)が、普段使いとして締めていた帯ということが兵児帯の名称の由来とされています。兵児というのは”15歳以上、25歳以下の青年のこと”を言います。ただ現在では女性用の兵児帯もあるので、「兵児帯=男性または子供用」というわけではないので覚えておきましょう。【舳先(舳)】読み方:へさき舳先(舳)は”船の先端部分のこと”の意味。【箆(篦)】読み方:へら箆(篦)は”竹・木・金属などを細長く平らに削って作られる道具のこと”の意味。※上はゴム箆(ごむべら)の写真箆は粘り気のあるものを混ぜたり、それを何かに塗ったりするときに用いられ、お菓子作りや料理の場面ではゴム・シリコン製の箆が使われることも多いです。【箒(帚)】読み方:ほうき箒(帚)は”ちりやごみなどをはく掃除(そうじ)道具のこと”の意味。【硼砂】読み方:ほうしゃ硼砂は”硼酸(ほうさん)ナトリウムの白色の結晶のこと”の意味。白色の脆(もろ)い柱状結晶で、天然・人工のどちらでも存在しますが、日本で産出されることはほとんどありません。天然だと塩湖が乾燥した跡地で産出されることが多く、人工的には硼酸に炭酸ナトリウムを加えて中和して産出します。【墨汁】読み方:ぼくじゅう墨汁は”墨(すみ)をすった黒い液のこと。特に、すぐに使えるように製造された墨色の液のこと”の意味。【埃】読み方:ほこり埃は”物の上にたまったり、空中に飛び散ったりする細かいちりのこと”の意味。【釦(鈕)】読み方:ボタン※上は釦(前者の意味)の写真※上は釦(後者の意味)の写真釦(鈕)は”衣類の合わせ目の片方につけ、もう片方の穴にはめて合わせ目を留めるもの/指で押して機械などを作動・停止させるための突起状のもの”の意味。【木履】読み方:ぽっくり木履は”女性用の駒下駄(こまげた)のひとつで、厚い台の底をくりぬき、後ろを丸く、前部を前のめりにし、漆(うるし)を塗ったもののこと”の意味。【畔】読み方:ほとり畔は”海や川・池などの水際(みずぎわ)のこと/その付近。近辺のこと”の意味。後者の意味は例えば、「道の畔を歩いていたときの出来事だ」や「私は焚火(たきび)の畔に座った」のように用いられます。【梵天】読み方:ぼんてん梵天は”耳かきの匙(さじ)の反対側にある、綿毛のような白い羽毛がついた部分のこと”の意味。梵天は、耳かきをしたあとの細かい耳垢(みみあか)を取るためにあります。耳かきをしたあとは、取りきれない細かい耳垢が耳の中に落ちているため、梵天を使ってからめとるように細かい耳垢を取ります。【雪洞】読み方:ぼんぼり雪洞は”小さな行灯(あんどん)のこと”の意味。行灯というのは”木や竹の枠に紙を貼り、中に油皿を入れて火を灯す照明具のこと”で、現在では中に火を灯すのではなく、電球を入れたりすることも多いです。↓マ行~【勾玉】読み方:まがたま勾玉は”古代、日本で装身具に使われていた、湾曲(わんきょく)した玉のこと”の意味。勾玉の材料には、瑪瑙(めのう)・翡翠(ひすい)・水晶などの鉱物が使用されていました。【薪】読み方:まき薪は”燃料にするために適当な大きさに切り割って乾燥させた木のこと”の意味。薪が直接地面に触れないようにし、雨に当たらない風通しの良い場所に積んで乾燥させます。【鉞】読み方:まさかり※上は鉞(まさかり)の写真鉞は”伐採(ばっさい)用の大形の斧(おの)のこと”の意味。つまり鉞というのは、斧の種類の中のひとつになります。※上は斧(おの)の写真一般的な斧は上の写真のような形で、斧というのは”木を叩き切ったり、割ったりする道具のこと”です。その形状から、鉞は木の枝を落としたり細い木を割るのに使われることが多く、斧は薪(まき)を叩き割るなど比較的大きめの木を割るのに使われることが多いです。【桝席(升席)】読み方:ますせき桝席(升席)は”劇場・相撲場(すもうば)などで、四角形に仕切った観客席のこと”の意味。一桝(ひとます)の定員は4人ほどで仕切られていることが多いです。【燐寸】読み方:マッチ燐寸は”軸木(じくぎ)の先に発火剤をつけた、摩擦によって火をつける道具のこと”の意味。軸木の先の発火剤には「塩素酸カリウム・二酸化マンガン・硫黄など”が使われ、容器などには”赤燐(せきりん)・流化アンチモンなど」が塗布されています。発火剤(軸木の先につける方)に赤燐・黄燐(おうりん)が用いられている燐寸もありますが、粗面ならどこにこすりつけても発火してしまうため、現在は製造が禁止されています。【松脂】読み方:まつやに松脂は”松の木の幹(みき)から分泌される樹脂のこと”の意味。松脂は、粘り気と芳香がある淡黄色の樹脂で、固化すると脆(もろ)いガラス状になります。【俎板(俎・真魚板)】読み方:まないた俎板(俎・真魚板)は”食材を料理するのに用いる板のこと”の意味。【眉墨(黛)】読み方:まゆずみ眉墨(黛)は”眉を描く墨(すみ)。アイブロウのこと”の意味。【万華鏡】読み方:まんげきょう※上は万華鏡を覗いたときの模様万華鏡は”円筒の中に3枚の長方形の鏡を三角に組み合わせ、色紙などの小片を入れ、回しながら覗(のぞ)いて模様の変化を楽しむ玩具(おもちゃ)のこと”の意味。【万灯】読み方:まんどう万灯は”木の枠に紙を貼って、中に火を灯し、長い柄(え)で高く上げて持つもの”の意味。現在では中に火を灯すのではなく、電球を入れたりすることも多いです。【万力】読み方:まんりき万力は”工作物を挟み、締めつけて固定する工具のこと”の意味。【木乃伊】読み方:ミイラ木乃伊は”人間または動物の死体が永(なが)く原形に近い形をとどめているもの”の意味。永くというのは、「永久」に近い意味で使われます。【神輿】読み方:みこし神輿は”祭礼のときに担ぐ、神霊を安置した輿(こし)のこと”の意味。輿というのは、”屋形(やかた)の下に担ぐための2本の長い棒を付けた乗り物のこと”です。【岬】読み方:みさき岬は”海または湖に向かって突き出した陸地の端のこと”の意味。【水瓶】読み方:みずがめ水瓶は”飲み水などを蓄えておくための瓶(かめ)のこと”の意味。瓶(かめ)というのは、”水・酒などを入れる、口が広く底の深い陶磁器のことのこと”を指します。【明朝体】読み方:みんちょうたい明朝体は”漢字の書体のひとつ”の意味。明朝体は書籍・雑誌・新聞などで用いられる基本的な書体で、縦線が太くて、横線が細いという特徴があります。中国の明朝(みんちょう)の時代に伝来したことからこの名称が付けられています。【筵(莚・蓆・席)】読み方:むしろ筵(莚・蓆・席)は”藺(い)・蒲(がま)・藁(わら)・竹などを編んで作った敷物のこと”の意味。【鞭】読み方:むち鞭は”馬・牛などを打って進ませるための革・竹などで作った細長いもの”の意味。【眼鏡】読み方:めがね(がんきょう)眼鏡は”視力の調整や目を保護するための器具のこと”の意味。「がんきょう」というのは、「めがね」の別名です。【鍍金】読み方:めっき鍍金は”金属または非金属の表面を、他の金属の薄い膜で覆うこと。また、そのようにしたもの”の意味。鍍金は、装飾・防食(金属の腐食を防ぐ)などの目的で行われます。【毛筆】読み方:もうひつ毛筆は”動物の毛で作られた筆のこと。また、その筆で書くこと”の意味。【籾】読み方:もみ※上は籾の写真籾は”脱穀(だっこく)の後の、外皮に包まれたままの米のこと/籾殻(もみがら)の略のこと”の意味。一般的には”脱穀の後の、外皮(籾殻)に包まれたままの米のこと”を指すことが多いです。脱穀の後に籾摺(もみす)りし、外皮(籾殻)を取り除いたものを「玄米(げんまい)」と呼びます。【銛】読み方:もり銛は”投げたり突いたりして、魚を刺して捕らえる漁具(ぎょぐ)のこと”の意味。【門扉】読み方:もんぴ門扉は”門の扉のこと”の意味。【紋服】読み方:もんぷく紋服は”紋(もん)をつけた和服のこと”の意味。紋というのは、”代々その家に伝わる家のしるしのこと”を指します。↓ヤ行~【屋形船】読み方:やかたぶね屋形船は”屋形(やかた)と、その下に座敷(ざしき)が設けられた船のこと”の意味。屋形というのは”船などの上に設けた屋根形の部分のこと”で、屋形船は川や海辺での遊覧、宴会や食事などに利用されます。【薬缶】読み方:やかん薬缶は”銅・アルミニウムなどから作られている、湯を沸かすのに用いる容器のこと”の意味。【櫓】読み方:やぐら※上は櫓(高楼)の写真※上は物見櫓の写真櫓は”城門や城壁の上に設けた高楼(こうろう)のこと/遠くを見るために材木などを高く組んで造った構築物。物見櫓(ものみやぐら)のこと”の意味。高楼というのは”高く造った建物のこと”で、前者の櫓(高楼)は敵情視察や射撃のために設けられます。【鏃(矢尻)】読み方:やじり鏃(矢尻)は”矢の先端に付ける、射当てたときに突き刺さる尖(とが)った部分のこと”の意味。【鑢】読み方:やすり鑢は”棒状や板状で、表面に細かな刻みのある鋼鉄製の工具のこと”の意味。工作物の表面を平らに削ったり、角(かど)を落としたりするのに用いられます。”厚手の紙や布に、金剛砂(こんごうしゃ)やガラス粉を塗りつけたもの”を「紙鑢(かみやすり)」と呼び、紙鑢のことも含めて鑢ということがあります。【屋台】読み方:やたい屋台は”移動できるようにした屋根付きの店のこと”の意味。自動車を改造して店にしているようなものも含まれます。屋台は祭り・行事のときなどでよく見かけ、飲食物や玩具(おもちゃ)などを売っています。【浴衣】読み方:ゆかた浴衣は”入浴後や夏に着る、木綿(もめん)で作った単衣(ひとえ)の着物のこと”の意味。単衣というのは”季節の変わり目(6月・9月)によく着られる着物”で、着物の生地が1枚だけで作られているものを言います。着物の生地が2枚で作られているものを「袷(あわせ)」と呼び、袷の着物は生地が2枚で作られていることから暖かく、6月~9月の時期だと暑いため着ることはほとんどありません。暑い時期には、涼しい単衣(生地が1枚だけ)の着物を着ることが多いです。【雪達磨】読み方:ゆきだるま雪達磨は”雪を丸めたものを2つ重ね、小石や木の枝などで目・鼻・口を付けたもの”の意味。【湯湯婆】読み方:ゆたんぽ湯湯婆は”暖房器具のひとつ”の意味。金属・陶器(とうき)製で、中にお湯を入れて寝床や足を温めるために用いられます。【葦簀】読み方:よしず※上は葦簀の写真葦簀は”葦(あし)の茎(くき)を並べて糸で編んだもの”の意味。葦簀は、日除けや目隠しなどの目的で用いられます。「葦(あし)」は別名で「葦(よし)」と呼ばれ、葦(よし)の茎を編んで作った簀(す)であることから「葦簀(よしず)」と名付けられました。簀というのは、”割り竹や葦(あし)などを粗く編んだもの”を指します。ちなみに葦簀と混同されがちなものに「簾(すだれ)」がありますが、これらの違いは”立て掛けるもの”なのか”上から垂らすもの”なのかです。※上は簾の写真葦簀は比較的大きなサイズで立て掛けて使い、簾の場合は上から垂らして使用します。(簾は、日除けや部屋の仕切りなどの目的で用いられます)【寄席】読み方:よせ寄席は”講談・落語・漫才などを興行(こうぎょう)する場所のこと”の意味。興行というのは、”料金を取ってお客さんに催し物を観覧してもらうこと”を言います。寄席は、漫才などを興行するための場所を指している言葉であって、ひとつひとつの席のことを指しているわけではないので覚えておきましょう。【鎧】読み方:よろい鎧は”身に着けて体を防護する武具のこと”の意味。↓ラ行~【欄干】読み方:らんかん欄干は”橋・階段などの縁(ふち)に、人が落ちるのを防いだり、装飾したりするのを目的として柵(さく)状に設置されたもの”の意味。【洋灯】読み方:ランプ洋灯は”石油を燃料とする照明具のこと”の意味。石油を入れた器に火を灯す芯(しん)をさし、その周りをガラス製の筒(つつ)で覆ったものを指します。【坩堝】読み方:るつぼ坩堝は”金属を強く熱して溶かすのに用いる筒形(つつがた)の深い容器のこと”の意味。【煉瓦】読み方:レンガ煉瓦は”粘土に砂・石灰などを混ぜて練り、長方体などに成型し、乾燥して窯(かま)で焼いたもの”の意味。【蝋燭】読み方:ろうそく蝋燭は”縒(よ)り糸や紙縒(こよ)りを芯(しん)として、その周りに蝋(ろう)やパラフィンを付け固めて円柱状に作ったもの”の意味。蝋というのは”脂肪酸とアルコールからなるエステル(酸とアルコールから生じる、水に溶けない化合物)のこと”で、熱に溶けやすく燃えやすい性質を持っています。パラフィンというのは”石油から分離された白色不透明の固体のこと”で、蝋燭の他に燐寸(マッチ)・クレヨンなどの原料として用いられます。パラフィンは、和名で「石蝋(せきろう)」と呼ばれます。【楼門】読み方:ろうもん楼門は”2階作りの門で、上部に屋根を持つもの”の意味。【緑青】読み方:ろくしょう緑青は”銅または銅合金の表面に生じる緑色の錆(さび)のこと”の意味。【肋木】読み方:ろくぼく肋木は”体操用具のひとつで、縦木に多くの横木を肋骨(ろっこつ)状に固定したもの”の意味。【轆轤】読み方:ろくろ轆轤は”回転式の装置で、円形の陶磁器を成形するときに用いる台のこと”の意味。台の上に粘土などを乗せ、台を回しながら粘土に指などを当てることで形を作っていきます。手で台を回すものや、台の下にある部分を足で蹴って回すものなどがあります。↓ワ行~【和琴】読み方:わごん和琴は”日本の弦楽器ひとつ”の意味。桐(きり)製の台に6本の弦を張った日本古来の琴(こと)で、右手に持った「琴軋(ことさき)」と呼ばれる撥(ばち)と左手の指で弾いて演奏します。【業物】読み方:わざもの業物は”名工が鍛えた、切れ味の良い刀剣のこと”の意味。【轍】読み方:わだち轍は”車が通ったあとに残る、車輪の跡のこと”の意味。「同じ轍(てつ)を踏む」という慣用句がありますが、これは前の車の車輪の跡にはまって転倒してしまうことから、”前の人と同じ失敗を繰り返すこと”の意味で用いられます。(単に「轍(てつ)を踏む」とだけ言うこともあります)例えば「おれと同じ轍を踏むのだけはやめてくれ」や「同じ轍を踏む可能性は十分にある」のように用いられます。【湾岸】読み方:わんがん湾岸は”湾の沿岸のこと”の意味。湾というのは”海が陸地に入り込んでいる所のこと”で、沿岸というのは”海・川・湖などに沿(そ)った陸地。また、海・川・湖などの陸地に沿った部分のこと”を指します。【腕章】読み方:わんしょう腕章は”目印として腕に巻いたり付けたりする布などのこと”の意味。道具・身近なモノの難読漢字(一覧表)※1:漢字表記が複数ある場合は、一般的に使われることが多いほうの漢字表記を優先しています。例 【行灯(行燈)】 ⇒ 【一般的に使われることが多い漢字表記(比較して一般的に使われることが少ない漢字表記)】※2:読み方が複数ある場合は、一般的に読まれることが多い読み方を優先し、どちらも一般的に読まれることが多い場合は五十音順に表記しています。例 【風車】 読み方:かざぐるま、ふうしゃ (どちらも一般的に読まれることが多いため五十音順で表記)漢字読み方備考欄足枷あしかせ畦道あぜみち鐙あぶみ行灯(行燈)あんどん庵(廬)いおり筏いかだ鋳型いがた錨(碇)いかり生け簀(生簀)いけす衣桁いこう漁火いさりび椅子いす疣いぼ鋳物いもの甍いらか刺青いれずみ(しせい)「いれずみ」は”入れ墨”と表記されることが多い囲炉裏いろり岩室いわむろ臼うす団扇うちわ畝(畦)うね畦は「あぜ」と読むことがほとんど産衣うぶぎ産毛うぶげ雲母うんも(きらら)「きらら」は、「うんも」の別名烏帽子えぼし襟えり縁石えんせき縁台えんだい大鋸屑おがくず桶おけ白粉おしろい御虎子おまる重石おもし玩具おもちゃ(がんぐ)自鳴琴オルゴール(じめいきん)「じめいきん」は、「オルゴール」の別名音叉おんさ櫂かい碍子がいし外套がいとう懐炉かいろ案山子(鹿驚)かかし篝かがり垣根かきね額縁がくぶち画材がざい風車かざぐるま、ふうしゃ「かざぐるま」と「ふうしゃ」で意味が異なる瘡蓋(痂)かさぶた風見鶏かざみどり瓦斯ガス鎹かすがい絣(飛白)かすり帷子かたびら滑車かっしゃ合羽かっぱ割烹着かっぽうぎ鬘かつら門松かどまつ鼎かなえ曲尺(矩尺)かねじゃく鞄かばん黴カビ画鋲がびょう兜かぶと釜かま蝦蟇口がまぐち竈かまど裃かみしも剃刀かみそり蚊帳かや唐獅子からじし硝子ガラス歌留多(骨牌)かるた枯山水かれさんすい画廊がろう簪かんざし鉗子かんし橇かんじき、そり「かんじき」と「そり」で意味が異なる岩礁がんしょう鉋かんな閂かんぬき甲板かんぱん甘味処かんみどころ(あまみどころ)生糸きいと煙管きせる(えんかん)「きせる」と「えんかん」で意味が少し異なる牛車ぎっしゃ衣笠(絹傘)きぬがさ杵きね脚立きゃたつ脚絆きゃはん急須きゅうす経木きょうぎ香車きょうしゃ錐きり巾着きんちゃく楔くさび櫛くし薬玉くすだま嘴(喙・觜)くちばし靴くつ沓石くついし轡くつわ鞍くら曲輪(郭・廓)くるわ鍬くわ懸魚げぎょ袈裟けさ下駄げた玄翁(玄能)げんのう碁石ごいし鯉幟こいのぼり格子こうし香典こうでん格天井ごうてんじょう行李こうり炬燵(火燵)こたつ小鼓こつづみ小包こづつみ鏝こて籠手(小手・篭手)こて瘤こぶ独楽こま塵箱(芥箱)ごみばこ紙縒り(紙縒)こより混凝土コンクリート賽子(骰子)サイコロ菜箸さいばし財布さいふ酒蔵さかぐら「しゅぞう」は”酒造”と表記されるため注意盃(杯)さかずき酒樽さかだる匙さじ桟敷さじき刺子さしこ砂州(砂洲)さす刺股さすまた早苗さなえ錆さび座布団ざぶとん作務衣さむえ鞘さや笊ざる三叉路さんさろ三線さんしん桟橋さんばし栞(枝折)しおり枝折戸しおりど敷居(閾)しきい鹿威しししおどし雫(滴)しずく竹刀しない鎬しのぎ芝生しばふ注連縄しめなわ赤銅しゃくどう車窓しゃそう鯱(鯱鉾)しゃちほこ鯱は「しゃち」と読むこともできる三味線しゃみせん杓文字しゃもじ砂利じゃり絨毯じゅうたん十二単じゅうにひとえ数珠じゅず襦袢じゅばん背負子しょいこ定規じょうぎ漏斗じょうご(ろうと)障子しょうじ装束しょうぞく如雨露じょうろ燭台しょくだい寝具しんぐ真珠しんじゅ真鍮しんちゅう水筒すいとう鋤すき頭巾ずきん双六すごろく生絹すずし(きぎぬ)硯すずり裾すそ簾すだれ磨硝子すりガラス擂粉木すりこぎ擂鉢すりばち寸胴ずんどう正鵠せいこく生石灰せいせっかい「しょうせっかい」は”消石灰”と表記されるため注意歳暮せいぼ井目せいもく蒸籠せいろ(せいろう)石鹸せっけん雪駄せった雪隠せっちん雪庇せっぴ千社札せんじゃふだ扇子せんす発条ぜんまい(ばね)「ぜんまい」と「ばね」で意味が少し異なる雑巾ぞうきん象牙ぞうげ草履ぞうり粗品そしな袖そで算盤そろばん松明たいまつ箍たが鏨(鑽)たがね凧たこ胼胝(胝)たこ山車だし襷たすき三和土たたき太刀たち鬣たてがみ炭団たどん煙草たばこ足袋たび袂たもと盥たらい達磨だるま束子たわし短冊たんざく楽車だんじり箪笥たんす卓袱台ちゃぶだい手水鉢ちょうずばち提灯ちょうちん蝶番ちょうつがい手斧ちょうな(ておの)猪口ちょこ衝立ついたて槌つち葛籠(葛篭)つづら角笛つのぶえ鍔(鐔)つば蕾つぼみ爪楊枝つまようじ氷柱つらら鶴嘴つるはし釣瓶つるべ天蚕糸てぐす梃子てこ手錠てじょう天蓋てんがい天井てんじょう天袋てんぶくろ伝馬船てんません投網とあみ樋とい砥石といし灯籠とうろう徳俵とくだわら髑髏どくろ(しゃれこうべ)「しゃれこうべ」は、「どくろ」の別名時計とけい徳利とっくり土嚢どのう登坂車線とはんしゃせん銅鑼ドラ渚(汀)なぎさ薙刀(長刀)なぎなた長押なげし鉈なた納屋なや鳴子なるこ納戸なんど膠にかわ肉球にくきゅう仮漆ニス螺子(捻子・捩子)ねじ軒のき鋸のこぎり熨斗のし鑿のみ暖簾のれん狼煙(烽火)のろし袴はかま刷毛はけ馬穴バケツ羽子板はごいた羽衣はごろも端材はざい鋏はさみ艀はしけ梯子はしご法被はっぴ波止場はとば鼻緒はなお埴輪はにわ飯盒はんごう干潟ひがた抽斗ひきだし魚籠びく庇ひさし柄杓ひしゃく櫃ひつ棺ひつぎ火鉢ひばち屏風びょうぶ鞴(吹子)ふいご布巾ふきん袱紗ふくさ不織布ふしょくふ襖ふすま文机ふづくえ(ふみづくえ)布団(蒲団)ふとん文箱ふばこ(ふみばこ)麓ふもと篩ふるい文鎮ぶんちん分銅ふんどう褌ふんどし貝独楽べいごま兵児帯へこおび舳先(舳)へさき箆(篦)へら箒(帚)ほうき硼砂ほうしゃ墨汁ぼくじゅう埃ほこり釦(鈕)ボタン木履ぽっくり畔ほとり梵天ぼんてん雪洞ぼんぼり勾玉まがたま薪まき鉞まさかり桝席(升席)ますせき燐寸マッチ松脂まつやに俎板(俎・真魚板)まないた眉墨(黛)まゆずみ万華鏡まんげきょう万灯まんどう万力まんりき木乃伊ミイラ神輿みこし岬みさき水瓶みずがめ明朝体みんちょうたい筵(莚・蓆・席)むしろ鞭むち眼鏡めがね(がんきょう)「がんきょう」は、「めがね」の別名鍍金めっき毛筆もうひつ籾もみ銛もり門扉もんぴ紋服もんぷく屋形船やかたぶね薬缶やかん櫓やぐら鏃(矢尻)やじり鑢やすり屋台やたい浴衣ゆかた雪達磨ゆきだるま湯湯婆ゆたんぽ葦簀よしず寄席よせ鎧よろい欄干らんかん洋灯ランプ坩堝るつぼ煉瓦レンガ蝋燭ろうそく楼門ろうもん緑青ろくしょう肋木ろくぼく轆轤ろくろ和琴わごん業物わざもの轍わだち湾岸わんがん腕章わんしょう項目1項目2項目3)★ -->関連ページ<難読漢字の一覧>⇒【一文字】難読漢字の一覧!⇒【野菜・果物・茸】難読漢字の一覧!⇒【魚・貝・海藻】難読漢字の一覧!⇒【動物】難読漢字の一覧!⇒【鳥】難読漢字の一覧!⇒【花・植物】難読漢字の一覧!⇒【虫】難読漢字の一覧!⇒【食べ物・飲み物】難読漢字の一覧!<読み間違えやすい漢字の一覧>⇒読み間違えやすい漢字一覧!⇒慣用読み(百姓読み)の一覧!<難読漢字の一覧(偏)>⇒【魚偏】難読漢字の一覧!⇒【虫偏】難読漢字の一覧!⇒【木偏】難読漢字の一覧!⇒【金偏】難読漢字の一覧!