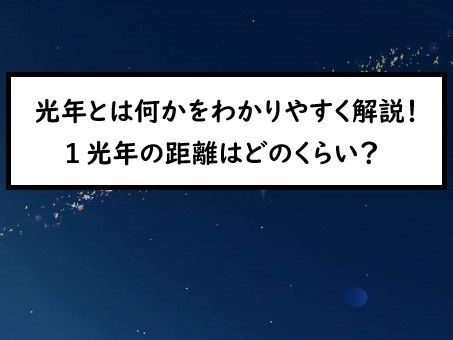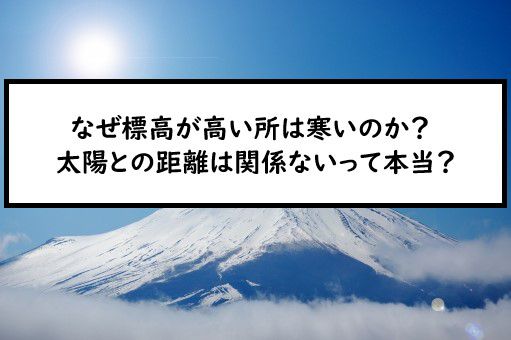さて天文学には”光年(こうねん)”という単位があります。この光年というのは時間を表す単位のことではなく、距離を表す単位だということはご存知でしょうか。「何万光年先に存在する惑星」というような言葉も聞きますが、これは一体どのくらいの距離があるのか疑問に感じますよね。そこでこのページでは、光年とは何かをわかりやすく解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次光年とは何かをわかりやすく解説!宇宙における距離を表す単位について天文単位[au]とは?パーセク[pc]とは?まとめ1.光年とは何かをわかりやすく解説!では光年とは何かをわかりやすく解説していきます。結論から言ってしまうと、光年(こうねん)とは、光の速度で年間に進む距離を表した単位のことです。光年の記号は、”light(光) year(年)”から[ly]が用いられています。”1光年であれば光の速度で1年間に進む距離”を表しており、”10光年であれば光の速度で10年間に進む距離”を表しています。光の速度は、1秒間あたりに約30万km(キロメートル)ほど進みます。なので1光年(つまり1[ly])とは約9兆4600億kmの距離のことを表しています。また光の速度がどのくらいの速度なのかあまりイメージが湧かないと思うので、簡単に言うと、1秒間に地球を7周半できる速さということになります。(地球1周の距離=約4万km)光の速度を秒速だけでなく、分速や時速に直したものを下にまとめています。次の章では”光年”以外の宇宙における距離の単位の解説をしていきます。2.宇宙における距離を表す単位についてでは光年以外の宇宙における距離の単位について見ていきましょう。光年に関してもそうでしたが、宇宙などの規模が大きなモノを対象とするときは、日常で用いている”km”のような距離の単位では、数字が大きくなりすぎてよく分からなくなります。なのでその対象(宇宙)の規模に合わせて、光年などの距離の単位が新しく作られました。宇宙における距離の単位には、天文単位・光年・パーセクという単位が用いられます。これらの単位を簡単にまとめると、下のようになります。単位記号距離定義天文単位au約1憶5000万km太陽と地球の平均的な距離光年ly約9兆4600億km光が1年間に進む距離パーセクpc約3.26光年=約30兆8400億km1天文単位が1秒角の角度を張るときの距離項目1項目2項目3項目4)★ -->光年については前の章で解説しているので、天文単位[au]とパーセク[pc]がどのような単位なのかそれぞれ見ていきましょう。天文単位[au]とは?天文単位とは、太陽と地球の平均的な距離を表した単位のことです。天文単位の記号は、”astronomical(天文の) unit(単位)”から[au]が用いられており、1天文単位は約1億5000万kmで、太陽と地球における平均的な距離を表しています。(10天文単位=15憶km)地球は太陽の周りを1年間かけて1周(公転)していますが、このとき地球と太陽における距離がいつも同じわけではありません。なので地球と太陽における”平均的な距離”を取っているんですね。その地球と太陽における平均的な距離(約1憶5000万km)を表した単位が、”天文単位[au]”となります。パーセク[pc]とは?パーセクとは、1天文単位が1秒角の角度を張るときの距離を表した単位のことです。パーセクの記号は、”parallax(視差) second(秒)”から[pc]が用いられており、1パーセクは約30兆8400億km(約3.26光年)で、1天文単位が1秒角の角度を張るときの距離を表しています。1天文単位が1秒角の角度を張るときの距離と言われても、よく分からないと思うので簡単にパーセクとは何かを図にすると下のようになります。上図のように1天文単位に対して、1秒の角度を張ったときの距離が1パーセクとなります。上図では1秒の角度がすごく大きく示されおり、実際の1秒の角度はもっと小さいので注意してください。以上が「光年とは何かをわかりやすく解説!1光年の距離はどのくらい?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、光年とは、光が年間に進む距離を表した単位のこと。1光年=約9兆4600億kmで、10光年=94兆6000億kmとなる。光年以外にも宇宙における距離の単位には、天文単位[au]とパーセク[pc]が存在する。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒銀河と銀河系と太陽系の違いとは?⇒なぜ太陽と月は地球とぶつからないのか?仕組みを簡単に図で解説!⇒月はなぜ光るのか?太陽と地球と月の位置関係をわかりやすく図で解説!⇒「すいきんちかもくどってんかい」とは何の順番を表している?⇒海王星とは?海王星の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!⇒海王星の英語名・読み方・由来とは?⇒なぜ朝が来ると明るくなって、夜が来ると暗くなるのか?⇒なぜ太陽は東から昇って、西に沈むのか?⇒太陽系とは何かをわかりやすく図で解説!⇒重力加速度とは?仕組みを分かりやすく図解!
ギモン雑学
「 距離 」の検索結果
-
-
さて山など標高が高い場所ほど寒く(気温が低く)なるというのは、実際に登山などで経験したり、聞いたりしてご存知かと思います。ではなぜ標高が高い場所ほど寒くなるのでしょうか。地上に比べて太陽までの距離が近くなって暖かくなりそうな気もしますが、標高が高くなれば太陽との距離も近くなると同時にどんどん寒くなっていきます。そこでこのページではなぜ標高が高い所は地上と比べて寒いのか?また太陽との距離は関係ないのかどうかを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次なぜ標高が高い所ほど寒いのか?高い所では地面からの熱で空気が暖められないから空気の量が少ないことで気温が下がるからまとめ1.なぜ標高が高い所ほど寒いのか?ではなぜ標高が高い所ほど寒いのかを簡単に見ていきましょう。結論から言ってしまうと、標高が高い場所ほど寒くなる理由は以下の2つです。高い所では地面からの熱で空気が暖められないから空気の量が少ないことで気温が下がるから上記の2つの理由により、標高が高い所は寒くなります。そして標高が高いほど気温が下がる理由には、太陽からの距離がどうか(近い・遠い)は関係ありません。なぜかというとそれは”太陽から地球までの距離”においては、”地球の地上から山頂までの距離”というのは大した距離ではないからです。太陽から地球までの距離はだいたい”1億4960万km”です。それに比べて日本で最も標高の高い山である富士山の頂上は、約3776m(3.776km)なので比べると大した距離ではありません。どちらにせよ地球上においては、太陽からの距離と気温は特に関係ないんですね。関連:太陽系とは何かをわかりやすく図で解説!さて本題に戻って標高が高い所ほど寒くなる理由について、それぞれ詳しく解説していきますね。高い所では地面からの熱で空気が暖められないからまず私たちが普段から気温が高い・気温が低いと言っているのは、空気の温度が高い・空気の温度が低いということを意味しています。空気の温度(気温)が上がるのは太陽光から直接空気が暖められるからではなく、太陽光に含まれている赤外線によって地面が暖められ、その地面から空気に熱が伝わるからです。(赤外線には物質を暖める性質があります)太陽光が直接空気を暖めることができないのは、簡単に言えば太陽光が空気を透過してしまうからです。(すべて透過してしまうわけではないですが、ほとんどが透過します)そして標高が高い山などでは太陽光が当たっている面が少ないため、地上と比べると周囲の空気を上手く暖めることができなくなります。これが標高が高いほど寒くなる1つ目の理由になります。関連:空気は太陽光で直接暖められないって本当?空気が暖まる仕組みとは?空気の量が少ないことで気温が下がるから標高が高くなると地上に比べて空気の量が少なくなるというのは、よく”空気が薄い”などと表現されることからもほとんどの人が知っていると思います。そしてこの空気の量が少なくなると起こるのが、気温が下がる(空気の温度が下がる)という現象になります。普通なら空気の温度を下げるときは空気を冷却して熱を奪えば良いですが、標高が高い所で起こるこの現象は外部からの熱の交換が一切関係ありません、つまり断熱した状態で、空気の温度が下がります。(この現象のことを断熱膨張と言います)断熱膨張について詳しい仕組みは下記をご覧ください。関連:断熱膨張とは?また断熱圧縮とは?どんな原理で温度変化するのか?これによりなぜ空気の温度が下がるのかというと、周囲の空気の量が少なくなり、その空気の体積が大きくなることで体積当たりの熱が少なくなるからです。周囲の空気の量が少なくなるということは、簡単に言えば、周囲の空気から押される力が弱くなるということです。(つまり気圧が小さくなるということ)そして周囲に存在する空気から押される力が弱くなるために、その空気の体積は地上に存在していたときと比較して大きくなります。なので例えば地上における空気が10の熱量を持っていたとして、その地上の空気を標高の高い所に移動させたとします。そうすると上図のように標高の高い所に移動させた地上の空気は、体積は大きくなりますがその空気自体が持っている熱量は変化しません。ですので地上から移動させた空気の体積当たりの熱量が減ってしまうんですね。体積当たりの熱量が減ってしまうということは、つまり空気の温度(気温)が下がるということです。これが標高が高くなるほど寒くなる理由の2つ目になります。関連:空気の膨張とは何か?空気の温度によって体積が変化する仕組みとは?以上が「なぜ標高が高い所は寒いのか?太陽との距離は関係ないって本当?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2.まとめこれまで説明したことをまとめますと、標高が高いほど気温が下がる理由には、太陽からの距離がどうかは関係ない<標高が高くなるほど寒くなる理由まとめ>高い所では地面からの熱で空気が暖められないから空気の量が少ないことで気温が下がるから (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒気圧とは何かをわかりやすく解説!なぜ気圧で人はつぶされないのか?⇒絶対零度とは?また絶対零度の温度は何度なのか?⇒絶対熱とは何か?絶対熱の温度は何度あるのか?⇒温度とは何か?物体の状態変化と温度の関係について解説!⇒空気とは何か?高い場所ほど空気が薄くなる理由とは?⇒密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?⇒熱と温度の違いとは?⇒雲とは何か?雲ができる仕組みを分かりやすく図解!⇒結露とは何か?仕組みを分かりやすく図解!