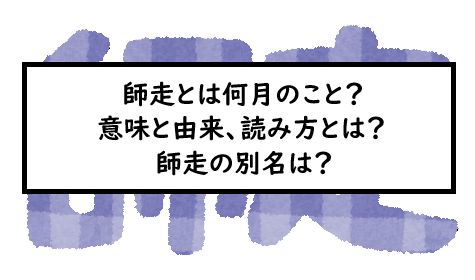さてあなたは師走とは何かをご存知でしょうか。いま現在では日本での暦は主に新暦が使われていますが、昔は新暦ではなく旧暦が使用されていました。師走というのは日本での旧暦の時代における月(1月、2月・・・)の名称なのですが、現在ではほとんど使用されることがないので分からない人も多いでしょう。そこでこのページでは師走とは何月のことを指しているのか?また師走の意味・由来・読み方・別名について簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次師走とは何月のことを指しているのか?師走の意味・由来・読み方について師走の別名とは何か?晩冬(ばんとう)梅初月(うめはつづき)雪月(ゆきづき)他の師走の別名(箇条書き)まとめ1.師走とは何月のことを指しているのか?では師走とは何月のことを指しているのか見ていきましょう。師走とは旧暦における月(1月、2月、3月・・・)の名称のことで、新暦(いま現在の暦)でいうところの”12月”のことを指しています。いまだと1年間が365日(うるう年だと366日)というのは一般的ですが、それはいま現在使用されているのが新暦だからです。(いま現在使用されている暦は、太陽暦のひとつであるグレゴリオ暦です)日本における旧暦では天保暦(太陰太陽暦のひとつ)が使用されていましたが、旧暦(天保暦)に従った場合は1年間が354日ということになります。そしてこの旧暦が使用されていたときの月の名称が”師走”であり、暦が新暦に改暦された現在では葉月という名称から”12月”に変更されました。ですが師走(旧暦の月)と12月(新暦の月)では季節にずれが発生していて、”だいたい1ヶ月~2ヶ月ほど”のずれがあるので注意が必要です。なので師走の時期は旧暦と新暦における季節のずれを考慮すると、新暦(現在の暦)でいうところの”12月下旬~2月上旬”のことを表していることになります。関連:旧暦の月(睦月、如月、弥生・・・)の意味と読み方、由来とは?関連:なぜ旧暦と新暦にずれが発生するのかを詳しく解説!2.師走の意味・由来・読み方についてでは師走の意味・由来・読み方について見ていきましょう。まず師走は旧暦における12月のことで、読み方は”師走(しわす)”になります。そして師走の意味・由来としては諸説ありますが、僧(お坊さん)がお経を唱えるため、各地を忙しく走り回ることからきている説が有力です。師走の”師”というのは師匠のことを意味しているのではなく、僧(お坊さん)のことを意味しており、僧などを敬っていう場合の言い方になります。(他にも師は教師のことを表して、学校の先生も忙しく走り回る月という説もあります)昔から年末にはお坊さん(僧)に自分の家まで来てもらい、お経を唱えてもらうというような風習がありました。いまではこのような風習はあまり残っていませんが、それだけ昔は年末になるとお坊さんにとってとても忙しい時期だったのですね。ちなみに”師走(しわす)”という読み方は当て字で、普通に読むと師走をしわすとは読むことはできません。いまでこそ師走と言えばしわすと読むのが常識となっていますが、師走(しわす)については当て字だということを覚えておきましょう。3.師走の別名とは何か?旧暦の月名である師走(しわす)ですが、実は師走という名称以外にも別名がたくさんあります。いまだと12月のことは12月としか言わず別名はありませんが、昔は月名に生活や季節に関連する呼び方をしていました。そしてその月を表す名称もひとつやふたつではありません。では師走の別名には一体どういう名称のものがあるのかを見ていきましょう。晩冬(ばんとう)師走が別名で晩冬(ばんとう)と呼ばれるのは、冬の終わりの方という理由からです。晩冬の”晩”には”終わりの方”という意味があるため、晩冬というのは冬の終わりの方であることを意味しています。現在の季節では12月と言えば冬が始まったばかりなのですが、旧暦の季節では冬というのは10月・11月・12月なので終わりの方にあたります。ですので晩冬は冬(10月・11月・12月)の終わりの方を意味しているので、旧暦の12月である師走の別名として晩冬(ばんとう)と呼ばれています。梅初月(うめはつづき)師走が別名で梅初月(うめはつづき)と呼ばれるのは、梅の花が咲き始めるころの月という理由からです梅の花の開花時期は他の花と比べてもかなり早く、梅の花はだいたい2月~3月にかけて咲きます。しかし季節が冬でも梅の品種によっては、早咲きの品種で12月下旬~1月に開花するものもあります。雪月(ゆきづき)師走が別名で雪月(ゆきづき)と呼ばれるのは、雪が降る月という理由からです旧暦における12月は現在の暦での12月下旬~2月上旬にあたるので、雪が降る地域ではすでに雪が積もり始めている時期です。地域によっては雪がほとんど降らないところもありますが、冬と言えば雪なので師走の別名として”雪月(ゆきづき)”と呼ばれています。他の師走の別名(箇条書き)”晩冬(ばんとう)”、”梅初月(うめはつづき)”、”雪月(ゆきづき)”以外にも、師走の別名として呼ばれている名称について下に箇条書きにしてみました。<師走の別名の一覧>乙子月(おとごづき)弟子月(おとごづき)親子月(おやこづき)年積月(としつむづき)果ての月(はてのつき)春待月(はるまちづき)黄冬(おうとう)季冬(きとう)窮陰(きゅういん)窮月(きゅうげつ)窮冬(きゅうとう)厳冬(げんげつ)除月(じょげつ)暮歳(ぼさい) などなど※上記以外にも師走の別名は数多く存在しています。以上が「師走とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?師走の別名は?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});4.まとめこれまで説明したことをまとめますと、師走(しわす)とは、旧暦における12月のこと。師走と新暦の12月には季節にずれがあり、師走は現在の12月下旬~2月上旬のことになる。師走の由来は、僧(お坊さん)がお経を唱えるために各地を忙しく走り回ることからきている。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒上旬と下旬と中旬の期間の違いとは?⇒新暦って何?旧暦との違いとは?⇒太陽暦とは?太陰暦と太陰太陽暦との違いって何?⇒ユリウス暦とは?グレゴリオ暦との違いって何?⇒紀元前とは?またBCとADの意味や表を分かりやすくまとめました!⇒今年と今年度の違いとは?年度の期間は目的によって異なるって本当?⇒和暦とは?西暦との違いは何か?⇒西暦とは何か?西暦はいつから使われた?西暦・和暦・干支の早見表!⇒うるう年(閏年)とは?4年に1度だけ366日になる仕組みを解説!⇒睦月とは何月のこと?意味と由来、読み方とは?睦月の別名は?