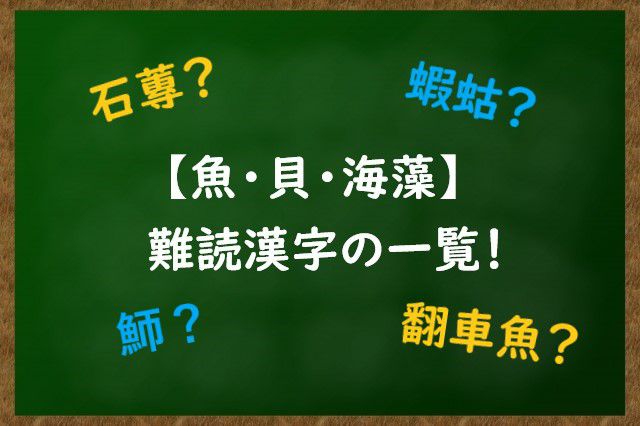このページでは魚・貝・海藻の難読漢字について簡単に一覧にしてまとめています。(魚・貝・海藻の難読漢字を新しく見つけ次第、追記していきます)どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次↓魚・貝・海藻の難読漢字の読み方や説明、写真などを載せています◆【ア行~】◇【カ行~】◆【サ行~】◇【タ行~】◆【ナ行~】◇【ハ行~】◆【マ行~】◇【ヤ行~】◆【ラ行~】◇【ワ行~】↓魚・貝・海藻の難読漢字とその読み方だけをザっと見たい方はこちら(同ページのリンクへ移動します)●魚・貝・海藻の難読漢字(一覧表)↓関連ページはこちら(同ページのリンクへ移動します)★関連ページ魚・貝・海藻の難読漢字※1:漢字表記が複数ある場合は、一般的に使われることが多いほうの漢字表記を優先しています(読み方の表記も同様)。例 【鮎並(鮎魚女)】 ⇒ 【一般的に使われることが多い漢字表記(比較して一般的に使われることが少ない漢字表記)】※2:読み方の横に「(一種)」「(総称)」の表記があるものは、以下のような意味になります。例 【ウツボ(一種)】 ⇒ 【(狭義では)ウツボ目ウツボ科ウツボ属に分類される海水魚の一種】【(広義では)ウナギ目ウツボ科に分類される海水魚の総称】の両方を意味例 【アジ(総称)】 ⇒ 【スズキ目アジ科に分類される海水魚の総称】を意味(アジという名称の特定の魚が存在するわけではない)※3:標準和名=【日本での正式な名称のこと】⇒学名と標準和名の違いとは?↓ア行~【鮎並(鮎魚女)】読み方:アイナメ鮎並というのは、”カサゴ目アイナメ科アイナメ属に分類される海水魚の一種”。鮎並(標準和名)は、別名で「油目(アブラメ)」「油子(アブラコ)」とも呼ばれています。【石蓴】読み方:アオサ(総称)石蓴というのは、”アオサ科アオサ属に分類される海藻の総称/(広義では)アオサ目に分類される海藻の総称”。【阿古屋貝】読み方:アコヤガイ阿古屋貝というのは、”ウグイスガイ目ウグイスガイ科アコヤガイ属に分類される二枚貝の一種”。養殖真珠(しんじゅ)の母貝とされ、天然の阿古屋貝でも殻内に真珠を持つことがあります。真珠は貝から採れる宝石の一種で、英語で「Pearl(パール)」と呼ばれています。【浅蜊(蜊・鯏)】読み方:アサリ(一種)※上は浅蜊(一種)の写真浅蜊というのは、”マルスダレガイ目マルスダレガイ科アサリ属に分類される二枚貝の一種/アサリ属に分類される二枚貝の総称”。模様は様々で、淡水の流れ込む浅海の砂泥地にいます。【鯵】読み方:アジ(総称)鯵というのは、”スズキ目アジ科に分類される海水魚の総称”。<真鯵>読み方:マアジ真鯵というのは、”スズキ目アジ科マアジ属に分類される海水魚の一種”。鯵というと、日本では一般的には真鯵を指すことが多いです。<丸鯵>読み方:マルアジ丸鯵というのは、”スズキ目アジ科ムロアジ属に分類される海水魚の一種”。真鯵と比較すると体高の割に左右の膨らみが大きく、断面が丸くなっていることが名称の由来になっています。<室鯵(鰘)>読み方:ムロアジ室鯵というのは、”スズキ目アジ科ムロアジ属に分類される海水魚の一種”。※上はくさやの写真脂肪分や旨みが少ないことから干物にされることが多く、伊豆(いず)諸島の特産品として知られる「くさや」(非常に強烈な臭いの干物)にも利用されています。くさやに用いるくさや汁のことを「魚室(むろ)」と呼んだことから、「室鯵(ムロアジ)」と名付けられたとされています。【穴子(海鰻)】読み方:アナゴ(総称)穴子というのは、”ウナギ目アナゴ科に分類される海水魚の総称”。<狆穴子>読み方:チンアナゴ狆穴子というのは、”ウナギ目アナゴ科チンアナゴ属に分類される海水魚の一種”。※上は狆(ちん)の写真日本犬の品種である「狆(ちん)」に顔つきが似ていることから名付けられ、細長い体を砂底から出してゆらゆら揺れている様子が人気です。<真穴子>読み方:マアナゴ真穴子というのは、”ウナギ目アナゴ科クロアナゴ属に分類される海水魚の一種”。穴子というと、一般的には真穴子のことを指すことが多いです。【甘子(天魚)】読み方:アマゴ甘子というのは、”サケ目サケ科サケ属に分類される淡水魚の一種”。河川で生まれて一生を河川で過ごす河川残留型(陸封型)を「甘子(アマゴ)」、生まれてから海へ下る降海型を「皐月鱒(サツキマス)」と呼びます。分類上、甘子と皐月鱒はどちらも同じ魚になります。【沖醤蝦】読み方:オキアミ(総称)沖醤蝦というのは、”オキアミ目に分類される甲殻類の総称”。プランクトン(浮遊生物)として知られ、飼料・釣り餌などに利用されます。【雨虎】読み方:アメフラシ(一種)※上は雨虎(一種)の写真雨虎というのは、”アメフラシ目アメフラシ科アメフラシ属に分類される軟体動物の一種/腹足綱後鰓類(ふくそくこうこうさいるい)の無楯類(むじゅんるい)に分類される軟体動物の総称”。体内に薄い貝殻を持ち、刺激を受けたり危険を感じると紫色の汁を放出し、それが煙幕での目くらましや外敵にとっての嫌な味であることからそれ以上襲われないようにする役割を果たします。この紫色の汁を放出した様子が、海水中に雨雲が立ち込めたように広がっていくことから「アメフラシ」と名付けられたとされています。<黒縁雨虎(黒縁雨降)>読み方:クロヘリアメフラシ黒縁雨虎というのは、”アメフラシ目アメフラシ科アメフラシ属に分類される軟体動物の一種”。体の各部が黒い線で縁取られていることから名付けられています。【鮎(香魚・年魚)】読み方:アユ鮎というのは、”キュウリウオ目キュウリウオ科アユ属に分類される淡水魚の一種”。綺麗な水を好み、その見た目の美しさから「清流の女王」とも呼ばれています。【鮑】読み方:アワビ(総称)鮑というのは、”ミミガイ科に分類される大型の巻貝の総称”。高級食材として知られ、コリコリとした食感が特徴的です。<蝦夷鮑>読み方:エゾアワビ蝦夷鮑というのは、”ミミガイ科アワビ属に分類される巻き貝の一種”。<黒鮑>読み方:クロアワビ黒鮑というのは、”ミミガイ科アワビ属に分類される巻き貝の一種”。【鮟鱇(華臍魚・琵琶魚)】読み方:アンコウ(一種)※上は鮟鱇(一種)の写真鮟鱇というのは、”アンコウ目アンコウ科アンコウ属に分類される海水魚の一種/アンコウ目アンコウ科に分類される海水魚の総称”。<黄鮟鱇(黄華臍魚・黄琵琶魚)>読み方:キアンコウ黄鮟鱇というのは、”アンコウ目アンコウ科キアンコウ属の海水魚の一種”。【烏賊(魷)】読み方:イカ(総称)烏賊というのは、”コウイカ目とツツイカ目に分類される軟体動物の総称”。<障泥烏賊>読み方:アオリイカ障泥烏賊というのは、”ツツイカ目ヤリイカ科アオリイカ属に分類される軟体動物の一種”。「障泥烏賊(アオリイカ)」は、大型で幅広である鰭(ひれ)の形などが、鞍(くら)の下で馬の胴体に巻く泥よけの馬具である「障泥・泥障(あおり)」に似ていたことから名付けられたとされています。<鯣烏賊>読み方:スルメイカ鯣烏賊というのは、”ツツイカ目アカイカ科スルメイカ属に分類される軟体動物の一種”。烏賊(鯣烏賊以外も用いられる)を切り開き、内臓を取り除いて干した食品のことを「鯣(するめ・スルメ)」と呼びます。<蛍烏賊>読み方:ホタルイカ蛍烏賊というのは、”ツツイカ目ホタルイカモドキ科ホタルイカ属に分類される軟体動物の一種”。※上は蛍烏賊が発光している様子蛍烏賊には体表に多数の発光器があり、蛍(ホタル)のように美しい発光(蛍烏賊は青白い光)をする烏賊であることから名付けられました。<紋甲烏賊>読み方:モンゴウイカ紋甲烏賊というのは、”雷烏賊(カミナリイカ:標準和名)の別名”。雷烏賊は、”コウイカ目コウイカ科コウイカ属に分類される軟体動物の一種”を指します。雷烏賊の名称は、雷が多い時期に漁獲されることに由来しています。紋甲烏賊は、背面に眼のような模様が多数あることから、”紋(模様)のある甲烏賊(コウイカ)”という意味で「紋甲烏賊(モンゴウイカ)」と名付けられました。<槍烏賊>読み方:ヤリイカ槍烏賊というのは、”ツツイカ目ヤリイカ科ヤリイカ属に分類される軟体動物の一種”。槍のように尖った鰭(ひれ)を持ち、見た目が槍に似ていることから名付けられました。【玉筋魚(鮊子)】読み方:イカナゴ(一種)※上は玉筋魚(一種)の写真玉筋魚というのは、”スズキ目イカナゴ科イカナゴ属に分類される海水魚の一種/スズキ目・ワニギス亜目・イカナゴ科に分類される海水魚の総称”。※上は小女子(コウナゴ)・新子(シンコ)の写真玉筋魚の稚魚は、東日本では「小女子(コウナゴ)」、西日本では「新子(シンコ)」と呼ばれています。【鶏魚(伊佐木・伊佐幾)】読み方:イサキ鶏魚というのは、”スズキ目イサキ科イサキ属に分類される海水魚の一種”。【石持(石首魚)】読み方:イシモチ石持というのは、”白口(シログチ:標準和名)の別名”。白口は、”スズキ目ニベ科シログチ属に分類される海水魚の一種”を指します。頭部に耳石(じせき)という平衡石(へいこうせき)があることから、別名で「石持(イシモチ)」と呼ばれています。【磯巾着(菟葵)】読み方:イソギンチャク(総称)磯巾着というのは、”イソギンチャク目に分類される刺胞(しほう)動物の総称”。口の周りに毒のある触手を多数持っていて、触手に「刺胞(しほう)」と呼ばれる毒液を注入する針を備えた細胞があります。<大疣磯巾着>読み方:オオイボイソギンチャク大疣磯巾着というのは、”イソギンチャク目ウメボシイソギンチャク科に分類される刺胞動物の一種”。<砂磯巾着>読み方:スナイソギンチャク砂磯巾着というのは、”イソギンチャク目ウメボシイソギンチャク科に分類される刺胞動物の一種”。<縦縞磯巾着>読み方:タテジマイソギンチャク縦縞磯巾着というのは、”イソギンチャク目タテジマイソギンチャク科に分類される刺胞動物の一種”。【鰯】読み方:イワシ(総称)鰯というのは、”ニシン目に分類される海水魚のうち、真鰯(マイワシ)・潤目鰯(ウルメイワシ)・片口鰯(カタクチイワシ)の総称”。<片口鰯>読み方:カタクチイワシ片口鰯というのは、”ニシン目カタクチイワシ科カタクチイワシ属に分類される海水魚の一種”。下顎(したあご)が小さく、上顎(うわあご)が大きく発達しているため、上顎だけのように見えることから名付けられました。<真鰯>読み方:マイワシ真鰯というのは、”ニシン目ニシン科マイワシ属に分類される海水魚の一種”。鰯というと、一般的には真鰯を指すことが多いです。【岩魚(嘉魚・鮇)】読み方:イワナ岩魚というのは、”サケ目サケ科イワナ属に分類される淡水魚の一種”。美しい見た目と獰猛(どうもう)な性質から、別名で「渓流の王様」(山女魚(ヤマメ)は「渓流の女王」)と呼ばれています。【石斑魚(鯎)】読み方:ウグイ石斑魚というのは、”コイ目コイ科ウグイ属に分類される淡水魚の一種”。基本的には淡水魚(淡水型)ですが、中には海に下る降海型もいます。【鱓】読み方:ウツボ(一種)※上は鱓(一種)の写真鱓というのは、”ウツボ目ウツボ科ウツボ属に分類される海水魚の一種/ウナギ目ウツボ科に分類される海水魚の総称”。鋭い歯と大きな口が特徴的で、細長い体が、矢を入れる容器である「靫(うつぼ)」に似ていることから名付けられました。<雲鱓>読み方:クモウツボ雲鱓というのは、”ウナギ目ウツボ科アラシウツボ属に分類される海水魚の一種”。<虎鱓>読み方:トラウツボ虎鱓というのは、”ウナギ目ウツボ科トラウツボ属に分類される海水魚の一種”。<鼻髭鱓(花髭鱓)>読み方:ハナヒゲウツボ鼻髭鱓というのは、”ウナギ目ウツボ科ハナヒゲウツボ属に分類される海水魚の一種”。【鰻】読み方:ウナギ(総称)鰻というのは、”ウナギ科ウナギ属に分類される回遊魚の総称”。<大鰻>読み方:オオウナギ大鰻というのは、”ウナギ目ウナギ科ウナギ属に分類される回遊魚の一種”。<日本鰻>読み方:ニホンウナギ日本鰻というのは、”ウナギ目ウナギ科ウナギ属に分類される回遊魚の一種”。日本で主に食べられているのは日本鰻で、鰻というと一般的には日本鰻のことを指します。<欧羅巴鰻>読み方:ヨーロッパウナギ欧羅巴鰻というのは、”ウナギ目ウナギ科ウナギ属に分類される回遊魚の一種”。【海胆(海栗)】読み方:ウニ(総称)海胆というのは、”ウニ綱に分類される棘皮(きょくひ)動物の総称”。「雲丹(ウニ)」の漢字が当てられているときは、動物ではなく、加工食品である「ウニ」のことを指します。<赤海胆(赤海栗)>読み方:アカウニ赤海胆というのは、”ホンウニ目オオバフンウニ科アカウニ属に分類される棘皮動物の一種”。<馬糞海胆(馬糞海栗)>読み方:バフンウニ馬糞海胆というのは、”ホンウニ目オオバフンウニ科バフンウニ属に分類される棘皮動物の一種”。見た目が「馬糞(ばふん)」に似ていることから名付けられました。<紫海胆(紫海栗)>読み方:ムラサキウニ紫海胆というのは、”ホンウニ目ナガウニ科ムラサキウニ属に分類される棘皮動物の一種”。【海牛】読み方:ウミウシ(総称)海牛というのは、”後鰓類(こうさいるい)のうち、貝殻が縮小・消失または体内に埋没した軟体動物の総称のこと”。海にいる蛞蝓(ナメクジ)のような生物で、牛の角のように2本の触覚があることが名前の由来になっています。<青海牛>読み方:アオウミウシ青海牛というのは、”裸鰓目(らさいもく)イロウミウシ科アオウミウシ属に分類される軟体動物の一種”。海牛というと、日本で最も一般的なのが青海牛になります。<小疣海牛>読み方:コイボウミウシ小疣海牛というのは、”裸鰓目イボウミウシ科コイボウミウシ属に分類される軟体動物の一種”。<更紗海牛>読み方:サラサウミウシ更紗海牛というのは、”裸鰓目イロウミウシ科アデヤカイロウミウシ属に分類される軟体動物の一種”。赤い網目状の模様が、染め物である「更紗(サラサ)」に似ていることから名付けられました。<光海牛>読み方:ヒカリウミウシ光海牛というのは、”裸鰓目フジタウミウシ科ヒカリウミウシ属に分類される軟体動物の一種”。刺激を受けると発光液を分泌して発光することから名付けられました。【鱏(海鷂魚)】読み方:エイ(総称)鱏というのは、”板鰓亜綱(ばんさいあこう)に分類される軟骨魚類のうち、鰓(エラ)が体の下面に開くものの総称”。ちなみに”板鰓亜綱に属する軟骨魚類のうち、鰓が体の側面に開くものの総称のこと”を「鮫(サメ)」と言います。<赤鱏>読み方:アカエイ※上は赤鱏(腹側)の写真赤鱏というのは、”トビエイ目アカエイ科アカエイ属に分類される海水魚の一種”。細長い尾には毒腺(どくせん)のある棘(トゲ)がいくつもついていて、尾を鞭(ムチ)のように払って刺そうとします。<燕鱏>読み方:ツバクロエイ燕鱏というのは、”トビエイ目ツバクロエイ科ツバクロエイ属に分類される海水魚の一種”。<鳶鱏>読み方:トビエイ鳶鱏というのは、”トビエイ目トビエイ科トビエイ属に分類される海水魚の一種”。【狗母魚(鱛)】読み方:エソ(総称)狗母魚というのは、”ヒメ目エソ科に分類される海水魚の総称”。<赤鱛(赤狗母魚)>読み方:アカエソ赤鱛というのは、”ヒメ目エソ科アカエソ属に分類される海水魚の一種”。<真鱛(真狗母魚)>読み方:マエソ真鱛というのは、”ヒメ目エソ科マエソ属に分類される海水魚の一種”。【海老(蝦)】読み方:エビ(総称)海老というのは、”甲殻類エビ目(十脚目)に分類される長尾類の総称”。海老(エビ)や蟹(カニ)の殻には「アスタキサンチン」という赤い色素が含まれていて、その赤い色素はタンパク質と結合していて、赤い色素は隠れてしまっています。ですが、この結合は加熱することで分解され、茹(ゆ)でたり焼いたりすることで赤い色素が現れて赤色に変化します。<伊勢海老(伊勢蝦・竜蝦)>読み方:イセエビ伊勢海老というのは、”エビ目イセエビ科イセエビ属に分類される甲殻類の一種”。大型のエビで、高級食材として知られています。<牛海老(牛蝦)>読み方:ウシエビ牛海老というのは、”エビ目クルマエビ科ウシエビ属に分類される甲殻類の一種”。大型の海老で、「ブラックタイガー」という別名で知られています。<車海老(車蝦)>読み方:クルマエビ車海老というのは、”エビ目クルマエビ科クルマエビ属に分類される甲殻類の一種”。大型のエビで、腹を丸めたときの縞(しま)模様が車輪のように見えることから名付けられています。<桜海老(桜蝦)>読み方:サクラエビ桜海老というのは、”エビ目サクラエビ科サクラエビ属に分類される甲殻類の一種”。小型のエビで、体色が桜の花のようなピンク色に見えることから名付けられたとされています。<牡丹海老(牡丹蝦)>読み方:ボタンエビ牡丹海老というのは、”エビ目タラバエビ科タラバエビ属に分類される甲殻類の一種”。体色が牡丹(ボタン)の花のように赤い色をしていることから名付けられたとされています。【追河】読み方:オイカワ追河というのは、”コイ目コイ科ハス属に分類される淡水魚の一種”。【虎魚(鰧)】読み方:オコゼ(一種)虎魚というのは、”鬼虎魚(オニオコゼ:標準和名)の別名/カサゴ目に属するオコゼ類の総称”。オコゼは基本的にどの種類にも鰭(ひれ)に毒針があります。<鬼虎魚(鬼鰧)>読み方:オニオコゼ鬼虎魚というのは、”カサゴ目オニオコゼ科オニオコゼ属に分類される海水魚の一種”。虎魚というと、一般的には鬼虎魚のことを指します。<鬼達磨虎魚(鬼達磨鰧)>読み方:オニダルマオコゼ鬼達磨虎魚というのは、”カサゴ目オニオコゼ科オニダルマオコゼ属に分類される海水魚の一種”。虎魚の中でも特に強い毒を持っているのが鬼達磨虎魚で、「ストナストキシン」と呼ばれる神経毒を毒針から分泌します。「ストナストキシン」はハブ毒の30倍ともいわれる非常に高い毒性を持っています。<葉虎魚(葉鰧)>読み方:ハオコゼ葉虎魚というのは、”カサゴ目ハオコゼ科ハオコゼ属に分類される海水魚の一種”。【老翁】読み方:オジサン老翁というのは、”スズキ目ヒメジ科ウミヒゴイ属に分類される海水魚の一種”。顔の前面に2本の髭(ひげ)があり、正面から見ると人のおじさんのように見えることから名付けられました。↓カ行~【牡蠣】読み方:カキ(総称)牡蠣というのは、”ウグイスガイ目イタボガキ科とベッコウガキ科に分類される二枚貝の総称”。身が牛乳のように乳白色であることや、栄養が豊富に含まれていることから、別名で「海のミルク」とも呼ばれています。<岩牡蠣(岩牡蛎)>読み方:イワガキ岩牡蠣というのは、”ウグイスガイ目イタボガキ科マガキ属に分類される二枚貝の一種”。<真牡蠣(真牡蛎)>読み方:マガキ真牡蠣というのは、”ウグイスガイ目イタボガキ科マガキ属に分類される二枚貝の一種”。【笠子(鮋・瘡魚)】読み方:カサゴ(一種)※笠子(一種)の写真笠子というのは、”スズキ目フサカサゴ科カサゴ属に分類される海水魚の一種/スズキ目フサカサゴ科に分類される海水魚の総称”。鰭(ひれ)には棘(トゲ)がついていて、基本的には毒性は弱いですが、種類によって強い毒性のものもいます。<伊豆笠子>読み方:イズカサゴ伊豆笠子というのは、”スズキ目フサカサゴ科フサカサゴ属に分類される海水魚の一種”。<蓑笠子>読み方:ミノカサゴ蓑笠子というのは、”スズキ目フサカサゴ科ミノカサゴ属に分類される海水魚の一種”。【鰍(杜父魚・鮖)】読み方:カジカ(一種)※上は鰍(一種)の写真鰍というのは、”スズキ目カジカ科カジカ属に分類される淡水魚の一種/スズキ目カジカ科に属する魚類の総称”。前者の意味の鰍(標準和名)は、別名で「鮴(ゴリ)」とも呼ばれています。【梶木(旗魚・舵木)】読み方:カジキ(総称)梶木というのは、”スズキ目マカジキ科とメカジキ科に分類される海水魚の総称”。<芭蕉梶木>読み方:バショウカジキ芭蕉梶木というのは、”スズキ目マカジキ科バショウカジキ属に分類される海水魚の一種”。【鰹(松魚・堅魚)】読み方:カツオ鰹というのは、”スズキ目サバ科カツオ属に分類される海水魚の一種”。鰹の魚肉を煮熟(しゃじゅく)(煮詰めること)させてから乾燥させた食品のことを「鰹節(かつおぶし)」、それを薄く削ったものを「削り節(けずりぶし)」と呼びます。【金頭(方頭魚・火魚・鉄頭)】読み方:カナガシラ金頭というのは、”カサゴ目ホウボウ科カナガシラ属に分類される海水魚の一種”。頭部が大きく、形が金槌(かなづち)に似ていることから名付けられました。【蟹(蠏)】読み方:カニ(総称)蟹というのは、”エビ目(十脚目)カニ下目(短尾下目)に分類される甲殻類の総称”。海老(エビ)や蟹の殻には「アスタキサンチン」という赤い色素が含まれていて、その赤い色素はタンパク質と結合していて、赤い色素は隠れてしまっています。ですが、この結合は加熱することで分解され、茹(ゆ)でたり焼いたりすることで赤い色素が現れて赤色に変化します。<毛蟹>読み方:ケガニ※加熱後の写真毛蟹というのは、”エビ目カニ下目クリガニ科ケガニ属に分類される甲殻類の一種”。<楚蟹>読み方:ズワイガニ※加熱後の写真楚蟹というのは、”エビ目カニ下目ケセンガニ科ズワイガニ属に分類される甲殻類の一種”。<鱈場蟹(多羅波蟹)>読み方:タラバガニ※加熱後の写真鱈場蟹というのは、”エビ目ヤドカリ下目(異尾下目)タラバガニ科タラバガニ属に分類される甲殻類の一種”。鱈場蟹は、蟹の仲間ではなく、実は「宿借(ヤドカリ)」の仲間になります。<花咲蟹>読み方:ハナサキガニ※加熱後の写真花咲蟹というのは、”エビ目ヤドカリ下目(異尾下目)タラバガニ科タラバガニ属に分類される甲殻類の一種”。鱈場蟹と同様に花咲蟹についても、蟹の仲間ではなく、実は「宿借(ヤドカリ)」の仲間になります。【魳(梭子魚・梭魚)】読み方:カマス(総称)魳というのは、”スズキ目カマス科に分類される海水魚の総称”。<赤魳(赤叺)>読み方:アカカマス赤魳というのは、”スズキ目カマス科カマス属に分類される海水魚の一種”。赤魳は、日本で最も一般的な魳になります。<大和魳(大和叺)>読み方:ヤマトカマス大和魳というのは、”スズキ目カマス科カマス属に分類される海水魚の一種”。【鰈】読み方:カレイ(総称)鰈というのは、”カレイ目カレイ科に分類される海水魚の総称”。鰈は鮃(ヒラメ)とよく間違えられますが、それぞれの口を見て判断するのが分かりやすいです。鮃は口が大きくて歯が尖っていますが、鰈は口が小さい、という違いがあります。<石鰈>読み方:イシガレイ石鰈というのは、”カレイ目カレイ科イシガレイ属に分類される海水魚の一種”。<烏鰈>読み方:カラスガレイ烏鰈というのは、”カレイ目カレイ科カラスガレイ属に分類される海水魚の一種”。<真鰈>読み方:マガレイ真鰈というのは、”カレイ目カレイ科マガレイ属に分類される海水魚の一種”。【川蜷(河貝子)】読み方:カワニナ川蜷というのは、”ニナ目カワニナ科カワニナ属に分類される巻き貝の一種”。【皮剥(鮍)】読み方:カワハギ(一種)※上は皮剥(一種)の写真皮剥というのは、”フグ目カワハギ科カワハギ属に分類される海水魚の一種/フグ目カワハギ科に分類される海水魚の総称”。<網目剥>読み方:アミメハギ網目剥というのは、”フグ目カワハギ科アミメハギ属に分類される海水魚の一種”。<薄葉剥>読み方:ウスバハギ薄葉剥というのは、”フグ目カワハギ科ウスバハギ属に分類される海水魚の一種”。<馬面剥>読み方:ウマヅラハギ馬面剥というのは、”フグ目カワハギ科ウマヅラハギ属に分類される海水魚の一種”。【間八(勘八)】読み方:カンパチ間八というのは、”スズキ目アジ科ブリ属に分類される海水魚の一種”。【鱚】読み方:キス(総称)鱚というのは、”スズキ目キス科に分類される海水魚の総称”。<白鱚>読み方:シロギス白鱚というのは、”スズキ目キス科キス属に分類される海水魚の一種”。【黍魚子(吉備奈仔)】読み方:キビナゴ黍魚子というのは、”ニシン目キビナゴ科キビナゴ属に分類される海水魚の一種”。【銀宝】読み方:ギンポ(一種)※上は銀宝(一種)の写真銀宝というのは、”スズキ目ニシキギンポ科ニシキギンポ属に分類される海水魚の一種/スズキ目ニシキギンポ科やイソギンポ科、ヘビギンポ科などに分類されるギンポ類の総称”。江戸時代の銀貨である「丁銀(ちょうぎん)」に形が似ていることが名前の由来とされています。【垢穢(九絵)】読み方:クエ垢穢というのは、”スズキ目ハタ科アカハタ属に分類される海水魚の一種”。【久慈目(口女)】読み方:クジメ久慈目というのは、”スズキ目アイナメ科アイナメ属に分類される海水魚の一種”。【熊之実(隈魚・隈之実)】読み方:クマノミ(一種)※上は熊之実(一種)の写真熊之実というのは、”スズキ目スズメダイ科クマノミ亜科クマノミ属に分類される海水魚の一種/スズキ目スズメダイ科クマノミ亜科に分類される海水魚の総称”。熊之実と磯巾着(イソギンチャク)は共生関係にあり、それぞれが一緒に生活し、お互いに利益を得ています。磯巾着の触手には毒がありますが、熊之実は特別な粘液によって守られるため触手に触れても問題なく、外敵が近づくと磯巾着の中に隠れてやり過ごします。そして磯巾着は、熊之実が周りを泳ぎ回ることで新鮮な海水(酸素)が送られてきます。<隠熊之実(隠隈魚)>読み方:カクレクマノミ隠熊之実というのは、”スズキ目スズメダイ科クマノミ亜科クマノミ属に分類される海水魚の一種”。<花弁熊之実>読み方:ハナビラクマノミ花弁熊之実というのは、”スズキ目スズメダイ科クマノミ亜科クマノミ属に分類される海水魚の一種”。【海月(水母・水月)】読み方:クラゲ(総称)海月というのは、”刺胞(しほう)動物のうち、淡水または海水で浮遊して生活する動物の総称”。海月の触手には、刺胞と呼ばれる毒液を注入する針がついていて、海月の種類によって毒性の強さは異なります。<兜海月(兜水母)>読み方:カブトクラゲ兜海月というのは、”カブトクラゲ目カブトクラゲ科カブトクラゲ属に分類される有櫛(ゆうしつ)動物の一種”。海月と表記されますが、実は兜海月は「クラゲ」の仲間ではありません(刺胞がないため毒もない)。<花笠海月(花笠水母)>読み方:ハナガサクラゲ花笠海月というのは、”淡水クラゲ目ハナガサクラゲ科ハナガサクラゲ属に分類される刺胞動物の一種”。<水海月(水水母)>読み方:ミズクラゲ水海月というのは、”旗口クラゲ目ミズクラゲ科ミズクラゲ属に分類される刺胞動物の一種”。【鯉】読み方:コイ鯉というのは、”コイ目コイ科コイ属に分類される淡水魚の一種”。※上は錦鯉(ニシキゴイ)の写真観賞用に改良された品種のことを総称して「錦鯉(ニシキゴイ)」と呼びます。【鯒(牛尾魚)】読み方:コチ(総称)鯒というのは、”スズキ目コチ科に分類される海水魚の総称”。<真鯒>読み方:マゴチ真鯒というのは、”スズキ目コチ科コチ属に分類される海水魚の一種”。鯒というと、一般的には真鯒のことを指します。<女鯒(目鯒・眼鯒)>読み方:メゴチ女鯒というのは、”スズキ目コチ科メゴチ属に分類される海水魚の一種”。<鰐鯒>読み方:ワニゴチ鰐鯒というのは、”スズキ目コチ科トカゲゴチ属に分類される海水魚の一種”。【鮗(鰶・子代)】読み方:コノシロ鰶というのは、”ニシン目ニシン科コノシロ属に分類される海水魚の一種”。【鮴】読み方:ゴリ(メバル)※上は鰍(カジカ:一種)の写真※上は鈍甲(ドンコ)の写真※上は葦登(ヨシノボリ)の写真※上は知知武(チチブ)の写真鮴を「ゴリ」と読むと、”鰍(カジカ:標準和名)の別名/地方での鈍甲(ドンコ)・葦登(ヨシノボリ)・知知武(チチブ)などの総称”の意味。鰍(カジカ)は”スズキ目カジカ科カジカ属に分類される淡水魚の一種/スズキ目カジカ科に属する魚類の総称”を指します。※上は白眼張(シロメバル)の写真鮴を「メバル」と読むと”カサゴ目メバル科メバル属に分類される海水魚の総称”の意味。「メバル」は鮴の他にも”眼張”と書き表され、一般的には”眼張”と表記されることが多いです。【権瑞】読み方:ゴンズイ※上は権瑞玉の写真権瑞というのは、”ナマズ目ゴンズイ科ゴンズイ属に分類される海水魚の一種”。背鰭(せびれ)と胸鰭(むなびれ)に毒棘(どくきょく)があります。集団で行動する習性があり、団子状に群れるため「ゴンズイ玉」と呼ばれています。↓サ行~【鮭(石桂魚・鯹)】読み方:サケ(一種)※上は鮭(一種)の写真鮭というのは、”サケ目サケ科サケ属に分類される海水魚の一種/サケ目サケ科に分類される海水魚の総称”。前者の意味の鮭(標準和名)は、別名で「白鮭(シロザケ)」とも呼ばれています。鮭と鱒(マス)はどちらも「サケ目サケ科」に分類され、両者に明確な違いはなく、ここでは主に名称で分けています。<銀鮭>読み方:ギンザケ銀鮭というのは、”サケ目サケ科サケ属に分類される海水魚の一種”。<紅鮭>読み方:ベニザケ紅鮭というのは、”サケ目サケ科サケ属に分類される海水魚の一種”。湖で生まれて一生を湖で過ごす湖沼残留型(陸封型)を「姫鱒(ヒメマス)」、生まれてから海へ下る降海型を「紅鮭(ベニザケ)」と呼びます。分類上、姫鱒と紅鮭はどちらも同じ魚になります。【栄螺(拳螺)】読み方:サザエ栄螺というのは、”古腹足目リュウテン(サザエ)科リュウテン属に分類される巻き貝の一種”。栄螺の殻の外側から焼いて加熱する調理法である「サザエの壺焼き」が有名です。【拶双魚】読み方:サッパ拶双魚というのは、”ニシン目ニシン科サッパ属に分類される海水魚の一種”。拶双魚(標準和名)は、別名で「飯借(ママカリ)」と呼ばれています。【鯖(青花魚)】読み方:サバ(総称)鯖というのは、”スズキ目サバ科サバ属・グルクマ属・ニジョウサバ属に分類される海水魚の総称”。<胡麻鯖>読み方:ゴマサバ胡麻鯖というのは、”スズキ目サバ科サバ属に分類される海水魚の一種”。<真鯖>読み方:マサバ真鯖というのは、”スズキ目サバ科サバ属に分類される海水魚の一種”。鯖というと、一般的には真鯖を指すことが多いです。【鮫(鯊)】読み方:サメ(総称)鮫というのは、”板鰓亜綱(ばんさいあこう)に属する軟骨魚類のうち、鰓(エラ)が体の側面に開くものの総称”。ちなみに”板鰓亜綱に属する軟骨魚類のうち、鰓が体の下面に開くものの総称”を「鱏(エイ)」と言います。”鯊”は「ハゼ」と読むことがほとんどです。<小判鮫(鮣)>読み方:コバンザメ小判鮫というのは、”スズキ目コバンザメ科コバンザメ属に分類される海水魚の一種”。鮫と表記されますが、実は小判鮫は鮫の仲間ではありません。頭部にある小判型の吸盤が名前の由来で、この吸盤を用いて大型のサメ類・カジキ類・ウミガメ・クジラなどに吸いつき、餌のおこぼれや寄生虫、排泄物を食べて生活します。<撞木鮫(双髻鯊・犁頭魚)>読み方:シュモクザメ(総称)撞木鮫というのは、”メジロザメ目シュモクザメ科に分類される海水魚の総称”。※上は撞木(鐘などを鳴らす木槌)の写真頭部が小さい鐘などを鳴らすときに用いるT字形の「撞木(しゅもく)」に似ていることから名付けられました。撞木鮫の頭部は左右に張り出していて、その先端に目がついているため、真正面は死角になります。ちなみに鐘を突いて鳴らすT字形でない真っすぐな棒のことも撞木と呼ぶため覚えておきましょう。<甚兵衛鮫(甚平鮫)>読み方:ジンベエザメ(ジンベイザメ)甚兵衛鮫というのは、”テンジクザメ目ジンベエザメ科ジンベエザメ属に分類される海水魚の一種”。「ジンベイザメ」は、「ジンベエザメ」(標準和名)の別名になります。甚兵衛鮫は、現存する魚類の中で最も大きな種とされています。<蝶鮫(鱘魚・鱘)>読み方:チョウザメ蝶鮫というのは、”チョウザメ目チョウザメ科チョウザメ属に分類される淡水魚の一種”。鮫と表記されますが、実は蝶鮫は鮫の仲間ではありません。蝶鮫の卵の塩漬けを「キャビア」と呼び、フォアグラ・トリュフと並んで世界三大珍味と言われています。<頬白鮫>読み方:ホオジロザメ(ホホジロザメ)頬白鮫というのは、”ネズミザメ目ネズミザメ科ホホジロザメ属に分類される海水魚の一種”。「ホオジロザメ」は、「ホホジロザメ」(標準和名)の別名になります。「人食いザメ」の呼び名がついていて、気性が荒く、非常に危険な鮫として知られています。<葦切鮫(吉切鮫)>読み方:ヨシキリザメ葦切鮫というのは、”メジロザメ目メジロザメ科ヨシキリザメ属に分類される海水魚の一種”。葦切鮫の鰭(ひれ)は、中華料理の高級食材としても知られる「鱶鰭(フカヒレ)」の原料になります。鱶鰭の原料となるため鰭を切り取りますが、鰭は鮫にとっての足であることから、「足を切る」から「ヨシキリ」に変化したのが由来とされています。(鱶鰭の「鱶(フカ)」というのは、”大型のサメ”を意味する言葉)【細魚(針魚・鱵)】読み方:サヨリ(一種)※上は細魚(一種)の写真細魚というのは、”ダツ目サヨリ科サヨリ属に分類される海水魚の一種/ダツ目サヨリ科に分類される魚類の総称”。<子持細魚>読み方:コモチサヨリ子持細魚というのは、”ダツ目サヨリ科コモチサヨリ属に分類される淡水・汽水(きすい)魚の一種”。【蝲蛄(蜊蛄・躄蟹)】読み方:ザリガニ(総称)蝲蛄というのは、”ザリガニ下目のうち、ザリガニ上科とミナミザリガニ上科に分類される甲殻類の総称”。<亜米利加蝲蛄(亜米利加蜊蛄)>読み方:アメリカザリガニ亜米利加蝲蛄というのは、”十脚目(エビ目)ザリガニ上科アメリカザリガニ科アメリカザリガニ属に分類される甲殻類の一種”。外来種ですが、現在では日本で最も一般的な蝲蛄になります。<日本蝲蛄(日本蜊蛄)>読み方:ニホンザリガニ日本蝲蛄というのは、”十脚目ザリガニ上科アジアザリガニ科アジアザリガニ属に分類される甲殻類の一種”。在来種で、亜米利加蝲蛄の移入により生息数が激減し、現在では絶滅危惧種に指定されています。【鰆(馬鮫魚)】読み方:サワラ(一種)※上は鰆(一種)の写真※上は青箭魚(サゴシ)の写真鰆というのは、”サバ目サバ科サワラ属に分類される海水魚の一種/サバ目サバ科サワラ属に分類される海水魚の総称”。鰆は出世魚(しゅっせうお)で、全長50cm未満のものを「青箭魚(サゴシ)」、50cm以上60cm未満のものを「柳(ヤナギ)」、60cm以上のものを「鰆(サワラ)」と言います。【珊瑚】読み方:サンゴ(総称)珊瑚というのは、”刺胞(しほう)動物のうち、石灰質など固い骨格を持つものの総称”。<錣珊瑚>読み方:シコロサンゴ錣珊瑚というのは、”イシサンゴ目ヒラフキサンゴ科シコロサンゴ属に分類される刺胞動物の一種”。<擂鉢珊瑚>読み方:スリバチサンゴ擂鉢珊瑚というのは、”イシサンゴ目キサンゴ科スリバチサンゴ属に分類される刺胞動物の一種”。<花笠珊瑚(花傘珊瑚)>読み方:ハナガササンゴ花笠珊瑚というのは、”イシサンゴ目ハマサンゴ科ハナガササンゴ属に分類される刺胞動物の一種”。【秋刀魚】読み方:サンマ秋刀魚というのは、”ダツ目サンマ科サンマ属に分類される海水魚の一種”。秋に獲れる刀のような見た目であることから「秋刀魚(サンマ)」の漢字が当てられています。【鱰】読み方:シイラ鱰というのは、”スズキ目シイラ科シイラ属に分類される海水魚の一種”。鱰(標準和名)は、高級魚として扱われ、ハワイや日本で「マヒマヒ」の別名で呼ばれています。【潮招(望潮)】読み方:シオマネキ(一種)※上は潮招(一種)の写真潮招というのは、”エビ目(十脚目)スナガニ科シオマネキ属に分類される甲殻類の一種/エビ目スナガニ科シオマネキ属に分類される甲殻類の総称”。潮が引いた干潟で、雄が雌の気を引くための「ウェービング(Waving)」(大きなハサミを上下に動かす行為)と呼ばれる求愛行動が、潮が早く満ちてくるように招いているように見えることから名付けられています。<白扇潮招>読み方:ハクセンシオマネキ白扇潮招というのは、”エビ目スナガニ科シオマネキ属に分類される甲殻類の一種”。<紅潮招>読み方:ベニシオマネキ紅潮招というのは、”エビ目スナガニ科シオマネキ属に分類される甲殻類の一種”。【蜆】読み方:シジミ(総称)蜆というのは、”マルスダレガイ目シジミ科に分類される二枚貝の総称”。<台湾蜆>読み方:タイワンシジミ台湾蜆というのは、”マルスダレガイ目シジミ科シジミ属に分類される二枚貝の一種”。<真蜆>読み方:マシジミ真蜆というのは、”マルスダレガイ目シジミ科シジミ属に分類される二枚貝の一種”。<大和蜆>読み方:ヤマトシジミ大和蜆というのは、”マルスダレガイ目シジミ科シジミ属に分類される二枚貝の一種”。【柳葉魚】読み方:シシャモ柳葉魚というのは、”キュウリウオ目キュウリウオ科シシャモ属に分類される海水魚の一種”。スーパーなどでよく見られるシシャモ(子持ちシシャモ)のほとんどは「樺太柳葉魚(カラフトシシャモ)」と呼ばれる魚で、本物のシシャモではなく、シシャモの代用魚になります。※上は樺太柳葉魚の写真樺太柳葉魚は”キュウリウオ目キュウリウオ科カラフトシシャモ属に分類される海水魚の一種”で、見た目がシシャモに似ていることから「樺太柳葉魚(カラフトシシャモ)」と名付けられました。樺太柳葉魚は英語で「Capelin(カペリンまたはキャペリン)」と言い、別名としても「カペリン(またはキャペリン)」と呼ばれています。【蝦蛄(青竜蝦)】読み方:シャコ(一種)※上は蝦蛄(一種)の写真蝦蛄というのは、”シャコ目シャコ科シャコ属に分類される甲殻類の一種/シャコ目に分類される甲殻類の総称”。<虎斑蝦蛄>読み方:トラフシャコ虎斑蝦蛄というのは、”シャコ目トラフシャコ科トラフシャコ属に分類される甲殻類の一種”。<紋花蝦蛄>読み方:モンハナシャコ紋花蝦蛄というのは、”シャコ目ハナシャコ科ハナシャコ属に分類される甲殻類の一種”。【白魚(鱠残魚・膾残魚・銀魚)】読み方:シラウオ(一種)※上は白魚(一種)の写真白魚というのは、”キュウリウオ目シラウオ科シラウオ属に分類される汽水魚の一種/キュウリウオ目シラウオ科に分類される汽水魚の総称”。【白子】読み方:しらこ(シラス)※上は白子(しらこ)の写真※上は白子(シラス)の写真「しらこ」と読むと”魚の精巣(せいそう)の俗称”。「シラス」と読むと”玉筋魚(イカナゴ)・片口鰯(カタクチイワシ)・鰻(ウナギ)などの稚魚(ちぎょ)”。【素魚(白魚)】読み方:シロウオ素魚というのは、”スズキ目ハゼ科シロウオ属に分類される海水魚の一種”。【鱸】読み方:スズキ(一種)※上は鱸(一種)の写真鱸というのは、”スズキ目スズキ科スズキ属に分類される海水魚の一種/スズキ目スズキ科スズキ属に分類される海水魚の総称”。前者の意味の鱸(標準和名)は、別名で「丸鱸(マルスズキ)」とも呼ばれています。鱸は出世魚(しゅっせうお)で、幼魚を「コッパ」、全長20cm~40cm未満のものを「鮬(セイゴ)」、全長40cm~60cm未満のものを「福子(フッコ)」、それ以上の大きさのものを「鱸(スズキ)」と呼んでいます。↓タ行~【鯛】読み方:タイ(総称)鯛というのは、”スズキ目タイ科に分類される海水魚の総称”。高級魚として知られ、紅白の体色や七福神の恵比寿様が鯛を持っていること、「めでたい(鯛)」といった語呂合わせなどの理由から、縁起物としてお祝いの席でよく用いられます。<赤魚鯛(阿候鯛)>読み方:アコウダイ赤魚鯛というのは、”カサゴ目メバル科メバル属に分類される海水魚の一種”。鯛と表記されますが、実は鯛の仲間ではありません。<真鯛>読み方:マダイ真鯛というのは、”スズキ目タイ科マダイ属に分類される海水魚の一種”。鯛というと、一般的には真鯛のことを指します。<的鯛(馬頭鯛)>読み方:マトウダイ的鯛というのは、”マトウダイ目マトウダイ科マトウダイ属に分類される海水魚の一種”。鯛と表記されますが、実は鯛の仲間ではありません。【高砂】読み方:タカサゴ※上は釣りあげられてから時間が経った高砂(グルクン)の写真高砂というのは、”スズキ目タカサゴ科タカサゴ属に分類される海水魚の一種”。海を泳いでいる間の高砂は青色をしていて、釣り上げられてから時間が経つと赤色に変化します。高砂(標準和名)は、沖縄では別名で「グルクン」とも呼ばれています。【蛸(章魚・鮹・鱆)】読み方:タコ(総称)蛸というのは、”頭足類タコ目(八腕目)に分類される軟体動物の総称”。蛸には吸盤の付いた足(正確には腕)が8本あり、丸く大きな頭のように見える部位は胴部で、本当の頭は眼や口が集まっている部分になります。蛸は上記のように、頭から足が生えているため「頭足類(とうそくるい)」と呼ばれています。<飯蛸(望潮魚)>読み方:イイダコ飯蛸というのは、”タコ目マダコ科マダコ属に分類される軟体動物の一種”。産卵直前の雌の胴部(頭に見える部分)に、飯粒状の卵が多く詰まっていることから名付けられました。<豹紋蛸>読み方:ヒョウモンダコ豹紋蛸というのは、”タコ目マダコ科ヒョウモンダコ属に分類される軟体動物の一種/タコ目マダコ科ヒョウモンダコ属に分類される4種類のタコの総称”。唾液(だえき)には神経毒である猛毒の「テトロドトキシン」(フグ毒として有名)が含まれているため、咬(か)まれると非常に危険です。豹柄(ヒョウがら)のような模様があることから「豹紋蛸(ヒョウモンダコ)」と名付けられ、豹柄は刺激を受けると青色に変化し、それ以外の部分は黄色に変化します。<真蛸(真章魚)>読み方:マダコ真蛸というのは、”タコ目マダコ科マダコ属に分類される軟体動物の一種”。蛸というと、一般的には真蛸を指すことが多いです。【太刀魚(立魚・帯魚・魛)】読み方:タチウオ太刀魚というのは、”スズキ目タチウオ科タチウオ属に分類される海水魚の一種”。見た目が「太刀(たち)」に似ていることから名付けられています。【駄津】読み方:ダツ(一種)※上は駄津(一種)の写真駄津というのは、”ダツ目ダツ科ダツ属に分類される海水魚の一種/ダツ目ダツ科に属する魚類の総称”。駄津は光るものに反応し、猛スピードで突進してくる習性があり、さらに両顎(あご)が前方に長く尖っているため非常に危険です。【竜の落とし子(海馬)】読み方:タツノオトシゴ(一種)※上は竜の落とし子(一種)の写真竜の落とし子というのは、”トゲウオ目ヨウジウオ科タツノオトシゴ属に分類される海水魚の一種/トゲウオ目ヨウジウオ科タツノオトシゴ属に分類される海水魚の総称”。見た目が想像上の動物である竜に似ていて、まるで竜が産み落とした子のように見えることから名付けられました。馬に似ていることからも”海馬”とも表記され、”海馬”は「アシカ」「トド」「セイウチ」と読むこともできます。<茨竜>読み方:イバラタツ茨竜というのは、”トゲウオ目ヨウジウオ科タツノオトシゴ属に分類される海水魚の一種”。<大海馬>読み方:オオウミウマ大海馬というのは、”トゲウオ目ヨウジウオ科タツノオトシゴ属に分類される海水魚の一種”。<黒海馬>読み方:クロウミウマ黒海馬というのは、”トゲウオ目ヨウジウオ科タツノオトシゴ属に分類される海水魚の一種”。【田螺】読み方:タニシ(総称)田螺というのは、”原始紐舌目(げんしちゅうぜつもく)タニシ科に分類される巻き貝の総称”。<大田螺>読み方:オオタニシ大田螺というのは、”原始紐舌目タニシ科タニシ属に分類される巻き貝の一種”。<姫田螺>読み方:ヒメタニシ姫田螺というのは、”原始紐舌目タニシ科ヒメタニシ属に分類される巻き貝の一種”。【鱈】読み方:タラ(総称)鱈というのは、”タラ目タラ科に分類される海水魚の総称”。<介党鱈(鯳)>読み方:スケトウダラ介党鱈というのは、”タラ目タラ科スケトウダラ属に分類される海水魚の一種”。「スケトウダラ」(標準和名)は、別名で「介宗鱈(助惣鱈):(スケソウダラ)」とも呼ばれています。介党鱈のすり身は、蒲鉾(かまぼこ)・竹輪(ちくわ)などの練り製品の主原料となり、卵巣は「鱈子(たらこ)」「辛子明太子(からしめんたいこ)」に用いられます。<真鱈>読み方:マダラ真鱈というのは、”タラ目タラ科マダラ属に分類される海水魚の一種”。鱈というと、一般的には真鱈を指すことが多いです。【常節(床伏・常伏)】読み方:トコブシ常節というのは、”古腹足目ミミガイ科トコブシ属に分類される巻き貝の一種”。【泥鰌(鰌・鯲)】読み方:ドジョウ(一種)※上は泥鰌(一種)の写真泥鰌というのは、”コイ目ドジョウ科ドジョウ属に分類される淡水魚の一種/コイ目ドジョウ科に分類される淡水魚の総称”。前者の意味の泥鰌(標準和名)は、別名で「真泥鰌(マドジョウ)」とも呼ばれています。<筋縞泥鰌>読み方:スジシマドジョウ筋縞泥鰌というのは、”コイ目ドジョウ科シマドジョウ属に分類される淡水魚の一種”。<仏泥鰌>読み方:ホトケドジョウ仏泥鰌というのは、”コイ目ドジョウ科ホトケドジョウ属に分類される淡水魚の一種”。【飛魚(𩹉)】読み方:トビウオ(一種)※上は飛魚(一種)の写真飛魚というのは、”ダツ目トビウオ科ツクシトビウオ属に分類される海水魚の一種/ダツ目トビウオ科に分類される海水魚の総称”。水上に飛び出し、胸鰭(むなびれ)を広げて滑空することから名付けられ、九州などでは別名で「アゴ」とも呼ばれています。【富魚(止水魚)】読み方:トミヨ(一種)※上は富魚(一種)の写真富魚というのは、”トゲウオ目トゲウオ科トミヨ属に分類される淡水・汽水魚の一種/トゲウオ目トゲウオ科トミヨ属に分類される淡水・汽水魚の総称”。<茨富魚>読み方:イバラトミヨ茨富魚というのは、”トゲウオ目トゲウオ科トミヨ属に分類される淡水・汽水魚の一種”。↓ナ行~【海鼠(生子)】読み方:ナマコ(総称)海鼠というのは、”ナマコ綱に分類される棘皮(きょくひ)動物の総称”。※上は海鼠腸(このわた)の写真海鼠の、腸などの内臓を塩辛にしたものは「海鼠腸(このわた)」と呼ばれ、雲丹(うに)・唐墨(からすみ)と並んで日本三大珍味と言われています。<赤海鼠>読み方:アカナマコ赤海鼠というのは、”楯手目(じゅんしゅもく)シカクナマコ科マナマコ属に分類される棘皮動物の一種”。<藤海鼠>読み方:フジナマコ藤海鼠というのは、”楯手目クロナマコ科クロナマコ属に分類される棘皮動物の一種”。<真海鼠>読み方:マナマコ真海鼠というのは、”楯手目シカクナマコ科マナマコ属に分類される棘皮動物の一種”。【鯰(魸)】読み方:ナマズ(一種)※上は鯰(一種)の写真鯰というのは、”ナマズ目ナマズ科ナマズ属に分類される淡水魚の一種/ナマズ目に分類される淡水魚の総称”。前者の意味の鯰(標準和名)は、別名で「真鯰(マナマズ)」「日本鯰(ニホンナマズ)」とも呼ばれています。<岩床鯰>読み方:イワトコナマズ岩床鯰というのは、”ナマズ目ナマズ科ナマズ属に分類される淡水魚の一種”。<琵琶湖大鯰>読み方:ビワコオオナマズ琵琶湖大鯰というのは、”ナマズ目ナマズ科ナマズ属に分類される淡水魚の一種”。【鰊(鯡)】読み方:ニシン鰊というのは、”ニシン目ニシン科ニシン属に分類される海水魚の一種”。内臓や頭などを取り除いて3枚におろし乾燥させたもの(干物)を「身欠きニシン(みがきニシン)」と呼びます。【鮸】読み方:ニベ鮸というのは、”スズキ目ニベ科ニベ属に分類される海水魚の一種”。↓ハ行~【馬鹿貝(馬珂貝)】読み方:バカガイ馬鹿貝というのは、”マルスダレガイ目バカガイ科バカガイ属に分類される二枚貝の一種”。※上は青柳(馬鹿貝のむき身)の写真馬鹿貝のむき身のことを「青柳(あおやぎ)」と呼びます。【鯊(沙魚・蝦虎魚)】読み方:ハゼ(総称)鯊というのは、”スズキ目ハゼ亜目に属する魚類の総称”。<虚鯊(虚沙魚)>読み方:ウロハゼ虚鯊というのは、”スズキ目ハゼ亜目ハゼ科ウロハゼ属に分類される汽水魚の一種”。<跳鯊(跳沙魚)>読み方:トビハゼ跳鯊というのは、”スズキ目ハゼ亜目ハゼ科トビハゼ属に分類される汽水魚の一種”。<真鯊(真沙魚)>読み方:マハゼ真鯊というのは、”スズキ目ハゼ亜目ハゼ科マハゼ属に分類される汽水魚の一種”。鯊というと、一般的には真鯊を指すことが多いです。【鰰(鱩・雷魚・燭魚)】読み方:ハタハタ鰰というのは、”スズキ目ハタハタ科ハタハタ属に分類される海水魚の一種”。鰰を塩漬けにし、しみ出た上澄みから作った調味料のことを「塩汁(しょっつる)」と言い、鰰など白身の魚や豆腐・野菜などを塩汁で味付けしたものを「塩汁鍋(しょっつるなべ)」と呼びます。※上は塩汁鍋(しょっつるなべ)の写真また、鰰の卵のことを「ぶりこ(または、ぶりっこ)」と呼び、ぶりこはヌルヌルとした粘液で覆われているのが特徴的です。【蛤(文蛤・浜栗)】読み方:ハマグリ(一種)※上は蛤(一種)の写真蛤というのは、”マルスダレガイ目マルスダレガイ科ハマグリ属に分類される二枚貝の一種/マルスダレガイ目マルスダレガイ科ハマグリ属に分類される二枚貝の総称”。<朝鮮蛤(汀線蛤)>読み方:チョウセンハマグリ朝鮮蛤というのは、”マルスダレガイ目マルスダレガイ科ハマグリ属に分類される二枚貝の一種”。【鱧】読み方:ハモ(一種)※上は鱧(一種)の写真鱧というのは、”ウナギ目ハモ科ハモ属に分類される海水魚の一種/ウナギ目ハモ科に分類される海水魚の総称”。【針千本(魚虎)】読み方:ハリセンボン(一種)※上は針千本(一種)の写真針千本というのは、”フグ目ハリセンボン科ハリセンボン属に分類される海水魚の一種/フグ目ハリセンボン科に分類される海水魚の総称”。体表に多数の棘(トゲ)があり、外敵への威嚇(いかく)を目的として、大量の水を飲むことによって膨らみます。<鼠河豚>読み方:ネズミフグ鼠河豚というのは、”フグ目ハリセンボン科ハリセンボン属に分類される海水魚の一種”。河豚(フグ)と表記されますが、針千本の仲間になります。<人面針千本>読み方:ヒトヅラハリセンボン人面針千本というのは、”フグ目ハリセンボン科ハリセンボン属に分類される海水魚の一種”。【針魚】読み方:ハリヨ(サヨリ)※上は針魚(ハリヨ)の写真※上は細魚(サヨリ)の写真「ハリヨ」と読むと、”トゲウオ目トゲウオ科イトヨ属に分類される淡水魚の一種”。「サヨリ」と読むと、”ダツ目サヨリ科サヨリ属に分類される海水魚の一種/ダツ目サヨリ科に属する魚類の総称”。ただ「サヨリ」は、一般的には「細魚(サヨリ)」と表記されることが多いです。【鰉】読み方:ヒガイ(総称)鰉というのは、”コイ目コイ科ヒガイ属に分類される淡水魚の総称”。<川鰉>読み方:カワヒガイ川鰉というのは、”コイ目コイ科ヒガイ属に分類される淡水魚の一種”。【海星(人手・海盤車)】読み方:ヒトデ(総称)海星というのは、”ヒトデ綱に分類される棘皮(きょくひ)動物の総称”。「人手・海星」の漢字表記は、ヒトデの5本の腕が5本の指を持つ人の手のように見えることや、その姿を星形に見立てたことに由来しています。<赤海星(赤人手)>読み方:アカヒトデ赤海星というのは、”ヒトデ綱アカヒトデ目ホウキボシ科アカヒトデ属に分類される棘皮動物の一種”。<糸巻海星(糸巻人手)>読み方:イトマキヒトデ糸巻海星というのは、”ヒトデ綱アカヒトデ目イトマキヒトデ科イトマキヒトデ属に分類される棘皮動物の一種”。<鬼海星(鬼人手)>読み方:オニヒトデ鬼海星というのは、”ヒトデ綱アカヒトデ目オニヒトデ科オニヒトデ属に分類される棘皮動物の一種”。<黄海星(黄人手)>読み方:キヒトデ黄海星というのは、”ヒトデ綱アカヒトデ目キヒトデ科キヒトデ属に分類される棘皮動物の一種”。黄海星(標準和名)は、別名で「真海星(マヒトデ)」とも呼ばれています。【鋸刺鮭】読み方:ピラニア(総称)※上はピラニア・ナッテリーの写真※上はピラニア・ブラックの写真鋸刺鮭というのは、”カラシン目セルラサルムス科に分類される淡水魚の総称”。群れて行動することを好み、血の臭いや水面を叩く音などに敏感に反応します。【平政】読み方:ヒラマサ平政というのは、”スズキ目アジ科ブリ属に分類される海水魚の一種”。【鮃(平目・比目魚)】読み方:ヒラメ(一種)※上は鮃(一種)の写真鮃というのは、”カレイ目ヒラメ科ヒラメ属に分類される海水魚の一種/カレイ目ヒラメ科とダルマガレイ科に分類される海水魚の総称”。鮃は鰈(カレイ)とよく間違えられますが、それぞれの口を見て判断するのが分かりやすいです。鮃は口が大きくて歯が尖っていますが、鰈は口が小さい、という違いがあります。【河豚(鰒・鯸・魨)】読み方:フグ(総称)河豚というのは、”フグ目フグ科とハコフグ科に属する魚類の総称”。河豚の多くの種類は神経毒である「テトロドトキシン」と呼ばれる猛毒を持っており、内臓の他に種類によっては皮や筋肉にも毒が含まれています。<草河豚>読み方:クサフグ草河豚というのは、”フグ目フグ科トラフグ属に分類される海水魚の一種”。<虎河豚>読み方:トラフグ虎河豚というのは、”フグ目フグ科トラフグ属に分類される海水魚の一種”。<箱河豚>読み方:ハコフグ箱河豚というのは、”フグ目ハコフグ科ハコフグ属に分類される海水魚の一種”。<真河豚>読み方:マフグ真河豚というのは、”フグ目フグ科トラフグ属に分類される海水魚の一種”。【鮒(鯽)】読み方:フナ(総称)鮒というのは、”コイ目コイ科フナ属に分類される淡水魚の総称”。<金鮒>読み方:キンブナ金鮒というのは、”コイ目コイ科フナ属に分類される淡水魚の一種”。<銀鮒>読み方:ギンブナ銀鮒というのは、”コイ目コイ科フナ属に分類される淡水魚の一種”。<源五郎鮒>読み方:ゲンゴロウブナ源五郎鮒というのは、”コイ目コイ科フナ属に分類される淡水魚の一種”。源五郎鮒の養殖個体のことを「平鮒(ヘラブナ)」または「河内鮒(カワチブナ)」と呼んでいます。【鰤】読み方:ブリ鰤というのは、”スズキ目アジ科ブリ属に分類される海水魚の一種”。鰤は出世魚(しゅっせうお)で、15cm未満の稚魚を「藻雑魚(モジャコ)」、15cm~35cm未満のものを「魚夏(魚偏+夏)(ワカシ)」「ツバス」、35cm~60cm未満のものを「魬(ハマチ)」「鰍(イナダ)」、60cm~80cm未満のものを「稚鰤(ワラサ)」「メジロ」、80cm以上のものを「鰤(ブリ)」と呼びます。(”鰍”は「カジカ」と読むこともでき、一般的には「カジカ」と読むことが多いです)【倍良(遍羅)】読み方:ベラ(総称)倍良というのは、”スズキ目ベラ科に分類される海水魚の総称”。<青倍良(青遍羅)>読み方:アオベラ青倍良というのは、”求仙(キュウセン:標準和名)の雄(オス)の呼び方”。求仙は、”スズキ目ベラ科キュウセン属に分類される海水魚の一種”。<赤倍良(赤遍羅)>読み方:アカベラ赤倍良というのは、”求仙(キュウセン:標準和名)の雌(メス)の呼び方”。求仙は、”スズキ目ベラ科キュウセン属に分類される海水魚の一種”。<赤笹之葉倍良(赤笹葉遍羅)>読み方:アカササノハベラ赤笹之葉倍良というのは、”スズキ目ベラ科ササノハベラ属に分類される海水魚の一種”。【竹麦魚(魴鮄)】読み方:ホウボウ(一種)※上は竹麦魚(一種)の写真竹麦魚というのは、”スズキ目ホウボウ科ホウボウ属に分類される海水魚の一種/スズキ目ホウボウ科に分類される海水魚の総称”。<蝉竹麦魚>読み方:セミホウボウ蝉竹麦魚というのは、”カサゴ目セミホウボウ科セミホウボウ属に分類される海水魚の一種”。竹麦魚と表記されますが、竹麦魚の仲間ではありません。【帆立貝(海扇)】読み方:ホタテガイ帆立貝というのは、”イタヤガイ目イタヤガイ科に分類される二枚貝の一種”。”貝”を略して「帆立(ホタテ)」と呼ばれることが多いです。【𩸽】読み方:ホッケ(一種)※上は𩸽(一種)の写真𩸽というのは、”カサゴ目アイナメ科ホッケ属に分類される海水魚の一種/カサゴ目アイナメ科ホッケ属に分類される海水魚の総称”。前者の意味の𩸽(標準和名)は、別名で「真𩸽(マホッケ)」とも呼ばれています。<縞𩸽>読み方:シマホッケ縞𩸽というのは、”北𩸽(キタノホッケ:標準和名)の別名”。北𩸽は、”カサゴ目アイナメ科ホッケ属に分類される海水魚の一種”。【海鞘(老海鼠・保夜)】読み方:ホヤ(総称)海鞘というのは、”ホヤ綱に分類される海産動物の総称”。<赤海鞘(赤老海鼠・赤保夜)>読み方:アカボヤ赤海鞘というのは、”ホヤ綱マボヤ目マボヤ科マボヤ属に分類される海産動物の一種”。<真海鞘(真老海鼠・真保夜)>読み方:マボヤ真海鞘というのは、”ホヤ綱マボヤ目マボヤ科マボヤ属に分類される海産動物の一種”。海鞘というと、一般的には真海鞘のことを指します。形がパイナップルに似ていることから、別名で「海のパイナップル」とも呼ばれています。【鯔(鰡・鮱)】読み方:ボラ鯔というのは、”ボラ目ボラ科ボラ属に分類される海水魚の一種”。※上は唐墨(からすみ)の写真鯔(ボラ)の卵巣を塩漬けして乾燥させたものを「唐墨(からすみ)」と呼び、雲丹(うに)・海鼠腸(このわた)と並んで日本三大珍味と言われています。鯔は出世魚(しゅっせうお)で、10cm未満のものを「オボコ」、10cm~15cm未満のものを「イナッコ」「鯐(スバシリ)」、15cm~30cm未満のものを「鯔(イナ)」、30cm~50cm未満のものを「鯔(ボラ)」、50cm以上のものを「鯔(トド)」(アシカ科のトドとは別)と呼びます。(「イナ」と「ボラ」と「トド」は漢字表記が同じなので注意が必要です)【法螺貝(吹螺・梭尾螺)】読み方:ホラガイ法螺貝というのは、”ホラガイ科ホラガイ属に分類される巻き貝の一種”。日本産の巻き貝では最大級の種類で、貝殻は楽器に加工され、合戦における戦陣の合図などに用いられました。↓マ行~【鮪】読み方:マグロ(総称)鮪というのは、”スズキ目サバ科マグロ属に分類される海水魚の総称”。<黄肌鮪(木肌鮪)>読み方:キハダマグロ黄肌鮪というのは、”スズキ目サバ科マグロ属に分類される海水魚の一種”。<黒鮪>読み方:クロマグロ黒鮪というのは、”スズキ目サバ科マグロ属に分類される海水魚の一種”。黒鮪(標準和名)は、別名で「本鮪(ホンマグロ)」とも呼ばれています。<目鉢鮪(目撥鮪)>読み方:メバチマグロ目鉢鮪というのは、”目鉢(メバチ:標準和名)の別名”。目鉢は、”スズキ目サバ科マグロ属に分類される海水魚の一種”。目鉢は、別名で「目鉢鮪(メバチマグロ)」「鉢鮪(バチマグロ)」とも呼ばれています。【鱒】読み方:マス(総称)鱒というのは、”サケ目サケ科の魚で名称に「~マス」とつくもの、またはサケ類(白鮭・紅鮭など)と呼ばれる魚を除くサケ科の魚の総称”。鱒と鮭(サケ)はどちらも「サケ目サケ科」に分類され、両者に明確な違いはなく、ここでは主に名称で分けています。<樺太鱒>読み方:カラフトマス樺太鱒というのは、”サケ目サケ科タイヘイヨウサケ属に分類される回遊魚の一種”。<桜鱒>読み方:サクラマス桜鱒というのは、”サケ目サケ科タイヘイヨウサケ属に分類される回遊魚の一種”。河川で生まれて一生を河川で過ごす河川残留型(陸封型)を「山女魚(ヤマメ)」、生まれてから海へ下る降海型を「桜鱒(サクラマス)」と呼びます。<虹鱒>読み方:ニジマス虹鱒というのは、”サケ目サケ科タイヘイヨウサケ属に分類される回遊魚の一種”。河川で生まれて一生を河川で過ごす河川残留型(陸封型)を「虹鱒(ニジマス)(英語:レインボートラウト)」、生まれてから海へ下る降海型を「鉄頭(テットウ)(英語:スチールヘッド)」と呼びます。(一般的には「カナガシラ」は”金頭”と表記されますが、鉄頭は「カナガシラ」と読むこともあるため注意が必要)【馬刀貝(馬蛤貝・蟶貝)】読み方:マテガイ(一種)※上は馬刀貝(一種)の写真馬刀貝というのは、”マルスダレガイ目マテガイ科マテガイ属に分類される二枚貝の一種/マルスダレガイ目マテガイ科に分類される二枚貝の総称”。鞘(さや)に収めた馬手差(めてざし)(右に差す腰刀のこと)に似ていることから名付けられました。【真魚鰹(鯧)】読み方:マナガツオ真魚鰹というのは、”スズキ目マナガツオ科マナガツオ属に分類される海水魚の一種”。鰹と表記されますが、鰹の仲間ではありません。【翻車魚】読み方:マンボウ(一種)※上は翻車魚(一種)の写真翻車魚というのは、”フグ目マンボウ科マンボウ属に分類される海水魚の一種/フグ目マンボウ科マンボウ属に分類される海水魚の総称”。【海松(水松)】読み方:ミル海松というのは、”ミル目ミル科ミル属に分類される緑藻の一種”。【海松貝(水松貝)】読み方:ミルガイ海松貝というのは、”マルスダレガイ目バカガイ科バカガイ属に分類される二枚貝の一種”。海松貝(ミルガイ)は、「海松食(ミルクイ)」(標準和名)の別名になります。【鯥】読み方:ムツ(一種)※上は鯥(一種)の写真鯥というのは、”スズキ目ムツ科ムツ属に分類される海水魚の一種/スズキ目ムツ科に分類される海水魚の総称”。<赤鯥>読み方:アカムツ赤鯥というのは、”スズキ目ホタルジャコ科アカムツ属に分類される海水魚の一種”。鯥と表記されますが、鯥の仲間ではありません。赤鯥(標準和名)は、一般的には別名で「喉黒(ノドグロ)」と呼ばれることが多いです。<黒鯥>読み方:クロムツ黒鯥というのは、”スズキ目ムツ科ムツ属に分類される海水魚の一種”。<白鯥>読み方:シロムツ白鯥というのは、”スズキ目ホタルジャコ科オオメハタ属に分類される海水魚の一種”。鯥と表記されますが、鯥の仲間ではありません。白鯥は、「大目羽太(オオメハタ)」(標準和名)の別名になります。【鯥五郎】読み方:ムツゴロウ鯥五郎というのは、”スズキ目ハゼ科ムツゴロウ属に分類される汽水魚の一種”。鯥五郎の雄は、雌の気を引くために(尾びれで地面を蹴って)ジャンプを繰り返してアピールします。乱獲や干拓などによる干潟の減少により、絶滅危惧種に指定されています。【紫貽貝】読み方:ムラサキイガイ紫貽貝というのは、”イガイ目イガイ科イガイ属に分類される二枚貝の一種”。紫貽貝(標準和名)は、別名で「ムール貝」とも呼ばれ、フランス料理に用いられます。【和布蕪(若布蕪)】読み方:メカブ和布蕪というのは、”若布(ワカメ)の根際の茎の左右についているひだ状の厚い葉のこと”。和布蕪はネバネバ感と、コリコリとした食感が特徴的で、このネバネバ感は「フコイダン」と呼ばれる水溶性食物繊維によるものです。【目高(鱂・麦魚・丁斑魚)】読み方:メダカ(総称)目高というのは、”ダツ目メダカ科メダカ属に分類される淡水魚の総称”。<北目高>読み方:キタノメダカ北目高というのは、”ダツ目メダカ科メダカ属に分類される淡水魚の一種”。<黒目高>読み方:クロメダカ黒目高というのは、”ダツ目メダカ科メダカ属に分類される淡水魚の一種”。<緋目高>読み方:ヒメダカ緋目高というのは、”ダツ目メダカ科メダカ属に分類される淡水魚の一種”。<南目高>読み方:ミナミメダカ南目高というのは、”ダツ目メダカ科メダカ属に分類される淡水魚の一種”。【赤目魚(眼奈太・目奈陀)】読み方:メナダ赤目魚というのは、”ボラ目ボラ科メナダ属に分類される汽水魚の一種”。【諸子】読み方:モロコ(一種)諸子というのは、”本諸子(ホンモロコ:標準和名)の別名/コイ目コイ科タモロコ属とスゴモロコ属に分類される淡水魚の総称”。<糸諸子>読み方:イトモロコ糸諸子というのは、”コイ目コイ科スゴモロコ属に分類される淡水魚の一種”。<数河諸子>読み方:スゴモロコ数河諸子というのは、”コイ目コイ科スゴモロコ属に分類される淡水魚の一種”。<田諸子>読み方:タモロコ田諸子というのは、”コイ目コイ科タモロコ属に分類される淡水魚の一種”。<本諸子>読み方:ホンモロコ本諸子というのは、”コイ目コイ科タモロコ属に分類される淡水魚の一種”。諸子というと、一般的には本諸子を指すことが多いです。↓ヤ行~【宿借(寄居虫)】読み方:ヤドカリ(総称)宿借というのは、”エビ目(十脚目)ヤドカリ科・ホンヤドカリ科・オカヤドカリ科などに分類される甲殻類の総称”。死んだ巻き貝の殻を借りて体を収めて棲(す)むことから名付けられ、宿借が成長したときには新しい巻き貝の殻に引っ越します。殻に体を収めているのは、外敵から自分の身を守ったり、水温の低下、乾燥などといった環境の変化から身を守るためです。<陸宿借(陸寄居虫)>読み方:オカヤドカリ陸宿借というのは、”エビ目オカヤドカリ科オカヤドカリ属に分類される甲殻類の一種”。<小紋宿借(小紋寄居虫)>読み方:コモンヤドカリ小紋宿借というのは、”エビ目ヤドカリ科ヤドカリ属に分類される甲殻類の一種”。<粗面宿借(粗面寄居虫)>読み方:ソメンヤドカリ粗面宿借というのは、”エビ目ヤドカリ科ヤドカリ属に分類される甲殻類の一種”。<本宿借(本寄居虫)>読み方:ホンヤドカリ本宿借というのは、”エビ目ホンヤドカリ科ホンヤドカリ属に分類される甲殻類の一種”。【山女魚(山女)】読み方:ヤマメ山女魚というのは、”サケ目サケ科タイヘイヨウサケ属に分類される淡水魚の一種”。美しい見た目から、別名で「渓流の女王」(岩魚(イワナ)は「渓流の王様」)と呼ばれています。河川で生まれて一生を河川で過ごす河川残留型(陸封型)を「山女魚(ヤマメ)」、生まれてから海へ下る降海型を「桜鱒(サクラマス)」と呼びます。分類上、山女魚と桜鱒はどちらも同じ魚になります。【葦登】読み方:ヨシノボリ(総称)葦登というのは、”スズキ目ハゼ科ヨシノボリ属に分類される淡水・汽水魚の総称”。<川葦登>読み方:カワヨシノボリ川葦登というのは、”スズキ目ハゼ科ヨシノボリ属に分類される淡水魚の一種”。<琵琶葦登>読み方:ビワヨシノボリ琵琶葦登というのは、”スズキ目ハゼ科ヨシノボリ属に分類される淡水魚の一種”。<瑠璃葦登>読み方:ルリヨシノボリ瑠璃葦登というのは、”スズキ目ハゼ科ヨシノボリ属に分類される淡水魚の一種”。↓ラ行~↓ワ行~【公魚(鰙・若鷺)】読み方:ワカサギ公魚というのは、”キュウリウオ目キュウリウオ科ワカサギ属に分類される淡水・汽水魚の一種”。※上は氷上の穴釣りの様子公魚釣りは、結氷した湖面にアイスドリルなどで穴を開けて、その穴から公魚を釣りあげる方法が有名です。【若布(和布・稚海藻)】読み方:ワカメ※茹(ゆ)でた後の若布の写真若布というのは、”コンブ目チガイソ科ワカメ属に分類される海藻の一種”。若布の元々の色は茶色で、茹(ゆ)でたりして熱を加えると緑色に変化します。これは若布の持っている赤い色素である「フコキサンチン」が、熱によって分解され退色し、緑の色素である「クロロフィル」の色が現れるためです。※上は和布蕪(メカブ)の写真ちなみに”若布の根際の茎の左右についているひだ状の厚い葉のこと”を「和布蕪(メカブ)」と呼びます。【藁素坊(藁苞)】読み方:ワラスボ藁素坊というのは、”スズキ目ハゼ科ワラスボ属に分類される海水魚の一種”。有明海(ありあけかい)のみに生息し、そのエイリアンのような見た目から、別名で「有明海のエイリアン」とも呼ばれています。干拓や環境の変化から生息数が減少し、絶滅危惧種に指定されています。魚・貝・海藻の難読漢字(一覧表)※1:漢字表記が複数ある場合は、一般的に使われることが多いほうの漢字表記を優先しています(読み方の表記も同様)。例 【鮎並(鮎魚女)】 ⇒ 【一般的に使われることが多い漢字表記(比較して一般的に使われることが少ない漢字表記)】※2:読み方の横に「(一種)」「(総称)」の表記があるものは、以下のような意味になります。例 【ウツボ(一種)】 ⇒ 【(狭義では)ウツボ目ウツボ科ウツボ属に分類される海水魚の一種】【(広義では)ウナギ目ウツボ科に分類される海水魚の総称】の両方を意味例 【アジ(総称)】 ⇒ 【スズキ目アジ科に分類される海水魚の総称】を意味(アジという名称の特定の魚が存在するわけではない)※3:標準和名=【日本での正式な名称のこと】⇒学名と標準和名の違いとは?漢字読み方備考欄鮎並(鮎魚女)アイナメ鮎並(標準和名)の別名は「油目(アブラメ)」「油子(アブラコ)」【石蓴】アオサ(総称)阿古屋貝アコヤガイ養殖真珠(しんじゅ)の母貝として知られている【浅蜊(蜊・鯏)】アサリ(一種)【鯵】アジ(総称)日本では一般的に真鯵を指すことが多い◆真鯵マアジ◆丸鯵マルアジ◆室鯵(鰘)ムロアジ伊豆諸島の特産品である「くさや」に利用される【穴子(海鰻)】アナゴ(総称)一般的には真穴子を指すことが多い◆狆穴子チンアナゴ◆真穴子マアナゴ甘子(天魚)アマゴ河川残留型(陸封型)を「甘子」、降海型を「皐月鱒(サツキマス)」と呼ぶ【沖醤蝦】オキアミ(総称)【雨虎】アメフラシ(一種)◆黒縁雨虎(黒縁雨降)クロヘリアメフラシ鮎(香魚・年魚)アユ別名で「清流の女王」とも呼ばれる【鮑】アワビ(総称)◆蝦夷鮑エゾアワビ◆黒鮑クロアワビ【鮟鱇(華臍魚・琵琶魚)】アンコウ(一種)◆黄鮟鱇(黄華臍魚・黄琵琶魚)キアンコウ【烏賊(魷)】イカ(総称)◆障泥烏賊アオリイカ◆鯣烏賊スルメイカ◆蛍烏賊ホタルイカ◆紋甲烏賊モンゴウイカ紋甲烏賊は、「雷烏賊(カミナリイカ)」(標準和名)の別名◆槍烏賊ヤリイカ【玉筋魚(鮊子)】イカナゴ(一種)玉筋魚の稚魚は東日本では「小女子(コウナゴ)」、西日本では「新子(しんこ)」と呼ぶ鶏魚(伊佐木・伊佐幾)イサキ石持(石首魚)イシモチ石持は、「白愚痴(シログチ)」(標準和名)の別名【磯巾着(菟葵)】イソギンチャク(総称)◆大疣磯巾着オオイボイソギンチャク◆砂磯巾着スナイソギンチャク◆縦縞磯巾着タテジマイソギンチャク【鰯】イワシ(総称)一般的には真鰯を指すことが多い◆片口鰯カタクチイワシ◆真鰯マイワシ岩魚(嘉魚・鮇)イワナ別名で「渓流の王様」とも呼ばれる石斑魚(鯎)ウグイ【鱓】ウツボ(一種)◆雲鱓クモウツボ◆虎鱓トラウツボ◆鼻髭鱓(花髭鱓)ハナヒゲウツボ【鰻】ウナギ(総称)日本では一般的に日本鰻のことを指す◆大鰻オオウナギ◆日本鰻ニホンウナギ◆欧羅巴鰻ヨーロッパウナギ【海胆(海栗)】ウニ(総称)加工した食品は「雲丹(ウニ)」と表記される。雲丹は「日本三大珍味」のひとつに数えられる◆赤海胆(赤海栗)アカウニ◆馬糞海胆(馬糞海栗)バフンウニ◆紫海胆(紫海栗)ムラサキウニ【海牛】ウミウシ(総称)◆青海牛アオウミウシ青海牛は、日本で最も一般的な海牛◆小疣海牛コイボウミウシ◆更紗海牛サラサウミウシ◆光海牛ヒカリウミウシ【鱏(海鷂魚)】エイ(総称)◆赤鱏アカエイ◆燕鱏ツバクロエイ◆鳶鱏トビエイ【鱛(狗母魚)】エソ(総称)◆赤鱛(赤狗母魚)アカエソ◆真鱛(真狗母魚)マエソ【海老(蝦)】エビ(総称)◆伊勢海老(伊勢蝦・竜蝦)イセエビ◆牛海老(牛蝦)ウシエビ牛海老(標準和名)の別名は「ブラックタイガー」◆車海老(車蝦)クルマエビ◆桜海老(桜蝦)サクラエビ◆牡丹海老(牡丹蝦)ボタンエビ追河オイカワ【虎魚(鰧)】オコゼ(一種)虎魚(一種)は、「鬼虎魚(オニオコゼ)」(標準和名)の別名◆鬼虎魚(鬼鰧)オニオコゼ◆鬼達磨虎魚(鬼達磨鰧)オニダルマオコゼ◆葉虎魚(葉鰧)ハオコゼ老翁オジサン【牡蠣(牡蛎)】カキ(総称)別名で「海のミルク」とも呼ばれる◆岩牡蠣(岩牡蛎)イワガキ◆真牡蠣(真牡蛎)マガキ【笠子(鮋・瘡魚)】カサゴ(一種)◆伊豆笠子イズカサゴ◆蓑笠子ミノカサゴ【鰍(杜父魚・鮖)】カジカ(一種)鰍(一種:標準和名)の別名は「鮴(ゴリ)」【梶木(旗魚・舵木)】カジキ(総称)◆芭蕉梶木バショウカジキ鰹(松魚・堅魚)カツオ金頭(方頭魚・火魚・鉄頭)カナガシラ【蟹(蠏)】カニ(総称)◆毛蟹ケガニ◆楚蟹ズワイガニ◆鱈場蟹(多羅波蟹)タラバガニ蟹と表記されるが、蟹の仲間ではなく、「宿借(ヤドカリ)」の仲間◆花咲蟹ハナサキガニ蟹と表記されるが、蟹の仲間ではなく、「宿借(ヤドカリ)」の仲間【魳(梭子魚・梭魚)】カマス(総称)◆赤魳(赤叺)アカカマス赤魳は、日本で最も一般的な魳◆大和魳(大和叺)ヤマトカマス【鰈】カレイ(総称)◆石鰈イシガレイ◆烏鰈カラスガレイ◆真鰈マガレイ川蜷(河貝子)カワニナ【皮剝(鮍)】カワハギ(一種)◆網目剥アミメハギ◆薄葉剥ウスバハギ◆馬面剥ウマヅラハギ間八(勘八)カンパチ【鱚】キス(総称)一般的には「白鱚(シロギス)」を指すことが多い◆白鱚シロギス黍魚子(吉備奈仔)キビナゴ【銀宝】ギンポ(一種)垢穢(九絵)クエ久慈目(口女)クジメ【熊之実(隈魚・隈之実)】クマノミ(一種)◆隠熊之実(隠隈魚)カクレクマノミ◆花弁熊之実ハナビラクマノミ【海月(水母・水月)】クラゲ(総称)◆兜海月(兜水母)カブトクラゲ海月と表記されるが、海月の仲間ではない◆花笠海月(花笠水母)ハナガサクラゲ◆水海月(水水母)ミズクラゲ鯉コイ観賞用に品種改良されたものを「錦鯉(ニシキゴイ)」と呼ぶ【鯒(牛尾魚)】コチ(総称)◆真鯒マゴチ◆女鯒(目鯒・眼鯒)メゴチ◆鰐鯒ワニゴチ鮗(鰶・子代)コノシロ鮴ゴリ(メバル)「ゴリ」と「メバル」で意味が異なる。「メバル」は”眼張”と表記されることが多い権瑞ゴンズイ【鮭(石桂魚・鯹)】サケ(一種)鮭(一種:標準和名)の別名は「白鮭(シロザケ)」。鮭と鱒(マス)に明確な違いはない◆銀鮭ギンザケ◆紅鮭ベニザケ湖沼残留型(陸封型)を「姫鱒(ヒメマス)」、降海型を「紅鮭」と呼ぶ栄螺(拳螺)サザエ拶双魚サッパ拶双魚(標準和名)の別名は「飯借(ママカリ)」【鯖(青花魚)】サバ(総称)一般的には「真鯖(マサバ)」を指すことが多い◆胡麻鯖ゴマサバ◆真鯖マサバ【鮫(鯊)】サメ(総称)鯊は「ハゼ」と読むことがほとんど◆小判鮫(鮣)コバンザメ鮫と表記されるが、鮫の仲間ではない◆撞木鮫(双髻鯊・犁頭魚)シュモクザメ(総称)◆甚兵衛鮫(甚平鮫)ジンベエザメ(ジンベイザメ)「ジンベイザメ」は、「ジンベエザメ」(標準和名)の別名◆蝶鮫(鱘魚・鱘)チョウザメ鮫と表記されるが、鮫の仲間ではない◆頬白鮫ホオジロザメ(ホホジロザメ)「ホオジロザメ」は、「ホホジロザメ」(標準和名)の別名◆葦切鮫(吉切鮫)ヨシキリザメ鰭(ひれ)は高級食材である「鱶鰭(フカヒレ)」の原料となる【細魚(針魚・鱵)】サヨリ(一種)針魚は「ハリヨ」と読むこともできる◆子持細魚コモチサヨリ【蝲蛄(蜊蛄・躄蟹)】ザリガニ(総称)日本では一般的に「亜米利加蝲蛄(アメリカザリガニ)」を指すことが多い◆亜米利加蝲蛄(亜米利加蜊蛄)アメリカザリガニ◆日本蝲蛄(日本蜊蛄)ニホンザリガニ【鰆(馬鮫魚)】サワラ(一種)鰆は出世魚として知られている【珊瑚】サンゴ(総称)◆錣珊瑚シコロサンゴ◆擂鉢珊瑚スリバチサンゴ◆花笠珊瑚(花傘珊瑚)ハナガササンゴ【秋刀魚】サンマ鱰シイラ鱰(標準和名)の別名は「マヒマヒ」【潮招(望潮)】シオマネキ(一種)◆白扇潮招ハクセンシオマネキ◆紅潮招ベニシオマネキ【蜆】シジミ(総称)◆台湾蜆タイワンシジミ◆真蜆マシジミ◆大和蜆ヤマトシジミ柳葉魚シシャモ【蝦蛄(青竜蝦)】シャコ(一種)◆虎斑蝦蛄トラフシャコ◆紋花蝦蛄モンハナシャコ【白魚(鱠残魚・膾残魚・銀魚)】シラウオ(一種)白子しらこ(シラス)「しらこ」と「シラス」で意味が異なる素魚(白魚)シロウオ白魚は「シラウオ」と読むことが多い【鱸】スズキ(一種)鱸(一種:標準和名)の別名は「丸鱸(マルスズキ)」【鯛】タイ(総称)一般的には「真鯛(マダイ)」のことを指す◆赤魚鯛(阿候鯛)アコウダイ鯛と表記されるが、鯛の仲間ではない◆真鯛マダイ真鯛(標準和名)の別名は「桜鯛(サクラダイ)」◆的鯛(馬頭鯛)マトウダイ鯛と表記されるが、鯛の仲間ではない高砂タカサゴ高砂(標準和名)の沖縄での別名は「グルクン」【蛸(章魚・鮹・鱆)】タコ(総称)一般的には「真蛸(マダコ)」を指すことが多い◆飯蛸(望潮魚)イイダコ◆豹紋蛸ヒョウモンダコ◆真蛸(真章魚)マダコ太刀魚(立魚・帯魚・魛)タチウオ【駄津】ダツ(一種)【竜の落とし子(海馬)】タツノオトシゴ(一種)海馬は「アシカ」「トド」「セイウチ」と読むこともできる◆茨竜イバラタツ◆大海馬オオウミウマ◆黒海馬クロウミウマ【田螺】タニシ(総称)◆大田螺オオタニシ◆姫田螺ヒメタニシ【鱈】タラ(総称)◆介党鱈(鯳)スケトウダラ介党鱈(標準和名)の別名は「介宗鱈・助惣鱈(スケソウダラ)」◆真鱈マダラ一般的には「真鱈(マダラ)」を指すことが多い常節(床伏・常伏)トコブシ【泥鰌(鰌・鯲)】ドジョウ(一種)泥鰌(一種:標準和名)の別名は「真泥鰌(マドジョウ)」◆筋縞泥鰌スジシマドジョウ◆仏泥鰌ホトケドジョウ【飛魚(𩹉)】トビウオ(一種)飛魚(一種:標準和名)の九州などでの別名は「アゴ」【富魚(止水魚)】トミヨ(一種)◆茨富魚イバラトミヨ【海鼠(生子)】ナマコ(総称)海鼠の、腸などの内臓を塩辛にしたものを「海鼠腸(このわた)」と呼ぶ。海鼠腸は「日本三大珍味」のひとつに数えられる◆赤海鼠アカナマコ◆藤海鼠フジナマコ◆真海鼠マナマコ【鯰(魸)】ナマズ(一種)鯰(標準和名)の別名は「真鯰(マナマズ)」「日本鯰(ニホンナマズ)」◆岩床鯰イワトコナマズ◆琵琶湖大鯰ビワコオオナマズ鰊(鯡)ニシン鮸ニベ馬鹿貝(馬珂貝)バカガイ馬鹿貝のむき身を「青柳(アオヤギ)」と呼ぶ【鯊(沙魚・蝦虎魚)】ハゼ一般的には「真鯊(マハゼ)」を指すことが多い◆虚鯊(虚沙魚)ウロハゼ◆跳鯊(跳沙魚)トビハゼ◆真鯊(真沙魚)マハゼ鰰(鱩・雷魚・燭魚)ハタハタ雷魚は「ライギョ」と読むことが多い【蛤(文蛤・浜栗)】ハマグリ(一種)◆朝鮮蛤(汀線蛤)チョウセンハマグリ【鱧】ハモ(一種)【針千本(魚虎)】ハリセンボン(一種)◆鼠河豚ネズミフグ河豚(フグ)と表記されるが、針千本の仲間◆人面針千本ヒトヅラハリセンボン針魚ハリヨ(サヨリ)「サヨリ」は”細魚”と表記されることが多い【鰉】ヒガイ(総称)◆川鰉カワヒガイ【海星(人手・海盤車)】ヒトデ(総称)◆赤海星(赤人手)アカヒトデ◆糸巻海星(糸巻人手)イトマキヒトデ◆鬼海星(鬼人手)オニヒトデ◆黄海星(黄人手)キヒトデ黄海星(標準和名)の別名は「真海星(マヒトデ)」【鋸刺鮭】ピラニア(総称)平政ヒラマサ【鮃(平目・比目魚)】ヒラメ(一種)【河豚(鰒・鯸・魨)】フグ(総称)◆草河豚クサフグ◆虎河豚トラフグ◆箱河豚ハコフグ◆真河豚マフグ【鮒(鯽)】フナ(総称)◆金鮒キンブナ◆銀鮒ギンブナ◆源五郎鮒ゲンゴロウブナ養殖個体を「平鮒(ヘラブナ)」「河内鮒(カワチブナ)」と呼ぶ鰤ブリ鰤は出世魚として知られている【倍良(遍羅)】ベラ(総称)◆青倍良(青遍羅)アオベラ「求仙(キュウセン)」(標準和名)の雄(オス)の呼び方◆赤倍良(赤遍羅)アカベラ「求仙(キュウセン)」(標準和名)の雌(メス)の呼び方◆赤笹之葉倍良(赤笹葉遍羅)アカササノハベラ【竹麦魚(魴鮄)】ホウボウ(一種)◆蝉竹麦魚セミホウボウ竹麦魚と表記されるが、竹麦魚の仲間ではない帆立貝(海扇)ホタテガイ略して「帆立(ホタテ)」と呼ばれることが多い【𩸽】ホッケ(一種)𩸽(一種:標準和名)の別名は「真𩸽(マホッケ)」◆縞𩸽シマホッケ縞𩸽は、「北𩸽(キタノホッケ)」(標準和名)の別名【海鞘(老海鼠・保夜)】ホヤ(総称)一般的には「真海鞘(マボヤ)」のことを指す◆赤海鞘(赤老海鼠・赤保夜)アカボヤ◆真海鞘(真老海鼠・真保夜)マボヤ別名で「海のパイナップル」とも呼ばれる鯔(鰡・鮱)ボラ卵巣を塩漬けして乾燥させたものを「唐墨(からすみ)」と呼ぶ。唐墨は「日本三大珍味」のひとつに数えられる法螺貝(吹螺・梭尾螺)ホラガイ【鮪】マグロ(総称)一般的には「黒鮪(クロマグロ)」を指すことが多い◆黄肌鮪(木肌鮪)キハダマグロ◆黒鮪クロマグロ黒鮪(標準和名)の別名は「本鮪(ホンマグロ)」◆目鉢鮪(目撥鮪)メバチマグロ目鉢鮪は、「目鉢(メバチ)」(標準和名)の別名【鱒】マス(総称)鱒と鮭(サケ)に明確な違いはない◆樺太鱒カラフトマス◆桜鱒サクラマス河川残留型(陸封型)を「山女魚(ヤマメ)」、降海型を「桜鱒」と呼ぶ◆虹鱒ニジマス河川残留型(陸封型)を「虹鱒」、降海型を「鉄頭(テットウ)」と呼ぶ【馬刀貝(馬蛤貝・蟶貝)】マテガイ(一種)真魚鰹(鯧)マナガツオ鰹と表記されるが、鰹の仲間ではない【翻車魚】マンボウ(一種)海松(水松)ミル海松貝(水松貝)ミルガイ海松貝は、「海松食(ミルクイ)」(標準和名)の別名【鯥】ムツ(一種)◆赤鯥アカムツ赤鯥(標準和名)の別名は「喉黒(ノドグロ)」。鯥と表記されるが、鯥の仲間ではない◆黒鯥クロムツ◆白鯥シロムツ白鯥は、「大目羽太(オオメハタ)」(標準和名)の別名。鯥と表記されるが、鯥の仲間ではない鯥五郎ムツゴロウ紫貽貝ムラサキイガイ紫貽貝(標準和名)の別名は「ムール貝」和布蕪(若布蕪)メカブ若布(ワカメ)の根際の茎につくひだ状の葉のこと【目高(鱂・麦魚・丁斑魚)】メダカ(総称)◆北目高キタノメダカ◆黒目高クロメダカ◆緋目高ヒメダカ◆南目高ミナミメダカ赤目魚(眼奈太・目奈陀)メナダ【諸子】モロコ(一種)諸子(一種)は、「本諸子(ホンモロコ)」(標準和名)の別名◆糸諸子イトモロコ◆数河諸子スゴモロコ◆田諸子タモロコ◆本諸子ホンモロコ【宿借(寄居虫)】ヤドカリ(総称)◆陸宿借(陸寄居虫)オカヤドカリ◆小紋宿借(小紋寄居虫)コモンヤドカリ◆粗面宿借(粗面寄居虫)ソメンヤドカリ◆本宿借(本寄居虫)ホンヤドカリ山女魚(山女)ヤマメ別名で「渓流の女王」とも呼ばれる。河川残留型(陸封型)を「山女魚」、降海型を「桜鱒(サクラマス)」と呼ぶ【葦登】ヨシノボリ(総称)◆川葦登カワヨシノボリ◆琵琶葦登ビワヨシノボリ◆瑠璃葦登ルリヨシノボリ公魚(鰙・若鷺)ワカサギ氷上の穴釣りが有名若布(和布・稚海藻)ワカメ根際の茎につくひだ状の葉を「和布蕪(メカブ)」と呼ぶ藁素坊(藁苞)ワラスボ別名で「有明海のエイリアン」とも呼ばれる項目1項目2項目3)★ -->関連ページ<難読漢字の一覧>⇒【一文字】難読漢字の一覧!⇒【野菜・果物・茸】難読漢字の一覧!⇒【動物】難読漢字の一覧!⇒【鳥】難読漢字の一覧!⇒【花・植物】難読漢字の一覧!⇒【虫】難読漢字の一覧!⇒【食べ物・飲み物】難読漢字の一覧!⇒【道具・身近なモノ】難読漢字の一覧!<読み間違えやすい漢字の一覧>⇒読み間違えやすい漢字一覧!⇒慣用読み(百姓読み)の一覧!<難読漢字の一覧(偏)>⇒【魚偏】難読漢字の一覧!⇒【虫偏】難読漢字の一覧!⇒【木偏】難読漢字の一覧!⇒【金偏】難読漢字の一覧!