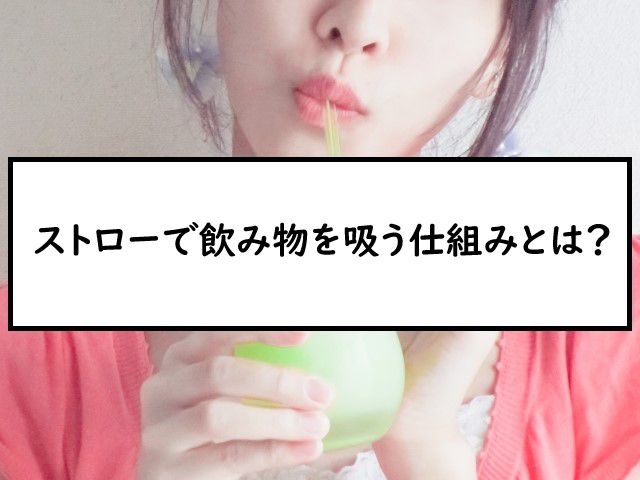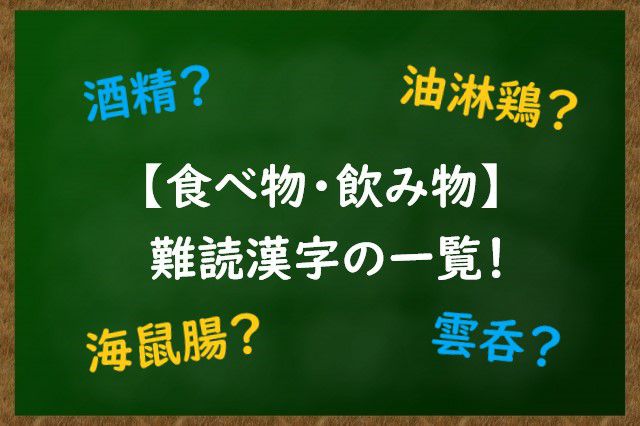さてコップに飲み物を入れて飲むとき、ストローを使用して飲むことがあります。ストローを使って飲むと、飲み物がストローの中を少しずつ上ってきて面白いですよね。ですがどんな仕組みで飲み物がストローの中を上がってくるのか、疑問に思ったことがある人もいるのではないでしょうか。そこでこのページでは、ストローで飲み物を吸うことができる仕組みを簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次ストローで飲み物を吸う仕組みについてストローの先端をふさぐと飲み物が落ちない理由まとめ1.ストローで飲み物を吸う仕組みについてではストローで飲み物を吸うことができる仕組みを見ていきましょう。結論から言ってしまうと、吸うことでストローの中の気圧が下がり、飲み物の上からかかる気圧よりも小さくなるからです。まず空気が存在しているところには気圧という力が発生するため、ほとんどのものにはあらゆる方向から気圧がかかっています。なのでコップに水(飲み物)とストローを入れたときには、下図のように気圧がかかっています。上図のようにストローの中と外の飲み物の両方に、上から同じ大きさの気圧がかかっています。つまりはストローの中と外の気圧の大きさは釣り合っているということです。ストローの中と外の気圧の大きさが釣り合っているからこそ水面の高さが同じになります。ではストローで飲み物を吸ったときはどのようになるのでしょうか?ストローで飲み物を吸ったときを図にすると下のようになります。飲み物をストローで吸うということは、まず先にストロー内の空気を吸うことから始まります。そして気圧の大きさというのは空気の量に比例します。なので存在する空気の量が多ければ気圧は大きくなり、存在する空気の量が少なければ気圧は小さくなります。飲み物を吸うことでストローの中の空気が少なくなるので、ストローの中と外で釣り合っていた気圧が変化します。ストローの外の気圧の方が大きくなり飲み物を上から押している気圧が、ストローの中の飲み物を口まで押し上げるということになります。関連:気圧とは何かをわかりやすく解説!なぜ気圧で人はつぶされないのか?2.ストローの先端をふさぐと飲み物が落ちない理由ではストローの先端をふさぐと飲み物が落ちない理由を見ていきましょう。まずストローの中に飲み物を入れた状態で、先端をふさいで空気が入らないようにします。次にストローの先端をふさいだまま上に持ち上げると、なぜかふさがっていない下の方から飲み物は落ちていきません。なぜ飲み物が下の方から落ちていかないのか?それはストローの中の飲み物の重さよりも、ストローの下から気圧によって押される力の方が大きいからです。気圧はあらゆる方向からかかるのでストローの下からもかかります。(上図の赤い矢印が気圧によってかかる力)そしてその気圧によって押される力が水の重さよりも大きいため、ストローの先端をふさいだ場合は水が落ちてこないんですね。ストローの先端をふさがないで飲み物を入れて持ち上げると、そのまま飲み物が下に落ちていってしまいます。これはストローの先端がふさがれておらず上からも下からも気圧がかかる状態なので、気圧の力が相殺されて単純に飲み物の重さだけがかかるようになります。だから先端がふさがれていないときは、すぐに下に落ちていってしまいます。ちなみに地上にかかる気圧の大きさを1気圧と表しますが、1気圧の大きさだと底面1[cm^2]の長さ10.33[m]の水柱等しい重さになります。なので底面が1[cm^2]で10.33[m]よりも短いストローであれば、水を入れても先端をふさいでいればストローから水が落ちてこないことになります。さすがにそこまで長いストローは使うことはありませんが面白いですよね。関連:1気圧とは?また何ヘクトパスカル(hPa)なのか?関連:なぜ単位は大文字と小文字で区別しなければいけないのか?以上が「ストローで飲み物を吸うことができる仕組みとは?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、ストローで飲み物を吸う仕組みは、吸うことで外で飲み物を押す気圧よりもストローの中の気圧が小さくなるため。飲み物を入れたままストローの先端をふさぐと、下から気圧に押される力の方が大きいので飲み物は落ちなくなる。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒水圧とは何か?わかりやすく図を用いて解説!⇒絶対零度とは?また絶対零度の温度は何度なのか?⇒コップに水滴がつく理由とは?分かりやすく仕組みを図で解説!⇒山でお菓子の袋が膨らむ仕組みとは?分かりやすく図で解説!⇒吸盤が壁にくっつく仕組みとは?⇒ピンポン玉のへこみの直し方とは?またへこみが直る仕組みについて⇒結露とは何か?仕組みを分かりやすく図解!⇒揮発性とは?揮発性が高い・低いとはどういう意味なのか?⇒圧力鍋とは何か?圧力鍋の仕組みをわかりやすく図解!⇒浮力とは何か?浮力の原理を簡単に図で解説!
ギモン雑学
「 飲み物 」の検索結果
-
-
このページでは食べ物・飲み物の難読漢字について簡単に一覧にしてまとめています。(食べ物・飲み物の難読漢字を新しく見つけ次第、追記していきます)どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次↓食べ物・飲み物の難読漢字の読み方や説明、写真などを載せています◆【ア行~】◇【カ行~】◆【サ行~】◇【タ行~】◆【ナ行~】◇【ハ行~】◆【マ行~】◇【ヤ行~】◆【ラ行~】◇【ワ行~】↓食べ物・飲み物の難読漢字とその読み方だけをザっと見たい方はこちら(同ページのリンクへ移動します)●食べ物・飲み物の難読漢字(一覧表)↓関連ページはこちら(同ページのリンクへ移動します)★関連ページ食べ物・飲み物の難読漢字※1:漢字表記が複数ある場合は、一般的に使われることが多いほうの漢字表記を優先しています(読み方の表記も同様)。例 【甘酒(醴)】 ⇒ 【一般的に使われることが多い漢字表記(比較して一般的に使われることが少ない漢字表記)】↓ア行~【甘酒(醴)】読み方:あまざけ甘酒というのは、”白米の粥(かゆ)に米麹(こめこうじ)を混ぜ、発酵させて作る甘い飲み物のこと/酒粕(さけかす)を水で溶いて甘味をつけた飲み物のこと”。前者の意味の甘酒はアルコールを含んでいませんが、後者の意味の甘酒は酒粕を使用しているためアルコールを含んでいます。【霰】読み方:あられ※上は雛霰(ひなあられ)の写真霰というのは、”糯米(もちごめ)を原料とし、小さく切って煎(い)ったり油で揚げたりして、醤油(しょうゆ)・砂糖などで味付けしたお菓子のこと”。”桃の節句(3月3日)の雛祭りに供えられる霰のこと”を「雛霰(ひなあられ)」と呼びます。※上は御欠の写真また霰は御欠(おかき)と似ていますが、それぞれの明確な違いは大きさで、小さいものは「霰」、大きいものは「御欠」と分類されています(大きさに明確な基準はない)。【酒精】読み方:アルコール酒精というのは、”酒の主成分のひとつ。炭化水素の水素原子をヒドロキシ基で置き換えた物質の総称のこと”。【泡盛】読み方:あわもり泡盛というのは、”沖縄特産の蒸留酒のこと”。泡盛のアルコール度数は一般的には30度前後で、種類によっては20度前後や50度前後のものもあります。【餡子】読み方:あんこ※上は粒餡(つぶあん)の写真※上は漉し餡(こしあん)の写真餡子というのは、”茹(ゆ)でた小豆(あずき)などの豆に砂糖などを混ぜて、甘く煮詰めて練ったもの”。豆の皮を残したものを「粒餡(つぶあん)」、皮を漉(こ)し取ったものを「漉し餡(こしあん)」と呼びます。【杏仁豆腐】読み方:あんにんどうふ杏仁豆腐というのは、”杏仁(きょうにん)をすりつぶした粉状のもの(杏仁霜)を水と合わせて混ぜ、その液体に牛乳や砂糖、寒天(またはゼラチン)などを加えて冷やしたもの”。杏子の種子の中にはアーモンドのような見た目の核があり、その核の部分のことを「杏仁(きょうにん)」と呼んでいます。※上は杏仁を砕いたものの写真※上は杏仁霜の写真杏仁の皮を剥くと白い部分が現れますが、その白い部分が杏仁豆腐に使われ、白い部分を粉状にしたものを「杏仁霜(きょうにんそう)」と言います。(杏仁豆腐は「きょうにんどうふ」と読むこともできますが、一般的には「あんにんどうふ」と読むことがほとんど)一般的に売られている杏仁豆腐の場合は、杏仁霜(粉)がアーモンドパウダーで代用されていることが多いです。【芋堅干】読み方:いもけんぴ芋堅干というのは、”薩摩芋(さつまいも)を細く切り、油で揚げて砂糖を絡(から)めたお菓子のこと”。【外郎】読み方:ういろう外郎というのは、”米粉(こめこ)に水・砂糖などを加えて蒸したお菓子のこと”。外郎は名古屋・山口・伊勢(いせ)などの名物として知られています。【烏龍茶】読み方:うーろんちゃ烏龍茶というのは、”茶葉の発酵途中で加熱して、発酵を止めた半発酵茶のこと”。【饂飩】読み方:うどん(ワンタン)※上は饂飩(うどん)の写真※上は雲呑(ワンタン)の写真「うどん」と読むと”小麦粉に水を加えて捏(こ)ねて延ばし、細長く切った食品のこと”。「ワンタン」と読むと”中華料理の一種。小麦粉をこねて薄くのばした皮に、豚の挽肉(ひきにく)やネギなどを包んだ料理のこと”。茹(ゆ)でてスープに入れたり、揚(あ)げたりして食べられます。「ワンタン」は”雲呑”と表記されることが多いです。【雲丹】読み方:ウニ雲丹というのは、”ウニの生殖巣(精巣と卵巣)を塩漬けにした食品のこと”。雲丹は他に海胆・海栗と書き表されることもありますが、トゲトゲの殻の付いたものを「海胆・海栗」、食品のことは「雲丹」と書き表されることが多いです。なので生物として捉えると「海胆・海栗」となり、食品として捉えると「雲丹」と表記されます。【御欠】読み方:おかき御欠というのは、”糯米(もちごめ)を原料とし、ある程度の大きさで切って煎(い)ったり油で揚げたりして、醤油(しょうゆ)・砂糖などで味付けしたお菓子のこと”。※上は霰の写真また御欠は霰(あられ)と似ていますが、それぞれの明確な違いは大きさで、小さいものは「霰」、大きいものは「御欠」と分類されます(大きさに明確な基準はない)。【御菜】読み方:おかず御菜というのは、”食事の際の副食物のこと”。例えばとんかつ定食(白米・味噌汁・とんかつ・キャベツ)だとすると、御菜は白米と味噌汁を除いた、とんかつとキャベツのことを指します。日本では「主食+汁物+副食(主菜+副菜など)」の構成が多く、上記の例でいうと「主食(白米)+汁物(味噌汁)」を除いた、「副食(とんかつ・キャベツ)」が御菜になります。【雪花菜(御殻)】読み方:おから雪花菜というのは、”豆腐を作るときにできる、大豆(だいず)をしぼったカスのこと”。大豆を煮てすりつぶしたものを漉(こ)したものが豆乳で、その残りカスが雪花菜です。そして豆乳に苦汁(にがり)などを加えて固めたものが豆腐になります。【粔籹】読み方:おこし粔籹というのは、”糯米(もちごめ)・粟(あわ)などを蒸して、乾かして煎(い)ったものを水飴(みずあめ)と砂糖で固めたお菓子のこと”。【御強】読み方:おこわ御強というのは、”赤飯(せきはん)のこと”。【御節】読み方:おせち御節というのは、”正月・節句(せっく)などに作る料理のこと”。ただ一般的には御節は、”主に正月に作る料理のこと”を指します。節句というのは”年中行事を行う日のうちで特に重要な日のこと”で、人日(じんじつ)・上巳(じょうし)・端午(たんご)・七夕(たなばた)・重陽(ちょうよう)の5つの日を指します。それぞれ人日(1月7日)・上巳(3月3日)・端午(5月5日)・七夕(7月7日)・重陽(9月9日)となります。【御田】読み方:おでん御田というのは、”蒟蒻(こんにゃく)・大根・つみれ・はんぺん・卵などを煮込んだ料理のこと”。【御萩】読み方:おはぎ御萩というのは、”糯米(もちごめ)や粳米(うるちまい)を炊き、軽く搗(つ)いて小さく丸めたものに、餡(あん)・黄粉(きなこ)などをつけたお菓子のこと”。御萩と牡丹餅(ぼたもち)は同じ食べ物で、食べる時期によって名称が区別され、それぞれ(牡丹と萩)の花の咲く季節に関係しています。牡丹(ボタン)の花は春頃に咲くため、春の彼岸で食べる場合は「牡丹餅」、萩(ハギ)の花は秋頃に咲くため、秋の彼岸で食べる場合は「御萩」と呼びます。↓カ行~【混合酒】読み方:カクテル混合酒というのは、”ベースとなる酒に、ジュースや他の酒などを混ぜて作る飲み物のこと”。ベースとなる酒は、主に「ウォッカ・テキーラ・ジン・ラム・リキュール」などがあります。【卵糖(家主貞良・加須底羅)】読み方:カステラ卵糖というのは、”小麦粉・鶏卵・砂糖などを混ぜて焼いたお菓子のこと”。【数の子(鯑)】読み方:かずのこ数の子というのは、”鰊(ニシン)の卵巣を塩漬けまたは乾燥させた食品のこと”。【鰹節】読み方:かつおぶし鰹節というのは、”鰹の魚肉を煮熟(しゃじゅく)(煮詰めること)させてから乾燥させた食品のこと”。鰹節は一般的には薄く削って使用し、その薄く削ったものを「削り節(けずりぶし)」(または鰹削り節)と呼びます。【蟹玉】読み方:かにたま蟹玉というのは、”中華料理のひとつ。溶き卵にほぐした蟹(カニ)の身と野菜などを入れて焼いた料理のこと”。蟹玉はあんかけタイプが一般的で、中国では「芙蓉蟹(フーヨーハイ)」と呼ばれます。【蒲鉾】読み方:かまぼこ蒲鉾というのは、”白身の魚肉をすりつぶして練り上げ、蒸したり、焼いたりした食品のこと”。蒲鉾は白色とピンク色の2色のものが一般的ですが、これは日本では紅白(こうはく)が縁起が良いとされているからです。【粥】読み方:かゆ粥というのは、”水を多くして米を軟らかく軟らかく煮た料理のこと”。【唐墨(鱲子・鰡子)】読み方:からすみ唐墨というのは、”鯔(ボラ)の卵巣を塩漬けして乾燥させた食品のこと”。長崎県が有名な産地で、雲丹(うに)・海鼠腸(このわた)と並んで日本三大珍味と言われています。【浮石糖(泡糖)】読み方:カルメラ浮石糖というのは、”砂糖に少量の水を加え、加熱して溶かし、重曹を加えてかき混ぜ、膨らませた軽石状のお菓子のこと”。浮石糖は一般的には、別名で「カルメ焼き」と呼ばれることが多いです。【咖喱】読み方:カレー咖喱というのは、”多種類の香辛料を混合させて調理された煮込み料理のこと”。【燗酒】読み方:かんざけ燗酒というのは、”温めた日本酒のこと”。燗(かん)は、”酒を器に入れて適度に温めること”を意味。【干瓢(乾瓢)】読み方:かんぴょう干瓢というのは、”夕顔(ユウガオ)の果肉を紐(ひも)状に剥いて乾燥させた食品”。夕顔の果実には細長い形の「長夕顔(ナガユウガオ)」と丸みを帯びた球状の「丸夕顔(マルユウガオ)」があり、主に丸夕顔から干瓢が作られます。【雁擬(雁擬き)】読み方:がんもどき雁擬というのは、”豆腐をつぶして、蓮根(れんこん)・牛蒡(ごぼう)などを混ぜて、油で揚げた料理のこと”。雁擬は、別名で「がんも」「飛竜頭(ひりょうず)」とも呼ばれています。雁(がん)という鳥の肉に似せた味ということから、「雁擬(がんもどき)」と名付けられました。【棊子麺(碁子麺)】読み方:きしめん棊子麺というのは、”幅が広くて薄い形状の饂飩(うどん)のこと”。棊子麺は、名古屋(愛知県)の名産になります。【黄粉】読み方:きなこ黄粉というのは、”大豆を炒(い)った後に、挽(ひ)いて粉にしたもの”。【沈菜】読み方:キムチ沈菜というのは、”朝鮮半島の代表的な漬(つ)け物のこと”。沈菜は、”大根・白菜(はくさい)などを主な材料として、それに唐辛子・生姜(しょうが)・ニンニクなどを合わせて漬け込んだもの”を指します。【餃子】読み方:ギョウザ餃子というのは、”小麦粉を捏(こ)ねて薄く伸ばした皮に、挽肉(ひきにく)・野菜を包んで焼いたり、茹でたり、蒸したりしたもの”。【切蒲英(切短穂)】読み方:きりたんぽ※上は切蒲英鍋の写真切蒲英というのは、”炊いた米をつぶして、杉串に円筒状に巻きつけて焼いたもの。また、それを串から抜いて切り、鶏肉や野菜などと煮た鍋料理のこと”。後者の意味は「切蒲英鍋(きりたんぽなべ)」とも呼ばれ、秋田県の郷土料理として知られています。【金鍔】読み方:きんつば金鍔というのは、”餡(あん)に水で溶いた小麦粉をつけ、鉄板の上で一面ずつ軽く焼いたお菓子のこと”。刀の鍔(つば)に似せて平たく成形されています。金鍔は、「金鍔焼き(きんつばやき)」の略称になります。【金団】読み方:きんとん金団というのは、”薩摩芋(さつまいも)などで作った餡に、砂糖で甘く煮た栗(くり)・隠元豆(インゲンマメ)などを混ぜた食品のこと”。隠元豆(一般的に白隠元豆が多い)で作られたものを「豆金団(まめきんとん)」、栗で作られたものを「栗金団(くりきんとん)」と呼びます。金団は”金運や勝負運を願う料理”としてお正月のおせち料理で用いられ、縁起の良い食べ物として知られています。【月餅】読み方:げっぺい月餅というのは、”干し柿・胡桃(くるみ)などを入れた餡を、小麦粉・砂糖・卵・油などを混ぜた生地で包んだ中国の焼き菓子のこと”。【巻繊汁】読み方:けんちんじる巻繊汁というのは、”崩した豆腐と千切り(繊切り)にした野菜を油で炒めたものを具とした汁物のこと”。巻繊は”椎茸(しいたけ)・ごぼう・にんじんなどを千切りにして味付けして、湯葉を巻いて油で揚げたもの”で、現在では”崩した豆腐を野菜とともに油で炒めて、醤油(しょうゆ)・酒などで味付けしたもの”を指します。【珈琲】読み方:コーヒー珈琲というのは、”コーヒーの木(アカネ科の常緑小高木)の種子(コーヒー豆)を煎(い)って粉にしたもの。また、その粉から湯または水で成分を抽出した飲み物のこと”。コーヒー豆にはカフェインや、ポリフェノールの一種であるクロロゲン酸などが多く含まれています。【海鼠腸】読み方:このわた海鼠腸というのは、”海鼠(ナマコ)の、腸などの内臓を塩辛にしたもの”。海鼠腸は、雲丹(うに)・唐墨(からすみ)と並んで日本三大珍味と言われています。【米粉】読み方:こめこ(ビーフン)※上はビーフンの写真「こめこ」と読むと”米を挽(ひ)いて粉末状にしたもの”。「ビーフン」と読むと”粳米(うるちまい)を原料とした麺の一種”。【蒟蒻】読み方:こんにゃく蒟蒻というのは、”蒟蒻芋(こんにゃくいも)を粉状にしたものを水で練り、石灰乳(消石灰を少量の水で懸濁したもの)を加えて、茹でて固めた食品のこと”。蒟蒻芋には毒があり生食はできないため、茹でてアルカリ処理を行うなどの毒抜きをしてから食用とすることができます。【昆布】読み方:こんぶ昆布というのは、”褐藻(かっそう)類コンブ科の海藻の総称のこと”。主に東北・北海道の沿岸に分布しており、長いものでは長さ数十メートルほどに達します。【金平糖】読み方:こんぺいとう金平糖というのは、”表面に突起がある小さい球状の砂糖菓子のこと”。↓サ行~【搾菜】読み方:ザーサイ搾菜というのは、”芥子菜(からしな)の変種の根に近い肥大した部分を、唐辛子と塩を用いて漬けた漬物のこと”。搾菜(漬物)の原料となる芥子菜の変種(植物)のことを指して「搾菜(ザーサイ)」と呼ぶこともあります。【白湯(素湯)】読み方:さゆ白湯というのは、”何も混ぜていない、水を沸(わ)かしただけのお湯のこと”。【炸醤麺】読み方:ジャージャーメン炸醤麺というのは、”豚の挽肉(ひきにく)や細かく切った筍(タケノコ)などを豆板醤(トウバンジャン)・甜麵醬(テンメンジャン)などで炒めて作った肉味噌を、茹でた麺の上に乗せた料理のこと”。【三鞭酒】読み方:シャンパン三鞭酒というのは、”フランスのシャンパーニュ地方特産のスパークリングワインのこと”。フランスのシャンパーニュ地方で生産されていて、決められた製法で造られたものしかシャンパンを名乗ることはできません。またシャンパンと言えば有名なのが「ドン・ペリニヨン」(略して「ドンペリ」)ですが、ドンペリは高級シャンパンとして世界中で有名です。ドンペリ(高級シャンパン)の名前は、最初にシャンパンを製造したと言われているドン・ペリニヨンという神父さんの名前から付けられたものです。【焼売】読み方:シュウマイ焼売というのは、”中国料理の点心(てんしん)のひとつ。豚の挽肉・ねぎ・ニンニクなどのみじん切りを、小麦粉で作った皮に包んで蒸したもの”。点心は、”中国料理で、食事代わりの軽い食べ物のこと”を指します。【紹興酒】読み方:しょうこうしゅ紹興酒というのは、”中国の代表的な醸造酒。蒸した糯米(もちごめ)・麦麹(むぎこうじ)・酒母(酵母を培養したもの)などを原料として造ったもの”。【小籠包】読み方:しょうろんぽう小籠包というのは、”中国料理の点心のひとつ。調理した豚の挽肉に刻(きざ)んだ野菜などを混ぜ、スープと一緒に小麦粉の生地(きじ)で包んだ小型の蒸し饅頭(まんじゅう)のこと”。点心は、”中国料理で、食事代わりの軽い食べ物のこと”を指します。【塩汁鍋】読み方:しょっつるなべ塩汁鍋というのは、”鰰(ハタハタ)など白身の魚や豆腐、野菜などを塩汁(しょっつる)で味付けした、秋田県の郷土料理のこと”。”鰯(イワシ)・鰰(ハタハタ)などを塩漬けにし、魚の成分が溶け合ってどろどろになった汁を濾したもの”を「塩汁(しょっつる)」と呼び、塩汁は秋田特産の魚醤油(うおじょうゆ)になります。鰰の卵のことを「ぶりこ(または、ぶりっこ)」と呼び、ぶりこはヌルヌルとした粘液で覆われているのが特徴的です。【汁粉】読み方:しるこ汁粉というのは、”小豆(あずき)の餡を水でのばして、餅または白玉などを入れたもの”。汁粉は、「お汁粉(おしるこ)」とも呼ばれています。一般的には”漉し餡(こしあん)を用いたもの”を「汁粉(しるこ)」、”粒餡(つぶあん)を用いたもの”を「善哉(ぜんざい)」と呼ぶことが多いです。【洋酒】読み方:ジン洋酒というのは、”玉蜀黍(トウモロコシ)・大麦・ライ麦を原料とし、杜松(ネズ)の実で香りづけをした蒸留酒のこと”。【成吉思汗】読み方:ジンギスカン成吉思汗というのは、”溝(みぞ)のついた兜形の鉄鍋で、羊肉の薄切りを焼いて食べる料理のこと”。成吉思汗は、北海道の郷土料理として知られています。【真薯(糝薯・真蒸・真丈)】読み方:しんじょ真薯というのは、”海老(エビ)・鶏肉・魚の白身などをすりつぶしたものに、山芋や卵白などを加えて、蒸したり茹でたりした練り物のこと”。【水団】読み方:すいとん水団というのは、”小麦粉を水で捏ねて団子状にし、その団子を入れた汁物のこと”。【鋤焼】読み方:すきやき鋤焼というのは、”肉(一般的には牛肉)や葱(ネギ)・豆腐などを、タレで焼いたり煮たりして食べる鍋料理のこと”。【寿司(鮨・鮓)】読み方:すし寿司というのは、”酢飯に魚介類などを組み合わせた日本料理のこと”。寿司における酢飯のことを「シャリ」、酢飯の上に乗っている食材のことを「ネタ」と呼びます。【鯣(鰑・寿留女)】読み方:するめ鯣は”烏賊(イカ)を切り開いて内臓を取り除き、干したりして乾燥させた食品のこと”の意味。鯣は日持ちがすることから「幸せが続く」という意味で縁起物とされています。ですが「するめ」の”する”の部分が、「擦る(博打などでお金がなくなること)」や「掏る(金品を盗み取ること)」を連想させてしまうため、「当たり」に言い換えて「あたりめ」と呼ばれるようになりました。なので「するめ」と「あたりめ」は、どちらも同じものを指しているため覚えておきましょう。【豆打】読み方:ずんだ豆打というのは、”枝豆(または空豆)を茹でてすりつぶして作る餡のこと”。【車厘】読み方:ゼリー車厘というのは、”ゼラチン・果汁・砂糖などを煮込んでから冷やして固めたお菓子のこと”。【善哉】読み方:ぜんざい善哉というのは、”小豆の餡を水でのばして、餅または白玉などを入れたもの”。一般的には”漉し餡(こしあん)を用いたもの”を「汁粉(しるこ)」、”粒餡(つぶあん)を用いたもの”を「善哉(ぜんざい)」と呼ぶことが多いです。【煎茶】読み方:せんちゃ煎茶というのは、”玉露(ぎょくろ)と番茶(ばんちゃ)の間の中級の品質の緑茶のこと”。【煎餅】読み方:せんべい煎餅というのは、”小麦粉・米粉などをこねて、薄く延ばして味付けして焼いたお菓子のこと”。【素麺(索麺)】読み方:そうめん素麺というのは、”小麦粉に塩水を加えて捏(こ)ね、線状に細く伸ばして乾燥させた食品のこと”。※上は茹でた後の素麺の写真素麺は乾燥している状態のものを茹(ゆ)でたり、煮込んだりして食べます。【曹達】読み方:ソーダ曹達というのは、”清涼飲料水の一種。炭酸水に甘味料・香料などを加えた飲み物のこと”。曹達は、「ソーダ水(すい)」の略になります。【蕎麦】読み方:そば蕎麦というのは、”そば粉に小麦粉・水・やまいも・卵白などをこねて、細く線状に切った食品のこと”。蕎麦にはいくつか種類があり、そば粉だけ(10割)を使用したものを「十割(じゅうわり)蕎麦」または「生蕎麦(きそば)」、2割が小麦粉・8割がそば粉を使用したものを「二八(にはち)蕎麦」と呼びます。(小麦粉を1割・そば粉を9割使用したものは「九割(きゅうわり)蕎麦」と呼びます)【素朧】読み方:そぼろ素朧というのは、”挽肉(ひきにく)や魚肉をほぐして味付けし、炒めた食品のこと”。↓タ行~【沢庵】読み方:たくあん沢庵というのは、”干した大根(ダイコン)を糠(ぬか)と塩で漬けたもの”。沢庵は、「沢庵漬け(たくあんづけ)」の略になります。沢庵が黄色いのは、塩漬けすることによって大根に含まれる辛味成分が分解され、黄色い色素を作るからです。【鱈子】読み方:たらこ鱈子というのは、”介党鱈(スケトウダラ)の卵巣を塩漬けした食品のこと”。「スケトウダラ(正式名称)」は、別名で「介宗鱈(助惣鱈):(スケソウダラ)」とも呼ばれています。※上は辛子明太子の写真また”介党鱈の卵巣を塩と唐辛子(トウガラシ)で漬けたもの”を「辛子明太子(からしめんたいこ)」(または略して「明太子(めんたいこ)」)と呼びます。辛子明太子は、博多(福岡県)の名産になります。【担々麺(担担麺)】読み方:タンタンメン担々麺というのは、”辣油(ラーユ)や唐辛子などで辛味を利(き)かせた挽肉(ひきにく)や搾菜(ザーサイ)を、茹でた中華麺の上に乗せた麺料理のこと”。【湯麺】読み方:タンメン湯麺というのは、”炒めた肉や野菜を塩味のスープと煮込み、それを茹でた中華麺の上にかけた麺料理のこと”。【乾酪】読み方:チーズ乾酪というのは、”乳製品の一種で、牛・羊・山羊(やぎ)などの乳を原料とし、乳酸菌と酵素、凝固剤によって固めて、乳清(にゅうせい)を取り除いた食品のこと”。乳清とは、”乳から乳脂肪分やカゼイン(乳に含まれるタンパク質の一種)などを取り除いた水溶液のこと”で、一般的に乳清は「ホエイ(またはホエー)」と呼ばれています。【筑前煮】読み方:ちくぜんに筑前煮というのは、”鶏肉・人参(ニンジン)・蓮根(レンコン)・牛蒡(ゴボウ)・椎茸(シイタケ)などを炒めて、砂糖・醤油(しょうゆ)などで味付けして煮詰めた料理のこと”。【竹輪】読み方:ちくわ竹輪というのは、”魚肉のすり身を、竹などの棒に巻きつけて焼いた食品のこと”。【粽】読み方:ちまき粽というのは、”米や米粉(こめこ)の餅(もち)を、茅(ちがや)・笹(ささ)・葦(あし)などの葉で包んで蒸したもの”。【叉焼(焼豚)】読み方:チャーシュー叉焼というのは、”豚肉を砂糖・酒・香辛料を混ぜた醤油に浸し、焼いた料理のこと”。叉焼は、形が崩れるのを防ぐためにネットやタコ糸で巻かれ、食べるときはネットやタコ糸を外してから薄切りにします。【炒飯】読み方:チャーハン炒飯というのは、”炊いた米を肉・卵・野菜などと一緒に炒めて、味付けした料理のこと”。【猪口齢糖(査古律・貯古齢糖)】読み方:チョコレート猪口齢糖というのは、”カカオ豆を焙煎(ばいせん)・粉砕し、粉砕したもの(カカオマス)を主原料として、砂糖・粉乳などを混ぜて練り固めたお菓子のこと”。略して「チョコ」とも呼ばれています。【縮緬雑魚】読み方:ちりめんじゃこ縮緬雑魚というのは、”鰯(イワシ)の稚魚を塩茹でして乾燥させた食品のこと”。【青椒肉絲】読み方:チンジャオロース青椒肉絲というのは、”豚肉または牛肉とピーマンを細切りにして炒め、オイスターソースなどで味付けした中華料理のこと”。【佃煮】読み方:つくだに佃煮というのは、”小魚・貝・海藻などを、醤油・味醂(みりん)・砂糖などで味を濃く煮詰めた保存食品のこと”。【捏ね】読み方:つくね捏ねというのは、”魚のすり身に卵・小麦粉などを混ぜて捏(こ)ね、団子状や棒状に成形して茹でたり蒸したりした食品のこと”。「つくね」は、”手で捏(こ)ねて作る。手で捏ねて丸くする”の「捏(つく)ねる」から転じたものです。なので生地(きじ)をあらかじめ成形(団子状・棒状など)しているものを「捏ね(つくね)」、生地をスプーンなどで摘み取った(あらかじめ成形していない)ものを「摘入(つみれ)」と呼びます。【摘入(抓入)】読み方:つみれ摘入というのは、”魚のすり身に卵・小麦粉などを混ぜて捏(こ)ね、スプーンなどで少しずつすくい取って茹でたり蒸したりした食品のこと”。「つみれ」は、”摘(つ)み取って入れる”の「摘み入れ」から転じたものです。なので生地をスプーンなどで摘み取った(あらかじめ成形していない)ものを「摘入(つみれ)」、生地をあらかじめ成形(団子状・棒状など)しているものを「捏ね(つくね)」と呼びます。【天津飯】読み方:てんしんはん天津飯というのは、”蟹玉(かにたま)をご飯の上に乗せて、とろみのあるタレをかけた日本発祥の中華料理のこと”。【碾茶】読み方:てんちゃ碾茶というのは、”覆い(遮光)をして育てた茶の木(チャノキ)の若芽を蒸して、揉まずに乾燥させた茶葉。また、その茶葉を用いた緑茶のこと”。※上は抹茶の写真”碾茶を臼(うす)で挽(ひ)いて粉末にしたもの”を「抹茶(まっちゃ)」と呼びます。【天麩羅(天婦羅)】読み方:てんぷら天麩羅というのは、”魚介・野菜・肉などに、水で溶いた小麦粉の衣をつけて油で揚げた料理のこと”。【甜面醤】読み方:テンメンジャン甜面醤というのは、”中華料理の調味料のひとつで、小麦粉を発酵させた甘い味噌のこと”。【豆板醤】読み方:トウバンジャン豆板醤というのは、”中華料理の調味料のひとつで、空豆(ソラマメ)・唐辛子(トウガラシ)などを発酵させた辛い味噌のこと”。【心太(瓊脂・心天)】読み方:ところてん心太というのは、”天草(テングサ)などの紅藻類の煮汁を濾(こ)して型に入れ、ゼリー状に固めた食品のこと”。【屠蘇】読み方:とそ屠蘇というのは、”屠蘇散(とそさん)の略のこと/屠蘇散を浸したみりんや酒のこと”。屠蘇散は、”山椒(さんしょう)・桔梗(ききょう)・白朮(びゃくじゅつ)・肉桂(にっけい)などを混ぜ合わせた漢方薬のこと”を指します。後者の意味の屠蘇は、”邪気を払って1年の健康を祈る”ことを目的として、新年に飲まれます。【濁酒(濁醪)】読み方:どぶろく濁酒というのは、”醪(もろみ)を搾(しぼ)らず、濾(こ)していない白く濁った酒のこと”。醪は、”酒・醤油などの醸造において、原料(米・米麹・水)を混合して発酵させたドロドロの液体のこと”を言います。濁酒は醪をそのまま飲むため、「醪酒(もろみざけ)」とも呼ばれています。(醪をまったく濾していない酒のことを「どぶろく」と呼び、少しでも濾した酒のことを「濁り酒(にごりざけ)」と呼んでいます)濁酒は原料となっている米・米麹(こめこうじ)が濾されずに残っているため、白濁しています。※上は酒粕の写真その白濁した醪(=濁酒)を濾したものが日本酒となり、醪の液体以外の部分(カス)が「酒粕(さけかす)」となります。【薯蕷】読み方:とろろ薯蕷というのは、”長芋(ながいも)や自然薯(じねんじょ)をすって作った食べ物のこと”。「とろろ」は、「とろろ芋(いも)」の略称になります。↓ナ行~【膾(鱠)】読み方:なます膾というのは、”生の魚や野菜などを細かく刻んで酢などで和(あ)えた料理のこと”。【鳴門】読み方:なると鳴門というのは、”魚肉のすり身を原料とし、断面に渦巻き状の模様がある蒲鉾(かまぼこ)の一種のこと”。鳴門は、「鳴門巻き(なるとまき)」の略称になります。【煮凝り】読み方:にこごり※上は煮凝り(後者の意味)の写真煮凝りというのは、”ゼラチン質の魚や肉の煮汁が冷めて固まったもの/ゼラチン質の魚や肉などを煮て、煮汁ごとゼラチン・寒天などで固めた料理のこと”。【煮麺】読み方:にゅうめん煮麺というのは、”茹でた素麺(そうめん)と具を、醤油味(または味噌味)のつゆで煮た料理のこと”。【濃餅汁(能平汁)】読み方:のっぺいじる濃餅汁というのは、”油揚げ・椎茸(しいたけ)・人参(にんじん)・里芋(さといも)・大根などを煮込み、塩・醤油などで味付けをし、片栗粉・葛粉(くずこ)などでとろみを付けた汁のこと”。濃餅汁は新潟県の郷土料理として有名ですが、実は全国各地に伝わる郷土料理になります。↓ハ行~【牛酪】読み方:バター牛酪というのは、”牛乳から分離したクリームを練り固めた、脂肪を主成分とする食品のこと”。【春雨】読み方:はるさめ春雨というのは、”緑豆(リョクトウ)などの澱粉(デンプン)から作った透明な糸状の食品のこと”。【麺麭(麭包)】読み方:パン麺麭というのは、”小麦粉・ライ麦粉などを原料とし、水と酵母などを加えて捏(こ)ね、発酵させて焼き上げた食品のこと”。【棒棒鶏(棒々鶏)】読み方:バンバンジー棒棒鶏というのは、”茹でた鶏肉を細く切ったものに、唐辛子・辣油(ラーゆ)・酢・醤油・胡麻などを混ぜたソースをかけた四川(しせん)料理のこと”。【半片(半平)】読み方:はんぺん半片というのは、”魚肉のすり身に山芋(ヤマノイモ)などを混ぜて茹でた食品のこと”。山芋は、別名で「自然薯(ジネンジョ)」とも呼ばれています。【皮蛋】読み方:ピータン皮蛋というのは、”家鴨(アヒル)の卵を塩・草木灰(そうもくばい)・石灰・泥につけて、発酵させた食品のこと”。草木灰は、”草や木を焼いてできる灰のこと”を指します。中国料理の前菜に用いられ、家鴨の卵の代わりに鶏卵や鶉(ウズラ)の卵が使用されることもあります。黄身は濃緑褐色、白身は褐色半透明の状態で固まっていて、殻を剥いてそのまま食べるだけでなく、食材として中国料理に使用されることも多いです。【麦酒】読み方:ビール麦酒というのは、”麦芽を粉砕して、穀類・水と一緒に加熱して、糖化した汁にホップを加えて苦みや香りをつけ、発酵させたアルコール飲料のこと”。ホップは”アサ科のつる性多年草植物のこと”で、麦酒に入れられるのはそのホップの花にあたる部分になります。※上はホップの花にあたる部分の写真このホップを加えることで、麦酒特有の苦みと香りが生まれます。【鹿尾菜(羊栖菜)】読み方:ひじき鹿尾菜というのは、”ホンダワラ科の海産の褐藻(かっそう)の一種のこと”。褐藻というのは”褐色(茶色に似ている)をしている藻類のこと”を言い、鹿尾菜はやや波の荒い海岸の岩の上に付着しています。鹿尾菜を取る前(つまり生きているとき)は黄褐色で、それを乾燥させたものは黒褐色の見た目をしています。普段から見ている鹿尾菜は、乾燥させたものなので黒褐色の見た目をしています。【乾蒸餅】読み方:ビスケット乾蒸餅というのは、”小麦粉に牛乳・卵・バター・砂糖などを混ぜて焼いたお菓子のこと”。【櫃まぶし(櫃塗し)】読み方:ひつまぶし櫃まぶしというのは、”お櫃(ひつ)などに入れられたご飯の上に、刻んだ鰻(ウナギ)の蒲焼(かばやき)がのせられた料理のこと”。櫃まぶしは、食べる側が茶碗(ちゃわん)などに自分で取り分けるのが基本的なスタイルになります。1杯目はご飯と鰻を取り分けてそのまま食べ、2杯目は薬味をのせて食べ、3杯目は薬味と一緒に出汁(だし)をかけて茶漬けにして食べます。櫃まぶしは、名古屋(愛知県)の郷土料理になります。【冷麦(冷や麦)】読み方:ひやむぎ冷麦というのは、”細打ちにした饂飩(うどん)を茹でて冷水で冷やし、汁(つゆ)をつけて食べる食品のこと”。日本農林規格(JAS)の定めている基準では、基本的には細いものから”素麺(そうめん)<冷麦(ひやむぎ)<饂飩(うどん)”のように区別されています。【冷奴(冷や奴)】読み方:ひややっこ冷奴というのは、”冷やした豆腐を醤油・薬味などで食べる料理のこと”。【鰭酒】読み方:ひれざけ鰭酒というのは、”河豚(フグ)・鯛(タイ)などの鰭を焼いて、それを燗酒(かんざけ)に入れたもの”。【麩(麸)】読み方:ふ麩というのは、”小麦粉から取り出したグルテン(植物性のタンパク質の一種)を主な原料とした食品のこと”。【鱶鰭(魚翅)】読み方:フカヒレ鱶鰭というのは、”鮫(サメ)の鰭を乾燥させた食品のこと”。鱶(ふか)というのは”大形の鮫のこと”で、鱶(大形の鮫)の鰭(ひれ)を使用することから、「鱶鰭(フカヒレ)」と名付けられました。鱶鰭に加工される部位は背ビレ・胸ビレ・尾ビレの3種類で、中華料理の材料に用いられ、高級食材として知られています。【北京ダック(北京烤鴨)】読み方:ペキンダック北京ダックというのは、”下処理した家鴨(アヒル)を丸ごと炉(ろ)で焼いた中華料理のこと”。【回鍋肉】読み方:ホイコーロー回鍋肉というのは、”豚肉をキャベツなどの野菜と炒め、豆板醬(トウバンジャン)などで味付けした四川(しせん)料理のこと”。【焙茶】読み方:ほうじちゃ焙茶というのは、”番茶を焙煎(ばいせん)して作った茶葉を用いた緑茶の一種のこと”。焙茶は紅茶のような見た目をしていますが、緑茶の一種に含まれています。【餺飥】読み方:ほうとう餺飥というのは、”小麦粉を練った平打ち麺と南瓜(カボチャ)などの野菜を味噌(みそ)で煮込んだ料理のこと”。餺飥は、山梨県の郷土料理になります。【牡丹餅】読み方:ぼたもち牡丹餅というのは、”糯米(もちごめ)や粳米(うるちまい)を炊き、軽く搗(つ)いて小さく丸めたものに、餡(あん)・黄粉(きなこ)などをつけたお菓子のこと”。牡丹餅と御萩(おはぎ)は同じ食べ物で、食べる時期によって名称が区別され、それぞれ(牡丹と萩)の花の咲く季節に関係しています。牡丹(ボタン)の花は春頃に咲くため、春の彼岸で食べる場合は「牡丹餅」、萩(ハギ)の花は秋頃に咲くため、秋の彼岸で食べる場合は「御萩」と呼びます。↓マ行~【人造牛酪】読み方:マーガリン人造牛酪というのは、”主に植物性の油脂を原料とし、食塩・乳化剤・着色料などを混ぜて、バターに似せて作った食品のこと”。【麻婆豆腐】読み方:マーボードウフ麻婆豆腐というのは、”豚の挽肉(ひきにく)・豆腐・葱(ネギ)などを、唐辛子・豆板醤(トウバンジャン)・花椒などを入れて炒めた四川料理のこと”。【真珠麿】読み方:マシュマロ真珠麿というのは、”メレンゲ(卵白を泡立てたもの)に、砂糖・ゼラチンなどを混ぜて作ったスポンジ状のお菓子のこと”。【神酒】読み方:みき神酒というのは、”神に供(そな)える酒のこと”。【麺麻(麺媽)】読み方:メンマ麺麻というのは、”筍(タケノコ)を茹で、発酵させてから乾燥させた食品のこと”。一般的には中国産の麻竹(マチク)の筍が用いられます。【最中】読み方:もなか最中というのは、”糯米(もちごめ)の粉を捏(こ)ねて、薄くのばして焼いた皮を2枚合わせ、その中に餡子(あんこ)などを詰めたお菓子のこと”。【醪(諸味)】読み方:もろみ醪というのは、”酒・醤油などの醸造において、原料を混合して発酵させたドロドロの液体のこと”。↓ヤ行~【飲茶】読み方:ヤムチャ飲茶というのは、”点心(てんしん)を食べながら、茶を飲む中国の習慣のこと”。点心は、”中国料理で、食事代わりの軽い食べ物のこと”を指します。【油淋鶏】読み方:ユーリンチー油淋鶏というのは、”鶏肉の唐揚げに、刻んだ長ネギと醤油ベースのタレをかけた中華料理のこと”。【湯葉(湯波・豆腐皮・油皮)】読み方:ゆば湯葉というのは、”豆乳を煮立てて、その表面にできた薄い皮をすくいとって作った食品のこと”。湯葉は蛋白質(たんぱくしつ)が豊富な食品で、生湯葉・干し湯葉があり、吸い物や煮物などに用いられます。「ゆば」の産地としては”京都・日光(栃木県)”が有名で、京都では「湯葉」、日光では「湯波」と表記されます。【柚餅子】読み方:ゆべし※上は柚餅子(前者の意味)の写真※上は柚餅子(後者の意味)の写真柚餅子というのは、”柚子(ユズ)の果実をくり抜いて、その中に糯米(もちごめ)・味噌・醤油・砂糖・胡桃(クルミ)などを混ぜたものを詰め、蒸して乾燥させた食品のこと/米粉・小麦粉・砂糖・味噌などを混ぜ、それに柚子の果汁や皮を加えて捏(こ)ねて蒸したお菓子のこと”。後者の意味のお菓子に胡桃が加えてあるものを「胡桃柚餅子(くるみゆべし)」と呼びます。【羊羹】読み方:ようかん羊羹というのは、”主に小豆(あずき)の餡(あん)を型に入れて、寒天で固めた和菓子のこと”。↓ラ行~【拉麺(老麺)】読み方:ラーメン拉麺というのは、”小麦粉に塩・梘水(かんすい)などを加えて練り、細長く引き伸ばしたものを茹でて、それを醤油味・味噌味などのスープに入れて、叉焼(チャーシュー)・麺麻(メンマ)などの具を上にのせた料理のこと”。梘水は、”食品添加物のひとつで、拉麺を作るときに小麦粉に混ぜる炭酸カリウムなどの溶液のこと”です。梘水を入れることで、柔らかさや弾力性をもたせ、独特の色合いと風味をつけます。【辣油】読み方:ラーゆ辣油というのは、”胡麻(ごま)油などの植物油に、唐辛子を入れて加熱し、油に唐辛子の辛味をつけた調味料のこと”。【老酒】読み方:ラオチュウ老酒というのは、”糯米(もちごめ)などを原料とする中国の醸造酒の総称のこと”。特に、紹興酒(しょうこうしゅ)の古いものを指すことが多いです。【羅火腿】読み方:ラフテー羅火腿というのは、”豚の三枚肉(ばら肉)またはもも肉の角切りを、泡盛・醤油・砂糖などで味付けして煮込んだ料理のこと”。羅火腿は、沖縄県の郷土料理になります。【糖酒】読み方:ラム糖酒というのは、”砂糖黍(サトウキビ)を原料として造られる蒸留酒のこと”。【小酒】読み方:リキュール小酒というのは、”醸造酒・蒸留酒に砂糖やシロップ、香料などを加えて造られる混成酒のこと”。↓ワ行~【葡萄酒】読み方:ワイン葡萄酒というのは、”葡萄(ブドウ)を発酵させて造られるアルコール飲料のこと”。【雲呑(饂飩)】読み方:ワンタン雲呑は”小麦粉を捏(こ)ねて薄くのばした皮に、豚の挽肉(ひきにく)や葱(ネギ)などを包んだ中華料理のこと”。茹でてスープに入れたり、油で揚げたりして食べられます。食べ物・飲み物の難読漢字(一覧表)※1:漢字表記が複数ある場合は、一般的に使われることが多いほうの漢字表記を優先しています(読み方の表記も同様)。例 【甘酒(醴)】 ⇒ 【一般的に使われることが多い漢字表記(比較して一般的に使われることが少ない漢字表記)】漢字読み方備考欄甘酒(醴)あまざけ霰あられ小さいものを「霰」、大きいものを「御欠(おかき)」と呼ぶ酒精アルコール泡盛あわもり沖縄特産の蒸留酒餡子あんこ「漉し餡(こしあん)」と「粒餡(つぶあん)」がある杏仁豆腐あんにんどうふ芋堅干いもけんぴ外郎ういろう名古屋・山口・伊勢(いせ)などの名物烏龍茶うーろんちゃ饂飩うどん(ワンタン)「ワンタン」は”雲呑”と表記されることが多い雲丹ウニ生物として捉えると「海胆・海栗」、食品として捉えると「雲丹」と表記される御欠おかき小さいものを「霰(あられ)」、大きいものを「御欠」と呼ぶ御菜おかず雪花菜(御殻)おから大豆(ダイズ)が原料粔籹おこし御強おこわ御強は、「赤飯(せきはん)」の別名御節おせち正月・節句などに作る料理(一般的には正月)御田おでん御萩おはぎ春の彼岸で食べるのを「牡丹餅(ぼたもち)」、秋の彼岸で食べるのを「御萩」と呼ぶ混合酒カクテル卵糖(家主貞良・加須底羅)カステラ数の子(鯑)かずのこ「鰊(ニシン)」の卵巣が原料鰹節かつおぶし蟹玉かにたま蒲鉾かまぼこ粥かゆ唐墨(鱲子・鰡子)からすみ「鯔(ボラ)」の卵巣が原料。長崎県の名産浮石糖(泡糖)カルメラ浮石糖の別名は「カルメ焼き」咖喱カレー燗酒かんざけ干瓢(乾瓢)かんぴょう「夕顔(ユウガオ)」が原料雁擬(雁擬き)がんもどき棊子麺(碁子麺)きしめん名古屋(愛知県)の名産黄粉きなこ「大豆(ダイズ)」が原料沈菜キムチ餃子ぎょうざ切蒲英(切短穂)きりたんぽ秋田県の郷土料理金鍔きんつば「金鍔焼き(きんつばやき)」の略称金団きんとん月餅げっぺい中国の焼き菓子巻繊汁けんちんじる珈琲コーヒー海鼠腸このわた「海鼠(ナマコ)」の腸や内臓が原料米粉こめこ(ビーフン)「こめこ」と「ビーフン」で意味が異なる蒟蒻(菎蒻)こんにゃく昆布こんぶ金平糖こんぺいとう搾菜ザーサイ白湯(素湯)さゆ炸醤麺ジャージャーメン三鞭酒シャンパン「ドン・ペリニヨン」(略してドンペリ)が有名焼売しゅうまい紹興酒しょうこうしゅ小籠包しょうろんぽう塩汁鍋しょっつるなべ秋田県の郷土料理汁粉しるこ漉し餡を用いたものを「汁粉」、粒餡を用いたものを「善哉(ぜんざい)」と呼ぶ洋酒ジン成吉思汗ジンギスカン北海道の郷土料理真薯(糝薯・真蒸・真丈)しんじょ水団すいとん鋤焼すきやき寿司(鮨・鮓)すし酢飯を「シャリ」、酢飯に乗せる食材を「ネタ」と呼ぶ鯣(鰑・寿留女)するめ鯣の別名は「あたりめ」豆打ずんだ「枝豆(えだまめ)」が原料車厘ゼリー善哉ぜんざい漉し餡を用いたものを「汁粉(しるこ)」、粒餡を用いたものを「善哉」と呼ぶ煎茶せんちゃ煎餅せんべい素麺(索麺)そうめん基本的には細いものから「素麺<冷麦(ひやむぎ)<饂飩(うどん)」と区別される曹達ソーダ曹達は、「ソーダ水(すい)」の略称蕎麦そば素朧そぼろ沢庵たくあん「大根(ダイコン)」が原料。「沢庵漬け(たくあんづけ)」の略称鱈子たらこ「介党鱈(スケトウダラ)」の卵巣が原料。介党鱈の別名は「介宗鱈(スケソウダラ)」担々麺(担担麺)タンタンメン湯麺タンメン乾酪チーズ筑前煮ちくぜんに竹輪ちくわ粽ちまき叉焼(焼豚)チャーシュー炒飯チャーハン猪口齢糖(査古律・貯古齢糖)チョコレート縮緬雑魚ちりめんじゃこ青椒肉絲チンジャオロース佃煮つくだに捏ねつくねあらかじめ成形しているものを「捏ね」、あらかじて成形していないものを「摘入(つみれ)」と呼ぶ摘入(抓入)つみれあらかじめ成形しているものを「捏ね(つくね)」、あらかじて成形していないものを「摘入」と呼ぶ天津飯てんしんはん碾茶てんちゃ碾茶を臼(うす)で挽いたものを「抹茶(まっちゃ)」と呼ぶ天麩羅(天婦羅)てんぷら甜面醤テンメンジャン小麦粉が原料豆板醤トウバンジャン「空豆(ソラマメ)」と「唐辛子(トウガラシ)」が原料心太(瓊脂・心天)ところてん「天草(テングサ)」などの紅藻類が原料屠蘇とそ濁酒(濁醪)どぶろく濁酒の別名は「醪酒(もろみざけ)」薯蕷とろろ薯蕷は、「とろろ芋(いも)」の略称膾(鱠)なます鳴門なると鳴門は、「鳴門巻き(なるとまき)」の略称煮凝りにこごり煮麺にゅうめん濃餅汁(能平汁)のっぺいじる新潟県の郷土料理として有名ですが、実は全国各地に伝わる郷土料理牛酪バター春雨はるさめ「緑豆(リョクトウ)」などのデンプンが原料麺麭(麭包)パン棒棒鶏(棒々鶏)バンバンジー半片(半平)はんぺん皮蛋ピータン「家鴨(アヒル)」の卵が原料麦酒ビール鹿尾菜(羊栖菜)ひじき乾蒸餅ビスケット櫃まぶし(櫃塗し)ひつまぶし名古屋(愛知県)の郷土料理冷麦(冷や麦)ひやむぎ基本的には細いものから「素麺(そうめん)<冷麦<饂飩(うどん)」と区別される冷奴(冷や奴)ひややっこ鰭酒ひれざけ麩(麸)ふ小麦粉から取り出したグルテン(植物性のタンパク質の一種)が原料鱶鰭(魚翅)フカヒレ「鮫(サメ)」の鰭が原料北京ダック(北京烤鴨)ペキンダック回鍋肉ホイコーロー焙茶ほうじちゃ餺飥ほうとう山梨県の郷土料理牡丹餅ぼたもち春の彼岸で食べるのを「牡丹餅」、秋の彼岸で食べるのを「御萩(おはぎ)」と呼ぶ人造牛酪マーガリン麻婆豆腐マーボードウフ真珠麿マシュマロ神酒みき麺麻(麺媽)メンマ「筍(タケノコ)」が原料最中もなか醪(諸味)もろみ飲茶ヤムチャ油淋鶏ユーリンチー湯葉(湯波・豆腐皮・油皮)ゆば京都・日光(栃木県)の名産。京都では「湯葉」、日光では「湯波」と表記される柚餅子ゆべし羊羹ようかん拉麺(老麺)ラーメン辣油ラーゆ老酒ラオチュウ羅火腿ラフテー沖縄県の郷土料理糖酒ラム小酒リキュール葡萄酒ワイン雲呑(饂飩)ワンタン饂飩は「うどん」と読むことが多い項目1項目2項目3)★ -->関連ページ<難読漢字の一覧>⇒【一文字】難読漢字の一覧!⇒【野菜・果物・茸】難読漢字の一覧!⇒【魚・貝・海藻】難読漢字の一覧!⇒【動物】難読漢字の一覧!⇒【鳥】難読漢字の一覧!⇒【花・植物】難読漢字の一覧!⇒【虫】難読漢字の一覧!⇒【道具・身近なモノ】難読漢字の一覧!<読み間違えやすい漢字の一覧>⇒読み間違えやすい漢字一覧!⇒慣用読み(百姓読み)の一覧!<難読漢字の一覧(偏)>⇒【魚偏】難読漢字の一覧!⇒【虫偏】難読漢字の一覧!⇒【木偏】難読漢字の一覧!⇒【金偏】難読漢字の一覧!