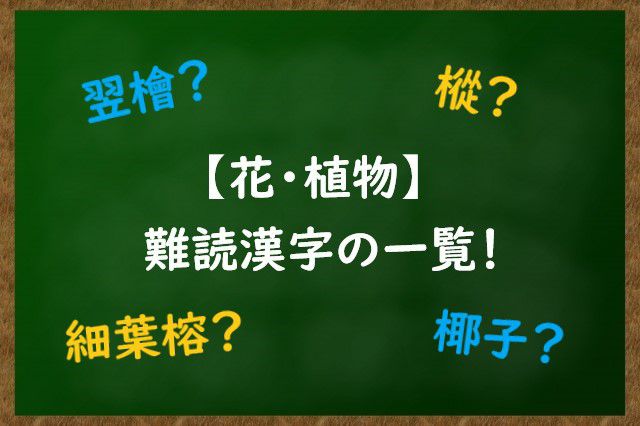このページでは花・植物の難読漢字について簡単に一覧にしてまとめています。(花・植物の難読漢字を新しく見つけ次第、追記していきます)どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次↓花・植物の難読漢字の読み方や説明、写真などを載せています◆【ア行~】◇【カ行~】◆【サ行~】◇【タ行~】◆【ナ行~】◇【ハ行~】◆【マ行~】◇【ヤ行~】◆【ラ行~】◇【ワ行~】↓花・植物の難読漢字とその読み方だけをザっと見たい方はこちら(同ページのリンクへ移動します)●花・植物の難読漢字(一覧表)↓関連ページはこちら(同ページのリンクへ移動します)★関連ページ花・植物の難読漢字※1:漢字表記が複数ある場合は、一般的に使われることが多いほうの漢字表記を優先しています(読み方の表記も同様)。例 【薊(莇)】 ⇒ 【一般的に使われることが多い漢字表記(比較して一般的に使われることが少ない漢字表記)】※2:読み方の横に「(一種)」「(総称)」の表記があるものは、以下のような意味になります。例 【シクラメン(一種)】 ⇒ 【(狭義では)ツツジ目サクラソウ科シクラメン属に分類される多年草の一種】【(広義では)ツツジ目サクラソウ科シクラメン属に分類される植物の総称】の両方を意味例 【アオイ(総称)】 ⇒ 【アオイ目アオイ科に分類される植物の総称】を意味(アオイという名称の特定の植物が存在するわけではない)※3:標準和名=【日本での正式な名称のこと】⇒学名と標準和名の違いとは?↓ア行~【葵】読み方:アオイ(総称)※上は立葵(タチアオイ)の写真葵というのは、”アオイ目アオイ科に分類される植物の総称”。【金合歓】読み方:アカシア※上は銀葉金合歓(ギンヨウアカシア)の写真金合歓というのは、”マメ目マメ科アカシア属に分類される常緑高木の総称/偽金合歓(ニセアカシア)の別名”。※上は御辞儀草(オジギソウ)の写真金合歓(マメ科アカシア属の常緑高木の総称)は別名で「ミモザ」(日本では銀葉金合歓を「ミモザ」と呼ぶことが多い)と呼ばれることも多いですが、本来ミモザは”「オジギソウ属(Mimosa)」に分類される植物の総称”を指しています。オジギソウ属の一種である「御辞儀草(オジギソウ)」の学名を「Mimosa pudica(ミモザプディカ)」といい、「ミモザ」は御辞儀草の別名としても用いられます。※上は偽金合歓(ニセアカシア)の写真また「アカシア蜂蜜(はちみつ)」という蜂蜜がありますが、これは「偽金合歓(ニセアカシア)」(マメ目マメ科ハリエンジュ属に分類される落葉高木の一種)の蜜から採った蜂蜜になります。標準和名は「針槐(ハリエンジュ)」で、その別名として「偽金合歓(ニセアカシア)」と呼ばれています。【朝顔(牽牛花・蕣)】読み方:アサガオ朝顔というのは、”ナス目ヒルガオ科サツマイモ属に分類される一年草の一種”。【薊(莇)】読み方:アザミ(総称)※上は野薊(ノアザミ)の写真薊というのは、”キク目キク科アザミ属に分類される植物の総称”。棘(トゲ)が多いことから、別名で「棘草(トゲクサ)」とも呼ばれています。【葦】読み方:アシ(ヨシ)葦というのは、”イネ目イネ科ヨシ属に分類される多年草の一種”。「アシ」は、「ヨシ」(標準和名)の別名になります。※上は茅葺き屋根の写真葦の茎を利用したものには「簾(すだれ)」「葦簀(よしず)」(竹なども用いられる)や、「茅葺き屋根(かやぶきやね)」などがあります。”屋根をふく材料とする草のこと”を「茅(かや)」と呼び、茅葺き屋根には他にも薄(ススキ)などが用いられます。【紫陽花】読み方:アジサイ紫陽花というのは、”ミズキ目アジサイ科アジサイ属に分類される落葉低木の一種”。紫陽花は土壌環境(酸性・アルカリ性)によって花色が変化(酸性だと青色、アルカリ性だとピンク色)することから、別名で「七変化(しちへんげ)」「八仙花(はっせんか)」とも呼ばれています。【翌檜(翌桧)】読み方:アスナロ翌檜というのは、”マツ目ヒノキ科アスナロ属に分類される常緑樹の一種”。【馬酔木】読み方:アセビ馬酔木というのは、”ツツジ目ツツジ科アセビ属に分類される常緑低木の一種”。葉には毒があり、馬が葉を食べると、毒で酔ったようにふらついてしまうことから、「馬酔木」という漢字が当てられています。【甘茶蔓】読み方:アマチャヅル甘茶蔓というのは、”スミレ目ウリ科アマチャヅル属に分類される多年草の一種”。葉を噛むと甘味があり、健康茶や薬用として用いられます。【菖蒲】読み方:アヤメ、ショウブ※上は菖蒲(アヤメ)の写真※上は菖蒲(ショウブ)の写真※上は花菖蒲(ハナショウブ)の写真「アヤメ」と読むと”キジカクシ目アヤメ科アヤメ属に分類される多年草の一種”。「ショウブ」と読むと”ショウブ目ショウブ科ショウブ属に分類される多年草の一種/花菖蒲(ハナショウブ:標準和名)の別名”。花菖蒲は、”キジカクシ目アヤメ科アヤメ属に分類される多年草の一種”を指します。※上が菖蒲(ショウブ)の葉の写真「ショウブ」はその葉や根を入れて沸かす風呂である「菖蒲湯(しょうぶゆ)」が有名で、5月5日の端午(たんご)の節句の日に健康を願って行われる年中行事です。菖蒲祭り(しょうぶまつり)の「ショウブ」は、「花菖蒲(ハナショウブ)」のことを指します。【蘆薈】読み方:アロエ(総称)※上は木立蘆薈(キダチアロエ)の写真※上はアロエベラの写真蘆薈というのは、”キジカクシ目ススキノキ科アロエ属に分類される植物の総称”。葉はギザギザがついていて多肉で、葉の表面を取り除いた葉肉の部分を食用とし、一般的に食用として流通している蘆薈は「木立蘆薈(キダチアロエ)」と「アロエベラ」になります。【粟】読み方:アワ粟というのは、”イネ目イネ科エノコログサ属に分類される多年草の一種”。五穀(ごこく)のひとつで、五穀とは一般的に「米・麦・粟(あわ)・黍(きび)・豆」の5種類の穀物を指します。【藺】読み方:イ藺というのは、”イネ目イグサ科イグサ属に分類される多年草の一種”。「藺(イ)」(標準和名)は、別名で「藺草(イグサ)」とも呼ばれています。※上は茣蓙(ござ)の写真藺の茎は、畳(たたみ)や茣蓙(ござ)の材料として用いられます。【虎杖】読み方:イタドリ虎杖というのは、”ナデシコ目タデ科ソバカズラ属に分類される多年草の一種”。擦り傷などの患部に若葉を揉(も)んでつけると痛みを和らげるのに役立つことから、「痛み取り」から変化して名付けられたとされています。【公孫樹(銀杏)】読み方:イチョウ公孫樹というのは、”イチョウ目イチョウ科イチョウ属に分類される落葉高木の一種”。一般的には銀杏は「ぎんなん」と読むことが多く、銀杏(ぎんなん)は”イチョウの実のこと”を指します。【猪子槌(牛膝)】読み方:イノコヅチ猪子槌というのは、”ナデシコ目ヒユ科イノコヅチ属に分類される多年草の一種”。【鬱金】読み方:ウコン※上は鬱金の地下茎の写真鬱金というのは、”ショウガ目ショウガ科ウコン属に分類される多年草の一種。また、その地下茎(ちかけい)のこと”。地下茎は肥大していて黄色っぽく、鬱金の地下茎を乾燥させて粉末にしたものを「ターメリック」と呼び、染料・香料・カレー粉などに用いられます。【空木(卯木)】読み方:ウツギ空木というのは、”ミズキ目アジサイ科ウツギ属に分類される落葉低木の一種”。幹(みき)の中が空洞であることから「空木」、また卯月(旧暦の4月)頃に花を咲かせることから「卯木」と表記されます。【独活(土当帰)】読み方:ウド独活というのは、”セリ目ウコギ科タラノキ属に分類される多年草の一種”。若い葉や茎は香りが強く、山菜として知られています。【漆】読み方:ウルシ漆というのは、”ムクロジ目ウルシ科ウルシ属に分類される落葉高木の一種”。漆の木に傷をつけ、その傷部分から分泌する樹液のことを「漆(うるし)」と呼ぶことも多く、採取した樹液から木屑(きくず)などを濾過(ろか)したものを「生漆(きうるし)」と言います。漆の木の樹液から精製された漆を器物の表面に塗ったり、模様を描く技術のことを「漆工芸(うるしこうげい)」「漆芸(しつげい)」、その漆塗りの器物のことを「漆器(しっき)」と呼びます。※上は漆器の写真漆(樹液)は固まると水を弾き、さらに防腐性・抗菌性も高いため、重宝されています。また完全に乾いていない漆(樹液)に触れたり、漆の木や葉に触れることでかぶれることがある(主成分であるウルシオールによるもの)ため注意が必要です。【金雀枝】読み方:エニシダ金雀枝というのは、”マメ目マメ科エニシダ属に分類される落葉低木の一種”。【狗尾草】読み方:エノコログサ狗尾草というのは、”イネ目イネ科エノコログサ属に分類される一年草の一種”。花穂(かすい)を猫の前で振ると猫がじゃれつくことから、別名で「猫じゃらし」とも呼ばれています。【槐】読み方:エンジュ槐というのは、”マメ目マメ科エンジュ属に分類される落葉高木の一種”。【大葉子(車前草)】読み方:オオバコ大葉子というのは、”シソ目オオバコ科オオバコ属に分類される多年草の一種”。【荻】読み方:オギ荻というのは、”イネ目イネ科ススキ属に分類される多年草の一種”。「荻(オギ)」という字は、「萩(ハギ)」という字によく似ているため注意が必要です。【朮】読み方:オケラ朮というのは、”キク目キク科オケラ属に分類される多年草の一種”。【御辞儀草(含羞草)】読み方:オジギソウ御辞儀草というのは、”マメ目マメ科オジギソウ属に分類される多年草の一種”。御辞儀草(標準和名)は、別名で「眠り草(ネムリグサ)」「ミモザ」とも呼ばれています。御辞儀草は別名で「ミモザ」と呼ばれますが、一般的には金合歓(アカシア)(マメ科アカシア属の常緑高木の総称)の別名として「ミモザ」と呼ぶことが多いです。ただ本来はミモザというと”「オジギソウ属(Mimosa)」に分類される植物の総称”を指し、オジギソウ属の一種である「御辞儀草(オジギソウ)」の学名を「Mimosa pudica(ミモザプディカ)」といい、御辞儀草の別名としても用いられます。葉に軽く触ると、葉が閉じていって垂れ下がる性質があり、その様子がお辞儀をしているように見えることから名付けられました。【白粉花】読み方:オシロイバナ白粉花というのは、”ナデシコ目オシロイバナ科オシロイバナ属に分類される多年草の一種”。白粉花の黒い種子を割ると、中から白い粉が出てきて、それを肌につけると白粉(おしろい)を塗ったように白くなることから名付けられました。【苧環】読み方:オダマキ(総称)※上は深山苧環(ミヤマオダマキ)の写真苧環というのは、”キンポウゲ目キンポウゲ科オダマキ属に分類される植物の総称”。【弟切草】読み方:オトギリソウ弟切草というのは、”キントラノオ目オトギリソウ科オトギリソウ属に分類される多年草の一種”。【男郎花】読み方:オトコエシ男郎花というのは、”マツムシソウ目オミナエシ科オミナエシ属に分類される多年草の一種”。(女郎花(オミナエシ)に対比させる形で)女郎花に見た目が似ていて、全体的に太くて毛深いことから「男郎花(オトコエシ)」と名付けられました。男郎花は白い花、女郎花は黄色い花を咲かせます。【巻耳】読み方:オナモミ巻耳というのは、”キク目キク科オナモミ属に分類される一年草の一種”。果実全体に棘(トゲ)があり、草むらに入ると衣類などにくっつくことから、別名で「ひっつき虫」「くっつき虫」とも呼ばれています。「ひっつき虫」と呼ばれる植物は巻耳以外にも多く存在し、どれも子孫(種子)を広範囲に運んでもらうために、種子や果実が動物の毛や衣類などにくっつきやすくなっています。【女郎花】読み方:オミナエシ女郎花というのは、”マツムシソウ目オミナエシ科オミナエシ属に分類される多年草の一種”。女郎花は秋の七草のひとつとして知られ、別名で「敗醤(はいしょう)」とも呼ばれています。女郎花を花瓶に挿してしばらくすると、腐った醤油(しょうゆ)のような臭いがすることから別名(敗醤)が名付けられています。(男郎花(オトコエシ)に対比させる形で)男郎花に見た目が似ていて、全体的に毛が細くて可憐な見た目から「女郎花(オミナエシ)」と名付けられました。女郎花は黄色い花、男郎花は白い花を咲かせます。【沢瀉(面高)】読み方:オモダカ沢瀉というのは、”オモダカ目オモダカ科オモダカ属に分類される多年草の一種”。【万年青】読み方:オモト万年青というのは、”キジカクシ目キジカクシ科オモト属に分類される多年草の一種”。【阿列布(阿利布)】読み方:オリーブ阿列布というのは、”シソ目モクセイ科オリーブ属に分類される常緑高木の一種”。果実は油分を多く含んでいるため、果実から油(オリーブオイル)を採ったり、食用としても用いられます。↓カ行~【海棠】読み方:カイドウ海棠というのは、”花海棠(ハナカイドウ:標準和名)の別名”。花海棠は、”バラ目バラ科リンゴ属に分類される落葉高木の一種”を指します。【楓(槭)】読み方:カエデ(総称)※上は伊呂波紅葉(イロハモミジ)(ムクロジ科カエデ属)の写真楓というのは、”ムクロジ目ムクロジ科カエデ属に分類される落葉高木の総称”。葉の形が蛙(カエル)の手に似ていることから「蛙手(カエルデ)」となり、それが略され「カエデ」となりました。※上はカナダの国旗の画像※上は砂糖楓の葉の写真楓を英語にすると「maple(メープル)」で、メープルシロップで有名なカナダの国旗にも砂糖楓(サトウカエデ)(ムクロジ科カエデ属に分類される落葉高木の一種)の葉がデザインされています。メープルシロップの原料は砂糖楓の樹液で、その樹液を煮詰めて水分を飛ばすとメープルシロップになります。【加加阿】読み方:カカオ加加阿というのは、”アオイ目アオイ科カカオ属に分類される常緑高木の一種”。※上はカカオの実(カカオポッド)の断面の写真※上はカカオ豆(種子)の写真加加阿の実(果実)を「カカオポッド」、白い果肉部分を「カカオパルプ」、白い果肉の中にある種子のことを「カカオ豆」と呼びます。上記の中で主にカカオ豆がチョコレートの原料として用いられます。【燕子花(杜若)】読み方:カキツバタ燕子花というのは、”キジカクシ目アヤメ科アヤメ属に分類される多年草の一種”。【樫】読み方:カシ(総称)※上は白樫(シラカシ)の写真樫というのは、”ブナ目ブナ科に分類される常緑高木の一群の総称”。【細葉榕(榕樹)】読み方:ガジュマル細葉榕というのは、”バラ目クワ科イチジク属に分類される常緑高木の一種”。細葉榕は観葉植物として人気で、沖縄県では細葉榕の大木には「キジムナー」と呼ばれる精霊が宿っていると伝えられています。【霞草】読み方:カスミソウ霞草というのは、”ナデシコ目ナデシコ科カスミソウ属に分類される多年草の一種”。【葛】読み方:カズラ、クズ※上は葛(クズ)の写真「カズラ」と読むと”蔓草(つるくさ)の総称のこと”。蔓草というのは、”茎(くき)が蔓になる草の総称”を指します。「クズ」と読むと”マメ目マメ科クズ属に分類される多年草の一種”。「クズ」は、秋の七草のひとつとして知られています。※上は葛粉の写真葛(クズ)は山野に多く自生していて、根からはデンプンを取ることができ、このデンプンのことを「葛粉(くずこ)」と言います。※上は葛餅の写真※上は葛湯の写真葛粉は葛餅(くずもち)、葛湯(くずゆ)などに用いられます。【桂】読み方:カツラ桂というのは、”ユキノシタ目カツラ科カツラ属に分類される落葉高木の一種”。【蒲】読み方:ガマ蒲というのは、”イネ目ガマ科ガマ属に分類される多年草の一種”。【枳殻(枸橘)】読み方:カラタチ枳殻というのは、”ムクロジ目ミカン科カラタチ属に分類される落葉低木の一種”。【唐松(落葉松)】読み方:カラマツ唐松というのは、”マツ目マツ科カラマツ属に分類される落葉高木の一種”。【雁草(雁金草)】読み方:カリガネソウ雁草というのは、”シソ目シソ科カリネソウ属に分類される多年草の一種”。【雁皮】読み方:ガンピ雁皮というのは、”フトモモ目ジンチョウゲ科ガンピ属に分類される落葉低木の一種”。樹皮の繊維がきめ細かく、和紙の原料として用いられます。【桔梗】読み方:キキョウ桔梗というのは、”キク目キキョウ科キキョウ属に分類される多年草の一種”。桔梗は、秋の七草のひとつとして知られています。【菊】読み方:キク菊というのは、”キク目キク科キク属に分類される多年草の一種”。【羊蹄】読み方:ギシギシ羊蹄というのは、”ナデシコ目タデ科スイバ属に分類される多年草の一種”。【黍】読み方:キビ黍というのは、”イネ目イネ科キビ属に分類される一年草の一種”。五穀(ごこく)のひとつで、五穀とは一般的に「米・麦・粟(あわ)・黍(きび)・豆」の5種類の穀物を指します。【擬宝珠】読み方:ギボウシ(総称)※上は大葉擬宝珠(オオバギボウシ)の写真擬宝珠というのは、”キジカクシ目キジカクシ科ギボウシ属に分類される多年草の総称”。【夾竹桃】読み方:キョウチクトウ夾竹桃というのは、”リンドウ目キョウチクトウ科キョウチクトウ属に分類される落葉低木の一種”。樹木全体に強力な毒成分(主にオレアンドリンなど)が含まれており、夾竹桃を植えた周りの土壌や、夾竹桃を燃やして出た煙にも毒性があるため注意が必要です。車の排気ガスや大気汚染、暑さや乾燥などにも強いため、緑化樹として公園や道路脇(わき)などに植えられています。【桐】読み方:キリ桐というのは、”シソ目キリ科キリ属に分類される落葉高木の一種”。【金盞花】読み方:キンセンカ金盞花というのは、”キク目キク科キンセンカ属に分類される一年草の一種”。【金鳳花】読み方:キンポウゲ金鳳花というのは、”馬の足形(ウマノアシガタ:標準和名)の別名”。馬の足形は、”キンポウゲ目キンポウゲ科キンポウゲ属に分類される多年草の一種”を指します。【金木犀】読み方:キンモクセイ金木犀というのは、”シソ目モクセイ科モクセイ属に分類される常緑低木の一種”。金木犀は、沈丁花(ジンチョウゲ)・梔子(クチナシ)と合わせて、日本の「三大芳香木」のひとつに数えられています。【枸杞】読み方:クコ枸杞というのは、”ナス目ナス科クコ属に分類される落葉低木の一種”。※上は乾燥させた枸杞の実(果実)の写真※上は杏仁豆腐の写真赤く熟した枸杞の実は、生食(なましょく)や乾燥させてから利用されます。一般的には乾燥させてから利用されることが多く、薬膳として杏仁豆腐(あんにんどうふ)などにトッピングされます。【楠(樟)】読み方:クスノキ楠というのは、”クスノキ目クスノキ科ニッケイ属に分類される常緑高木の一種”。楠(樟)の葉・枝などのチップを水蒸気蒸留することで「樟脳(しょうのう)」と呼ばれる白い結晶を精製することができます。英語では「カンフル(camphor)」(または「カンファー」)と呼ばれ、主に防虫剤、他にも防臭・医薬品などに用いられます。ちなみに”ダメになりかけた物事を蘇らせる効果のある措置のこと”の意味で使われる「カンフル剤」のカンフルは、樟脳が由来になります。これは昔に樟脳が強心剤(衰弱した心臓の働きを高めるための薬剤)としても使われていたことからきています。【梔子(梔・巵子・山梔子)】読み方:クチナシ梔子というのは、”リンドウ目アカネ科クチナシ属に分類される常緑低木の一種”。梔子は、沈丁花(ジンチョウゲ)・金木犀(キンモクセイ)と合わせて、日本の「三大芳香木」のひとつに数えられています。【椚(櫟・橡・櫪)】読み方:クヌギ椚というのは、”ブナ目ブナ科コナラ属に分類される落葉高木の一種”。【桑】読み方:クワ(総称)※上は山桑(ヤマグワ)の写真桑というのは、”バラ目クワ科クワ属に分類される植物の総称”。※上は蚕(カイコ)の写真桑の葉は蚕(カイコ)の餌(えさ)として利用され、蚕の吐いた糸(繊維)が絹糸の原料となることから、養蚕(ようさん)などのために栽培されます。【芥子(罌粟)】読み方:ケシ芥子というのは、”キンポウゲ目ケシ科ケシ属に分類される一年草の一種”。未熟な果実の乳液が阿片(アヘン)・モルヒネなどの麻薬の原料となることから、一般の栽培は法律で禁止されています。【欅(槻)】読み方:ケヤキ欅というのは、”バラ目ニレ科ケヤキ属に分類される落葉高木の一種”。【紫雲英】読み方:ゲンゲ紫雲英というのは、”マメ目マメ科ゲンゲ属に分類される多年草の一種”。紫雲英(標準和名)は、別名で「蓮華草(レンゲソウ)」とも呼ばれています。【楮】読み方:コウゾ楮というのは、”バラ目クワ科コウゾ属に分類される落葉低木の一種”。楮は、和紙の原料として栽培されています。【河骨(川骨)】読み方:コウホネ河骨というのは、”スイレン目スイレン科コウホネ属に分類される多年草の一種”。泥の中に伸びる白い地下茎が動物の骨のように見えることから名付けられました。【御形】読み方:ゴギョウ御形というのは、”母子草(ハハコグサ:標準和名)の別名”。母子草は、”キク目キク科ハハコグサ属に分類される多年草の一種”を指します。若い茎・葉を食用とし、春の七草のひとつとして知られています。【秋桜】読み方:コスモス(一種)秋桜というのは、”大春車菊(オオハルシャギク:標準和名)の別名/キク目キク科コスモス属に分類される植物の総称”。大春車菊は、”キク目キク科コスモス属に分類される一年草の一種”を指します。【胡蝶蘭】読み方:コチョウラン胡蝶蘭というのは、”キジカクシ目ラン科コチョウラン属に分類される多年草の一種”。【小楢】読み方:コナラ小楢というのは、”ブナ目ブナ科コナラ属に分類される落葉高木の一種”。【辛夷】読み方:コブシ※上は辛夷の花と蕾(つぼみ)の写真※上は辛夷の果実の写真辛夷というのは、”モクレン目モクレン科モクレン属に分類される落葉高木の一種”。名称の由来として、蕾(つぼみ)の形が握りこぶしに似ていることから名付けられた説や、辛夷の果実がでこぼこしていて握りこぶしに似ていることから名付けられた説があります。↓サ行~【榊】読み方:サカキ榊というのは、”ツツジ目モッコク科サカキ属に分類される常緑小高木の一種”。榊は日本では古くから神事に用いられ、神棚や祭壇に供えられています。【山茶花(茶梅)】読み方:サザンカ山茶花というのは、”ツツジ目ツバキ科ツバキ属に分類される常緑小高木の一種”。【番紅花(咱夫藍)】読み方:サフラン番紅花というのは、”キジカクシ目アヤメ科クロッカス属に分類される多年草の一種。また、その雌蕊(めしべ)を乾燥させた香辛料のこと”。花の中央にある黄色いのが雄(お)しべで、赤色のものが香辛料などに用いられる雌(め)しべになります。【仙人掌(覇王樹)】読み方:サボテン(総称)※上は金鯱(キンシャチ)の写真仙人掌というのは、”ナデシコ目サボテン科に分類される植物の総称”。仙人掌は英語で「カクタス(cactus)」といい、棘(トゲ)は葉や茎が変化したものになります。【沙羅双樹(娑羅双樹)】読み方:サラソウジュ(シャラソウジュ)沙羅双樹というのは、”アオイ目フタバガキ科サラノキ属に分類される常緑高木の一種”。「サラソウジュ」(標準和名)は、別名で「シャラソウジュ」とも呼ばれています。【百日紅(猿滑・紫薇)】読み方:サルスベリ百日紅というのは、”フトモモ目ミソハギ科サルスベリ属に分類される落葉高木の一種”。樹皮がツルツルしていて、猿ですら滑り落ちてしまいそうなことから名付けられています。【椹(花柏・弱檜)】読み方:サワラ椹というのは、”ヒノキ目ヒノキ科ヒノキ属に分類される常緑高木の一種”。【山椒】読み方:サンショウ山椒というのは、”ムクロジ目ミカン科サンショウ属に分類される落葉低木の一種”。山椒は、葉・花・実(果実)・樹皮に至るまであらゆる部位が食用になる植物で、その独特な香りから香辛料などに用いられます。【紫苑】読み方:シオン紫苑というのは、”キク目キク科シオン属に分類される多年草の一種”。【樒(梻)】読み方:シキミ※上は樒の果実の写真樒というのは、”アウストロバイレヤ目マツブサ科シキミ属に分類される常緑小高木の一種”。※上は八角(はっかく)の写真全体的にアニサチンなどの毒を含み、特に果実に猛毒があり、樒の果実は中華料理の香辛料として用いられる「八角(はっかく)」(英語ではスターアニス)によく似ているため注意が必要です。【篝火花】読み方:シクラメン(一種)篝火花というのは、”ツツジ目サクラソウ科シクラメン属に分類される多年草の一種/ツツジ目サクラソウ科シクラメン属に分類される植物の総称”。【羊歯(歯朶)】読み方:シダ※上は裏白(ウラジロ)の写真羊歯というのは、”裏白(ウラジロ:標準和名)の別名/シダ植物の総称”。裏白は、”シダ綱ウラジロ科ウラジロ属に分類される多年草の一種”を指します。【枝垂桜】読み方:シダレザクラ枝垂桜というのは、”バラ目バラ科サクラ属に分類される落葉高木の一種”。【枝垂柳】読み方:シダレヤナギ枝垂柳というのは、”キントラノオ目ヤナギ科ヤナギ属に分類される落葉高木の一種”。【射干(著莪・胡蝶花)】読み方:シャガ射干というのは、”キジカクシ目アヤメ科アヤメ属に分類される多年草の一種”。【石楠花(石南花)】読み方:シャクナゲ(総称)※上は本石楠花(ホンシャクナゲ)の写真石楠花というのは、”ツツジ目ツツジ科ツツジ属シャクナゲ亜属に分類される常緑低木の総称”。【芍薬】読み方:シャクヤク芍薬というのは、”ユキノシタ目ボタン科ボタン属に分類される多年草の一種”。美女を形容する言葉として「立てば芍薬(シャクヤク)、座れば牡丹(ボタン)、歩く姿は百合(ユリ)の花」がありますが、これは元々は漢方の生薬(しょうやく)の使い方を示す言葉です。イラ立ちやすい女性は芍薬の根、座ってばかりいるような女性は牡丹の根の皮、フラフラ歩く女性は百合の根を用いると良い、という意味になります。【茉莉花(耶悉茗・素馨)】読み方:ジャスミン(総称)※上は羽衣茉莉花(ハゴロモジャスミン)の写真茉莉花というのは、”シソ目モクセイ科ソケイ属に分類される植物の総称”。【棕櫚(棕梠・椶櫚)】読み方:シュロ(一種)※上は和棕櫚(ワジュロ)の写真棕櫚というのは、”和棕櫚(ワジュロ:標準和名)の別名/ヤシ目ヤシ科シュロ属に分類される植物の総称”。【沈丁花(瑞香)】読み方:ジンチョウゲ沈丁花というのは、”フトモモ目ジンチョウゲ科ジンチョウゲ属に分類される常緑低木の一種”。沈丁花は、金木犀(キンモクセイ)・梔子(クチナシ)と合わせて、日本の「三大芳香木」のひとつに数えられています。【忍冬(吸い葛)】読み方:スイカズラ忍冬というのは、”マツムシソウ目スイカズラ科スイカズラ属に分類される常緑蔓性木本の一種”。細長い花筒の奥に蜜(みつ)があり、かつて子供が口にくわえて甘い蜜を吸っていたことに由来しています。【杉】読み方:スギ杉というのは、”マツ目ヒノキ科スギ属に分類される常緑高木の一種”。杉というと、屋久杉(やくすぎ)(鹿児島県)・秋田杉(秋田県)・吉野杉(奈良県)などがありますが、これらは地域名称であって、同種の杉になります(別の種類の杉というわけではない)。屋久杉は「縄文杉(じょうもんすぎ)」と呼ばれることもありますが、これは”屋久島に生えている天然の杉(これが屋久杉)の中にある、ひとつの個体を指している固有名称”です。【酸塊】読み方:スグリ(一種)※上は房酸塊(フサスグリ)の写真※上は黒酸塊(クロスグリ)(別名:カシス)の写真酸塊というのは、”ユキノシタ目スグリ科スグリ属に分類される落葉低木の一種/ユキノシタ目スグリ科スグリ属に分類される落葉低木の総称”。「黒酸塊(クロスグリ)」(標準和名)は、別名で「カシス」とも呼ばれています。【薄(芒・尾花)】読み方:ススキ薄というのは、”イネ目イネ科ススキ属に分類される多年草の一種”。薄の穂が動物の尾に似ていることから、別名で「尾花(おばな)」とも呼ばれています。尾花(おばな)は、秋の七草のひとつとして知られています。【蘿蔔(清白)】読み方:スズシロ蘿蔔というのは、”大根(ダイコン:標準和名)の別名”。大根は、”アブラナ目アブラナ科ダイコン属に分類される越年草の一種。また、その根のこと”を指します。大根は葉と肥大した根を食用とし、蘿蔔は春の七草のひとつとして知られています。【菘(鈴菜)】読み方:スズナ菘というのは、”蕪(カブ:標準和名)の別名”。蕪は、”アブラナ目アブラナ科アブラナ属に分類される越年草の一種。また、その胚軸(はいじく)のこと”を指します。蕪は葉と肥大した胚軸(葉と根の間の部分)を食用とし、白色の他にも赤・黄・紫色など多くの種類があります。菘(スズナ)は、春の七草のひとつとして知られています。【鈴蘭】読み方:スズラン鈴蘭というのは、”キジカクシ目キジカクシ科スズラン属に分類される多年草の一種”。全体的に毒(「コンバラトキシン」や「コンバロシド」など)を含み、特に根茎に強い毒があります。白い鈴を吊るしたかのような花をつけ、ラン科の植物に似ていることから名付けられました。【菫】読み方:スミレ(トリカブト)/ 一種(総称)※上は菫(スミレ)の写真※上は奥鳥兜(オクトリカブト)の写真「スミレ」と読むと”キントラノオ目スミレ科スミレ属に分類される多年草の一種/キントラノオ目スミレ科スミレ属に分類される植物の総称”。「トリカブト」と読むと”キンポウゲ目キンポウゲ科トリカブト属に分類される植物の総称”。全体的に毒(「アコニチン」や「メサコニチン」など)を含み、特に根に強い毒があります。また「トリカブト」は菫の他にも「鳥兜(トリカブト)」と書き表され、一般的には「鳥兜」と表記されることがほとんどです。【芹】読み方:セリ芹というのは、”セリ目セリ科セリ属に分類される多年草の一種”。若葉は香りが良く食用とし、春の七草のひとつとして知られています。【栴檀(楝)】読み方:センダン栴檀というのは、”ムクロジ目センダン科センダン属に分類される落葉高木の一種”。【千日紅】読み方:センニチコウ千日紅というのは、”ナデシコ目ヒユ科センニチコウ属に分類される一年草の一種”。千日紅(標準和名)は、別名で「千日草(センニチソウ)」とも呼ばれています。【蘇鉄(鉄樹・鉄蕉)】読み方:ソテツ蘇鉄というのは、”ソテツ目ソテツ科ソテツ属に分類される落葉低木の一種”。鉄分を肥料にするとよく育つため、枯れそうになったときに、幹(みき)や根元に鉄の釘(くぎ)を打ち込んだり与えると蘇ることに由来しています。【染井吉野】読み方:ソメイヨシノ染井吉野というのは、”バラ目バラ科サクラ属に分類される落葉高木。桜(サクラ)の一品種”。【冬青】読み方:ソヨゴ冬青というのは、”ニシキギ目モチノキ科モチノキ属に分類される常緑低木の一種”。↓タ行~【橘】読み方:タチバナ橘というのは、”ムクロジ目ミカン科ミカン属に分類される常緑小高木の一種”。橘(標準和名)は、別名で「大和橘(ヤマトタチバナ)」「日本橘(ニッポンタチバナ)」とも呼ばれています。【蓼】読み方:タデ(総称)※上は柳蓼(ヤナギタデ)の写真蓼というのは、”ナデシコ目タデ科イヌタデ属に分類される植物の総称”。蓼の葉や茎(くき)には特有の香りと辛味があります。「蓼食う虫も好き好き(たでくうむしもすきずき)」ということわざがありますが、これは蓼のような辛(から)いものでも好んで食べる虫がいることから、”人の好みは様々であること”の意味で用いられます。例えば「蓼食う虫も好き好きというが、いくらなんでもあいつだけはないだろう」のように用いられます。【煙草(莨・烟草)】読み方:タバコ煙草というのは、”ナス目ナス科タバコ属に分類される多年草の一種(栽培種としては一年草として扱われる)”。※上は紙巻きタバコの写真※上は葉巻(はまき)(別名:シガー)の写真煙草の葉の成分には強い依存性がある「ニコチン」が含まれており、煙草の葉は「葉巻(はまき)(別名:シガー)」や「紙巻きタバコ」などの原料として用いられます。【蒲公英】読み方:タンポポ(総称)※上は西洋蒲公英(セイヨウタンポポ)の写真※上は蒲公英の冠毛の写真蒲公英というのは、”キク目キク科タンポポ属に分類される多年草の総称”。花を咲かせた後に「冠毛(かんもう)」と呼ばれる綿毛のついた種子を生じ、風に乗ってその種子を遠くまで運びます。【鬱金香】読み方:チューリップ鬱金香というのは、”ユリ目ユリ科チューリップ属に分類される多年草の一種”。※上は鬱金(ウコン)の写真チューリップの花の香りが、香辛料などで使われる鬱金(ウコン)に似ていたことから、「鬱金香」と表記されるようになりました。【栂】読み方:ツガ栂というのは、”マツ目マツ科ツガ属に分類される常緑高木の一種”。【土筆(筆頭菜)】読み方:ツクシ※上は土筆(ツクシ)の写真※上は杉菜(スギナ)の写真土筆というのは、”杉菜(スギナ)の胞子茎(ほうしけい)”。杉菜は、”トクサ目トクサ科トクサ属に分類される多年草の一種”を指します。胞子茎は”胞子を作る部位のこと”を指し、杉菜と土筆は地下でつながっていて、杉菜を「栄養茎」、土筆を「胞子茎」と呼びます。【黄楊(柘植)】読み方:ツゲ(一種)※上は黄楊(一種)の写真黄楊というのは、”ツゲ目ツゲ科ツゲ属に分類される常緑低木の一種/ツゲ目ツゲ科ツゲ属に分類される植物の総称”。前者の意味の黄楊(標準和名)は、別名で「本黄楊(ホンツゲ)」とも呼ばれています。【躑躅】読み方:ツツジ(総称)※上は山躑躅(ヤマツツジ)の写真躑躅というのは、”ツツジ目ツツジ科ツツジ属に分類される植物の総称”。【椿(海石榴・山茶)】読み方:ツバキ椿というのは、”藪椿(ヤブツバキ:標準和名)の別名”。藪椿は”ツツジ目ツバキ科ツバキ属に分類される常緑高木の一種”の意味。種子から椿油(つばきあぶら)を採ることができ、食用油・整髪料・機械油などに用いられます。【石蕗(艶蕗・橐吾)】読み方:ツワブキ石蕗というのは、”キク目キク科ツワブキ属に分類される多年草の一種”。【満天星】読み方:ドウダンツツジ(ドウダン)満天星というのは、”ツツジ目ツツジ科ドウダンツツジ属に分類される落葉低木の一種”。「ドウダン」は、「ドウダンツツジ」(標準和名)を略したものになります。【木賊(砥草)】読み方:トクサ木賊というのは、”トクサ目トクサ科トクサ属に分類される多年草の一種”。茎の表面は珪酸(ケイ酸)を多く含んでいて硬く、茎で物を磨くことができます。昔は茎を歯磨きなどに使っていたことから、別名で「歯磨草(はみがきぐさ)」とも呼ばれています。【蕺草】読み方:ドクダミ蕺草というのは、”コショウ目ドクダミ科ドクダミ属に分類される多年草の一種”。蕺草(標準和名)は、別名で「十薬(じゅうやく)」とも呼ばれています。「ドクダミ」の名称から毒がありそうな感じはしますが、毒はなく、古くから民間薬として利用されてきました。「ドクダミ」は、現之証拠(ゲンノショウコ)・千振(センブリ)と合わせて、日本の「三大民間薬」のひとつに数えられます。「毒をダミする」が語源で、「毒を矯正する・止める(つまり毒を治す)」の意味から名付けられています。【野老】読み方:トコロ(一種)※上は鬼野老(オニドコロ)の写真野老というのは、”鬼野老(オニドコロ:標準和名)の別名/ユリ目ヤマノイモ科ヤマノイモ属に分類される多年草の総称”。鬼野老は、”ユリ目ヤマノイモ科ヤマノイモ属に分類される多年草の一種”を指します。【巴草】読み方:トモエソウ巴草というのは、”キントラノオ目オトギリソウ科オトギリソウ属に分類される多年草の一種”。【鳥兜(草鳥頭・菫)】読み方:トリカブト(総称)※上は奥鳥兜(オクトリカブト)の写真鳥兜というのは、”キンポウゲ目キンポウゲ科トリカブト属に分類される植物の総称”。全体的に毒(「アコニチン」や「メサコニチン」など)を含み、特に根に強い毒があります。また、菫は「トリカブト」と読むこともできますが、「スミレ」と読むことがほとんどです。【団栗】読み方:ドングリ団栗というのは、”椚(クヌギ)・小楢(コナラ)・樫(カシ)など、ブナ科に分類される植物の果実”。↓ナ行~【薺(撫菜)】読み方:ナズナ薺というのは、”アブラナ目アブラナ科ナズナ属に分類される越年草の一種”。若葉を食用とし、春の七草のひとつとして知られています。薺(標準和名)は、別名で「ぺんぺん草(ペンペングサ)」とも呼ばれています。【撫子(瞿麦)】読み方:ナデシコ(一種)撫子というのは、”河原撫子(カワラナデシコ:標準和名)の別名/ナデシコ目ナデシコ科ナデシコ属に分類される植物の総称”。河原撫子は、”ナデシコ目ナデシコ科ナデシコ属に分類される多年草の一種”を指します。撫子(河原撫子)は秋の七草のひとつで、別名で「大和撫子(ヤマトナデシコ)」とも呼ばれています。(大和撫子は、清楚で美しい女性のたとえ、としても用いられます)【七竈(花楸樹)】読み方:ナナカマド七竈というのは、”バラ目バラ科ナナカマド属に分類される落葉高木の一種”。非常に燃えにくく、7回竈(かまど)に入れても燃え残ってしまうという説や、7回または7日間竈に入れることで良質な炭を得ることができるという説などから名付けられています。【楡】読み方:ニレ(一種)※上は春楡(ハルニレ)の写真楡というのは、”春楡(ハルニレ:標準和名)の別名/バラ目ニレ科ニレ属に分類される植物の総称”。春楡は、”バラ目ニレ科ニレ属に分類される落葉高木の一種”を指します。【接骨木(庭常)】読み方:ニワトコ接骨木というのは、”マツムシソウ目ガマズミ科ニワトコ属に分類される落葉低木の一種”。枝や幹を煎(せん)じて水あめ状になったものを、骨折の治療の際の湿布(しっぷ)剤に用いたことから、「接骨木」と表記されています。【白膠木】読み方:ヌルデ白膠木というのは、”ムクロジ目ウルシ科ヌルデ属に分類される落葉小高木の一種”。※上は五倍子の写真白膠木の若芽や若葉などに、油虫(アブラムシ)が寄生して生じる虫こぶを「五倍子(ごばいし・ふし)」と呼びます。(虫こぶは”植物に虫が産卵・寄生したときに、植物が防衛反応を起こして、その部分が異常な発育をしたもの”)中は空洞で、殻に苦味の成分である「タンニン」を多く含み、薬用・インク・染料などに利用され、昔はお歯黒(おはぐろ)にも用いられました。【杜松】読み方:ネズ杜松というのは、”マツ目ヒノキ科ビャクシン属に分類される常緑小高木の一種”。杜松(標準和名)は、別名で「鼠刺し(ネズミサシ)」とも呼ばれています。杜松の鋭く尖った針状の葉を、鼠の通り道などに置いて鼠除け(ねずみよけ)にしていたことから「鼠刺し(ネズミサシ)」となり、それが縮まって「ネズ」になったとされています。【合歓木】読み方:ネムノキ合歓木というのは、”マメ目マメ科ネムノキ属に分類される落葉高木の一種”。夜になると、小葉が閉じて垂れ下がり、それが眠っているように見えることから名付けられています。【鋸草】読み方:ノコギリソウ鋸草というのは、”キク目キク科ノコギリソウ属に分類される多年草の一種”。葉が鋸(のこぎり)の歯のような形をしていることから名付けられています。↓ハ行~【萩】読み方:ハギ(総称)※上は山萩(ヤマハギ)の写真萩というのは、”マメ目マメ科ハギ属に分類される落葉低木の総称”。萩というと、一般的には「山萩(ヤマハギ)」を指すことが多く、秋の七草のひとつに数えられる萩も「山萩」のことを指しています。「萩(ハギ)」という字は、「荻(オギ)」という字によく似ているため注意が必要です。【繁縷(蘩蔞)】読み方:ハコベ(ハコベラ)繁縷というのは、”ナデシコ目ナデシコ科ハコベ属に分類される越年草の一種”。「ハコベラ」は、「ハコベ」(標準和名)の別名になります。若い葉・茎を食用とし、「ハコベラ」は春の七草のひとつとして知られています。【榛】読み方:ハシバミ榛というのは、”ブナ目カバノキ科ハシバミ属に分類される落葉低木の一種”。【芭蕉】読み方:バショウ芭蕉というのは、”ショウガ目バショウ科バショウ属に分類される多年草の一種”。【蓮】読み方:ハス蓮というのは、”ヤマモガシ目ハス科ハス属に分類される多年草の一種”。蓮の地下茎のことを「蓮根(レンコン)」と呼び、野菜として食用とされています。【櫨の木(櫨・黄櫨)】読み方:ハゼノキ櫨の木というのは、”ムクロジ目ウルシ科ウルシ属に分類される落葉小高木の一種”。櫨の木(標準和名)は、略して「櫨(ハゼ)」とも呼ばれています。【淡竹】読み方:ハチク淡竹というのは、”イネ目イネ科マダケ属に分類される植物。竹の一種”。淡竹の筍(タケノコ)は、えぐ味がなく美味だとされますが、一般的に日本で食用となっているのは「孟宗竹(モウソウチク)」の筍が多いです。淡竹は、日本では孟宗竹(モウソウチク)・真竹(マダケ)と合わせて、「日本三大有用竹」のひとつに数えられています。【荷薄】読み方:ハッカ(一種)※上は日本薄荷(ニホンハッカ)の写真荷薄というのは、”日本薄荷(ニホンハッカ:標準和名)の別名/シソ目シソ科ハッカ属に分類される植物の総称”。日本薄荷は”シソ目シソ科ハッカ属に分類される多年草の一種”を指します。日本薄荷は、葉・茎に「薄荷油(はっかゆ)」を多く含んでおり、主成分は「メントール(メンソール)(別名:薄荷脳)」で、強い香りがあるため清涼剤・香料に用いられます。(薄荷油の原料は、主に日本薄荷が使用されています)【華尼拉】読み方:バニラ※上は華尼拉のさやの写真華尼拉というのは、”キジカクシ目ラン科バニラ属に分類される多年草の一種。また、その植物から抽出された香料”。種子は香料の原料となり、さやごと収穫(収穫時には甘い香りはしない)し、さやごと発酵・乾燥を繰り返すと甘い香りを発するようになります。※上は発酵・乾燥を繰り返したさやの写真※上はバニラビーンズ(種子)の写真さやの中には非常に小さな黒い種子がたくさん入っていて、その小さな黒い種子を「バニラビーンズ」(さやごと指してバニラビーンズということもある)と呼びます。そして華尼拉の香り成分をアルコールで抽出したものを「バニラエッセンス」といい、お菓子作りなどに用いられます。【浜梨(浜茄子)】読み方:ハマナス※上は浜梨の果実の写真浜梨というのは、”バラ目バラ科バラ属に分類される落葉低木の一種”。果実はローズヒップ(バラ科バラ属に分類される植物の果実の総称)として食用になり、ビタミンCを豊富に含んでいます。赤く熟した果実が甘酸っぱいので、梨にたとえて「浜梨(ハマナシ)」と名付けられ、それが変化して「ハマナス」になったとされています。【浜木綿】読み方:ハマユウ浜木綿というのは、”キジカクシ目ヒガンバナ科ハマオモト属に分類される多年草の一種”。浜辺に生える植物であることや、楮(コウゾ)の木の皮から作られる白い繊維を原料とした布である「木綿(ゆう)」に似ていることから名付けられています。(木綿は、一般的には「もめん」と読むことが多いです)【薔薇】読み方:バラ(総称)※上は薔薇(アンクル ウォルター)の写真薔薇というのは、”バラ目バラ科バラ属に分類される植物の総称”。茎や葉には棘(トゲ)があり、”薔薇・枳殻(カラタチ)などの棘のある木の総称”を「茨(いばら)」と呼びます。「綺麗(きれい)な薔薇には棘がある」という慣用句がありますが、これは「綺麗な薔薇=美しい女性」「棘=危険な(恐ろしい)一面」にたとえて、”美しい女性には危険な一面があるから気をつけなさい”という意味で使われます。【春紫苑】読み方:ハルジオン春紫苑というのは、”キク目キク科ムカシヨモギ属に分類される多年草の一種”。【柊】読み方:ヒイラギ※上は柊(モクセイ科)の写真※上は西洋柊(モチノキ科)の写真柊というのは、”シソ目モクセイ科モクセイ属に分類される常緑小高木の一種/西洋柊(セイヨウヒイラギ:標準和名)の別名”。西洋柊は”ニシキギ目モチノキ科モチノキ属に分類される常緑小高木の一種”を指します。西洋柊(モチノキ科)の葉が、柊(モクセイ科)のギザギザしている葉の形に似ていることから「西洋柊(セイヨウヒイラギ)」の名称が付けられています。どちらも葉の形など見た目が似ていますが、柊(モクセイ科)は秋から冬頃に白い花を咲かせ、西洋柊(モチノキ科)は冬頃に赤色の果実をつけます。※上は柊鰯(ひいらぎいわし)の写真また柊と西洋柊のギザギザの葉は魔除(まよ)けになると考えられ、節分には「柊鰯(ひいらぎいわし)」、クリスマスにはクリスマスリースなどに用いられます。柊鰯(節分)には柊(モクセイ科)、クリスマスリース(クリスマス)には西洋柊(モチノキ科)が使用されます。【稗】読み方:ヒエ稗というのは、”イネ目イネ科ヒエ属に分類される一年草の一種”。【彼岸花】読み方:ヒガンバナ彼岸花というのは、”キジカクシ目ヒガンバナ科ヒガンバナ属に分類される多年草の一種”。彼岸花(標準和名)は、別名で「曼珠沙華(マンジュシャゲ)」とも呼ばれています。秋の彼岸頃に、花茎を伸ばして鮮やかな赤色の花を咲かせることから名付けられています。【楸】読み方:ヒサギ(キササゲ)※上は木大角豆(キササゲ)の写真※上は赤芽柏(アカメガシワ)の写真「ヒサギ」と読むと”木大角豆(キササゲ:標準和名)の別名/赤芽柏(アカメガシワ:標準和名)の別名”の意味。赤芽柏は、”キントラノオ目トウダイグサ科アカメガシワ属に分類される落葉高木の一種”を指します。「キササゲ」(木大角豆)と読むと”シソ目ノウゼンカズラ科キササゲ属に分類される落葉高木の一種”の意味。【菱】読み方:ヒシ菱というのは、”フトモモ目ミソハギ科ヒシ属に分類される一年草の一種”。【雛罌粟(雛芥子)】読み方:ヒナゲシ雛罌粟というのは、”キンポウゲ目ケシ科ケシ属に分類される一年草の一種”。雛罌粟(標準和名)は、別名で「虞美人草(グビジンソウ)」「シャーレイポピー」「コクリコ」とも呼ばれています。【檜(桧)】読み方:ヒノキ檜というのは、”マツ目ヒノキ科ヒノキ属に分類される常緑高木の一種”。【向日葵】読み方:ヒマワリ向日葵というのは、”キク目キク科ヒマワリ属に分類される一年草の一種”。※上は向日葵の果実(一般的には”向日葵の種”と呼ばれる)の写真※上は向日葵の種子(果実の殻を割って出てきた部分)の写真一般的に向日葵の種(たね)と呼ばれるのは、実は向日葵の果実のことを指し、本来は果実の殻(縞模様)を割って出てきた部分が種(種子)になります。向日葵の種子は食用で、日本で食べられることはあまりないですが、世界的には健康食品としてよく知られています。【白檀】読み方:ビャクダン白檀というのは、”ビャクダン目ビャクダン科ビャクダン属に分類される常緑小高木の一種”。【風信子(飛信子)】読み方:ヒヤシンス風信子というのは、”キジカクシ目キジカクシ科ヒヤシンス属に分類される多年草の一種”。【藤袴】読み方:フジバカマ藤袴というのは、”キク目キク科ヒヨドリバナ属に分類される多年草の一種”。藤袴は、秋の七草のひとつとして知られています。【仏桑花】読み方:ブッソウゲ仏桑花というのは、”アオイ目アオイ科フヨウ属に分類される常緑低木の一種”。また仏桑花は「ハイビスカス」と呼ばれることもありますが、フヨウ属の学名・英名が「Hibiscus(ハイビスカス)」なので、ハイビスカスという名称は”フヨウ属に分類される植物の総称”として使われることも多いです。ですのでハイビスカスは、仏桑花の類似のフヨウ属の植物を指す場合にも使われるため、”仏桑花=ハイビスカスというわけではない”ので覚えておきましょう。【橅(山毛欅・椈)】読み方:ブナ橅というのは、”ブナ目ブナ科ブナ属に分類される落葉高木の一種”。橅(標準和名)は、別名で「白橅(シロブナ)」とも呼ばれています。【箒木(帚木)】読み方:ホウキギ箒木というのは、”ナデシコ目ヒユ科バッシア属に分類される一年草の一種”。乾燥した茎枝を箒(ホウキ)として用いていたことから名付けられています。箒木は、別名で「コキア」とも呼ばれています。【鳳仙花(染指草)】読み方:ホウセンカ鳳仙花というのは、”フウロソウ目ツリフネソウ科ツリフネソウ属に分類される一年草の一種”。【鬼灯(酸漿)】読み方:ホオズキ鬼灯というのは、”ナス目ナス科ホオズキ属に分類される多年草の一種”。夏頃に黄白色の花を咲かせ、その後にがく(花びらの付け根)部分が大きくなり果実を包みます。鬼灯の果実は観賞用と食用のものがありますが、日本で栽培されている鬼灯の多くは観賞用です。観賞用の鬼灯には毒性(アルカロイドなど)があるため、食用にすることはできないので注意が必要です。【朴の木】読み方:ホオノキ朴の木というのは、”モクレン目モクレン科モクレン属に分類される落葉高木の一種”。日本に自生する樹木の中では最大級の葉・花を持っていて、大きな葉は食べ物を包んだり焼いたりするときに用いられます。ホオノキの「ホオ」は、「包(ほう)」の意味で、大きな葉で食べ物を包むことから名付けられています。朴の木(標準和名)は、略して「朴(ホオ)」とも呼ばれています。【木瓜】読み方:ボケ(キュウリ・マルメロ)※上は木瓜(ボケ)の写真※上は木瓜(ボケ)の果実の写真「ボケ」と読むと”バラ目バラ科ボケ属に分類される落葉低木の一種”。果実は熟すと黄色くなり、苦味や酸味が強いため生食はできませんが、ジャム・果実酒などに用いられます。※上は胡瓜(キュウリ)の写真※上は胡瓜(キュウリ)の果実の写真「キュウリ」と読むと”ウリ目ウリ科キュウリ属に分類される一年草の一種。また、その果実のこと”。※上は熟した胡瓜(キュウリ)の果実の写真果実は熟すと黄色くなり、昔は黄色い状態のものを食用としていましたが、味や食感が悪くなるため、現在では未成熟な状態(緑色)の果実を野菜として食用にしています。「キュウリ」は、一般的には”胡瓜”と表記されることが多いです。※上は木瓜(マルメロ)の写真※上は木瓜(マルメロ)の果実の写真「マルメロ」と読むと”バラ目バラ科マルメロ属に分類される落葉高木の一種”。果実は熟すと黄色くなり、強い酸味があり、硬いため生食はできませんが、ジャム・果実酒などに用いられます。【菩提樹】読み方:ボダイジュ菩提樹というのは、”アオイ目アオイ科シナノキ属に分類される落葉高木の一種”。仏教の開祖であるお釈迦様が、菩提樹の木の下で悟りを開いたとされることが名称の由来になっています。【牡丹】読み方:ボタン牡丹というのは、”ユキノシタ目ボタン科ボタン属に分類される落葉低木の一種”。美女を形容する言葉として「立てば芍薬(シャクヤク)、座れば牡丹(ボタン)、歩く姿は百合(ユリ)の花」がありますが、これは元々は漢方の生薬(しょうやく)の使い方を示す言葉です。イラ立ちやすい女性は芍薬の根、座ってばかりいるような女性は牡丹の根の皮、フラフラ歩く女性は百合の根を用いると健康に良い、という意味になります。【仏の座】読み方:ホトケノザ※上は小鬼田平子(コオニタビラコ)の写真※上は小鬼田平子(食用部分)の写真※上は仏の座(後者の意味)の写真仏の座というのは、”小鬼田平子(コオニタビラコ:標準和名)の別名/シソ目シソ科オドリコソウ属に分類される越年草の一種”。前者の意味である仏の座(=小鬼田平子)は、”キク目キク科ヤブタビラコ属に分類される越年草の一種”を指します。「ホトケノザ」は春の七草のひとつとして知られていますが、これは前者の意味の「仏の座(=小鬼田平子)」を指しています。仏の座(後者の意味)は、花の下にある葉の形が仏様がすわる台座のように見えることから名付けられています。↓マ行~【木春菊】読み方:マーガレット木春菊というのは、”キク目キク科モクシュンギク属に分類される多年草の一種”。【真菰】読み方:マコモ真菰というのは、”イネ目イネ科マコモ属に分類される多年草の一種”。緑色の葉を何枚か剥いでいくと、白い可食部位が現れ、その部分を「真菰茸(マコモダケ)」と呼びます。【木天蓼】読み方:マタタビ木天蓼というのは、”ツバキ目マタタビ科マタタビ属に分類される落葉低木の一種”。猫(トラやヒョウなどの大型ネコ科動物にも効果あり)に木天蓼を与えると「マタタビ反応」が起こり、リラックスした表情になったり、ゴロゴロ転げまわったり体を擦り寄せたりします。これは木天蓼に含まれる成分(マタタビラクトン・ネペタラクトールなど)が中枢神経を刺激することによるものです。【毬藻】読み方:マリモ毬藻というのは、”シオグサ目アオミソウ科マリモ属に分類される緑藻(りょくそう)類の一種”。毬藻というと、北海道の「阿寒湖(あかんこ)」に生息するものが有名で、美しい球体状を作ることから特別天然記念物に指定されています。【満作(万作・金縷梅)】読み方:マンサク満作というのは、”ユキノシタ目マンサク科マンサク属に分類される落葉小高木の一種”。【水芭蕉】読み方:ミズバショウ水芭蕉というのは、”オモダカ目サトイモ科ミズバショウ属に分類される多年草の一種”。【三椏(三又・三叉)】読み方:ミツマタ三椏というのは、”フトモモ目ジンチョウゲ科ミツマタ属に分類される落葉低木の一種”。三椏は、和紙や紙幣(日本銀行券)の原料として用いられます。1本の枝から3本の枝が分かれていることから名付けられています。【木槿(槿)】読み方:ムクゲ木槿というのは、”アオイ目アオイ科フヨウ属に分類される落葉低木の一種”。【葎】読み方:ムグラ(総称)※上は八重葎(ヤエムグラ)の写真葎というのは、”荒れ地や野原に生い茂る雑草の総称”。【木斛】読み方:モッコク木斛というのは、”ツツジ目モッコク科モッコク属に分類される常緑高木の一種”。【樅】読み方:モミ樅というのは、”マツ目マツ科モミ属に分類される常緑高木の一種”。クリスマスツリーは、一般的に樅の若木が用いられることが多いです。【紅葉】読み方:モミジ(こうよう)「モミジ」と読むと”楓(カエデ:総称)の別名”。楓というのは、”ムクロジ目ムクロジ科カエデ属に分類される落葉高木の総称”を指します。「こうよう」と読むと”木の葉が黄・赤色に変わること。また、その色づいた木の葉のこと”。↓ヤ行~【椰子(椰)】読み方:ヤシ(総称)椰子というのは、”ヤシ目ヤシ科に分類される植物の総称”。椰子の実(果実)というのは、様々なヤシ科の植物の実を指しますが、一般的には「ココナッツ(ココヤシの実)」を指すことが多いです。※上はココナッツの果肉(白い固形部分)とココナッツミルクの写真果実の中にある白い固形部分(果肉)と液体部分を食用とし、白い固形部分を砕いて水とともに混ぜて濾(こ)したものが「ココナッツミルク」になります。※上は未成熟のココナッツ(ココヤシの果実)の写真※上はココナッツウォーター(ココナッツジュース)の写真また液体部分は「ココナッツウォーター(ココナッツジュース)」と呼ばれていて、成熟(繊維で覆われ茶色)してくると中のココナッツウォーターは果肉(白い固形部分)などに変化していくため、一般的には未成熟のココナッツ(緑色)から採ることが多いです。ココナッツウォーターは透明な液体で、観光地では未成熟のココナッツ(緑色)に穴を開けて、そこからストローを挿して飲むことが多いです。※上はナタデココの写真ちなみにココナッツウォーターに酢酸菌(さくさんきん)を加えて発酵させたものを「ナタデココ」と呼び、弾力のある歯ごたえがあり、デザートなどに用いられます。【八手(八つ手)】読み方:ヤツデ八手というのは、”セリ目ウコギ科ヤツデ属に分類される常緑低木の一種”。葉が掌(てのひら)状に深い切れ込みがあることから名付けられています。葉が8つに裂けているものもありますが、全ての葉が8つに裂けているわけではなく、八手の「八」は”数が多い”という意味で用いられます。【宿り木(寄生木・宿木)】読み方:ヤドリギ宿り木というのは、”ビャクダン目ビャクダン科ヤドリギ属に分類される常緑低木の一種”。地面に根を張らずに、他の樹木の幹や枝に根を食い込ませ、宿主である樹木の養分と水分を吸い取って成長します。【山吹】読み方:ヤマブキ山吹というのは、”バラ目バラ科ヤマブキ属に分類される落葉低木の一種”。【楪(杠・譲葉)】読み方:ユズリハ楪というのは、”ユキノシタ目ユズリハ科ユズリハ属に分類される常緑高木の一種”。春先に新しい葉が出ると、譲るように古い葉が落ちることから名付けられています。【百合】読み方:ユリ(総称)※上は山百合(ヤマユリ)の写真百合というのは、”ユリ目ユリ科ユリ属に分類される多年草の総称”。美女を形容する言葉として「立てば芍薬(シャクヤク)、座れば牡丹(ボタン)、歩く姿は百合(ユリ)の花」がありますが、これは元々は漢方の生薬(しょうやく)の使い方を示す言葉です。イラ立ちやすい女性は芍薬の根、座ってばかりいるような女性は牡丹の根の皮、フラフラ歩く女性は百合の根を用いると良い、という意味になります。【蓬(艾)】読み方:ヨモギ蓬というのは、”キク目キク科ヨモギ属に分類される多年草の一種”。※上は蓬餅(草餅)の写真蓬には特有の匂いがあり、若葉を餅(もち)などに混ぜこんだものを「蓬餅(よもぎもち)」「草餅(くさもち)」と呼びます。昔は草餅には蓬以外の草を使っていましたが、いま現在では草餅にも蓬が使われているため蓬餅・草餅はどちらも同じ和菓子のことを指します。↓ラ行~【竜胆(龍胆)】読み方:リンドウ竜胆というのは、”リンドウ目リンドウ科リンドウ属に分類される多年草の一種”。根茎を乾燥させたものは非常に苦く、中国では代表的な苦味で知られる「熊胆(ゆうたん)」よりもさらに苦いことから「竜胆」という漢字が当てられています。竜胆の葉を疫病(えきびょう)の薬として用いていたことから、別名で「疫病草(えやみぐさ)」とも呼ばれています。【連翹】読み方:レンギョウ(一種)連翹というのは、”シソ目モクセイ科レンギョウ属に分類される落葉低木の一種/シソ目モクセイ科レンギョウ属に分類される植物の総称”。【蝋梅(蠟梅)】読み方:ロウバイ蝋梅というのは、”クスノキ目ロウバイ科ロウバイ属に分類される落葉低木の一種”。↓ワ行~【勿忘草(忘れな草)】読み方:勿忘草(一種)※上は真勿忘草(シンワスレナグサ)の写真勿忘草というのは、”真勿忘草(シンワスレナグサ:標準和名)の別名/シソ目ムラサキ科ワスレナグサ属に分類される植物の総称”。真勿忘草は、”シソ目ムラサキ科ワスレナグサ属に分類される多年草の一種”を指します。【蕨】読み方:ワラビ※上は早蕨(さわらび)の写真蕨というのは、”シダ目コバノイシカグマ科ワラビ属に分類される多年草の一種”。蕨の若芽のことを「早蕨(さわらび)」と呼び、山菜として食べられています。※上は蕨粉(わらびこ)の写真※上は蕨餅(わらびもち)の写真蕨は根茎からデンプンを取り、そのデンプンのことを「蕨粉(わらびこ)」と呼び、蕨粉に水と砂糖を加えて練ったものを「蕨餅(わらびもち)」と言います。【吾亦紅(吾木香)】読み方:ワレモコウ吾亦紅というのは、”バラ目バラ科ワレモコウ属に分類される多年草の一種”。花・植物の難読漢字(一覧表)※1:漢字表記が複数ある場合は、一般的に使われることが多いほうの漢字表記を優先しています(読み方の表記も同様)。例 【薊(莇)】 ⇒ 【一般的に使われることが多い漢字表記(比較して一般的に使われることが少ない漢字表記)】※2:読み方の横に「(一種)」「(総称)」の表記があるものは、以下のような意味になります。例 【シクラメン(一種)】 ⇒ 【(狭義では)ツツジ目サクラソウ科シクラメン属に分類される多年草の一種】【(広義では)ツツジ目サクラソウ科シクラメン属に分類される植物の総称】の両方を意味例 【アオイ(総称)】 ⇒ 【アオイ目アオイ科に分類される植物の総称】を意味(アオイという名称の特定の植物が存在するわけではない)※3:標準和名=【日本での正式な名称のこと】⇒学名と標準和名の違いとは?漢字読み方備考欄葵アオイ(総称)金合歓アカシア(総称)金合歓の別名は「ミモザ」朝顔(牽牛花・蕣)アサガオ薊(莇)アザミ(総称)薊の別名は「棘草(トゲクサ)」葦アシ(ヨシ)「アシ」は、「ヨシ」(標準和名)の別名紫陽花アジサイ紫陽花(標準和名)の別名は「七変化(しちへんげ)」「八仙花(はっせんか)」翌檜(翌桧)アスナロ馬酔木アセビ甘茶蔓アマチャヅル菖蒲アヤメ、ショウブ「アヤメ」と「ショウブ」で意味が異なる蘆薈アロエ(総称)粟アワ藺イ藺(標準和名)の別名は「藺草(イグサ)」虎杖イタドリ公孫樹(銀杏)イチョウ銀杏は「ぎんなん」と読むことが多い猪子槌(牛膝)イノコヅチ鬱金ウコン地下茎を乾燥させて粉末にしたものを「ターメリック」と呼ぶ空木(卯木)ウツギ独活(土当帰)ウド漆ウルシ金雀枝エニシダ狗尾草エノコログサ狗尾草(標準和名)の別名は「猫じゃらし」槐エンジュ大葉子(車前草)オオバコ荻オギ「萩(ハギ)」という字によく似ているため注意が必要朮オケラ御辞儀草(含羞草)オジギソウ御辞儀草(標準和名)の別名は「眠り草(ネムリグサ)」「ミモザ」(「ミモザ」は、一般的には「アカシア」の別名として使われることが多い)白粉花オシロイバナ苧環オダマキ(総称)弟切草オトギリソウ男郎花オトコエシ巻耳オナモミ巻耳(標準和名)の別名は「ひっつき虫」「くっつき虫」(巻耳だけを指す別名ではない)女郎花オミナエシ女郎花(標準和名)の別名は「敗醤(はいしょう)」。秋の七草のひとつ沢瀉(面高)オモダカ万年青オモト阿列布(阿利布)オリーブ果実は、オリーブオイルの原料海棠カイドウ海棠は、「花海棠(ハナカイドウ)」(標準和名)の別名楓(槭)カエデ(総称)「砂糖楓(サトウカエデ)」の樹液は、メープルシロップの原料加加阿カカオカカオ豆(種子)は、チョコレートの原料燕子花(杜若)カキツバタ樫カシ(総称)細葉榕(榕樹)ガジュマル霞草カスミソウ葛カズラ、クズ「カズラ」と「クズ」で意味が異なる。「クズ」は、秋の七草のひとつ桂カツラ蒲ガマ枳殻(枸橘)カラタチ唐松(落葉松)カラマツ雁草(雁金草)カリガネソウ雁皮ガンピ桔梗キキョウ秋の七草のひとつ菊キク羊蹄ギシギシ黍キビ擬宝珠ギボウシ(総称)夾竹桃キョウチクトウ桐キリ金盞花キンセンカ金鳳花キンポウゲ金鳳花は、「馬の足形(ウマノアシガタ)」(標準和名)の別名金木犀キンモクセイ金木犀は、沈丁花(ジンチョウゲ)・梔子(クチナシ)と合わせて、日本の「三大芳香木」のひとつに数えられる枸杞クコ楠(樟)クスノキ楠の材は「樟脳(しょうのう)」の原料梔子(梔・巵子・山梔子)クチナシ梔子は、沈丁花(ジンチョウゲ)・金木犀(キンモクセイ)と合わせて、日本の「三大芳香木」のひとつに数えられる椚(櫟・橡・櫪)クヌギ桑クワ(総称)芥子(罌粟)ケシ麻薬の原料となるため、一般の栽培は法律で禁止されている欅(槻)ケヤキ紫雲英ゲンゲ紫雲英(標準和名)の別名は「蓮華草(レンゲソウ)」楮コウゾ河骨(川骨)コウホネ御形ゴギョウ御形は、「母子草(ハハコグサ)」(標準和名)の別名。御形は春の七草のひとつ秋桜コスモス(一種)秋桜(一種)は、「大春車菊(オオハルシャギク)」(標準和名)の別名胡蝶蘭コチョウラン小楢コナラ辛夷コブシ榊サカキ山茶花(茶梅)サザンカ番紅花(咱夫藍)サフラン雌しべは香辛料に用いられる仙人掌(覇王樹)サボテン(総称)沙羅双樹(娑羅双樹)サラソウジュ(シャラソウジュ)「シャラソウジュ」は、「サラソウジュ」(標準和名)の別名百日紅(猿滑・紫薇)サルスベリ椹(花柏・弱檜)サワラ山椒サンショウ紫苑シオン樒(梻)シキミ篝火花シクラメン(一種)羊歯(歯朶)シダ(一種)羊歯(一種)は、「裏白(ウラジロ)」(標準和名)の別名枝垂桜シダレザクラ枝垂柳シダレヤナギ射干(著莪・胡蝶花)シャガ石楠花(石南花)シャクナゲ(総称)芍薬シャクヤク茉莉花(耶悉茗・素馨)ジャスミン(総称)棕櫚(棕梠・椶櫚)シュロ(一種)棕櫚(一種)は、「和棕櫚(ワジュロ)」(標準和名)の別名沈丁花(瑞香)ジンチョウゲ沈丁花は、金木犀(キンモクセイ)・梔子(クチナシ)と合わせて、日本の「三大芳香木」のひとつに数えられる忍冬(吸い葛)スイカズラ杉スギ「屋久杉(鹿児島県)・秋田杉(秋田県)・吉野杉(奈良県)」などが有名酸塊スグリ(一種)「黒酸塊(クロスグリ)」(標準和名)の別名は「カシス」薄(芒・尾花)ススキ薄(標準和名)の別名は「尾花(おばな)」。尾花(おばな)は、秋の七草のひとつ蘿蔔(清白)スズシロ蘿蔔は、「大根(ダイコン)」(標準和名)の別名。蘿蔔は、春の七草のひとつ菘(鈴菜)スズナ菘は、「蕪(カブ)」(標準和名)の別名。菘は、春の七草のひとつ鈴蘭スズラン菫スミレ(トリカブト)/一種(総称)「トリカブト」は、”鳥兜”と表記されることがほとんど芹セリ春の七草のひとつ栴檀(楝)センダン千日紅センニチコウ千日紅(標準和名)の別名は「千日草(センニチソウ)」蘇鉄(鉄樹・鉄蕉)ソテツ染井吉野ソメイヨシノ冬青ソヨゴ橘タチバナ橘(標準和名)の別名は「大和橘(ヤマトタチバナ)」「日本橘(ニッポンタチバナ)」蓼タデ(総称)煙草(莨・烟草)タバコ煙草の葉は「葉巻」「紙巻きタバコ」の原料蒲公英タンポポ(総称)鬱金香チューリップ栂ツガ土筆(筆頭菜)ツクシ「杉菜(スギナ)」の胞子茎(ほうしけい)黄楊(柘植)ツゲ(一種)黄楊(標準和名)の別名は「本黄楊(ホンツゲ)」躑躅ツツジ(総称)椿(海石榴・山茶)ツバキ「藪椿(ヤブツバキ)」(標準和名)の別名石蕗(艶蕗・橐吾)ツワブキ満天星ドウダンツツジ(ドウダン)「ドウダン」は、「ドウダンツツジ」(標準和名)の略木賊(砥草)トクサ木賊(標準和名)の別名は「歯磨草(はみがきぐさ)」蕺草ドクダミ蕺草(標準和名)の別名は「十薬(じゅうやく)」野老トコロ(一種)野老(一種)は、「鬼野老(オニドコロ)」(標準和名)の別名巴草トモエソウ鳥兜(草鳥頭・菫)トリカブト(総称)菫は「スミレ」と読むことがほとんど団栗ドングリ薺(撫菜)ナズナ薺(標準和名)の別名は「ぺんぺん草(ペンペングサ)」。薺は、春の七草のひとつ撫子(瞿麦)ナデシコ(一種)撫子(一種)は、「河原撫子(カワラナデシコ)」(標準和名)の別名。撫子(河原撫子)は、秋の七草のひとつ七竈(花楸樹)ナナカマド楡ニレ(一種)楡(一種)は、「春楡(ハルニレ)」(標準和名)の別名接骨木(庭常)ニワトコ白膠木ヌルデ杜松ネズ杜松(標準和名)の別名は「鼠刺し(ネズミサシ)」合歓木ネムノキ鋸草ノコギリソウ萩ハギ(総称)一般的には「山萩(ヤマハギ)」を指す。萩(山萩)は秋の七草のひとつ。「荻(オギ)」という字によく似ているため注意が必要繁縷(蘩蔞)ハコベ(ハコベラ)「ハコベ」(標準和名)の別名は「ハコベラ」。「ハコベラ」は春の七草のひとつ榛ハシバミ芭蕉バショウ蓮ハス蓮の地下茎を「蓮根(レンコン)」と呼ぶ櫨の木(櫨・黄櫨)ハゼノキ櫨の木(標準和名)は、略して「櫨(ハゼ)」とも呼ばれる淡竹ハチク淡竹は、孟宗竹(モウソウチク)・真竹(マダケ)と合わせて、「日本三大有用竹」のひとつに数えられる薄荷ハッカ(一種)薄荷(一種)は、「日本薄荷(ニホンハッカ)」(標準和名)の別名華尼拉バニラ浜梨(浜茄子)ハマナス浜木綿ハマユウ薔薇バラ(総称)春紫苑ハルジオン柊ヒイラギ稗ヒエ彼岸花ヒガンバナ彼岸花(標準和名)の別名は「曼珠沙華(マンジュシャゲ)」楸ヒサギ(キササゲ)「ヒサギ」と「キササゲ」で意味が少し異なる菱ヒシ雛罌粟(雛芥子)ヒナゲシ雛罌粟(標準和名)の別名は「虞美人草(グビジンソウ)」「シャーレイポピー」「コクリコ」檜(桧)ヒノキ向日葵ヒマワリ白檀ビャクダン風信子(飛信子)ヒヤシンス藤袴フジバカマ秋の七草のひとつ仏桑花ブッソウゲ橅(山毛欅・椈)ブナ橅(標準和名)の別名は「白橅(シロブナ)」箒木(帚木)ホウキギ箒木(標準和名)の別名は「コキア」鳳仙花(染指草)ホウセンカ鬼灯(酸漿)ホオズキ朴の木ホオノキ朴の木(標準和名)は、略して「朴(ホオ)」とも呼ばれる木瓜ボケ(キュウリ・マルメロ)「ボケ」と「キュウリ」と「マルメロ」で意味が異なる菩提樹ボダイジュ牡丹ボタン仏の座ホトケノザ「小鬼田平子(コオニタビラコ)」(標準和名)の別名。仏の座(小鬼田平子)は、春の七草のひとつ木春菊マーガレット真菰マコモ葉を何枚か剥いで現れる白い可食部位を「真菰茸(マコモダケ)」と呼ぶ木天蓼マタタビ猫の好物毬藻マリモ北海道にある「阿寒湖(あかんこ)」の毬藻が有名満作(万作・金縷梅)マンサク水芭蕉ミズバショウ三椏(三又・三叉)ミツマタ材は「紙幣(日本銀行券)」の原料木槿(槿)ムクゲ葎ムグラ(総称)木斛モッコク樅モミ若木は「クリスマスツリー」に用いられる紅葉モミジ(こうよう)「モミジ」と「こうよう」で意味が異なる椰子(椰)ヤシ(総称)八手(八つ手)ヤツデ宿り木(寄生木・宿木)ヤドリギ山吹ヤマブキ楪(杠・譲葉)ユズリハ百合ユリ(総称)蓬(艾)ヨモギ竜胆(龍胆)リンドウ竜胆(標準和名)の別名は「疫病草(えやみぐさ)」連翹レンギョウ(一種)蝋梅(蠟梅)ロウバイ勿忘草(忘れな草)ワスレナグサ(一種)勿忘草(一種)は、「真勿忘草(シンワスレナグサ)」(標準和名)の別名蕨ワラビ吾亦紅(吾木香)ワレモコウ項目1項目2項目3)★ -->関連ページ<難読漢字の一覧>⇒【一文字】難読漢字の一覧!⇒【野菜・果物・茸】難読漢字の一覧!⇒【魚・貝・海藻】難読漢字の一覧!⇒【動物】難読漢字の一覧!⇒【鳥】難読漢字の一覧!⇒【虫】難読漢字の一覧!⇒【食べ物・飲み物】難読漢字の一覧!⇒【道具・身近なモノ】難読漢字の一覧!<読み間違えやすい漢字の一覧>⇒読み間違えやすい漢字一覧!⇒慣用読み(百姓読み)の一覧!<難読漢字の一覧(偏)>⇒【魚偏】難読漢字の一覧!⇒【虫偏】難読漢字の一覧!⇒【木偏】難読漢字の一覧!⇒【金偏】難読漢字の一覧!