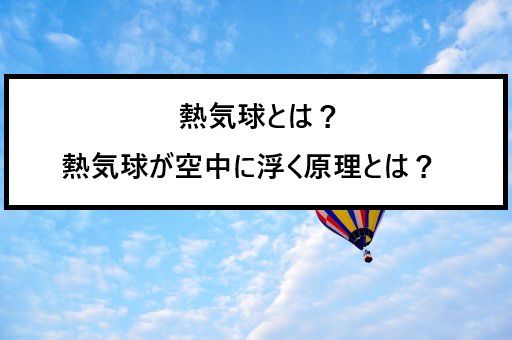さてあなたは熱気球を見たことがあるでしょうか。実際に熱気球が飛んでいるところを見たことがある人は少ないかもしれませんが、テレビなどで熱気球の飛んでいる映像を見たことはありますよね。そしてなぜ熱気球が空中に浮かぶことができるのか、その原理について疑問に感じている人も多いみたいです。そこでこのページでは熱気球とは何か?また熱気球が空中に浮く原理について簡単に解説します。どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次熱気球とは?熱気球はどんな原理で空中に浮いているの?まとめ1.熱気球とは?では熱気球とは何か見ていきましょう。熱気球(ねつききゅう)とは、気密性の高い袋の中にバーナーで暖めた空気を送ることで、空中に浮かぶことができる乗り物です。”暖かい空気は軽くなって、冷たい空気が重くなる”と聞いたことがないでしょうか。この原理を利用している乗り物が熱気球になります。(詳しい原理については次の章で解説していきます)そして熱気球は空中を自由に飛び回ることができると思っている人も多いですが、実はそうではありません。熱気球が自由に移動できるのは上昇と下降だけで、空中で左右には自由に移動させることはできません。バーナーを用いて火力を調整することで上下の移動が可能になり、熱気球を左右に移動させるには、自然現象である”風(かぜ)”を利用します。高度によって風の強さや吹く方向も違うため、バーナーの火力を調整しながら風の吹く方向を読む必要があります。次の章で熱気球が空中に浮かぶ原理について解説します。関連:空気の温度で重さは変わる?暖かい空気は軽く冷たい空気が重い仕組みとは?関連:風の正体とは?どんな原理で吹いているのか?2.熱気球はどんな原理で空中に浮いているの?では熱気球がどんな原理で空中に浮いているのか見ていきましょう。熱気球が空中に浮く原理は、熱気球内の空気と外の空気の密度差によるものです。空気の温度を変化させることで空気の体積は大きくなったり小さくなったりしますが、それによって空気自体の密度の大きさも変わります。上図のように暖かい空気は密度が小さく、冷たい空気は密度が大きくなるんですね。そして密度が小さいものほど軽くなり、密度の大きいものほど重くなります。だから暖かい空気(密度が小さい)は軽くなって、冷たい空気(密度が大きい)は重くなるということです。熱気球は簡易的ですが上図のような構造です。球皮の下の部分が狭くなっているのは、球皮内の暖められた空気を逃がしにくくするためです。まず球皮の中には通常の温度の空気が存在していますが、バーナーで少しずつ球皮の中の空気を熱していきます。そうするとバーナー近くに存在する空気がどんどん暖められていき、その空気は密度が小さくなるので軽くなり球皮内で上昇します。バーナーで暖められた空気の体積が大きくなることで、元から球皮内に存在していた空気は少なからず外へと追い出されます。そして熱気球が空中に浮く原理は球皮内と外の空気の密度差によるものです。この密度差を分かりやすく表現したものに、水に沈むものと水に浮かぶものがあります。では水に沈むものと浮かぶものは何が違うのでしょうか?正解を言ってしまうと、水に沈むものと浮かぶものでは密度の大きさが違います。水に沈んでしまうものは水よりも密度が大きい(重い)もので、水に浮かぶものは水よりも密度が小さい(軽い)ものなんですね。イメージしにくいと感じる人はこのように考えてみてください。”浮く”というのは軽いものの下に重いものが入り込むことで起こります。もっと簡単に言えば、重いものの上に軽いものが乗っかっているイメージです。だから水に浮いているものというのは密度が小さくて水よりも軽いものなので、それより重い水がそのものの下に入り込んでいくことで浮いているように見えます。本来は水の上に乗っかっているだけなんですね。それが水の上に浮くということです。なので熱気球もこれと同じようにイメージしてみると分かりやすくなります。球皮内の空気はバーナーで暖められることで密度が小さくなり、外の空気よりも軽くなります。これにより外の空気は暖められた空気よりも重いので下に入り込もうとします。そうすることで暖められた空気は軽いためどんどん上へと追いやられ、球皮内で暖められた空気によって上へ行こうとする力が発生します。そして>球皮内の暖かい空気によって上へ行こうとする力が、熱気球の重さ(球皮、バスケット、バーナーなど)よりも大きくなれば空中に浮くようになります。上図のように暖められた空気が上に行こうとする力が、熱気球の重さよりも小さければ浮くことはできなくなります。その場合は球皮内の空気をもっと暖めなて軽く(密度を小さく)しなければいけません。ちなみに熱気球は外気温が低いほど空中に浮きやすくなります。その理由は球皮内と外の空気の温度差が大きくなることで、空気の密度差もより大きくなるからです。密度の大きい空気(冷たい空気)ほど暖められた空気の下に入り込みやすくなるので、外気温が低いほど熱気球は空中に浮きやすくなるんですね。関連:密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?関連:浮力とは何か?浮力の原理を簡単に図で解説!以上が「熱気球とは?また熱気球はどんな原理で空中に浮いているのか?」でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});3.まとめこれまで説明したことをまとめますと、熱気球とは、気密性の高い袋の中にバーナーで暖めた空気を送ることで、空中に浮かぶことができる乗り物のこと。熱気球は球皮内の空気と外の空気の密度差によって空中に浮かんでいる。外気温が低いほど空気に大きな密度差が生まれるので、熱気球は空中に浮かびやすくなる。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});関連ページ⇒風船にヘリウムガスを入れると空中に浮く理由とは?⇒煙とは?黒い煙や白い煙の正体って何?⇒空気の膨張とは何か?空気の温度によって体積が変化する仕組みとは?⇒圧力鍋とは何か?圧力鍋の仕組みをわかりやすく図解!⇒山でお菓子の袋が膨らむ仕組みとは?分かりやすく図で解説!⇒真空とは何か?分かりやすく図で解説!⇒気温と温度と室温の違いとは?⇒なぜ空中に浮く風船と浮かない風船があるのか?⇒なぜ標高が高い所は寒いのか?太陽との距離は関係ないって本当?⇒浮力と流体の密度の関係について。流体の密度で浮力が変化する仕組みとは?