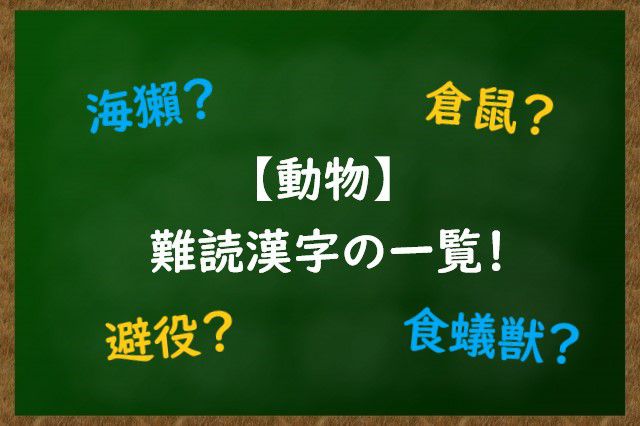このページでは動物の難読漢字について簡単に一覧にしてまとめています。(動物の難読漢字を新しく見つけ次第、追記していきます)どうぞご覧ください。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});目次↓動物の難読漢字の読み方や説明、写真などを載せています◆【ア行~】◇【カ行~】◆【サ行~】◇【タ行~】◆【ナ行~】◇【ハ行~】◆【マ行~】◇【ヤ行~】◆【ラ行~】◇【ワ行~】↓動物の難読漢字とその読み方だけをザっと見たい方はこちら(同ページのリンクへ移動します)●動物の難読漢字(一覧表)↓関連ページはこちら(同ページのリンクへ移動します)★関連ページ動物の難読漢字※1:漢字表記が複数ある場合は、一般的に使われることが多いほうの漢字表記を優先しています(読み方の表記も同様)。例 【海豹(水豹)】 ⇒ 【一般的に使われることが多い漢字表記(比較して一般的に使われることが少ない漢字表記)】※2:読み方の横に「(一種)」「(総称)」の表記があるものは、以下のような意味になります。例 【アライグマ(一種)】 ⇒ 【(狭義では)食肉目アライグマ科アライグマ属に分類される哺乳類の一種】【(広義では)食肉目アライグマ科アライグマ属に分類される哺乳類の総称】の両方を意味例 【アリクイ(総称)】 ⇒ 【有毛目アリクイ亜目に分類される哺乳類の総称】を意味(アリクイという名称の特定の動物が存在するわけではない)※3:標準和名=【日本での正式な名称のこと】⇒学名と標準和名の違いとは?↓ア行~【指猿】読み方:アイアイ指猿というのは、”霊長目(別名:サル目)アイアイ科アイアイ属に分類される哺乳類の一種”。その見た目から死や災害をもたらす悪魔の使いや不吉の象徴と考える地域も存在し、それによる駆除や森林伐採などによる生息地の破壊などから生息数が減少し、絶滅危惧種に指定されています。【海豹(水豹)】読み方:アザラシ(総称)海豹というのは、”食肉目(別名:ネコ目)アザラシ科に分類される哺乳(ほにゅう)類の総称”。<顎鬚海豹>読み方:アゴヒゲアザラシ顎鬚海豹というのは、”食肉目アザラシ科アゴヒゲアザラシ属に分類される哺乳類の一種”。<胡麻斑海豹>読み方:ゴマフアザラシ胡麻斑海豹というのは、”食肉目アザラシ科ゴマフアザラシ属に分類される哺乳類の一種”。<銭形海豹>読み方:ゼニガタアザラシ銭形海豹というのは、”食肉目アザラシ科ゴマフアザラシ属に分類される哺乳類の一種”。【海驢(葦鹿)】読み方:アシカ(一種)海驢というのは、”加州海驢(カリフォルニアアシカ:標準和名)の別名/食肉目(ネコ目)アシカ科に分類される哺乳類の総称”。<加羅哇哥斯海驢>読み方:ガラパゴスアシカ加羅哇哥斯海驢というのは、”食肉目アシカ科アシカ属に分類される哺乳類の一種”。<加州海驢>読み方:カリフォルニアアシカ加州海驢というのは、”食肉目アシカ科アシカ属に分類される哺乳類の一種”。海驢というと、一般的には加州海驢を指します。【洗熊(浣熊)】読み方:アライグマ(一種)洗熊というのは、”食肉目(ネコ目)アライグマ科アライグマ属に分類される哺乳類の一種/食肉目アライグマ科アライグマ属に分類される哺乳類の総称”。前足を水中に入れて、獲物を探している様子が手を洗っているように見えることから名付けられています。【食蟻獣(蟻食・蟻喰)】読み方:アリクイ(総称)食蟻獣というのは、”有毛目(ゆうもうもく)アリクイ亜目(虫舌亜目)に分類される哺乳類の総称”。蟻(アリ)や白蟻(シロアリ)を食べることから名付けられ、英語でも「アントイーター(anteater)」と呼ばれています。前足の大きくて鋭い爪で蟻塚(ありづか)を壊したり、巣穴に粘着性の唾液の突いた細長い舌を突っ込んで蟻を舐めとって捕食します。<大蟻食>読み方:オオアリクイ大蟻食というのは、”有毛目アリクイ亜目アリクイ科オオアリクイ属に分類される哺乳類の一種”。<小蟻食>読み方:ミナミコアリクイ小蟻食というのは、”有毛目アリクイ亜目アリクイ科コアリクイ属に分類される哺乳類の一種”。【羊駱駝】読み方:アルパカ羊駱駝というのは、”鯨偶蹄目(くじらぐうていもく)ラクダ科ビクーニャ属に分類される哺乳類の一種”。羊駱駝は、「駱駝(ラクダ)」の仲間になります。威嚇(いかく)・自己防衛のために唾液(だえき)を吐きかける習性があり、この唾液は強烈な臭いを発します。【犰狳(鎧鼠)】読み方:アルマジロ(総称)犰狳というのは、”被甲目(ひこうもく)アルマジロ科に分類される哺乳類の総称”。犰狳というと丸くなるイメージですが、実は大半の種類は丸くなることができません。<三帯犰狳>読み方:ミツオビアルマジロ三帯犰狳というのは、”被甲目アルマジロ科ミツオビアルマジロ属に分類される哺乳類の一種”。三帯犰狳は、数少ない丸くなることのできる犰狳の一種になります。【鬣蜥蜴(立髪竜)】読み方:イグアナ(総称)鬣蜥蜴というのは、”有鱗目(ゆうりんもく)イグアナ科に分類される爬虫(はちゅう)類の総称”。<海鬣蜥蜴>読み方:ウミイグアナ海鬣蜥蜴というのは、”有鱗目イグアナ科ウミイグアナ属に分類される爬虫類の一種”。<緑鬣蜥蜴>読み方:グリーンイグアナ緑鬣蜥蜴というのは、”有鱗目イグアナ科グリーンイグアナ属に分類される爬虫類の一種”。鬣蜥蜴というと、一般的には緑鬣蜥蜴を指すことが多いです。【鼬(鼬鼠)】読み方:イタチ(総称)鼬というのは、”食肉目(ネコ目)イタチ科イタチ属に分類される哺乳類の総称”。<白鼬>読み方:オコジョ※上は白鼬(夏毛)の写真白鼬というのは、”食肉目イタチ科イタチ属に分類される哺乳類の一種”。1年に2回換毛(毛が抜け替わること)し、夏は背側が茶色で腹側が白色(夏毛)となり、冬は全身が白色(冬毛)になります(どちらも尻尾の先は黒色)。<朝鮮鼬>読み方:チョウセンイタチ朝鮮鼬というのは、”西比利亜鼬(シベリアイタチ:標準和名)の別名”。西比利亜鼬は、”食肉目イタチ科イタチ属に分類される哺乳類の一種”。西比利亜鼬は、「朝鮮鼬(チョウセンイタチ)」の他に、別名で「大陸鼬(タイリクイタチ)」とも呼ばれています。<日本鼬>読み方:ニホンイタチ日本鼬というのは、”食肉目イタチ科イタチ属に分類される哺乳類の一種”。鼬というと、一般的には日本鼬を指すことが多いです。【猪(豬)】読み方:イノシシ(一種)猪というのは、”鯨偶蹄目イノシシ科イノシシ属に分類される哺乳類の一種/鯨偶蹄目イノシシ科の哺乳類の総称”。※上はウリ坊(猪の子供)の写真※上は縞瓜(シマウリ)の写真猪の子供は生後4カ月くらいまで体に縞(しま)模様があり、その見た目が縞瓜(シマウリ)に似ていることから「ウリ坊(ぼう)」と呼ばれています。<日本猪>読み方:ニホンイノシシ日本猪というのは、”鯨偶蹄目イノシシ科イノシシ属に分類される哺乳類。猪(一種)の亜種”。<琉球猪>読み方:リュウキュウイノシシ琉球猪というのは、”鯨偶蹄目イノシシ科イノシシ属に分類される哺乳類。猪(一種)の亜種”。【井守(蠑螈)】読み方:イモリ(総称)井守というのは、”有尾目(ゆうびもく)(別名:サンショウウオ目)イモリ科の両生類の総称”。自己防衛のために皮膚に毒を持っている種類が多いです。<赤腹井守>読み方:アカハライモリ赤腹井守というのは、”有尾目イモリ科イモリ属に分類される両生類の一種”。赤腹井守(標準和名)は、別名で「日本井守(ニホンイモリ)」とも呼ばれています。井守というと、一般的には赤腹井守を指すことが多いです。赤腹井守の皮膚(皮・筋肉)からは、「テトロドトキシン」(通称:フグ毒)と呼ばれる神経毒が分泌されています。<尻剣井守>読み方:シリケンイモリ尻剣井守というのは、”有尾目イモリ科イモリ属に分類される両生類の一種”。<南疣井守>読み方:ミナミイボイモリ南疣井守というのは、”有尾目イモリ科ミナミイボイモリ属に分類される両生類の一種”。【海豚(鯆)】読み方:イルカ(総称)海豚というのは、”鯨偶蹄目に分類される鯨類のうち、小型の種の総称”。海豚(イルカ)と鯨(クジラ)は分類学的には明確には区別されておらず、一般的には体長4~5m以下のものを海豚と呼び、それ以上の体長のものを鯨と呼ぶことが多いです。<鎌海豚>読み方:カマイルカ鎌海豚というのは、”鯨偶蹄目マイルカ科カマイルカ属に分類される哺乳類の一種”。背鰭(せびれ)の形が草などを刈るときの鎌に似ていることから名付けられています。<白海豚>読み方:シロイルカ白海豚というのは、”鯨偶蹄目イッカク科シロイルカ属に分類される哺乳類の一種”。白海豚(標準和名)は、別名で「ベルーガ」とも呼ばれています。<砂滑>読み方:スナメリ砂滑というのは、”鯨偶蹄目ネズミイルカ科スナメリ属に分類される哺乳類の一種”。砂の上を滑るように泳ぐことや、砂の中に隠れている魚に向かって口から勢いよく水を吹く様子が砂を舐めているように見えることから名付けられています。<半道海豚>読み方:ハンドウイルカ半道海豚というのは、”鯨偶蹄目マイルカ科ハンドウイルカ属に分類される哺乳類の一種”。海豚というと、一般的には半道海豚を指すことが多いです。半道海豚(標準和名)は、別名で「坂東海豚(バンドウイルカ)」とも呼ばれ、一般的には坂東海豚と呼ばれることが多いです。【兎】読み方:ウサギ(総称)※上は兎(ネザーランド・ドワーフ)の写真※上は兎(ホーランド・ロップイヤー)の写真兎というのは、”兎形目(とけいもく)(別名:ウサギ目)ウサギ科に分類される哺乳類の総称”。他の動物に比べて耳が大きく発達し、周囲の音を聞き分けたり、長い耳を風に当てることで体温調節をしています。【海亀(魭)】読み方:ウミガメ(総称)海亀というのは、”カメ目ウミガメ科とオサガメ科に分類される爬虫類の総称”。爬虫類で肺呼吸のため、水中では息ができないので、海面に顔を出して息継ぎをします(体内に酸素を溜める)。基本的には生涯を海中で過ごし、雌(メス)の産卵のとき以外は陸上にはあがってきません。<青海亀>読み方:アオウミガメ青海亀というのは、”カメ目ウミガメ科アオウミガメ属に分類される爬虫類の一種”。青海亀(標準和名)は、別名で「正覚坊(ショウガクボウ)」とも呼ばれています。<赤海亀>読み方:アカウミガメ赤海亀というのは、”カメ目ウミガメ科アカウミガメ属に分類される爬虫類の一種”。<玳瑁(瑇瑁)>読み方:タイマイ玳瑁というのは、”カメ目ウミガメ科タイマイ属に分類される爬虫類の一種”。※上は鼈甲細工の写真玳瑁の甲羅は「鼈甲(べっこう)」と呼ばれ、鼈甲細工の原料とされるため高額で取引され、乱獲されたことにより絶滅寸前(現在は絶滅危惧種に指定)になりました。ただワシントン条約により国際取引が禁止され、日本では1993年に玳瑁の甲羅の輸入は停止されています。【狼】読み方:オオカミ(一種)狼というのは、”食肉目(ネコ目)イヌ科イヌ属に分類される哺乳類の一種とその亜種の総称”。前者の意味の狼(標準和名)は、別名で「灰色狼(ハイイロオオカミ)」「大陸狼(タイリクオオカミ)」とも呼ばれています。<森林狼>読み方:シンリンオオカミ森林狼というのは、”カナダ北西部や五大湖地域などに生息する狼(一種)の亜種”。<北極狼>読み方:ホッキョクオオカミ北極狼というのは、”北極圏周辺に生息する狼(一種)の亜種”。【霍加皮】読み方:オカピ霍加皮というのは、”鯨偶蹄目キリン科オカピ属に分類される哺乳類の一種”。霍加皮は、「麒麟(キリン)」の仲間に分類されています。【膃肭臍(海狗)】読み方:オットセイ(総称)膃肭臍というのは、”食肉目(ネコ目)アシカ科のうち、キタオットセイ属とミナミオットセイ属に分類される哺乳類の総称”。<南阿弗利加膃肭臍>読み方:ミナミアフリカオットセイ南阿弗利加膃肭臍というのは、”食肉目アシカ科ミナミオットセイ属に分類される哺乳類の一種”。<南亜米利加膃肭臍>読み方:ミナミアメリカオットセイ南亜米利加膃肭臍というのは、”食肉目アシカ科ミナミオットセイ属に分類される哺乳類の一種”。【袋鼠】読み方:オポッサム(総称)袋鼠というのは、”オポッサム目オポッサム科に分類される哺乳類の総称”。<北袋鼠>読み方:キタオポッサム北袋鼠というのは、”オポッサム目オポッサム科オポッサム属に分類される哺乳類の一種”。【猩猩(猩々)】読み方:オランウータン(総称)猩猩というのは、”霊長目(サル目)ヒト科オランウータン属に分類される哺乳類の総称”。マレー語の「orang(人)+ hutan (森)=森の人」から名付けられました。<蘇門荅剌猩猩>読み方:スマトラオランウータン蘇門荅剌猩猩というのは、”霊長目ヒト科オランウータン属に分類される哺乳類の一種”。<勃泥亜猩猩(婆羅猩猩)>読み方:ボルネオオランウータン勃泥亜猩猩というのは、”霊長目ヒト科オランウータン属に分類される哺乳類の一種”。↓カ行~【蛙】読み方:カエル(総称)蛙というのは、”無尾目(むびもく)(別名:カエル目)に分類される両生類の総称”。蛙の幼生(子ども)のことを「御玉杓子(オタマジャクシ)」と呼びます。実はほとんどの蛙は毒を持っており、皮膚から毒を含んだ分泌液を出して、皮膚を守っています。なので蛙を触った手で、目や傷口などに触らないようにしましょう。<牛蛙>読み方:ウシガエル牛蛙というのは、”無尾目アカガエル科アメリカアカガエル属に分類される両生類の一種”。雄(オス)の鳴き声が牛に似ていることが名前の由来です。<土蛙>読み方:ツチガエル土蛙というのは、”無尾目アカガエル科ツチガエル属に分類される両生類の一種”。土蛙(標準和名)は、背中に疣(イボ)状の突起が多くあることから、別名で「疣蛙(イボガエル)」とも呼ばれています。<殿様蛙>読み方:トノサマガエル殿様蛙というのは、”無尾目アカガエル科トノサマアカガエル属に分類される両生類の一種”。敵を威嚇(いかく)するときに腹部を膨らませて体をのけぞらせている姿が、堂々としている殿様のように見えることが名前の由来と言われています。<日本雨蛙>読み方:ニホンアマガエル日本雨蛙というのは、”無尾目アカガエル科アカガエル属に分類される両生類の一種”。一般的には略して「雨蛙(アマガエル)」と呼ぶことが多いです。<蟇蛙>読み方:ヒキガエル(一種)蟇蛙というのは、”日本蟇蛙(ニホンヒキガエル:標準和名)の別名/無尾目ヒキガエル科に分類される両生類の総称”。日本蟇蛙は、”無尾目ヒキガエル科ヒキガエル属に分類される両生類の一種”を指します。蟇蛙は、別名で「蝦蟇(ガマ、ガマガエル)」とも呼ばれています。【金蛇(蛇舅母)】読み方:カナヘビ(一種)金蛇というのは、”日本金蛇(ニホンカナヘビ:標準和名)の別名/有鱗目カナヘビ科に分類される爬虫類の総称”。<青金蛇>読み方:アオカナヘビ青金蛇というのは、”有鱗目カナヘビ科クサカナヘビ属に分類される爬虫類の一種”。<日本金蛇>読み方:ニホンカナヘビ日本金蛇というのは、”有鱗目カナヘビ科カナヘビ属に分類される爬虫類の一種”。金蛇というと、一般的には日本金蛇のことを指します。<宮古金蛇>読み方:ミヤコカナヘビ宮古金蛇というのは、”有鱗目カナヘビ科カナヘビ属に分類される爬虫類の一種”。【河馬】読み方:カバ(一種)河馬というのは、”鯨偶蹄目カバ科カバ属に分類される哺乳類の一種/鯨偶蹄目カバ科に分類される哺乳類の総称”。<小人河馬>読み方:コビトカバ小人河馬というのは、”鯨偶蹄目カバ科コビトカバ属に分類される哺乳類の一種”。食用のための狩猟や生息地の減少、水質汚染などにより数が減っていて、絶滅危惧種に指定されています。【水豚(川豚)】読み方:カピバラ水豚というのは、”齧歯目(げっしもく)(別名:ネズミ目)テンジクネズミ科カピバラ属に分類される哺乳類の一種”。水豚は、「鼠(ネズミ)」の仲間に分類されています。【避役(変色竜・変色龍)】読み方:カメレオン(総称)避役というのは、”有鱗目カメレオン科に分類される爬虫類の総称”。避役の皮膚の細胞は外からの光・熱などによって色が変化し、擬態(ぎたい)して周囲に溶け込むだけでなく、異性の気を引いたり敵を威嚇したり、体温調節などの役割もあります。<烏帽子避役>読み方:エボシカメレオン烏帽子避役というのは、”有鱗目カメレオン科カメレオン属に分類される爬虫類の一種”。※上は烏帽子のイラスト頭部が烏帽子(えぼし)を被っているように見えることから名付けられています。<地中海避役>読み方:チチュウカイカメレオン地中海避役というのは、”有鱗目カメレオン科カメレオン属に分類される爬虫類の一種”。【羚羊(氈鹿)】読み方:カモシカ(一種)氈鹿というのは、”日本羚羊(ニホンカモシカ:標準和名)の別名/鯨偶蹄目ウシ科カモシカ属に分類される哺乳類の総称”。<日本羚羊(日本氈鹿)>読み方:ニホンカモシカ日本羚羊というのは、”鯨偶蹄目ウシ科カモシカ属に分類される哺乳類の一種”。羚羊というと、一般的には日本羚羊のことを指します。日本羚羊は、特別天然記念物に指定されています。【鴨嘴(鴨嘴獣)】読み方:カモノハシ鴨嘴というのは、”単孔目(たんこうもく)(別名:カモノハシ目)カモノハシ科カモノハシ属に分類される哺乳類の一種”。哺乳類でありながら卵を産むという他と違った繁殖形態をとることで知られています。鴨嘴は毒を持っていて、雄(オス)の後ろ足にある蹴爪(けづめ)に毒があり、雌(メス)は毒を持っていません。雌の後ろ足にも蹴爪はありますが、成長に伴い蹴爪自体がなくなります。【獺(川獺)】読み方:カワウソ(総称)獺というのは、”食肉目(ネコ目)イタチ科カワウソ亜科に分類される哺乳類の総称”。<小爪獺>読み方:コツメカワウソ小爪獺というのは、”食肉目イタチ科カワウソ亜科ツメナシカワウソ属に分類される哺乳類の一種”。<欧亜獺>読み方:ユーラシアカワウソ欧亜獺というのは、”食肉目イタチ科カワウソ亜科カワウソ属に分類される哺乳類の一種”。【長尾驢(袋鼠・更格廬)】読み方:カンガルー(総称)長尾驢というのは、”双前歯目(そうぜんしもく)(別名:カンガルー目)カンガルー科に分類される哺乳類の総称”。袋鼠は「オポッサム」と読むことが多いです。<赤長尾驢>読み方:アカカンガルー赤長尾驢というのは、”双前歯目カンガルー科カンガルー属に分類される哺乳類の一種”。<大長尾驢>読み方:オオカンガルー大長尾驢というのは、”双前歯目カンガルー科カンガルー属に分類される哺乳類の一種”。<黒長尾驢>読み方:クロカンガルー黒長尾驢というのは、”双前歯目カンガルー科カンガルー属に分類される哺乳類の一種”。【狐】読み方:キツネ(総称)狐というのは、”食肉目(ネコ目)イヌ科キツネ属およびその近縁に分類される哺乳類の総称”。狐などの動物の体内には「エキノコックス」と呼ばれる寄生虫がいる場合があり、人体に「エキノコックス症」と呼ばれる感染症(肝臓の病気など)を引き起こすことで知られています。狐などの動物の糞(ふん)や体毛にはエキノコックス(寄生虫)の卵が付着している可能性があるため、それらに触った手で食べ物を食べてしまうと、卵が体内に入り感染してしまいます。<赤狐>読み方:アカギツネ赤狐というのは、”食肉目イヌ科キツネ属に分類される哺乳類の一種”。狐というと、一般的には赤狐を指すことが多いです。<銀狐>読み方:ギンギツネ銀狐というのは、”北半球に広く生息する赤狐(アカギツネ)の亜種”。<本土狐>読み方:ホンドギツネ本土狐というのは、”北半球に広く生息する赤狐(アカギツネ)の亜種”。【麒麟(騏驎)】読み方:キリン麒麟というのは、”鯨偶蹄目キリン科キリン属に分類される哺乳類の一種”。麒麟は動物の中で最も睡眠時間が短く、立ったままの仮眠は2時間ほどで、地面に座ってぐっすり眠るのは1日に数分~20分ほどになります。これは常にライオンなどの肉食動物を警戒し、すぐに逃げられるように長い睡眠時間をとらなくなったとされています。【鯨】読み方:クジラ(総称)鯨というのは、”鯨偶蹄目に分類される鯨類のうち、大型の種の総称”。鯨(クジラ)と海豚(イルカ)は分類学上、明確には区別されておらず、一般的には体長4~5m以下のものを海豚、それ以上の体長のものを鯨と呼ぶことが多いです。<座頭鯨>読み方:ザトウクジラ座頭鯨というのは、”鯨偶蹄目ナガスクジラ科ザトウクジラ属に分類される哺乳類の一種”。<白長須鯨>読み方:シロナガスクジラ白長須鯨というのは、”鯨偶蹄目ナガスクジラ科ナガスクジラ属に分類される哺乳類の一種”。<抹香鯨>読み方:マッコウクジラ抹香鯨というのは、”鯨偶蹄目マッコウクジラ科マッコウクジラ属に分類される哺乳類の一種”。抹香鯨の腸内に発生する結石のことを「龍涎香(りゅうぜんこう)」と呼び、香水や漢方薬に用いられます。腸の分泌物からとれる龍涎香が、「抹香(まっこう)」に似た香りがすることから「抹香鯨(マッコウクジラ)」と名付けられました。【貂熊(屈狸)】読み方:クズリ貂熊というのは、”食肉目(ネコ目)イタチ科クズリ属に分類される哺乳類の一種”。貂熊(標準和名)は、別名で「黒穴熊(クロアナグマ)」とも呼ばれています。【熊】読み方:クマ(総称)熊というのは、”食肉目(ネコ目)クマ科に分類される哺乳類の総称”。<月輪熊>読み方:ツキノワグマ月輪熊というのは、”食肉目クマ科クマ属に分類される哺乳類の一種”。胸に三日月のような模様があることから名付けられ、個体によっては三日月模様が欠けていたり、模様自体がない個体も存在します。<羆(緋熊・樋熊)>読み方:ヒグマ羆というのは、”食肉目クマ科クマ属に分類される哺乳類の一種”。北極熊(ホッキョクグマ)と並びクマ科では最大の種で、性格は臆病で警戒心が強いです。<北極熊>読み方:ホッキョクグマ北極熊というのは、”食肉目クマ科クマ属に分類される哺乳類の一種”。北極熊(標準和名)は、全身が白い体毛に覆われているように見えることから、別名で「白熊(シロクマ)」とも呼ばれています。北極熊の肌は真っ黒で、体毛は透明で内部が空洞になっている特殊な構造になっており、散乱光によって白く見える仕組みになっています。【子守熊(袋熊)】読み方:コアラ子守熊というのは、”双前歯目(カンガルー目)コアラ科コアラ属に分類される哺乳類の一種”。ユーカリという植物の葉を食べますが、ユーカリの葉には「青酸配糖体(せいさんはいとうたい)」と呼ばれる毒が含まれています。子守熊は毒を分解する微生物や酵素を持っているため体内で解毒することができます。子守熊は動物の中で最も睡眠時間が長く(1日18~22時間)、これは繊維質で毒性のあるユーカリの葉を常食としているため、消化するのに多くのエネルギーを必要とすることから(睡眠でエネルギーを蓄える)だと言われています。【蝙蝠】読み方:コウモリ(総称)蝙蝠というのは、”翼手目(よくしゅもく)(別名:コウモリ目)に分類される哺乳類の総称”。<油蝙蝠>読み方:アブラコウモリ油蝙蝠というのは、”翼手目ヒナコウモリ科アブラコウモリ属に分類される哺乳類の一種”。油蝙蝠(標準和名)は、家屋に棲みつくことから、別名で「家蝙蝠(イエコウモリ)」とも呼ばれています。油蝙蝠は、日本で最も一般的な蝙蝠になります。<菊頭蝙蝠>読み方:キクガシラコウモリ菊頭蝙蝠というのは、”翼手目キクガシラコウモリ科キクガシラコウモリ属に分類される哺乳類の一種”。【大猩猩(大猩々)】読み方:ゴリラ(総称)大猩猩というのは、”霊長目(サル目)ヒト科ゴリラ属に分類される哺乳類の総称”。<西大猩猩>読み方:ニシゴリラ西大猩猩というのは、”霊長目ヒト科ゴリラ属に分類される哺乳類の一種”。ちなみに西大猩猩の亜種である「ニシローランドゴリラ」の学名を「Gorilla gorilla gorilla(ゴリラ ゴリラ ゴリラ)」と言います。<山地大猩猩>読み方:マウンテンゴリラ山地大猩猩というのは、”霊長目ヒト科ゴリラ属に分類される哺乳類の一種”。↓サ行~【犀】読み方:サイ(総称)犀というのは、”奇蹄目(きていもく)(別名:ウマ目)サイ科に分類される哺乳類の総称”。犀の角(つの)は、爪や髪の毛と同じタンパク質の一種である「ケラチン」と呼ばれる成分から構成されています。<印度犀>読み方:インドサイ印度犀というのは、”奇蹄目サイ科インドサイ属に分類される哺乳類の一種”。<黒犀>読み方:クロサイ黒犀というのは、”奇蹄目サイ科クロサイ属に分類される哺乳類の一種”。<白犀>読み方:シロサイ白犀というのは、”奇蹄目サイ科シロサイ属に分類される哺乳類の一種”。【山椒魚(鯢・䱱魚)】読み方:サンショウウオ(総称)山椒魚というのは、”有尾目(サンショウウオ目)サンショウウオ科・オオサンショウウオ科などに分類される両生類の総称”。<大山椒魚>読み方:オオサンショウウオ大山椒魚というのは、”有尾目オオサンショウウオ科オオサンショウウオ属に分類される両生類の一種”。<霞山椒魚>読み方:カスミサンショウウオ霞山椒魚というのは、”有尾目サンショウウオ科サンショウウオ属に分類される両生類の一種”。<墨西哥鯢>読み方:メキシコサンショウウオ※上は墨西哥鯢(白変種)(一般的には「ウーパールーパー」)の写真墨西哥鯢というのは、”有尾目トラフサンショウウオ科トラフサンショウウオ属に分類される両生類の一種”。白変種の個体は、一般的には別名で「ウーパールーパー」、他には個体に関係なく「メキシコサラマンダー」とも呼ばれています。【鹿】読み方:シカ(総称)鹿というのは、”鯨偶蹄目シカ科に分類される哺乳類の総称”。多くのシカ科の雌(メス)は角を持ちませんが、馴鹿(トナカイ)は雄(オス)と雌のどちらも角を持っています。<馴鹿>読み方:トナカイ馴鹿というのは、”鯨偶蹄目シカ科トナカイ属に分類される哺乳類の一種”。荷物や人間を載せたそりを引くためにも利用され、サンタクロースのそりを引く動物としてのイメージが強いです。<日本鹿>読み方:ニホンジカ日本鹿というのは、”鯨偶蹄目シカ科シカ属に分類される哺乳類の一種”。日本鹿には、「蝦夷鹿(エゾジカ)」「屋久鹿(ヤクシカ)」「九州鹿(キュウシュウジカ)」などの亜種が存在します。<箆鹿(篦鹿)>読み方:ヘラジカ箆鹿というのは、”鯨偶蹄目シカ科ヘラジカ属に分類される哺乳類の一種”。雄の成獣が箆(へら)のような平たい角を持つことが名前の由来になっています。【縞馬(斑馬)】読み方:シマウマ(総称)縞馬というのは、”奇蹄目(ウマ目)ウマ科ウマ属のうち、白黒の縞模様を持つ種の総称”。縞馬は、馬と比較して小柄で、人が乗ったり重い荷物を運ばせるのは難しいです。【亜米利加豹】読み方:ジャガー※上は亜米利加豹(黒変種)の写真亜米利加豹というのは、”食肉目(別目:ネコ目)ネコ科ヒョウ属に分類される哺乳類の一種”。全身が黒い「黒変種(こくへんしゅ)」と呼ばれるタイプもいますが、普通の亜米利加豹と色以外に違いはありません。【鯱】読み方:シャチ鯱というのは、”鯨偶蹄目マイルカ科シャチ属に分類される哺乳類の一種”。【胡狼】読み方:ジャッカル(総称)胡狼というのは、”食肉目(ネコ目)イヌ科イヌ属に分類される哺乳類で、狼(オオカミ)や狐(キツネ)に似た中小型種の総称”。<背黒胡狼>読み方:セグロジャッカル背黒胡狼というのは、”食肉目イヌ科イヌ属に分類される哺乳類の一種”。【儒艮】読み方:ジュゴン儒艮というのは、”海牛目(かいぎゅうもく)(別名:ジュゴン目)ジュゴン科ジュゴン属に分類される哺乳類の一種”。※上はマナティーの写真東洋では「儒艮」、西洋では「マナティー」が人魚のモデルになった動物とされています。【鼈】読み方:スッポン(一種)鼈というのは、”カメ目スッポン科スッポン属に分類される爬虫類の一種/カメ目スッポン科に分類される爬虫類の総称”。前者の意味の鼈(標準和名)は、別名で「日本鼈(ニホンスッポン)」「極東鼈(キョクトウスッポン)」とも呼ばれています。【海象(海馬)】読み方:セイウチ海象というのは、”食肉目(ネコ目)セイウチ科セイウチ属に分類される哺乳類の一種”。↓タ行~【狸】読み方:タヌキ(総称)狸というのは、”食肉目(ネコ目)イヌ科タヌキ属に分類される哺乳類の総称”。狸はとても臆病な動物で、(大きな音などに)驚くと一時期的に気を失うことがあります。このことから”都合の悪いときに、わざと眠ったふりをすること”の意味で「狸寝入り(たぬきねいり)」ということわざが使われます。<本土狸>読み方:ホンドタヌキ本土狸というのは、”食肉目イヌ科タヌキ属に分類される哺乳類の一種”。狸というと、一般的には本土狸のことを指します。本土狸(標準和名)は、別名で「日本狸(ニホンタヌキ)」とも呼ばれています。【狩猟豹】読み方:チーター狩猟豹というのは、”食肉目(別名:ネコ目)ネコ科チーター属に分類される哺乳類の一種”。世界最速の哺乳類といわれ、100mの距離を3秒~4秒程度で走り、約3秒間で時速0kmから時速96kmまで加速できるとされています。【黒猩猩(黒猩々)】読み方:チンパンジー黒猩猩というのは、”霊長目(サル目)ヒト科チンパンジー属にに分類される哺乳類の一種”。【貂(黄鼬)】読み方:テン(総称)貂というのは、”食肉目(ネコ目)イタチ科テン属に分類される哺乳類の総称”。<黒貂>読み方:クロテン黒貂というのは、”食肉目イタチ科テン属に分類される哺乳類の一種”。<本土貂>読み方:ホンドテン本土貂というのは、”食肉目イタチ科テン属に分類される哺乳類の一種”。貂というと、一般的には本土貂を指すことが多いです。本土貂(標準和名)は、別名で「日本貂(ニホンテン)」とも呼ばれています。【蜥蜴(石竜子)】読み方:トカゲ(総称)蜥蜴というのは、”有鱗目トカゲ亜目に分類される爬虫類の総称”。<東青舌蜥蜴>読み方:ヒガシアオジタトカゲ東青舌蜥蜴というのは、”有鱗目トカゲ亜目トカゲ科アオジタトカゲ属に分類される爬虫類の一種”。青っぽい色の舌を持つことが名前の由来になります。<襟巻蜥蜴>読み方:エリマキトカゲ襟巻蜥蜴というのは、”有鱗目トカゲ亜目アガマ科エリマキトカゲ属に分類される爬虫類の一種”。地上での移動のほとんどは2本足で直立走行し、危険を感じると襟(えり)状の皮膚を広げて威嚇(いかく)します。<太顎鬚蜥蜴>読み方:フトアゴヒゲトカゲ太顎鬚蜥蜴というのは、”有鱗目トカゲ亜目アガマ科アゴヒゲトカゲ属に分類される爬虫類の一種”。喉(のど)の部分にある棘(トゲ)が太い顎髭(あごひげ)のように見えることが名前の由来になります。【海馬(胡獱)】読み方:トド海馬というのは、”食肉目(ネコ目)アシカ科トド属に分類される哺乳類の一種”。↓ナ行~【樹懶】読み方:ナマケモノ(総称)※上は二指樹懶(フタユビナマケモノ)の写真樹懶というのは、”有毛目ナマケモノ亜目に分類される哺乳類の総称”。動作はゆっくりしていて、長い鉤爪(かぎづめ)を木の枝に引っ掛けてぶら下がり、生涯のほとんどを木にぶら下がって過ごします。<二指樹懶>読み方:フタユビナマケモノ(総称)二指樹懶というのは、”有毛目ナマケモノ亜目フタユビナマケモノ科フタユビナマケモノ属に分類される哺乳類の総称”。フタユビナマケモノ科の仲間は、前足の指の数が2本で、後足の指の数は3本あり、尻尾(しっぽ)はありません。<三指樹懶>読み方:ミユビナマケモノ(総称)三指樹懶というのは、”有毛目ナマケモノ亜目ミユビナマケモノ科ミユビナマケモノ属に分類される哺乳類の総称”。ミユビナマケモノ科の仲間は、前後両足の指の数が3本あり、小さな尻尾があります。【沼狸(海狸鼠)】読み方:ヌートリア沼狸というのは、”齧歯目(ネズミ目)ヌートリア科ヌートリア属に分類される哺乳類の一種”。【鵺(鵼・夜鳥・奴延鳥)】読み方:ヌエ鵺というのは、”日本の伝承に登場する妖怪”。猿(サル)の顔、狸(タヌキ)の胴体、虎(トラ)の手足、蛇(ヘビ)の尾を持つとされています。【鼠】読み方:ネズミ(総称)鼠というのは、”齧歯目(ネズミ目)ネズミ亜目に分類される哺乳類の総称”。<溝鼠>読み方:ドブネズミ溝鼠というのは、”齧歯目ネズミ亜目ネズミ科クマネズミ属に分類される哺乳類の一種”。下水道や側溝などの湿った場所に生息することが名前の由来になります。ちなみに溝(どぶ)は”雨水・汚水などが流れる溝(みぞ)”を指します。<二十日鼠(廿日鼠・鼷)>読み方:ハツカネズミ二十日鼠というのは、”齧歯目ネズミ亜目ネズミ科ハツカネズミ属に分類される哺乳類の一種”。他の鼠よりも小さく、妊娠期間が20日ほどであることが名前の由来になります。↓ハ行~【鬣犬】読み方:ハイエナ(総称)鬣犬というのは、”食肉目(ネコ目)ハイエナ科に分類される哺乳類の総称”。腐った肉にいる有害な微生物から身を守る内臓器官や骨を消化できる胃を持っているため、他の肉食動物が食べることができない腐肉や骨も噛み砕いて食べ、それを消化して栄養にすることができます。このように鬣犬が腐肉や骨を食べることによって、サバンナを掃除してくれることから、別名で「サバンナの掃除屋(掃除人)」とも呼ばれています。<褐色鬣犬>読み方:カッショクハイエナ褐色鬣犬というのは、”食肉目ハイエナ科シマハイエナ属に分類される哺乳類の一種”。<縞鬣犬>読み方:シマハイエナ縞鬣犬というのは、”食肉目ハイエナ科シマハイエナ属に分類される哺乳類の一種”。<斑鬣犬>読み方:ブチハイエナ斑鬣犬というのは、”食肉目ハイエナ科ブチハイエナ属に分類される哺乳類の一種”。【獏(貘)】読み方:バク(総称)獏というのは、”奇蹄目(ウマ目)バク科に分類される哺乳類の総称/中国に伝わる想像上の動物”。獏(後者の意味)は「人の悪夢を食べる動物」として知られていますが、これは中国に伝わる空想上の動物で、実際の動物である獏(前者の意味)を指しているわけではありません。<亜米利加獏>読み方:アメリカバク亜米利加獏というのは、”奇蹄目バク科バク属に分類される哺乳類の一種”。<中米獏>読み方:ベアードバク中米獏というのは、”奇蹄目バク科バク属に分類される哺乳類の一種”。<馬来獏>読み方:マレーバク馬来獏というのは、”奇蹄目バク科バク属に分類される哺乳類の一種”。獏というと、一般的には馬来獏を指すことが多いです。【白鼻芯(白鼻心)】読み方:ハクビシン白鼻芯というのは、”食肉目(ネコ目)ジャコウネコ科ハクビシン属に分類される哺乳類の一種”。電線の上を移動したり、民家の床下・屋根裏などに棲みつくこともあります。額から鼻先まで白い線があることが名前の由来になります。【倉鼠】読み方:ハムスター(総称)※上はゴールデンハムスターの写真※上はジャンガリアンハムスターの写真倉鼠というのは、”齧歯目(ネズミ目)キヌゲネズミ科キヌゲネズミ亜科に分類される哺乳類の総称”。倉鼠というと、一般的には「ゴールデンハムスター」がよく知られています。【針鼠(蝟)】読み方:ハリネズミ(総称)針鼠というのは、”真無盲腸目(しんむもうちょうもく)ハリネズミ科ハリネズミ亜科に分類される哺乳類の総称”。名前に鼠(ネズミ)と表記されますが、鼠の仲間ではありません。<四指針鼠>読み方:ヨツユビハリネズミ四指針鼠というのは、”真無盲腸目ハリネズミ科ハリネズミ亜科アフリカネズミ属に分類される哺乳類の一種”。針鼠というと、一般的には四指針鼠を指すことが多いです。針鼠の中で唯一、後足の指の数が4本しかないことが名前の由来になります。【熊猫】読み方:パンダ(総称)熊猫というのは、”大熊猫(ジャイアントパンダ)と小熊猫(レッサーパンダ)の総称”。<大熊猫>読み方:ジャイアントパンダ大熊猫というのは、”食肉目(ネコ目)クマ科ジャイアントパンダ属に分類される哺乳類の一種”。熊猫というと、一般的には大熊猫を指すことが多いです。果物などを食べることもありますが、ほとんどは竹や笹(ササ)の葉・幹(みき)・若芽(タケノコのこと)を食べます。<小熊猫>読み方:レッサーパンダ小熊猫というのは、”食肉目レッサーパンダ科レッサーパンダ属に分類される哺乳類の一種”。「レッサー(lesser)」は”小さい方の”という意味の英語なので、レッサーパンダは「小さい方のパンダ」を意味します。【海狸】読み方:ビーバー(総称)海狸というのは、”齧歯目(ネズミ目)ビーバー科ビーバー属に分類される哺乳類の総称”。※上は海狸の巣海狸は、木の枝や砂・泥などを用いてダムを作って川の水をせき止め、そのダム湖の中央に木の枝などで巣を作る習性があります。<亜米利加海狸>読み方:アメリカビーバー亜米利加海狸というのは、”齧歯目ビーバー科ビーバー属に分類される哺乳類の一種”。【狒狒(狒々・狒)】読み方:ヒヒ(総称)狒狒というのは、”霊長目(サル目)オナガザル科ヒヒ属に分類される哺乳類の総称”。<阿努比斯狒狒>読み方:アヌビスヒヒ阿努比斯狒狒というのは、”霊長目オナガザル科ヒヒ属に分類される哺乳類の一種”。<黄色狒狒>読み方:キイロヒヒ黄色狒狒というのは、”霊長目オナガザル科ヒヒ属に分類される哺乳類の一種”。<飛布狒狒>読み方:マントヒヒ飛布狒狒というのは、”霊長目オナガザル科ヒヒ属に分類される哺乳類の一種”。雄(オス)は頭から腰にかけて長い毛があり、肩から背にかけて覆われている長い毛がマントのように見えることが名前の由来になります。【亜米利加獅(米獅)】読み方:ピューマ亜米利加獅というのは、”食肉目(ネコ目)ネコ科ピューマ属に分類される哺乳類の一種”。【豹】読み方:ヒョウ(総称)豹というのは、”食肉目(ネコ目)ネコ科ヒョウ属に分類される哺乳類の総称”。種類に関係なく突然変異で毛色が黒い個体(黒変種)が生じることがあり、そのような黒い個体を「黒豹(クロヒョウ)」と呼びます。<阿弗利加豹>読み方:アフリカヒョウ阿弗利加豹というのは、”食肉目ネコ科ヒョウ属に分類される哺乳類の一種”。<雪豹>読み方:ユキヒョウ雪豹というのは、”食肉目ネコ科ヒョウ属に分類される哺乳類の一種”。【蛇】読み方:ヘビ(総称)蛇というのは、”有鱗目ヘビ亜目に分類される爬虫類の総称”。<青大将>読み方:アオダイショウ青大将というのは、”有鱗目ヘビ亜目ナミヘビ科ナメラ属に分類される爬虫類の一種”。毒を持っていない蛇で、日本本土では最も大きな蛇になります。<響尾蛇>読み方:ガラガラヘビ(総称)響尾蛇というのは、”有鱗目ヘビ亜目クサリヘビ科ガラガラヘビ属に分類される爬虫類の総称”。有毒の蛇で、尾の先端にある脱皮殻の集まったものが、赤ちゃんをあやすためのガラガラに似ていることから名付けられています。<眼鏡蛇>読み方:コブラ(総称)眼鏡蛇というのは、”有鱗目ヘビ亜目コブラ科に分類される爬虫類の総称”。有毒の蛇で、眼鏡蛇の一部の種類は、筋肉で毒腺に圧力をかけることで毒液を飛ばすことができます。<地潜>読み方:ジムグリ地潜というのは、”有鱗目ヘビ亜目ナミヘビ科ナメラ属に分類される爬虫類の一種”。毒を持っていない蛇で、腹部は市松模様(元禄模様)状になっていることから、別名で「元禄蛇(げんろくへび)」とも呼ばれています。<波布(飯匙倩)>読み方:ハブ(一種)波布というのは、”有鱗目ヘビ亜目クサリヘビ科ハブ属に分類される爬虫類の一種/有鱗目ヘビ亜目クサリヘビ科ハブ属に分類される爬虫類の総称”。前者の意味の波布(標準和名)は、別名で「本波布(ホンハブ)」とも呼ばれています。有毒の蛇で、奄美(あまみ)群島・沖縄諸島に生息し、非常に攻撃性が強く好戦的です。波布というと「ハブ酒(しゅ)」が有名で、下処理をした波布と薬草などを酒(泡盛など)の中に漬け込んで熟成させたものになります。熟成期間は基本的には1~5年ほど(長いものでは10年以上)で、アルコール度数の強い酒に長期間漬けることによって波布の毒が無毒化されます。<日計(熇尾蛇・竹根蛇)>読み方:ヒバカリ日計というのは、”有鱗目ヘビ亜目ナミヘビ科ヒバカリ属に分類される爬虫類の一種”。毒を持っていない蛇ですが、昔は毒蛇とされており、「噛まれたら命がその日ばかり」が名前の由来になっています。<蝮>読み方:マムシ蝮というのは、”日本蝮(ニホンマムシ:標準和名)の別名”。日本蝮は、”有鱗目ヘビ亜目クサリヘビ科マムシ属に分類される爬虫類の一種”を指します。有毒の蛇で、基本的にはおとなしく臆病な性格をしており、距離さえとっていれば攻撃してくることはまずありません。<山楝蛇(赤楝蛇)>読み方:ヤマカガシ山楝蛇というのは、”有鱗目ヘビ亜目ナミヘビ科ヤマカガシ属に分類される爬虫類の一種”。日本にいる蛇の中で最も強い毒を持っていて、基本的にはおとなしく臆病な性格をしており、距離さえとっていれば攻撃してくることはまずありません。↓マ行~【猫鼬】読み方:マングース(総称)猫鼬というのは、”食肉目(ネコ目)マングース科に分類される哺乳類の総称”。鼠(ネズミ)・蛇(ヘビ)などを捕食するため、1910年に、沖縄に波布(ハブ)退治のために移入されました。しかし猫鼬は主に昼間に行動し、波布は夜間に行動するため、両者が出会うチャンスは極めて低く失敗に終わりました。<小人猫鼬>読み方:コビトマングース小人猫鼬というのは、”食肉目マングース科コビトマングース属に分類される哺乳類の一種”。<縞猫鼬>読み方:シママングース縞猫鼬というのは、”食肉目マングース科ガンビアマングース属に分類される哺乳類の一種”。【山魈】読み方:マンドリル山魈というのは、”霊長目(サル目)オナガザル科マンドリル属に分類される哺乳類の一種”。【鼯鼠(鼺鼠・鼫)】読み方:ムササビ鼯鼠というのは、”齧歯目(ネズミ目)リス科ムササビ属に分類される哺乳類の一種”。長い前足と後足の間に「飛膜(ひまく)」(皮膚のひだ)と呼ばれる膜があり、飛膜を広げてグライダーのように滑空し、木から木へと飛び移ります。【狢(貉)】読み方:ムジナ※上は狢(穴熊)の写真狢というのは、”穴熊(アナグマ:標準和名)の別名”。穴熊は、”食肉目(ネコ目)イタチ科アナグマ属に分類される哺乳類の一種”を指します。狸(タヌキ)・白鼻芯(ハクビシン)なども狢と呼ぶことがありますが、一般的には狢というと穴熊のことを指します。【土竜(鼴鼠)】読み方:モグラ(総称)土竜というのは、”真無盲腸目モグラ科に分類される哺乳類の総称”。多くの土竜は地下にトンネルを掘って生活し、地表付近でトンネルを掘ったときに、地表に押し上げられて盛り上がった跡を「モグラ塚(づか)」と呼びます。<神戸土竜>読み方:コウベモグラ神戸土竜というのは、”真無盲腸目モグラ科モグラ属に分類される哺乳類の一種”。<日不見>読み方:ヒミズ日不見というのは、”真無盲腸目モグラ科ヒミズ属に分類される哺乳類の一種”。日不見は夜行性で、日中は土の中に潜っているため、日光が当たるところには出てこないことから名付けられています。【鼯鼠(摸摸具和)】読み方:モモンガ(一種)鼯鼠というのは、”日本鼯鼠(ニホンモモンガ:標準和名)の別名/齧歯目(ネズミ目)リス科モモンガ属に分類される哺乳類の総称”。前足と後足の間に「飛膜(ひまく)」(皮膚のひだ)と呼ばれる膜があり、飛膜を広げてグライダーのように滑空し、木から木へと飛び移ります。<日本鼯鼠>読み方:ニホンモモンガ日本鼯鼠というのは、”齧歯目リス科モモンガ属に分類される哺乳類の一種”。日本鼯鼠(標準和名)は、別名で「本土鼯鼠(ホンドモモンガ)」とも呼ばれています。また生息地によって「本州鼯鼠(ホンシュウモモンガ)」「山陰鼯鼠(サンインモモンガ)」「九州鼯鼠(キュウシュウモモンガ)」のように分類される場合もあります。<袋鼯鼠>読み方:フクロモモンガ袋鼯鼠というのは、”双前歯目(カンガルー目)フクロモモンガ科フクロモモンガ属に分類される哺乳類の一種”。鼯鼠と表記されますが、実は鼯鼠の仲間ではなく、長尾驢(カンガルー)や子守熊(コアラ)の仲間になります。鼯鼠の仲間ではありませんが、鼯鼠同様に飛膜があり、飛膜を広げてグライダーのように滑空し、木から木へと飛び移ります。↓ヤ行~【山羊(野羊)】読み方:ヤギ(総称)山羊というのは、”鯨偶蹄目ウシ科ヤギ属に分類される哺乳類の総称”。紙を好んで食べるイメージがありますが、食べることができるのは昔の紙の材質(自然由来の植物)で、現代の紙は化学薬品やインクが使われているため食べることはできません。(正確にいうと、食べることはできますが、山羊の体に悪いため食べさせないようにしましょう)【山荒(豪猪)】読み方:ヤマアラシ(総称)山荒というのは、”齧歯目(ネズミ目)ヤマアラシ科・アメリカヤマアラシ科に分類される哺乳類の総称”。危険が迫ったときに針を逆立てながら、相手に対して後ろ向きで突進してきます。草・木の葉・樹皮・木の根・果実などを食べ、周りの植物を根まで掘り出して食い荒らし、山の木を枯らしてしまうことが名前の由来になっています。<鬣山荒>読み方:タテガミヤマアラシ鬣山荒というのは、”齧歯目ヤマアラシ科ヤマアラシ属に分類される哺乳類の一種”。鬣山荒(標準和名)は、別名で「阿弗利加鬣山荒(アフリカタテガミヤマアラシ)」とも呼ばれています。<印度鬣山荒>読み方:インドタテガミヤマアラシ印度鬣山荒というのは、”齧歯目ヤマアラシ科ヤマアラシ属に分類される哺乳類の一種”。【山鼠(冬眠鼠)】読み方:ヤマネ山鼠というのは、”齧歯目(ネズミ目)ヤマネ科ヤマネ属に分類される哺乳類の一種”。山鼠(標準和名)は、別名で「日本山鼠(ニホンヤマネ)」とも呼ばれています。【家守(守宮・壁虎)】読み方:ヤモリ(一種)家守というのは、”日本家守(ニホンヤモリ:標準和名)の別名/有鱗目ヤモリ科に分類される爬虫類の総称”。<日本家守>読み方:ニホンヤモリ日本家守というのは、”有鱗目ヤモリ科ヤモリ属に分類される爬虫類の一種”。垂直なガラス面にも張り付いて行動でき、尾は自切・再生することができます。↓ラ行~【獅子】読み方:ライオン(総称)獅子というのは、”食肉目(ネコ目)ネコ科ヒョウ属に分類される哺乳類の総称”。獅子は、一般的には「しし」と読むことがほとんどです。雄(オス)はたてがみが特徴的で、雌(メス)にはたてがみはありません。複数の雌と群れを作り、そこに雄1頭で君臨する様子から、別名で「百獣の王」とも呼ばれています。【駱駝】読み方:ラクダ(総称)駱駝というのは、”鯨偶蹄目ラクダ科ラクダ属に分類される哺乳類の総称”。駱駝は栄養を脂肪に変えてコブに溜(た)めており、餌(えさ)が見つからないときはそのコブの脂肪を少しずつ使って命をつないでいます。<一瘤駱駝>読み方:ヒトコブラクダ一瘤駱駝というのは、”鯨偶蹄目ラクダ科ラクダ属に分類される哺乳類の一種”。<二瘤駱駝>読み方:フタコブラクダ二瘤駱駝というのは、”鯨偶蹄目ラクダ科ラクダ属に分類される哺乳類の一種”。【海獺(猟虎・獺虎・海猟)】読み方:ラッコ海獺というのは、”食肉目(ネコ目)イタチ科ラッコ属に分類される哺乳類の一種”。海獺は主に海岸から1km以内の、岩場があり、海藻が茂っている環境に生息しています。休むときや寝るときは、そのまま寝ると流されてしまうため、海藻を体に巻きつけてから寝ます。(群れでいるときで近くに海藻がないときは、手を繋いで群れからはぐれないようにします)【騾馬】読み方:ラバ騾馬というのは、”奇蹄目(ウマ目)ウマ科ウマ属に分類される哺乳類の一種”。雄(オス)の驢馬(ロバ)と、雌(メス)の馬の交雑種で、馬のような体格と驢馬の頑丈さを持っています。【栗鼠】読み方:リス(総称)栗鼠というのは、”齧歯目(ネズミ目)リス科に分類される哺乳類の総称”。<蝦夷鼯鼠>読み方:エゾモモンガ蝦夷鼯鼠というのは、”齧歯目リス科モモンガ属に分類される哺乳類の一種”。鼯鼠(モモンガ)と同様に前足から後足、後足から尾の付け根まで「飛膜(ひまく)」(皮膚のひだ)と呼ばれる膜があり、飛膜を広げてグライダーのように滑空し、木から木へと飛び移ります。鼯鼠(モモンガ)と表記されますが、栗鼠(リス)の仲間になります。<蝦夷栗鼠>読み方:エゾリス蝦夷栗鼠というのは、”齧歯目リス科リス属に分類される哺乳類の一種”。<縞栗鼠>読み方:シマリス(総称)縞栗鼠というのは、”齧歯目リス科シマリス属に分類される哺乳類の総称”。縞栗鼠というと、日本では一般的に「西比利亜縞栗鼠(シベリアシマリス)」を指します。<日本栗鼠>読み方:ニホンリス日本栗鼠というのは、”齧歯目リス科リス属に分類される哺乳類の一種”。日本栗鼠(標準和名)は、別名で「本土栗鼠(ホンドリス)」とも呼ばれています。【驢馬】読み方:ロバ(総称)驢馬というのは、”奇蹄目(ウマ目)ウマ科ウマ属ロバ亜属に分類される哺乳類の総称”。ウマ科の中で最も小型ですが、力が強く、古くから家畜(荷物の運搬など)として利用されます。英語では「ドンキー(donkey)」と呼ばれ、「ドンキー(donkey)」には驢馬の他にも”まぬけ。のろま”という意味もあります。↓ワ行~【鰐】読み方:ワニ(総称)鰐というのは、”ワニ目に分類される爬虫類の総称”。<入江鰐>読み方:イリエワニ入江鰐というのは、”ワニ目クロコダイル科クロコダイル属に分類される爬虫類の一種”。動物の中で最も噛(か)む力が強いとされ、主に汽水域に生息し、入り江や三角州のマングローブ林を好むことが名前の由来になっています。<暹羅鰐>読み方:シャムワニ暹羅鰐というのは、”ワニ目クロコダイル科クロコダイル属に分類される爬虫類の一種”。暹羅(シャム)というのは、タイ王国の旧名で、”暹羅(シャム)産の鰐(ワニ)”という意味から「暹羅鰐(シャムワニ)」と名付けられています。<西阿弗利加小人鰐>読み方:ニシアフリカコビトワニ西阿弗利加小人鰐というのは、”ワニ目クロコダイル科コビトワニ属に分類される爬虫類の一種”。西阿弗利加小人鰐(標準和名)は、別名で「西阿弗利加小型鰐(ニシアフリカコガタワニ)」とも呼ばれています。動物の難読漢字(一覧表)※1:漢字表記が複数ある場合は、一般的に使われることが多いほうの漢字表記を優先しています(読み方の表記も同様)。例 【海豹(水豹)】 ⇒ 【一般的に使われることが多い漢字表記(比較して一般的に使われることが少ない漢字表記)】※2:読み方の横に「(一種)」「(総称)」の表記があるものは、以下のような意味になります。例 【アライグマ(一種)】 ⇒ 【(狭義では)食肉目アライグマ科アライグマ属に分類される哺乳類の一種】【(広義では)食肉目アライグマ科アライグマ属に分類される哺乳類の総称】の両方を意味例 【アリクイ(総称)】 ⇒ 【有毛目アリクイ亜目に分類される哺乳類の総称】を意味(アリクイという名称の特定の動物が存在するわけではない)※3:標準和名=【日本での正式な名称のこと】⇒学名と標準和名の違いとは?漢字読み方備考欄指猿アイアイ【海豹(水豹)】アザラシ(総称)◆顎鬚海豹アゴヒゲアザラシ◆胡麻斑海豹ゴマフアザラシ◆銭形海豹ゼニガタアザラシ【海驢(葦鹿)】アシカ(一種)海驢(一種)は、「加州海驢(カリフォルニアアシカ)」(標準和名)の別名◆加羅哇哥斯海驢ガラパゴスアシカ◆加州海驢カリフォルニアアシカ【洗熊(浣熊)】アライグマ(一種)【食蟻獣(蟻食・蟻喰)】アリクイ(総称)◆大蟻食オオアリクイ◆南小蟻食ミナミコアリクイ羊駱駝アルパカ羊駱駝は「駱駝(ラクダ)」の仲間【犰狳(鎧鼠)】アルマジロ(総称)大半の種類は丸くなることができない◆三帯犰狳ミツオビアルマジロ数少ない丸くなることのできる犰狳の一種【鬣蜥蜴(立髪竜)】イグアナ(総称)一般的には「緑鬣蜥蜴(グリーンイグアナ)」を指すことが多い◆海鬣蜥蜴ウミイグアナ◆緑鬣蜥蜴グリーンイグアナ【鼬(鼬鼠)】イタチ(総称)一般的には「日本鼬(ニホンイタチ)」を指すことが多い◆白鼬オコジョ◆朝鮮鼬チョウセンイタチ朝鮮鼬は、「西比利亜鼬(シベリアイタチ)」(標準和名)の別名◆日本鼬ニホンイタチ【猪(豬)】イノシシ(一種)猪の子供を「ウリ坊」と呼ぶ◆日本猪ニホンイノシシ日本猪は、猪(一種)の亜種◆琉球猪リュウキュウイノシシ琉球猪は、猪(一種)の亜種【井守(蠑螈)】イモリ(総称)一般的には「赤腹井守(アカハライモリ)」を指すことが多い◆赤腹井守アカハライモリ赤腹井守(標準和名)の別名は「日本井守(ニホンイモリ)」◆尻剣井守シリケンイモリ◆南疣井守ミナミイボイモリ【海豚(鯆)】イルカ(総称)目安として体長4~5m以下のものを「海豚(イルカ)」、それ以上のものを「鯨(クジラ)」と呼ぶことが多い◆鎌海豚カマイルカ◆白海豚シロイルカ白海豚(標準和名)の別名は「ベルーガ」◆砂滑スナメリ◆半道海豚ハンドウイルカ半道海豚(標準和名)の別名は「坂東海豚(バンドウイルカ)」【兎】ウサギ(総称)【海亀(魭)】ウミガメ(総称)◆青海亀アオウミガメ青海亀(標準和名)の別名は「正覚坊(ショウガクボウ)」◆赤海亀アカウミガメ◆玳瑁(瑇瑁)タイマイ玳瑁の甲羅は「鼈甲(べっこう)」と呼ばれ、鼈甲細工の原料となる【狼】オオカミ(一種)狼(一種:標準和名)の別名は「灰色狼(ハイイロオオカミ)」「大陸狼(タイリクオオカミ)」◆森林狼シンリンオオカミ◆北極狼ホッキョクオオカミ霍加皮オカピ霍加皮は「麒麟(キリン)」の仲間【膃肭臍(海狗)】オットセイ(総称)◆南阿弗利加膃肭臍ミナミアフリカオットセイ◆南亜米利加膃肭臍ミナミアメリカオットセイ【袋鼠】オポッサム(総称)袋鼠は「カンガルー」と読むこともできる◆北袋鼠キタオポッサム【猩猩(猩々)】オランウータン(総称)◆蘇門荅剌猩猩スマトラオランウータン◆勃泥亜猩猩(婆羅猩猩)ボルネオオランウータン【蛙】カエル(総称)蛙の幼生(子ども)を「御玉杓子(オタマジャクシ)」と呼ぶ◆牛蛙ウシガエル◆土蛙ツチガエル土蛙(標準和名)の別名は「疣蛙(イボガエル)」◆殿様蛙トノサマガエル◆日本雨蛙ニホンアマガエル一般的には略して「雨蛙(アマガエル)」と呼ばれている◆蟇蛙ヒキガエル(一種)蟇蛙(一種)は、「日本蟇蛙(ニホンヒキガエル)」(標準和名)の別名。蟇蛙の別名は「蝦蟇(ガマ、ガマガエル)」【金蛇(蛇舅母)】カナヘビ(一種)金蛇(一種)は、「日本金蛇(ニホンカナヘビ)」(標準和名)の別名◆青金蛇アオカナヘビ◆日本金蛇ニホンカナヘビ◆宮古金蛇ミヤコカナヘビ【河馬】カバ(一種)小人河馬コビトカバ水豚(川豚)カピバラ【避役(変色竜・変色龍)】カメレオン(総称)◆烏帽子避役エボシカメレオン◆地中海避役チチュウカイカメレオン【羚羊(氈鹿)】カモシカ(一種)羚羊(一種)は、「日本羚羊(ニホンカモシカ)」(標準和名)の別名◆日本羚羊(日本氈鹿)ニホンカモシカ特別天然記念物に指定されている鴨嘴(鴨嘴獣)カモノハシ【獺(川獺)】カワウソ(総称)◆小爪獺コツメカワウソ◆欧亜獺ユーラシアカワウソ【長尾驢(袋鼠・更格廬)】カンガルー(総称)袋鼠は「オポッサム」と読むことが多い◆赤長尾驢アカカンガルー◆大長尾驢オオカンガルー◆黒長尾驢クロカンガルー【狐】狐(総称)一般的には「赤狐(アカギツネ)」を指すことが多い◆赤狐アカギツネ◆銀狐ギンギツネ◆本土狐ホンドギツネ麒麟(騏驎)キリン麒麟は、動物の中で最も睡眠時間が短い【鯨】クジラ(総称)目安として体長4~5m以下のものを「海豚(イルカ)」、それ以上のものを「鯨(クジラ)」と呼ぶことが多い◆座頭鯨ザトウクジラ◆白長須鯨シロナガスクジラ◆抹香鯨マッコウクジラ抹香鯨の腸内に発生する結石を「龍涎香(りゅうぜんこう)」と呼ぶ貂熊(屈狸)クズリ貂熊(標準和名)の別名は「黒穴熊(クロアナグマ)」【熊】クマ(総称)◆月輪熊ツキノワグマ◆羆(緋熊・樋熊)ヒグマ◆北極熊ホッキョクグマ北極熊(標準和名)の別名は「白熊(シロクマ)」【子守熊(袋熊)】コアラ(総称)子守熊は、最も睡眠時間が長い動物【蝙蝠】コウモリ(総称)一般的には(日本では)「油蝙蝠(アブラコウモリ)」を指す◆油蝙蝠アブラコウモリ油蝙蝠(標準和名)の別名は「家蝙蝠(イエコウモリ)」◆菊頭蝙蝠キクガシラコウモリ【大猩猩(大猩々)】ゴリラ(総称)◆西大猩猩ニシゴリラ◆山地大猩猩マウンテンゴリラ【犀】サイ(総称)◆印度犀インドサイ◆黒犀クロサイ◆白犀シロサイ【山椒魚(鯢・䱱魚)】サンショウウオ(総称)◆大山椒魚オオサンショウウオ◆霞山椒魚カスミサンショウウオ◆墨西哥鯢メキシコサンショウウオ白変種の個体は、一般的には別名で「ウーパールーパー」と呼ばれる【鹿】シカ(総称)◆馴鹿トナカイそりを引く動物のイメージが強い◆日本鹿二ホンジカ◆箆鹿(篦鹿)ヘラジカ【縞馬(斑馬)】シマウマ(総称)亜米利加豹ジャガー鯱シャチ【胡狼】ジャッカル(総称)◆背黒胡狼セグロジャッカル儒艮ジュゴン人魚のモデルになったとされている【鼈】スッポン(一種)鼈(一種:標準和名)の別名は「日本鼈(ニホンスッポン)」「極東鼈(キョクトウスッポン)」海象(海馬)セイウチ海馬は「トド」と読むことが多い【狸】タヌキ(総称)一般的には「本土狸(ホンドタヌキ)」を指す◆本土狸ホンドタヌキ本土狸(標準和名)の別名は「日本狸(二ホンタヌキ)」狩猟豹チーター狩猟豹は、世界最速の哺乳類黒猩猩(黒猩々)チンパンジー【貂(黄鼬)】テン(総称)一般的には「本土貂(ホンドテン)」を指すことが多い◆黒貂クロテン◆本土貂ホンドテン本土貂(標準和名)の別名は「日本貂(ニホンテン)」【蜥蜴(石竜子)】トカゲ(総称)◆東青舌蜥蜴ヒガシアオジタトカゲ◆襟巻蜥蜴エリマキトカゲ◆太顎鬚蜥蜴フトアゴヒゲトカゲ海馬(胡獱)トド【樹懶】ナマケモノ(総称)◆二指樹懶フタユビナマケモノ(総称)◆三指樹懶ミユビナマケモノ(総称)沼狸(海狸鼠)ヌートリア鵺(鵼・夜鳥・奴延鳥)ヌエ日本の伝承に登場する妖怪【鼠】ネズミ(総称)◆溝鼠ドブネズミ◆二十日鼠(廿日鼠・鼷)ハツカネズミ【鬣犬】ハイエナ(総称)別名で「サバンナの掃除屋(掃除人)」とも呼ばれる◆褐色鬣犬カッショクハイエナ◆縞鬣犬シマハイエナ◆斑鬣犬ブチハイエナ【獏(貘)】バク(総称)一般的には「馬来獏(マレーバク)」を指すことが多い◆亜米利加獏アメリカバク◆中米獏ベアードバク◆馬来獏マレーバク白鼻芯(白鼻心)ハクビシン【倉鼠】ハムスター(総称)【針鼠】ハリネズミ(総称)一般的には「四指針鼠(ヨツユビハリネズミ)」を指すことが多い。鼠(ネズミ)と表記されるが、鼠の仲間ではない◆四指針鼠ヨツユビハリネズミ【熊猫】パンダ(総称)一般的には「大熊猫(ジャイアントパンダ)」を指すことが多い◆大熊猫ジャイアントパンダ◆小熊猫レッサーパンダ【海狸】ビーバー(総称)◆亜米利加海狸アメリカビーバー【狒狒(狒々・狒)】ヒヒ(総称)◆阿努比斯狒狒アヌビスヒヒ◆黄色狒狒キイロヒヒ◆飛布狒狒マントヒヒ亜米利加獅(米獅)ピューマ【豹】ヒョウ(総称)◆阿弗利加豹アフリカヒョウ◆雪豹ユキヒョウ【蛇】ヘビ(総称)◆青大将アオダイショウ◆響尾蛇ガラガラヘビ(総称)◆眼鏡蛇コブラ(総称)◆地潜ジムグリ地潜(標準和名)の別名は「元禄蛇(げんろくへび)」◆波布(飯匙倩)ハブ(一種)波布(一種:標準和名)の別名は「本波布(ホンハブ)」◆日計(熇尾蛇・竹根蛇)ヒバカリ◆蝮マムシ蝮は、「日本蝮(ニホンマムシ)」(標準和名)の別名◆山楝蛇(赤楝蛇)ヤマカガシ【猫鼬】マングース(総称)◆小人猫鼬コビトマングース◆縞猫鼬シママングース山魈マンドリル鼯鼠(鼺鼠・鼫)ムササビ鼯鼠は「モモンガ」と読むこともできる狢(貉)ムジナ狢は、「穴熊(アナグマ)」(標準和名)の別名【土竜(鼴鼠)】モグラ◆神戸土竜コウベモグラ◆日不見ヒミズ【鼯鼠(摸摸具和)】モモンガ(一種)鼯鼠(一種)は、「日本鼯鼠(ニホンモモンガ)」(標準和名)の別名。鼯鼠は「ムササビ」と読むこともできる◆日本鼯鼠ニホンモモンガ日本鼯鼠(標準和名)の別名は「本土鼯鼠(ホンドモモンガ)」◆袋鼯鼠フクロモモンガ鼯鼠と表記されるが、鼯鼠の仲間ではない【山羊(野羊)】ヤギ(総称)【山荒(豪猪)】ヤマアラシ(総称)◆鬣山荒タテガミヤマアラシ鬣山荒(標準和名)の別名は「阿弗利加鬣山荒(アフリカタテガミヤマアラシ)」◆印度鬣山荒インドタテガミヤマアラシ山鼠(冬眠鼠)ヤマネ山鼠(標準和名)の別名は「日本山鼠(ニホンヤマネ)」【家守(守宮・壁虎)】ヤモリ(一種)家守(一種)は、「日本家守(ニホンヤモリ)」(標準和名)の別名◆日本家守ニホンヤモリ【獅子】ライオン(総称)獅子は、一般的には「しし」と読むことがほとんど。別名で「百獣の王」とも呼ばれる【駱駝】ラクダ(総称)コブには脂肪が蓄えられている◆一瘤駱駝ヒトコブラクダ◆二瘤駱駝フタコブラクダ海獺(猟虎・獺虎・海猟)ラッコ騾馬ラバ雄の驢馬(ロバ)と、雌の馬の交雑種【栗鼠】リス(総称)◆蝦夷鼯鼠エゾモモンガ鼯鼠と表記されるが、栗鼠(リス)の仲間◆蝦夷栗鼠エゾリス◆縞栗鼠シマリス(総称)日本では一般的に「西比利亜縞栗鼠(シベリアシマリス)」を指す◆日本栗鼠ニホンリス日本栗鼠(標準和名)の別名は「本土栗鼠(ホンドリス)」驢馬ロバ【鰐】ワニ(総称)◆入江鰐イリエワニ動物の中で最も噛む力が強いとされている◆暹羅鰐シャムワニ◆西阿弗利加小人鰐ニシアフリカコビトワニ西阿弗利加小人鰐(標準和名)の別名は「西阿弗利加小型鰐(ニシアフリカコガタワニ)」項目1項目2項目3)★ -->関連ページ<難読漢字の一覧>⇒【一文字】難読漢字の一覧!⇒【野菜・果物・茸】難読漢字の一覧!⇒【魚・貝・海藻】難読漢字の一覧!⇒【鳥】難読漢字の一覧!⇒【花・植物】難読漢字の一覧!⇒【虫】難読漢字の一覧!⇒【食べ物・飲み物】難読漢字の一覧!⇒【道具・身近なモノ】難読漢字の一覧!<読み間違えやすい漢字の一覧>⇒読み間違えやすい漢字一覧!⇒慣用読み(百姓読み)の一覧!<難読漢字の一覧(偏)>⇒【魚偏】難読漢字の一覧!⇒【虫偏】難読漢字の一覧!⇒【木偏】難読漢字の一覧!⇒【金偏】難読漢字の一覧!