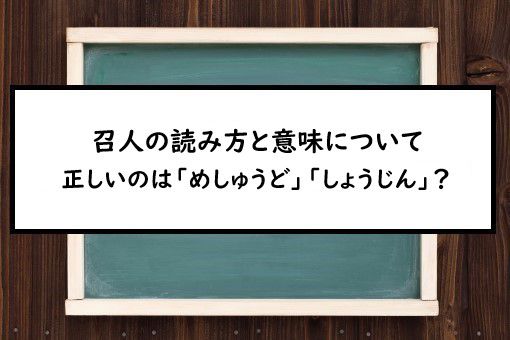1.召人の正しい読み方は「めしゅうど」「しょうじん」?
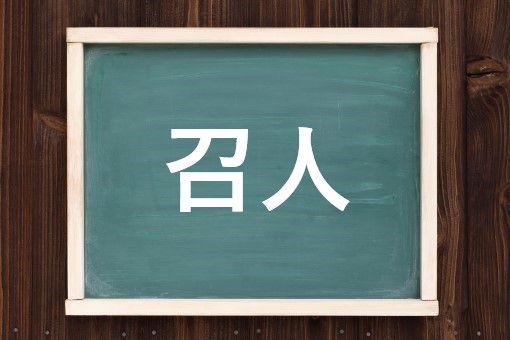
結論から言ってしまうと、召人の正しい読み方は「めしゅうど」「めしうど」「めしびと」になります。
召人の”召”は「め(す)」「め(し)」「しょう」、”人”は「ひと」「にん」「じん」(連濁により「びと」)と読むことができますが、召人を「しょうじん」と読むのは間違いです。
(連濁とは、2つの語が結びついて1つの語になるときに、発音しやすくするために、後ろの語の語頭が清音から濁音に変化する現象のこと)
ただ一般的には召人は「めしゅうど」と読むことが多いです。
また召人の”人”の読み方は連濁により「びと」と読むことはできますが、
もともとそれ単体では「うど」という読み方をすることはできません。
召人のように「めしびと」ではなく、「めしうど」と変化して読むのは、日本語の音便(おんびん)のひとつである”ウ音便”と呼ばれているものです。
(音便とは、”発音しやすくするために、言い方を変えること”です)
ウ音便とは、”語中・語尾の「く」「ぐ」「ひ」「び」「み」などの音が、「う」の音に変化する現象のこと”を言います。
召人であれば、”召人(めしびと) → 召人(めしうど)”となり、「び」の音が「う」の音に変化します。
「び」の音が「う」の音に変化して、そこからさらに発音しやすいように変化して召人は「めしうど」と読まれるようになりました。
そして召人を「めしうど」ではなく、「めしゅうど」と読むのは、日本語の”音韻融合(おんいんゆうごう)”によるものです。
音韻融合とは、”前の語と後ろの語の音が合わさる現象のこと”です。
召人であれば、召人(めしうど)[mesiudo] → 召人(めしゅうど)[mesyuudo]
音韻融合の例として、召人の他にも狩人(かりゅうど)があります。
・狩人(かりうど)[kariudo] → 狩人(かりゅうど)[karyuudo]
このように召人は日本語の音便のひとつであるウ音便により「めしうど」、音韻融合により「めしゅうど」と読むことができます。
次の章で召人の意味について解説していきます。
2.召人の意味について
3.まとめ
これまで説明したことをまとめますと、
- 召人の正しい読み方は「めしゅうど」「めしうど」「めしびと」のすべてで、「しょうじん」は間違い。
- 召人は「舞楽などをするために召された人のこと/和歌所の寄人のこと/歌会始めの際、題にちなんだ和歌を詠むように選ばれた人のこと」の意味。
関連ページ
<難読漢字の一覧>
(写真あり)藜、櫛、羆など
(写真あり)竜髭菜、青梗菜、蕗など
(写真あり)岩魚、栄螺、鱧など
(写真あり)海驢、犀、猫鼬など
(写真あり)花鶏、信天翁、杜鵑など
(写真あり)薊、金木犀、百合など
(写真あり)水黽、蟋蟀、蟷螂など
(写真あり)外郎、皮蛋、雲呑など
(写真あり)行灯、暖簾、轆轤など
<読み間違えやすい漢字の一覧>
哀悼、重複、出生、集荷など
依存、過不足、続柄など
<難読漢字の一覧(偏)>
(写真あり)鯆、鰍、鰉など
(写真あり)蝗、蠍、蝮など
(写真あり)梲、栂、樅など
(写真あり)鎹、鍬、釦など
<覚えておきたい知識>
鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など
(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど